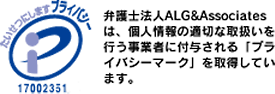勾留とは?拘留との違いや要件、期間などをわかりやすく解説


「勾留(こうりゅう)」とは、罪を犯した疑いのある人物を逮捕した後に、その人物の身柄を刑事施設に一定期間拘束することをいいます。
勾留するかどうかを判断するのは検察官であり、勾留の必要性が認められた場合に、裁判官に対して勾留請求がなされます。
裁判官が勾留請求を認めると、最大で20日間の勾留が実施され、仕事や学校、対人関係に悪影響を及ぼす可能性が高くなります。勾留を回避するには、迅速かつ適切な対応が必要です。
本記事では、勾留に着目し、拘留との違いや要件などについて、詳しく解説していきます。
目次
勾留とは
「勾留」とは、逮捕された人の身柄を、一定期間、刑事施設に拘束する手続きです。これは、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合や、被害者に危害を加える可能性があると判断された場合に行われます。勾留が認められると、被疑者は留置場などに収容され、自由を制限されることになります。
勾留には、起訴前の「被疑者勾留」と、起訴後の「被告人勾留」の2種類があります。
被疑者勾留は、裁判官が勾留を認めるとまず10日間実施され、必要に応じてさらに10日間延長されるため、最大で20日間の拘束が可能です。一方、被告人勾留は起訴後に行われ、原則として刑事裁判が終わるまで身柄拘束が続きます。
いずれの場合も、長期間の拘束となる可能性があるため、仕事や家庭、社会生活に大きな影響を及ぼすことになります。
勾留と拘留の違い
「勾留(こうりゅう)」と「拘留(こうりゅう)」は、どちらも人の自由を制限する制度ですが、意味は大きく異なります。
勾留と拘留の違い
-
勾留
被疑者や被告人が証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断される場合に、裁判所から許可を得て一定期間身柄拘束する措置。 -
拘留
軽微な罪を犯した被告人を1日以上30日未満の期間、刑事施設で身柄拘束する刑罰の一種。
どちらも「こうりゅう」と読みますが、勾留は捜査のための拘束、拘留は刑罰としての拘束という違いがあります。
勾留と留置の違い
勾留と留置は、どちらも逮捕した人物の身柄を拘束する措置ですが、「身柄拘束の期間」と「決定を下す者」に違いがあります。
勾留と留置の違い
-
勾留
勾留は、検察官の請求と裁判官の決定によって行われる長期間の身柄拘束を指します。 -
留置
留置は、警察が行う逮捕直前の一時的な身柄拘束を指します。
留置は、警察が単独で行う一時的な身柄拘束であるため、裁判官の承認を得る必要はありません。
警察署内に収容されることを意味する留置は、被疑者が逮捕後に警察の下にいる最大48時間まで可能です。つまり、留置は検察に送致されるまで(逮捕後48時間以内)に終了するのが基本です。
勾留と逮捕の違い
「勾留」と「逮捕」は、どちらも警察などが人を拘束する手続きですが、意味や期間が違います。
勾留と逮捕の違い
-
勾留
勾留は、逮捕に続き行う長期の身柄拘束で、検察官の請求に基づいて裁判官が決定を下します。 -
逮捕
逮捕は、逃亡や証拠隠滅を防止するために、即座に行う短期間の身柄拘束です。
つまり、逮捕は「すぐに身柄を確保するための措置」、勾留は「捜査を進めるための長期的な拘束」といえます。
勾留の要件
勾留の要件は、被疑者または被告人に「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」があり、以下のいずれかに該当することです。
- 住居不定である
- 証拠隠滅のおそれがある
- 逃亡のおそれがある
身柄拘束は、人の自由を奪う行為であるため、人権侵害にもつながるおそれがあります。そのため、法律で定められた要件を満たした場合に限り、勾留が認められます。
住居不定である
逮捕前に、ホームレス状態であったり、ネットカフェ暮らしをしていたりすると、住居不定と認定されるでしょう。
住居不定の被疑者は、釈放した場合に所在不明となるおそれが大きく、捜査及び刑罰権の行使に支障をきたすおそれが大きいため、住居不定であれば、勾留される可能性が高くなります。
証拠隠滅のおそれがある
証拠隠滅は、物的な証拠隠滅、例えば、盗んだものを捨てるとか、盗撮した画像をスマホ内から消去するなどがありえます。
証拠隠滅の対象はそのような物的証拠にとどまらず、人的証拠も含まれます。
例えば、事件に関して共犯者と口裏合わせをする、事件の目撃者に自己に有利な証言をするように働きかけるなどです。
逃亡のおそれがある
逃亡のおそれは、被疑者や被告人の所在が不明になる可能性があることを意味します。逃亡のおそれの判断要素には、「被疑者や被告人の状況」「犯した罪の重さ」などに加え、「共犯者の有無」といったさまざま事情が挙げられ、これらを総合的に考慮して判断されます。
逮捕から勾留までの流れ
逮捕から勾留が決定するまでの流れは、以下のとおりです。
- 逮捕
逮捕後は、警察からの取り調べを受けながら、留置場に収容されます。 - 送致
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄と事件の資料を検察に引き継ぎます(送致)。 - 勾留請求
送致後は、検察からの取り調べを受け、送致されてから24時間以内に検察官によって勾留請求を行うかどうかの判断が下されます。勾留請求は、裁判官に対して行われます。 - 勾留質問
検察官から勾留請求があると、裁判官は、勾留の可否を判断するために、被疑者に対し勾留質問を行います。 - 勾留
裁判官が勾留請求を認めると、10日間の勾留が実施されます。捜査状況次第では、さらに10日間の延長が可能ため、勾留は最大で20日間行えます。
勾留の決定は、最終的に裁判官が行いますが、その前提として検察官による「勾留請求」が必要です。検察官が勾留を請求しなければ、被疑者は釈放されるため、長期間の身柄拘束を避けるには、検察官に勾留請求をしないよう働きかけることが重要です。
裁判官が勾留請求を認めるかどうかを判断する際には、「勾留質問」という手続きが行われます。これは、裁判官が被疑者本人から事情を聞き取る場であり、その内容によっては勾留請求が却下されることもあります。
勾留後の処分
裁判官が検察官からの勾留請求を認めると、まず10日間の勾留が行われ、その後は捜査状況に応じて勾留期間が延長されます。延長は+10日間可能ですので、最大で20日間勾留される可能性があります。
検察官は、勾留期間満了日までに被疑者を起訴するか・不起訴とするかを判断し、「不起訴」または「略式起訴」と判断された場合は、勾留期間満了後に釈放されます。しかし、「起訴」された場合には、起訴後も勾留が続きます。
起訴後勾留となれば、刑事裁判が終わるまで勾留が続くため、仕事や学校、対人関係などに悪影響が及ぶ可能性が高まります。そのため、「保釈」(裁判所が定める保釈保証金を納めることで一定期間身柄の拘束を解いてもらえる制度)を請求して、一時的な釈放を求めます。
ただし、保釈を認めてもらうには、法律で定められる要件を満たし、裁判所が保釈を許可した場合に限られます。
起訴の基礎知識や主な流れなどについては、以下のページをご覧ください。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
勾留の期間はどのくらい?
勾留の期間は、起訴前と起訴後で異なり、起訴前に行われるものを被疑者勾留、起訴後に行われるものを被告人勾留といいます。
被疑者勾留の場合
被疑者勾留は、警察に逮捕されてから起訴されるまでの身柄拘束を指します。
起訴までの身柄拘束は、原則20日間までとされているため、勾留期間は10日~20日間です。
被告人勾留の場合
被告人勾留は、起訴されてからの身柄拘束を指します。
起訴後の勾留期間は、原則2ヶ月と決められていますが、継続する必要があると認められた場合は、1ヶ月ごとに更新できます。
起訴前の勾留
起訴前の勾留は、警察に逮捕されてから起訴されるまでの身柄拘束であるため、勾留は基本的に短期間となります。起訴前の勾留期間は、原則10日間(さらに10日間の延長が可能なため、最大で20日間)とされていますが、10日以内に釈放される場合もあります。
たとえば、比較的軽微な犯罪の場合には、被害者と示談することなどにより、勾留されても10日以内に釈放される可能性があります。
検察官は、勾留満了日までに起訴もしくは不起訴の決定を下さなければなりませんが、勾留期間中にその判断ができない場合には、処分保留とします。
処分保留とは、検察官が起訴・不起訴の決定を下さずに、一旦被疑者を釈放する処分です。処分保留で釈放されても、手続上、事件はまだ終了していないため、起訴・不起訴・再逮捕の可能性は残ったままです。
起訴後の勾留
起訴後の被告人勾留の期間は、起訴されてから2ヶ月です(刑事訴訟法60条2項)。
勾留の期間は1ヶ月ごとに更新可能であり(刑事訴訟法60条2項)、実務上、裁判が継続する限りは、勾留期間も延長され続けることが通常です。
起訴後の勾留から解放されるには、起訴後から認められる保釈請求等の手続きが必要です。
勾留延長の「やむを得ない事由」
起訴前の勾留は、最大で20日間まで認められています。ただし、勾留期間を延長するには、刑事訴訟法第208条第2項に定められた「やむを得ない事由」が必要です。
この「やむを得ない事由」としては、以下のような事情が挙げられます。
- 共犯者、関係者がいる
- 被疑者や関係者の供述が異なる
- 共犯者の身柄確保が遅れている
- 多数の被疑事実がある
- 関係者が多く、証拠の収集に時間がかかる
- 証拠の解析に時間がかかる
- 被疑者が黙秘しており、真相解明に時間がかかる など
これらの事情が認められると、検察官は裁判官に対して勾留延長を請求します。裁判官が延長を許可した場合、勾留期間はさらに10日間延びることになります。特に重大事件や組織的犯罪では、勾留延長が行われる可能性が高いといえます。
勾留中に面会や連絡をとることはできる?
接見禁止処分がなされていなければ、勾留中でも被疑者・被告人と面会や連絡をとることができます。
接見禁止処分は、証拠隠滅や共犯者との口裏合わせなどを防止するために、弁護人以外の人物との面会や手紙のやり取りを禁止する処分です。
接見禁止処分は、被疑者が罪を否認している事件や組織犯罪の可能性が高い事件の場合に出されやすいです。
この接見禁止処分がなされていなければ、弁護士以外の人物(家族や知人等)でも、被疑者・被告人と面会したり、差入れしたりできます。
なお、接見禁止処分は、裁判所に対する「準抗告または抗告」や「接見禁止処分の一部解除」の申立てにより解除できる可能性があります。準抗告・抗告とは、裁判所が下した処分について、弁護士または検察官が不服を申し立てる手続きで、被疑者の段階で行う手続きを準抗告といいます。
一方で抗告は、被告人の段階で行う手続きを指します。これらの申立てを裁判所が認めると、接見禁止処分の全部または一部が解除されます。
接見について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
勾留の回避・早期釈放のポイント
勾留の回避や早期釈放を目指すには、以下のポイントを押さえる必要があります。
- 早急に弁護士に依頼する
- 準抗告・勾留取消請求を行う
- 不起訴処分を目指す
- 保釈請求する
事前に上記のポイントを押さえておくことで、勾留の回避や早期釈放となる可能性を高められます。逮捕された方や逮捕されそうな方は、ぜひご参考になさってください。
早急に弁護士に依頼する
刑事事件の手続きは、想像以上のスピードで進んでいくため、勾留の回避や早期釈放を目指すには、早急に弁護士に依頼する必要があります。
刑事事件で依頼できる弁護士には、私選弁護人と国選弁護人が挙げられ、選任できるタイミングや弁護士費用の負担に違いがあります。
私選弁護人と国選弁護人の違い
| 選任できるタイミング | 弁護士費用の負担 | |
|---|---|---|
| 私選弁護人 | いつでも | 自分または家族が負担する |
| 国選弁護人 | 勾留確定後または起訴後 | 国が負担する |
私選弁護人は、自分または家族が直接契約して依頼する弁護士であるため、逮捕前または逮捕直後からなど、いつでも弁護士を選任できます。一方で、国選弁護人は、経済的な理由で弁護士への依頼ができない場合に、国が弁護士を選任してくれる制度です。
国選弁護人が被疑者勾留が確定した後でなければ依頼できません。勾留の回避や早期釈放を目指すとなれば、勾留が確定する前に弁護活動を始める必要があるため、私選弁護人への依頼が不可欠でしょう。私選弁護人であれば、早期の段階から弁護活動を始められます。
国選弁護人と私選弁護人の違いやメリットなどについて知りたい方は、以下のページをご覧ください。
準抗告・勾留取消請求を行う
勾留決定に対する準抗告は、勾留決定をした裁判官の判断が不当であることを主張し、勾留決定された判断の変更を求める、勾留決定を争う不服申立の手続として、よく申し立てることがあります。
勾留取消請求は、勾留決定後の事情の変化を理由として、事後的に勾留を取消してもらう手続きです。
例えば、勾留決定後に被害者と示談が成立したことを理由に、勾留取消請求をすることが考えられます。
不起訴処分を目指す
不起訴処分となれば、長期間の勾留を回避し、早期釈放を実現できます。また、捜査機関から捜査対象となった履歴である前歴は付きますが、“前科”は付きません。そのため、不起訴処分の獲得は、逮捕された後にもっとも目指すべき結果です。
被害者が存在する刑事事件の場合は、被害者との示談成立が刑事処分の判断に大きく影響します。「犯行態様が悪質でない」「初犯である」なども有利な情状として考慮されますが、被害者との示談成立にはより強い効力があります。
しかし、被害者との示談成立は決して容易ではないため、刑事事件に精通した弁護士への依頼が不可欠でしょう。
「不起訴にしたい・前科を付けたくない」と思われる方は、以下のページもご参考になさってください。
保釈請求する
勾留を避けられなかった場合は、「保釈請求」を行い、一時的に釈放されることを目指すことが重要です。
保釈は、法律で定められた条件を満たし、裁判所が指定する保釈金を納めることで認められます。保釈が許可されると、被告人は釈放され、通常の生活に戻ることができます。
保釈金は、裁判所の条件を守っていれば、裁判終了後に全額返還されます。ただし、保釈金の金額は事件の内容や被告人の経済状況によって異なり、罪が重く被害が大きいほど高額になる傾向があります。
勾留に関するよくある質問
未決勾留の日数はどのように数えますか?
未決勾留とは、被疑者や被告人が刑事裁判で判決が出るまでの間、刑事施設に身柄を拘束されている状態を指します。起訴前の勾留(被疑者勾留)と、起訴後の勾留(被告人勾留)の両方を含む言葉です。
未決勾留の日数は、実際に勾留されていた期間をもとに数えられます。具体的には、「勾留が始まった日から判決が言い渡される前日まで」が未決勾留日数となります。
勾留は人の自由を制限する重大な措置であるため、裁判官の判断によって、未決勾留の日数の一部または全部が刑期に算入されることがあります。これは、刑の軽減につながる可能性がある重要なポイントです。
勾留中の生活は何をして過ごすのでしょうか?
勾留中の生活は、起床や食事、入浴、就寝時間などが細かく定められた制限の多い環境で過ごします。自由時間や外部との接触は限られ、読書や面会、取り調べなども施設のルールに厳しく従う必要があります。当然、携帯電話やインターネットの使用、外部との自由なやり取りは禁じられているため、勾留中は不安や孤独を感じやすいです。
また、裁判所から接見禁止処分がなされた場合には、弁護人以外の接見が禁じられ、解除されるまでその状態が続きます。
勾留される場所はどこになりますか?
勾留される場所は、起訴前と起訴後で異なるのが一般的です。
起訴前は主に警察署内の「留置場」、起訴後は法務省が管轄する「拘置所」に収容されます。
留置場は各警察署に設置されており、数も多く、身柄の一時的な拘束に使われます。一方、拘置所は全国に限られた数しかなく、起訴された被告人や死刑囚などが収容される施設です。
ただし、地域によっては拘置所が遠方にあるため、起訴後も引き続き留置場に収容されるケースもあります。反対に都市部では、勾留が決定するとすぐに拘置所へ移送されることが一般的です。また、拘置所の収容人数が限界に達している場合には、例外的に留置場が代用されることもあります。
勾留された・勾留されそうな場合は早急に弁護士法人ALGにご相談ください
逮捕された場合、勾留されないことが極めて重要です。
勾留されると最大10日間拘束され、仕事や家庭など社会生活に大きな影響が生じます。
勾留されないように、被疑者に有利な証拠を収集して、検察官や裁判官に勾留しないように働きかけることができるのは、弁護士だけです。
また、勾留されたまま起訴されてしまった場合、勾留が続いてしまうので、速やかに保釈請求をしなければなりませんが、保釈請求を的確におこなうには、弁護士の関与は不可欠といえるでしょう。
身柄事件は、時間との勝負です。家族が逮捕されてしまった場合、早急に弁護士に相談してください。