弁護士依頼前
約729万円
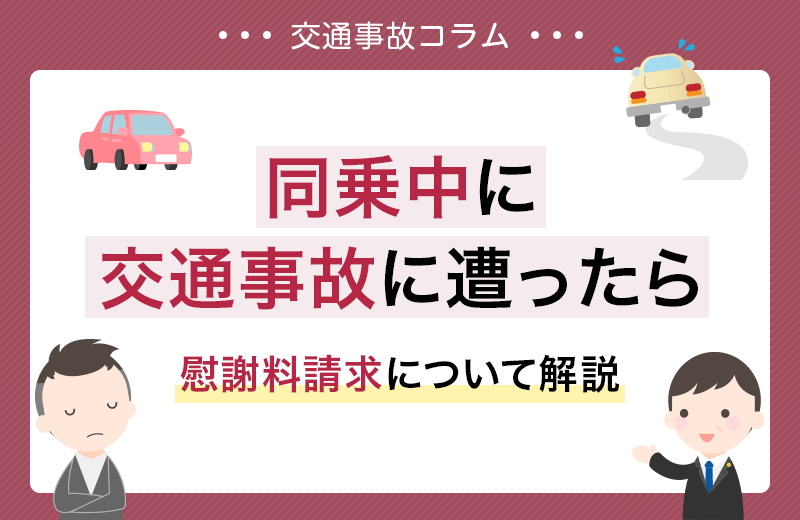
交通事故は自分の車を運転しているときだけでなく、他人が運転する車に乗っているときにも起こるものです。
友人や知人、家族などが運転する車に乗っているときに、交通事故の被害にあって怪我をした場合、同乗者は誰に対して慰謝料などの損害賠償金を請求すればよいのでしょうか?
この記事では、同乗者の事故をいくつかのパターンに分けて、慰謝料の請求相手や相場、同乗者が使える保険などについて解説します。同乗中の事故に遭われた方は、ぜひご一読ください。
弁護士依頼前
約729万円

弁護士依頼後
約1275万円
適正な賠償額を獲得
目次
友人や家族などが運転する車に同乗していて事故に遭い、怪我をした場合、同乗した車の運転者と相手方車両の運転者のうち、事故の責任がある方、つまり過失がある方に、慰謝料などの損害賠償金を請求することになります。
どちらにも過失がある場合は、両方に対して、それぞれ全額の賠償金を請求することが可能です。
相手方車両の運転者(以下、相手方)の過失が100%の場合は、相手方にのみ、慰謝料などの損害賠償金を請求することが可能です。
運転者に過失がなければ、運転者に不法行為は成立せず、損害賠償責任が生じないためです。
例えば、同乗する車が後続車から追突されたり、センターラインオーバーや信号無視により衝突されたりしたなど、いわゆるもらい事故のケースがあてはまります。
このケースでは、相手方が加入する自賠責保険や任意保険(対人賠償保険など)から、賠償金が支払われるのが通例です。
相手方が無保険等の理由で賠償金を支払えない場合は、運転者が加入する人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険を利用し、保険金を受け取るという方法があります。
運転者に100%の過失がある場合は、同乗者への不法行為は運転者が一人で行ったものとなるため、運転者にのみ、損害賠償金を請求することになります。
例えば、運転者が一方的に相手方に追突した場合や、運転者が前方不注意で電柱にぶつかるなど自損事故を起こしたようなケースがあてはまります。
このケースでは、運転者が加入する自賠責保険や任意保険(対人賠償保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険など)から、賠償金が支払われるのが通例です。
運転者と相手方のどちらにも過失がある場合は、お互いが共同で不法行為を行った(事故を発生させ、同乗者に怪我をさせた)ことになるため、同乗者はどちらに対しても、全額の損害賠償金を請求できます。
例
損害賠償金が1000万円の場合
ただし、2倍の額がもらえるというわけではなく、運転者または相手方が同乗者に1000万円全額支払うと、他方からさらに賠償金を支払ってもらうことはできなくなります。
交通事故の慰謝料には、以下の3種類があります。
それぞれどのような場合に受けとれる慰謝料なのか、概要を表にまとめましたのでご参考ください。
| 入通院慰謝料 | 事故により怪我を負い、入院や通院を強いられた精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。 初診日~完治または症状固定までの通院期間、実際に入通院した日数、通院頻度、怪我の症状、治療内容などに基づき算定される。 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 事故により後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対して支払われる慰謝料。 自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、認定された等級に応じた慰謝料が支払われる。 |
| 死亡慰謝料 | 事故により被害者が死亡した場合の、本人及び遺族の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料。 被害者の家庭内での立場や遺族の数、扶養人数などに基づき算定される。 |
また、交通事故では、慰謝料を計算するときに使用する3つの基準があります。
それぞれの特徴を以下の表にまとめましたので、ご参考ください。
| 自賠責基準 | 自賠責保険による支払基準で、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準。 被害者側に過失がない事故の場合は最も低額となることが多い。入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり。 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。 自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向あり。 |
| 弁護士基準 | 過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。 弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われ、被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となることが多い。(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載) |
慰謝料の金額は自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に高額になります。
そのため、適切な慰謝料を受け取りたいとお考えの方は、弁護士への相談をおすすめします。
なお、同乗車の慰謝料も運転者が被害者であるときと同じく、これらの算定基準を用いて計算されるため、交通事故の被害が運転者か同乗者かで慰謝料の相場が変わることはありません。
交通事故の慰謝料について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
運転者と相手方どちらにも賠償金を請求できる場合、それぞれにいくらずつ請求するかは同乗者が自由に決められます。例えば、運転者と相手方どちらにも800万円の賠償金を請求できるとします。
一方に600万円、他方に200万円請求してもよいですし、一方に800万円全額請求するのでも構いません。
ただし、全体の賠償額は変わらないため、一方から800万円の賠償金を全額受け取ったなら、他方からさらに払ってもらうことはできなくなります。
また、800万円の賠償金のうち、運転者と相手方が何割ずつ負担するかは、過失割合などをもとに両者間で決めて後日清算されます。
なお、賠償金の踏み倒しを防ぐためには、任意保険に加入している側や資力がある側に多く請求するのが望ましいでしょう。
同乗中に事故に遭い、むちうちの怪我を負った場合の慰謝料相場を実際に計算してみましょう。なお、任意保険基準は独自に算定基準を持っており、非公開であるため割愛させていただきます。
【例】他覚的所見のないむちうちで通院3ヶ月(実通院日数40日)の場合の入通院慰謝料相場自賠責基準
自賠責基準では、1日4300円と定められており、以下の式のいずれか金額が低い方が採用されます。
これを例に当てはめると、以下のようになります。
よって、自賠責基準での入通院慰謝料相場は34万4000円となります。
弁護士基準
弁護士基準では、「赤い本」に掲載されている入通院慰謝料算定表を用いて算出します。今回は他覚的所見がないむちうちなので、別表Ⅱ(軽傷用)を使用します。
入院0ヶ月、通院3ヶ月の交わる部分を確認すると、入通院慰謝料相場は53万円となります。
| むちうち等他覚的所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||
| 通院 | A’B’ | 35 | 66 | 92 | ||||||||||||
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | ||||||||||||
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | ||||||||||||
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | ||||||||||||
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | ||||||||||||
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | ||||||||||||
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | ||||||||||||
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | ||||||||||||
次に、むちうちの症状が後遺症として残り、後遺障害等級14級が認定された場合の慰謝料相場を見ていきましょう。
後遺障害等級14級の慰謝料は自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円と定められています。入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を合計すると、自賠責基準で66万4000円、弁護士基準で163万円となり、大きな差が生まれることが分かります。
| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料 | 34万4000円 | 53万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 |
むちうちの慰謝料計算方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
相手方保険会社から提示される慰謝料は、弁護士基準で算出される金額より低くなるケースが少なくありません。
適正な慰謝料を請求するためには、ご自身の状況に応じた相場を把握しておくことが重要です。
以下の自動計算機では、必要事項を入力するだけで、受け取るべき慰謝料の相場を簡単に算出できます。ぜひご活用ください。
なお、慰謝料の金額は個別事情によって大きく異なりますので、詳細を知りたい方は弁護士への相談をおすすめします。
合わせて読みたい関連記事
増額しなければ成功報酬はいただきません
運転者に過失があったとしても、同乗者の過失は基本的には0とされています。
しかし、同乗者が運転者の安全運転の妨害をしたり、事故を起こした車の所有者であったりする場合は、同乗者にも事故を起こした責任があるとして、同乗者の過失の程度に応じて、慰謝料が減額されることがあります。
さらに、事故状況によっては、同乗罪または車両提供罪に問われ、刑罰が科される可能性もあります。
以下のようなケースに当てはまる場合は、運転者の安全運転の妨害をしたとして、同乗者が請求できる慰謝料などの損害賠償額が減額される可能性があります。
運転者が飲酒していることを同乗者が知りながら、運転者に運転を要求したり、見て見ぬふりをして同乗したりした場合は、同乗者にも事故を起こした過失があるとされ、損害賠償額が20~25%程度減額されるケースがあります。
なお、飲酒運転を知りながら同乗した者は、以下の刑が科される可能性があります。
同乗罪として
また、飲酒運転を知りながら車を貸した者も、以下の刑が科される場合があります。
車両提供罪として
運転者が無免許(免許の有効期限切れ、免許停止など)であることを知っていながら同乗した場合、同乗者にも事故を起こした過失があるとされ、損害賠償金が減額される可能性があります。
ケースにより異なりますが、20%程度減額された例もあります。
なお、無免許運転を知りながら同乗した者は、同乗罪として、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、また、無免許運転を知りながら車を貸した者も、車両提供罪として、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を受ける可能性があります。
運転者が危険運転(スピード違反、信号無視、あおり運転など)をしていながら、同乗者が止めようとしなかったり、運転者をあおったりした場合には、同乗者にも事故発生の過失が認められます。
このようなケースで同乗者の責任が重いと判断されると、損害賠償額が10~30%程度減額されることがあります。
なお、運転者に危険運転致死傷罪、妨害運転罪などが成立する場合には、同乗者も共犯として刑罰を受ける可能性があります。
自分の車を他人に運転させて同乗しているときに、運転者が人身事故を起こした場合、運転者だけでなく、同乗者も車の所有者として、損害賠償責任を負います。
これを運行供用者責任といいます(自動車損害賠償保障法3条)。
この場合、運転者と所有者は、被害者に対してそれぞれ全額の賠償責任を負うことになります。
被害者に支払うべき賠償金額が、所有者が加入する自賠責保険の支払い上限額を超える場合には、所有者が加入する任意保険から賠償金を支払うか、任意保険に未加入の場合は、所有者自身が負担しなければなりません。
シートベルトは搭乗者の身を守るものであり、全搭乗者に着用が義務付けられています。また、チャイルドシートについても、0~5歳の子供を車に乗せる時は、着用が必須とされています。
特に小さな子供は、チャイルドシートの使用を嫌がることもあるでしょう。
しかし、「かわいそうだから」とチャイルドシートを使用せず事故に遭ってしまうと、大怪我を負うリスクが高く、最悪の場合死亡事故につながるおそれもあります。
このように、シートベルトやチャイルドシートを正しく着用していないと、正しく着用して事故に遭った場合より、大きな事故となる可能性が高くなります。
そのため、そうした過失が損害拡大に起因したものと判断され、損害賠償額が減額される可能性があります。
運転者の好意により無償で同乗していた際に事故に遭うと、慰謝料が減額される可能性があります。これは「好意同乗による減額」に該当し、同乗者にも一定の責任があると判断されることがあるためです。
ただし、すべての事例で減額が認められるわけではありません。
単に車に乗せてもらっただけで、事故に関して何の落ち度もない場合には、基本的に減額されません。
一方、以下のような状況では、同乗者にも一定の責任があると判断され、慰謝料が減額される可能性もあります。
対人賠償責任保険は、被害者が契約者の家族(配偶者、父母、子供)である場合には適用されません。そのため、運転者である家族に賠償金を請求した場合、家族が加入する自賠責保険と家族自身から賠償金が支払われることになります。
とはいえ、家族から賠償金を受け取っても、そもそも家計が一緒であるため、意味がないといえるでしょう。
そこで、家族が賠償金の請求相手となる場合は、以下のような対処法を検討しましょう。
慰謝料の他にも、同乗者として事故の被害にあった場合、以下のような損害賠償金を請求することができます。
交通事故の損害賠償の相場について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
交通事故で同乗中に怪我をしてしまった場合でも、状況によっては保険を使って補償を受けられます。
ただし、どの保険を利用できるかは、請求相手と加入している保険によって異なります。
以下で詳しく見ていきましょう。
交通事故で同乗者が怪我をした場合、まずは相手方の自賠責保険から補償を受けるのが一般的です。
自賠責保険では、治療費や入通院慰謝料、休業損害などの「傷害部分」について、最大120万円までが支払われる仕組みになっています。
ただし、損害額がこの上限を超える場合には、相手方が加入している任意保険の「対人賠償責任保険」によって、超過分が補償されます。
なお、自賠責保険の支払いは、通常、任意保険会社との示談が成立した後に一括で支払われるケースが多く、交渉の内容によって金額や支払い時期が変わることもあります。
また、相手方が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険の上限を超えた損害について、相手方本人に直接請求する必要があります。
自賠責保険の慰謝料相場や限度額について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
同乗した車の運転者が加入している任意保険に人身傷害補償保険がついている場合、同乗者も保険金の支払い対象となります。
人身傷害補償保険とは?
契約者本人・契約車両の同乗者が事故で死傷した際に適用され、治療費や慰謝料、休業損害などが補償されます。
過失相殺が行われないため、被害者の負担が軽減されるメリットがあります。
さらに、支払いのタイミングが比較的早く、示談成立を待たずに受け取れるケースもあるため、事故後の生活支援としても有効です。
同乗した車の運転者が加入している任意保険に搭乗者傷害保険が含まれている場合、同乗者にも保険金が支払われます。
搭乗者傷害保険とは?
契約車両に乗っていたすべての搭乗者(運転者を含む)が事故によって死傷した場合に、保険金が支払われるものです。
この保険では、あらかじめ契約時に設定された定額の保険金が支払われるため、実際の損害額に関係なく、迅速な補償が可能です。
また、過失割合の影響を受けない点も特徴で、事故の責任が一部搭乗者にある場合でも、減額されることなく保険金を受け取ることができます。
同乗者自身やその家族が人身傷害補償保険に加入している場合、事故によって怪我を負うと保険金を受け取れる可能性があります。
この保険は、契約者本人だけでなく、契約内容によっては家族や同乗者にも適用されることがあり、補償範囲の広さが特徴です。
特に、契約プランによっては他人の車に同乗していた場合でも補償対象となることがあり、事故の状況にかかわらず治療費や慰謝料、休業損害などが支払われるケースもあります。
増額しなければ成功報酬はいただきません
同乗中に事故に遭った場合は、弁護士への相談をおすすめします。
同乗中の事故では、誰に慰謝料を請求すれば良いのか分からないケースも多いと思いますが、弁護士であれば適切な慰謝料を請求できるよう、交渉していきます。
また、弁護士費用が心配で、弁護士への依頼をためらってしまう場合もあるでしょう。
同乗中の事故であれば、ご自身に弁護士費用特約がついていない場合でも、運転者や家族の特約が使用できる可能性があります。
弁護士費用特約は、弁護士相談料、弁護士費用を一定額保険会社が負担してくれるものであり、使用できれば費用を気にせずに依頼できます。まずは保険を確認してみましょう。
弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
事故の概要
依頼者が親族の運転する車に同乗中、運転者がハンドル操作を間違え、ガードレールにぶつかるという事故が発生しました。依頼者は肋骨骨折等の怪我を負い、約1年の入通院治療後、後遺障害等級併合9級の認定を受けました。
その後、相手方(同乗車の運転者)から賠償金額729万円が提示されましたが、適正な金額であるか判断できず、弁護士法人ALGにご依頼されました。
事件進捗
弁護士が相手方の示談案を精査したところ、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、逸失利益などの提示額が弁護士基準よりも相当低い金額に抑えられていました。
そこで、弁護士基準による慰謝料の増額交渉を行いました。
結果的に、当方の主張が認められ、相手方の当初の提示額から500万円以上アップした約1275万円の賠償金(既払い金を除く)を獲得することに成功しました。
事故の概要
依頼者(19歳男性)は、友人からドライブに誘われ、後部座席に乗車したところ、運転者である友人が暴走して、電信柱にぶつかり、依頼者が車外に投げ出されるという事故が発生しました。
相手方(運転者である友人)は、自動車が改造車で後部座席にシートベルトがないことをわかっていて同乗した点に着目し、以下の提示をしました。
しかし、依頼者は相手方の暴走により重い高次脳機能障害を負ったため過失割合に納得がいかずご依頼されました。
事件進捗
担当弁護士は、裁判で弁護士基準の損害額を目安に、依頼者と相手方の過失割合を「2:8」に修正するよう主張し、当方の主張を認める裁判上の和解が成立しました。
依頼者は相手方の当初の提示額から5900万円以上アップした、約8000万円の賠償金を受け取りました。
同乗中の事故は、事故の責任が誰にあるかにより慰謝料の請求先が変わり、運転者が家族である場合は使えない保険の種類もあるため、損害賠償請求が複雑になりやすく、当事者間でもめやすい傾向にあります。
また、同乗者と運転者が知り合いであるため慰謝料を請求しにくいというのも、同乗中の事故ならではの事情でしょう。
弁護士法人ALGは、同乗者事故の事案を多く取り扱った実績がありますので、経験的知識をフル活用し、同乗者の方に有利な条件での示談成立と慰謝料の増額を目指し、尽力することが可能です。
同乗中の事故でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
