弁護士依頼前
約17万円
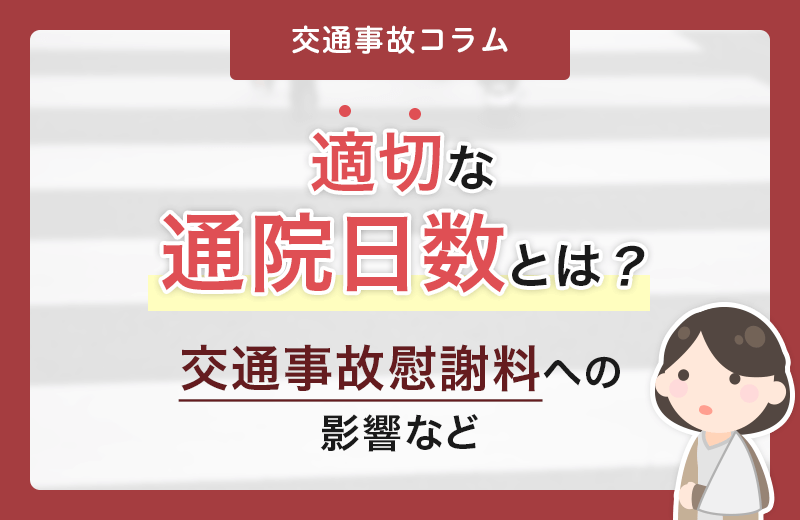
交通事故の慰謝料は通院日数によって金額が変動します。ただし、やみくもに通院日数を増やせばいいものではありません。怪我の程度に応じて適切な通院頻度で治療をすることが重要です。
交通事故の慰謝料を計算するには、3つの基準があります。その中でも最も高額になる弁護士基準では、通院日数ではなく通院期間で計算するため、日数に影響されずに慰謝料が高額になる可能性が高まります。
この記事では、慰謝料と通院日数の関係や3つの算定基準と計算方法、適切な通院頻度などについて解説していきます。
弁護士依頼前
約17万円

弁護士依頼後
約65万円
約48万円の増加
目次
交通事故の慰謝料は、実際の通院日数や通院期間によって金額が増減することがあります。
慰謝料には、
の3つがあります。
このうち、通院日数や通院期間が関係する慰謝料は入通院慰謝料、後遺障害慰謝料です。
死亡慰謝料については、死亡した被害者の属性や遺族の人数、扶養家族の有無により決まるため、通院日数の影響を受けません。
入通院慰謝料とは、交通事故の怪我で入院・通院したことによる精神的苦痛に対する補償です。
精神的苦痛とはいえ、苦痛の感じ方は人それぞれであり、目に見えるものではありません。
そこで、入通院慰謝料額を算定するため、実通院日数や通院期間をもとにして計算していきます。
そのため、入通院慰謝料には直接的に通院日数や通院期間の長さが影響します。
| 実通院日数 | 実際に通院した日数 |
|---|---|
| 通院期間 | 治療開始日~完治または症状固定日までが基本 |
実通院日数をもとに入通院慰謝料を計算するか、通院期間をもとに計算するかは、用いる算定基準によって異なります。
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
後遺障害慰謝料の金額は、認定を受けた後遺障害等級ごとに決められているので、通院日数や期間による影響を直接的に受けることはありません。
例えば、最も症状が重い後遺障害等級1級なら、弁護士基準で2800万円、最も症状が軽い後遺障害等級14級なら110万円と定められています。そのため、通院日数や期間によって後遺障害慰謝料が増減することはありません。
しかし、後遺障害等級認定では、ケガの治療経過についても考慮されるため、通院期間に比べて通院日数が極端に少なかったり、通院期間が短すぎたりすると、後遺障害等級がそもそも認定されない可能性があります。
この意味で、後遺障害慰謝料は通院日数や期間によって間接的に影響を受けます。
例えば、むちうちで後遺障害14級に認定されるためには、一般的に通院日数合計60日以上、治療期間6ヶ月以上が必要とされていますのでご注意ください。
適切な交通事故慰謝料を受け取るためには、むちうちなど軽傷の場合、週2~3日、月10日程度治療のために通院することをおすすめします。
通院期間に対して通院日数があまりに少なすぎると、慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
一方、通院日数が多すぎると、過剰診療と判断されて、治療費の支払いを早期に打ち切られたり、慰謝料が減額されたりするおそれがあります。
仕事や家事・育児などで忙しい方も多いでしょうが、損することがないよう、適切な頻度で通院することが大切です。
ケガの状況や治療経過等によって適切な頻度は変わってくるため、主治医や弁護士に相談し判断を仰ぐのが良いでしょう。
交通事故で負ったケガの通院日数が少ないと、適切な慰謝料を受け取れなくなる可能性があります。
通院日数が少なすぎると、相手方保険会社から怪我の程度が軽いとみなされ、入通院慰謝料が減額されるおそれがあります。
また、保険会社から治療費の支払いを早期に打ち切られる可能性もあります。治療費の打ち切りにともない治療も止めると、治療期間が短くなるため、入通院慰謝料も少なくなります。
さらに、通院日数が少ないと後遺症の程度も過小評価され、低い後遺障害等級しか認定されず、後遺障害慰謝料が低額になってしまう可能性があります。慰謝料の減額を防ぐためにも、主治医の指示に従いながら、適切な頻度で通院することが重要です。
通院日数が少ないことによる慰謝料への影響については、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
以下のようなケースでは、実通院日数×3.5で計算した日数を慰謝料算定の基礎となる通院期間とすることがあります。
【例】骨折で通院9ヶ月、実通院日数30日
このように慰謝料額に大きな差が生じることがわかります。
ただし、3.5倍ルールはあくまで例外です。
相手方から本ルールの適用を求められた場合は、症状の重さや通院頻度が少ない理由などを主張し、通院期間に基づき慰謝料算定するよう反論する必要があります。
通院日数とは、実際に通院のため病院へ行った日数を表しています。
そのため、次のような通院も通院日数として数えられます。
これに対して、1日に複数の病院を受診しても、通院日数を2日とすることはできません。通院のために使った日数は1日だけなので、通院日数は「1日」しかカウントされないのです。
次に、通院日数と通院期間の違いについて、表と具体例で見ていきましょう。
| 実通院日数 | 交通事故による怪我の治療のために、実際に通院した日数 |
|---|---|
| 通院期間 | 治療開始日~完治または症状固定日までが基本 |
具体例
⇒「通院期間」を聞かれているので、通院にかかった期間は2ヶ月となります。
増額しなければ成功報酬はいただきません
交通事故の慰謝料の算定には直接的、間接的に通院日数や期間が影響すると解説してきました。
次は慰謝料を算定する3つの基準について、下表で確認しましょう。
| 自賠責基準 |
|
|---|---|
| 任意保険基準 |
|
| 弁護士基準 |
|
これらの基準はそれぞれ計算方法が異なり、金額も大きく変わってきます。
以下で実際にどのように計算するのか見ていきましょう。
なお、任意保険基準については保険会社ごとに金額が異なるため、ここでは省略します。
自賠責基準による慰謝料は、実際に入通院した日数をもとに計算します。
1日あたりの入通院慰謝料である4300円に、
のどちらか少ない方をかけることで、慰謝料を算出します。
【例】通院期間1ヶ月、実際に通院した日数8日のケース
この場合、通院期間1ヶ月>8日×2であるため、対象日数は、短いほうの8日×2の16日となります。
そのため、慰謝料は、4300円×16日=6万8800円となります。
自賠責基準による慰謝料は、通院頻度を2日に1日以上、つまり月の半分以上通院しない限りは、入通院日数が大きな影響を与えることになります。
なお、自賠責基準を利用する場合の詳しい計算方法は、下記の記事で説明しています。
合わせて読みたい関連記事
弁護士基準では、交通事故の赤い本に載っている「慰謝料算定表」をもとに、入通院期間に応じた慰謝料を算出します。
算定表は2種類あります。他覚所見のないむちうちやすり傷など軽傷の場合は別表Ⅱ、骨折や脱臼など重傷の場合は別表Ⅰを使って算定します。別表Ⅰのほうが高額な基準です。
算定表上で考慮されるのは入院期間と通院期間なので、弁護士基準の場合、基本的には通院日数は金額に影響しません。また、弁護士基準によって算定される金額は、他の基準の場合と比べたときに、最も高額になりやすいと考えられています。
下の表は、入院せずに通院治療のみをした場合の入通院慰謝料の金額をまとめたものです。
| 通院期間 | 重傷 | 軽傷 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 28万円 | 19万円 |
| 2ヶ月 | 52万円 | 36万円 |
| 3ヶ月 | 73万円 | 53万円 |
| 4ヶ月 | 90万円 | 67万円 |
| 5ヶ月 | 105万円 | 79万円 |
| 6ヶ月 | 116万円 | 89万円 |
| 7ヶ月 | 124万円 | 97万円 |
| 8ヶ月 | 132万円 | 103万円 |
| 9ヶ月 | 139万円 | 109万円 |
なお、弁護士基準を利用する場合の詳しい計算方法は、下記の記事で説明しています。
合わせて読みたい関連記事
増額しなければ成功報酬はいただきません
後続車に追突されて怪我をした依頼者は、6ヶ月にわたって通院を続けたものの、実際に通院したのは30日にも満たない日数だけでした。
そのため、保険会社からは約17万円という弁護士基準を下回る慰謝料が提示されていましたが、依頼者にとっては到底納得できない金額でした。
そこで弊所は、通院期間を基準に計算する「弁護士基準」で慰謝料を算定し、合意を目指すことにしました。
まずは、通院日数と通院頻度が少なかった理由を依頼者から詳しく聞き取り、そのうえで、保険会社に対して依頼者の通院日数・頻度が合理的だったことを説明しました。
そして、依頼者の通院日数・頻度が合理的である旨を説明する「意見書」を添付して損害賠償を請求しました。
その結果、弊所が提示した金額の8割にあたる約65万円を慰謝料として認める内容で合意することができました。
この金額は、弁護士基準で算定した金額を上回るものでした。
リハビリのための通院は、身体の状態を事故前に戻そうとするものなので、治療の一環として通院日数に含まれます。
ただし、以下のような理由でリハビリのために通院した日は、通院日数に含むことはできません。
症状固定後のリハビリ
症状の改善を目的とした治療とはいえないので、通院日数には含まれません。
示談が成立した後のリハビリ
「治療の一環」といえる場合もありますが、一度した示談を撤回して再請求することは困難なため、通院日数に含めて治療費や慰謝料を請求することは基本的に認められません。
自宅療養中であってもギプス装着期間は入通院日数に含めます。
また、弁護士基準では、「入院待機中およびギプス固定中など安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることができる」とされています。
例えば、骨折の場合、患部を固定し安静にして折れた部分がくっつくのを待つだけで、積極的な治療を行わないこともあります。
このような場合、患部をギプス等で固定して自宅療養をしていた期間は治療期間といえるので、自宅療養期間を入院期間とみなして慰謝料を計算できる可能性があります。
通院日数や通院期間は慰謝料に直接的・間接的に影響を与えるため、適切な頻度で通院しましょう。
しかし、適切な通院日数を判断するためには、交通事故に関する知識はもちろん、医学的な知識も必要です。そのため、交通事故の通院日数については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の金額は、通院日数だけでなく、個々の被害者の事情によっても増減しますが、弁護士なら、交渉の落としどころを踏まえた妥当な請求額を見極めることができます。
ご依頼者様にとって最善の結果が得られるよう尽力しますので、通院するうえで疑問やご不安のある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
