主婦が交通事故に遭った場合の逸失利益はどうなる?
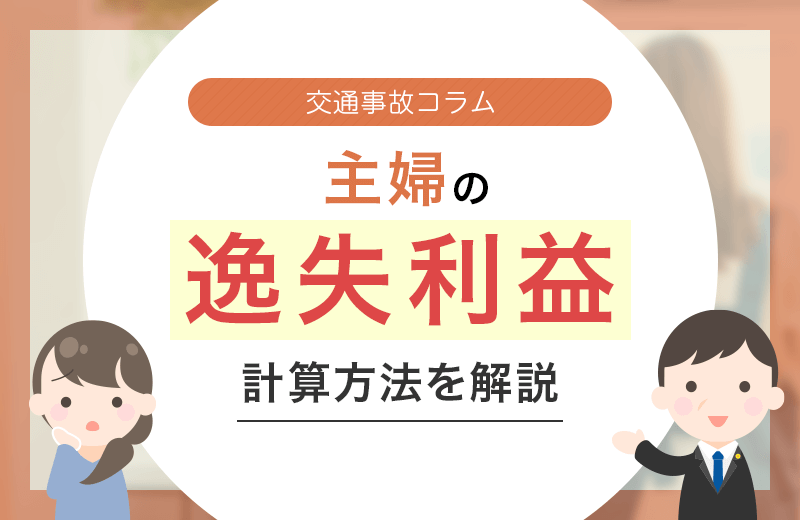
交通事故の被害に遭った場合、加害者に対して治療費や慰謝料などの損害賠償を請求することができます。
この損害賠償には、交通事故に遭わなければ将来得られたはずの収入である逸失利益も含まれます。
交通事故で被害者が亡くなってしまった場合や、被害者に後遺障害が残ってしまった場合に請求できる逸失利益は、被害者の事故前の収入をベースに算出します。
では、事故の被害者が主婦だった場合、逸失利益は請求できないのでしょうか。
計算方法を含めて、主婦が交通事故に遭った場合の逸失利益について本記事で詳しく解説していきます。
目次
主婦の逸失利益は認められる?
交通事故の被害者が主婦だった場合でも、逸失利益が認められる可能性があります。
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ将来得られたはずの利益のことで、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類があります。
| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害逸失利益は、事故による後遺障害がなければ得られたはずの将来の利益のことです。 後遺障害等級が認定された場合に請求できる逸失利益です。 |
|---|---|
| 死亡逸失利益 | 死亡逸失利益は、被害者が事故に遭わず生きていれば得られたはずの将来の利益のことです。 交通事故で被害者が亡くなってしまった場合に請求できる逸失利益です。 |
主婦が家族のために無償で行う家事労働は外注すれば対価が発生することから、経済的な価値があると認められています。
そのため、交通事故による死亡や後遺障害が原因で主婦の家事労働に支障をきたす場合は「事故による減収があった」と考えて、性別や年齢、専業・兼業を問わず逸失利益が認められます。
主婦・主夫の後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残らなければ得られたはずの将来の利益のことです。
事故によるケガの治療を続けても完治せず、医師に「症状固定」と診断された後、後遺障害等級が認定された場合に逸失利益の請求が認められます。
【後遺障害逸失利益の計算式】
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入
基礎収入とは、逸失利益を計算するにあたってベースとなる被害者の収入のことです。
事故前の現実の収入に基づいて基礎収入が算定されます。
以下、現実に収入が発生しない専業主婦(主夫)の基礎収入について詳しくみていきましょう。
専業主婦(主夫)の場合
専業主婦の場合、家事労働は現実に収入は発生しないものの、経済的な価値のある労働として認められることから、公的データを用いて金銭に換算し、基礎収入を求めます。
このとき用いられるのが、厚生労働省が毎年発表している労働者賃金に関する統計データ=賃金センサスです。
賃金センサスは、性別・年齢・学歴・雇用形態・就業形態等で平均賃金をまとめた資料で、専業主婦の場合は現実の収入の代わりに、基本的には、事故前年度の「女性労働者の全年齢平均賃金」を用いて基礎収入を算出します。
これは、性別によって家事労働の重度が変わらないことから専業主夫も同様で、男性であっても女性労働者の平均賃金を用います。
では、家事労働に加えてアルバイトやパートで現実に収入を得ている兼業主婦の場合はどうなるのでしょうか。
次項で詳しくみていきましょう。
兼業主婦の場合
兼業主婦の場合、現実の収入が賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金を上回っているかどうかによって、基礎収入の算定方法が異なります。
-
現実の収入が、女性労働者の全年齢平均賃金を上回っている場合
事故前の現実の収入に基づいて基礎収入を算出します。
-
現実の収入が、女性労働者の全年齢平均賃金を下回っている場合
事故前年度の女性労働者の全年齢平均賃金を用いて基礎収入を算出します。
なお、仕事と家事の両方に支障が出たからといって、現実の収入に家事労働分を加算することはありません。
労働能力喪失率
労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって5~100%と、それぞれ数値が設定されています。
具体的な各等級に対応する喪失率は下表の通りです。
後遺障害の等級は、症状固定と診断された後、後遺障害等級の認定申請を行うことで確定します。
従事する職業内容等によって評価が増減することがありますが、交渉段階では下表の数値を適用させることが多いでしょう。
| 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
| 100% | 100% | 100% | 92% | 79% | 67% | 56% |
| 第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
| 45% | 35% | 27% | 20% | 14% | 9% | 5% |
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、原則として、症状固定と診断された日から就労可能年数である67歳までの期間を指します。
ただし、後遺障害の内容・程度や、被害者の職業・年齢・健康状態などの個別の事情によって、労働能力喪失期間は調整されることがあります。
たとえば、交通事故における代表的なケガのひとつである「むちうち」による後遺症で、後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された場合の労働能力喪失期間は5年程度が目安になります。
高齢主婦の場合
後遺障害逸失利益の計算上、労働能力喪失期間を67歳までと区切っているため、67歳に近い、あるいは67歳を超えている高齢主婦の場合は調整が必要になります。
高齢主婦の労働能力喪失期間の具体的な定め方は、次のとおりです。
-
症状固定と診断された日に67歳を超えている高齢主婦
簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とする
-
症状固定と診断された日に67歳に近い高齢主婦
次のうち、いずれか長い方を労働能力喪失期間とする
- 症状固定と診断された日から67歳までの年数
- 簡易生命表の平均余命の2分の1
ライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、逸失利益から中間利息を控除するために用いられる係数のことです。
後遺障害逸失利益は、交通事故に遭わなければ受け取れるはずだった将来の収入を前倒しして一括で受け取ることになるため、本来よりも余分に受け取れる利息=中間利息が発生すると考えられています。
中間利息を逸失利益に含めたままだと、事故の加害者と被害者の公平性を欠くことになるので、中間利息控除を行って適正な金額に調整する必要があるのです。
増額しなければ成功報酬はいただきません
- 料金について、こちらもご確認ください。
-
- ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
- ※事案によっては対応できないこともあります。
- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
主婦・主夫の死亡逸失利益の計算方法
死亡逸失利益とは、交通事故によって被害者が亡くならなければ得られたはずの将来の利益のことです。
【死亡逸失利益の計算式】
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
基礎収入や就労可能年数、ライプニッツ係数の考え方は、後遺障害逸失利益の場合と同様です。
以下で、「生活費控除」について詳しくみていきましょう。
生活費控除について
生活費控除は、交通事故によって被害者が亡くなったことで不要になった生活費を逸失利益から差し引くことを指します。
もっとも、亡くなった被害者の生活費を把握することは難しいため、被害者の家族構成や家庭内での立場といった属性ごとに、次のように一定の基準が設定されています。
主婦が交通事故で亡くなった場合の生活費控除率は30%が目安になります。
| 一家の支柱の場合かつ被扶養者1人の場合 | 40% |
|---|---|
| 一家の支柱の場合かつ被扶養者2人以上の場合 | 30% |
| 女性(主婦、独身、幼児等を含む)の場合 | 30% |
| 男性(独身、幼児等を含む)の場合 | 50% |
専業主婦の後遺障害逸失利益の計算例
2024年に交通事故に遭い、症状固定と診断されたときに40歳だった専業主婦が、後遺障害等級10級に認定された場合の後遺障害逸失利益を実際に計算していきましょう。
| 基礎収入 (事故前年2023年の女性労働者の全年齢平均賃金) |
399万6500円 |
|---|---|
| 労働能力喪失率 (後遺障害等級10級) |
27% |
| 労働能力喪失期間に対応する ライプニッツ係数 |
|
これらを計算式にあてはめると、次のようになります。
399万6500円×27%×18.327=1977万5840円
したがって、40歳の専業主婦が後遺障害等級10級に認定された場合の後遺障害逸失利益は1977万5840円となります。
増額しなければ成功報酬はいただきません
- 料金について、こちらもご確認ください。
-
- ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
- ※事案によっては対応できないこともあります。
- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
主婦の逸失利益に関する解決事例
専業主夫としての適切な後遺障害逸失利益と後遺障害等級14級が認定された事例
専業主夫が被害者であったこの事故では、家族である妻子が被害者と住民票が別であったため、主婦業の実態が争われました。
保険会社は、主夫としての損害を認めない姿勢でしたが、実際には同居しているという資料を懸命に収集し、粘り強く交渉した結果、被害者が専業主夫であると認められました。
また、後遺障害についても、保険会社の治療打ち切り連絡に対し、弁護士が治療延長を交渉した結果、頸椎捻挫としては長期となる約8カ月の通院が実現し、後遺障害等級14級を獲得することとなりました。
等級が獲得できたことで後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料の請求も可能となりました。
被害者が主夫であること、そして、治療延長交渉によって等級獲得となり、被害者の賠償額は最終的に約120万円の増額となりました。
後遺障害等級12級と専業主婦の逸失利益が認められた事例
右肩痛の症状について後遺障害等級12級を認定された専業主婦が被害者であるこの事故では、休業損害1か月、労働能力喪失期間5年として、保険会社から提示されていました。
しかしそれぞれの期間が短く、不相当であるとして、弁護士は被害者から治療経過の聞き取りを行い、医療記録の精査を行いました。
そこで、治療中の固定処置やその後の右肩痛から長期間にわたり腕を上げることが困難で、家事労働への支障が出ていることが判明しました。
更に、後遺障害の症状の原因についても検討し、後遺障害の今後の残存についても提示期間の5年は短すぎるとして保険会社へ根拠ある主張を行いました。
その結果、休業損害は5か月分が認められ、逸失利益の期間についても14年となり、約650万円の増額に至りました。
主婦の逸失利益についてご不明点があれば弁護士にご相談ください
主婦業と一口で言っても、主婦業に携わる人の事情はそれぞれです。事情が違えば、失われた利益も一律とはいかないでしょう。
勿論、原則的な計算式はありますが、誰でも適正額が導けるといった単純なものではありません。
そして保険会社は多数の交通事故に対応しているプロですので、あいまいな意見ではすぐに反論されてしまいます。
家事労働は日常生活の営みに直結する労働です。日常を取り戻すには少しでも早くケガを癒すことが先決です。
主婦の逸失利益について不明点があれば一人で悩まず、弁護士へご相談ください。
交通事故の経験豊富な弁護士であれば、保険会社との交渉にも強い味方となり、あなたの不安を解消することができるでしょう。
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
- 料金について、こちらもご確認ください。
-
- ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
- ※事案によっては対応できないこともあります。
- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。


