弁護士依頼前
20対80
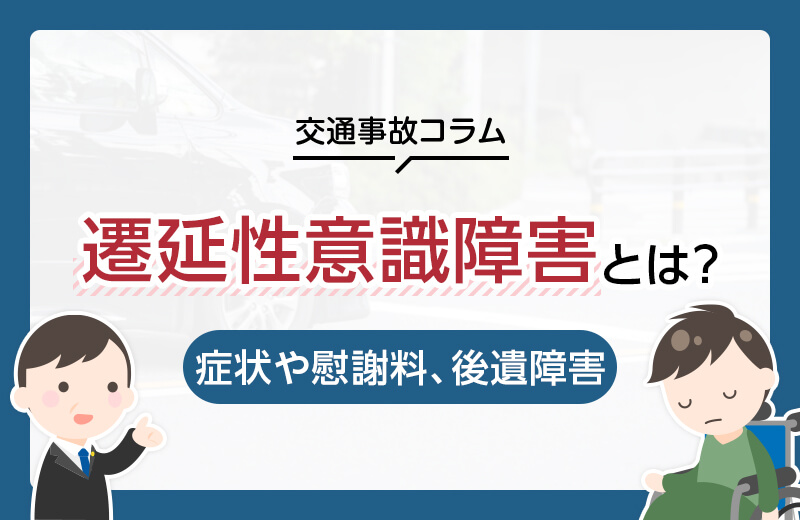
交通事故によって脳に大きなダメージを受けると、遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)を引き起こすことがあります。
遷延性意識障害は、いわゆる植物状態とも呼ばれ、被害者ご本人は当然ながら、ご家族の方の精神的・肉体的・経済的な負担も大きくなります。
大切なご家族が交通事故で遷延性意識障害となってしまい、どうすればよいか不安に感じていらっしゃる方に向けて、遷延性意識障害となった場合の後遺障害や損害賠償について、わかりやすく解説していきたいと思います。
事故被害者の方やご家族の方の、不安や負担がすこしでも緩和できるよう、この記事がお役に立てれば幸いです。
弁護士依頼前
20対80

弁護士依頼後
10対90
より有利になるよう修正
目次
遷延性意識障害とは、重度の昏睡状態・意識障害が長く続いている状態のことです。
自力で呼吸したり目を開けたりすることは可能ですが、外部からの刺激に反応を示さず、意思疎通ができない状態が長く続き、寝たきりになることから植物状態とも呼ばれます。
遷延性意識障害は治る?
遷延性意識障害は、回復の見込みは非常に厳しいと考えられています。
脊髄電気刺激法や脳深部電気刺激法などの治療が行われますが、有効な治療法は確立されていません。
身体機能の悪化を防ぐためのリハビリを行いつつ、被害者自身の自然治癒力による回復を待つことが一般的で、その間は体位交換・排せつケア・痰吸引などの介護が必要になります。
なお、遷延性意識障害の方は、肺炎や敗血症などのさまざまなリスクを抱えているため、平均余命が短い傾向にあります(およそ3年程度)。
遷延性意識障害の症状は、自分では体を動かすことも言葉を発することもできず、寝たきりの状態になることです。
日本脳神経外科学会では、治療しても改善がみられずに、次の6項目を満たす状態が3ヶ月以上続いた場合を遷延性意識障害と定義しています。
交通事故で遷延性意識障害となってしまう原因として、「事故によって脳に大きなダメージを受けること」が挙げられます。
事故の衝撃で頭部が損傷することにより、
などの深刻な脳損傷が生じ昏睡状態に陥ることで、遷延性意識障害に至ると考えられています。
遷延性意識障害の定義では3ヶ月以上の症状継続が要件となっているため、少なくとも6ヶ月を経過すれば後遺障害等級認定の対象になりますが、実務上は1年以上の経過観察を経て、医師から症状固定と判断されることが多いです。
症状固定とは?
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を指します。
症状固定後は治療費や休業損害の支払いが打ち切られるため、次のステップとして、残存した後遺症について補償を受けるために後遺障害等級認定の申請を行います。
症状固定の注意点
症状固定のタイミングで退院を促されるケースも多く、以降は自宅介護や施設介護が必要になります。
また、損害賠償金を受け取るまでの金銭的負担も増えるので、保険会社から症状固定を急かされても、医師と相談しながら慎重に対応することが大切です。
遷延性意識障害で症状固定となった後、後遺障害等級が認定されると、残存した後遺障害によって事故後も受け続ける身体的・精神的苦痛に対する補償=後遺障害慰謝料が請求できるようになります。
以下、もう少し詳しく解説していきます。
後遺障害とは、交通事故による怪我が治療を続けても完治することなく残ってしまった身体的・精神的な後遺症のうち、自賠責保険が定める認定要件にあてはまるものをいいます。
後遺障害は内容・重さに応じて1級~14級の等級に分類されていて、将来にわたって介護が必要となる遷延性意識障害は、後遺障害等級のなかで最も重い等級である【1級1号】に該当します。
| 等級 | 後遺障害の内容 |
|---|---|
| 1級1号(要介護) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
遷延性意識障害における後遺障害等級認定の申請手続きには、医師が作成した後遺障害診断書のほか、CT・MRIなどの画像診断の資料や日常生活状況報告書といった資料が必要で、より確実に等級認定を受けるためには、交通事故や後遺障害に詳しい弁護士へ相談することがおすすめです。
交通事故の後遺障害に強い弁護士の探し方については、以下ページをご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
後遺障害慰謝料とは、交通事故が原因で残存した後遺障害によって、事故後も受け続ける身体的・精神的苦痛に対する賠償のことです。
認定された後遺障害等級に応じて慰謝料の金額が変わり、遷延性意識障害で1級の後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料の相場は、自賠責基準で1650万円、弁護士基準で2800万円です。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級1号(要介護) | 1650万円 | 2800万円 |
自賠責基準・弁護士基準とは?
自賠責基準、弁護士基準は、損害賠償金の算定に用いられる基準のことで、ほかに任意保険基準があります。
算定基準のうち、弁護士が算定に用いる弁護士基準の損害賠償金が最も高額になる傾向にあります。
増額しなければ成功報酬はいただきません
交通事故が原因で遷延性意識障害となった場合に請求できる損害賠償金には、慰謝料・治療関係費・休業損害・逸失利益・将来介護費用・付添看護費・成年後見人費用など、さまざまなものがあります。
遷延性意識障害となると、被害者ご自身はもちろん、そのご家族の生活が一変し、将来にわたって介護が必要になることから、精神的・肉体的・経済的な負担が大きくなります。
こうした負担を少しでも軽くするために、損害に見合った適切な賠償金を請求することが重要です。
以下、損害賠償金の請求にあたって争点になりやすい項目について、詳しくみていきましょう。
交通事故で遷延性意識障害となった場合、後遺障害慰謝料のほかに、入通院慰謝料や近親者慰謝料が請求できます。
| 入通院慰謝料 | 入通院慰謝料とは、交通事故が原因で入院・通院を強いられたことによる身体的・精神的苦痛に対する賠償のことです。 事故後から症状固定となるまでの入通院期間や通院日数に応じた金額が請求できます。 |
|---|---|
| 近親者慰謝料 | 近親者慰謝料とは、被害者の家族などの近親者が被った精神的苦痛に対する賠償のことです。 交通事故で被害者が亡くなったり、将来的に介護が必要な後遺障害が残ったりした場合に、近親者固有の権利として慰謝料請求できる場合があります。 |
近親者慰謝料について、近親者の範囲や金額が争点になることも多いので注意が必要です。
後遺障害逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ得られたはずの将来の収入に対する賠償です。
被害者の事故前の収入・年齢・職業や、後遺障害によって失われた労働能力の程度を考慮して金額がきまります。
後遺障害逸失利益の計算式 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
遷延性意識障害となった場合、植物状態となって働くことができないので労働能力喪失率は100%となって、逸失利益が高額になる傾向にあります。
そのため、保険会社から平均余命や生活費控除が主張され、逸失利益が低く見積もられることがあるので注意が必要です。
交通事故後から症状固定となるまでに発生した治療に関する費用は、全額請求することができます。
治療関係費として請求できる費用
なお、生命維持のために将来必要となることが予想される将来治療費や、医師が必要と認めた場合の特別室使用料についても請求できる可能性がありますが、保険会社から必要性を否定されることもあるので注意が必要です。
遷延性意識障害では将来にわたり介護が必要となるため、将来介護費も請求することができます。
このほか、介護に必要な住宅・車の改造費・車椅子購入費用・紙おむつや医療機器などの介護用品購入費用についても請求することが可能です。
遷延性意識障害では将来の費用が発生し続けることから、損害としてきちんと計上されているか、適正額であるか注意して確認する必要があります。
交通事故で遷延性意識障害となった場合、以下のように意思表示ができない被害者本人に代わって損害賠償請求する人が必要になります。
成年後見人とは?
成年後見人とは、植物状態や認知症などで意思表示ができない人に代わって法律行為をおこなう人のことです。
家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをすると、成年後見人を選任してもらうことができます。
本人が意思表示できるようになるか、亡くなるまで後見人の任務が続き、その間は定期的に報酬が発生します。
遷延性意識障害となると、意識を取り戻して元の状態に戻ることは非常に難しいといわれています。
そのうえ、24時間365日気を抜くことのできない介護が続くことから、ご家族は精神的・肉体的・経済的な負担を同時に背負うことになります。
弁護士法人ALGでは、事故被害者の方やそのご家族の方が抱える不安・負担が少しでも緩和できるように、これまでの経験と知識を活かして全力でサポートいたします。
遷延性意識障害の損害賠償請求で争点になりやすい将来の費用や逸失利益について、弁護士基準の適正額を主張し、漏れなく請求することができるほか、成年後見人に関するお悩みにもアドバイスが可能なので、まずはお気軽にお問い合わせください。
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
