弁護士依頼前
0円
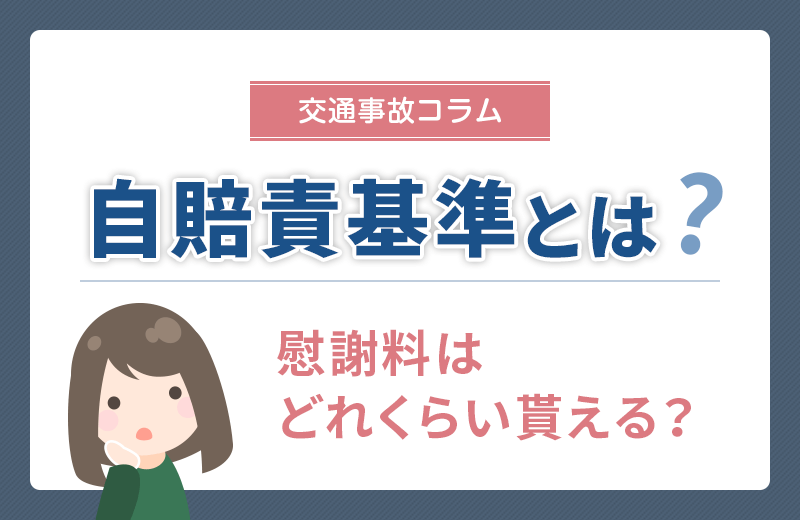
交通事故の被害に遭った時、保険会社が提示する慰謝料はなにを根拠にしているのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
慰謝料は被害者の精神的苦痛なのだから、他人が見積もることなんてできない!と思われるかもしれません。
しかし、実際には、慰謝料は3つ基準を基に計算されており、その中でも最低限の補償とされているのが自賠責基準です。
本稿では自賠責基準の内容や具体的な金額をご説明しますので、ご自分の慰謝料の最低ラインを適切に把握するためにお役立てください。
弁護士依頼前
0円

弁護士依頼後
約900万円
約900万円の増加
目次
自賠責基準とは、自賠責保険が交通事故の被害者に支払う賠償額を定めた基準のことです。
自賠責保険は公道を走るすべての自動車に加入が義務付けられている強制保険であり、交通事故で負傷した被害者の救済を目的としています。
交通事故の賠償金を算定する基準には、自賠責基準以外にも、任意保険基準、弁護士基準があります。どの基準を用いるかによって、慰謝料額が変わってきます。
自賠責基準は基本的な対人賠償を確保するための基準であるため、3つの基準の中で最も低額な慰謝料となることが多いです。
自賠責基準のメリットは、加害者が任意保険に未加入でも一定の補償が受けられることですが、最も低額な基準という点がデメリットです。
| 自賠責基準 |
|
|---|---|
| 任意保険基準 |
|
| 弁護士基準 |
|
増額しなければ成功報酬はいただきません
「自賠責保険からの保険金は120万円まで」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、実はこれは傷害部分についての保険金の上限額です。
自賠責保険が支払う、ケガにより生じた損害への保険金の上限額は120万円までと定められています。これは、治療費や入通院慰謝料、休業損害など傷害に関するすべての費用を合計した金額です。
しかし、事故によるケガは予想以上に出費を伴い、この金額では足りないことが多いです。
治療期間が長くなって、治療費が増えたり、休業損害の支払いが必要となったりする場合は、すぐに120万円を使い切り、被害者が受け取れる慰謝料も減ってしまう可能性があるため注意が必要です。
損害額が120万の上限額を超えたとしても、泣き寝入りする必要はありません。
上限額以上であろうと、交通事故による損害ならば相手方へ請求できます。
加害者が任意保険に加入している場合には任意保険会社に請求するのが一般的です。
しかし、保険会社は独自の基準で計算した賠償額を提案してくるため、最も低額な自賠責基準を下回っていないか注意する必要があります。
加害者が無保険の場合は、加害者本人に請求することになりますが、賠償金を支払うだけの資力がないことも多く、交渉が難しいケースが多々あります。
相手から賠償を受けることが難しければ、人身傷害保険など被害者自身の保険でカバーできる場合があります。一度ご自身の保険会社にご確認ください。
加害者が無保険の場合の対処法については、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
慰謝料とは、精神的な苦痛に対する賠償金のことです。
交通事故の慰謝料には、以下のとおり「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」と3つあります。
| 入通院慰謝料 |
|
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 |
|
| 死亡慰謝料 |
|
では、自賠責基準を使って3つの慰謝料を計算してみましょう。
自賠責基準の入通院慰謝料額は入院、通院にかかわらず、一日あたり4300円です。
日数をカウントするには、①通院期間(事故日~完治日または症状固定日)と、②実際に通院した日数の2倍のいずれか少ない日数を採用します。
例えば、他覚所見のないむちうちで通院期間3ヶ月、実通院日数30日のケースを想定します。
① > ②であるため、②を対象日数とします。
そのため、自賠責基準による入通院慰謝料は、4300円×60日=25万8000円となります。
入通院慰謝料の日数カウントの原則は前述のとおりですが、状況によっては7日加算と言われる、通院期間に7日を加算する例外があります。
例えば、事故から8日後以降に治療を開始した場合や、診断書に治癒見込(まだ治癒に至っていないが、このまま治癒が見込める状態)や転医等と書かれている場合には、この7日加算が行われます。
日数が加算されれば慰謝料額の計算にも影響がありますが、この加算は通院期間に加算され、実通院日数には加算されないので、前述の②が採用されるケースでは、結果として慰謝料増額とはなりません。
等級に該当するほどの重い後遺症が残った場合には、後遺障害慰謝料が支払われます。
このときの自賠責基準は下表のとおり、各等級に応じて金額が決まっています。
特に重い障害である1級と2級に関しては、別表第1,2で金額が異なっています。
別表第1については、介護を要する状態の後遺障害のときに適用される為、別表第2と比べて高額になっているのです。
更に被扶養者がいるなど、個別の事情があれば下記の慰謝料額より増額されることがあります。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準での後遺障害慰謝料 | |
|---|---|---|
| 別表第1 | 1級 | 1650万円 |
| 2級 | 1203万円 | |
| 別表第2 | 1級 | 1150万円 |
| 2級 | 998万円 | |
| 3級 | 861万円 | |
| 4級 | 737万円 | |
| 5級 | 618万円 | |
| 6級 | 512万円 | |
| 7級 | 419万円 | |
| 8級 | 331万円 | |
| 9級 | 249万円 | |
| 10級 | 190万円 | |
| 11級 | 136万円 | |
| 12級 | 94万円 | |
| 13級 | 57万円 | |
| 14級 | 32万円 | |
事故によって、不幸にも被害者が死亡した場合には死亡慰謝料が支払われます。
自賠責基準における死亡慰謝料は、亡くなった本人に対する金額と、その遺族に対して支払われる金額の合計額となっています。
但し、死亡事故に対する自賠責保険の上限額は、被害者1名につき3000万円となっています。
死亡慰謝料のほかにも葬儀費用や逸失利益などもこの金額に含まれるので、死亡慰謝料については以下に示す基準額且つ上限額の範囲内での支払いになります。
死亡した被害者本人の死亡慰謝料は、一律400万円と定額になっています。
この金額は、被害者の年齢や職業、年収など故人の属性に左右されることはありません。
また、家庭内での立場によって変わることもありません。
死亡慰謝料の請求は、死亡した被害者の配偶者、子、父母だけに認められています。
請求できる権利を持つものを請求権者と言いますが、遺族の慰謝料は、下表のとおり、その請求権者の人数によって金額が決まっています。
更に被害者に被扶養者が一人でもいれば、慰謝料が増額することになります。
例えば、遺族が配偶者と二人の子供(被扶養者)であった場合の死亡慰謝料は、
400万円(本人分)+750万円(遺族分)+200万円(被扶養者加算)=1350万円
となります。
| 請求権者 | 近親者固有の死亡慰謝料 |
|---|---|
| 1人 | 550万円 |
| 2人 | 650万円 |
| 3人以上 | 750万円 |
| 被扶養者がいる場合 | 上記+200万円 |
過失割合とは、その事故における被害者の落ち度の程度を表します。
通常、損害賠償額はこの過失割合に応じて過失相殺され、賠償額は減額となります。
しかし、自賠責保険は被害者の最低限の補償を守る強制保険である為、過失割合が7割未満の場合には、そもそも過失相殺されないという決まりがあります。
過失割合が7割を超えると減額対象となりますが、下表のとおり、傷害事案に関しては過失がどれほどあっても2割減までとなっています。
通常過失7割であれば、賠償額も7割減額となりますが、自賠責基準においては、たとえ過失が7割を超えたとしてもその減額を部分的なものに留め、被害者救済を最優先としています。
| 自身の過失割合 | 傷害 | 後遺傷害・死亡 |
|---|---|---|
| 7割未満 | 過失相殺なし | 過失相殺なし |
| 7割~8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
増額しなければ成功報酬はいただきません
適切な慰謝料を受け取るためには、最も高額な弁護士基準で請求することが必要です。
しかし、弁護士基準による正確な慰謝料の算出には専門知識が求められます。
また、保険会社は営利企業であるため、自社の支払いを抑えようと、多少強引でも自賠責基準や任意保険基準で決めてしまうことがほとんどです。
そのため、被害者が自分で弁護士基準の慰謝料を請求しても、保険会社が応じることはまずないでしょう。
弁護士が弁護士基準で請求すれば、保険会社も裁判を警戒し、金額面について大きく譲歩する可能性があります。
また、弁護士に、保険会社の提示額が適切かの判断や、後遺障害等級認定手続きも任せられるため、慰謝料増額の可能性も高まります。十分な慰謝料を受け取りたいならば、弁護士にご相談ください。
交通事故を弁護士に依頼するメリットについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
依頼者が自転車で走行中、車にノーブレーキで衝突され、肋骨骨折や気胸などのケガを負った事案です。
6ヶ月間の治療後、後遺障害12級6号と認定されましたが、相手方保険会社から提示された賠償額236万円が適切か判断できず、弁護人法人ALGにご依頼されました。
保険会社の提示額を確認したところ、後遺障害に関する損害については自賠責基準による低い金額が提示され、入通院慰謝料や休業損害も増額の余地があると判断されました。
担当弁護士が弁護士基準額での提示をしたところ、慰謝料などを80%にし、賠償金を410万円とする回答がありました。
ケガの重さやご本人の希望も踏まえ、慰謝料などを90%程度にするよう再び交渉したところ、当初提示額から約2倍の460万円の賠償金を受け取ることに成功しました。
自賠責基準は基本的な対人賠償を確保する基準であるため、最も低額な慰謝料となるケースが多いことをご理解ください。
保険会社からの提示は会社ごとの基準に従っていますが、その金額が自賠責基準を確実に上回る保証はありません。 必ず提示額の根拠と最低ラインが確保されているかを確認し、安易に示談しないよう注意しましょう。
とはいえ、自賠責基準以下であることに気づいても、保険会社相手の増額交渉はなかなか大変です。
相手は示談交渉ばかりしている百戦錬磨のプロですので、簡単には増額に応じてくれません。
弁護士であれば、自賠責基準ではなく、最も高額な弁護士基準で賠償額の提示を行うことができます。保険会社の対応に悩む必要はありません。まずは私たちにご相談ください。
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
