弁護士依頼前
20対80
依頼者様:過失割合20
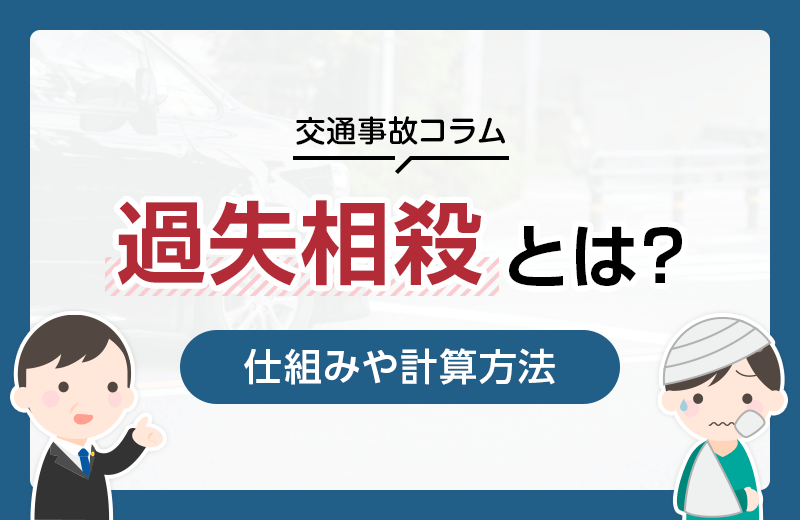
交通事故は加害者だけに過失があるものだけではありません。被害者にも過失が付くことがほとんどです。 被害者にも過失が付いた場合、その過失分だけ受け取れる損害賠償額が減額されます。これを過失相殺(かしつそうさい)といいます。 この記事では、交通事故の過失相殺とは何か、 計算方法などについてわかりやすく解説していきます。弁護士法人ALGによる解決事例もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
弁護士依頼前
20対80
依頼者様:過失割合20

弁護士依頼後
10対90
依頼者様:過失割合10
適正な過失割合に修正
目次
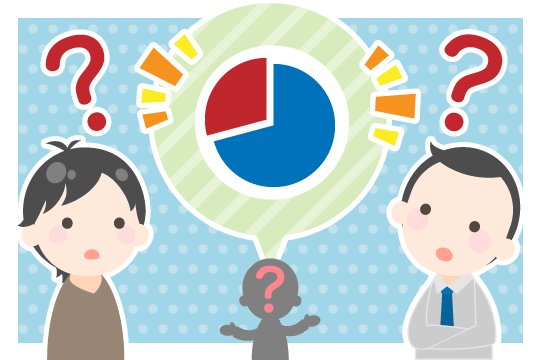
過失相殺(かしつそうさい)とは、 被害者に過失が付いた場合に、その過失分に相当する額だけ損害賠償金が減額されることです。 被害者にも過失がある場合、加害者だけが損害賠償金の全額を支払うのは公平ではないことから、 民法第722条に定められています。
【民法第722条】
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる
「過失相殺」と似た言葉に「損益相殺」がありますが、これらはまったく異なる性質である点に注意しましょう。
損益相殺とは
損益相殺とは、損害額の一部を示談前に相手方保険会社から受け取ったり、相手方保険会社以外からその事故に関する金銭を受け取ったりした場合に、被害者が二重取りにならないよう示談時に調節を行うこと 交通事故の損害賠償金に関しては、以下のような金銭が損益相殺の対象となります。
通常、過失割合は、示談交渉の中での当事者間の合意または裁判手続きにおける和解や判決で決まります。 示談交渉では、まず、加害者側の任意保険会社の担当者が過失割合を提示するのが一般的です。 しかし、保険会社が提示する過失割合は確定的なものではなく、これに納得がいかなければ、協議や交渉により過失割合の修正を求め、それでも決着がつかなければ裁判手続きで争うことになります。
過失相殺の計算は、以下の流れで行います。
損害賠償金に過失相殺を適用する計算式は、次のとおりです。
過失相殺後の損害賠償金=過失相殺前の損害賠償金×(100%-自身の過失割合) では、具体的例を用いて過失相殺について詳しく見ていきましょう。
過失割合8対2のケースでは、過失相殺により損害賠償金はどのくらい減額されるでしょうか。以下の前提条件を用いて、実際に計算してみましょう。
【前提条件】
今回の例では、被害者の損害額は300万円です。被害者の過失は2割なので、過失相殺した結果は、以下のとおりになります。
300万円×(100%-20%)=240万円続いて、加害者の損害額は100万円なので、その金額にも過失相殺を適用します。
100万円×(100%-80%)=20万円交通事故の過失割合は、「9対0」のように片側賠償となる場合もあります。 これは、被害者にも本来過失が1割あるが、加害者が被害者への損害賠償請求権を放棄したため、被害者が支払う賠償金は0円になるということです。
具体例を用いて見ていきましょう。
【前提条件】
交通事故の過失相殺は、以下のようなケースで注意が必要です。
では、どのようなことに注意すべきなのか、詳しく見ていきましょう。
被害者が子供の場合は、事理弁識能力の有無で過失相殺の考え方が変わります。 事理弁識能力とは、損害の発生を察知して回避する能力であり、5~6歳以上の子供であれば備わっていると認められる傾向にあります。
子供にも過失が認められ、過失相殺の対象 となります。
過失と認められる行動があったとしても過失相殺の対象とはなりません。
| 被害者の能力 | 能力が備わる年齢 | 備考 |
|---|---|---|
| 事理弁識能力 | おおむね 5~6歳以上 |
損害の発生を避けるのに必要な注意をする能力 |
加害者が高級車の場合、修理費が高額になることが予想されます。 そのため、被害者の過失割合が小さくても、加害者の被った損害の方が高額な場合、被害者の方が多く損害賠償金を支払うことになる可能性があります。 具体例を用いて詳しく見ていきましょう。
| 加害者 (過失割合8) | 被害者 (過失割合2) | |
|---|---|---|
| 損害額 | 500万円 | 100万円 |
| 相手に支払う額 | 80万円 (100万円の8割) |
100万円 (500万円の2割) |
| 実際に受け取る額 | 20万円 (100万円-80万円) |
0円 (80万円-100万円) |
増額しなければ成功報酬はいただきません
過失相殺に納得できない場合は、安易に示談に応じないようにしましょう。 対処法として、以下の方法が挙げられます。
① 正しい過失割合を主張する
まずは、相手方保険会社から提示された過失割合の根拠を確認しましょう。そうすることで、何を根拠に正しい過失割合を主張すればいいかが見えてきます。
② 弁護士に相談する
過失割合の交渉は、法律や交通事故の専門知識を要します。 弁護士であれば、過去の判例や事故類型から適切な過失割合を算出し、法的根拠をもって主張・立証することが可能であり、過失割合が修正される可能性が高まるでしょう。
過失相殺について弁護士に依頼するメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
このように、交通事故を弁護士に依頼するメリットは、過失割合や過失相殺だけではありません。交通事故全体について包括的にサポートをしてもらうことができ、示談交渉もスムーズに進む可能性が高まります。また、弁護士に依頼すると法的に正しい損害賠償金を主張していきますので、示談金が増額する可能性が高まることも大きなポイントです。
交通事故を弁護士に依頼すべき6つのメリットについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
【事案の概要】 依頼者運転の自転車が路地の曲がり角付近を走行中、進行方向から相手方自動車が曲がり角を曲がってきてそのまま走行し、衝突した事故です。この事故で依頼者は、鋤骨骨折、腰椎捻挫等の傷害を負いました。 その後、過失割合について当事務所に依頼されました。 【担当弁護士の活動・結果】 担当弁護士は、事故状況等を詳細に聴取し、具体的な事故の状況を踏まえ、まずは物損の交渉に当たりました。 すると、相手方保険会社からは過失割合5:5と提示されました。 しかし、具体的な事故状況を踏まえ適切な過失割合について相手方保険会社と協議を重ねた結果、2:8という割合で賠償交渉することについて合意に至りました。 残存症状につき、後遺障害等級認定を得られたこと及び物損と同様に有利な過失割合で示談に至った点で被害者の方にもご満足いただける形で示談に至ることができました。
【事案の概要】 横断歩道がない道路を横断していた依頼者が、その道路を走行していた自動車に轢かれ、意識不明で、全く意思疎通ができなくなりました。 依頼者本人から依頼を受けることができない状態であったため、成年後見人を選任された後、当事務所に依頼されました。 【担当弁護士の活動】 担当弁護士が受任後、まずは後遺障害等級認定申請を行いました。その結果、後遺障害等級別表第1第1級が認定されました。それをもとにして、損害額の計算を行い、保険会社と交渉を開始しました。 この交渉で大きな争点となったのは、過失割合であり、相手方保険会社は20(被害者):80(加害者)という主張を行っていました。 当方弁護士は、加害者の警察に対する説明をもとに過失割合を検討し、弁護士紹介を利用して警察の記録を入手しました。そこで、意見書を作成し、加害者の責任を加重できる部分があることを説明し、過失割合10(被害者)対90(加害者)が適切であると主張しました。 【結果】 担当弁護士の粘り強い交渉により、相手方保険会社はこの意見書を踏まえ、過失割合10(被害者):90(加害者)に応じてきたことから示談が成立しました。
過失割合や過失相殺は、交通事故の損害賠償金を受け取るうえでとても重要な項目ですが、専門知識を要するため、分からないことも多くあるでしょう。 過失割合や過失相殺について少しでも不安やお悩みがある場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。 私たちは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、過失割合や過失相殺について分かりやすく説明します。また、ご相談者様の事故や怪我の状況から正しい過失割合を導き、法的根拠をもって相手方保険会社と交渉していくことが可能です。 「こんなことで弁護士に相談してもいいのかな」と相談をためらっている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、弁護士はいつでもあなたの味方です。少しでもお悩みがある場合は、お気軽にお問い合わせください。
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
