弁護士依頼前
未提示
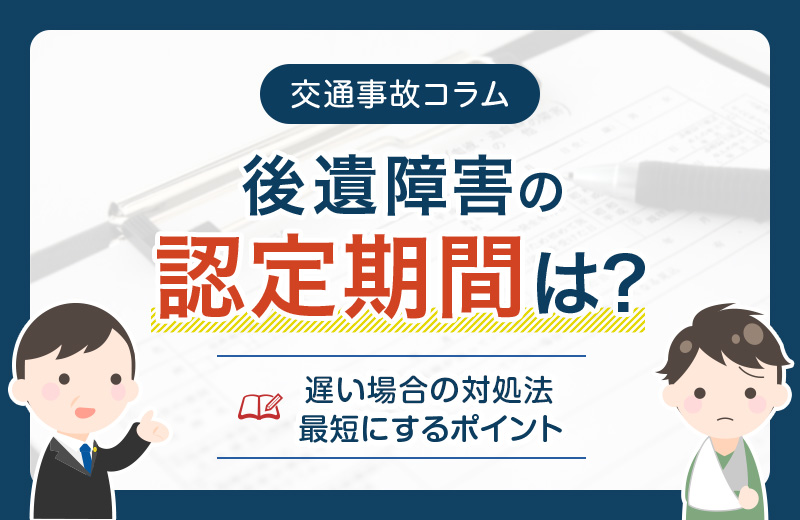
交通事故のケガが治療を尽くしても完治せず、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を申請することになります。
後遺障害の認定が受けられると、後遺症によって生じた損害に対する賠償金を請求することができるので、一刻も早く後遺障害の認定を受けたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、後遺障害の認定期間について、結果がわかるまでに時間がかかる理由や、認定期間を最短にするポイントなどを解説していきます。
これから後遺障害の認定を受けようとされている方も、すでに申請して結果がいつわかるか不安に感じている方も、ぜひ参考になさってください。
弁護士依頼前
未提示

弁護士依頼後
約1500万円
(自賠責分を含む)
適正な賠償額を獲得
弁護士依頼前
認定前

弁護士依頼後
12級13号
認定をサポート
目次
後遺障害等級が認定されるまでの期間は早くて1ヶ月、基本的に2~3ヶ月程度かかることが多いです。
以下は2022年度の後遺障害等級認定の審査にかかった期間のデータです。
| 認定期間 | 割合 |
|---|---|
| 30日以内 | 73.7% |
| 31日~60日 | 14.0% |
| 61日~90日 | 6.7% |
| 90日以上 | 5.6% |
この統計からもわかるように、約87%の方は申請から2ヶ月以内に結果が出ていることになります。
2ヶ月以上経っても結果が届かない場合は、審査に時間がかかっていると考えてよいでしょう。
とはいえ、あくまで平均的な目安の期間にすぎません。
後遺症の内容や程度によっては審査に時間がかかり、結果がわかるまでに6ヶ月~1年以上かかるケースもあるためご注意ください。
交通事故が起きてから後遺障害が認定されるまでの流れを、簡単に紹介します。
このように、加害者側の任意保険会社を通して申請する方法を事前認定といいます。
事前認定のほかに、被害者ご自身が直接申請する被害者請求という方法もあります。
後遺障害の2つの申請方法については、以下ページで詳しく解説していますのであわせてご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
後遺障害等級認定の申請をしてから60日以上経っても結果が通知されない場合は、次のような事情で審査に時間がかかっていると考えられます。
後遺障害等級認定に時間がかかる理由として、保険会社から審査機関への書類提出が遅れている可能性が考えられます。
後遺障害等級認定では、加害者側の任意保険会社または自賠責保険会社を介して、審査機関に申請書類を提出することになります。
しかし、保険会社の担当者は、同時に多くの事故案件を対応していることが珍しくありません。
そのため、業務が滞っていて、審査機関への書類提出が後回しになってしまうケースがあります。
とくに、加害者側の任意保険会社を通して申請する事前認定の場合、申請に必要な書類のほとんどを保険会社側が用意することになるため、より手続きに時間がかかる傾向にあります。
後遺障害等級認定の審査の多くは、提出された書類に基づいて行われます。
後遺障害診断書や事故発生状況報告書などの提出書類に不備があると、再提出や追加資料の提出を求められるため、審査が長引く原因になります。
場合によっては、病院で再検査を受けたり、必要書類を再度取り寄せたりする必要があります。
特に審査機関は医師の作成した後遺障害診断書を最も重視します。
後遺障害診断書の内容に不備があると、審査に時間がかかるだけでなく、適切な等級認定を得られなくなるリスクもあります。
医師に症状や経過を具体的に伝え、後遺障害診断書に正確な内容を記載してもらうことが大切です。
医療照会とは、被害者の後遺症の症状や所見、治療経過について、医師に対して書面で回答を求めることをいいます。
提出書類だけでは後遺障害の判断が難しいケースや、異議申立てによる再審査において医療照会が行われることがあります。
医療照会で医師からの返答が遅れていると、その間は待つしかないので審査が進まず、認定に時間がかかってしまいます。
後遺症の症状が複雑だったり、複数の後遺症があったりすると、認定期間が長引く傾向にあります。 とくに審査が長引きやすいケースと、その理由は次のとおりです。
高次脳機能障害は時間経過とともに症状が軽減していく傾向があるので、そもそも症状固定診断までに時間がかかります。
また、症状が多岐にわたるので資料も多いことや、ほかの後遺症とは異なる専門の審査が必要になることから、認定期間が長引きやすいです。
外貌醜状では、ほかの後遺症では通常行われない面接が行われるため、その分認定までに時間がかかります。
複数の後遺症がある場合は、それぞれの後遺症ごとに審査を行ったうえで総合的な判断がなされるため、後遺症が多いほど認定までに時間がかかります。
増額しなければ成功報酬はいただきません
後遺障害等級認定が遅れると、以下のような不都合が生じる可能性があります。
交通事故の損害賠償請求には時効があります。
時効が過ぎてしまうと、慰謝料を含めた損害賠償金を支払ってもらえなくなります。
後遺障害の認定期間が長引くと、示談交渉でつかえる時間が短くなるので、注意しなければなりません。
時効が迫っている場合には、時効の更新や完成猶予の措置をとることで、時効の完成を遅らせることができます。
後遺障害の認定に時間がかかりそうな場合は、認定に対する対策とともに、時効に対する対策も講じる必要があるので、一度弁護士に相談してみましょう。
後遺障害等級認定が遅くなると、示談金の受け取りも遅くなる可能性があります。
示談交渉は基本的に後遺障害等級認定が終わらなければ開始できないからです。
示談金は後遺障害等級の認定結果をもとに算出されるため、認定が終わらない限り、示談金の確定や支払い手続きは進みません。
後遺障害が残ると、通院のために仕事を休んだり退職したりして収入が減ることが予想されます。
基本的に示談金は示談成立後に支払われるため、後遺障害等級認定に時間がかかるほど、生活に影響を与えるリスクがあります。
後遺障害等級の認定が遅いと感じた場合に、被害者の方がとれる2つの対処法をご紹介します。
いずれの方法も必ず認定が早まるとはかぎりませんが、試してみる価値はあります。
保険会社に書類を提出してから2ヶ月以上なにも連絡がない場合は、まずは保険会社に進捗状況を確認してみましょう。
調査事務所への提出が遅れている場合、保険会社に問い合わせることで優先して対応してもらえる可能性がありますし、状況を確認することで安心して待つことができます。
もっとも、保険会社から調査事務所へ書類が提出されていて、審査がすでにはじまっている場合は、保険会社で対応してもらえることはないので、審査が終わるのを待つことになります。
事前認定で後遺障害の認定に時間がかかっている場合は、被害者請求への切り替えを検討しましょう。
後遺障害等級認定の申請は、事前認定から被害者請求へ切り替えることができます。
加害者側の任意保険会社を通して申請したものの、保険会社の対応が遅く、手続きが滞っていて時間がかかるようであれば、被害者請求に切り替えてご自身主導で手続きを進めた方が、結果的に後遺障害の認定を早められる可能性があります。
被害者請求の場合、ご自身で申請書類を集める必要があるので、手続きに不安のある方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
被害者請求を弁護士に依頼するメリットについて、以下ページで詳しく解説していますのであわせてご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
後遺障害の認定期間を最短にするポイントを2つご紹介します。
いずれも被害者ご自身でとれる対処法になるので、次項で詳しくみていきましょう。
これから後遺障害等級認定を申請する方は、最初から被害者請求で申請することで、保険会社の対応を待つ時間を短縮できます。
被害者請求ではご自身で申請書類を準備・提出するので、保険会社による書類の提出遅れを回避できます。
また、後遺障害の認定に有効な証拠・資料をご自身で集めて提出できれば、納得いく結果が得られやすくなるので、審査や異議申立てにかかる時間を短縮できる可能性があります。
弁護士に依頼することで、後遺障害の申請手続きをスムーズに進めてもらえることから、認定期間の短縮が期待できます。
後遺障害の申請について経験・知識が豊富な弁護士であれば、煩雑な被害者請求の手続きをすべて任せることができます。
等級認定に備えた検査・通院の仕方、後遺障害診断書の内容のほか、事前認定で等級認定が見込めそうかもアドバイスが受けられるので、期間短縮だけでなく、被害者の方の負担軽減にもつながります。
なお、弁護士であれば弁護士基準で慰謝料請求することができるので、後遺障害が認定されなかった場合でも慰謝料の増額が見込めるというメリットもあります。
後遺障害に強い弁護士の探し方やメリットについては、以下ページで詳しく解説していますのであわせてご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
依頼者が自転車を運転して横断歩道を横断中、安全確認せずに左折してきた相手車と衝突し、足のひざを骨折した事案です。
その後、治療を継続していくにあたり、相手方との交渉を弁護士に任せたいと弁護士法人ALGにご依頼されました。
担当弁護士が具体的な事故状況や治療経過等を詳しくヒアリングし、症状固定後は資料を収集して被害者請求により後遺障害等級認定の申請を行った結果、後遺障害12級13号と認定されました。
認定された等級を踏まえて相手方保険会社との示談交渉を進め、多くの損害賠償金について当方の主張どおりに認められました。
結果的には裁判をした場合よりも有利な内容で示談するに至り、後遺障害部分の自賠責保険金を含めて約1500万円の示談金を受け取ることに成功しました。
後遺障害の認定に時間がかかると、賠償金の受け取りが遅れてしまい生活に影響することも少なくありません。
手続きが進められず焦ってしまうと、不利な結果となるおそれがあるため、「後遺障害の認定に時間がかかっている」と感じたら、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人ALGでは、これまで数々の交通事故問題に取り組んだ実績があり、後遺障害の認定に関する知識・経験が豊富な弁護士も多く在籍しています。
後遺障害の認定期間が長引いているときの対処法はもちろん、これから後遺障害の認定を最短で受けたいとお考えの方に向けてもアドバイス・サポートが可能です。
後遺障害の認定申請をどのように進めればよいか迷ったら、ぜひ私たちにご相談ください。
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
