弁護士依頼前
約1870万円
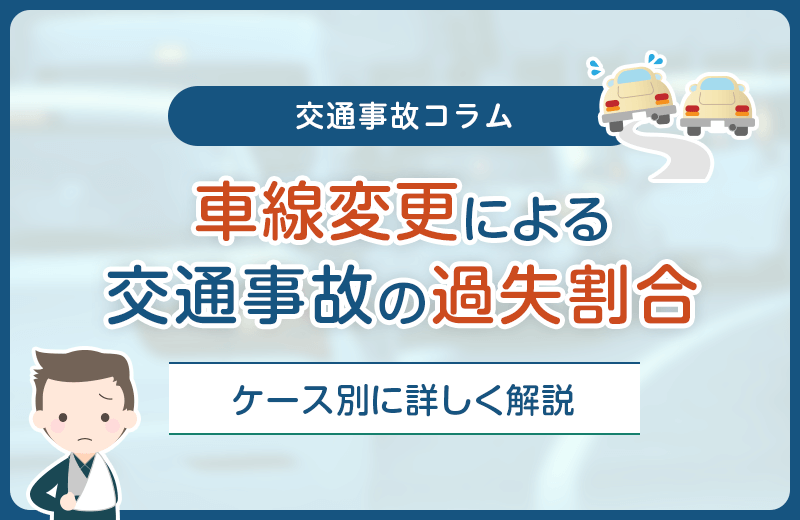
車同士の事故には様々な事故形態がありますが、その中で揉めやすい事故の一つが車線変更による事故です。
車線変更による事故の典型例は、前方の車両が車線変更を行い、直進していた後方車両と衝突するケースです。ただ、車線変更での事故も、実際は様々であり、事故の状況により、過失割合が大きく変動することもあります。
この記事では、車線変更の事故に着目し、様々な事故形態での過失割合について解説していきます。
弁護士依頼前
約1870万円

弁護士依頼後
約3170万円
約1300万円の増額
目次
過失割合とは、交通事故で当事者双方にどの程度の責任があるかを割合で示すものです。
交通事故では一方だけが完全に悪いケースは少なく、「7:3」や「2:8」など、双方に過失があることが一般的です。
過失割合は警察が決めるものと思われがちですが、実際には当事者や保険会社、弁護士が示談交渉を通じて決めていきます。
過失割合は損害賠償額に大きく影響するため、示談交渉の中でも特に争いになりやすい項目です。
たとえば、損害賠償金が100万円であっても、被害者に2割の過失があると、被害者の責任分の2割分が差し引かれるため(過失相殺)、被害者は80万円しか受け取れません。
そのため、加害者側の保険会社が提示する過失割合を鵜呑みにせず、納得できない場合は反論し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することが必要です。
交通事故の過失割合の決まり方については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考にしてください。
合わせて読みたい関連記事
車線変更をした前方の車両が直進する後方車に衝突される事故では、基本的な過失割合は、車線変更をした前方の車:直進している後方の車=7:3となります。
法律上は、車線変更をみだりに行ってはならず、変更先の車線を走る車を妨害するような場合は、車線変更をしてはいけません。
そのため、車線変更する側が後方車両より安全に配慮する立場にあるといえるので、車線変更で追突事故を起こしてしまった場合には、車線変更をした側に大きな過失があることになります。
他方で、後方車両については「まっすぐ走っていただけなのに過失が30%も付くの?」と思われるかもしれません。
30%という過失は、後方車両に軽度の前方不注視があったことが前提とされています。十分に前方に注意していれば事故を防げたという観点から、30%の過失が付きます。
重過失とは、故意に等しい重大な過失のことをいいます。
重過失に当てはまると、過失割合に加算され過失修正されてしまいます。過失が修正されることで、基本過失割合7(車線変更した前方車):3(直進する後方車)から過失割合が変更されます。
具体的には以下のケースが重過失に当てはまります。
重過失に当たる事情
以下のような状況では、直進車に過失がないと判断され、過失割合が10対0になる可能性があります。
ここでは、ケース別に車線変更後の事故の過失割合について見ていきましょう。
まずは下表にまとめましたので、ご覧ください。
| 事故状況の具体例 | 車線変更車 | 直進車 | |
|---|---|---|---|
| 交差点内で車線変更した場合 | 8 | 2 | |
| ウィンカーを出さずに車線変更した場合 | 9 | 1 | |
| 車線変更が禁止されている場合 | 9 | 1 | |
| 直進車がゼブラゾーン(導流帯)を走行した場合 | 6 | 4 | |
| 車線変更車がスピード違反した場合(30キロ以下の速度超過) | 9 | 1 | |
| 直進車に初心者マークがある場合 | 8 | 2 | |
| 高速道路で追越車線に進路変更した場合 | 8 | 2 | |
| バイクと事故を起こした場合 | 車線変更をしたのがバイク | 6 | 4 |
| 直進車がバイク | 8 | 2 | |
| 駐車中の車に衝突した場合 | 10 | 0 | |
交差点では、追い越しのための車線変更は禁止されています。具体的には、追い越し行為は交差点とその手前30m以内の場所では、行ってはいけません。
そのため、車線変更を行った側の過失割合が重くなります。前方車:後方車=8:2もしくは、9:1となります。
車線変更車がウィンカーを出さずに車線変更し、事故を起こした場合、過失割合は車線変更車:後方車=9:1となります。
法律上、車線変更をする3秒前に合図を出さなければならないと定められています。そもそも、基本過失割合の「7:3」というのも、車線変更をする側の自動車が適切に指示器を出すことを前提にされています。
そのため、規則を守らないで、ウィンカーを出さず車線変更で事故を起こした場合はより重い責任が科せられます。
一方、「相手が道路交通法に違反したにもかかわらず後続車の過失割合が0にならないのか?」という質問が多数あります。
例えば、直進車同士並走していて、突然一方が車線変更しようとしたところ、直進車の側面にぶつかられた場合です。
事故状況により、車線変更をした自動車の動向が極めて悪質で直進車が避けようがない事故では、過失割合0というのもありますが、過失割合0と認定されるのは、稀であるとお考え下さい。
強引な車線変更によって真横から衝突した場合、基本過失割合「車線変更車:直進車=7:3」が修正され、車線変更車の過失が重く評価される可能性があります。
そもそもこの7:3という過失割合は、前方を走る車が進路変更するケースを前提としています。
一方、並走していた車両が強引に車線変更をして真横から衝突したケースや、車線変更車が後方から追いついてきて、まだ直進車の前に出ていないにもかかわらず、無理に車線変更して側面に衝突したようなケースでは、直進車が事故を避けるのは困難です。
実際にこうした状況では、直進車の過失が0%と認定された裁判例も複数存在します。
とはいえ、保険会社との交渉では「動いている車に過失ゼロは難しい」とされることが多く、示談で10対0が認められるのは例外的です。
車線と車線の間が黄色の実線道路では、隣の車線への追い越し禁止されており、車線変更はできません。
車線変更を禁止しているエリアで車線変更をし、事故を起こした場合の過失割合は、車線変更車:後方直進車=9:1となり、2割の過失が追加されてしまいます。
車線変更が禁止されているエリアでは、事故の有無にかかわらず、法律上の禁止により重い責任が科せられます。
車線変更した車と直進車がゼブラゾーンを走行して事故を起こした場合の過失割合は、車線変更車:直進車=6:4または5:5になります。
ゼブラゾーンとは、車両が安全に、円滑に走行できるように誘導するための区画線のことです。道路上にしましま模様で書かれていることからゼブラゾーンと呼ばれています。
ゼブラゾーンを走行することは、道路交通法上問題ありませんし、ゼブラゾーンを走行したことによる罰則もありません。
しかし、ゼブラゾーンはみだりに進入するべきではないと考えられているため、ゼブラゾーンを走行中にほかの車両と衝突した場合は1割~2割ほど過失割合が加算されることになります。
ゼブラゾーンでの事故の過失割合や慰謝料について知りたい方は、こちらのリンクをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
スピード違反は一般道で15~30キロの速度超過の場合は著しい過失として過失割合が1割加算されます。30キロ以上の速度超過の場合は重過失として過失割合が2割加算されます。
法定速度であれば、ブレーキを踏み事故を回避できたかもしれませんが、スピード違反の場合ではブレーキが間に合わず事故につながってしまう確率が高まります。
著しい過失と重過失の場合の過失割合を下表にまとめましたので、ご参考ください。
| 事故状況の具体例 | 時速15~30キロの速度超過 | 時速30キロ以上の速度超過 |
|---|---|---|
| 車線変更者がスピード違反 | 8(車線変更車):2(直進車) | 9(車線変更車):1(直進車) |
| 直進車がスピード違反 | 6(車線変更車):4(直進車) | 5(車線変更車):5(直進車) |
車線変更を行う車には「後方の安全を十分に確認し、他の車の進行を妨げてはならない」という法的義務があります。そのため、車線変更車が死角にいた直進車に気づかず衝突した場合でも、基本的な過失割合は「車線変更車7:直進車3」になります。
ただし、これはあくまで基本的な目安であり、事故状況によって過失割合は変動します。
たとえば、車線変更時にウィンカーを出していなかった場合や、車線変更禁止場所での進路変更だったような場合には、車線変更車の過失が90%以上となることがあります。
また、直進車がゼブラゾーンを走行していたり、スピードを出しすぎていたりした場合などは、直進車側にも10%~20%の過失が加算される可能性があります。
直進車に初心者マークがある場合は直進車の過失割合が1割軽減されます。
つまり、過失割合は車線変更車:直進車(初心者マーク)=8:2となります。
初心者マークは免許を取得してから1年未満のドライバーに車の前後に取り付けなければならないことが道路交通法で定められています。
初心者マークは周りの車に「運転に不慣れだ」とアピールするだけでなく、周りの車も十分に注意しなければならないことがすぐに分かります。
後方直進車が、初心者マークがついていることで、車線変更にはいつもより十分に注意しなければならないところ、車線変更によって事故を起こしたことから基本過失割合より重い過失割合が加算されます。
高速道路で発生する車線変更事故については、状況に応じて基本的な過失割合が定められています。
| 事故状況の具体例 | 基本の過失割合 |
|---|---|
| 追越車線への変更 | 8(車線変更車):2(直進車) |
| 走行車線への変更 | 7(車線変更車):3(直進車) |
| 本線への合流 | 7(合流車):3(本線車) |
高速道路での事故では、車線変更や合流をした車の方が、一般的に過失が大きくなります。
たとえば、走行車線から追越車線に移った車と、追越車線を直進していた車が衝突した場合の基本過失割合は、8(車線変更車):2(直進車)となります。
また、追越車線から走行車線へ戻る場合や、複数の走行車線間を移動した際の事故では、7(車線変更車):3(直進車)とされます。
さらに、加速車線から本線に合流しようとした車が本線の直進車と衝突した場合も、7(合流車):3(本線車)となります。
なお、直進車が優先でも、合流車に全く譲らない運転は危険です。事故防止には、互いの注意と譲り合いが大切です。
下表は、バイクと自動車の車線変更による事故における過失割合をまとめたものです。
バイクは自動車に比べ交通弱者であるため、「立場の弱い者の過失割合が低くなる」といった原則があり、基本過失割合は8(車線変更車):2(バイク)です。
| 事故状況の具体例 | 過失割合 |
|---|---|
| 車線変更をしたのがバイクだった場合 | 6(バイク):4(自動車) |
| 直進車がバイクだった場合 | 2(バイク):8(自動車) |
車線変更後に駐停車中の車に衝突した場合の過失割合は10(車線変更車):0(駐停車両)になります。
例えば、車線変更後に信号待ちをしている車両に衝突してしまった事故などでは追突事故と同じ過失割合となります。
なぜなら、駐停車している車は後ろから追突してくる車との衝突を避けることが通常であれば不可能であり、過失割合は0になります。
増額しなければ成功報酬はいただきません
過失割合はこのようにさまざまな事故形態によって過失割合が変わります。交通事故に詳しくなければ過失割合がどのくらいになるのかの判断は難しく、つい相手方保険会社の主張を受け入れがちです。
しかし、過失割合は損害賠償額に大きく影響するため、自社の損失を少なくしようと被害者に多く過失が付いている可能性も考えられます。
また、前記の表はあくまで目安であり、絶対的なものではありません。微妙な事故状況や、交渉対応でも過失割合は前後しますので、その点はご注意ください。
相手方保険会社が提示する過失割合に少しでも違和感を抱いた場合は交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
平成30年(ワ)第1561号 神戸地方裁判所 令和2年6月4日判決
片側3車線の道路で起きた交通事故です。自動車Aは、北側から接続する道路を南に進み、青信号に従って左折して第1車線に入りました。
この道路では前方に渋滞が発生しており、自動車Aはその最後尾につくためにスピードを落として走っていました。
ちょうど自動車Bの横に差しかかったところで、自動車Bが第2車線から突然第1車線に車線変更してきて、自動車Aの側面にぶつかったという事案です。
裁判所の判断裁判所は以下を理由に、本件事故はすべてBの不注意によるものと認めて、BとAの過失割合を10:0と判断しました。
判例のポイント車線変更による事故について、車線変更車の責任が100%認められた裁判例です。
本件事故は、Aが第1車線を徐行していたところに、Bが第2車線から突然車線変更してきて接触したというものでした。
裁判所は、Bが進路変更のときに周囲の安全を十分に確認せず、漫然と車線変更したことが事故の原因であると認定しています。
また、本件ではドライブレコーダーの映像が決定的な証拠となっている点もポイントです。
車線変更時の事故では、事故状況の記録や証拠の確保が、過失割合の判断に大きく影響することが示されています。
車線変更での事故は、スピード違反やウィンカーが出ていない、車線変更禁止場所など状況により過失割合が変動します。ただし、交通事故に詳しくない方にとっては、その過失割合が本当に正しいのか判断するのは難しいものです。
過失割合は示談交渉で決まりますが、相手方の保険会社が提示する内容が必ずしも正しいとは限らず、被害者に不利な割合が示されることもあります。
提示された過失割合に疑問がある場合は、交通事故に精通する弁護士法人ALGにご相談ください。
法的根拠に基づいて正当な過失割合を主張し、示談交渉も代行することで、精神的な負担を軽減しながら適切な解決を目指します。交通事故でお困りの方は私たちにお任せください。
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
