弁護士依頼前
約17万円
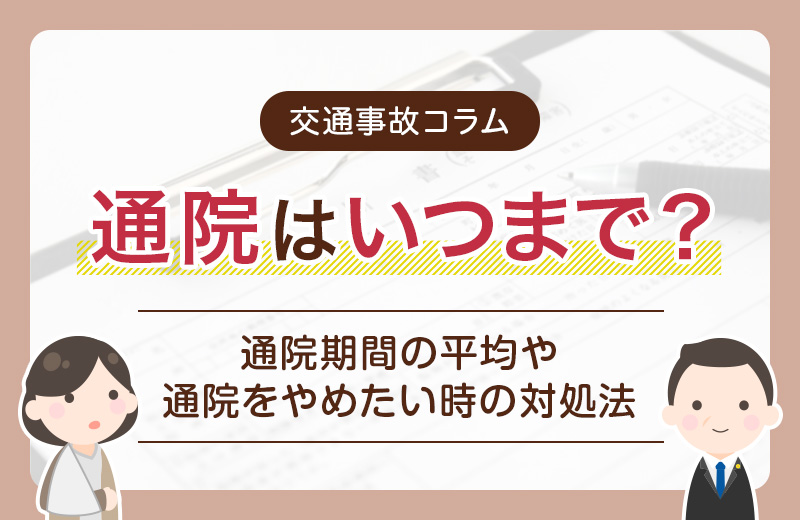
交通事故によるケガの治療は、いつまで、どのくらいの頻度で通院するべきか疑問に思う方は多いでしょう。
痛みがなくなったからと自己判断で通院を終えたり、心配だからと過剰に通院したりすると、慰謝料などの賠償金を十分にもらえなくなるリスクがあります。
適切な賠償金を受け取るためには、完治または症状固定と診断されるまで、適切な頻度で通院し続けることが大切です。
この記事では、適切な賠償金を得るために知っておくべき、通院期間・頻度について解説します。
通院期間の目安や注意点にも触れますので、ぜひお役立てください。
弁護士依頼前
約17万円

弁護士依頼後
約65万円
約48万円の増額
目次
交通事故の通院は、医師から完治または症状固定と診断されるまで続けることが必要です。
完治とは、ケガが完全に治り事故前に戻った状態をいいます。一方、症状固定とは、完治しておらず症状はまだ残っているものの、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を指します。
症状固定後に残った症状は後遺症として扱われ、後遺障害等級認定の対象となります。
通院期間はケガの程度や治療の進み具合によって異なりますが、例えば、むちうちでは3ヶ月から6ヶ月程度が目安とされています。
交通事故の通院をやめるタイミングは、医師が判断します。
医師がケガの症状や治療の経過を診たうえで、完治または症状固定と判断し、そこで初めて通院を終えることになります。痛みがなくなったからと自己判断で通院を終えると、損害賠償請求に影響が出るため、医師の判断に従うことが重要です。
もっとも、ケガの症状について最もよくわかっているのは被害者自身です。
主治医から症状固定と診断されたとしても、まだ治療により症状が改善していると感じるのであれば、治療の継続をお願いするべきでしょう。
仕事や育児などに追われて通院する暇がないという方もいらっしゃるかと思います。
しかし、交通事故での通院は、自己判断ではなく、医師から完治または症状固定と告げられるまで続けることが必要です。
この理由として、以下が挙げられます。
ここでは、症状固定や完治まで通院が必要な3つの理由について解説します。
交通事故の損害賠償については、以下のページで詳しく解説しています。
ぜひご一読ください。
合わせて読みたい関連記事
交通事故の治療費は、相手方の保険会社が直接病院に支払うことが多く、これを一括対応といいます。
しかし、自己判断で通院をやめると、保険会社が事故と治療との因果関係がなくなったと判断し、治療費の支払いを打ち切ることがあります。
通院をやめた後に症状が悪化して、通院を再開したとしても、保険会社から支払いを拒否される可能性が高いです。そのため、医師から完治または症状固定と診断されるまで、通院を続けることが必要です。
また、通院頻度が低い場合や、マッサージばかりのリハビリなど漫然治療が続く場合も、これ以上治療は必要ないとして、治療費の打ち切りに合う可能性が高いです。通院頻度や処方、施術は、医師の指示に従うことが必要です。
自己判断で通院をやめると、後遺障害等級認定で不利になる可能性があります。
後遺障害等級認定とは、後遺症が後遺障害であるかどうかを判断して、後遺症の症状や重さに応じて1級~14級に分類する手続のことです。後遺障害等級として認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能となります。
後遺障害等級認定では、治療の経過が考慮されます。そのため、通院期間が短い、通院頻度が少ないといった場合は、症状が軽かったとして認定を受けられない可能性があります。
また、後遺障害等級認定では、医師が作成する後遺障害診断書の提出が必須です。
通院期間や通院日数が少ないと、後遺症の症状を細かく記述できなくなり、認定が難しくなることがあります。
交通事故の後遺障害については、以下のページで詳しく解説しています。
ぜひご一読ください。
合わせて読みたい関連記事
入通院慰謝料とは、交通事故により入通院することで生じた精神的苦痛への賠償金です。
入通院慰謝料の金額には、通院日数や通院期間も大きく影響します。
そのため、一時的に痛みなどがなくなったからといって、自己判断で通院を中断すると、本来の通院期間より短くなり、慰謝料も低額になってしまいます。
また、入通院慰謝料は基本的に通院期間が長いほど高額となりますが、必要以上に長く通院すると過剰診療と判断されて、減額される可能性があります。
慰謝料の減額を防ぐには、主治医の意見を尊重したうえで、週2~3日(月に10日)を目安に通院治療を続けることが必要です。
増額しなければ成功報酬はいただきません
通院期間は、ケガの部位や状態などによって異なります。
ケガ別の、通院期間の目安をみてみましょう。
| ケガの種類 | 症状固定までの目安 |
|---|---|
| 打撲 | 数週間~1ヶ月 |
| むちうち・捻挫 | 3ヶ月(軽傷)~ 6ヶ月(重症) |
| 骨折 | 6ヶ月 |
ケガの部位や程度、被害者の年齢や健康状態にもよりますが、多くは上記の期間内に症状が軽快すると考えられています。
ケガが完治するのが理想ですが、治療を尽くしても症状の改善が見込めない場合は、いつまでも治療を続けることはできず、治療に区切りをつける意味で、上記の期間を目安に医師から症状固定と判断されることがあります。
医師からまだ完治や症状固定の診断を受けていないけれど、「お金がかかる」「忙しい」などの理由で、通院をやめたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、以下のケースごとの対処法についてご紹介します。
被害者の方で治療費を一時的に立て替えている場合は、経済的な理由で通院の中止を考えることもあるでしょう。通院中の金銭的負担は以下の方法で軽減できるため、お試しください。
健康保険の活用治療費の自己負担を1~3割に抑えられます。
加害者側の自賠責保険への被害者請求示談成立前に自賠責保険分を先に受け取れます。
治療費や入通院慰謝料、休業損害など傷害に関する賠償金は合計120万円まで支払われます。
加害者側の自賠責保険への仮渡金請求示談成立前にケガの状態に応じて5万~290万円を受け取れます。
最終的な賠償額が決定したときに差引き精算されます。
加害者側の任意保険への内払い請求交渉すれば、示談成立前に賠償金の一部を先払いしてくれる可能性があります。
「仕事が忙しくて通院する時間がない」「病院に行くのが億劫」などの理由で通院をやめたい場合は、病院の変更や通院頻度の再検討を行うことをおすすめします。
例えば、自宅から近い病院や、平日の夜や土日の診療も行っている病院に変更すれば、通院の負担を抑えられます。
また、病院はそのままが良いと思う場合は、主治医に通院頻度を減らせないか相談すると良いでしょう。現状より通院日数を少なくできれば、通院の負担を和らげることができます。
ただし、主治医と相談して決めたとしても、通院頻度が低くなりすぎると入通院慰謝料が減額されたり、治療費が打ち切られたりするおそれがあります。少なくとも月に1回程度は通院するよう心がけましょう。
増額しなければ成功報酬はいただきません
交通事故の通院期間については、医師の指示に従うのはもちろん、ほかにも注意すべきことがあります。
適正な賠償を受けるためにも、特に以下の2つのポイントを守ることが必要です。
相手方の保険会社から、治療費の打ち切りを打診されても、安易に受けないようにしましょう。
保険会社は、ケガの症状ごとにあらかじめ想定した治療の終了時期になると、「そろそろ治療が終了する頃なので、治療費を打ち切ります」と連絡してくることがあります。
このとき、医師が治療を継続すべきと判断しているのであれば、保険会社の打診には応じずに、治療費の延長をしてもらえるよう交渉しましょう。
保険会社の打診を安易に受け入れて治療を終了してしまうと、通院期間・日数が減って、受け取れる慰謝料が少なくなったり、後遺障害等級認定に不利になるなど、適正な賠償金が受け取れなくおそれがあるためです。
交通事故の治療打ち切りについて、以下のページで詳しく解説しています。
ぜひご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
通院日数が多ければ、その分慰謝料が増額するわけではありません。
入通院日数や期間は交通事故の慰謝料に影響します。
しかし、だからといって、単純に通院日数を増やせばいいというものではありません。
自己判断で通院日数を増やしてしまうと、必要かつ相当な治療ではない治療を繰り返している過剰診療と判断されて、治療費や慰謝料が減額される可能性があります。
合わせて読みたい関連記事
信号待ちをしていた依頼者の車に相手車が追突し、依頼者が首に挫傷を負った事案です。
依頼者の通院期間は約6ヶ月であるものの、実際に通院した日数は30日に満たないものでした。
慰謝料の相場は、裁判では一般的に通院期間等により決められますが、通院頻度が著しく低いと通院日数をもとに慰謝料が算定されることがあります。これを根拠に、相手方保険会社は約17万円という低額な慰謝料を提示してきました。
そこで、弁護士は裁判基準での慰謝料を受け取るため、依頼者から通院頻度が少なかった事情を詳しく聴き取り、保険会社に通院頻度が合理的であることを説明しました。
その結果、保険会社が当初の提示額より約48万円増額した、約65万円の賠償金の支払いに応じ、裁判基準を上回る金額を得ることに成功しました。
交通事故が原因でケガを負ったにもかかわらず、通院期間・頻度が適切ではないという理由で、本来受け取れるはずだった賠償金が減ってしまうのは、被害者の方にとって本意ではないはずです。
適正な賠償金を受け取るためにも、医師の指示に従い、適切な通院期間・頻度で治療を受けましょう。
弁護士法人ALGには、医学知識の豊富な弁護士も在籍しているので、通院方法や後遺障害等級認定についてもアドバイスやサポートが可能です。
治療を受けるために減ってしまった収入を補うための、休業損害や逸失利益の請求や、賠償金の増額に向けた示談交渉も、弁護士に任せていただけます。
事故によるケガの通院で、少しでも不安に感じることがあれば、私たち弁護士法人ALGへ一度ご相談ください。
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
