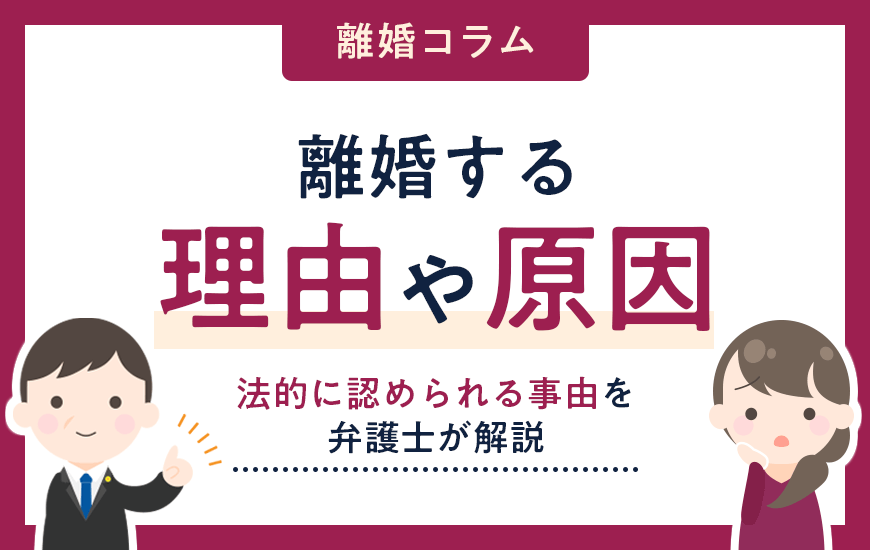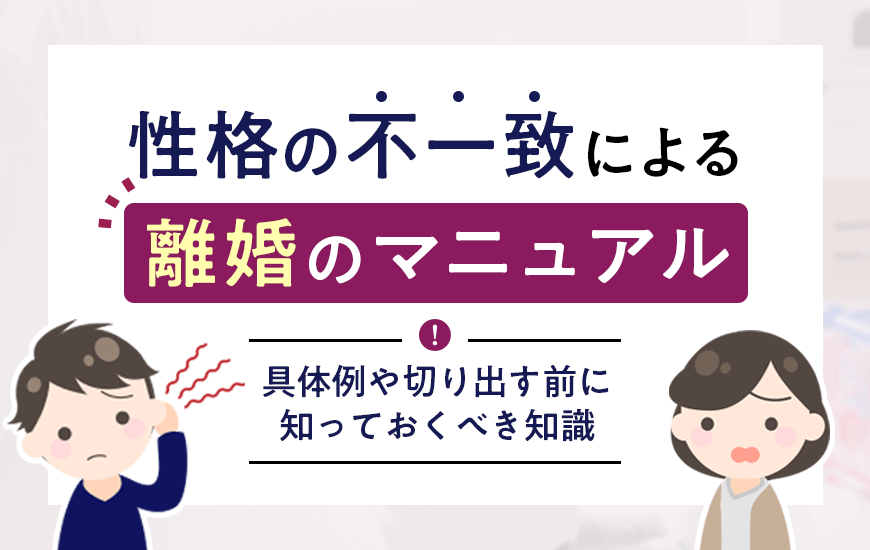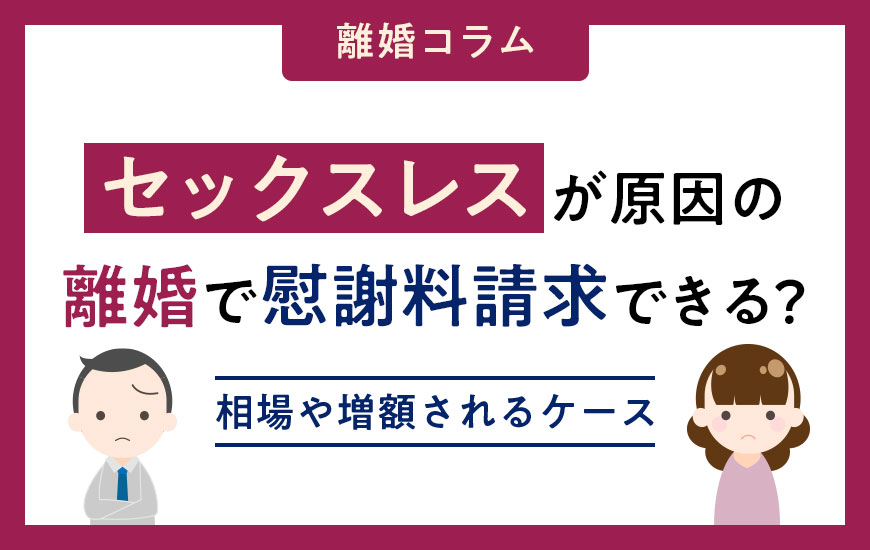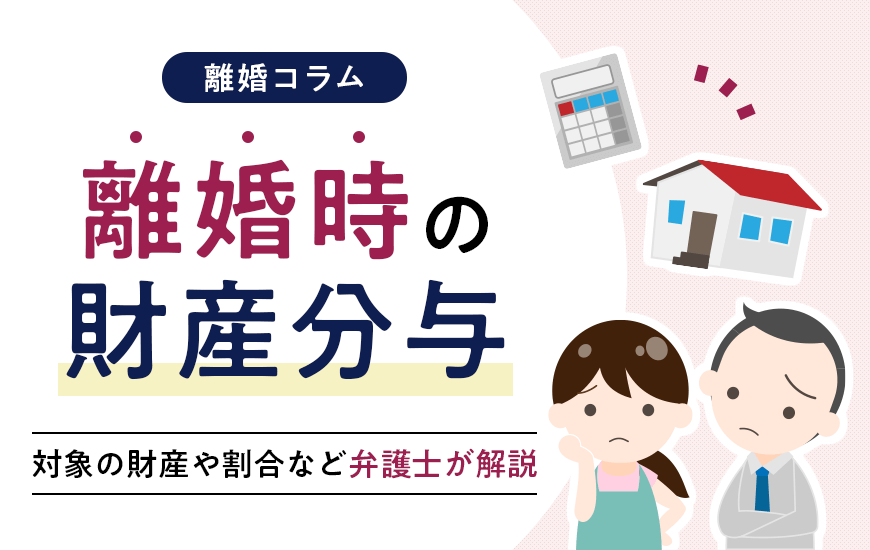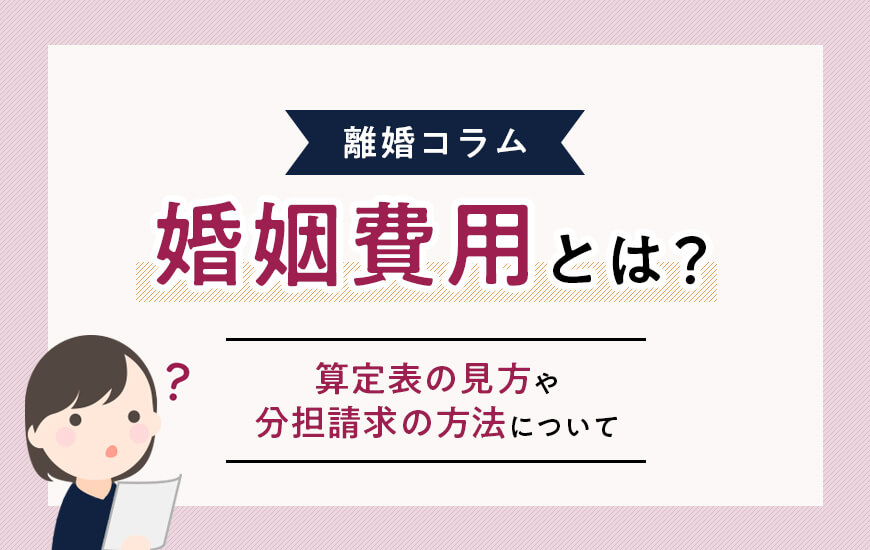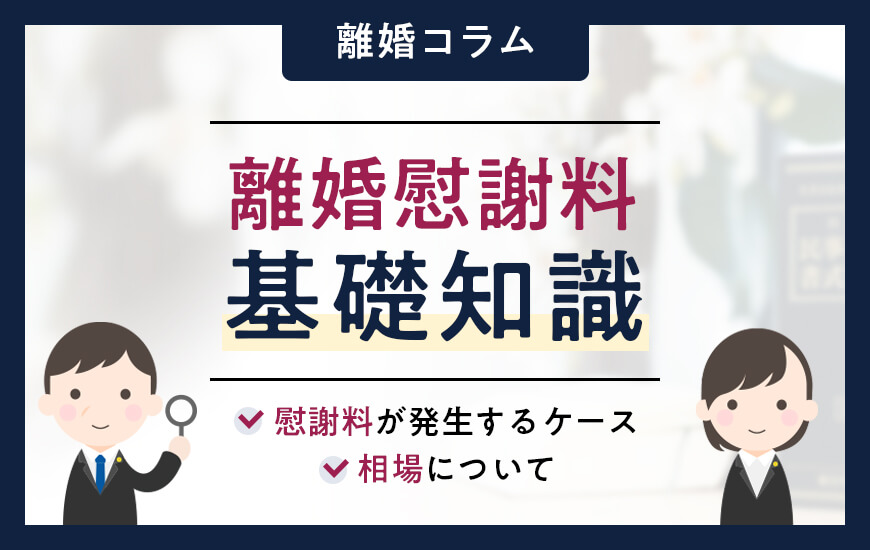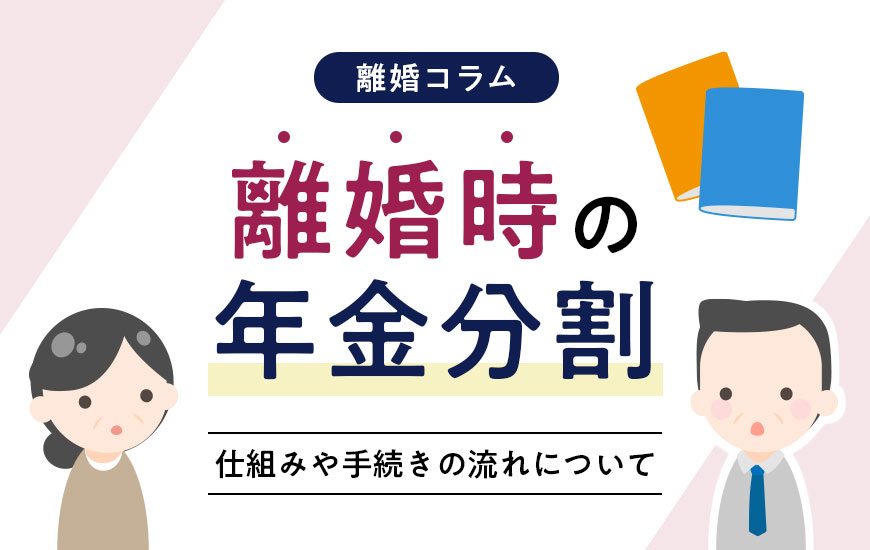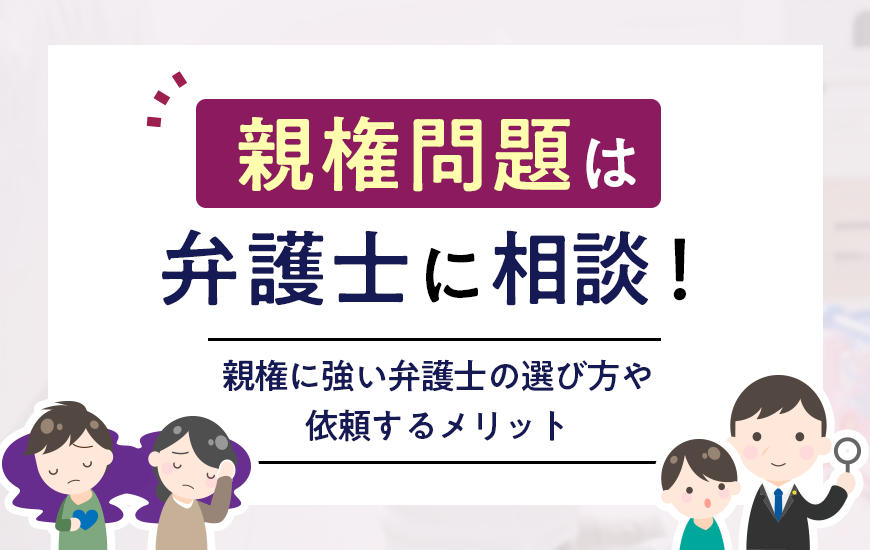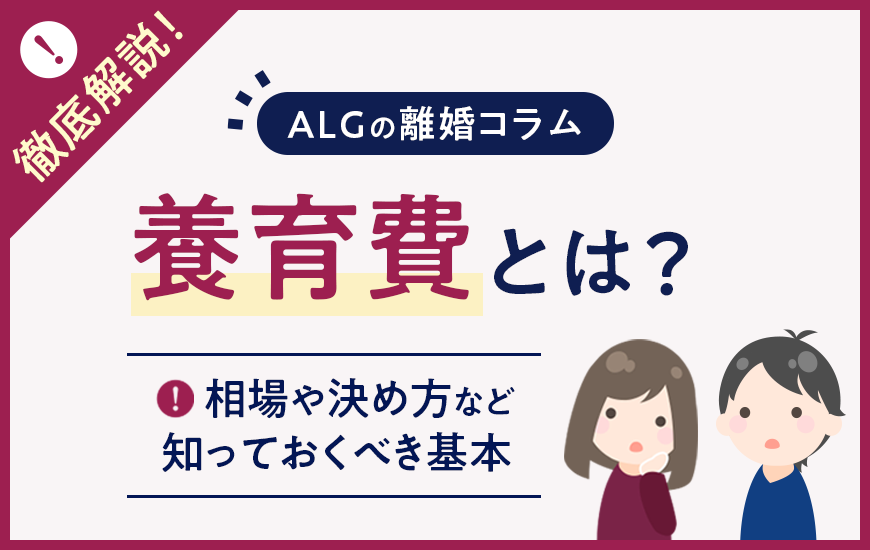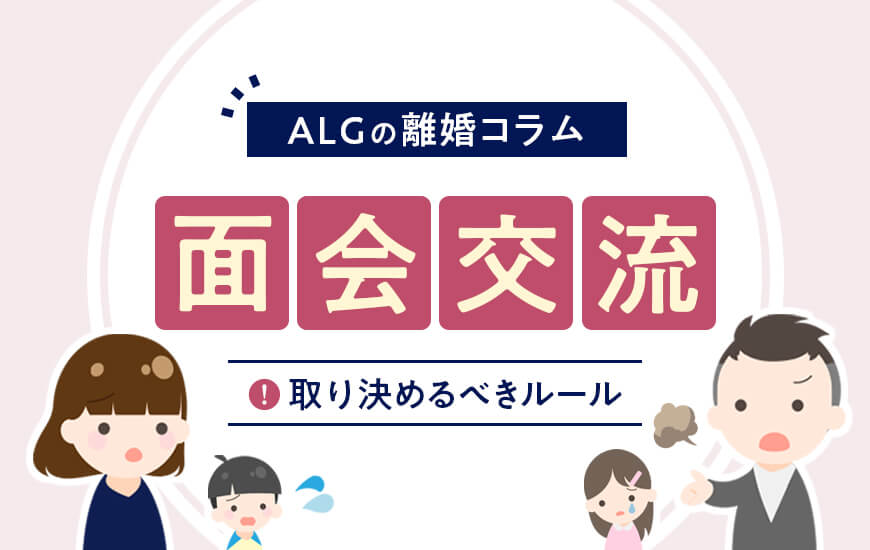30代で離婚を考えたら|離婚に至る理由や決めておくべきことを解説

30代というと公私ともに多忙な世代です。
キャリアアップや妊娠・出産など、人生の選択に葛藤の多い世代でもあり、離婚について悩まれている方も少なくありません。
実際、30代は離婚率の高い世代だという統計もあって、離婚理由にも30代特有の特徴があります。
本ページでは、離婚を検討されている30代の方に向けて、どのような理由で離婚するケースが多いのか、なにを決める必要があるのかを解説します。
30代で離婚するメリットやデメリットも紹介していくので、後悔の少ない選択ができるよう参考になさってください。
目次
30代で多い離婚の理由は?
近年、30代は離婚率がとくに高い世代だといわれています。
厚生労働省が発表した人口動態統計で年代別の離婚率をみてみると、2022年に離婚した30代夫婦は、妻が30%で最も離婚率が高く、夫は27%と40代の次に高い離婚率となりました。
| 2022年に離婚した夫婦(17万9099件)の年代別離婚率 | |
|---|---|
<夫>
|
<妻>
|
離婚に至る理由はさまざまですが、30代に多い離婚の理由は次のとおりです。
- 性格の不一致
- 子供を持つかどうか・セックスレス
- 共働きによるすれ違い
- 転勤や海外赴任
- 家事育児の分担でもめる
このうち、性格の不一致は30代に限らず、ほかの世代でも最も多い離婚理由ですが、それ以外は「公私ともに多忙な世代」ならではの30代特有の理由といっても過言ではありません。
それぞれの離婚理由について、次項でもう少し詳しくみていきましょう。
「こんな理由で離婚できる?」と悩まれている方は、以下ページをご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
性格の不一致
世代や性別を問わず、離婚の理由で最も多いのが“性格の不一致”です。
30代の夫婦では、
- 夫婦として一緒に暮らすなかで、価値観や金銭感覚の違いに我慢できなくなった
- 子供の教育方針について対立することが増えた
など、性格や価値観の違いが浮き彫りになり、今後の人生を考えて「やり直すなら早い方がいい」と離婚に至るケースが多く見受けられます。
◆注意!性格の不一致は法定離婚事由に該当しません
夫婦の話し合いによる協議離婚や調停離婚で離婚が成立せず裁判へ発展した場合、性格の不一致だけでは法定離婚事由に該当せず離婚が認められないため、ほかの事情とあわせて婚姻を継続しがたい重大な事由があることを主張しなければなりません。
詳しくは以下ページをご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
子供を持つかどうか・セックスレス
30代夫婦の間で、子供を持つかどうかで意見がすれ違い、離婚に至るケースが少なくありません。
キャリアアップを優先したり、30代半ばを過ぎてからの妊娠・出産のリスクから、「子供を持たない」という選択をされる夫婦も増える一方で、次のような事情で夫婦の意見が合わずに、離婚を考える方もいらっしゃいます。
- 自分は早く子供が欲しいのに、配偶者がキャリアを優先して協力してくれない
- なかなか子供ができず、夫婦の間で子供に対する意見がすれ違うようになった など
とくに、子供を持ちたくない配偶者とセックスレスになってしまった場合、相手への不満が募るのも無理はありません。
病気などの正当な理由なく、一方的に夫婦の触れ合いを長期間拒むようなケースでは、法定離婚事由に該当して裁判で離婚が認められるだけでなく、慰謝料を請求できる可能性もあります。
詳しくは以下ページをご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
共働きによるすれ違い
30代といえば男女ともに働き盛りで、社会で活躍する女性が増えた昨今、共働きによるすれ違いで離婚する夫婦も増えました。
- 夫婦ともにキャリア志向で、夫婦生活や子供に関する考えにずれが生じた
- 仕事が忙しくて、夫婦一緒に過ごす時間が少ない など
共働きの場合、お互いが経済的に自立していて離婚後の生活を心配する必要のないことから、離婚に踏み切りやすい傾向にあります。
転勤や海外赴任
働き盛りの30代に多い転勤や海外赴任がきっかけとなって離婚に至るケースも、30代夫婦の離婚理由の特徴のひとつです。
- 配偶者の転勤・海外赴任で、住みなれない場所での生活に不安・不満が募った
- 転勤・海外赴任先についてきてほしいと言われたけれど、今の仕事を辞めたくない
- 転勤・海外赴任先についていきたくないと言われて、相手と言い争いになった
- 転勤・海外赴任で仕方なく離れて暮らすことになり、夫婦の間ですれ違うことが増えた など
転勤や海外赴任をきっかけにお互い納得して別居したものの、すれ違いが増えて最終的に離婚に至るケースも少なくありません。
家事育児の分担でもめる
共働きなのに、家事育児の分担が不公平という理由で離婚に至る夫婦が多いのも、30代夫婦の特徴のひとつです。
共働きなのに、家事や育児の負担が一方に偏ると、夫婦の間で家事育児の分担をめぐってトラブルに発展しやすくなります。
女性の社会進出が増えているにもかかわらず、いまだに「家事育児は女性の役割」という考えが根強く残っていて、女性が働きながら家事育児のほとんどを行っていると不満が募り、耐え切れなくなって離婚を切り出すケースが多くみられます。
30代で離婚するメリットやデメリット
30代で離婚を検討されている方に向けて、メリットとデメリットを紹介します。
30代はやり直すのに遅くない年代ですが、焦って離婚してしまうと後悔することもあるので、メリットとデメリットを知ったうえで、離婚すべきかどうかを慎重に判断しましょう。
メリット
30代で離婚するメリットとして、次のようなものが挙げられます。
- 30代は離婚しても、再婚や再就職など、再出発が十分間に合う
- 離婚後新たに仕事をはじめたとしても、キャリアアップできる可能性がある
- 配偶者に対するストレスから解放されて、新しい生活を始められる
- 離婚を選択することで、築き上げた生活環境を変化させずに済むことがある など
デメリット
30代で離婚するデメリットとして、次のようなものが挙げられます。
- 子供がいる場合、離婚による子供への影響に配慮が必要になる
- 養育費の支払期間が長くなることにより、未払いが生じる可能性がある
- 子供との面会交流が難しくなる可能性がある
- 住宅ローンが残っていたりして、財産分与で揉める可能性がある など
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
30代で離婚する際に決めておくべき7つのこと
「やり直すなら30代のうちに・・・!」と離婚を焦ると、経済的に困窮することになったり、子供に大きな負担がかかったりして、離婚を後悔することになりかねません。
新しい人生の再スタートがスムーズに切れるように、離婚後の生活を思い描きながら、お金のことや子供のことを離婚前にしっかり決めておきましょう。
次項では、離婚前に決めておくべき7つの事柄について詳しく解説していきます。
30代で離婚する際に決めておくべきお金のこと
- ①財産分与
- ②婚姻費用
- ③慰謝料
- ④年金分割
30代で離婚する際に決めておくべき子供のこと
- ⑤親権
- ⑥養育費
- ⑦面会交流
お金のこと
離婚するにあたっては、財産分与、婚姻費用、慰謝料、年金分割といった、お金のことについてきちんと取り決めておきましょう。
①財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚する際に公平に分け合うことをいいます。
30代夫婦が離婚する場合、財産分与の対象となる共有財産はそれほど多くないかもしれませんが、家や車のローンを組んで間もないことが多いので、ローンが残った財産をどのように分けるのか、離婚後はどちらがローンを支払うのかなど、しっかり話し合って決める必要があります。
ローン返済中の財産分与でお困りの方や、相手が財産を隠すかもしれないと不安に感じていらっしゃる方は、弁護士に相談することをおすすめします。
離婚時の財産分与について詳しくお知りになりたい方は、以下ページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
②婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦や未成年の子供が一般的な社会生活を送るうえで必要な生活費のことをいいます。
夫婦は法律上、婚姻費用を分担して生活を経済的に助け合う義務を負っています。
したがって、離婚前に別居するケースでは、収入の少ない側から収入の多い側に婚姻費用を請求することができるのです。
離婚を前提に別居する場合や、離婚すべきか迷っていて一度距離を置きたいと考えている場合も、まずは婚姻費用を受け取りながら生活を安定させたうえで、次のステップへ進むことが大切です。
婚姻費用については、以下ページでも詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
③慰謝料
慰謝料とは、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛に対する金銭的な補償のことをいいます。
30代夫婦の離婚で慰謝料が請求できる可能性があるケース例
- 配偶者に不倫された
- 配偶者からDV・モラハラを受けた
- 健康上の理由もないのに一方的に性交渉を拒否された など
離婚に至った場合の慰謝料の相場は、一般的に200万~300万円程度といわれていますが、婚姻期間の長さや子供がいるかどうかなどの事情によって金額は変わります。
夫婦間の話し合いがまとまらない場合、調停や裁判で慰謝料を請求することになりますが、その際は不法行為を客観的に裏付ける証拠が必要になります。
離婚慰謝料の相場や証拠については、以下ページでも詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
④年金分割
年金分割とは、夫婦が婚姻中に協力して納めた厚生年金の保険料を離婚する際に分け合うことをいいます。
専業主婦の場合や、配偶者より収入が低い場合、離婚時に年金分割を行うことで将来受け取る年金の額に反映してもらえるため、忘れないようにしましょう。
【年金分割の方法】
年金分割には2種類の方法があります。
- 分割の割合を夫婦の話し合いによって決定する合意分割
- 会社員や公務員の配偶者の扶養に入っていた3号被保険者に適用される3号分割
3号分割の場合は配偶者の合意なく単独で請求できますが、合意分割は話し合いで合意できない場合、調停や審判で年金分割について取り決めることになります。
「自分はどの方法で年金分割できるのか?」や「どうやって請求すればよいのか?」など、年金分割について詳しくお知りになりたい方は、以下ページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
子供のこと
夫婦のあいだに子供がいる場合、親権、養育費、面会交流についても、あらかじめ取り決めておきましょう。
⑤親権
親権とは、未成年の子供が健全に成長できるように監護・教育を行ったり、子供の財産を管理したりする権利や義務のことをいいます。
夫婦の間に未成年の子供がいる場合、離婚後にどちらが親権者となるのかを決めなければなりません。
30代夫婦の場合、子供はまだ幼いことが多いので、母親が親権者になる可能性が高いですが、夫婦の話し合いによってどちらが親権者になるのかを決めることが可能です。
◆話し合いがまとまらない場合は調停や裁判で親権者を決める
調停や裁判では、必ずしも母親が親権を獲得できるとは限りません。
子供との関わり方や生活環境など、子供の幸せのためにはどちらが親権者にふさわしいのかが重視されます。
親権を獲得したいとお考えの方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談するメリットや弁護士の選び方について以下ページで解説していますので、あわせてご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
⑥養育費
養育費とは、子供を監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
養育費の金額や支払方法、支払期間などは夫婦で話し合いって自由に取り決めることができます。
30代夫婦の場合、離婚後の養育費の支払期間が長くなることが多いので、未払いに備えて支払いが滞ったときのペナルティも決めておき、話し合いで合意できた内容は強制執行認諾文言付き公正証書として合意書を作成しておきましょう。
◆話し合いがまとまらない場合は調停や審判で養育費について決める
審判では、裁判所が作成した“養育費算定表”を用いて、夫婦それぞれの年収や、子供の年齢・人数などから標準的な養育費を算定し、具体的な金額を決定します。
算定表は一般公開されているので、協議離婚や離婚調停でも参考として用いられます。
養育費の取り決めについて不安がある方や、具体的な金額がお知りになりたい方は弁護士へ相談することをおすすめします。
詳しくは以下ページをご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
⑦面会交流
面会交流とは、離れて暮らす親子が定期的・継続的に交流することをいいます。
面会交流について法的な決まりはないので、夫婦間で自由に取り決めることができますが、面会交流の方法や日時、頻度、時間、場所、待ち合わせ方法など、後にトラブルとならないように具体的に決めておき、公正証書で合意書を作成しておくことが大切です。
◆話し合いがまとまらない場合は調停や審判で面会交流について決める
面会交流は子供が健全に成長するために欠かせないものなので、連れ去りや子供へのDVといった危険がない限り、裁判所は面会交流を行うことに前向きです。
夫婦間で話し合うときにどのようなことを決めておくべきか、面会交流の決め方など、以下ページでさらに詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
30代で離婚をお考えの方は弁護士にご相談ください
30代は離婚して人生の再スタートを切るのに、十分間に合う年代です。
だからといって感情のまま、無計画に離婚を進めてしまうと後悔するおそれもあるので、離婚するメリットとデメリットを踏まえて、夫婦でよく話し合うことが大切です。
子供のことや、共働き・転勤・海外赴任によるすれ違いなどで「このままでいいのかな?」、「離婚して新しい人生を再スタートすべき?」とお悩みの方は、一度弁護士法人ALGまでご相談ください。
30代夫婦の離婚問題にも数多く携わってきた弁護士が、経験や知識を活かし、ご相談者様にとって最善の選択ができるようにアドバイスいたします。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)