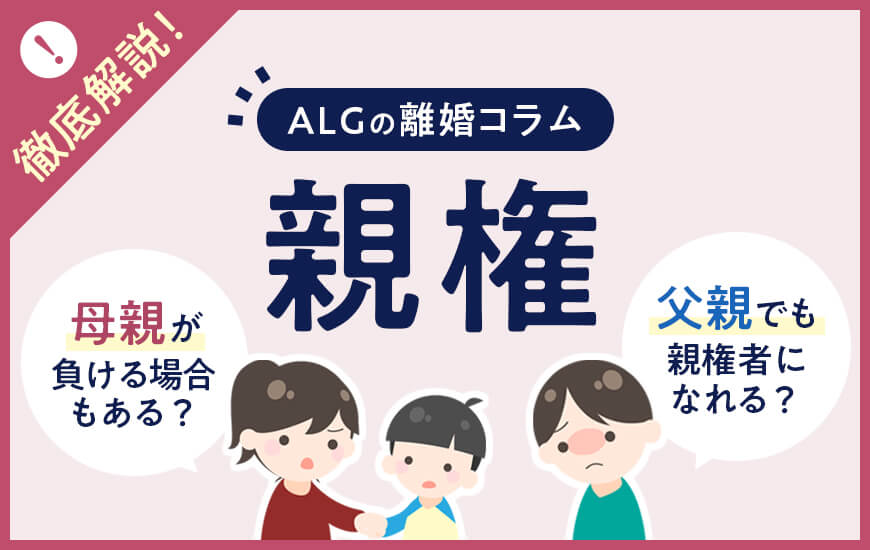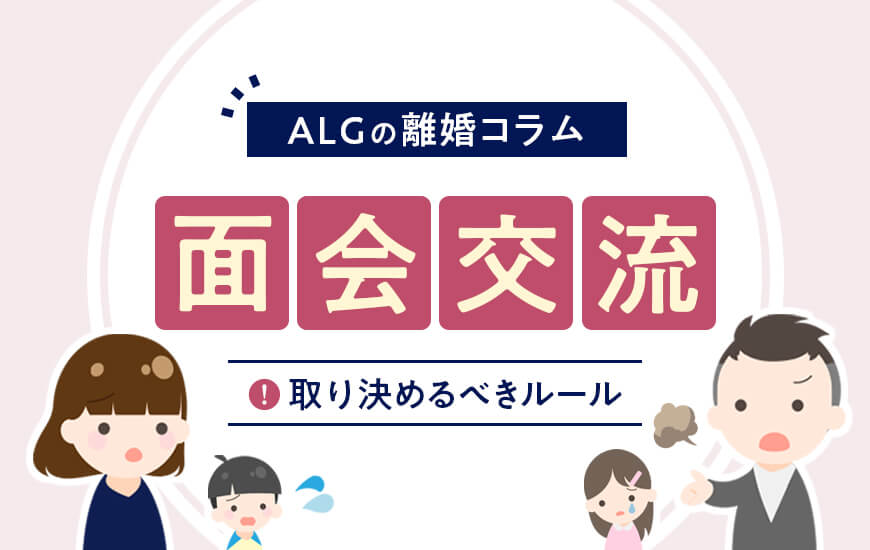親権者の変更方法|離婚後に変更可能なケースや取り戻すポイントなど
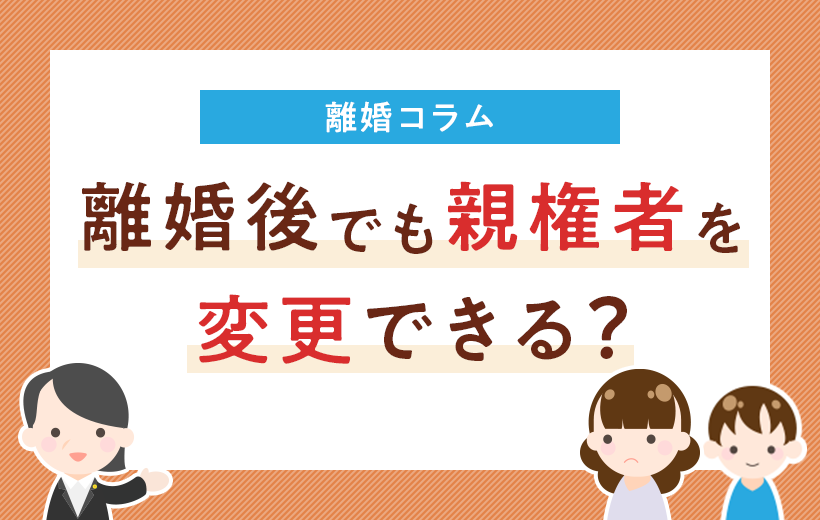
離婚時に夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、離婚後に子供を監護養育する親権者を決めなければなりません。
しかし、離婚後何らかの事情により親権者を変更したいと考える場合もあるでしょう。
親権者は父母の話し合いだけでは変更することができず、家庭裁判所の手続きを経なければなりません。
この記事では離婚後の親権者変更に着目し、離婚後の親権者変更手続きや離婚後に親権を取り戻すポイントなどについて解説していきます。
目次
離婚後の親権者変更手続き
離婚後、父母の事情の変化などを理由に親権者を変更することが可能です。ただし、父母の話し合いのみでは変更できません。
親権者を変更することは、子供の現在の生活環境や今後の人生に大きな影響を及ぼす重大な事柄であり、父母の話し合いのみで簡単に決めることは妥当ではないと考えられているからです。
そのため、離婚後に親権者を変更する際には、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。
一方、監護者の変更は父母の話し合いのみで決めることができます。
ただし、当事者間の話し合いで合意できなければ家庭裁判所の手続きを利用して話し合いを行います。
親権者を変更する際の流れは以下のとおりです。
- 親権者変更調停の申し立て
- 調停が不成立の場合は親権者変更審判
次項では親権者変更手続きについて詳しく解説していきます。
親権者変更調停の申立て
親権者を変更したい場合は、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てる必要があります。申立先の家庭裁判所は、相手方の住所を管轄する家庭裁判所となります。
必要書類と費用は以下のとおりです。
| 必要書類 |
|
|---|---|
| 費用 |
|
親権者変更調停が成立した場合
調停が成立し、親権者が変更された場合は、戸籍法による届け出義務があります。
そのため、調停が成立してから10日以内に以下の書類を役所に届け出る必要があります。
- 調停調書謄本
- 父母それぞれの戸籍謄本
調停が不成立の場合は親権者変更審判
調停で折り合いがつかず、調停不成立となった場合は、自動的に審判手続きに移行します。
審判では、裁判官があらゆる状況を調査して親権者変更をするべきかどうかを検討し、決定を下します。
審判になると裁判官は調査官により作成された調査報告書を参考に審判をします。
裁判官は調査官の調査を重視しますので、調査官の調査への対応は親権者変更審判の当事者にとって大事なポイントです。
親権者変更の例外
例外的に親権者変更調停や審判を行わなくても親権者を変更できるケースがあります。
認知した父親を親権者に指定したり、離婚後に産まれた子供について、父親を親権者に指定したりする場合は、父母が合意して届け出ができ、家庭裁判所の手続きは不要です。
合わせて読みたい関連記事
親権者の変更が可能なケース
親権者変更調停を申し立てても必ず親権変更が認められるわけではありません。
親権者の変更が認められるには、現在の環境を変えてでも親権者を変更するべき理由が必要です。
具体的には、以下のようなケースにおいては親権者変更が認められやすいでしょう。
- 親権者による子供への虐待・育児放棄している
- 親権者が行方不明・重大な病気になった・死亡した
- 15歳以上の子供が親権者の変更を望んでいる
- 養育状況が大幅に変化する
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
親権者による子供への虐待・育児放棄している
現在の親権者が子供に虐待・育児放棄をしている場合は、親権者の継続が子供の健やかな成長を妨げることは明らかです。
このケースは、非親権者や祖父母などの親族が家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てれば、親権者変更が認められる可能性は高いでしょう。
親権者が行方不明・重大な病気になった・死亡した
親権者が行方不明になったり、重大な病気になったり、死亡したりしたケースでは、親権者の変更が認められやすくなります。
重大な病気とは、精神的な病気や長期で入院をする場合が含まれます。
ただし、親権者が死亡した場合、「未成年後見人」という手続きが始まり、「未成年後見人」が子供の法的代理人となります。
親権者が死亡したからといって、何の手続きもなしに非親権者である親が親権者となるわけではありません。
親権者を変更するためには、非親権者が未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、親権者変更の審判を申し立てる必要があります。
15歳以上の子供が親権者の変更を望んでいる
親権者変更の申立てがされたとき、子供が15歳以上であれば、裁判所は子供の意思を確認します。
15歳以上の子供は、自分の人生についてある程度の判断能力があると認められるため、親権者を変更すべきかの判断ができると考えられているためです。
※2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられたため、18歳から親権者の変更は不要となりました
養育状況が大幅に変化する
子供の養育状況が大きく変わった場合も親権者の変更が認められやすくなります。
具体例としては以下になります。
- 親権者が海外転勤になった場合
- 転職して多忙となり子供の世話が十分にできなくなった場合
ただ、環境の変化によって必ずしも親権者を変更するべきと判断される訳ではありません。
環境の変化により、子供に悪影響を及ぼすような場合に限って親権者変更が認められます。
親権者の変更が難しいケース
親権者の変更が難しいケースとして、以下のようなものが挙げられます。
- 再婚のために子供の親権者を変更するケース
- 面会交流が守られないために親権者を変更するケース
親権者が再婚により子供の存在が疎ましくなってしまうことや、再婚相手が難色を示すこともあるかもしれません。
しかし、これは単なる親の都合であり、親権者変更が認められる可能性は低いでしょう。
面会交流をさせないからといって、子供の監護・養育を怠っているわけではなく、親権者変更が認められる可能性は低いでしょう。
このようなケースではまず、面会交流調停を申し立て、子供との面会交流を求めましょう。
面会交流については、以下のページでも詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
離婚後に親権を取り戻すためのポイント
離婚後に親権を取り戻したいと考える場合、以下の3つのポイントがあります。
- 調停委員を味方につける
- 家庭裁判所調査官の調査
- 弁護士への依頼を検討する
次項でそれぞれについて詳しく解説していきます。
①調停委員を味方につける
調停委員を味方につけることは、親権者変更調停においてとても重要です。
調停では、調停委員が進行役となり、当事者双方の主張を聞いて、お互いが納得できるよう解決に向けた調整をしてくれます。
そのため、調停委員を少しでも味方につけることができれば、親権者変更調停を自身に有利な流れで進めていける可能性が高まります。
調停委員と話すときは、以下の点に注意して、調停委員の理解をより得られるよう工夫すると良いでしょう。
- 礼儀正しく冷静に対応する
- わかりやすく主張を伝える
- 嘘をつかず事実のみ伝える
②家庭裁判所調査官の調査によって調停・審判を優位に進められることがある
親権者変更を行うに当たって、家庭裁判所の調査官による調査が行われることがあります。
具体的には、以下のような調査が行われます。
- 家庭訪問や学校訪問を行って養育環境や子供が健全に調査しているかを調査する
- 親権者変更について子供の意見を聞き取る
調査の結果、子供の養育環境に問題があることや健全な発育が阻害されていることが判明すれば、親権者変更調停・審判を有利に進めることができるでしょう。
③弁護士への依頼を検討する
親権者変更調停は、必ずしも弁護士に依頼しなければならないという決まりはなく、ご自身でも対応できます。
ただし、弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを受けることができるでしょう。
- 法律の知識や経験を踏まえたアドバイスがもらえる
- 親権者変更に対し真剣であるという印象を調停委員に与えることができる
- 調停の場で依頼者が親権者にふさわしいことを主張・立証できる
親権を獲得するためには、いくつかのポイントを押さえ、効果的な主張・立証をする必要がありますので、弁護士への相談も検討されると良いでしょう。
離婚後に親権者の変更ができた裁判例
離婚後に親権者の変更ができた裁判例をご紹介します。
事案の概要
申立人(父)と相手方(母)は、相手方を親権者とする協議離婚が成立し、相手方は未成年者(子)を連れて実家に戻りました。
しかし、相手方は次第に家族と不仲になり、子供への監護がおろそかになっていったため、次第に姉を中心とする相手方の家族が未成年者の監護を担うようになりました。
相手方は賃貸物件へ転居するも、未成年の子はこれを拒否し、相手方実家にとどまりました。
審判における未成年者に対する調査でも、未成年者は母親である相手方とは生活したくない、現在の生活を続けたい、また将来的には父親である申立人と生活したい旨を述べていました。
裁判所の判断
離婚後、相手方の未成年者への関わり方が変化し、しかも、相手方と未成年者が生活拠点を異にするなど、未成年者をめぐる監護状況に変更が生じているため、その状況に応じて未成年者の親権者を相手方から申立人に変更する必要があると認めました。
(平成25年(家)第6345号 平成26年2月12日 東京家庭裁判所 審判)
離婚後の親権者変更に関する質問
父親から母親へ親権者を変更する際の有利になるポイントはありますか?
現在は、「母親」だからといって親権者変更に有利だとは限りません。
「父親」でも「母親」でも大事なのは子供が健やかに成長していけるかという点です。
子供に愛情を注ぎ、子供が安心して暮らせる環境があることを調停委員にしっかりと伝えることが大切です。
離婚後に親権者の変更を行った場合、戸籍はどうなりますか?
離婚後に親権者の変更が認められた場合、子供の戸籍を「親権者」の戸籍に移すために、親権者変更届を提出した後、子供の住所を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行い、許可が下りたら、母(父)の氏を称する「入籍届」を役所に提出します。
親権者を変更したい場合は弁護士法人ALGにご相談ください!
離婚後に親権者を変更したいと思うことは、子供に愛情を注いでいるからこそ当然のお気持ちでしょう。
しかし、手続きを有利に進めるためにはどうしたらいいかお悩みではないでしょうか。
離婚後の親権者変更については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、離婚や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。
弁護士は、親権者変更について知識や経験を踏まえたアドバイスができるだけでなく、調停の場に一緒に出席し、調停委員に対して主張・立証することが可能です。
離婚後の親権者変更は、当事者間の話し合いでは変更できず、調停を経なければなりません。
慣れない手続きでお悩みやご不安もあるかと思いますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)