離婚したくない場合に離婚調停でとるべき対処法とやってはいけない行動
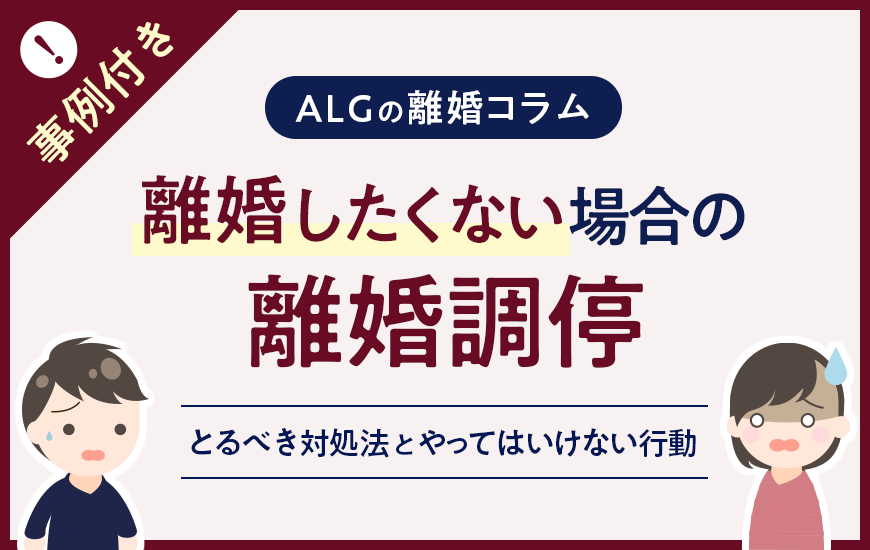
離婚したくないのに、いきなり離婚調停の通知が届いたら、「離婚するしかないのか」と悩んだり、困惑したりするかと思います。
離婚調停を申し立てられたからといって、必ずしも離婚が成立するわけではありませんのでご安心ください。
ただし、将来的に離婚に繋がってしまう可能性もありますので、離婚調停において適切な対応をとる必要があります。 そこで、本記事では・・・
- 離婚調停で離婚したくない人がとるべき5つの対処法
- 離婚したくない人がやってはいけない3つの行動
などについて、離婚したくないのに離婚調停を申し立てられた方に向けて、参考になるようにわかりやく解説いたします。
目次
離婚したくないのに離婚調停を申し立てられたらどうなる?
離婚調停とは、正式には「夫婦関係調整調停(離婚)」といい、家庭裁判所で調停委員を介して様々な離婚問題について話し合いで解決を図る手続きをいいます。
家庭裁判所から離婚調停の申立書や呼出状などが届いたら、「離婚したくないのに離婚させられてしまう」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、離婚調停はあくまでも話し合いでの手続きですので、夫婦のどちらかが離婚に合意しなければ成立しません。
よって、離婚調停を申し立てられたからといって、強制的に離婚が成立することはありません。
離婚を拒否すれば調停は不成立
離婚調停は、調停委員が介入したうえで、当事者間で話し合い、合意することで解決する手続きです。
よって、離婚調停を申し立てた側は離婚を望んでいても、一方の配偶者が離婚を拒否していると、話し合いは平行線となるので調停は不成立になります。
調停不成立になると裁判に進む可能性がある
離婚調停が不成立になり調停が終了しても、夫婦の一方が離婚を望んでいる場合は、離婚裁判を提起してくる可能性があります。
離婚裁判は、裁判官が夫婦双方の主張を聞いたり証拠を確認したうえで、総合的に離婚の可否や離婚条件について判断を下します。
離婚裁判の一番の特徴は、夫婦双方の合意がなくても、裁判上で離婚が認められる事由(法定離婚事由)があれば、強制的に離婚を成立させることができる点です。
ご自身に法定離婚事由にあてはまる離婚原因があるのであれば、離婚裁判を起こされるのを防ぐ必要があり、できる限り離婚調停において穏便なかたちで解決することが得策です。
離婚調停で離婚したくない人がとるべき5つの対処法
離婚調停を申し立てられたけれども、離婚したくない場合には次の5つの対処法があります。
- 離婚届の不受理申出書を提出する
- 離婚したい理由を確認する
- 調停委員から共感を得られる言動をする
- 夫婦関係調整調停(円満)の申立てを検討する
- 裁判に進んだ場合を考えて準備する
次項でそれぞれ詳しく解説していきましょう。
①離婚届の不受理申出書を提出する
離婚届の不受理申出書とは、離婚届が勝手に提出されても受理されないようにあらかじめ役所に申し出る手続きをいいます。
離婚に応じないとわかると、相手は強硬手段として、夫婦双方が同意していないにも関わらず勝手に離婚届を提出してしまうケースがあります。
離婚届を提出されると、役所は形式的な不備しか確認しませんので、そのまま離婚手続きが進められて、離婚届が受理されて、離婚が成立してしまいます。一度離婚が受理されると、裁判所での手続きを踏まなければ取り消すことができません。
勝手に離婚届を提出されてしまうような事態になることを防ぐために、離婚届不受理申出書を提出しておくと安心です。
②離婚したい理由を確認する
相手がなぜ離婚したいと思っているのか理由を聞くことは大切です。
離婚の理由を知れば、今までのご自身の言動で何が問題だったかがわかり、今後どのように言動をあたらためていくかを伝えて改善していくと離婚を回避できるかもしれません。
一方で、離婚理由がご自身の言動に問題があるわけでなく、相手が不倫相手と結婚したいために別れたいという場合もあります。
離婚理由が相手の不倫による場合は、相手は離婚原因を作った責任のある配偶者として有責配偶者になりますが、基本的に有責配偶者からの離婚の請求は認められません。
相手が不倫している状況では、ご自身がどのような条件を提示しても、相手の離婚意思が変わる可能性は低いかもしれませんが、離婚裁判に備えて、不倫の事実を客観的に証明できる証拠を集めておくと離婚を阻止できる可能性があります。
いずれにせよ、離婚理由を知ることでご自身のとるべき対応も異なってきますので、まずは理由を確認しましょう。
③調停委員から共感を得られる言動をする
離婚調停では、夫婦が直接話し合いを行うのではなく、調停委員が夫婦双方から交互に聞き取りを行って話を進めていきます。
また、離婚調停の結論を出す際に、調停委員の意見や判断が大きく影響します。
そのため、離婚調停では調停委員を味方につけることが有効です。
調停委員にご自身の主張を正しく理解してもらい共感を得られれば、こちらの意見が通りやすくなる可能性があります。
例えば、夫婦関係を修復できそうな事情や離婚したらあまりにも気の毒だと思わせるような事情などを伝えて共感を得られると、調停委員が味方になってくれる可能性があります。
④夫婦関係調整調停(円満)の申立てを検討する
夫婦関係調整調停(円満)は、略称して円満調停と呼び、家庭裁判所で夫婦関係を円満に改善するための話し合いを行う手続きのことです。
円満調停においては、第三者である裁判官や調停委員から客観的な意見を聞いたり、助言を受けながら、夫婦関係の改善を図っていきます。
円満調停を申し立てたら必ずしも復縁できるとは限りませんが、客観的に判断して欲しい場合や意見が分かれている場合などに有効な手段といえます。
なお、離婚調停中であったとしても、円満調停を申し立てることはできます。
⑤裁判に進んだ場合を考えて準備する
離婚調停で話し合っても、離婚について双方の意見が平行線の場合には、離婚調停は不成立となり、終了します。
調停不成立になると、相手から離婚裁判を提起される可能性がありますが、別居期間が長期にわたり、既に婚姻関係が破綻しているなど、裁判で離婚が認められてしまう可能性が高い場合には、離婚調停で離婚に応じた方がいい可能性があります。
離婚裁判になると、法律や過去の裁判例に基づき、裁判所が厳格に判断をするので、調停よりも柔軟な解決を図ることが難しくなります。その結果、調停での離婚よりも離婚条件が悪化するケースもあるのです。
離婚裁判に進みそうな場合は、早めに弁護士に相談して対策を練っておくといいでしょう。
裁判で離婚が認められる可能性が高いケース
離婚をしたくなくても、離婚裁判に進んだら離婚が認められる可能性が高いのは次のようなケースです。
- 自分自身が不倫している
- 自分自身が配偶者に暴力を振るった
- 自分自身が配偶者にモラハラを行った
- 収入を得ているのに配偶者に生活費を渡していない
- 自分自身が多額の借金をしている
- 自分自身がギャンブルや浪費癖がある
- 性交渉の拒否をしている(セックスレスである)
- 長期間別居している など
上記のようなケースでは、離婚を回避するには、離婚裁判に持ち込まずに離婚調停で関係修復のための話し合いをすることが大切です。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
離婚したくない人がやってはいけない3つの行動
離婚調停の際に、離婚したくない人がやってはいけない行動があります。
具体的には次のような行動です。
- 調停への出席を拒否・無視する
- 感情に任せて相手を非難する
- 暴力や脅し、一方的な説得
次項でそれぞれ詳しく確認していきましょう。
①調停への出席を拒否・無視する
正当な理由もなく離婚調停への出席を拒否や無視すると、調停委員から悪印象をもたれる可能性があります。複数回無断で欠席すると、5万円以下の過料を課されるおそれもあります。
さらに、離婚裁判に移行した後も、裁判への出席を拒否すると、裁判を申し立てた相手の請求がすべて認められて、相手の全面勝訴となり離婚が成立してしまいます。
やむを得ない事情があって調停に出席できない場合には、裁判所に事前に事情を説明しておけば、1~2回程度欠席しても特段不利になることはありません。
②感情に任せて相手を非難する
離婚調停では、離婚したいと思っている相手から、都合のいいことばかり言われて腹立たしい気持ちになるかもしれません。
だからと言って、感情的になって、相手のことを非難するのはいけません。
なぜなら、相手を感情的に非難する発言はモラハラ扱いされるおそれがあります。
モラハラ行為は、裁判で離婚が認められる理由(法定離婚事由)にもなるので、モラハラだと認定されると意思に反して離婚が成立してしまう可能性があります。
また調停委員からの心証も悪くなりますし、話し合いが円滑に進まなくなります。
夫婦関係を修復したいのであれば、気持ちを落ち着かせて建設的な話し合いを行うように心掛けしょう。
③暴力や脅し、一方的な説得
話し合っているときにカッとなって暴力や脅迫をする言動もいけません。
裁判で離婚が認められる理由(法定離婚事由)に該当して、離婚したくなくても有責配偶者となり、離婚が認められる可能性があります。
また、「結婚生活を続けよう」、「子供の親である責任を果たすように」などといった一方的な説得をしても相手は気持ちが冷めている状態ですので、心に響きません。
復縁したいのであれば、相手の気持ちを尊重しながら離婚したい原因を解消できるよう、話し合うように心掛けてください。
離婚調停で離婚を回避するためには弁護士への相談がおすすめ!
弁護士は、離婚したいときに相談するイメージがあるかもしれませんが、離婚を回避したいときにも相談できます。
弁護士であれば、離婚調停を申し立てられても、離婚調停に同席し、感情的にならずに今の気持ちや状況、希望などを代弁するので前向きな話し合いができます。
また、弁護士は数多くの離婚調停を経験しており、今まで培った経験やノウハウを持ち合わせているので、調停委員が味方になってくれる可能性が高くなります。
相手から離婚調停を申し立てられて、離婚を拒否したいと思っているのであれば、できるだけ早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士の介入により離婚調停で離婚を回避できた弁護士法人ALGの解決事例
夫婦円満調停の結果、離婚を回避した事例
【事案概要】
依頼者の不倫が発覚し、相手方は子供を連れて家を出ていきました。
離婚を求める相手方と離婚したくない依頼者とで話し合いは平行線となっていたところ、相手方が離婚調停等を申し立ててきました。
依頼者は自分自身に非があることを認めたうえで、離婚を断固として拒否したいとのことで、ご相談・ご依頼されました。
【弁護士方針・弁護士対応】
当方からは円満調停を申し立てることにしました。
まずは、調停のなかで謝罪および反省を伝えるために謝罪文を資料として提出しました。
また、どうしても離婚が避けられないのなら親権を希望するとして、家庭裁判所調査官調査を行ってもらいました。
【結果】
調査の結果、子供は依頼者と離れたくない、家を出ての生活や将来に不安や負担が大きいといった心情を有していることがわかりました。
すると、相手方の態度は軟化しました。
当方は今後、家計管理や不貞再発防止措置を受け入れて改心することをかたちで残すこととしました。
一方で、相手方も夫婦関係の再構築を目指すことに同意して、子供と一緒に家に戻り、無事に離婚を回避することができました。
妻からの離婚請求を受けた後、夫婦円満調停で解決した事例
【事案概要】
家計管理を巡って相手方である妻と喧嘩となり、依頼者である夫が離婚を口にしたところ、相手方から弁護士を立てて、離婚調停を申し立ててきました。
依頼者は夫婦関係の修復を望んで、ご相談・ご依頼されました。
【弁護士方針・弁護士対応】
まずは、相手方に謝罪の意思を伝えることから始めました。
それと並行して、当方から円満調停を申し立てました。
もう一度、やり直そうという強い思いを具体的に伝えること、それを自分の言葉で述べること、自分事ではなく相手の気持ちを想像することなどを意識するようにアドバイスをして調停へ臨みました。
【結果】
調停では、調停委員に本人から謝罪の場を設けてもらったところ、相手方の態度が軟化し、「今回限りは許す。」といい、無事に離婚をせずに解決することができました。
離婚を回避しつつ、月額6万円の婚姻費用を獲得できた事例
【事案概要】
依頼者である妻は、相手方である夫が自宅を出て別居を開始し、さらに離婚調停を申し立てられたので、離婚調停に対応してほしいとのことでご依頼されました。
なお、両名の間には、子供が2人いますがすでに2人とも成人されていました。
【弁護士方針・弁護士対応】
依頼者は離婚には応じない意向であること、婚姻費用の支払いに関する合意がなされていないことから、当方から婚姻費用分担請求調停の申立てをお勧めして、対応しました。
【結果】
婚姻費用分担請求調停では、分担額月6万円と算定され、双方合意し調停が成立しました。
離婚調停は、双方折り合うことができなかったことから調停不成立で終わりました。
依頼者としては、婚姻費用を確保しつつ、離婚を回避できたので大変安堵されました。
離婚したくないのに離婚調停を申し立てられてしまった場合は弁護士法人ALGへご相談ください!
基本的に、離婚調停を申し立てられても、当事者双方の合意がなければ、離婚は成立しません。
ただし、そのまま適切な対応をしないと将来的に離婚に繋がってしまうかもしれません。
離婚したくないのに離婚調停を申し立てられてしまった方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士は離婚調停の場へ一緒に同席しますので、代わりにご自身の気持ちや主張を効果的に伝えてもらえます。
また、離婚したくない場合は離婚調停の対応だけでなく、関係修復のための働きかけもしなくてはいけません。
関係修復のための働きかけは、相手が主張する離婚理由によって異なります。
具体的にどうすればいいのかは弁護士からアドバイスを受けて、改善の努力をすれば夫婦関係が修復できる可能性があります。
まずは、弁護士法人ALGにお気軽にお問合せください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)



















