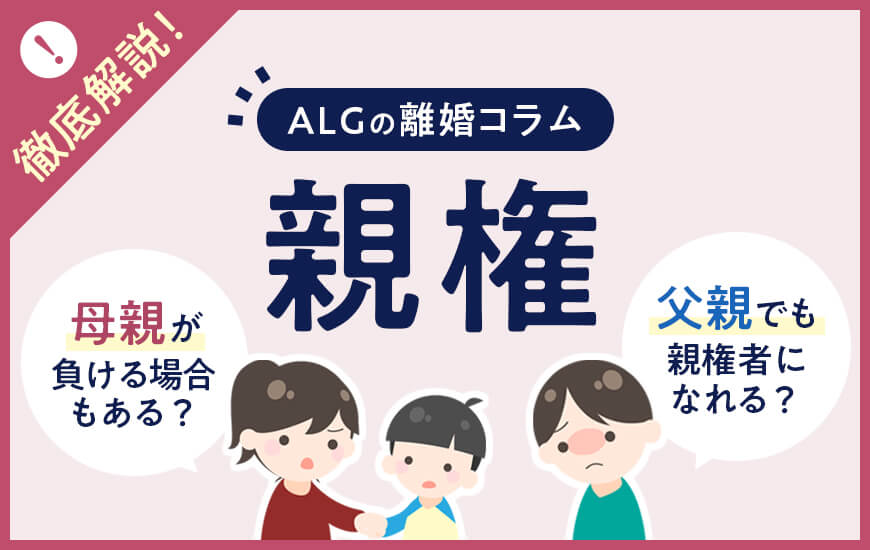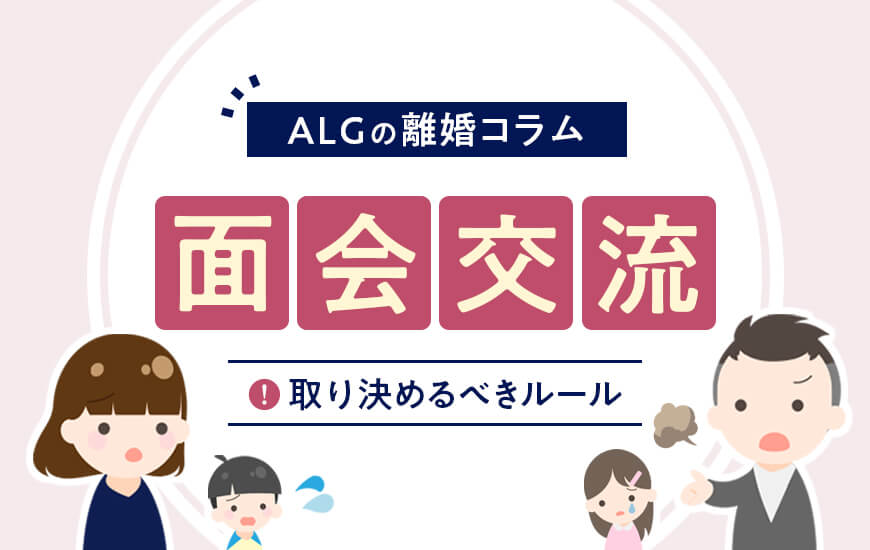監護権と親権|違いや分ける必要性、決定の際の判断基準など
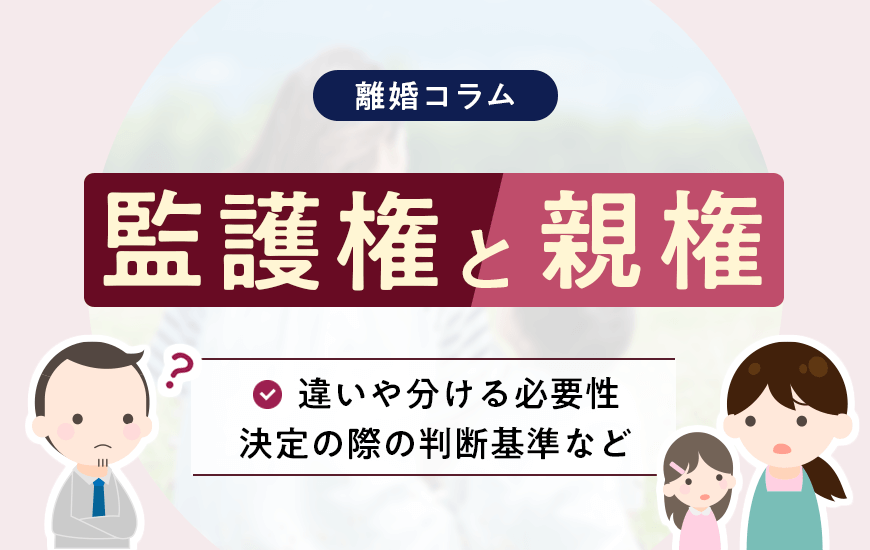
婚姻中は夫婦がそれぞれ親権を持つ「共同親権」となりますが、日本では離婚時に父母どちらかを親権者と定める「単独親権制度」を導入しています。
離婚の条件のなかでも親権は特に揉めやすく、離婚の話し合いが長期化するケースも多くあります。
親権の中には「監護権」というものがあり、親権者と監護権者を分けることが可能です。
こうした取り決めを行うことで、離婚問題を早期に解決できる可能性があります。
この記事では、親権と監護権を分けるメリット・デメリット、手続きの方法などについて解説していきます。
目次
親権と監護権の違い
親権とは
親権とは、子供の財産を管理する財産管理権、子供と一緒に暮らし監護・養育する身上監護権の2つから成り立っている権利や義務のことです。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
財産管理権
- 包括的な財産の管理権
簡単に言うと、子供の財産を管理する権限を持つことです。 - 子供の法律行為に対する同意見
ここでいう法律行為とは、売買、貸し借り、アルバイトなどの労働契約などが主に該当します。
身上監護権
- 身分行為の代理権
15歳未満の子供の養子縁組の代諾や相続の承認や放棄などの親の同意・代理権です。 - 居所指定権
子供の居所を指定する権利です。実質的に子供と暮らすことができる、とても重要な権利です。 - 職業許可権
子供の就職を許可したり、取り消しや制限をする権利です。
これらは親の権利であり、子供を保護し肉体的・精神的にも成長させていく親の義務でもあるといえます。
親権については以下で詳しく解説しています。併せてご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
監護権とは
監護権とは、親権のうち【身上監護権】をいいます。
監護権者は子供と一緒に暮らし、日常の世話や教育を行うことができます。(民法第820条・監護教育権)
婚姻中は父母双方が親権や監護権を持ちます。
しかし、離婚後は「単独親権制度」となりますので、父母のどちらかを親権者と定めなければなりません。
一般的には親権者となった親が監護権を持ちますが、親権と監護権は分けることも可能です。
詳しく見ていきましょう。
監護権と親権は分けることができる
日本では「単独親権制度」を採用していますので、離婚時には父母どちらかを親権者として定めなければなりません。
しかし、親権の問題は「どちらが子供と一緒に暮らすか」という点で争いになりやすく、話し合いが長期化する場合も多くあります。
そうした場合に、親権者と監護権者を分けることにより、話し合いがスムーズに進むケースもあります。
また、以下の事情により親権者と監護権者を分けるケースがあります。
- 親権者が海外赴任や病気で監護することができない
- 親権者が子供を虐待している
- 財産管理は父親の方が良いが、子供が小さいため母親が監護権を持ち子供を世話する方が、都合が良い など
このような事情から親権者と監護権者を分ける場合もありますが、財産を管理する親と身の回りの世話をする親が別にいることは、実生活上の不都合が生じる場合もあるでしょう。
そのため、親権者と監護権者は同じ方が子供の福祉にとって良いとされています。
親権者と監護権者を分けた場合の権利の違いについては、下表をご参考ください。
| 親権者 | 監護権者 | |
|---|---|---|
| 監護教育権 | × | 〇 |
| 居所指定権 | × | 〇 |
| 懲戒権 | × | 〇 |
| 職業許可権 | × | 〇 |
| 子供の財産管理権 | 〇 | × |
| 法律行為の代理権 | 〇 | × |
| 身分行為の代理権 | 〇 | × |
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
親権と監護権を分けるとどうなる?
監護権は、子供と暮らしながら育てていく権利であり義務でもあります。
しかし、離婚届には「親権者」を記載する欄はありますが、「監護権者」を記載する欄はありません。
もし、離婚時に親権と監護権を分ける場合は、離婚協議書や公正証書として書面に残しておかないと、トラブルになりかねないので注意が必要です。
ここからは、親権と監護権を分ける場合のメリットとデメリットについて見ていきましょう。
親権と監護権を分けるメリット
親権と監護権を分けた場合、以下のようなメリットが挙げられます。
親権問題の早期解決につながる
親権について話し合いで決まらないと離婚調停や離婚裁判にまでもつれ込み、長い期間争うことになってしまいます。
このような場合に、相手に親権(監護権)を譲り、自分が監護権(親権)を持つことで、協議や和解による早期解決ができる可能性があります。子供とつながる安心感
非監護権者は普段子供と生活を共にしません。
そのため親としての責任が薄れてしまいがちですが「親権」を持つことで自分も親としての安心感を持てるだけでなく、養育費の不払い率を下げることができます。
親権と監護権を分けるデメリット
親権と監護権を分けた場合、以下のようなデメリットが考えられます。
- 子供が交通事故に遭った時に損害賠償を求める裁判を起こす場合
- 子供の預金口座を作りたい場合
このように、子供のために法律行為を行う必要が生じた場合は親権者の同意が必要となります。
親権者は子供の財産管理権を持ち、その中には「財産の管理」と「法律行為の同意権」を含むため、このようなトラブルになった場合にスムーズに動けないのはデメリットといえるでしょう。
親権と監護権を分ける場合の手続き
親権と監護権を分けるには、離婚する際にどうするのかを決めます。
一般的な手続きの流れは以下のとおりです。
- 夫婦での話し合い
- 調停の申立て
- 裁判による判決
離婚裁判までもつれ込んだとしても、裁判所は親権と監護権を分けることに消極的であるため、認められる可能性はほぼありません。
できれば①、②で決められることが望ましいでしょう。
①夫婦での話し合い
まずは親権と監護権について、夫婦で話し合いましょう。
また、話し合いの際には子の利益を優先とするのが重要です。
親権者と監護権者を分ける場合、監護権者は離婚届に記載しないだけでなく、戸籍にも反映されません。
後から「言った・言わない」のトラブルを避けるためにも、親権者と監護権者の取り決めについては、離婚協議書や公正証書として残しておくことが大切です。
これらの書面は、相手方が約束を守らなかった場合に大事な証拠となります。
②調停の申し立て
話し合いで折り合いが付かない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てます。
調停とは、調停委員を介し、話し合いによって解決を目指す手続きです。
監護権者は、子供を監護・養育し、子供の健やかな成長を助ける重要な役割です。
そのため、調停では「自分が監護権者として適任であること」を主張・立証していきます。
子供の年齢や性格、生活環境などの聞き取りが行われたり、必要に応じて書類を提出するなどして、子供の利益を尊重した取り決めができるよう話し合われます。
監護権者について当時者双方で合意できたら調停成立となり、話し合った内容が記載された「調停調書」が作成されます。
③裁判による判決
調停で双方が合意できない場合は、離婚裁判を提起して争うことになります。
裁判では、話し合いなどは行われず、主に書面で双方が親権者としてふさわしいことを主張・立証していきます。
一通りの主張・立証が尽くされたタイミングで、裁判官から和解を進められることが多いですが、和解できない場合には裁判官が判決を下すことになります。
しかし、裁判では親権者と監護権者を分けることに消極的であり、認められない可能性が高いです。
監護権の獲得が難しい場合には、どうしたら良いでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
監護権の獲得が難しい場合にすべきこと
監護権の獲得が難しい場合は、積極的な面会交流を求めましょう。
面会交流とは、子供と一緒に暮らさない方の親が子供と定期的に直接面会や間接面会を行うことです。
積極的な面会交流は、子供が両親のどちらからも愛されていると実感できる大事な機会です。
そのため、子供と一緒に暮らしている親が「会わせたくない」と主張しても、合理的理由がなければ基本的には面会交流の拒否は認められません。
面会交流については、決まった方法はなく、会える回数や時間などは自由に決められます。
後からトラブルになるのを避けるためにも、決めた内容は離婚協議書や公正証書などの書面に残しておきましょう。
面会交流については以下でも詳しく解説しています。併せてご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
調停や裁判での監護権者の判断基準
離婚裁判で、話し合いがまとまらない場合は裁判所が判断を下します。
その際の判断基準として、「どちらのもとで生活する方が子供は幸せになれるか」「子供の幸せ」という点から監護権者を決めます。
調停や裁判での監護権者の判断基準は以下のとおりです。
- これまでの子育ての状況
- 今後の子育ての状況
- 子供の年齢
- 子供の意思
監護権を変更する方法
監護権者に関しては後で変更することもできます。
当事者間の話し合いで変更することもできますが、まとまらない場合には家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
なお、調停前にあらかじめ監護権者の変更に合意していたとしても、それだけの理由で家庭裁判所が変更を認めてくれるわけではありません。
変更が認められやすい事情としては以下のようなケースが挙げられます。
- 親権者・監護権者の育児放棄
- 親権者・監護権者による虐待
監護権者が監護を怠った場合の罰則
幼い子供を放ったまま遊びに出かける、出かけた先で子供を置き去りにする、など監護権者が子供の監護を怠ると、児童虐待防止違反や保護責任者遺棄罪などの犯罪が成立する場合があります。
監護権は親の権利であるのと同時に、義務でもあります。
育児放棄は虐待として刑事罰を科される可能性があるだけでなく、監護権が元配偶者に移る場合もあります。
子供の監護を怠った場合に考えられる罰則を見ていきましょう。
【保護責任者遺棄罪・不保護罪(刑法218条)】
保護責任者遺棄罪・不保護罪とは、幼年者等を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、またはその生存に必要な保護をしなかった場合に刑事責任を問われる犯罪です。
⇒3月以上5年以下の懲役
【保護責任者遺棄等致死傷罪(刑法219条)】
保護責任者遺棄等致死傷罪とは、遺棄したこと、あるいは生存に必要な保護をしなかった結果、幼年者等に傷害を負わせ、あるいは幼年者等を死亡させた場合に成立する犯罪です。
⇒傷害:3月以上15年以下の懲役 死亡:3年以上の有期懲役(上限20年)
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
監護権に関するよくある質問
監護権と親権を分けた場合の子供の戸籍はどうなりますか?
監護権と親権を分けた場合、子供の戸籍は親権者の戸籍に残ります。
例として、婚姻中はA田さんだった夫婦が離婚し、夫が親権者、妻が監護権者になったとします。
離婚後は原則として旧姓に戻すことから(戻さず婚姻時の氏を使うこともできます)、妻はB木さんになりました。
しかし、一緒に暮らす子供は親権者の戸籍に残るので、子供の苗字はA田のままということになります。
監護権者と親権者はどちらが養育費を払うことになりますか?
親権者と監護権者を分けた場合、養育費は親権者が監護権者に支払います。
養育費は子供を監護・養育するために必要な費用であるため、子供と一緒に暮らし、育てている監護権者に支払われます。
養育費の金額は、裁判所の「養育費算定用」を参考にしましょう。
親権者と監護権者を分けた場合、児童扶養手当はどちらに支給されますか?
児童扶養手当は一定額の上限がありますが、子供を監護しているひとり親に支払われるものです。
したがって、子供と一緒に暮らす監護権者に支給されます。
申請には戸籍謄本や住民票が必要となりますが、子供は父親の戸籍に入りますので注意しましょう。
また、監護権者であることが証明できず、児童扶養手当が支給されないおそれもあります。
監護権者であることを主張するためにも、離婚協議書や公正証書にその旨を記載しておくと安心です。
父親が親権や監護権を獲得することは可能ですか?
父親が親権・監護権を獲得することは可能ですが、割合としてかなり低いのが実情です。
しかし、親権や監護権を獲得するうえで最も大事なのは、「どちらと暮らした方が子供は幸せなのか」という点です。
例えば、母親が虐待や育児放棄など子供に悪影響を与える場合、母親と暮らせば子供の福祉に背いてしまいます。
このような場合には、父親に親権や監護権が認められやすくなるでしょう。
私たち弁護士法人ALGには、父親が親権や監護権を獲得した事例が多数あります。
ぜひ一度ご相談ください。
監護権のみ獲得していた場合、再婚しても問題ありませんか?
再婚をしても子供の親権や監護権に影響はありません。
再婚前から監護権をもっていれば、再婚後も子供の監護権者となります。
ただし、一緒に暮らす子供と再婚相手を養子縁組したい場合は注意が必要です。
法律上、15歳未満の子供が養子縁組をするためには、法定代理人の代諾が必要です。
この法定代理人とは親権者を指します。
つまり、親権者が子供と再婚相手との養子縁組を認めない限り、再婚相手と子供を養子縁組させることはできません。
離婚時の親権・監護権について不安なことがあれば弁護士にご相談ください
離婚の際に「親権」の問題は大きな争いになりやすく、当事者間ではなかなか決められない問題です。
通常は、親権と監護権は両親のどちらかが持つことになりますが、事情があれば「親権」と「監護権」を分けることができます。
早く離婚をしてしまいたいからと、親権と監護権を相手に譲ってしまうことはおすすめできません。
しかし、当人同士では話がまとまらないなど、上手に話し合えないこともあるでしょう。
そういう時は弁護士にご相談ください。
親権、監護権についてわかりやすく説明し、どうするのがベストな選択なのか、一緒に考え早期解決を目指していきます。
親権や監護権を決めるときに大切なのは「自分が子供と暮らしたい気持ち」ではなく「子供の幸せ」です。
冷静な話し合いをするためにも私たちにご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)