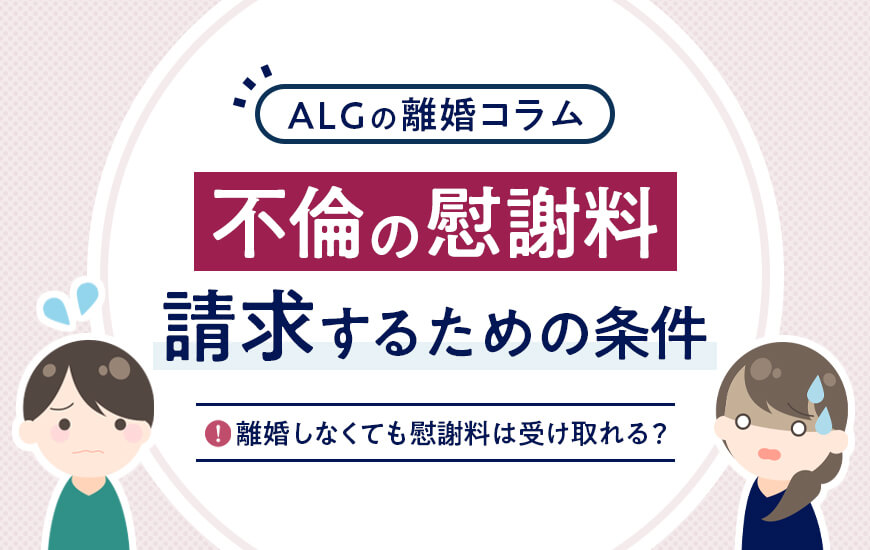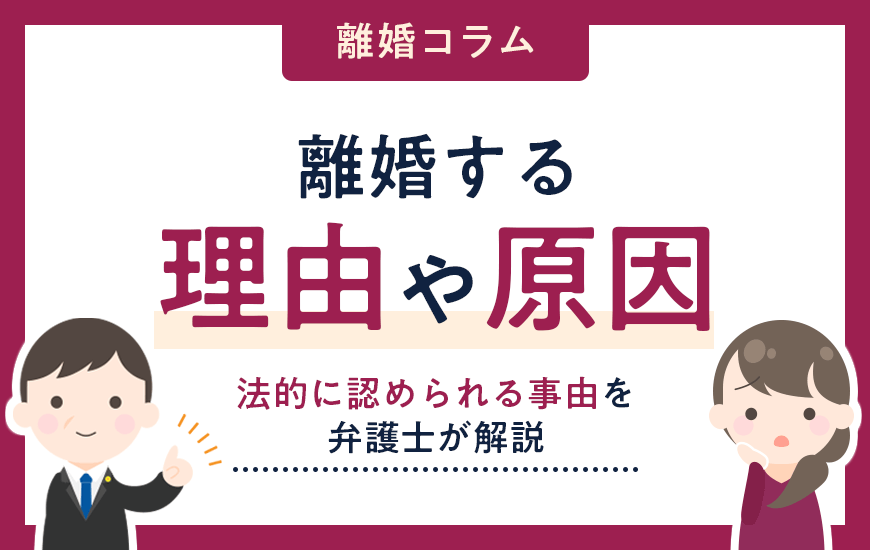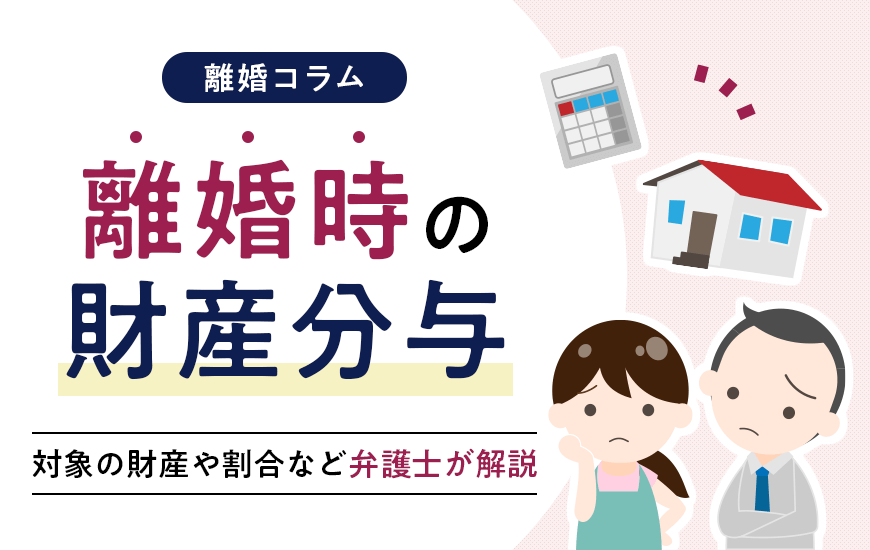内縁関係とは?定義や証明方法、慰謝料が発生するケースなど
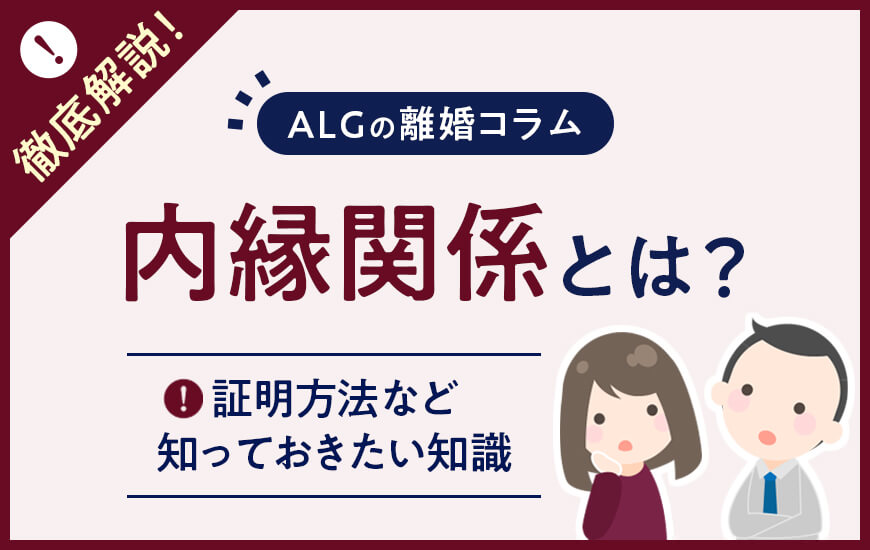
近年、夫婦の在り方が多様化するなかで、内縁関係を選択する方が増えています。
内縁関係という言葉に法律上の明確な定義はありませんが、実態としては法律婚の夫婦と変わらない共同生活を営む男女の関係を指します。
内縁関係を選択することで、夫婦別性の実現、別れても戸籍に×がつかない、家同士のしがらみに縛られにくいなどのメリットがある一方、特有のデメリットや注意点も存在します。
この記事では、内縁関係の基礎知識や、注意すべき点などについて詳しく解説していきます。
目次
内縁関係とは
内縁関係とは、婚姻届は提出していないものの、お互いに「婚姻の意思」を持ち、「夫婦同然の共同生活」を営んでいる男女の関係を意味します。
例えば、以下のような事情があれば、内縁関係にあると認められやすくなります。
- 結婚式を挙げた
- 冠婚葬祭に夫婦として出席するなど、周囲からも夫婦として扱われている
- 普段から、契約書などにお互いの続柄を「(内縁)妻」「(内縁)夫」などと記載している
- 住民票上の世帯を同一にしている
- 長期間同居し、家計の財布を同じくしている
男女の関係が法的に内縁関係にあると認められると、法律婚の夫婦に準じた法律上の権利・義務が生じます。
しかし、相続権や、子供と父親との関係など、法律婚の夫婦とは決定的に異なる点も存在します。
相続人になることができない
法律婚の夫婦は、自動的にお互いの法定相続人になり、相手が亡くなった後に遺産を相続する権利を有します。
しかし、内縁関係の夫婦には、相続権が発生しません。
どんなに長い間一緒に暮らし、夫婦同然の生活をしていても、相手名義の不動産や預貯金などの遺産を相続することはできないのです。
そのため、相手に自分の財産を承継させるためには、生前贈与や遺言書による遺贈など、事前にしっかりとした対策を講じておく必要があります。
子供が生まれた場合は認知が必要
内縁関係の場合は、産まれた子供と父親の間に法律上の父子関係を発生させるために、認知の手続きが必要です。
内縁の夫が子供を認知しなかった場合、法律上の父子関係が成立しないため、内縁の夫は父親としての扶養義務を負わず、養育費の支払い義務も生じません。
また、子供にも父親の相続権は認められません。
このような状況は、子供にとって相当のデメリットであるといえるでしょう。
内縁関係にある夫婦の子供が、法律婚の夫婦の子供と同等の法的な保護を受けるためには、内縁の夫から子供を認知してもらわなければなりません。
戸籍や住民票はどうなる?
内縁関係の場合、入籍の手続きは経ないため、お互いの戸籍は別々のまま、何も変動はありません。
しかし、住民票については、2人の世帯を同一にし、対外的に2人が内縁関係にあることを示すことができます。
例えば、住民票上の世帯主との続柄を「妻(未届)」「夫(未届)」とすることで、2人が婚姻の意思をもって夫婦同然の共同生活を営んでいること、すなわち、2人が内縁関係にあるということを、客観的に証明する有力な証拠となり得ます。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
内縁関係の証明方法
内縁関係にある夫婦が社会保障や公的扶助など、法的な保護を受ける場合、2人が内縁関係であることを証明しなければならないこともあります。
内縁関係を証明する方法には、以下のようなものがあります。
- 住民票
- 賃貸物件などの契約書
- 同居期間
- 給与明細書
- 健康保険証
- 遺族年金証書
- その他
では、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
住民票
内縁関係を証明する書類として、最も役に立つのは住民票です。
住民票上の世帯を同一にしておけば、2人が一緒に暮らしていることや同居期間の長さを証明することができます。
さらに、続柄を「妻(未届)」または「夫(未届)」とすることで、2人は「夫婦同然の共同生活をおくり、婚姻の意思がある関係」であること、内縁関係にあることをより認められやすくなります。
住民票は「同居」と「婚姻の意思」の2つを示せる公的な書類であることから、内縁関係を証明する手段として、最も証拠価値が高いものであるといえるでしょう。
賃貸物件などの契約書
2人が一緒に暮らす物件の賃貸借契約書も、証拠の1つとして有用です。
例えば、物件の契約者が内縁の夫である場合、契約書において同居人との続柄を
- 内縁の妻
- 妻(未婚)
- 妻(未届)
などと記載しておくと、2人が「婚姻の意思をもって同居している夫婦同然の関係=内縁関係」であることを対外的に示すことができます。
同居期間
「●年間同居していれば内縁関係が認められる」という絶対的な基準は存在しませんが、同居期間が長ければ長いほど有利でしょう。
一般的には、3年程度の同居期間があれば、内縁関係が認められやすくなる傾向にあります。
しかし、3年というのもあくまでも目安に過ぎず、夫婦の個別の状況により判断されます。
例えば、すでに結婚式を挙げているなどの事情があれば、3年より短い同居期間でも、内縁関係の成立が認められる可能性があります。
給与明細書
給与明細書は、内縁関係の証明資料として活用できるケースがあります。
勤務先に内縁のパートナーを「被扶養者」として申告し、家族手当や扶養手当、住宅手当などが支給されている場合、その事実は2人が夫婦同然の生活を送っていることを示す有力な根拠です。
このように、給与明細に記載された手当の内容を、内縁関係の実態を客観的に裏付ける証拠として、法的な場面でも役立たせられる可能性があります。
健康保険証
健康保険証も、内縁関係の存在を裏付ける資料として活用されることがあります。
内縁の妻が、内縁の夫の健康保険において「被扶養者」として認められ、健康保険証が交付された場合、その保険証は内縁関係の存在を示す有力な証拠のひとつになります。
健康保険法では、被保険者(内縁の夫)の扶養を受けている内縁の配偶者についても、一定の要件を満たすことで「被扶養者」として認定される可能性があります。
例えば、内縁の夫が民間企業に勤務している場合、その企業の健康保険制度を通じて、内縁の妻にも健康保険証が交付されることがあります。
なお、令和6年12月2日以降は、健康保険証の新規発行は行われていませんので、ご注意ください。
遺族年金証書
遺族年金の受給を証明する遺族年金証書も、内縁関係を証明する証拠となります。
内縁の妻(夫)が遺族年金を受給している場合、その事実自体が「2人が内縁関係にあったこと」を意味します。
したがって、遺族年金証書は、内縁関係を示す手がかりとして活用できます。
ただし、遺族年金を受給するには、様々な証拠を用いて「内縁関係にあり、2人で生計を維持していた」ことなどを証明する必要があるため、証書そのものよりも「どのような証拠や手続きで受給が認められたか」という経緯の方が重視されます。
その他
その他にも、以下のような資料も、内縁関係を証明する証拠として役に立つ可能性があります。
- 事実婚に関する契約書(内縁証明書)
- 遺言書
- 自動車保険
- 内縁関係であることを確認するために2人の間で交わした確認書等
- 内縁関係であることを認める旨の会話の音声データ、メールやLINEのやり取り
- 結婚式や披露宴を行ったことの証明書や招待状、写真等
- 子供を認知した事実
- 内縁の相手の姓を名乗っている書類(連名の年賀状や公共料金の名義等)
- 国民年金第3号被保険者となっていることを証明する書類 など
内縁関係で慰謝料が発生するケース
内縁関係の夫婦も、法律婚の夫婦とほぼ同じように扱われ、一定の法的保護を受けることができます。
その一方で、法律婚の夫婦と同じように、お互いに守るべき義務も負うため、以下のようなケースでは、慰謝料が発生する場合もあります。
- 相手が浮気(不貞行為)をした
- 正当な理由なく内縁関係を解消された
- 既婚者であることを隠していた
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
相手が浮気(不貞行為)をした
内縁関係にある相手が、浮気(肉体関係を伴う不貞行為)をした場合、法律婚と同様に「貞操義務違反」による精神的苦痛に対して慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料の相場は200万~300万円程度(※)とされており、内縁関係の長さや生活実態、不貞行為の回数などによって増減します。
(※)法律婚の不貞行為による慰謝料相場であり、内縁関係の場合は同額か相場を下回る場合があります
また、浮気相手に対しても慰謝料を請求できますが、そのためには以下のいずれかを証明する必要があります。
- 浮気相手が内縁関係の存在を知っていた(故意)
- 注意すれば内縁関係に気付けたのに怠った(過失)
つまり、浮気相手が「2人が内縁関係にあると知っていた」または「少し注意すれば気付けた」場合、慰謝料の対象となります。
浮気・不倫の慰謝料請求について、もっと詳しく知りたい方は、下記の記事も併せてご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
正当な理由なく内縁関係を解消された
内縁関係が成立しているにもかかわらず、相手から一方的に関係を解消・破棄された場合、それが「正当な理由」に基づかないものであれば、不法行為とみなされ、慰謝料を請求できる可能性があります。
このようなケースでの慰謝料相場は、30万~200万円程度とされており、内縁関係の長さや解消の経緯などによって金額は変動します。
「正当な理由」とは?
民法第770条に定められた「法定離婚事由」に該当する場合が、正当な理由の判断基準となります。具体的には、以下の5つです。
- 不貞行為(肉体関係を伴う浮気・不倫)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、一方的に家を出ていくなど)
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由(DV、モラハラ、借金問題など)
これらに該当しないにもかかわらず、内縁関係を一方的に解消された場合は、精神的苦痛に対する慰謝料が認められる場合があります。
法的に認められる離婚事由について、もっと詳しく知りたい方は、下記の記事も併せてご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
既婚者であることを隠していた
相手が既婚者であることを隠してバツイチや独身のフリをしていたり、既婚者と知っていても「妻との関係はもう破綻している」「もう離婚することが決まっている」などと嘘を言い、騙されて内縁関係を結んでいたりした場合も、貞操権の侵害等を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。
なお、当事者の一方または双方に法律上の配偶者がいるにも関わらず結ばれた内縁関係を重婚的内縁関係といいます。
内縁関係で慰謝料が発生しないケース
内縁関係で慰謝料を請求できる場合もあれば、以下のケースのように慰謝料を請求できない場合もあります。
- 内縁関係を立証できない
- 事実上破綻していた
- 重婚的内縁関係だった
どのような事情があると慰謝料を請求できないのか、確認していきましょう。
内縁関係を立証できない
内縁関係を証明する客観的な証拠がない場合には、慰謝料は請求できない可能性があります。
内縁関係の夫婦にも法律婚の夫婦と同様の権利や義務が認められていますが、その前提として「内縁関係が成立していること」を客観的に証明する必要があります。
内縁関係を証明する代表的な方法
以下のような証拠があると、内縁関係が認められやすくなります。
- 住民票の続柄が「妻(未届)」または「夫(未届)」となっている
- 結婚式を挙げている
- 親族や友人、職場などから「夫婦」として認識されている
- 相手の被扶養者として健康保険証の交付を受けている
- 生活費や家賃を共同で負担していた記録がある
- 長期間の同居実績がある
事実上破綻していた
すでに内縁関係が破綻している場合、慰謝料は請求できない可能性が高いです。
内縁関係が事実上すでに終わっている状態であれば、相手に浮気されたり、関係の解消を告げられたりしても、精神的苦痛が生じたとは認められにくく、慰謝料の請求は難しくなるでしょう。
例えば、以下のような状況では、内縁関係がすでに解消されていると判断される可能性が高くなります。
- すでに別居しており、長期間にわたって連絡を取っていない
- 同居や生活の実態がなくなっている
- 周囲からも夫婦関係が継続していると見られていない
このような状態で相手がほかの人と関係を持ったとしても、すでに内縁関係が解消されていると判断されれば、慰謝料の対象にはなりません。
重婚的内縁関係だった
重婚的内縁関係とは、当事者の一方または双方に、法律上の配偶者がいる状態で結ばれた内縁関係をいいます。
相手に法律上の妻または夫がいることを知りながら内縁関係に至ったとしても、そもそもそれ自体が公序良俗に反する関係であるため、内縁関係を一方的に解消されても、基本的には慰謝料は発生しません。
ただし、相手に既婚であることを隠されていたとか、法律上の配偶者との関係が形骸化していることが明らかであるなど特段の事情があれば、慰謝料の請求が認められる可能性も、ゼロではありません。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
内縁関係における相続方法
内縁の夫婦は法律上の婚姻関係にないため、民法の規定は適用されず相続権は発生しません。
そのため、内縁のパートナーに自分の財産を相続させるには、あらかじめ以下のような対策を講じておく必要があります。
- 生前贈与をする
- 遺言書で遺贈する
- 特別縁故者になる
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
生前贈与をする
生前贈与とは、存命中に、自身の財産を無償で相手にあげることです。
生前贈与を行うことで、法定相続人になれない内縁のパートナーに対しても、自分の財産を承継させることができます。
生前贈与を行う際は、以下の点に留意しておきましょう。
- 贈与の額が年間(1月1日~12月31日までの間)で110万円以上になると、贈与税が発生する
- 贈与額を年間110万円未満に抑えたとしても、連年贈与または定期贈与とみなされれば、贈与税が発生する
贈与税の発生を防ぐため、年間の贈与額や支払方法に留意し、専門家のアドバイスを受けながら計画的に行いましょう。
遺言書で遺贈する
遺言書は故人の生前の意思が反映されているため、遺言書に書かれた内容は、法定相続の規定よりも優先されます。
そのため、予め遺言書を作成し、遺言書の中で、内縁のパートナーに財産を譲り渡すことを指定(=遺贈)しておけば、法律上の配偶者でない内縁のパートナーも、遺産を受け取ることができます。
なお、遺言書の書き方には厳格な決まりがあり、法律で定められた形式を充たしていないと、その遺言書は無効となってしまいます。
また、法定相続人から遺留分(法律で保障されている最低限度の遺産の取り分)を請求された場合、その分の財産は渡さなければならないため、注意が必要です。
特別縁故者になる
特別縁故者とは、「亡くなった人(被相続人)と特別近しい関係にあった人」をいいます。
被相続人に法定相続人がいなければ、遺産を相続できる人がいないため、遺産は最終的には国のものになってしまいます。
この点、内縁の妻(夫)が家庭裁判所で被相続人の特別縁故者として認められると、被相続人の遺産の全部または一部を受け取ることが可能となります。
特別縁故者として認められるためには、被相続人に法定相続人がおらず遺言書もないという事情が必要であり、加えて、以下のいずれかの要件を満たさなければなりません。
- 被相続人と生計を同じくしていた
- 被相続人の看護療養に努めた
- その他被相続人と特別の縁故があった
なお、特別縁故者が相続した財産が3000万円を超える場合は、通常の2割加算の相続税が課されます。
内縁関係の解消方法
内縁関係は、当事者間の合意や不貞行為などの法定離婚事由があれば、特別な手続きや書類の提出なしに解消することができます。
法律婚のように離婚届を提出する必要はありません。
一方、当事者間の話し合いがまとまらない場合や、相手が関係解消に応じない場合は、家庭裁判所に内縁関係調整調停を申し立て、調停委員を間に挟んで話し合いを行うことが可能です。
内縁関係調整調停について、次項で詳しく見ていきましょう。
内縁関係調整調停について
内縁関係の解消について2人の話し合いで解決できなかった場合、家庭裁判所に「内縁関係調整調停」を申し立てることができます。
調停では、調停委員を仲介役として、内縁関係を解消するかどうか、また、慰謝料や財産分与はどうするかなどの諸条件について、話し合うことができます。
調停の申立てに必要となる費用や書類は、裁判所や事案によって異なりますが、標準的なものは以下のとおりです。
- 収入印紙1200円分
- 郵便切手(1000円前後。金額や内訳は、裁判所によって異なる。)
- 申立書 合計3通(裁判所用、相手用、自分用)
- 事情説明書 1通
- 連絡先等の届出書 1通
- 進行に関する照会回答書 1通
- 子に関する事情説明書(未成年の子供がいる場合) 1通
- 年金分割のための情報通知書(年金分割制度についても話し合う場合) 1通
内縁関係についてよくある質問
内縁関係の場合でも扶養義務はありますか?
内縁関係の夫婦の場合も、法離婚の夫婦と同様に、相手に対する扶養義務を負います。
内縁のパートナーが仕事をしていない、収入が低くて自力での生活が成り立たないような場合には、互いに助け合い、相手を経済的に支えていかなければなりません。
この扶養義務に違反して、相手に生活費を渡さなかったり、自分の趣味やギャンブルに使って相手を経済的に困窮させたりするような場合には、内縁関係を解消する正当な理由にもなり得ますし、慰謝料を請求される可能性もあります。
内縁関係を解消する際に財産分与を行うことはできますか?
内縁関係を解消する際には、法律婚と同様に「財産分与」が認められることがあります。
これは、内縁関係にあった期間中に、2人が協力して築いた財産について、公平に清算する必要があるという考え方に基づいています。
財産分与の対象となるのは、内縁期間中に形成された財産であり、基本的には「どちらの名義か」「どちらがいくら稼いだか」にかかわらず、公平に分配できます。
このように、内縁関係の解消時にも、法律婚と同じルールで財産分与を求めることができます。
なお、当事者間の話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することも可能です。
財産分与については、もっと詳しく知りたい方は、下記の記事も併せてご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
別居していたら内縁関係が解消されたと判断されますか?
基本的には、別居をすることで内縁関係が解消されたと判断される可能性が高いでしょう。内縁関係が成立するためには、2人に「婚姻の意思」があることのほか、2人が「共同生活」を営んでいることが要求されます。
そのため、相手の同意を得ずに一方的に別居に踏み切っても、共同生活が終了してしまえば、内縁関係を成立させるための要件を欠いてしまうため、その時点で内縁関係は解消されたと判断されるでしょう(一方的な内縁関係の破棄に伴う慰謝料の問題は生じます)。
しかし、単身赴任や病気療養のための入院のように、別居が一時的なものである場合や、離れて暮らすことに正当な理由が存在する場合は、内縁関係の解消とは認められない可能性が高いです。
内縁関係に関するお悩みは弁護士法人ALGにご相談ください
内縁関係であっても、事案によっては法律上の夫婦と同じような法律の保護を受けることができます。
内縁のパートナーとの関係でお悩みの場合も、ためらわずに法律の専門家である弁護士へ相談しましょう。
しかし、弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
どの弁護士にも、専門分野や得意分野があります。内縁関係に関するトラブルについては、特に離婚や男女関係のトラブルに精通した弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人ALGには、経験豊富な弁護士が多数在籍しており、離婚問題をはじめ、内縁関係など男女関係についてのトラブルの解決実績も豊富に有しております。
内縁関係に関してお悩みの際は、是非お気軽に弁護士法人ALGまでご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)