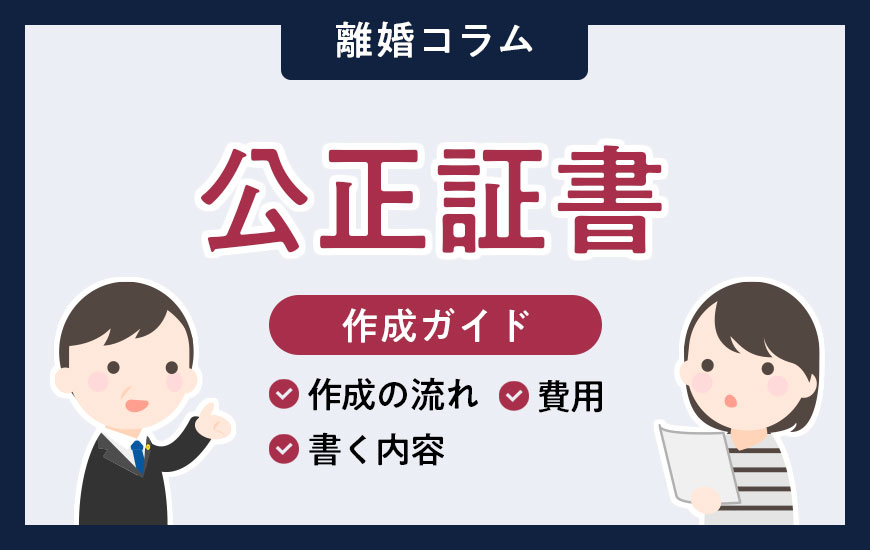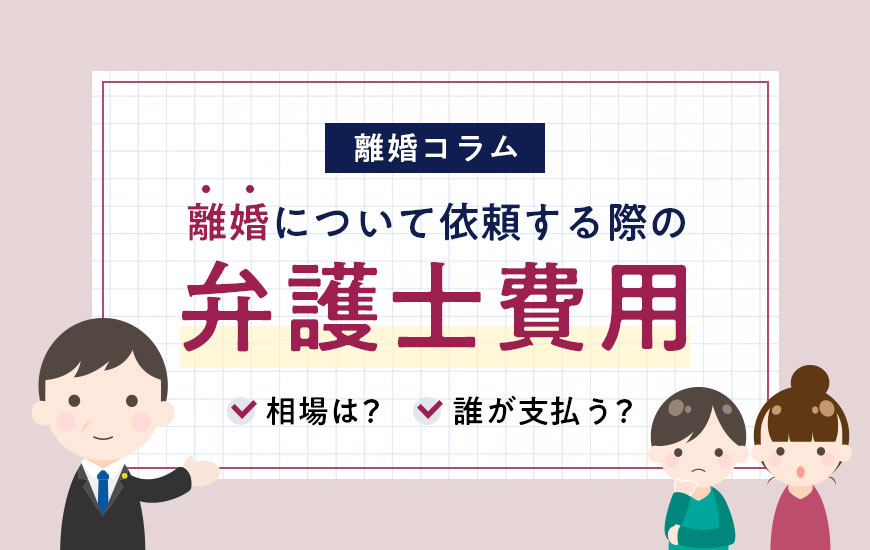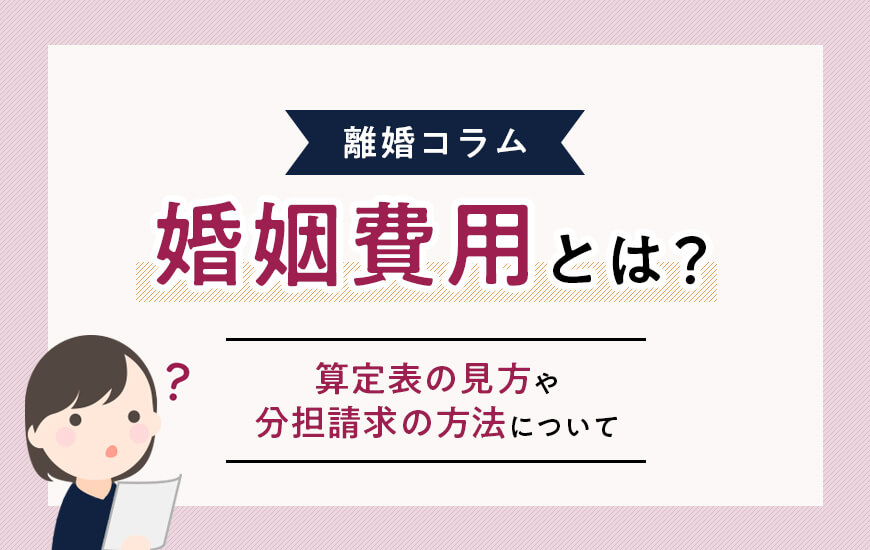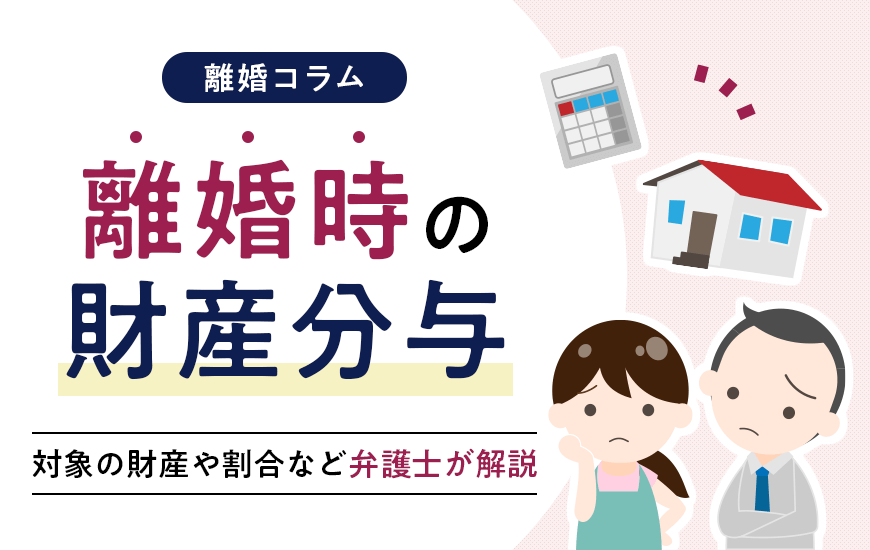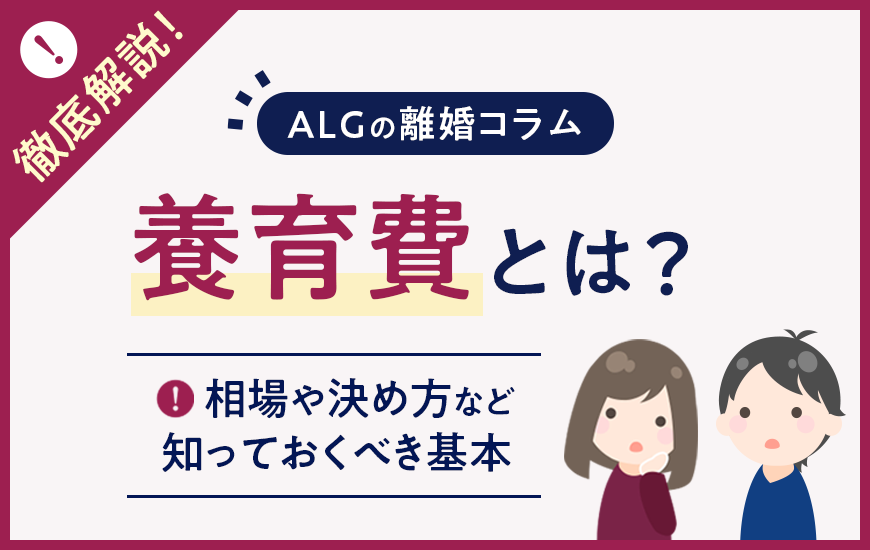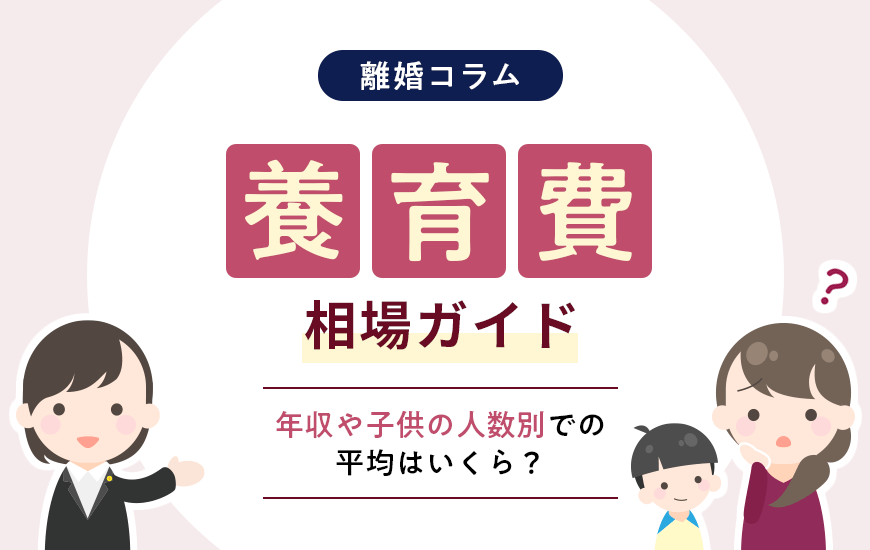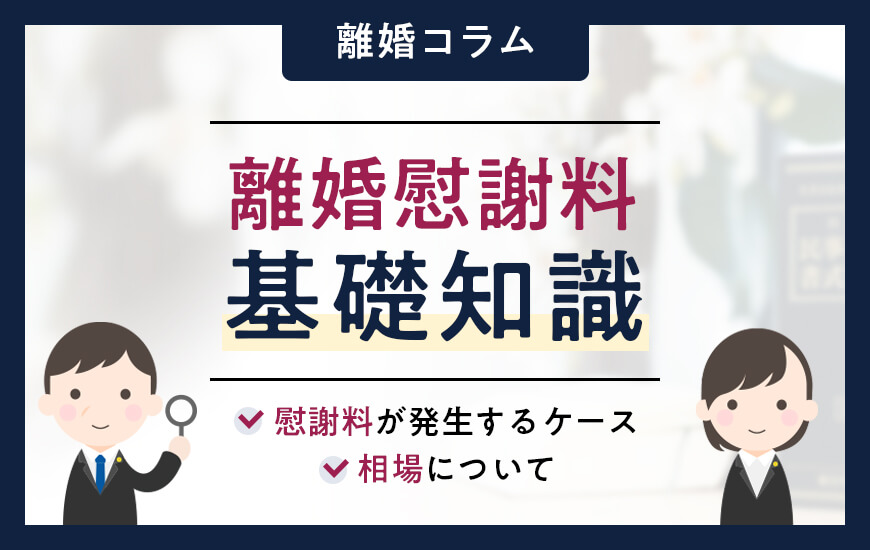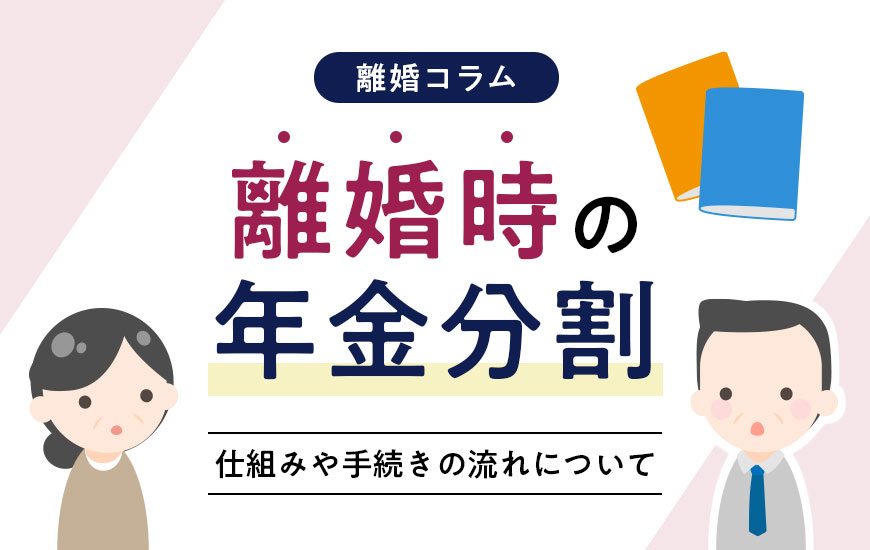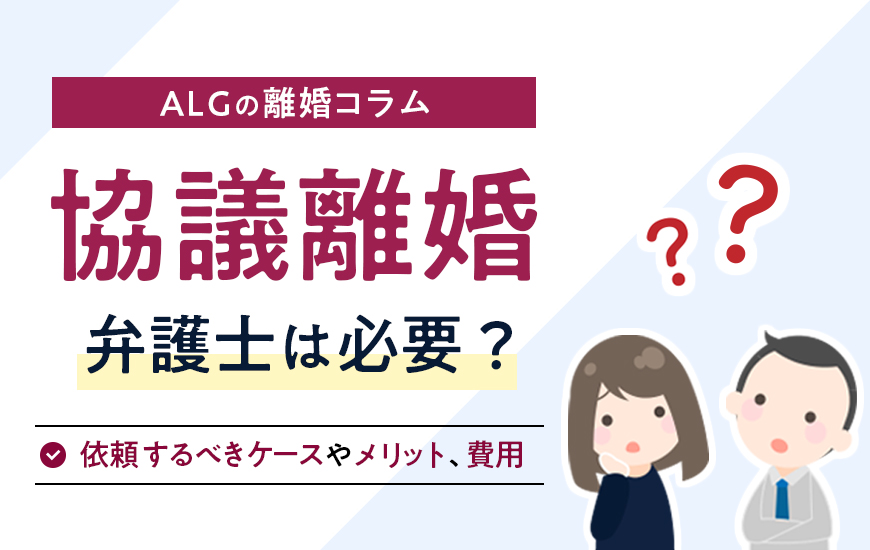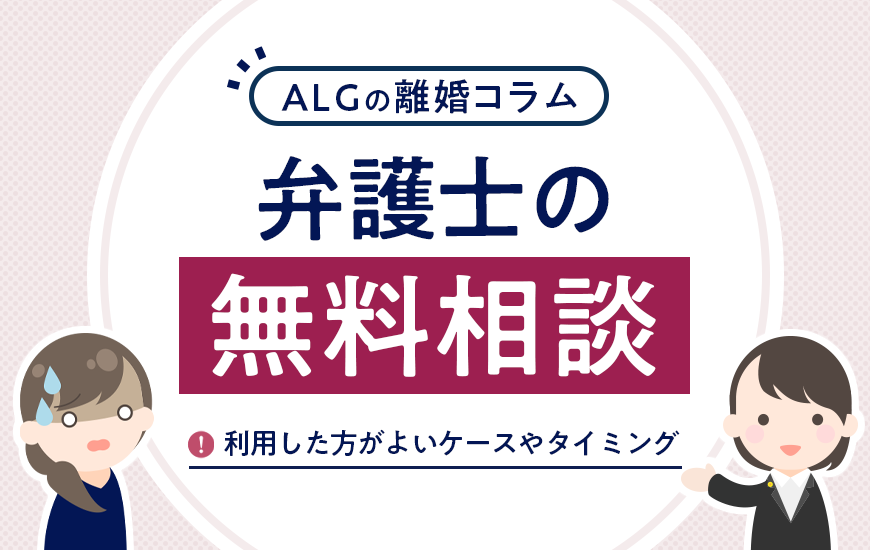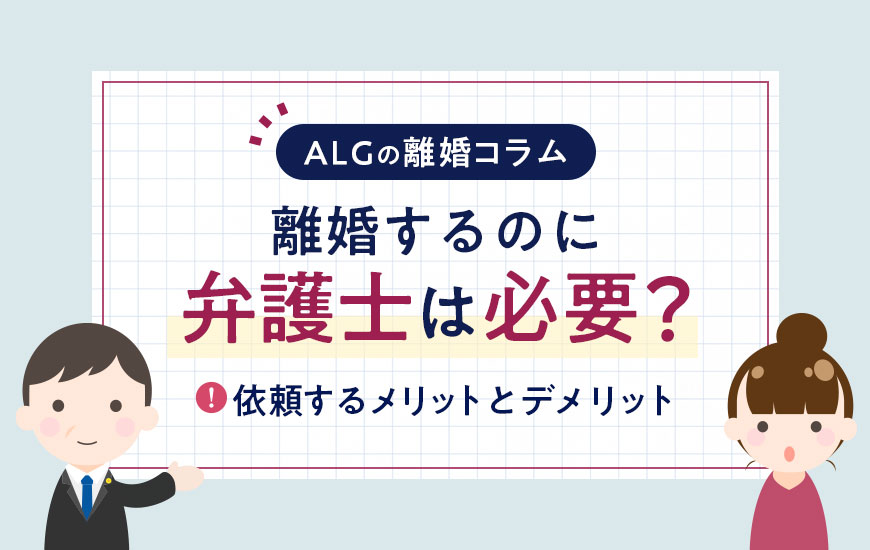離婚にかかる費用相場はいくら?費用の抑えるためのポイントなど解説
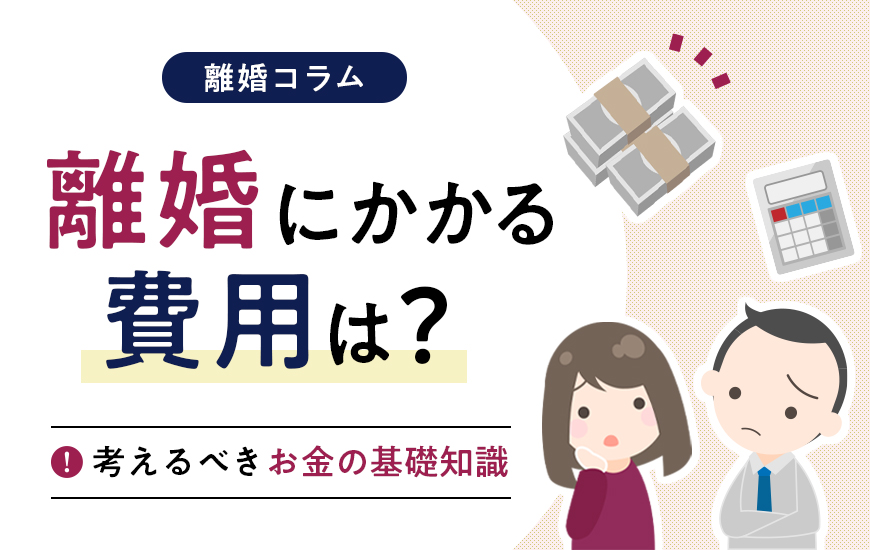
昨今では、3組に1組が離婚する時代といわれているように、離婚が身近なものになってきました。
しかし、離婚をするためにかかる費用や、離婚後の生活にかかる費用などが分からずに不安だという方もいらっしゃるでしょう。
離婚にかかる費用としては慰謝料や養育費、婚姻費用、弁護士費用、裁判費用などが挙げられます。
離婚に向けて準備をするときには、お金で困ることのないように、費用についてしっかり調べておく必要があります。
この記事では、離婚にかかる費用の相場や考えておくべきお金、離婚費用を抑えるためのポイント、費用がかかっても弁護士に相談するメリットなどについて解説します。
目次
離婚費用の相場はいくら?
離婚のためにかかる費用は、離婚の方法によって大きく変わります。
夫婦間の話し合いで離婚する「協議離婚」は、離婚届を提出するだけであれば、基本的に費用はかかりません。
ただし、離婚協議書の作成を弁護士に依頼する場合には、相談料や書類の作成料がかかります。
離婚協議書を公正証書にする場合には公証役場に対しても数万円程度の手数料がかかります。
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に申し立てて「離婚調停」や「離婚裁判」を行うことになります。
調停や裁判を行うためには、申立費用がかかります。弁護士に依頼すると、着手金や報酬金などの費用が追加されます。
協議離婚の費用
夫婦の話し合いで離婚する方法のことを協議離婚といいます。
協議離婚では、夫婦が話し合い、納得したうえで離婚届を市区町村の窓口に提出し、離婚が成立します。
基本的に費用はかかりません。
しかし、金銭の支払いを約束する場合、口約束だけでは「言った・言わない」のトラブルになるおそれがあります。
そのため、「公正証書」という形で残すことをおすすめしています。
公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう書面で、改ざんのおそれがありません。
さらに強制執行認諾文言付き公正証書にしておけば、約束した金銭が支払われない場合には、強制執行によって相手の財産を差し押さえることができます。
公正証書を作成するときには、作成費用(手数料)がかかります。書面で約束した金額が大きいと、作成費用も高額になります。
公正証書の作成費用
離婚のときに公正証書を作成する場合には、「自分で作成するか」「弁護士に依頼するか」によって、費用が大きく変わります。
公正証書は、養育費や財産分与などについて取り決めた金額に応じた手数料がかかります。
また、作成を弁護士に依頼する場合には、書類の作成などのために、15万~20万円程度の費用がかかります。
弁護士に依頼するメリットとしては、書類の内容に不備がないようにチェックしてもらえることや、将来的に相手が約束を守らなかった場合に、強制的に支払いを履行させる強制執行に対応できるような内容にしてもらえるなどがあります。
専門家のサポートを受けておけば、将来におけるトラブルを防ぐことにつながります。
なお、公正証書の作成にかかる費用は、どちらが負担するかを当事者が話し合って決めるのが一般的です。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 1万1000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 1万7000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 2万3000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 2万9000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 4万3000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円超過ごとに1万3000円加算 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円超過ごとに1万1000円加算 |
| 10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円超過ごとに8000円を加算 |
離婚の公正証書については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚調停の費用
夫婦の話し合いがまとまらず、離婚できない場合には離婚調停を申し立てます。
離婚調停とは家庭裁判所の手続きで、裁判官と調停委員で構成されている調停委員会を間に入れて、円満な解決を目指すための話し合いです。
離婚調停では、同時に離婚に関わる他の調停も申して立てることができます。離婚調停の費用は、基本的に申し立てた側が負担します。
主な費用は表にまとめましたのでご確認ください。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 収入印紙代 | |
| ・夫婦関係調整調停(離婚) | 1200円 |
| ・養育費請求調停 | 1200円(子供1人に付き) |
| ・面会交流調停 | 1200円(子供1人に付き) |
| ・財産分与請求調停 | 1200円 |
| ・年金分割の割合を定める調停 | 1200円 |
| ・慰謝料請求調停 | 1200円 |
| ・婚姻費用の分担請求調停 | 1200円 |
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 発行費用450円(郵送で取得する場合は別途郵送費などが必要) |
| 切手代 | 1000円程度 |
| その他必要な資料についての取得費用 | 資料によって異なる |
- 収入印紙代
2つの調停を同時に申し立てると、「1200円+1200円=2400円」の収入印紙代が必要となります。 - 切手代
申し立てる家庭裁判所によって金額が異なりますので、購入前に家庭裁判所に確認しましょう。
離婚調停は、弁護士へ依頼せずに自分で申し立てれば、費用は抑えられます。
しかし、離婚の際には財産分与や養育費など決めなければならないことが多くあり、すべてについて一人で対応するのは難しいでしょう。
また、相手が弁護士を立てている場合には話し合いが不利になるおそれもあるため、なるべく弁護士に相談してから申し立てることをおすすめします。
離婚裁判の費用
調停をしても話し合いがまとまらず、離婚できない場合には、離婚裁判を提起することになります。
離婚裁判では、裁判官が、法律で定められている離婚事由があり、離婚請求を認めるべきかについて判断します。
離婚裁判に必要な費用は、裁判でどういった判断を求めるかによります。
費用については表にまとめましたのでご確認ください。
また、裁判で鑑定や証人が必要となった場合には、鑑定費用や証人の日当が必要となります。
離婚裁判の費用は、原則として裁判を起こした側が負担します。
ただし、判決によっては、費用の一部を相手に負担させることが認められる場合もあります。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 離婚のみの場合 | 1万3000円 |
| 離婚と合わせて財産分与などを求める場合 | 各1200円を加算する 例)離婚、財産分与を合わせて請求 1万3000円+1200円(財産分与)=1万4200円 |
| 離婚請求と合わせて慰謝料を請求する場合の費用 | 1万3000円と慰謝料請求に対する収入印紙代を比べて、多額の方に財産分与などの手数料を加算 例)離婚、財産分与、慰謝料300万円を請求 慰謝料300万円の収入印紙は2万円で、離婚のみを求める1万3000円よりも多額なので、2万円+1200円(財産分与)=2万1200円 |
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 発行費用450円(郵送で取得する場合は別途郵送費などが必要) |
| 切手代 | 5000~6000円程度(家庭裁判所により異なる) |
| その他必要な資料についての取得費用 | 資料によって異なる |
弁護士費用
離婚を弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。
弁護士費用の内訳は、相談料や着手金、報酬金、日当、実費などです。
弁護士費用の金額を表にまとめましたのでご確認ください。
| 項目 | 費用相場 |
|---|---|
| 相談料 | 30分など一定時間は初回無料~1時間1万円程度 |
| 着手金(依頼時に発生する費用) | 20万~40万円程度 |
| 報酬金 | |
| ・基本報酬金 | 20~40万円 |
| ・成功報酬金 | 20~40万円 |
| 離婚成立 | 20~50万円 |
| 親権獲得 | 10~20万円 |
| 慰謝料や財産分与など | 合意金額または回収金額の10~20% |
| 日当(調停・裁判への出頭費用) | 0~5万円程度 |
| 実費 | 印紙代、切手代、交通費 |
弁護士費用は、基本的には依頼人が支払わなければなりません。
しかし、相手に離婚理由があるときには、損害賠償額の10%ほどを弁護士費用として相手に負担してもらえる可能性があります。
弁護士法人ALGに離婚と不貞行為の慰謝料を請求する訴訟の依頼をしていただいた場合には、主に以下のような費用がかかることになります。
- 相談料(1時間30分):1万1000円程度(初回30分無料)
- 着手金:50万円程度
- 諸経費:3万3000円程度
- 離婚の成功報酬:50万円程度
- 慰謝料(200万円)の成功報酬:33万円程度
- 日当や実費:かかった日数や費用による
離婚の弁護士費用が気になる方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
離婚に伴う引っ越し費用
離婚した場合、多くの方は元配偶者とは別の家で暮らすことになります。
そのため、引っ越し費用が必要です。
必要な費用の目安については以下の表をご覧ください。
| 必要なもの | 相場 |
|---|---|
| 引越し費用 | 数万~30万円 |
| 家具家電一式の購入費用 | 20万円~100万円程度 |
引っ越しは離婚にともなう費用のため、元配偶者に引っ越し費用を支払ってほしい、せめて折半してほしいと思う方もいらっしゃるかもしれません。
実は、引っ越し費用は法的に請求できると認められているものではありません。
離婚時の請求費目の中にも「引っ越し費用」という費目はありません。
そのため、財産分与や慰謝料、ご自身の独身時代の貯蓄から捻出しなければなりません。
しかし、引っ越し費用は法的には認められていないものの、任意の交渉で元配偶者が了承をすれば支払ってもらえることもあります。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
離婚の際に考えるべき5種類の「お金」
離婚をすると、夫婦はそれぞれ別の人生を歩むことになりますので、主に以下の5つのお金について考える必要があります。
- 婚姻費用
- 財産分与
- 養育費
- 慰謝料
- 年金分割
これらのお金について、次項より解説します。
①婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦と未成年の子供が生活をするために必要な費用のことです。
具体的には、居住費や生活費、医療費、子供の教育費、娯楽のための費用等が含まれます。
婚姻中である限り、たとえ夫婦が不仲で別居していても、一般的には収入の多い方が少ない方に対して、婚姻費用を支払う義務があります。
ただし、婚姻費用は基本的に婚姻費用の分担請求をしたときから支払いの義務が生じることになっているため、過去の分を請求するのは難しいことに注意しましょう。
婚姻費用について知りたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
②財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦で築き上げた財産を離婚時に公平に分配する制度のことです。
分配の割合は夫婦で相談して決めることができますが、基本的には夫婦の収入の差に関わらず、専業主婦(夫)であっても均等に半分の財産を受け取ることが可能です。
財産分与の対象となるものには、婚姻期間中に夫婦が2人で協力して形成したすべての財産です。
具体的には不動産、家財道具、車、預貯金、株式などが挙げられます。
合わせて読みたい関連記事
③養育費
養育費とは、未成年の子供を監護・養育するために必要となる費用のことです。
離婚後も子供と暮らしていく親(監護者)は子供と離れて暮らす親(非監護者)に対して毎月一定の金額を養育費として請求することができ、子供の生活費や教育費が含まれます。
養育費は夫婦の話し合いで双方が合意できればいくらになっても構いません。
しかし、夫婦で揉めてしまう場合は家庭裁判所が公表している養育費算定表を参考にすると良いでしょう。
④慰謝料
離婚慰謝料とは、離婚により精神的苦痛を負った場合に請求できるもので、不法行為に基づく損害賠償として位置づけられます。
例えば、配偶者の不法行為、DV、ハラスメント行為を理由に離婚する場合に慰謝料を請求できる可能性があります。
合わせて読みたい関連記事
⑤年金分割
年金分割とは、婚姻中に夫婦が納めた厚生年金の「保険料」を離婚時に分け合う制度です。
将来受け取る年金の額を均等に分配するわけではありません。
年金分割の請求には期限があるので注意しましょう。
年金分割の請求期限は原則として、離婚した翌日から2年間です。
離婚の年金分割については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚費用を抑えるためのポイント
離婚費用を抑えるためのポイントとして、主に以下のようなものが挙げられます。
- 協議離婚を目指す
- 法テラスを利用する
- 無料相談を利用する
これらのポイントについて、次項より解説します。
①協議離婚を目指す
協議離婚を成立させることができれば、少ない負担で離婚できますので、まずは話し合いによる解決を目指しましょう。
夫婦間の話し合いで離婚の合意ができれば、特別な手続きは必要なく、離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
裁判所への申立費用などもかからないので安心です。
また、弁護士に依頼する場合でも、調停や裁判に比べて弁護士費用も比較的安く済みます。
例えば、着手金の相場は30万円程度で、調停や裁判を申し立てるときの着手金よりも低めです。
費用を抑えながら離婚を進めたい方は、早めに弁護士に相談し、協議離婚で解決するための戦略を練っておくことをおすすめします。
協議離婚で弁護士に相談するべきケースについては、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
②法テラスを利用する
法テラスとは、日本司法支援センターの愛称であり、法律トラブルに悩む方が安心して相談できる窓口です。
離婚や養育費、財産分与などの問題について、弁護士による無料相談を最大で30分×3回まで受けることができます。
また、弁護士費用の立替制度もあり、費用を分割で返済できるため、まとまったお金がなくても安心して依頼できます。
法テラスを利用するには、収入や資産が一定の基準以下であることが必要です。
例えば、東京特別区などに住んでいる1人世帯であれば、月収が20万200円以下であり、資産は180万円以下であることが目安となっています。
また、相談内容が正当な権利の保護に関するものであること、勝訴の見込みがあることも条件です。
③無料相談を利用する
離婚にかかる費用を少しでも抑えたいと考えている方は、まずは弁護士の無料相談を活用することをおすすめします。
最近では初回の相談が無料で受けられる法律事務所も増えてきており、電話やLINEなどを使って気軽に相談できる環境が整ってきています。
特に、相手側にすでに弁護士がついているケースや、DVやモラハラなどの深刻な問題を抱えているケース、離婚の条件について話し合いがうまく進まないケース等では、早い段階で専門家に相談することで、無駄な費用や時間をかけずに済む可能性が高まります。
無料相談によって、今の状況に合ったアドバイスを受けることができるだけでなく、弁護士費用の見積もりや、今後の流れについても丁寧に説明してもらえることが多いです。
弁護士に無料相談できる窓口を知りたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
費用がかかっても離婚を弁護士に相談・依頼するメリット
離婚について弁護士に相談や依頼をすると、弁護士費用がかかってしまいますが、それでも相談するメリットとして主に次のようなものが挙げられます。
- 適切な金額の慰謝料を受け取れる
法的根拠に基づいて、相手に請求できる慰謝料の相場や妥当性などを判断してもらえるため、適切な金額の慰謝料を受け取れる可能性が高まります。 - 話し合いがスムーズにまとまる
夫婦だけで話し合うと、双方が互いに悪口を言うことで感情的な対立になりがちですが、弁護士が間に入ることで冷静に話し合いを進めることができます。 - 書類作成などの手続きを任せることができる
離婚協議書や財産分与の明細書の作成、年金分割といった複雑な手続きもすべて任せられるので、安心して話し合いを進められます。
離婚について弁護士に依頼するメリットを知りたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
離婚後に受けられる公的支援制度
お金がないまま離婚をするなど厳しい状況の場合、金銭面でサポートしてくれるさまざまな公的支援があります。
以下に一例をあげますが、一度ご自身でお住まいの自治体へ問い合わせてみるのも良いでしょう。
- 応急小口資金
低所得世帯が病気、給与の盗難・紛失、火災等の被災などで緊急に資金が必要となった場合にその資金を無利子で貸してくれる制度です。 - 自立支援教育訓練給付金
母子・父子家庭の経済的な自立を支援するため、その能力開発の取り組みを支援するものです。児童扶養手当を受けているか、または同等の所得水準にあり、現に20歳に満たない児童を扶養している方が対象です。
ひとり親への助成制度
母子(父子)家庭には、児童扶養手当や住宅手当など国や自治体が経済的支援する以下のような制度があります。
また、以下の制度はお住いの自治体によって制度の有無が異なる場合もあるため、ご注意ください。
- 児童扶養手当
- 児童手当
- 医療費助成制度
- 住宅手当
- 生活保護制度
- 母子父子寡婦福祉資金貸付制度
- 児童育成制度
離婚の方法や理由によって費用は変わります。お困りの方は弁護士法人ALGにご相談ください
離婚は離婚の方法や理由によって費用が変動します。
弁護士費用はご相談者様にとってネックとなる部分ですが、離婚をご自身で進めようとすると、うまく進まないことがあったり、慰謝料や財産分与で納得のいく結果が出なかったりする可能性があります。
離婚を弁護士に依頼することは、費用面だけでなく離婚そのものを成功させるうえで重要となるでしょう。
相手のある離婚だからこそ、弁護士が入ることでスムーズな話し合いができる可能性が高まります。
また弁護士は法律の専門家であるため、ご夫婦の状況に寄り添い、適切な慰謝料や財産分与の金額を算出いたします。
弁護士法人ALGでは、初回の無料相談も承っております。離婚に関するお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)