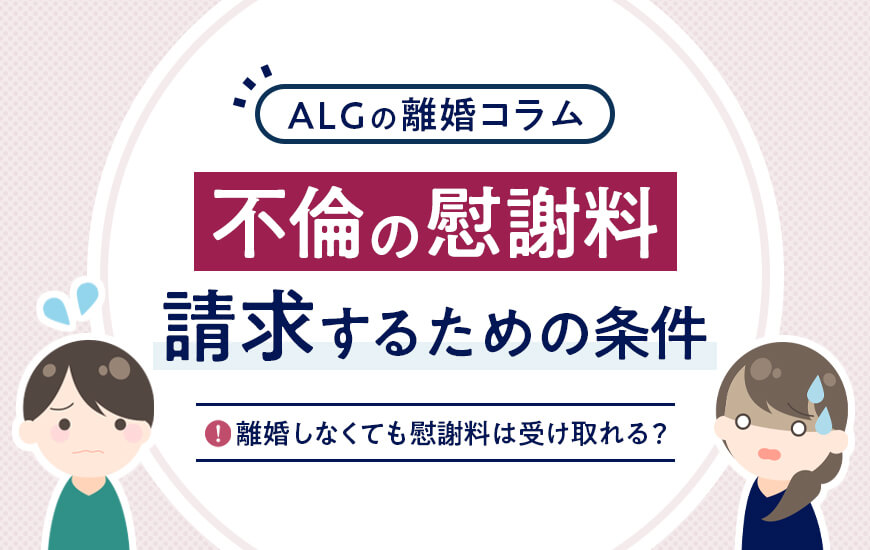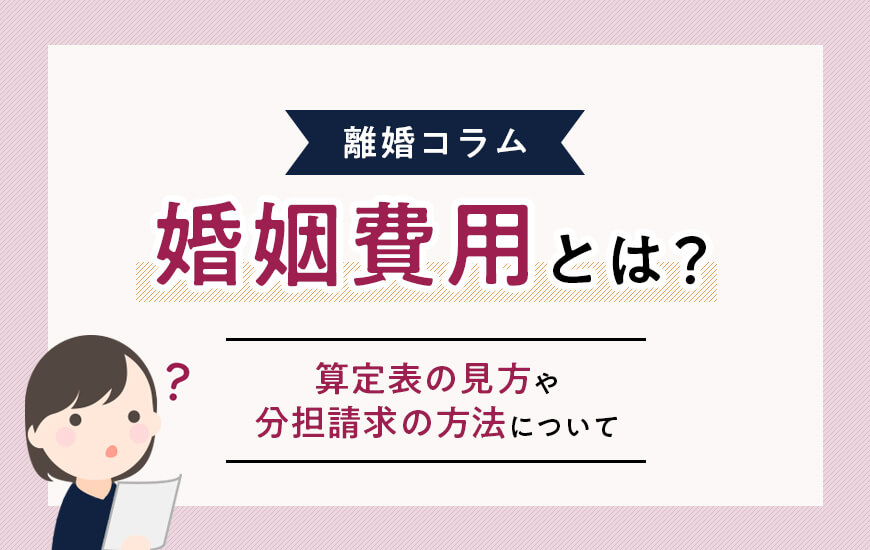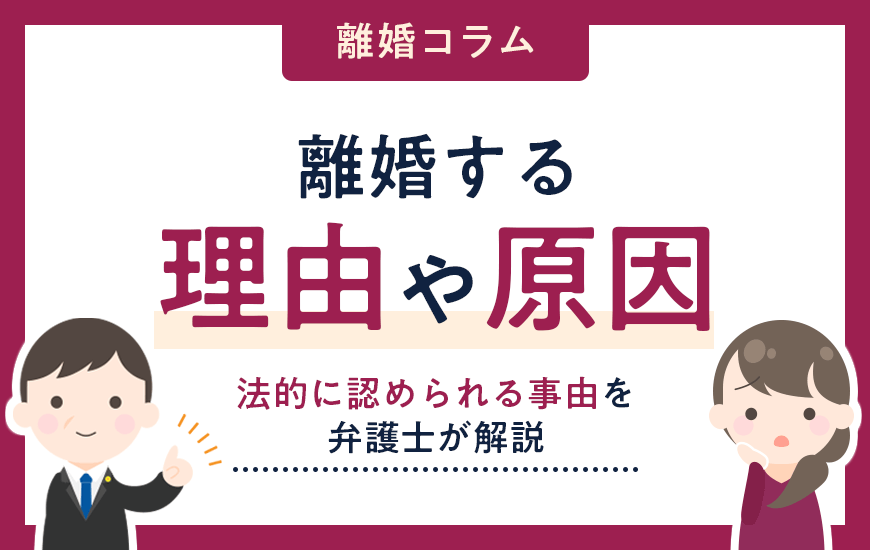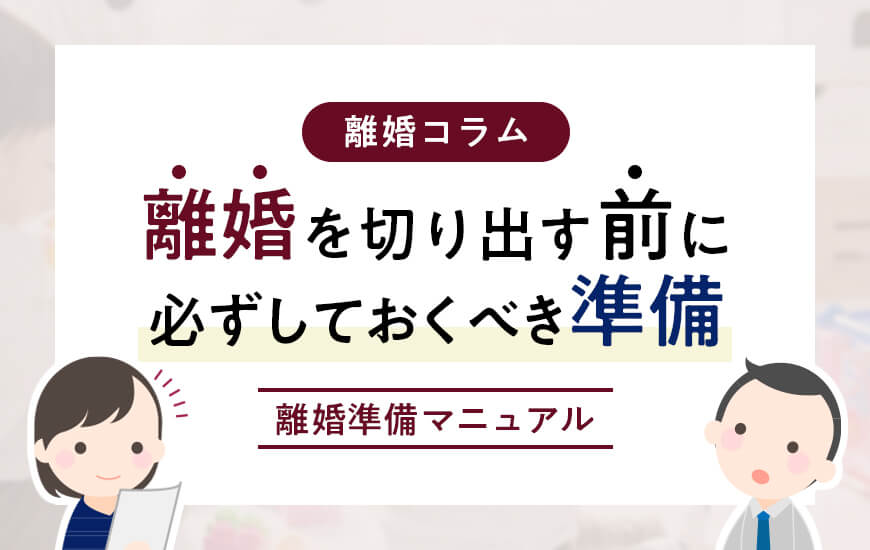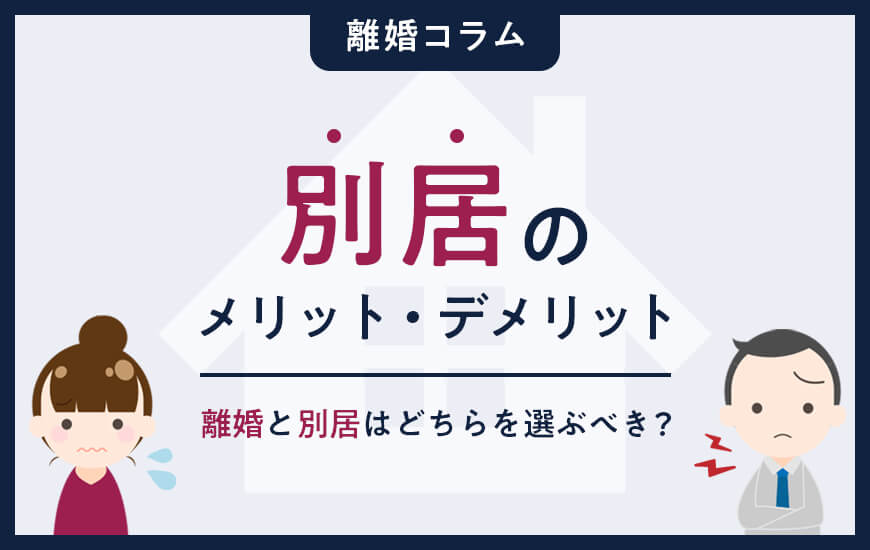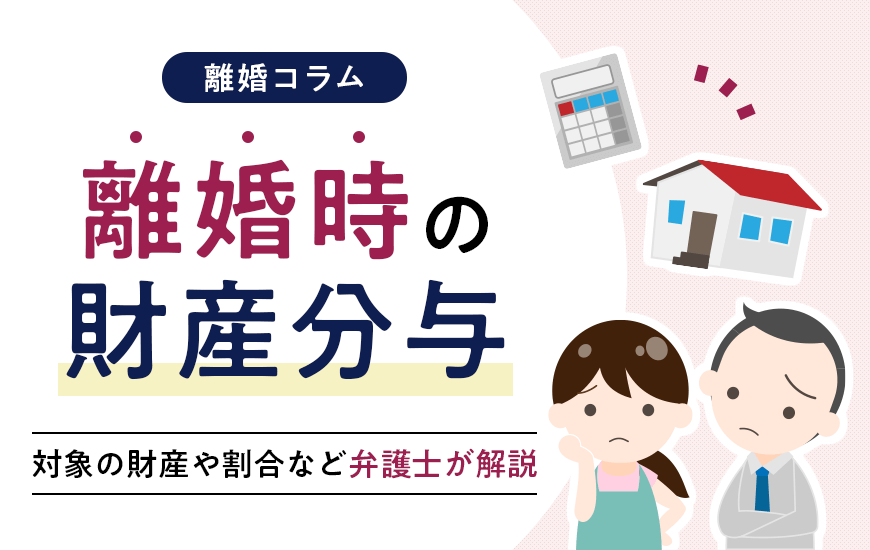家庭内別居とは?メリット・デメリットや適切なやり方を解説
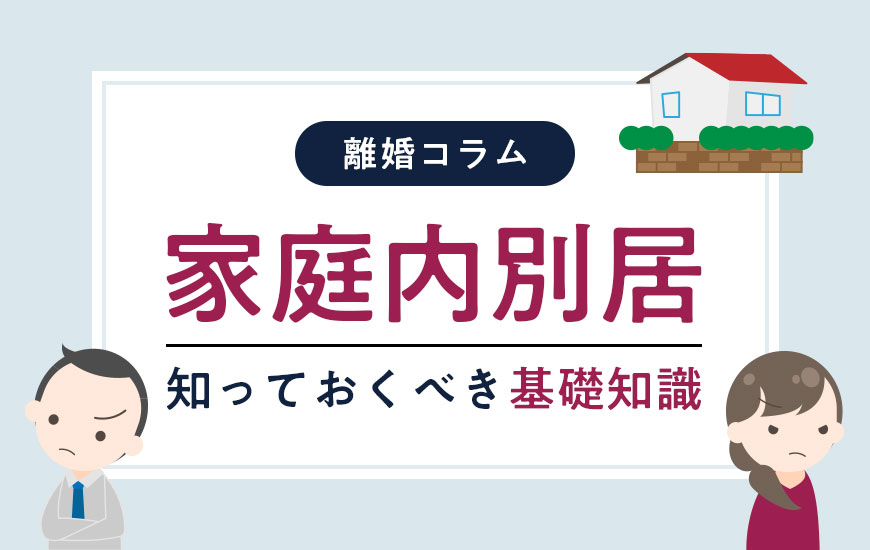
価値観の不一致を理由に衝突していたり、浮気などが原因で関係が悪化したり、様々な理由から家庭内別居をされている方もいらっしゃいます。
あまり良いイメージを持たれない「家庭内別居」ですが、なかにはそれが「良い選択」と考えている方もいるでしょう。
この記事では、家庭内別居のメリット・デメリットや、円満に過ごすコツ、離婚を考える際に知っておきたいことなどについて解説していきます。ぜひご参考ください。
目次
家庭内別居とは
家庭内別居とは、夫婦が同じ家に住みながらも、夫婦仲が悪いため、夫婦としての共同生活を行わず別々に生活している状態のことです。
家庭内別居は、子供の存在や経済的な理由から別居や離婚にまでは至っていませんが、いつ離婚してもおかしくはない険悪な状態であることが一般的です。
家庭内別居の特徴
家庭内別居の主な特徴は以下のとおりです。
- 顔すら合わせない
- 夫(妻)が何をしているか分からない
- 家にいるかどうかもハッキリしない
- 食事は別々
- 寝室も別々
- 子供はいずれかの親に付きっ切り
同じ家に住みながらも、本来の夫婦としての協力や会話、愛情が全くない状態が家庭内別居の特徴といえます。
家庭内別居と仮面夫婦の違い
仮面夫婦は人前では仲の良い夫婦を演じているけれども家の中では関係が冷え切っている夫婦を指すものと思われます。
仮面夫婦を家庭内別居だと考えている夫婦もいらっしゃると思いますが、人前で仲の良い夫婦を演じているのであれば、夫婦として完全な破綻をしているとまでいえない可能性があります。
ただ、家庭内別居も仮面夫婦も、厳密な定義はなく、境界線があるわけではないので、当事者の認識や呼び方の差に過ぎないでしょう。
家庭内別居をするメリット
離婚ではなく家庭内別居を選択している夫婦が多いのは、「経済面の負担が少ない」「世間体を気にしなくていい」といったメリットがあるからです。
次項で、2つのメリットについて詳しく見ていきましょう。
経済面の負担が少ない
離婚をしたら、家賃や生活費などを自分で賄っていかなければなりませんが、家庭内別居状態では住む場所もあり、さらに婚姻中ではあるので生活費を分担することができます。
世間体を気にしなくていい
離婚をすると、職場や子供の学校に隠し通すことは、まずできません。
対して、家庭内別居では他の人から見たら、夫婦関係が冷え切っているとは気づかれず世間体を守ることができます。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
家庭内別居をするデメリット
一方、家庭内別居には以下のようなデメリットもあるため、慎重に検討する必要があります。
- 同じ家にいるだけでストレスを感じる
- 夫婦関係が修復しづらくなる
- 子供に悪影響を及ぼす可能性がある
- 不倫の慰謝料が認められないリスクが生じる
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
同じ家にいるだけでストレスを感じる
「相手の顔を見るのが嫌だ」「同じ空気を吸うのも嫌だ」といったところまで関係が悪化している場合、同じ家にいるだけでストレスになります。
夫婦関係が修復しづらくなる
一度別居をして、自分や相手方を見つめなおすことで、夫婦関係を修復し、改めて夫婦としてやり直す方は実際にもいらっしゃいます。
ただ、家庭内別居を選択し、顔も見るのも嫌だというような状態を継続し、一切会話が無いような夫婦関係が長期化すると、そこから夫婦関係を修復するのは難しいでしょう。
子供に悪影響を及ぼす可能性がある
子供のために家庭内別居を選択された方もいるでしょう。
しかし、その選択が子供に悪影響を及ぼす可能性もあります。
たとえ小さな子供であっても、大好きなお父さん・お母さんの顔色や不穏な空気には敏感です。
仲良くしてほしいと思い、話の中心に入ってみたり、逆に気をつかって何も言えなくなってしまったり、子供は親の顔色をうかがいながら行動するようになってしまうこともあります。
夫婦関係が冷え切った中で生活することは子供にとっても相当なストレスとなり、精神的に不安定になったり、体調を崩してしまう場合もあります。
子供に悪影響を少しでも与えないようにするためには、子供が両親から愛されていると実感できるよう工夫することが大切です。
不倫の慰謝料請求が認められないリスクが生じる
家庭内別居中に相手が不倫した場合、慰謝料の請求が認められない可能性があります。
そもそも、不倫の開始が、婚姻関係が破綻した後だった場合には慰謝料の請求はできません。
同居を継続している家庭内別居は完全に夫婦が違う家に住む別居の場合と比べて、「婚姻関係が破綻している」と判断されにくいです。
しかし、家計が別々で家事分担もせず、性交渉も全くないなど、同居していても夫婦としての実態がないような場合は、「婚姻関係が破綻している」と判断されることもあり、不倫慰謝料の請求は認められない場合があります。
不倫慰謝料については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
家庭内別居のやり方
家庭内別居をする際は、以下のようなルールや話し合いをすることで、なるべく相手とトラブルなく過ごせるでしょう。
- 家庭内別居のルールを決める
- 家庭内別居の生活費について話し合う
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
家庭内別居のルールを決める
家庭内別居を行うときは、2人の距離の取り方を決める必要があります。
夫婦関係に問題があるからこそ、家庭内別居が発生します。
そのため、お互いに適度な距離感を保つことが必要です。
具体的には以下のようなルールの例があります。
- お互いのことを干渉しない
- 会話は無くても挨拶はする
- ひとりになれる空間を持つ
- 共有場所の使い方を決める
- 食事について決める
- 生活費などお金の管理について決める
- 子供の行事や接し方
- 休日の過ごし方
家庭内別居中の生活費について話し合う
家庭内別居中であっても、婚姻関係にあれば、収入の多い方から少ない方へ婚姻費用を請求できます。
婚姻費用とは夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。
離婚するつもりで別居したけど、専業主婦で収入がない、働いているが生活費が足りない。
そのような場合に、配偶者に離婚が成立するまで費用の分担を求めることができます。
配偶者から婚姻費用を渡したくないと言われるかもしれませんが、話し合いから始め、別居後や離婚後の生活のためにも婚姻費用をしっかりと受け取りましょう。
婚姻費用に含まれるものとして、具体的には以下のような費用が挙げられます。
- 家族全員の食費や光熱費、被服費などの生活費
- 家賃や固定資産税など、住宅の維持に必須となる居住費
- 保育園代や学費、習い事の月謝など、子供の養育費
- 通院費、治療費などの医療費
ただし、これらの費用については、各家庭の事情や状況によって異なります。
婚姻費用については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
家庭内別居から離婚することは可能?
家庭内別居から離婚することは、離婚の方法によっては可能です。
夫婦の話し合いによる離婚(協議離婚)や家庭裁判所の調停手続きによる離婚(離婚調停)では、基本的に夫婦で合意すれば、離婚の理由は何でも構いません。
お互いが離婚に合意できれば家庭内別居からでも離婚が成立します。
一方、離婚裁判では、「法定離婚事由」に該当する離婚理由がなければ離婚が認められるのは難しくなります。
「家庭内別居をしている」という理由だけでは、法定離婚事由に該当しているとは判断されにくいでしょう。
ただし、家庭内別居により相当期間に及んで婚姻関係が破綻していることを証拠とともに主張できれば、離婚が認められる可能性もあります。
離婚理由については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
家庭内別居での離婚が認められるケース
家庭内別居に至った理由や状況によっては、法定離婚事由のひとつである「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとして、離婚が認められることもあります。
例えば、以下のようなケースでは、婚姻を継続しがたい重大な事由に当たる可能性があります。
- 配偶者の分の家事を一切行わない
- 完全に家計を分離している
- 相手の不貞行為が原因で家庭内別居に至った など
ただし、家庭内別居は「婚姻関係が破綻している」ことが分かりにくいため、裁判所に離婚を認めてもらうのが難しい場合もあります。
家庭内別居は何年続くと離婚できる?
離婚裁判により離婚が認められるためには、「婚姻関係が破綻している」ことを示す客観的な事情として相当な別居期間が必要とされており、目安は一般的に3~5年とされています。
しかし、家庭内別居の場合は、夫婦が同じ家に住んでいることから、婚姻関係が破綻しているか否かを客観的に判断するのが難しいのが実情です。
家庭内別居により「婚姻関係が破綻している」状態が相当期間経過していることを証拠によって客観的に証明できれば、離婚が認められる可能性があります。
家庭内別居から離婚するためにすべきこと
家庭内別居から離婚するためには、事前に以下のような準備をすることが大切です。
離婚原因を証明する証拠を集める
裁判で離婚が認められるには、法定離婚事由が必要です。家庭内別居を理由に離婚したい場合は、以下のような家庭内でも別居状態であることが分かる証拠を集め、証明することが大切です。
- 必要最低限の会話しかしていないことが分かるLINE、メール
- 配偶者に生活費を渡さない
- 配偶者の食事を作らない、洗濯をしない
- 部屋に鍵をかけているなど、完全に生活が別であること
離婚条件を決めておく
離婚の際は、親権や養育費、面会交流、財産分与、年金分割など決めておくべき条件がたくさんあります。スムーズな話し合いができるよう、譲れる条件と譲れない条件を整理しておきましょう。
離婚後の生活について考えておく
離婚後は自分で生計を立てなければならないため、経済的な自立の準備が必要です。離婚後に住む家の確保や仕事の確保はもちろん、しばらく生活できるように少しずつ貯金していくことが大切です。
離婚準備については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
家庭内別居から完全別居する方法と注意点
相手と同じ家にいることに耐えられなくなった場合や、離婚を本格的に考え始めた場合には、家庭内別居から、別居に移ることを考えると思います。
別居は、家庭内別居と比べ、完全に住居が別々になることからストレスからは解放されるかもしれません。
しかし、別居に移ると離婚になる確率が上がりやすく、夫婦の修復がしづらくなることもあるため、やり直す可能性を考えている場合は注意が必要です。
別居をする時には、以下の点に注意しましょう。
完全別居に移る際には、相手の同意を得る
正当な理由なく、勝手に家を出ると、相手方に悪意の遺棄に当てはまると言って争われ、裁判が長期化する場合があります。
共有財産を調べておく
別居をすると、共有財産について調べづらくなってしまいます。
離婚時の財産分与のためにも、夫婦の共有財産は、家を出ていく前に調べておきましょう。
離婚するにあたっての別居や財産分与については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
家庭内別居に関するQ&A
離婚成立後も同居したまま、家庭内別居することは可能ですか?
離婚後であっても双方が同意しているのであれば、同居をして家庭内別居を続けることは可能です。
離婚後同居を選んだ場合、仕事と新しい住居の調節や家賃の負担、子供の転校等に悩むことなく、金銭的負担や夫婦、子供の負担を減らすことができます。
一方、離婚後も同居している場合は、母子(父子)手当てが受け取れない可能性が高くなります。
また、夫婦間に埋まらない溝がある場合は、毎日顔を合わせることが精神的ストレスとなるので、現実的には離婚後の同居は難しいでしょう。
共働き夫婦の場合、家庭内別居中の生活費はどうなりますか?
共働きの場合でも、夫婦のどちらか一方の収入が高い場合には、婚姻費用の分担義務が生じ、生活費を他方に支払わなければなりません。
家庭内別居でも、婚姻費用を請求することができます。
夫の収入が多い場合をイメージされる方が多いでしょうが、妻の方が収入が多い場合には、妻が夫に対し婚姻費用を支払わなければなりません。
なお、家庭内別居に至った原因は婚姻費用には関係ありません。
たとえ不仲であっても正式に離婚するまでは、婚姻費用を支払う義務があります。
専業主婦でも離婚を前提とした家庭内別居はできますか?
専業主婦であっても、家庭内別居をすることは可能です。
しかし、家庭内別居では、夫婦の間で、生活費が別になったり、お金の管理が別々になったりすることがあります。
そうなってしまうと、専業主婦の方は余力が無ければ生活ができなくなってしまいます。
家庭内別居であっても、婚姻中であれば「婚姻費用」を請求できます。
家庭内別居をしているからといって相手の言いなりにならないようにしましょう。
家庭内別居について不安なことがあれば、一度弁護士にご相談ください。
家庭内別居から離婚に移る夫婦は少なくありません。家庭内別居をしていても、ストレスになり離婚したいと思う方もいらっしゃることでしょう。
「子供がいるから離婚できない」など、家庭内別居の理由は様々でしょうが、お子様はその悩みを感じ取ってしまいます。
家族がストレスなく過ごすためにも、家庭内別居でお悩みの方は一度弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、家庭内別居から、別居に移るべきか、離婚をするべきか、または再構築をするべきか、一緒に悩み、アドバイスをしていきます。
また、配偶者に不貞行為やDVなどがある場合などは、離婚に向けて一緒に戦っていきましょう。
家庭内別居でお悩みの方、私たち弁護士法人ALGに一度ご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)