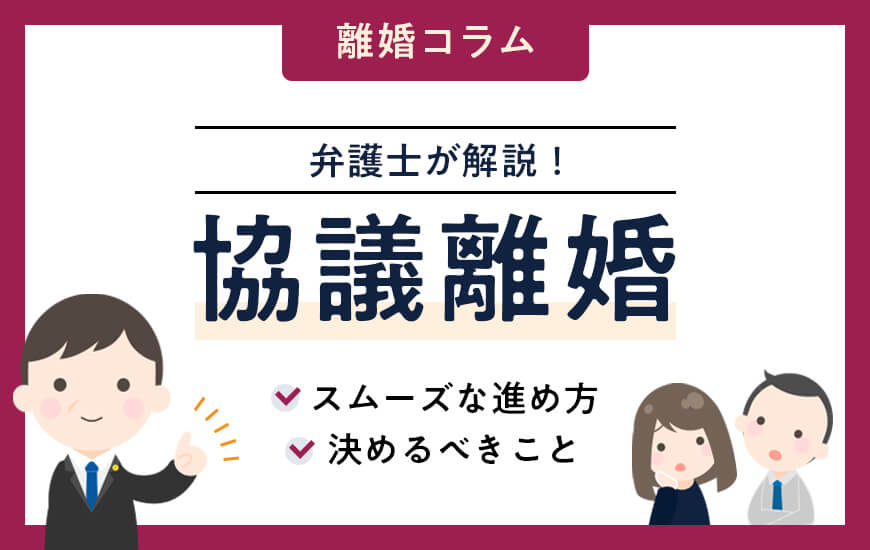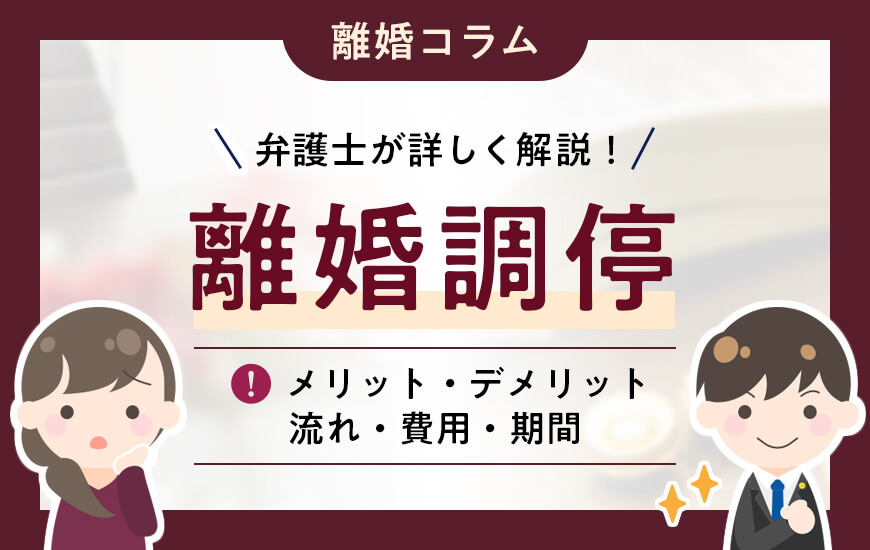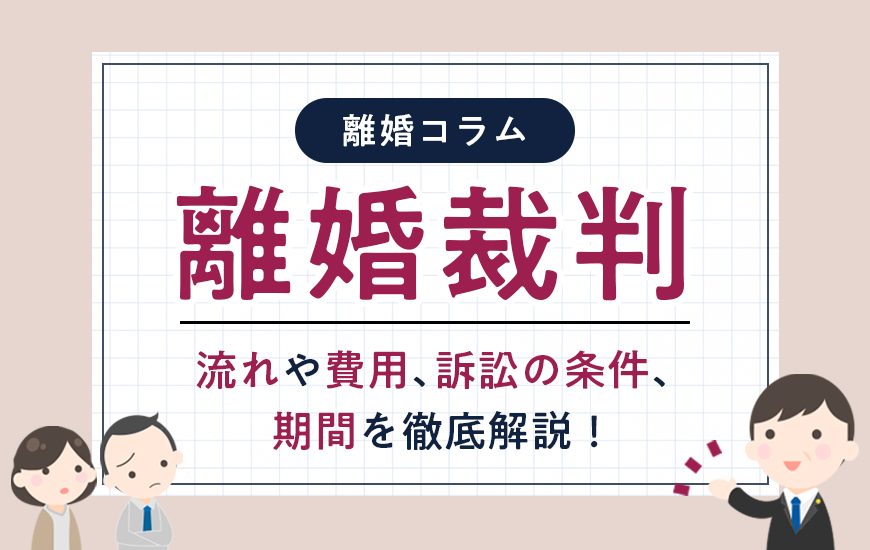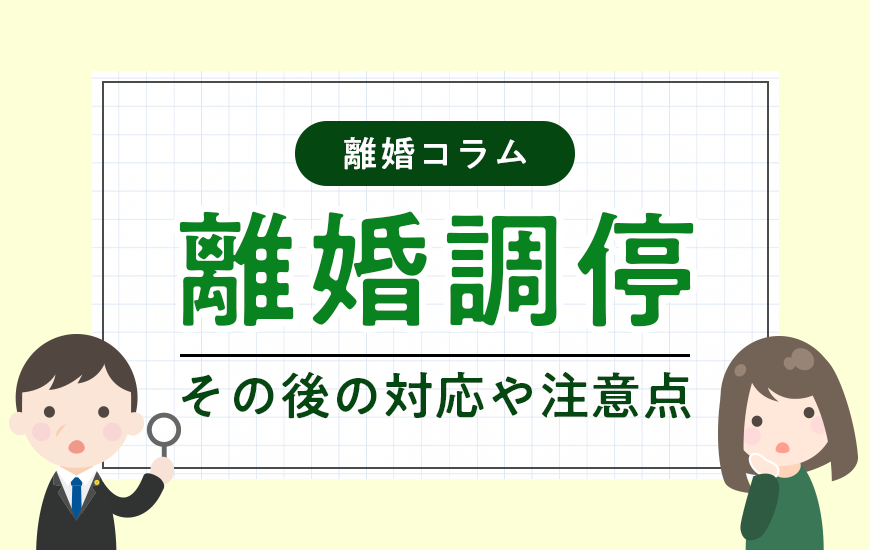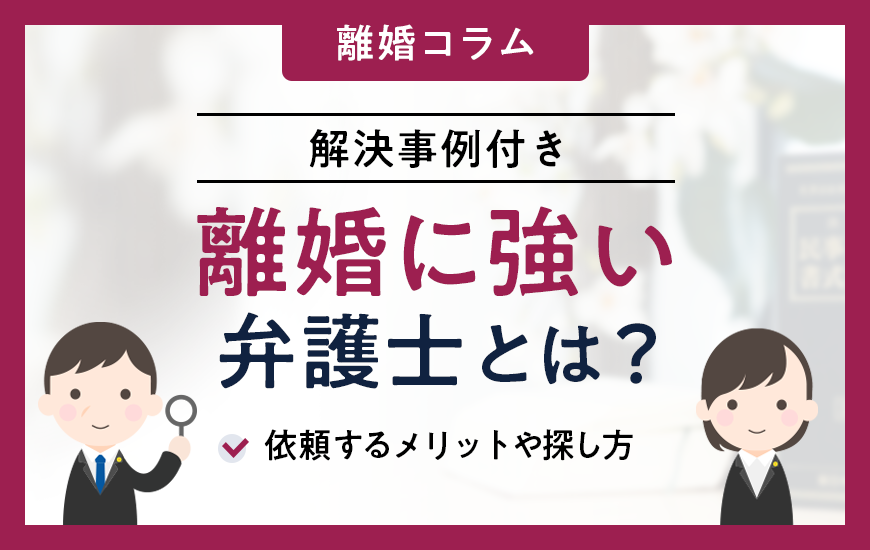離婚までの平均期間はどれくらい?協議・調停・裁判離婚を比較
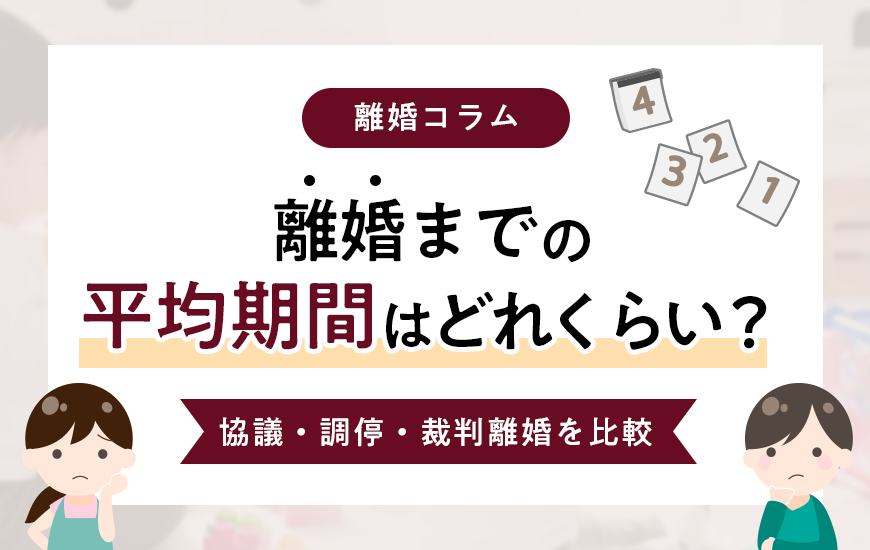
離婚を検討している方は、離婚が成立するまでにどのくらい期間を要するのか気になるかと思います。
離婚成立までにかかる期間は、離婚手続きの方法によって異なります。
離婚そのものは、離婚届を提出すれば成立しますが、離婚後のトラブルを防ぐためには、しかるべき離婚手続きの方法をとって、離婚条件を取り決める必要があります。
そこで本記事では、
など離婚成立までの平均期間に焦点をあてて、わかりやすく解説いたします。
目次
離婚成立までにかかる平均期間は1年以内
厚生労働省が発表した「令和4年度 離婚に関する統計の概況」によると、令和2年では、別居したときから離婚届けを提出するまでの平均期間は1年未満の割合が82.8%と最も多くなっています。
離婚手続き別にみると、協議離婚では別居期間が1年未満が86.2%、離婚裁判では別居期間が1年未満が56.8%となっています。
離婚手続きには主に協議離婚、離婚調停、離婚裁判の3つの方法があります。これらのうち、どの手続きを用いて離婚するかによって、離婚成立までの平均期間は変わってきます。
協議離婚の平均期間
協議離婚とは、当事者間での話し合いで離婚の成立を目指す方法です。
裁判所の手続きを利用しませんので、簡便に離婚できる方法になります。
日本では協議離婚が多いとされています。
協議離婚で離婚が成立するまでの平均期間は6ヶ月~1年です。
夫婦の話し合いが円滑に進めば、平均期間よりはるかに早く離婚が成立する可能性もあります。
お互い納得したうえで離婚届を提出して受理されれば、即日の離婚成立も可能です。
一方で当事者間の話し合いが、なかなかまとまらなければ1年以上かかる場合もあります。
協議離婚について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚調停の平均期間
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員に仲介してもらいながら、話し合いによる離婚の成立を目指す手続きです。
当事者だけの話し合いでは、離婚に関する問題で合意できないときに利用します。
離婚調停で離婚が成立するまでの平均期間は6ヶ月~1年です。
離婚調停は、申し立てから約1ヶ月後に第1回目の調停期日が設定されるのが一般的です。
第1回目では話がまとまらず、第2回目、第3回目と回数を重ねていくケースが多いです。
離婚調停期日は、1ヶ月~1ヶ月半に1回程度の頻度で開催されます。
離婚調停の成立または不成立は、第4回目の調停期日までには決まるといわれているため、離婚が成立するまでには6ヶ月程度かかることになります。
ただし、1回の期日の所要時間は約2時間なので、争点が多い事案では調停期日が多くなり、離婚成立までに1年、2年とかかるケースもあります。
離婚調停について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚裁判の平均期間
離婚裁判とは、離婚調停を行っても離婚に関する問題が解決できなかった場合に、家庭裁判所に裁判を提起して、判決によって強制的に離婚を目指す手続きです。
離婚裁判は、調停前置主義によって、離婚調停が不成立となった場合にはじめて提起できます。
離婚裁判で離婚が成立するまでの平均期間はおよそ1年~2年になります。
家庭裁判所に訴状を提出してから、およそ1ヶ月~1ヶ月半ほどで、第1回目の口頭弁論期日が開かれ、その後離婚裁判の審理は、1ヶ月~1ヶ月半に1回ほどのペースで行われることになります。
ただし、離婚裁判は必ずしも判決で終わるわけではなく、和解で終了するケースも多いです。
和解の場合は、判決に至る前に夫婦双方が合意するので、判決に至るよりも早く終了することになります。
離婚裁判について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚の平均期間が長くなる4つのケース
早く離婚をしたいと考えても、どうしても離婚成立するまでの期間が長期化するケースがあります。
主に次のようなケースです。
- 相手が離婚に応じてくれない
- 離婚条件がまとまらない
- 離婚時に子供がいる
- 調停や裁判へ発展した
①相手が離婚に応じてくれない
夫婦の一方が「離婚したい」と考えても、他方の配偶者が「離婚したくない」と考えていて離婚に応じてくれない場合は、離婚するかどうかの根本のところで主張が異なっているわけですから、長期化する傾向にあります。
話し合いでは離婚するかどうかを決めてから、その後に離婚条件などを決めることになるので、離婚が成立するまでにはそれなりの期間を要します。
相手が頑なに離婚に応じない場合は、協議離婚や離婚調停では解決できない可能性があり、最終的に離婚裁判まで進むケースがあります。
その場合には、協議離婚→離婚調停→離婚裁判と3つの手続きを順番に進めなければならないため、長期化する可能性が高いといえます。
②離婚条件がまとまらない
離婚する際は、慰謝料や財産分与、年金分割など離婚条件について決める必要があります。
離婚自体には合意できていても、離婚条件がまとまらない場合は長期化する傾向にあります。
例えば、マイホームを所有している場合は、離婚後どちらがマイホームに住むのか、住宅ローンの負担はどうするのか、連帯保証人を変更できるのかなど複雑な問題が発生します。
また、相手の不倫やDV・モラハラなどの有責行為が原因で離婚する場合は、慰謝料をできるだけ多く支払ってもらいたい者とできるだけ慰謝料の金額を抑えたいと考える者との話し合いがなかなかまとまらないということもあり得ます。
③離婚時に子供がいる
離婚する際に子供がいると、親権や養育費、面会交流など子供に関する問題を取り決める必要があります。夫婦だけの家庭より決めなければいけない事柄が増えるため、離婚する際に長期化する傾向にあります。
特に親権については、離婚届に親権者を記載する欄があり、親権者が決まらないと離婚できません。
夫婦それぞれが、親権を取りたいと主張し、話し合いを重ねても、お互い親権を譲る気がない場合は、平行線をたどってしまい、長期化します。
④調停や裁判へ発展した
当事者間での話し合いを重ねても、夫婦の一方が離婚を拒否していたり、離婚条件で折り合いがつかなかったりする場合には、離婚調停や離婚裁判など家庭裁判所の手続きに進むことになります。
調停を経なければ、基本的に裁判を起こせないという調停前置主義のルールがあるため、調停を省略して裁判を提起することはできません。
離婚調停の申立てをしてから第1回目の調停期日の開催までには、1ヶ月~1ヶ月半程度かかります。
第1回目の期日で解決するケースは少なく、第2回、第3回と期日を重ねていきますので、解決までの期間は長引きます。
調停が不成立になれば、離婚裁判を提起することになりますが、離婚裁判も提起してから第1回目の口頭弁論期日の開催までに1ヶ月~1ヶ月半程度かかります。
その後、1ヶ月~1ヶ月半に1回のペースで期日が開催されるので、解決するまでには年単位の時間を要することが多いです。
合わせて読みたい関連記事
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
離婚手続きの期間を平均より短くする3つのポイント
離婚手続きの期間を平均より短くする3つのポイントをご紹介します。
- 離婚手続きで決める内容を明確にする
- 離婚条件の優先順位を決める
- 離婚問題に強い弁護士に相談する
①離婚手続きで決める内容を明確にする
離婚に関する問題を話し合う中で、何を決めるべきかをはっきりしていないと話し合いが効率よく進みません。
そこで、夫婦で決めるべき内容を事前に明確にしておくことが大切です。
例えば、次のような事柄をまとめておいて、その点に集中して話し合うとスムーズです。
- 親権を決める
- 財産分与(不動産、自動車、預貯金)をどう分けるか決める(マイホームはどうするか、自身が把握している財産以外に共有財産はないか確認する)
- 養育費の金額・支払方法・支払期限を決める(養育費算定表による養育費の相場は〇万円)
- 面会交流をどうするか決める
など自分自身が見てわかりやすいようにまとめておきましょう。
②離婚条件の優先順位を決める
離婚条件は、残念ながら、自分の希望通りに適うとは限りません。
相手にも離婚条件の希望があるため、すべて希望通りにしようとすると離婚手続きは長期化します。
離婚が成立するまでの期間を短くするためには、離婚条件の優先順位をつけて譲歩できる条件は譲歩し、譲歩できない条件は譲歩しないと自分のなかではっきりさせておくことが大切です。
例えば、親権は譲れないけど、慰謝料の金額は多少低くなっても構わない、親権を譲ってもいい代わりにきちんと面会交流を実施してもらいたいなどです。
③離婚問題に強い弁護士に相談する
離婚問題に精通している弁護士に相談して、離婚手続きを進めるのも、離婚までの期間を短縮するためのひとつの方法です。
離婚手続きを何度も経験している方は少ないでしょうから、離婚する際に取り決めなければならないことがはっきりとはわからないことも多いと思います。
弁護士が介入すれば、取り決めることをきちんと整理し、代わりに相手と話し合いしてもらうことも可能ですので、結果的に離婚までの期間を短くすることが可能です。
離婚に強い弁護士について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
弁護士の介入により協議離婚が早期解決した事例
本件は、相手方が離婚を拒否している状況で、弁護士が依頼を受けて協議を開始したところ、離婚に応じてもらえた事例です。
相手方は、定職に就かず、家事や育児にもほとんど参加しておらず、マッチングアプリに登録して女性とやり取りをしていました。
依頼者が離婚を切り出しても、相手方からは拒否されていたため、当事務所にご依頼いただきました。
早速、弁護士から相手方に受任通知を送付し、協議を開始したところ、依頼者の離婚意思の強さが伝わって、相手側が離婚に応じる態度に変わりました。
そこで、依頼者の希望を尊重して、なるべく早く離婚することを重視しながら、主に離婚条件について話し合うことになりました。
結婚していた期間が短かったので、財産分与はお互いに請求せず、月5万円の養育費と年金分割について合意して、受任から2ヶ月程度で離婚することが決まりました。
離婚の平均期間に関する質問
平均何ヶ月もかかる離婚の手続き期間中の生活費はどうしたらいいですか?
離婚手続き期間中の生活費が心配だという方はとても多いと思います。
離婚がまだ成立していない状況で別居をしている場合や同居していても夫婦のうち収入の多い方が生活費を入れない場合などは、夫婦のうち収入の少ない方が収入の多い方に生活費(住居費、食費、光熱費、医療費、養育費など)として婚姻費用を請求して受け取ることができます。
夫婦間での話し合いでは、婚姻費用の支払いについて合意できなければ、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てて請求することができます。
ただし、婚姻費用は、婚姻期間中のみに請求できます。
離婚が成立すると婚姻費用の請求はできませんので注意が必要です。
離婚の手続き期間中は子供と面会交流できますか?
離婚の手続き期間中でも子供との面会交流はできます。
面会交流は、父母が離婚や別居をしても、子供が、両方の親から愛されていると感じながら育つことで、健やかに成長するために必要だと考えられています。
そのため、離婚手続き期間中でも、子供と離れて暮らす親は子供と面会交流を行うことができます。
ただし、子供を虐待するおそれがある、面会交流時に子供を連れ去る可能性があるなど面会交流をすることで子供の心身の健全な成長に悪影響を与える可能性があると判断される場合は面会交流を認められない、もしくは面会交流の内容や頻度を制限される場合もあります。
離婚問題を平均期間よりも早く解決したい方は弁護士法人ALGへご相談ください!
離婚を切り出してから離婚が成立するまで、場合によっては相当な期間を要するケースもあります。
離婚手続き中は精神的な負担が大きくなるため、できるだけ早く問題を解決し、心身ともに落ち着きたいと考える方が多いでしょう。
離婚問題を早く解決したい方は、ぜひ弁護士法人ALGへご相談ください。
弁護士法人ALGは、離婚問題に精通した弁護士が多数在籍しています。
もちろん、スピード解決を成功させた実績も多数あります。
弁護士法人ALGにご相談いただければ、ご希望に沿った条件で、円滑な離婚成立を目指して対応いたします。
まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)