離婚時に住宅ローンが残ってる!ローンは財産分与の対象?返済方法は?
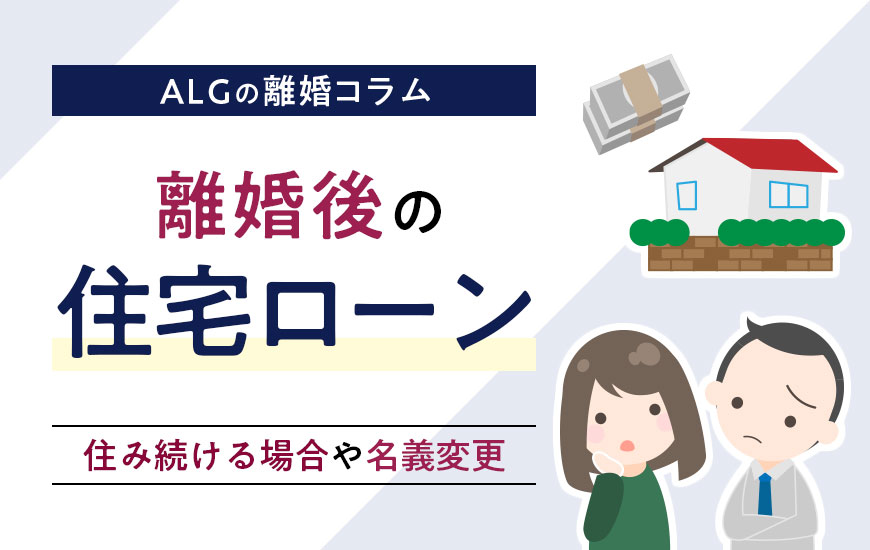
離婚の際には、夫婦が築き上げた財産を分配する「財産分与」を行います。財産分与の対象財産には、現金や預貯金のほかに、不動産も含まれます。
そのため、離婚時に住宅ローンが残っている場合、「残りのローンは誰が払うのか」「名義や財産分与はどうなるのか」など、さまざまな問題が起こりやすくなります。
離婚後のトラブルを回避するためにも、住宅ローンについて慎重に取り決めをしておくことが大切でしょう。
この記事では、離婚の際に住宅ローンについて確認すべきことや、ケース別の返済方法などについて、詳しく解説していきます。ぜひご参考ください。
目次
離婚の際に住宅ローンについて確認すべきこと
離婚時に住宅ローンが残っている場合、住宅の財産分与を行うにあたり、まずは、以下の内容について事前に確認しておきましょう。
- 住宅の名義
- ローンの契約内容(特に債務者や連帯保証人が誰になっているか)
- 住宅ローンの残高や家の価値
- ローンを負担する割合
では、それぞれについて、以下で詳しく見ていきましょう。
住宅の名義
住宅購入時の売買契約書や登記を見て、名義を確認しましょう。
登記が見つからない場合は、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することで住宅の名義人を確認できます。
住宅を売却できるのは名義人だけです。
マイホームを購入するときに夫婦の共同名義にするケースがよくありますが、離婚後どちらかが家に住み続ける場合は家の名義は単独名義にしておくことをお勧めします。
理由は次のような問題が生じるおそれがあるからです。
-
離婚後、住宅を売却したくなっても名義を持つ元配偶者の同意を得なければ売却が難しくなる
元配偶者の同意がない場合は自身の持分だけを売却することになりますが、そもそも買い手を見つけるのは非常に困難ですし、仮に買い手が見つかったとしても、売却額は通常よりも相当低額になってしまいます。
-
元配偶者が亡くなった場合は、元配偶者の持ち分は遺族に相続される
例えば、亡くなった名義人が再婚して新しい配偶者と子供がいる場合は、元配偶者と新しい配偶者や子供が共有名義となり、手続きの関係性が複雑になります。
-
固定資産税や都市計画税などの維持費の支払いも不公平になり後からトラブルになるおそれがある。
後々のトラブルを事前に防ぐためにも家を住み続ける人の単独名義にしておきましょう。
ローンの契約内容
住宅ローンを契約したときの「金銭消費賃借契約書」を確認すればローンの契約内容がわかります。
債務者が誰になっているか、連帯保証人は誰なのか確認しましょう。
住宅ローンの契約形態で考えられるのが、次の4つのケースです。
-
単独債務型
夫か妻どちらか単独で返済義務を負っていて、もう一方の配偶者は負担がないケース。
-
連帯債務型
夫婦共同で住宅ローンの契約者になっているケース。
どちらかが家に住み続ける場合は単独債務への変更を検討しましょう。 -
連帯保証型
夫婦どちらかが住宅ローンの契約者となり、もう一方の配偶者や親等が住宅ローンの連帯保証人になっているケース。
契約者が家に住み続ける場合は、連帯保証人の変更を検討しましょう。 -
ペアローン
夫婦が1人ずつ別々の住宅ローンの債務者となった上で、お互いがそれぞれもう一方の配偶者の連帯保証人となっているケース。
どちらかが住み続ける場合は、相手のローンを買い取るか、借り換えなどによってペアローンを一本化して解消するなど検討しましょう。
住宅ローンの残高や家の価格
住宅ローンの残高は「償還表(返済予定表)」や「残高証明書」などで確認できます。
家の価格は、様々な方法で調べられますが、よく利用されるのが不動産会社に査定してもらう方法です。
査定額は不動産会社によって異なるため複数の不動産会社に査定してもらいましょう。
住宅ローンの残額と家の価値を知ることで、売却によって住宅ローンが完済できるのか(アンダーローン)、住宅ローンが残るのか(オーバーローン)を把握でき、不動産を売却するかどうか、売却しない場合は誰が住み続けるか、など方針が大きく変わります。
アンダーローンとは
アンダーローンとは、家の売却価格がローン残額を上回っている状態をいいます。
売却方法は、不動会社に委託して買い手を見つけてもらう「仲介」と不動産買取業者が直接買い取ってくれる「業者買取」の2つの方法があります。
家を売却した価格で住宅ローンを完済し、売買手数料などを差し引いたうえで手元に残った現金は、財産分与の対象となります。
オーバーローンとは
オーバーローンとは、家の査定額が住宅ローン残額を下回り、家を売却してすべて返済に充てても、負債が残ってしまう場合をいいます。
住宅ローン返済中の不動産は抵当権が設定されており、完済して抵当権を外さないと売却できません。
解決方法として、ひとつは住宅ローンの残債を自己資金で支払ってから売却する方法です。
離婚時に残っている住宅ローンは財産分与の対象?
財産分与は婚姻後に夫婦が協力して築いたプラスの財産を分ける制度です。
住宅ローンはマイナスの財産ですので、住宅ローンそのものは財産分与の対象とはなりません。
よって、基本的には住宅ローンの返済義務は住宅ローンの名義人が負うことになります。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
離婚したら住宅ローンは誰が払う?ケース別の返済方法
離婚後も妻が住む場合
妻が親権を獲得した場合、子供の生活環境を変えずに済むため、離婚後に妻がそのまま住み続けるケースは少なくありません。
ただし、住宅ローンが残っている場合は誰がローンを支払うか問題になります。
どのようなことに注意すべきか、詳しく見ていきましょう。
夫が住宅ローンをそのまま払う
自宅を取得するのが妻である以上、本来は妻が住宅ローンの支払い義務を負うことになりますが、夫が引き続きローンを支払うと合意することも可能です。
妻が専業主婦のため資力がないケースや、夫が養育費や慰謝料の代わりにローンを支払い続けるというケースなどが考えられます。
この場合は、夫がローンを滞納した場合のリスクに備えて、公正証書を作成しておきましょう。
なお、強制執行認諾文言付き公正証書にすると、支払が滞った場合に強制執行の申立てをすることで、銀行口座や財産を差し押さえることが可能となります。
また、住宅ローンは債務者が継続的に居住することが前提のため、夫が債務者となっていて、妻が住み続ける場合には、あらかじめローンの借入先に了承を得ておいた方が良いでしょう。
ローンを支払う人が住んでいないとなると、契約違反にあたる可能性があり、注意が必要です。
妻が住宅ローンを払う
妻が自宅を取得するのであれば、妻が住宅ローンも支払うのが基本です。
ただし、住宅ローンの名義人が夫の場合、借入先の銀行などは、離婚後、住宅ローンの名義人を夫から妻に変更することを通常は認めてくれません。
住宅ローンの名義人変更が認められるのは、以下のような場合に限られます。
- 住宅の価値が住宅ローン残高を大きく上回っている場合
- 妻の資力が夫と同程度の場合
- 妻が資力のある保証人を付けることができる等の場合
また、連帯保証人や連帯債務者、ペアローンを単独債務にする変更は簡単には認められないため、注意が必要です。
このように、住宅ローンの名義人を変更するのは難しいことが多いため、住宅ローンの名義人は夫のままにし、妻が住宅ローンに相当する分を夫に直接支払うと合意する方法もあります。
住宅の名義変更をする
住宅を夫名義のままにしておくと、夫の財産となります。
住宅ローンが残っていない場合は、妻名義に変更しても問題ありません。
しかし、住宅ローンが残っている場合は、金融機関に名義変更の承諾を得る必要があります。
金融機関との契約内容によっては、住宅ローン完済前に勝手に住宅の名義変更をすると、契約違反となり、住宅ローン残額の一括返済を請求されるおそれもあります。
住宅ローンが残っている状態で住宅の名義変更したい場合は、貯金や親族に援助してもらってローンを完済するか、妻の収入があれば住宅ローンの借り換えをするか、もしくは、住宅ローンの完済まで待って、「住宅ローンが完済したあとは妻の名義にする」と公正証書を作成して合意しておく方法などを行いましょう。
離婚後も夫が住む場合
住宅ローンの名義人である夫がそのまま家に住み続ける場合は、離婚後も夫がローンの支払いを続けることになります。
ただし、妻が連帯保証人となっている場合、夫のローン支払いが滞ったときに、妻に返済義務が生じるため注意が必要です。
連帯保証人を契約後に変更するためには、借入先に交渉して了承を得る必要があります。しかし、認められるのは基本的に難しいのが実情です。
妻が連帯保証人から免れるためには、新しい連帯保証人をつけるか、保証協会を利用するか、まとまったお金を入金する必要があります。
その他にも、住宅の評価額がアンダーローンの場合は、財産分与をする必要があります。
住宅を売却する場合
自宅にどちらかが済み続けたいと強い希望がなければ、離婚する際に住宅を売却して、売却益を住宅ローンの返済に充てる方法があります。
この場合、住宅ローンを完済後、売却に必要な諸経費を除いた残額を夫婦で分与することになります。
残ローン<売却額 の場合
住宅の売却額から残ローンを差し引いた金額を財産分与することができるため、比較的揉めずに財産分与を進められるでしょう。
売却額<残ローン の場合
この場合は、住宅を売っても残ローンを完済することができません。そのため、基本的には夫婦のどちらか一方が住み続け、ローンも支払うことになります。
どうしても売却したい場合には、任意売却をご検討ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
離婚の際の住宅ローンについてよくある質問
離婚したら住宅ローンを契約している銀行などに報告する義務はありますか?
離婚をしたことは、銀行に報告する義務があります。
銀行と債務者が取り交わす「契約書」には、届出事項に変更が生じた場合の報告義務が記載されています。
離婚により、氏名や住所等、届出の内容が変わる場合には、変更内容を銀行に報告しましょう。
離婚の報告は、「報告しにくい」「気が進まない」と思われるかもしれませんが、報告を怠ると契約違反としてローンの残債を一括で返済するよう求められる可能性もあります。
今後も滞りなくローンを返済できると信頼してもらうためにも、忘れずに離婚の報告を行いましょう。
離婚後、夫が住宅ローンを支払っている家に妻が住む場合でも母子手当を受け取ることはできますか?
元夫が住宅ローンを支払っている家に母子が住む場合、母子手当(児童扶養手当)は全部または一部の支給がストップする可能性があります。
母子手当の支給には、扶養義務者(この場合母である妻)の所得制限だけでなく、元夫からの養育費の8割程度が加算されます。
養育費には、生活費や教育費だけでなく、ローンや家賃など子供の監護・養育に関係あるものも含まれます。
そのため、元夫がローンを支払っている家に住んでいる場合には、元夫から援助を受けているのと等しい状態となりますので、母子手当の支給に影響が出る場合があります。
離婚後の住宅ローンの支払いと養育費を相殺することはできますか?
離婚後の住宅ローンの支払いと養育費を相殺することは可能です。
非親権者が住宅ローンを支払う家に親権者と子供が済む場合には、養育費の計算にあたり、住宅ローンの支払を考慮することができます。
養育費の代わりに非親権者が住宅ローンを支払うことを、当時者双方が合意していれば問題なく相殺することができます。
反対に、非親権者が住宅ローンの残る家にそのまま住む場合は、住宅ローンの支払いと子供の監護・養育に関わる費用に関係性がないため、住宅ローンとは別に養育費の支払いが必要です。
ただし、住宅ローンと養育費の相殺は、非親権者がローンを滞納する、住宅ローンの契約違反となる、などのトラブルになる場合もあります。
そのため、後から「言った・言わない」のトラブルを避けるためにも公正証書を作成し、書面に残しておくことが重要です。
離婚後、持ち家に非名義人の妻が住み続ける場合でも住宅ローン控除を受けられますか?
離婚時の話し合いの結果、住宅ローンの名義人である夫が家を出て、非名義人である妻が住み続けるケースも少なくありません。
しかし、このケースでは適用条件に当てはまらないため、住宅ローン控除は受けることができません。
控除要件の一部には、“新築または取得の日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること”と明記されています。
つまり、住宅ローン控除を受けるためには、名義人がその家に住んでいなければなりません。
また、婚姻期間中にペアローンで住宅ローンを組んでいた場合、離婚後も家に住み続ける名義人は住宅ローン控除を受けることができます。
一方、離婚後に家を出る名義人は住宅ローンを組んでいたとしても、要件を満たすことができないため、住宅ローン控除を受けることはできません。
離婚時に共同名義から単独名義で住宅ローンを借り換える場合、贈与税などの税金は発生しますか?
贈与税や登録免許税が発生する可能性があります。
贈与税
離婚後、共同名義から単独名義で住宅ローンを借り換える場合、家も住宅ローンの名義人の単独名義となります。
この時、家の価値と住宅ローンの残債に大きな差が生じ、家の価値が著しく高い場合には贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。
登録免許料
共有名義を単独名義に変更する際などに共有部分を取得すると、法務局で名義変更の手続きをしなければなりません。その際に、「登録免許料」がかかります。
離婚する際に住宅ローンがまだ残っている場合は弁護士にご相談ください
離婚する際に住宅ローンが残っていると、家を売却するのか、どちらが住み続けるのか、大きな問題となります。
また、双方が住み続けたいと考えている場合や、残ローンより家の評価額が低い、オーバーローンの場合には、財産分与が複雑化するケースも少なくありません。
離婚時の住宅ローンについては、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
ご相談者様の状況やご希望を丁寧にヒアリングし、最善のアドバイスをさせていただきます。
また、住宅ローンの問題だけでなく、財産分与をはじめ、他の離婚条件なども併せて相手方と交渉をし、ご相談者様が離婚後の生活を安心して送れるようにサポートいたします。
離婚時の住宅ローンについては、私たちにお気軽にお問い合わせください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)



















