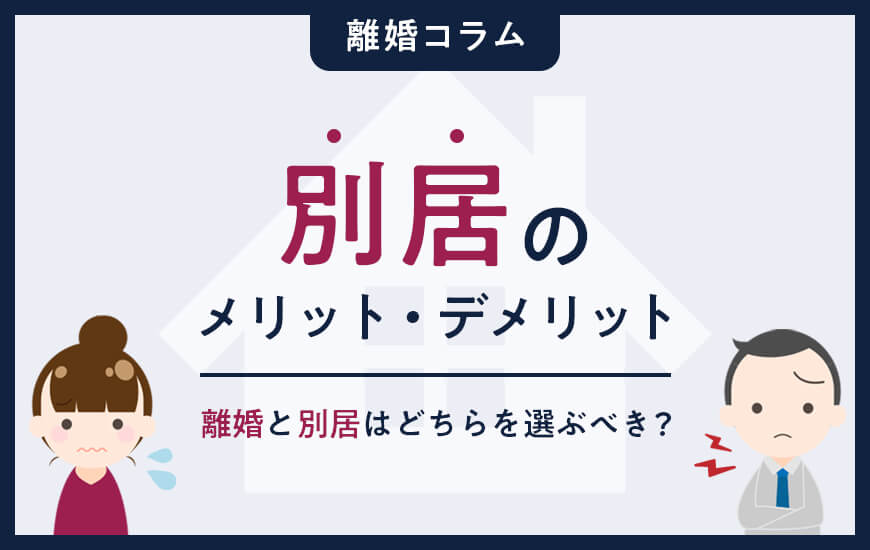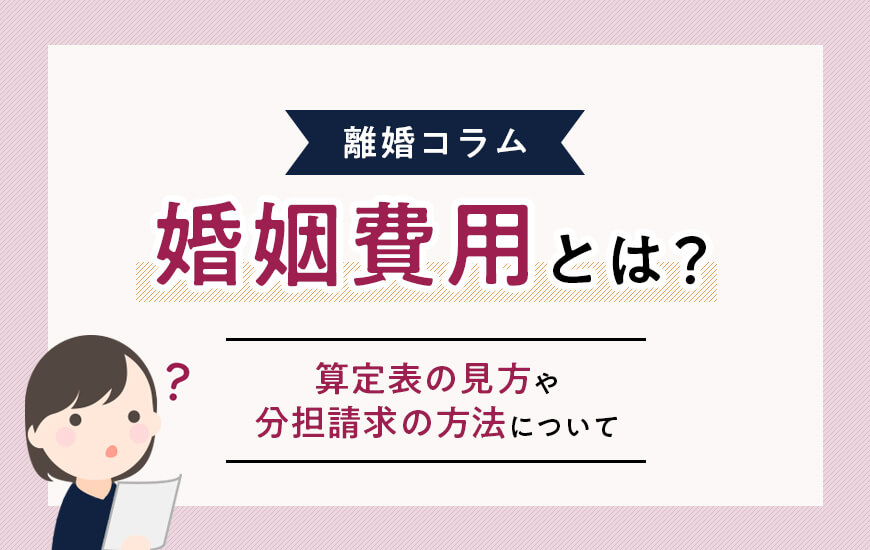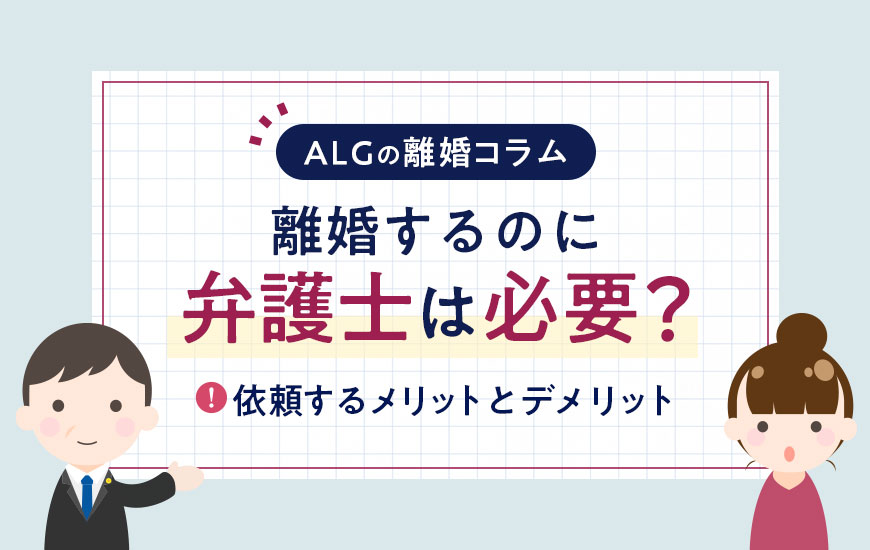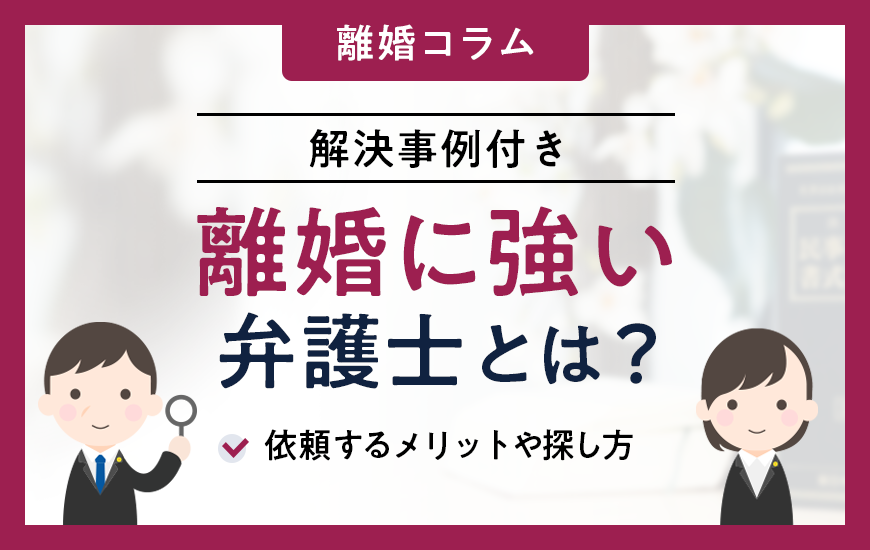【ケース別】離婚のメリット・デメリットとは?

結婚し日常生活を共に過ごしていれば、様々なトラブルや小さな不満が積み重なり「離婚したい」と思うこともあるでしょう。
しかし、衝動的に離婚話を進めてしまうのはおすすめできません。
まずは、離婚のメリット・デメリットをしっかり理解したうえで検討することが大切です。
この記事では、「男女別」、「子供がいる夫婦」、「熟年離婚の場合」に分けて離婚のメリット・デメリット、離婚を決意する前にやっておくべきことなどについて解説していきます。
目次
離婚するメリット・デメリットは?
まずは、離婚するメリット・デメリットを見ていきましょう。
離婚するメリット
-
自由に生活できる
離婚によって、家族に縛られず自由に生活できます。例えば、休日をどう過ごすか、何を買うか、何をするかといったことを自由に決められるようになります。
新しく事業を始めたり、再就職をしたりと、将来の人生設計も自由に描くことができるでしょう。 -
新たな恋や再婚ができる
離婚をすると元配偶者との婚姻関係が終了するので、誰と交際しても文句を言われることはありません。
恋をすることはもちろん、本当に分かり合える人と再婚して、新しい家庭を築くことも自由です。
離婚するデメリット
-
ひとりで生活しなければならない
離婚すれば、元配偶者と分担していたことのすべてを一人で行わなければなりません。家事や仕事も自分で担う必要があるため、精神的負担を感じる場合もあります。 -
子供に影響を及ぼす
離婚は夫婦の問題ですが、子供にも影響を与えてしまいます。
特に小さな子供は両親と一緒に暮らすことを希望することが多く、様々な場面で子供に寂しい思いをさせてしまう可能性があります。
焦って離婚をしてしまうと、あとから後悔することもありますので、ご自身のケースに合った離婚のメリット・デメリットをよく検討することが大切です。
【ケース別】離婚のメリット・デメリット
男性の場合
男性特有の離婚のメリット・デメリットには、以下のようなものが挙げられます。
男性の離婚のメリット
-
「家族のために」から解放される
これまで家族のために仕事を頑張ってきた男性にとって、離婚により家族を支えるプレッシャーから解放されることは大きなメリットとなります。
離婚後は、自分のやりたい仕事や生き方にチャレンジできるようになるでしょう。 -
お小遣い制でなくなる
婚姻期間中は、生活費が優先となるため、夫はお小遣い制というご家庭も少なくないでしょう。
しかし、離婚後はお小遣い制がなくなり、自分の裁量でお金を使えるようになる場合もあります。
男性の離婚のデメリット
女性の場合
女性特有の離婚のメリット・デメリットには、以下のようなものが挙げられます。
女性の離婚のメリット
-
自分のペースで生活できる
婚姻中は夫の帰宅時間までに家事を終わらせたり、食事を合わせたりするなど自分のペースで生活できていなかったのではないでしょうか。
離婚後は、あなたの自由な時間に、自分のペースで家事や生活ができるようになります。 -
義父母や親族、夫の友人や会社との付き合いがなくなる
結婚生活を送っていると、夫の親族や友人、会社の同僚との付き合いを求められ、ストレスとなる女性も少なくありません。
離婚をすれば他人になるので、付き合いがなくなることもメリットの一つです。
女性の離婚のデメリット
-
自分で働いて稼ぐ必要が生じる
離婚後は夫と別世帯になるため、生活費は自分で稼ぐ必要があります。特に専業主婦だった場合は、仕事を見つけることから始めなければなりません。
年齢や職歴のブランクがあると再就職が難しくなる可能性があり、離婚の大きなデメリットになるかもしれません。 -
車が使えなくなる可能性がある
これまで夫に運転を任せていた場合、離婚後は自分で運転して買い物や子供の送迎などをしなければなりません。
運転免許がない、ペーパードライバーの場合には、自家用車を利用できず不便になる可能性もあります。
子あり夫婦の場合
子供がいる夫婦は、子供のことも考えながら離婚を検討する必要があります。
以下、子あり夫婦の離婚のメリット・デメリットを見ていきましょう。
子あり夫婦の離婚のメリット
-
DVやモラハラから子供を守れる
子供が直接親からDVやモラハラを受けていたり、両親間のDVやモラハラを目の当たりにすることは、子供の健全な成長に悪影響を与えかねません。
子供のためにも、離婚をした方が良いケースもあるでしょう。 -
教育方針の違いによるストレスがなくなる
子供のしつけや習い事、進学など教育方針について意見が合わないと大きなストレスとなります。
離婚をすることで、こうしたストレスから解放され、一貫した教育方針で子供を育てられる場合もあります。
子あり夫婦の離婚のデメリット
-
子供が寂しい思いをする
親の離婚によって子供は大好きな父または母と暮らせなくなってしまうため、悲しみや不安、寂しさを感じるおそれがあります。
また、入学式や卒業式など片親の参加で子供が寂しい思いをすることもあります。 -
環境の変化により子供の心身に影響を及ぼす
“離婚に伴って苗字が変わる”、“引っ越しや転校で友達と離れ離れになる”など、離婚という親の都合で子供の環境に様々な変化が起こり、子供の心身に影響を及ぼす可能性があります。
熟年離婚の場合
高齢者の離婚、いわゆる熟年離婚は、結婚生活が長い(多くの場合で20年以上)こと、お互いに年齢を重ねていること、子育てが一段落していることなどが特徴といえます。
これらの特徴をふまえた熟年離婚のメリット・デメリットを見ていきましょう。
熟年離婚のメリット
-
ストレスのない生活を送れる
特に子供が独立していたり、夫が定年退職して家に毎日いると、夫婦生活の閉塞感も強くなります。
離婚することで、お互いがストレスなく生活ができるようになり、老後の人生を自由に生きられるようになります。 -
配偶者や義親の介護から解放される
この先、自分の親だけでなく配偶者やその親の面倒まで見るのかと不安に感じている方も多いでしょう。
離婚によって、こうした負担から解放され、自分自身の老後を安心して過ごすことができます。
熟年離婚のデメリット
-
経済的に苦しくなるおそれがある
専業主婦やパート主婦の方が熟年離婚をすると、金銭的に困窮するおそれがあります。年金分割を受けても月々の生活費として十分な金額にならないケースがほとんどです。
離婚前に必要な生活費を把握し、再就職先を探すなど対策をとっておきましょう。 -
介護を頼れる人がいない
熟年離婚をした場合、介護を頼れる人がいなくなる可能性もあります。
天涯孤独となり、老人ホームへの入居を余儀なくされる場合もあるでしょう。子供がいれば頼れるかもしれませんが、余計な負担をかけてしまう心配もあります。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
離婚を決意する前にやっておくべき5つのこと
離婚を決意する前に以下の5つのことをやっておきましょう。
- 離婚の原因を考える
- 夫婦で話し合う機会を設ける
- 別居を検討してみる
- 浮気などの証拠を集めておく
- 離婚後の金銭的負担に備える
①離婚の原因を考える
離婚したい理由を明確にし、問題点が改善可能かどうか見極めましょう。
性格の不一致であれば、相手の何が嫌なのか、なぜそれが嫌だと感じるのか、解決方法はないかを考えましょう。
離婚前にしっかりと修復の可能性を探らないと、離婚後に後悔する可能性が高まります。離婚以外に修復の方法はなかったのかと悩む方も多いですし、離婚なんてしなければよかったと自分を責めてしまう方もいます。
問題点が明らかになったら、それが改善可能なのか不可能なのか考えましょう。
改善可能であれば夫婦間で話し合ったり、カウンセリングを受けてみたりすることができます。
しかし、改善不可能であれば、我慢して生活するか離婚するかの2択となります。我慢が難しいようであれば本格的に離婚について検討することとなります。
②夫婦で話し合う機会を設ける
後悔しない離婚をするためには、夫婦でよく話し合うことが大切です。
自分は離婚したいと思っていても相手はどう思っているのかは話し合わなければ分からないものです。問題点は何なのか、夫婦関係を修復できる可能性があるのかよく話し合いましょう。
また話し合いではつい感情的になりがちですが、冷静に話し合うことを心がけましょう。
感情的になってはお互いの意見をきちんと聞くことができません。どうしても冷静に話し合えない場合は、弁護士などの第三者を間に挟むこともおすすめです。
③別居を検討してみる
いきなり離婚をするのではなく、別居をして一時的に距離を置くことで、離婚について冷静に考えることができます。
また、相手にDVやモラハラがある場合は身の安全を確保するためにすぐに別居してください。
別居のメリット・デメリットにはどのようなものがあるのかについても、あわせて見ていきましょう。
別居のメリット
-
長期の別居だと離婚が認められやすくなる
離婚裁判に至った場合に別居期間が3~5年ほど経っていると、婚姻関係が破綻しているとして、法定離婚事由の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚が認められやすくなります。
そのため、別居後、修復を考えている場合は、別居期間があまり長期に及ばないように注意しましょう。 -
相手に離婚の意思が強いことを伝え、プレッシャーを与えられる
離婚したいと申し出たにも関わらず、配偶者が本気に受け止めてくれない場合には、別居することによりこちらの離婚意思が強いことを示せるため、配偶者が真剣に受け止めるようになります。
別居のデメリット
-
夫婦関係がさらに悪化する場合がある
別居することでお互いの心が離れていってしまい、さらには別居によって配偶者の離婚意思が強まり、夫婦関係の修復が困難になってしまう場合もあります。 -
婚姻費用の支払いが生じる
別居をしても、婚姻関係にあることにかわりはないため、収入の多い方は収入の少ない方に生活費として婚姻費用を支払う必要があります。
多くの場合、男性から女性に支払われます。 -
証拠収集が難しくなる
相手が不貞行為などの有責配偶者である場合、証拠を集めることで有利に離婚することができる可能性が高まります。
しかし、別居をしてしまうと十分な証拠を集めることが難しくなるでしょう。
離婚前の別居や婚姻費用については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
④浮気などの証拠を集めておく
離婚を決意したら、次は離婚を有利に進めるために証拠を集めることが大切です。
また、相手の浮気などを理由に慰謝料を請求したいと考えている場合も同様に、証拠を集めることで相手が言い逃れできなくなり、有利に離婚を進められる可能性が高まります。
しかし、一般の方ではどのような証拠が有効であるか分からないことも多いでしょう。そのため、浮気の証拠集めは弁護士に相談することをおすすめします。
ご自身に不利にならないような証拠の集め方についてもアドバイスしてもらえるでしょう。
正当な離婚理由があることを証明するのに有効な証拠として、以下のようなものがあります。
| 離婚理由 | 証拠の例 |
|---|---|
| 不貞行為(不倫・浮気) | ・ラブホテルに入る写真・動画 ・不貞行為を認めた音声 ・メール、LINEなどのメッセージ など |
| DV・モラハラ | ・DVやモラハラを受けている音声や動画 ・医師の診断書 ・日記・メモ など |
| 悪意の遺棄 | ・生活費が振り込まれなくなったとわかる通帳の入金記録 ・相手が別のところに住んでいることが分かる資料 など |
| その他(セックスレス、借金など) | ・生活状況を表した表 ・相手の給与明細やクレジットカードの利用明細 など |
⑤離婚後の金銭的負担に備える
特に専業主婦(夫)の場合、離婚後は生活に困窮するおそれがあります。
そのため、離婚後に必要なお金・生活費について計算しておく必要があります。
特に、長年専業主婦(夫)であった方であれば、就職先も思うように見つけられない可能性もあり、離婚前から貯金や就職先を見つけておくことが大切です。
また、離婚時には下記の表にある費目を受け取ることができます。
年金分割は離婚時に受け取れるものではありませんが、将来のために必要であるため忘れず手続きするようにしましょう。
離婚時に受け取れるものの概要は下表をご覧ください。
| 離婚時にもらえるお金 | 内容 |
|---|---|
| 財産分与 | 婚姻時に夫婦が築き上げた財産を均等に分配すること |
| 慰謝料 | 離婚によって生じた精神的苦痛を慰める目的で支払われる賠償金 |
| 養育費 | 子供の監護や養育のために必要な費用 |
| 年金分割 | 婚姻期間中の厚生(共済)年金記録を当事者間で分割することができる制度 |
離婚問題を弁護士に相談・依頼するメリット
離婚について弁護士に依頼することで、さらなるメリットを得られる可能性が高まります。
離婚は相手のあることですから、必ずしも「離婚したい」と打ち明けた際にすぐに合意してもらえるものではありません。
配偶者が離婚に応じない場合は話し合いが長引き、精神的に疲弊してしまうでしょう。
その場合に弁護士が第三者として間に入ることで、冷静に話し合うことができ、離婚までスムーズに交渉を進めることが可能になります。
また、弁護士は法律の専門家であることから、財産分与や慰謝料、養育費など金銭面で揉めそうな場合に適切な金額を算出し、相手方と交渉することできます。
そのため、適正な条件で離婚できる可能性が高まります。
離婚に弁護士は必要なのかについては以下のリンクで詳しく解説しています。
ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚問題に関する弁護士法人ALGの解決事例
弁護士が離婚交渉をサポートし、有利な条件で離婚成立させた事例
事案の概要
依頼者と相手方は、結婚し同居した直後、相手方が自宅を出る形で別居を開始しました。その後、依頼者は相手方より自宅退去を求められたため、慰謝料や生活費の清算等を適切に行うために相談に来られ、当事務所に依頼されました。
担当弁護士の活動
当初、相手方は、慰謝料はおろか解決金の支払いも拒否したため、担当弁護士からの指示のもと、なぜ別居に至ったのかを説明する主張書面と清算したい生活費等の詳細を資料付きで相手方代理人へ提示しました。
解決結果
その後、交渉を続けるなかで、相手方の態度が軟化し、解決金150万円を支払うこと、生活費の清算を行うことを条件として依頼者に有利な形で協議離婚が成立しました。
300万円の不貞慰謝料を獲得し、離婚成立に至った事例
事案の概要
相手方が不貞行為を行い、その不貞行為によって依頼者が精神的に疲弊している状況でした。気持ちの整理を付けたいという思いで、当事務所に依頼されました。
担当弁護士の活動
相手方と不貞相手へ不貞慰謝料請求の訴訟提起を行いました。訴訟で相手方は以下の点を主張していました。
- 当初は不貞行為の存在を否認し、その後も不貞行為に至ったのは1回のみであるとして、継続的な不貞関係を認めなかった
- 不貞関係に至った時点ですでに依頼者と相手方の婚姻関係は破綻していた
- 依頼者が相手方へ暴力をふるった
- 慰謝料を支払う旨の念書は依頼者から脅されて書いたものであり、無効である
これらの主張に対し、弁護士は依頼者と相手方の婚姻関係の破綻や依頼者の暴力は相手方の不貞をきっかけとして生じたものであると書面で主張しました。
解決結果
その結果、相手方と不貞相手は合計300万円の慰謝料の支払い義務を負うとの内容で和解が成立しました。また、依頼者と相手方は訴訟提起前に離婚が成立しました。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
離婚のメリット・デメリットに関するよくある質問
離婚することによる税金面でのメリット・デメリットはありますか?
例えば、妻や子供が夫の社会保険に加入している場合、離婚によって夫の支払う税金が増える可能性があります。
離婚をすると、妻は夫の扶養から外れ、妻が親権を持つ場合は子供も夫の扶養から外れることになります。
そのため、扶養する家族がいないとなると「配偶者控除」や「扶養控除」といった節税の特典を受けられなくなってしまいます。
一方、離婚して親権を取得した母親や父親は母子世帯・父子世帯として要件を満たせば、所得税や住民税が軽減されるというメリットがあります。
相手が離婚に応じてくれるか不安です。拒否されたら離婚できませんか?
離婚する夫婦の多くが、協議離婚という夫婦だけでの話し合いによる方法で離婚に至っています。
しかし、協議離婚は夫婦間の合意によって成立するため、夫婦間で離婚の合意が難しいようであれば、離婚することはできません。
夫婦間で合意ができない場合は、離婚裁判を起こし、離婚ができるのか裁判官に判決を下してもらうことになりますが、裁判では、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)がなければ、離婚は認められません。
そのため、相手との離婚理由が不貞行為(浮気・不倫)やDVなどではなく、性格の不一致のみである場合は離婚が認めらない可能性があります。
裁判で離婚が認められる法定離婚事由は以下のとおりです。
- 相手に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄があった時
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚裁判では、離婚したい理由が①から⑤までの法定離婚事由のいずれかに該当しなければ離婚は認められず、離婚を求める側が、これらの離婚事由があることを具体的に主張し、有効な証拠によって証明していかなければなりません。
弁護士に依頼すれば、専門的知識が必要なこれらの主張や立証を任せることができます。
合わせて読みたい関連記事
離婚するかどうかで判断に迷ったら、一人で悩まず弁護士にご相談ください。
離婚にはメリット・デメリットがあるため、離婚するかどうかは、両者を比較して慎重に判断することが重要です。
とはいえ、離婚のメリット・デメリットは夫婦ごとに異なるため、詳しくは私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
離婚に悩んでいる方は、ご事情に沿って、離婚のメリット・デメリットを詳しく説明いたします。
また、離婚を決意された方には、離婚が有利にスムーズに進むよう尽力いたします。
離婚はなかなか周りに相談できるものではなく、ひとりで悩まれてしまう方も少なくありません。
しかし、ひとりで悩むことは精神的ストレスとなってしまいます。離婚についてのお悩みは私たちにご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)