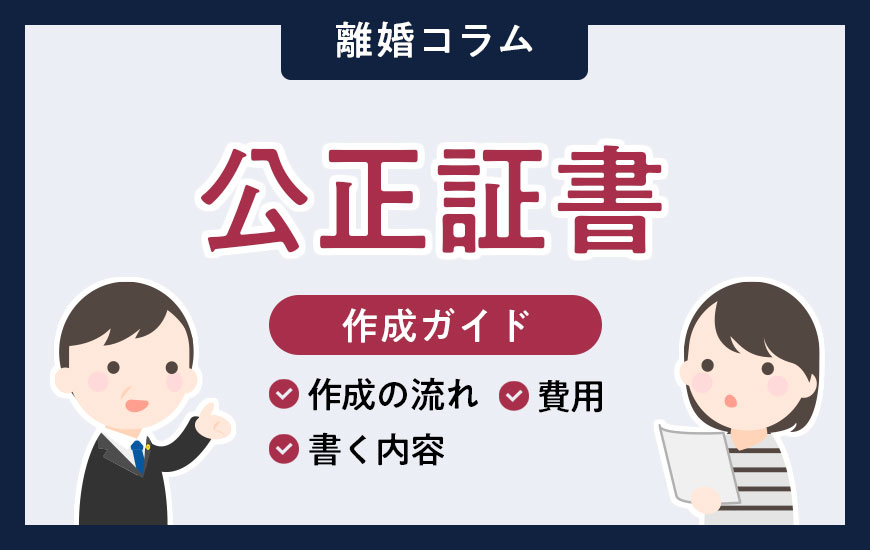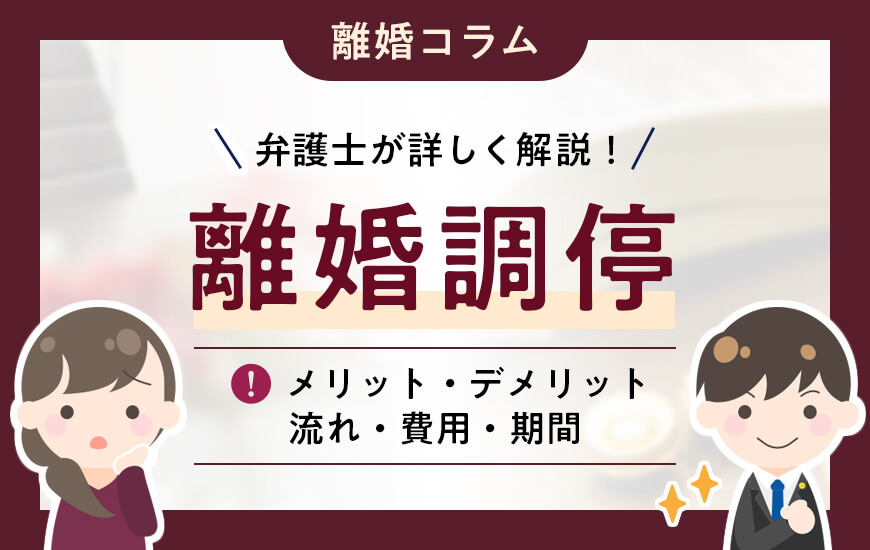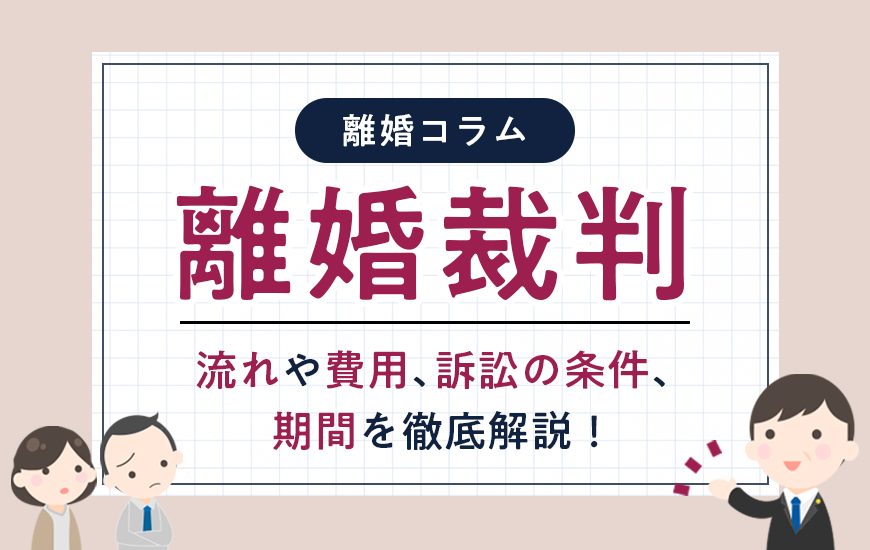離婚したらペットはどちらが引き取る?考慮される3つのポイント
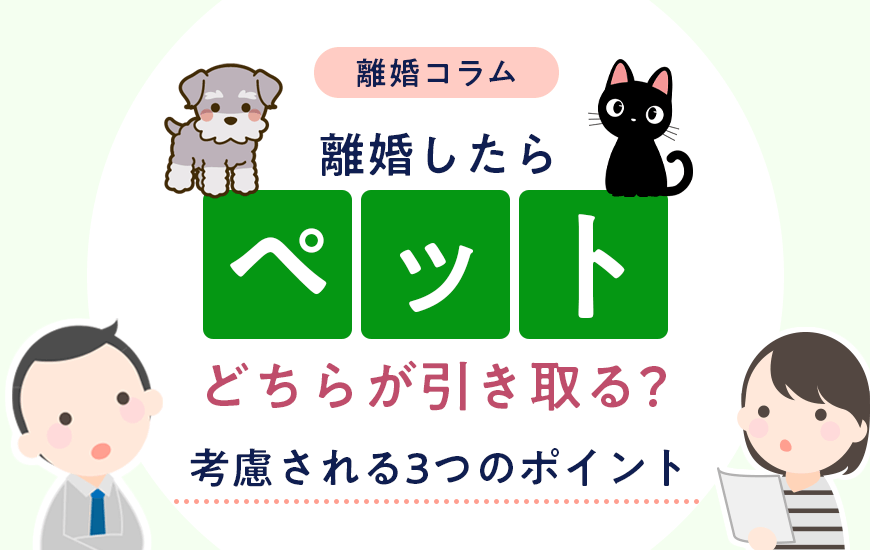
夫婦が離婚するとき、子どもがいると親権・養育費・面会交流といった条件を取り決めなければなりませんが、ペットの場合はどうすればよいのでしょうか。
家族同然の犬や猫などのペットとの別れはつらいもので、離婚するときにどちらがペットを引き取るのかでもめることがあります。
そこで本記事では、離婚したらペットはどちらが引き取るのかに着目して、ペットの所有権の取り扱いや、どちらが引き取るのかを決める際のポイントを解説していきます。
離婚後もペットと一緒に暮らしたいとお考えの方、離婚後ペットに会えなくなるかもしれないという方、ぜひ参考になさってください。
目次
離婚したらペットの所有権はどうなる?
家族同然とはいえ、日本の法律では、ペットは物(動産)として扱われます。
したがって、車や家財道具などと同様にペットの所有権は「財産分与の対象」となり、どちらが引き取るのかは財産分与のルールに則って取り決めることになります。
◆財産分与とは?
財産分与とは、離婚時に夫婦の財産を公平に分け合うことです。
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して築いた、預貯金・不動産・車・家財道具などの共有財産です。
ペットは、飼い始めたタイミングによって共有財産になるかどうかが変わります。
結婚前から飼っていたペット
結婚前から飼っていたペットは、もともと飼っていた方の特有財産となるため、財産分与の対象にはなりません。
基本的に、結婚前から飼っている方がペットを引き取ることになりますが、夫婦で話し合って離婚後のペットの引き取り親を決めることも可能です。
◆結婚前の同棲期間中に一緒に飼い始めた場合は?
同棲中に二人の資金で飼い始めたペットは、夫婦の共有財産に該当します。そのため、結婚中に飼い始めたペットと同様に、共有財産として財産分与の対象になります。
結婚中に飼い始めたペット
結婚中に飼い始めたペットは、夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。
財産分与は夫婦それぞれ2分の1ずつ分け合うのが基本ですが、ペットを物理的に分け合うことはできないので、夫婦で話し合ってどちらか一方がペットを引き取ることになります。
夫婦の話し合いで、どちらがペットを引き取るのか揉めてしまう場合は、調停や裁判でどちらが引き取るのかを決めることになります(詳細は後述します)。
離婚時のペットの財産分与で考慮される3つのポイント
子どもの親権と同様に、家族同然のペットの所有権についてもどちらが獲得するのかで揉めやすいです。
子どもの親権はどちらかといえば母親が獲得するケースが多いのですが、ペットの場合、所有権を獲得できる可能性は夫も妻も半々です。
話し合いで解決できずに家庭裁判所の離婚調停や離婚裁判で、離婚に際してペットをどちらが引き取るのか、財産分与で決めるにあたって考慮されるポイントが3つあります。
- 主にペットの世話をどちらがしていたか
- どちらに懐いているか
- 経済面など離婚後の飼育環境はどちらが整っているか
夫婦で話し合う際の参考にもなるので、この3つのポイントについて次項で詳しく解説していきましょう。
①主にペットの世話をどちらがしていたか
まずは、主にペットの世話をどちらがしていたのか(婚姻中の飼育実績)が考慮されます。
飼育実績はペットに対する愛情や飼育能力を評価する材料になります。
また、日ごろからペットの世話をしていたのであれば、離婚後も世話を怠らないという信頼感もあり、ペットも世話をしてくれる人に懐く傾向にあります。
そのため、婚姻中夫婦のどちらが世話をしていたのかが、ペットの引き取り親を決める判断材料のひとつになります。
②どちらに懐いているか
ペットが夫婦のどちらに懐いているかも考慮されます。
より懐いている方と一緒に暮らす方がペットも幸せです。
また、懐いている方が引き取り親となることで飼育放棄のリスクを回避できることからも、ペットが懐いている方が有利になります。
③経済面など離婚後の飼育環境はどちらが整っているか
経済面など、離婚後の飼育環境はどちらが整っているかも考慮されます。
子どもの養育費のように、離婚後のペットの飼育にかかる費用を支払い続ける義務はないため、引き取り親がペットを無理なく飼育できる経済力があるかどうかが判断材料になります。
また、離婚後の住まいがペット不可の住居だと飼育放棄のリスクがあることから、ペットを安心して飼育できる環境が整っているかどうかも重要視されます。
離婚時にどちらがペットを引き取るかを決める方法
離婚時にどちらがペットを引き取るかを決める方法には、夫婦間の話し合いで決める方法と、調停や裁判で決める方法があります。
離婚に関するほかの条件と同様に、まずは夫婦間でしっかり話し合います。
話し合いで解決できない場合は家庭裁判所の調停や裁判手続きを利用して、どちらがペットを引き取るかを取り決めることになります。
夫婦間の話し合い
離婚時にどちらがペットを引き取るかについて、まずは夫婦間でよく話し合って決めることが基本です。
財産分与は夫婦それぞれ2分の1ずつが基本ですが、生き物であるペットを分け合うことはできないので、話し合ってどちらが引き取るかを決めます。
話し合いのポイント
話し合いでは、
- 離婚後の経済面や飼育環境はどちらが整っているか
- どちらと暮らすことがペットの幸せか
- どちらが快適に過ごせるか
を考えることが大切です。
ペットを引き取ることをどうしても譲れない場合には、離婚後もペットと会わせることを条件にしたり、ほかの財産の取得分を少なくしたり、解決金を支払うなどして、ほかの条件で譲歩することも有効な場合があります。
取り決めた内容は公正証書に残す
夫婦間の話し合いで合意できたら、取り決めた内容はほかの離婚条件とともに離婚協議書などの書面にまとめて公正証書化しておきましょう。
公正証書化しておけば、取り決めた内容が守られなかったときに裁判を経ずに強制執行の手続きがとれるようになります。
公正証書に記載するためにペットについて決めておく内容
- どちらが引き取り親になるのか
- 離婚後の面会交流(頻度、方法、場所、待ち合わせ方法など)
- 離婚後の飼育費用(分担する金額、支払期間、支払方法、支払期限など)
- 取り決めた内容が守られなかったときの対処法 など
以下ページで、公正証書化するメリットや公正証書の作成方法について解説していますので、あわせてご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
話し合いがまとまらない場合は調停や裁判
夫婦間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の離婚調停手続きを利用して解決をはかります。
調停でも解決できない場合、最終的には離婚裁判で、どちらがペットの引き取り親にふさわしいのかを決定してもらうことになります。
| 離婚調停 | 離婚調停とは、離婚の可否や条件について、家庭裁判所で調停委員を介して話し合う手続きのことをいいます。 調停では、自分がペットの引き取り親にふさわしいことを調停委員に主張していくことが重要になります。 |
|---|---|
| 離婚裁判 | 離婚裁判とは、話し合いや調停で問題が解決しなかった場合に、裁判所の判決によって強制的に離婚の可否や条件を決定する手続きのことをいいます。 裁判では、自分がペットの引き取り親にふさわしいことを、証拠に基づき立証していくことが重要になります。 |
離婚調停や離婚裁判の手続きについては、以下ページで詳しく解説していますのであわせてご参考ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
引き取り親にならない場合は離婚後ペットに会えない?
引き取り親にならない場合でも、離婚後ペットに会える可能性はあります。
ただし、ペットの場合は子どもの面会交流を定めるような法律の規定はないため、夫婦間で話し合って離婚後の交流方法について取り決めておく必要があります。
離婚後どのくらいの頻度で会うのか、交流方法や場所、そして合意した内容が守られなかったときのペナルティなど、具体的な内容を取り決めておき、合意内容は書面にまとめて公正証書化しておきましょう。
離婚時にペットを引き取ったら養育費を請求できる?
離婚後のペットの養育費については、法律上の請求権は認められていないため、請求できないのが一般的です。
子どもの養育費については、親に未成年の子どもに対する扶養義務があることから離婚後も養育費を支払わなければなりませんが、ペットの場合は引き取る親が飼育費用を負担すべきものと考えられています。
もっとも、夫婦間で話し合って合意できれば、「離婚後も定期的にペットに合わせることを条件に飼育費用の一部を月々支払う」などと取り決めることも可能です。
金額や支払方法・期限を明確にして公正証書化した書面を作成しておけば、飼育費用の支払いが滞った場合に強制執行の手続きがとれて安心です。
離婚時にペットの連れ去りがあった場合の対処法は?
離婚が成立する前にペットが連れ去られてしまった場合、基本的には夫婦間で話し合って解決します。
結婚後に飼い始めたペットであれば夫婦の共有財産になるため、話し合いによって解決できない場合は調停や裁判の手続きを利用して、ペットの所有権を争うことになります。
このとき、連れ去られた後の飼育実績に問題ないと判断されると、ご自身が不利になる可能性があるため、早めに離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
なお、結婚前にご自身が飼っていたペットを連れ去れた場合や、ご自身を引き取り親として合意した後にペットを連れ去られた場合は、ペットの所有権はご自身にあるため、裁判で返還を求めたり、強制執行手続きをとったりする方法が考えられます。
離婚後のペットの引き取りについて不安がある場合は弁護士にご相談ください
離婚しても家族同然のペットと離れたくなくて、「自分がペットを引き取りたい!」と考えるのは無理もありません。
とはいえ、相手も同じように考えていて、なかなか話し合いがまとまらない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人ALGには、離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。
数々の経験を活かし、ペットの所有権を獲得するためのアドバイスをはじめ、相手の方との交渉や裁判所の手続きなど、幅広いサポートが可能です。
ご相談者様が大切なペットと一緒に幸せな再スタートができるよう尽力いたしますので、まずはお気軽に私たちにご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)