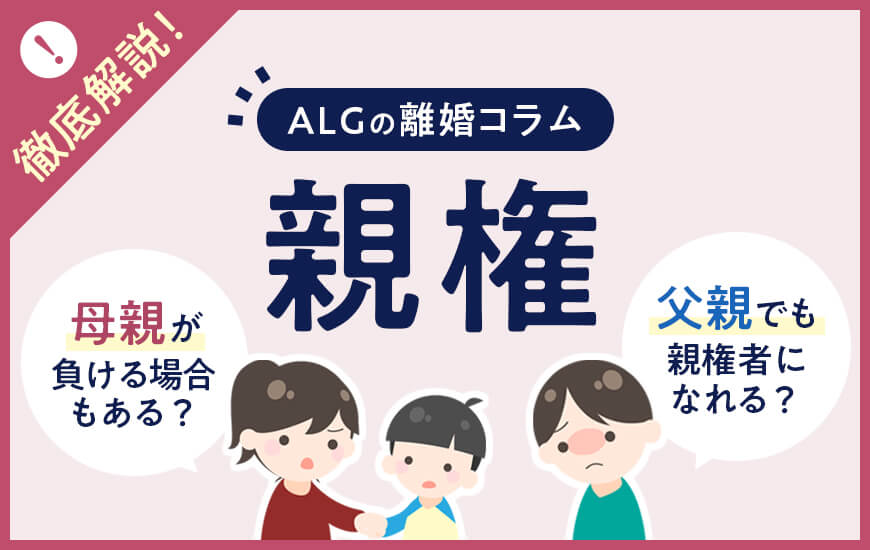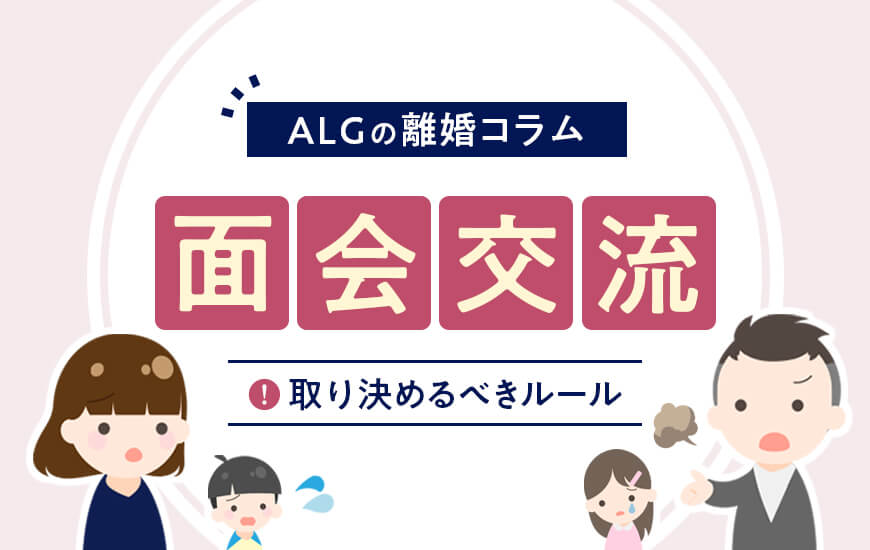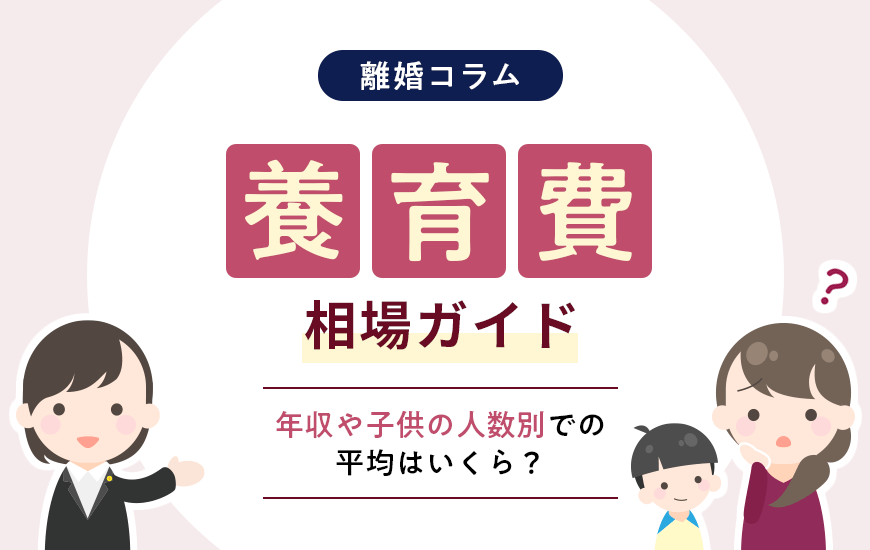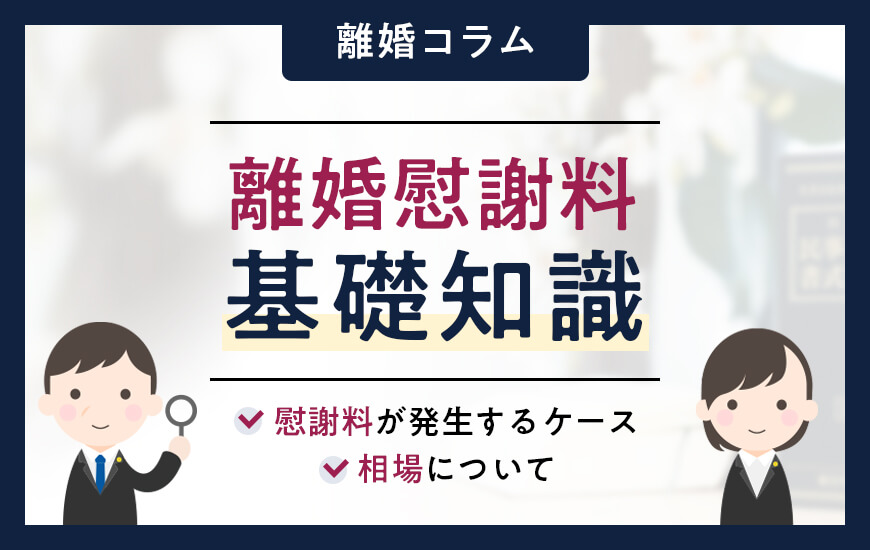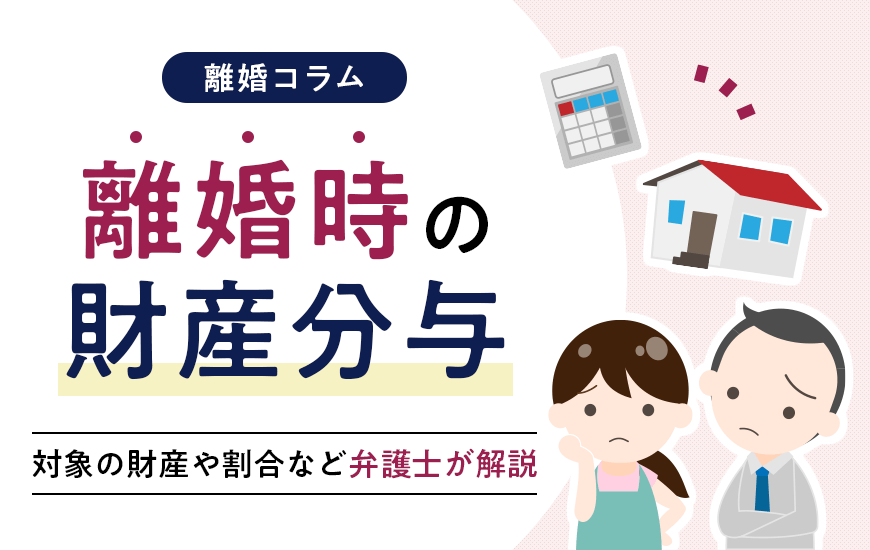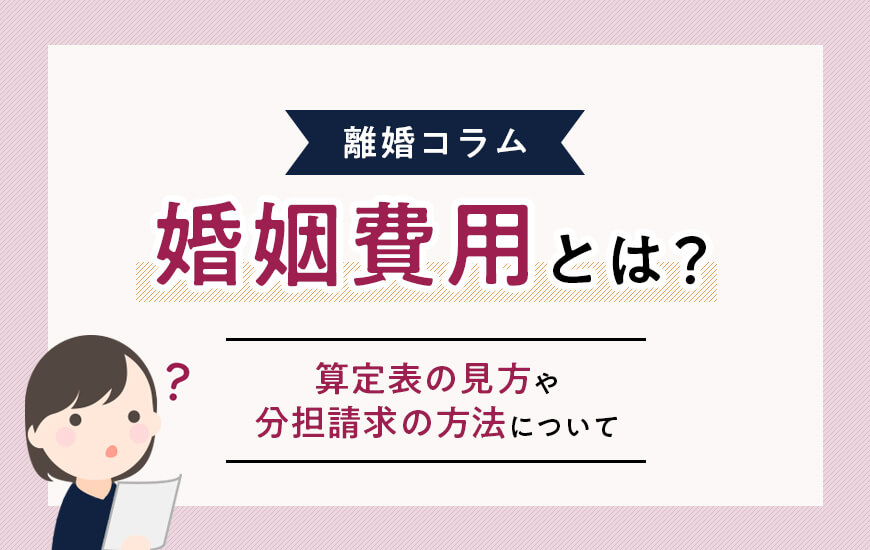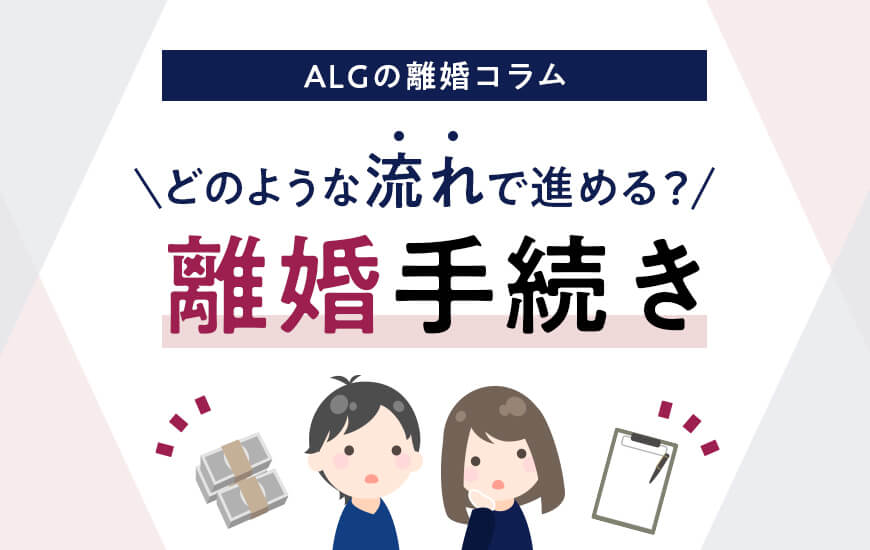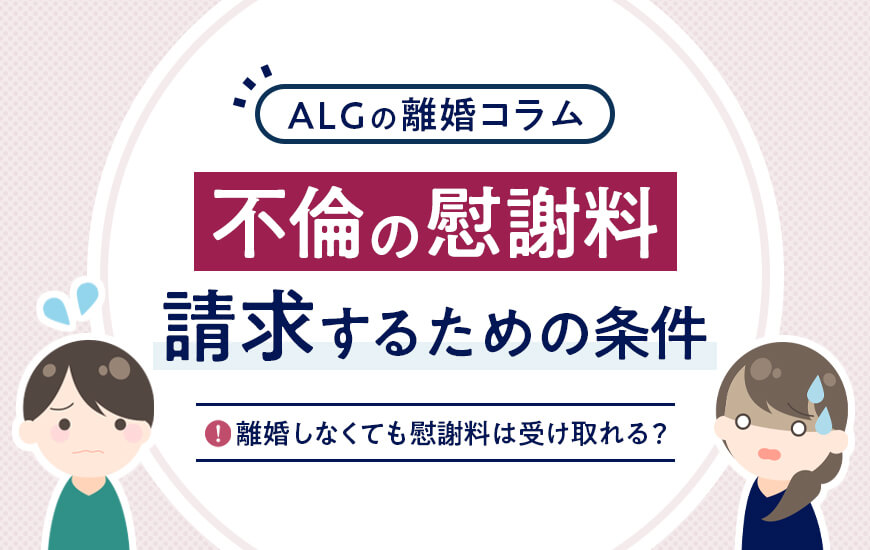妊娠中だけど離婚…?子供の戸籍・親権・養育費や慰謝料はどうなる?
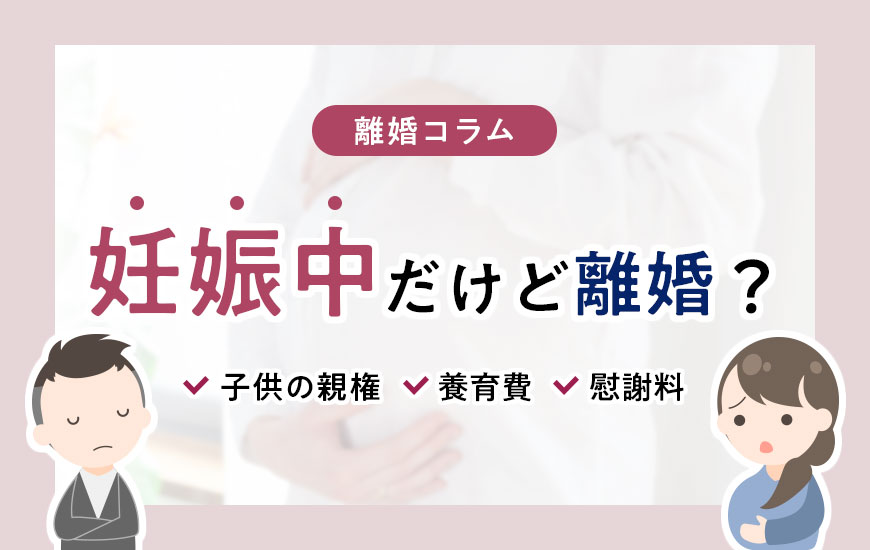
マタニティブルーという言葉があるように、妊娠中はホルモンバランスの影響で精神的に不安定となり、夫婦にすれ違いが生じやすくなります。
その結果、未来への不安や配偶者への不満が募り、妊娠中に妻から、あるいは夫から離婚を切り出されるケースも少なくありません。
妊娠中でも離婚することは可能です。もっとも、妊娠中の離婚はリスクが多いので、生まれてくる子供のことやお金のことなど、慎重に検討しなければなりません。
本記事では、妊娠中に離婚した場合、子供の戸籍や親権はどうなるのか、養育費や慰謝料の条件はどのように決めるのかを詳しく解説していきます。
妊娠中に離婚を検討されている方の参考になれば幸いです。
目次
妊娠中でも離婚はできる?
法律で制限されていないので、妊娠中でも離婚することは可能です。
もっとも、妊娠中は精神的に不安定になることが多いので、後になって離婚を後悔しないためにも、相手に離婚を切り出す前に離婚したい理由を明確にしておくことが大切です。
<妊娠中に離婚を考える妻の理由・原因>
- 妊娠中に何もしてくれない旦那にイライラする
- 妊娠中旦那が頻繁に飲み会や遊びに行くなど配慮がない
- 妊娠による心身の不調を受け入れてもらえない
- いつまでも父親になる自覚のない夫に不安を感じる
- 妊娠中に不倫・浮気をされた
<妊娠中に離婚を考える夫の理由・原因>
- 妊娠の影響による妻の変化が受け入れられない
- 父親になることへの重圧に耐えられない
- スキンシップの減少やセックスレスが不満
- 不倫・浮気の相手との関係を続けたい
- 妻の浮気が発覚して、お腹の中の子供が自分の子供ではないことが分かった
妊娠中に離婚するリスク
妊娠中の離婚はリスクも多いので、健康面に配慮しながら離婚の手続きを進める必要があります。
以下、妊娠中の離婚のリスクについても確認しておきましょう。
- 子育てしながら働ける就職先が少ない
- 子供の預け先を見つけるのが難しい
- 経済的に困窮してしまうおそれがある
- 調停や裁判に発展した場合、心身ともに大きな負担がかかる
妊娠中に離婚すると子供の戸籍はどうなる?
妊娠中に離婚すると、子供が離婚してから300日以内に産まれたかどうかで対応が変わります。以下では離婚後300日以内に産まれた場合とそうでない場合に分けて解説していきます。
①離婚後300日以内に出産した場合
この場合は、元夫の子供として推定されるとして(嫡出推定)結婚している夫婦同様に嫡出子として元夫の戸籍に記載されます。その後母親は、子供を自分の戸籍に移して母親の氏を名乗らせることができます。妊娠中の離婚では基本的にこのケースとなります。
②離婚後300日経過後に出産した場合
離婚から300日を経過して産まれた子供は「非嫡出子」として母親の戸籍に入ります。非嫡出子とは婚姻関係のない男女の間に産まれた子供のことをいいます。
子供を母親の戸籍に入れたい場合
子供を母親の戸籍に入れたい場合には以下のような手続きをします。
①離婚後役所で母親が筆頭者となる新しい戸籍を作る
②家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判申立」を行う
【必要書類】
- 申立書
- 子供1人につき収入印紙800円、82円切手
- 子供の戸籍謄本
- これから入籍しようとする親の戸籍謄本
- 印鑑
③市区町村へ「入籍届」を提出
【必要書類】
- 子供1人につき入籍届1枚
- 家庭裁判所が発行する「子の氏の変更許可審判申立」
- 戸籍謄本(本籍地の場合は省略可)
- 印鑑
離婚後すぐに再婚を考えている場合
令和6年4月1日の民法改正後、離婚後300日以内に再婚・出産した場合は、再婚した夫の子供と推定されるようになったため、再婚した夫の戸籍に記載されます。
これに伴って女性の再婚禁止期間も廃止され、女性でも離婚後すぐに再婚できるようになりました。
民法改正前の再婚・出産
民法改正前は、「離婚後300日以内に産まれた子供は元夫の子供」と推定されるなかで、「婚姻後200日経過後に産まれた子供は現夫の子供」と推定されるため、推定期間の重複を避ける目的で、女性に対して「離婚後の再婚禁止期間は100日」と定められていました。
父親と子供の親子関係を否定したい場合
妊娠中に離婚し、母親が再婚しないまま離婚後300日以内に産まれた子供は、実際に血縁関係があるかどうかを問わず、元夫の子供と嫡出推定され、元夫の戸籍に記載されてしまいます。
「妻が浮気していて自分の子供ではない」など、父親と子供の戸籍上の親子関係を否定したい場合は、嫡出否認の手続きが必要です。
嫡出否認
嫡出推定される父子関係を否定するためには、家庭裁判所に嫡出否認調停を申し立てる必要があります。
令和6年4月1日の民法改正により、次のとおり申立人や期間が変更されました。
- 申し立てられる人の範囲が父親に限らず、子供および母親にも拡大された
- 申し立てられる期間が、1年から3年に伸長された
| 申立人 | 申立期間 |
|---|---|
| 父親 | 子供の出生を知ったときから3年 |
| 元夫 | |
| 子供 | 子供の出生のときから3年 |
| 母親 |
<客観的に血縁上の親子関係がないことが明らかな場合>
懐胎した時期に夫が海外赴任していたり別居していたりして、客観的に血縁上の親子関係がないことが明らか(嫡出推定が及ばない)な場合、戸籍上の父子関係を否定するためには、家庭裁判所に親子関係不存在確認調停を申し立てる必要があります。
妊娠中に離婚したら親権はどちらが持つのか?
妊娠中に離婚した場合、原則として産まれてくる子供の親権は母親となります。
ただし、離婚後300日以内に産まれた場合には、協議や調停で双方が合意すれば父親を親権者とすることも可能です。
しかし、子供の年齢が小さいうちは「母性優先の原則」によって、母親に親権が認められやすくなるでしょう。
離婚の親権については以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
生まれた子供との面会交流は必要?
面会交流とは、離れて暮らす親と子供が定期的・継続的に交流することです。
面会交流は子供が健全に成長するために欠かせず、子供のための権利でもあることから、親権者が「子供と面会させたくない」と思っても、戸籍上の親子である限りは正当な理由なく拒否することはできません。
ただし、面会交流が認められない例として以下のようなものが挙げられます。
- 子供が自分の意見をしっかりと述べられる年齢で、面会交流を拒否している場合
- 子供に虐待をする恐れがある場合
- 子供に精神的負担が生じる場合
面会交流については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
妊娠中に離婚した場合に請求できるお金とは?
妊娠中に離婚する場合、妊娠中や出産後は収入を得る手段が限られるため経済的に困窮するおそれがあります。
そこで、離婚後に経済面で困らないように、「妊娠中に離婚した場合に請求できるお金」を紹介していきます。
養育費
養育費とは、子供を監護・教育するために必要な費用のことです。
養育費の金額は、裁判所が発表している養育費算定表を参考にして決定することが一般的です。
母親が再婚せずに離婚後300日以内に産まれた子供は元夫の子供と推定されるため、元夫に対して養育費を請求することができます。
養育費の金額や支払期間、支払方法について、元夫と話し合って取り決めておきましょう。
母親が再婚せずに離婚後300日以降に産まれた子供の場合
母親が再婚せずに離婚後300日以降に産まれた子供は、元夫の子供と推定されない非嫡出子となるため、元夫に養育費を請求するためには、元夫に認知してもらう必要があります。
母親が再婚した後に産まれた子供の場合
母親が再婚した後に産まれた子供は、再婚した夫の子供と推定されるため、元夫に養育費を請求することは基本的にできません。
養育費については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
慰謝料
慰謝料とは、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛に対する金銭的な補償のことです。
離婚の慰謝料は、婚姻期間の長さや不法行為の悪質性などのさまざまな事情によって金額が異なりますが、200万~300万円程度が相場といわれています。
単に妊娠中に離婚したというだけでは慰謝料は請求できない
離婚の慰謝料が請求できるのは、配偶者の不貞行為や、DV・モラハラなどの不法行為が認められるケースに限られます。
配偶者の不法行為が原因で妊娠中に離婚する場合は、離婚後の生活資金を確保するためにも、証拠を集めたうえで慰謝料を請求しましょう。
離婚の慰謝料については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が築いてきた財産を、離婚時に原則として2分の1ずつ分け合うことです。
離婚時に妊娠していても財産分与を受けられることに変わりはないで、忘れないようにしましょう。
離婚の財産分与については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚後の生活費
離婚後のご自身の生活費は、元夫に請求することができません。
法律上、夫婦は生活費(婚姻費用)を分担する義務を負っていますが、これは婚姻中に限られます。
離婚前の別居段階であれば生活費を請求できますが、離婚してしまうと生活費を分担する義務はなくなります。
離婚後の子供の生活費については“養育費”として戸籍上の父親(元夫)に請求することができますが、ご自身の生活費は請求が認められないことが多いので注意が必要です。
もっとも、離婚後の生活費を財産分与として受け取れる可能性があるので(扶養的財産分与)、まずは夫婦でよく話し合ってみましょう。
婚姻費用については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
出産費用を元夫に請求できるか?
出産費用を元夫に請求できるかについては、出産費用をいつ請求するかによって変わってきます。
夫婦間にはお互いを扶養する義務があります。この扶養義務を根拠に、離婚前の婚姻期間中であれば、妊娠中の通院費や入院費なども婚姻費用として請求できます。
しかし、離婚が成立すると婚姻費用の分担義務がなくなってしまうので、出産費用を元夫に請求するのは難しいでしょう。もっとも、相手が任意に出産費用を払ってくれる可能性もありますので、まずは一度請求してみるのも良いかもしれません。
シングルマザーが受けられる公的支援
シングルマザーが受けられる公的支援は以下のようなものがあります。
【児童扶養手当】
国が支給を行っている制度で、母子家庭及び父子家庭を対象としています。母子家庭や父子家庭になった原因は離婚でも死別でも理由は問われません。
- 支給対象者…0~18歳に達して最初の3月31日までの間の年齢の子供
- 支給金額…扶養人数や所得によって支給金額が異なります。支給区分は、「全額支給」「一部支給」「不支給」の3区分に分けられています。
【ひとり親の医療費助成制度】
母子(父子)家庭を対象に、世帯の保護者や子供が病院で診察を受けた際の自己負担分を居住する市区町村が助成する制度です。
- 支給対象者…母子(父子)家庭で、0~18歳に到達して3月31日までの年齢の子供
- 支給金額…保険医療費の自己負担額の一部を市区町村が負担してくれます。
【生活保護】
何らかの理由で困っている人に対し、国が必要な保護をして最低限度の生活を保障しながら、本人が自立することを目的とした制度です。
- 支給対象者…生活保護を受けるには4つの条件があります。
- 援助してくれる身内や肉親がいない
- 資産を一切持っていない
- やむを得ない理由で働けない
- 月の収入が月の最低生活費を下回り、上記1~3を満たしている
- 支給金額…厚生労働省が定めた計算式があります。
その他にも市区町村ごとに母子(父子)家庭が受けられる制度があります。ホームページなどで調べておきましょう。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
妊娠中に離婚する方法と流れ
妊娠中に離婚する方法は、夫婦の話し合い(協議)による方法と、裁判所の手続き(調停・裁判)を利用する方法があって、一般的には次のような流れで手続きを行います。
健康面に配慮しながら、必要に応じて別居するなどして手続きを進めましょう。
- 夫婦の話し合い(協議離婚)
まずは夫婦で離婚や離婚条件について話し合います。
双方が合意できたら離婚協議書を作成して公正証書化しておきましょう。
役場に離婚届を提出すれば協議離婚が成立します。 - 協議がまとまらなければ調停離婚
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用します。
調停委員を介した話し合いで双方が合意できれば、“調停調書”が作成されて調停離婚が成立します。 - 調停が成立しなければ裁判離婚
調停が成立しなければ、裁判を起こします。
双方の主張や提出された証拠をもとに、離婚の可否や条件について裁判所が最終的な判決を下します。
離婚の手続きについては以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
妊娠中の離婚に関するQ&A
妊娠中に夫から離婚したいと言われました。夫に慰謝料を請求できますか?
妊娠中であっても、ただ「離婚したい」と言われたことに対する慰謝料の請求は難しいでしょう。しかし、もし夫が不倫・DVなどの不貞行為があり、離婚を切り出された場合は慰謝料を請求できます。
その場合には証拠が何より大事となります。不倫であれば、メールや写真、動画、浮気の自白の録音などが証拠になります。DVであれば、怪我の写真やDVのあった記録、診断書が有効でしょう。
不倫の慰謝料については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
現在2人目を妊娠中です。子供ごとに親権者を分けることはできますか?
父母が合意できていれば、兄弟姉妹をそれぞれ別の親権者に定めることは可能です。
しかし、裁判所の考えでは「兄弟(姉妹)不分離の原則」により、兄弟(姉妹)は離さず一緒に育てる方が子供にとって利益があり好ましいと考えています。兄弟(姉妹)で同じ環境で感情を共有し、喧嘩をしたり、仲直りしたりすることで社会性も育まれることでしょう。
そのため、一般的には子の利益を守るためには、「兄弟(姉妹)不分離の原則」が適用されることが多いでしょう。
離婚の親権については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
中絶を理由に離婚する場合、夫への慰謝料請求は可能ですか?
以下のような理由がある場合は夫へ慰謝料を請求できます。
- 中絶を強要した場合
- 避妊していると嘘をついた場合
- 強姦された場合
- 中絶の際に夫の協力がなかった場合
このような事情が合った場合の慰謝料の相場は100~200万円程度でしょう。その他にも不貞行為やDVがあり、証拠がある場合は慰謝料が増額される可能性もあります。
しかし、上記のような理由がなく、夫婦が合意の上で性交渉を行い妊娠した場合の中絶では、双方に責任があると言えるので不法行為になりません。そのため、慰謝料は発生しないと考えられます。
妊娠中の離婚は弁護士にご相談ください。あなたとお子様の未来のためにサポートします。
妊娠中の精神的な不安定さから、夫婦ともに「離婚」が頭をよぎることもあるでしょう。 妊娠中、離婚について迷われている方は、結論を出す前に弁護士へ相談してみることをおすすめします。
弁護士に相談することで、離婚したい気持ちが一過性のものかどうか明確になりますし、最善の条件で離婚できるようアドバイスが受けられます。
また、離婚を決意された場合には、心身ともに負担の大きい離婚の手続きを弁護士へ一任することもできるので、不安な気持ちを長引かせないためにも、まずは弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。
生まれてくるお子様やご自身にとって最良の選択ができるように、弁護士が全力でサポートいたします。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)