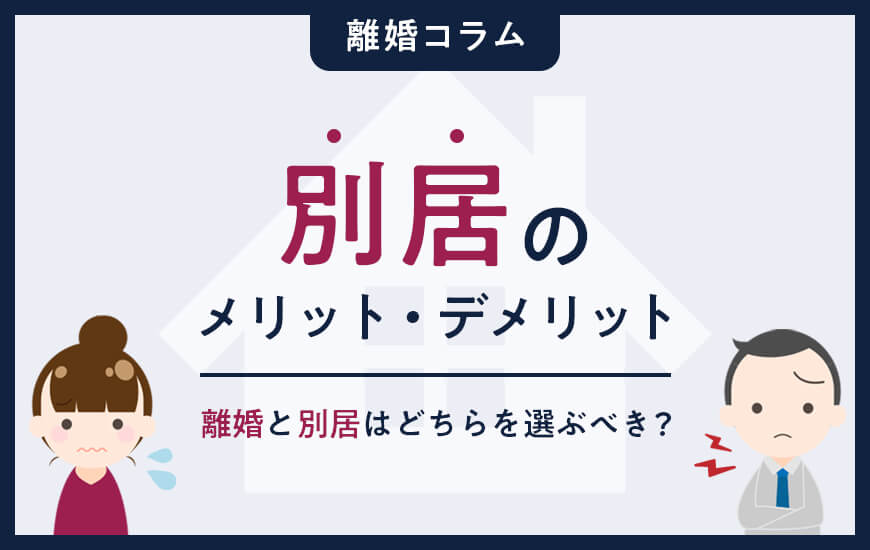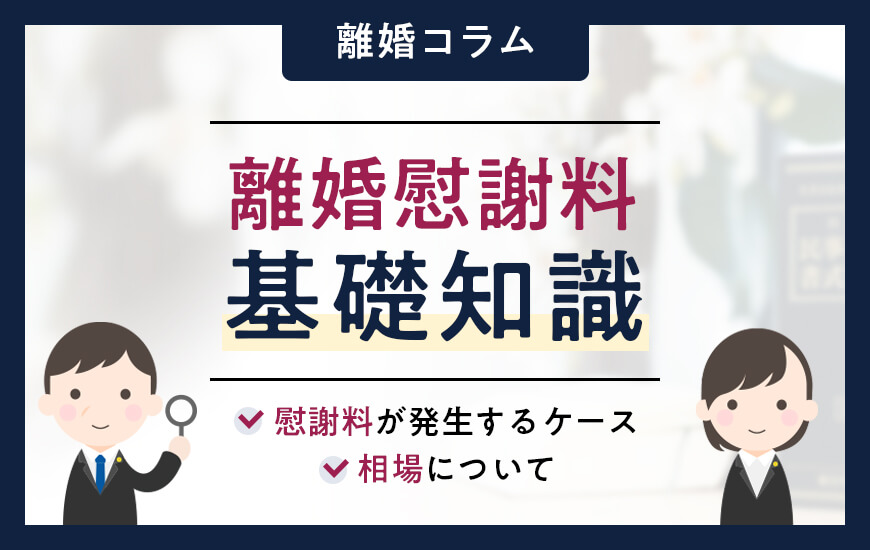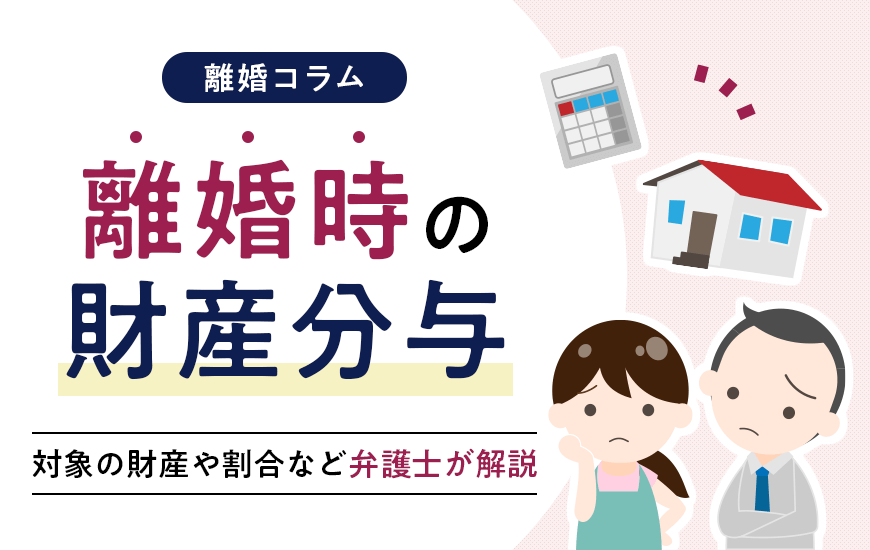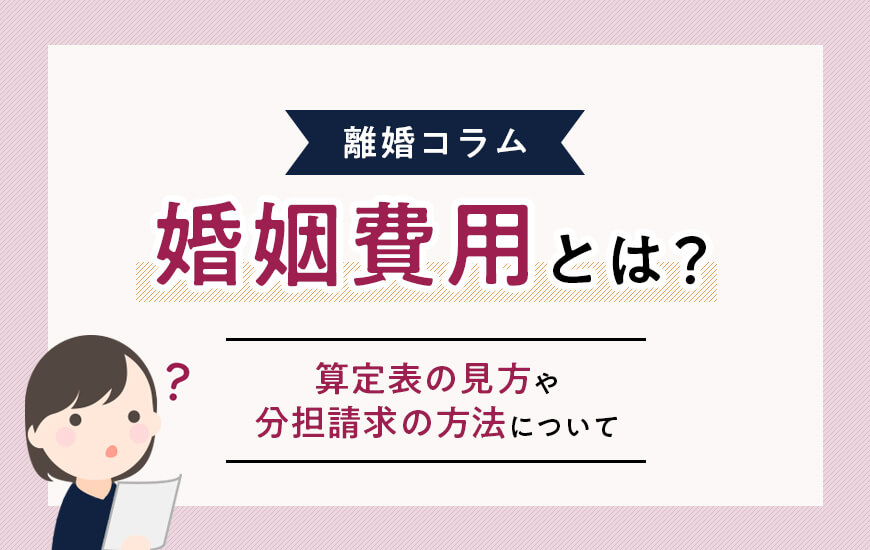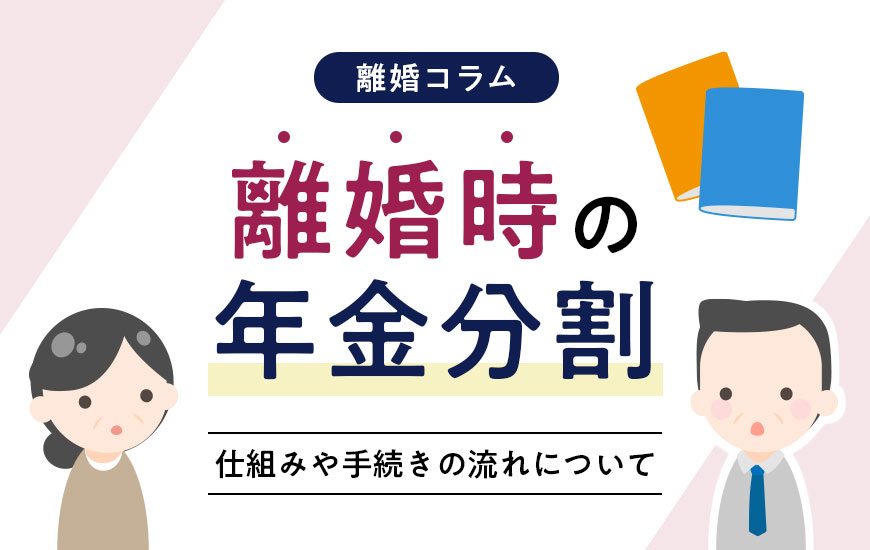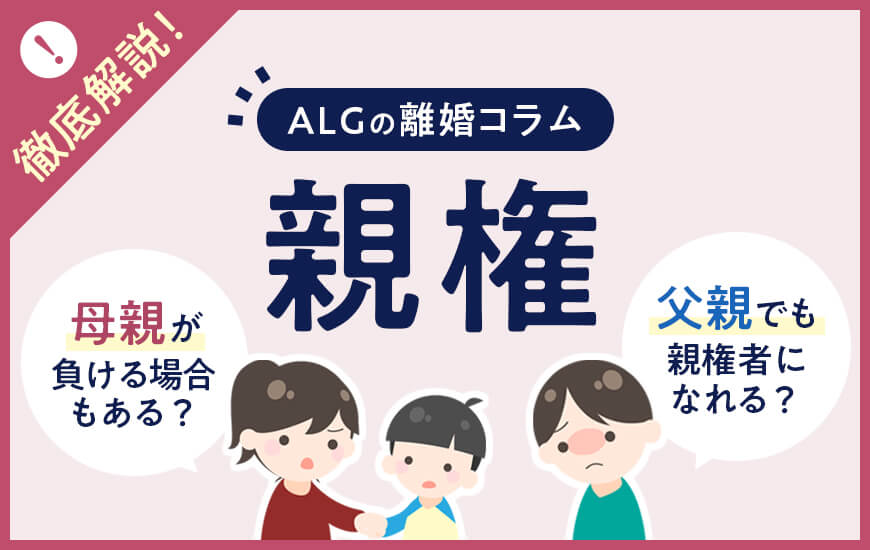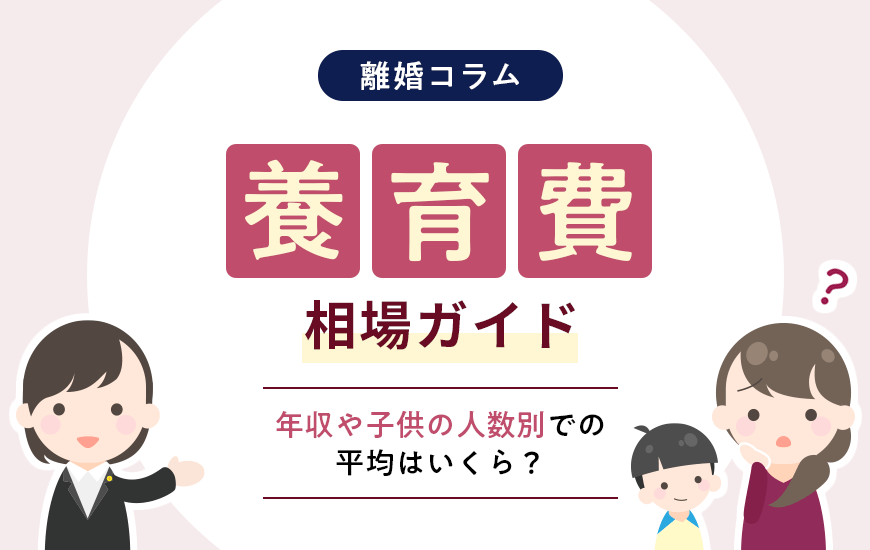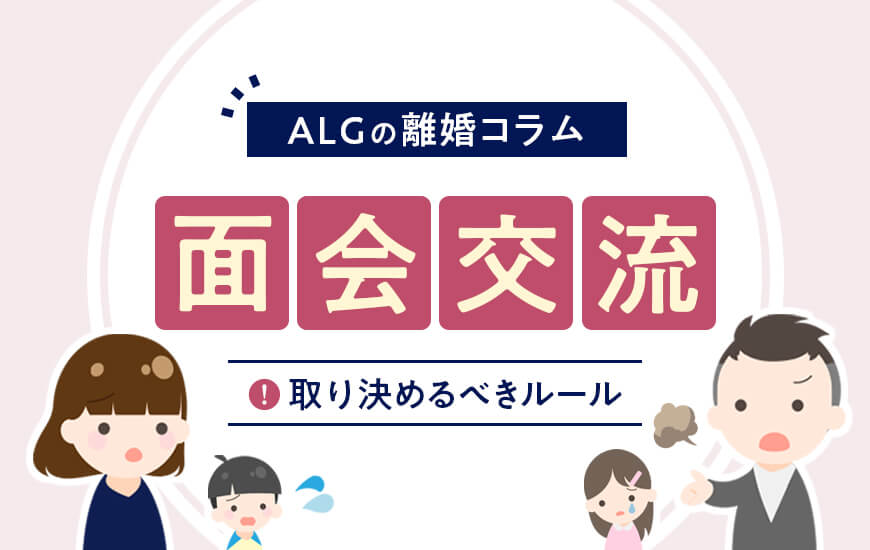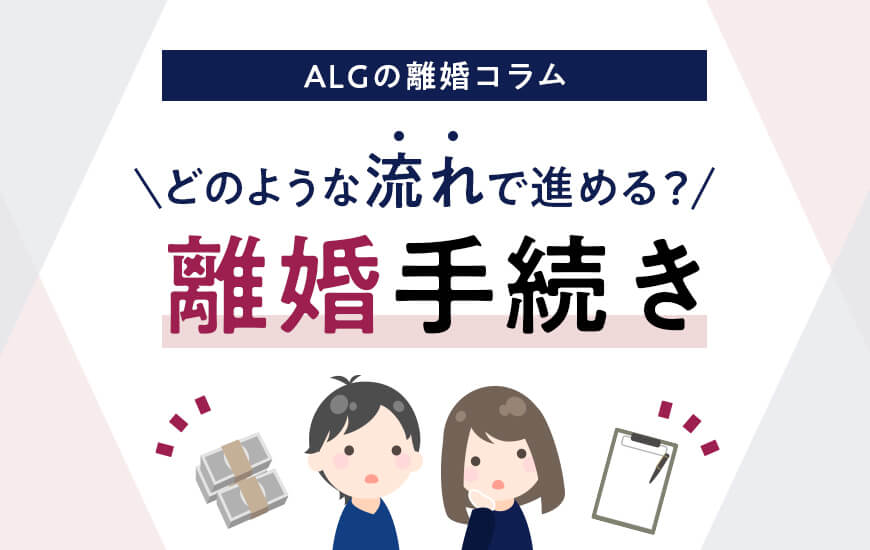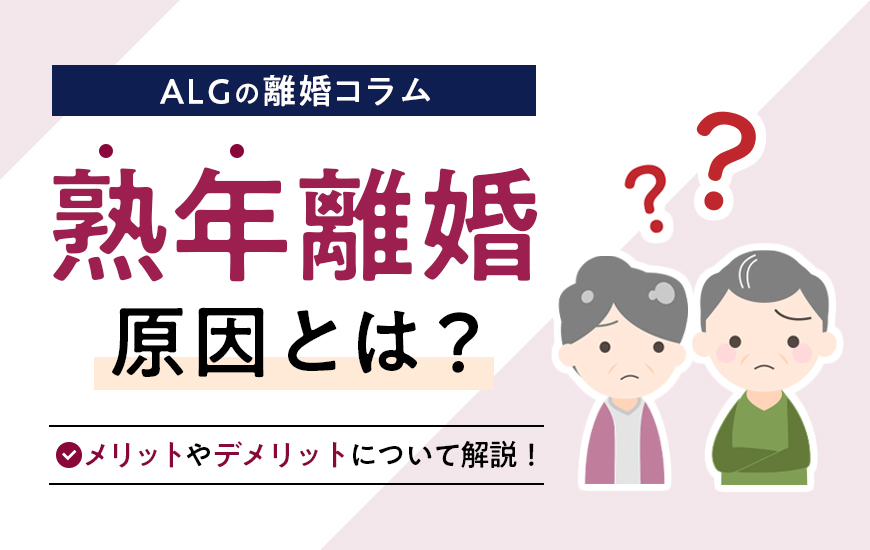【弁護士監修】離婚前の準備ですることリスト【7選】
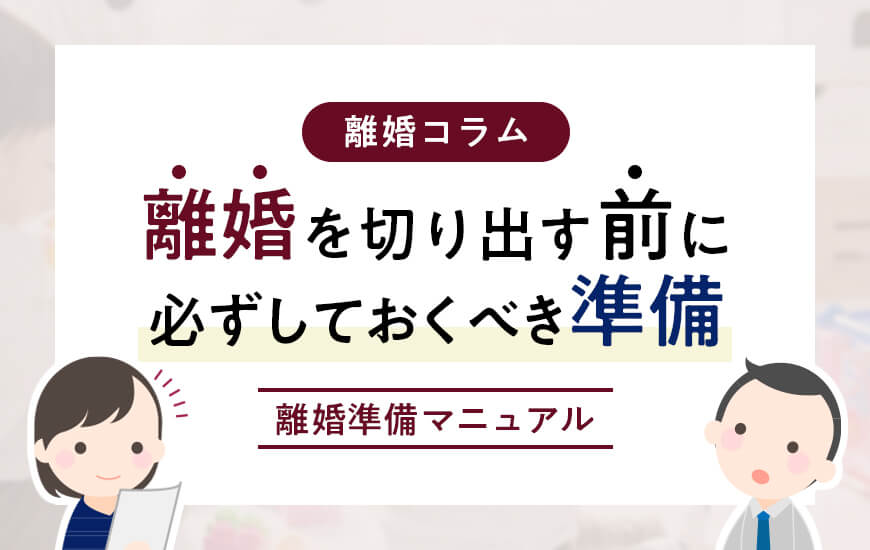
離婚を検討されている場合は、事前に準備をしてから離婚を切り出すことが大切です。
「離婚に準備があるの?」と疑問に思われるかもしれませんが、離婚時には子供のことやお金のことなど、様々なことを決める必要があります。
また、場合によっては弁護士に相談することで離婚交渉がスムーズかつ有利に進む可能性もあります。
離婚後に後悔しないためにも、離婚の準備について理解を深めておきましょう。
この記事では、離婚前に準備することをリスト化して詳しく解説していきます。ぜひご参考ください。
目次
前準備をせずに離婚するリスク
前準備をせずに、離婚を切り出してしまうと、不利な条件で離婚してしまう可能性や、最悪の場合、離婚後、経済的に困窮してしまう可能性があります。
こうしたリスクを防ぐためにも、まずは一度「本当に離婚したいのか」を考え直す時間を取りましょう。
ご自身と向き合ってもなお、離婚したいと思う場合には、離婚の準備を進めます。
具体的にどのような準備をすればいいのか、次で詳しく解説していきます。
離婚前に準備することリスト
離婚前に準備することは以下のとおりです。
- 離婚後の生活設計を考える
- 離婚理由を整理する
- 離婚の原因となる証拠を用意する
- 離婚条件を考える
- 離婚後の子供のための準備をする
- 精神的な自立を目指す
- 離婚に強い弁護士に相談する
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
①離婚後の生活設計を考える
離婚後には、経済的な自立が必要です。特に専業主婦やパート社員は仕事での収入が少なく、離婚後の経済面で困る場面が多くあります。
女性の場合、男性より収入が少ないことで、離婚後の経済面で不安を抱える方も多くいらっしゃいます。その場合には以下の準備をしておきましょう。
準備しておくこと
- 仕事の確保
安定した仕事の確保、早めに求職活動を始める、資格取得などのスキルアップを目指す - 公的扶助の検討
児童扶養手当、児童手当、就学援助などを調べておく - 住まいの確保
早めに住居を確保する、実家に住むことも検討する
離婚する際に必要なお金
離婚する際に転居する場合は、引っ越し費用、敷金礼金、家賃、当面の生活費などが必要です。
そこで、離婚する際に必要なお金が100万円ほどかかると考えて、あらかじめ準備しておけば心に余裕が生まれます。
100万円を貯めることは簡単なことではないですが、離婚前から貯金しておくことをおすすめします。このお金は配偶者に気付かれないように準備しましょう。必ずあなた名義の通帳で用意してください。
また、離婚の話し合いが調停や裁判に移行した場合にはその分お金がかかります。余裕をもって用意しましょう。
②離婚理由を整理する
離婚は話し合いによって双方が合意すれば成立します。しかし、配偶者が離婚に応じない場合は、離婚を求めて争うことになります。
まずは、家庭裁判所の調停手続きとなりますが、調停でも合意できない場合は裁判へと移行します。
しかし、裁判では、民法で定められている法定離婚事由に該当する離婚理由がなければ、基本的に離婚は認められません。
法定離婚事由(民法770条)
| 不貞行為 | 配偶者に不貞行為があったとき |
|---|---|
| 悪意の遺棄 | 配偶者から悪意で遺棄されたとき |
| 3年以上の生死不明 | 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき |
| 強度の精神病 | 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき |
| その他婚姻を継続し難い重大な事由 | 婚姻関係が破綻して婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがないとき |
例えば、離婚したい理由が性格や価値観の不一致で、法定離婚事由に該当しない場合には、別居を検討するのも一つの手です。
別居が長期間にわたり、夫婦関係が破綻していると裁判所に判断されれば、婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとして、離婚請求が認められる可能性が高まります。
離婚と別居については、以下で詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
③離婚の原因となる証拠を用意する
離婚の意思を伝えても、応じてもらえなかったり、条件がかみ合わなかったり、離婚の話がスムーズに進まないこともよくあります。より自分に有利な条件で離婚をするためにも、離婚の原因となる証拠を集めることが大切です。
この証拠は、離婚自体の請求に必要なことはもちろんのこと、慰謝料や財産分与、婚姻費用の請求など、さまざまな場面で有効となります。
しかし、証拠を自分ですべて集めるのは難しく、ますます離婚から遠ざかってしまいます。よりスムーズな離婚を目指す場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
有効な証拠となるものを以下の表にまとめます。
| 離婚理由 | 慰謝料請求に必要な証拠 |
|---|---|
| 不貞行為(浮気・不倫) |
|
| DV・モラハラ |
|
| 悪意の遺棄 |
|
| その他(セックスレスなど) |
|
④離婚条件を考える
離婚する際には、親権や養育費、面会交流など子供に関する条件や、慰謝料や財産分与、年金分割などお金に関する条件について話し合います。
例えば、「親権は絶対に獲得したい」「配偶者と不貞相手の双方に慰謝料を請求したい」など、譲れない条件があれば明確にしておくことで、話し合いがスムーズに進む可能性があります。
ただし、あれもこれも譲れないとなると、感情的な言い争いになってしまいます。そのため、譲れる条件についても考えておきましょう。
慰謝料
相手が不倫やDVなど「法的離婚事由」に該当する行為をしていた場合には、慰謝料を請求できます。
弁護士に相談するなどをして、まずは請求できる金額の相場を知りましょう。
請求する金額が決まったら、一括で受け取るのか、分割の場合はどのように受け取るのか、支払い方法について決めておきましょう。ただ、離婚慰謝料を請求しても相手が応じるとは限りません。
離婚慰謝料を請求するためには、不倫やDVなどの離婚の原因となる行為があったことを証明しなければなりません。そのため、離婚慰謝料を請求するためには十分に証拠を集めておくことが必要です。
離婚慰謝料については以下のページで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に公平に分け合う制度です。基本的には収入の差は関係なく一方が専業主婦であっても、公平に2分の1の財産を受け取ることができます。
財産分与で分配の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が2人で協力して作り上げたすべての共有財産です。
共有財産の代表的なものとして、以下のようなものが挙げられます。
- 夫婦が共同名義で購入した土地や不動産
- 家具、家電などの家財道具
財産分与するときには、財産が夫婦の共有財産であることの証明必要です。財産分与の対象となるものをリスト化し、それぞれの根拠資料を集めましょう。
また、配偶者の隠し財産がないか確認することも必要です。隠し財産が離婚後に発覚した場合は、離婚後2年以内であればその分の財産分与を請求できます。
離婚の財産分与については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
婚姻費用
婚姻費用は、「夫婦と未成熟の子」という家族全員が、その収入や財産、社会的地位に応じて通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことをいいます。
法的に婚姻関係にある夫婦は、お互いの収入や家庭内での役割に応じて、この婚姻費用を分担する義務があります。これは別居していても、婚姻生活が終わるまで変わりません。
婚姻費用の金額については、夫婦で話し合って決めることも可能です。話し合いで決まらない場合は、「婚姻費用算定表」を使用し相当額を算出します。
婚姻費用だけでは生活をする上で十分な金額とはいえないかもしれませんが、別居の上離婚し、再出発するための重要なお金になります。
婚姻費用については以下で詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
年金分割
年金分割とは夫婦が婚姻中に納めた厚生年金や共済年金について離婚時にお互いが公平になるように多い方から少ない方に分配する手続きです。
年金分配制度は夫婦のどちらか一方、または夫婦2人が厚生年金、共済年金に加入している場合に限ります。夫婦どちらも国民年金の場合は、そもそも分割できないので注意が必要です。年金分割をするためにも、お互いの加入状況などを調べておきましょう。
年金分割については以下のリンクをご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
親権
親権者を決める基準には以下のようなものがあります。
- 子への愛情
- 収入などの経済力
- 代わりに面倒を見てくれる人(履行補助者)の有無
- 親の年齢や心身の健康状態など親の監護能力
- 住宅事情や学校関係の生活環境
- 子供の年齢や性別、発育状況
- 環境の変化が子供の生活に影響する可能性
- 兄弟姉妹が分かれることにならないか
- 子供本人の意思
このように、親権者になる条件は、子供を十分に養育していけるか、子供の幸せのためにはどちらを親権者とした方が良いかなど子供の利益を中心として考えられることになります。
離婚の親権については以下で詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
養育費
養育費とは、未成年の子供を監護し、養育していくうえで必要となる費用のことです。子供を監護する親は、子供を監護していない親に対し毎月一定の金額の養育費を請求することができます。
養育費の金額は双方が納得できれば好きな金額に決めることができますが、家庭裁判所の実務では、「養育費算定表」を使用して、双方の収入に応じてその家庭に合った相場を算出します。
養育費について決めておくべきことは以下のようなものが挙げられます。
- 養育費の金額(月額)
- 支払い期日
- 支払い方法
- 支払い期間(いつまで支払うか)
条件が決まったらその内容を公正証書に残しておくようにしましょう。
離婚の養育費については以下で詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
面会交流
面会交流とは、離婚後や別居中に子供と同居していない親と子供が面会を含む親子として交流を行うことです。
面会交流について決めておくべきことに以下のようなものが挙げられます。
- 面会交流の頻度
- 面会交流の時間
- 面会交流の場所
- 元夫婦の連絡方法
- 子の受け渡し、引き渡し場所
- 宿泊の有無
- 学校行事への参加
- 遠方の場合は交通費の負担
- 祖父母との面会交流
面会交流については以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
⑤離婚後の子供のための準備をする
夫婦の間に子供がいる場合には、上記で解説した準備に加えて、子供に関する準備も必要です。離婚によって自分の環境が大きく変わり、余裕がなくなってしまいがちですが、子供の気持ちや状況にも配慮して進めていくことが大切です。
離婚後の子供のための準備
- 離婚後に通う保育園・幼稚園、学校について決めておく
- 子供の面倒を見られないときの預け先を決めておく
- 子供の戸籍や姓をどうするか決めておく
- 子供名義の通帳の姓を変更する
- どのような助成金や手当を受けられるか調べておく
どの準備も離婚後の子供の生活のためにとても重要ですが、なかでも助成金や手当は市区町村によって受けられるものが異なります。
新居に引っ越した際に市区町村が変わる場合は、引っ越し先で受けられる助成金や手当を確認しておきましょう。
以下のリンクでは、子供の氏の変更方法や必要な手続きなどについて詳しく解説しています。ぜひご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
⑥精神的な自立を目指す
離婚は結婚と違い祝福されることはなく、人によっては離婚したということに偏見を持つ人もいるかもしれません。また、たくさんのことを夫婦と乗り越えてきた中で、これからは自分で決め、行動していかなければなりません。
離婚の話がまとまらない場合は、調停や裁判にも辞さない覚悟や強い意志が求められます。しかし、離婚によって人生が新しく切り開かれる方もいらっしゃることでしょう。
明るい未来のためにも、精神的に自立し自分の人生を切り開いていくことが大切です。
⑦離婚に強い弁護士に相談する
離婚の準備として、早い段階から弁護士に相談することも大切です。離婚に詳しい弁護士に相談することで、どのような準備が必要なのか、決めておくべき条件などについてアドバイスを受けることができます。
また、離婚を切り出すことで相手が離婚を回避するために弁護士を立てる可能性もあります。相手が弁護士に依頼した場合はこちら側も弁護士に依頼すべきでしょう。
相手が弁護士を立てた場合で、自分も弁護士に依頼する場合とそうでない場合のメリット・デメリットをみていきましょう。
自分も弁護士に依頼する場合
- メリット
-
- 対等な立場で交渉でき、不利な結果になりにくい
- 精神的負担を軽減できる
- 調停や裁判など複雑な手続きを任せることができる
- デメリット
-
- 弁護士費用がかかる
弁護士に依頼しない場合
- メリット
-
- 弁護士費用がかからない
- デメリット
-
- 専門知識・ノウハウなどの面で不利になる可能性がある
- 相手弁護士と直接交渉しなければならず、精神的負担がかかる
- 調停や裁判など複雑な手続きを自分だけで対応しなければならない
弁護士に依頼する場合、費用はかかりますが受けられるメリットは多くあります。有利な条件で離婚するためにも、離婚問題の実績や経験が豊富な弁護士に相談しましょう。
離婚の準備にかかる期間
離婚の準備にかかる期間は、6ヶ月~1年程度でしょう。
「少しでも早く離婚したい」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、焦りは禁物です。離婚は子供のことやお金のことを決める必要があるため、お互いが納得できるよう話し合いを重ねることが大切です。
さらに、現在仕事をしていない方は、離婚後の生活を維持するためにも仕事を探したり、住居を探したりする期間も必要です。
離婚後の明るい生活のためにも、焦らず離婚の準備を進めましょう。
離婚の切り出し方と適切なタイミング
離婚は、切り出し方やタイミングも重要です。
離婚の切り出し方
- 感情的にならず冷静に伝える
- 相手を責めない
切り出すタイミング
- 十分な準備ができた上で切り出す(証拠がそろう、経済的に自立できる状態)
- 落ち着いて話ができるタイミングを見計らう
離婚を切り出す際には、お酒などが入っておらず、お互いが落ち着いて話し合えるタイミングで伝えましょう。
離婚理由によっては相手を責めたくなるかもしれませんが、感情的な話し合いは良い結果を生みません。相手を非難するような言い方は避け、冷静に話し合いましょう。
ただし、相手からDVを受けているような場合は、離婚を切り出すことでDVの被害が拡大してしまうおそれもあります。そのため、離婚の準備ができていなくても別居をしたり、シェルターに避難したり、まずは身の安全を確保しましょう。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
離婚準備に関するQ&A
熟年離婚の際に準備しておくべきことはありますか?
何の準備もせず、熟年離婚してしまうと、不利な条件で離婚してしまったり、離婚後に後悔することになったりします。熟年離婚の準備として以下のようなものが挙げられます。
- 財産分与や年金分割など離婚に関わるお金で、当面の生活費をどのくらい確保できるかを確認する
- 離婚後の住まいをどうするか考え、必要に応じて物件探しを行う
- やりがいや目標を探しておく
- 定年退職前であれば、退職金の支給の確認をする
熟年離婚について以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
専業主婦の場合、どのような離婚準備が必要でしょうか?
専業主婦の場合、離婚によって金銭的な問題が不安となるでしょう。そこで、離婚後の生活に備えて、以下のような準備をしましょう。
- 離婚後の住まいを考える
まずは、新しい住まいはどこにするのか検討し、家賃相場を把握しておくことが重要です。また、家賃の支払いが難しい場合は、実家に住まわせてもらうことも検討しましょう。 - 離婚後の生活費を計算する
離婚後はご自身の収入で生活しなければなりません。さらに、子供の親権者となった場合は子供に関する費用も必要です。毎月どのくらいの費用がかかり、どのくらいの収入が必要なのか計算しましょう。 - 仕事を探す
離婚後の生活のために、経済的に自立することが重要です。正規雇用での採用が難しい場合は、派遣社員や契約社員として働きながら、養育費や助成金、手当を活用して生活水準を保てるよう努めましょう。
夫に知られず密かに離婚準備をしたいのですが、その際に気を付けることはありますか?
離婚の準備をしていることを知られないためには、「離婚したい」という態度を出さないことが重要です。
相手に、「離婚を考えている」と悟られてしまうと、財産を隠されたり、証拠を隠されたりするおそれがあります。集めた証拠が相手にバレてしまうと、離婚が泥沼化し、離婚成立まで時間がかかってしまう場合もありますので、証拠は切り出すまで知られないようにしましょう。
男女別で必要となる離婚の準備について教えて下さい。
男女別の離婚の準備は以下のとおりです。
男性の場合
- 妻に渡す財産の把握
- 扶養控除などの変更、会社へ報告
- 離婚後の家事、家庭のやりくりなど
- 養育費、面会交流の頻度
- 慰謝料の有無
女性の場合
- 離婚時にもらえるお金を確認
- 離婚後の住居の確保
- 離婚後の仕事の確保
- 養育費の金額、面会交流
離婚前にやってはいけないことはありますか?
離婚後にトラブルになったり、離婚したことを後悔しないためには、離婚前にやってはいけないことがあります。
- 離婚準備が整う前に相手へ離婚したいと告げる
離婚準備が十分に整っていない段階で相手に離婚したいと告げてしまうと、共有財産を隠されたり、不貞行為の証拠を隠されたり、思い通りの条件で離婚ができなくなる可能性があります。 - 離婚時に不利な行動をする
「どうせ離婚するのだから」という気持ちで不倫や、攻撃的な発言を繰り返すことは避けましょう。離婚する際に慰謝料を請求されたり不利な離婚条件で離婚することになる場合もあります。
離婚の準備でお困りの際は弁護士にご相談ください
離婚の準備は簡単そうに見えて、決めなければならないことがたくさんあり、根気のいることです。
しかし、離婚の準備をせず早急に離婚をしてしまうと、本来もらえるべきお金をもらえなかったり、離婚の話が拗れてしまったりします。
早い段階から弁護士に相談することで、準備不足や漏れがないようアドバイスしてもらう事が可能です。また、入念に準備をしても相手が離婚に素直に応じてくれるかはわかりません。
協議で話がまとまらない場合は調停や裁判に移行します。その際にも、弁護士が付き添うことができ、あなたの心強い味方となります。ひとりで離婚準備することが難しいと感じた時は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)