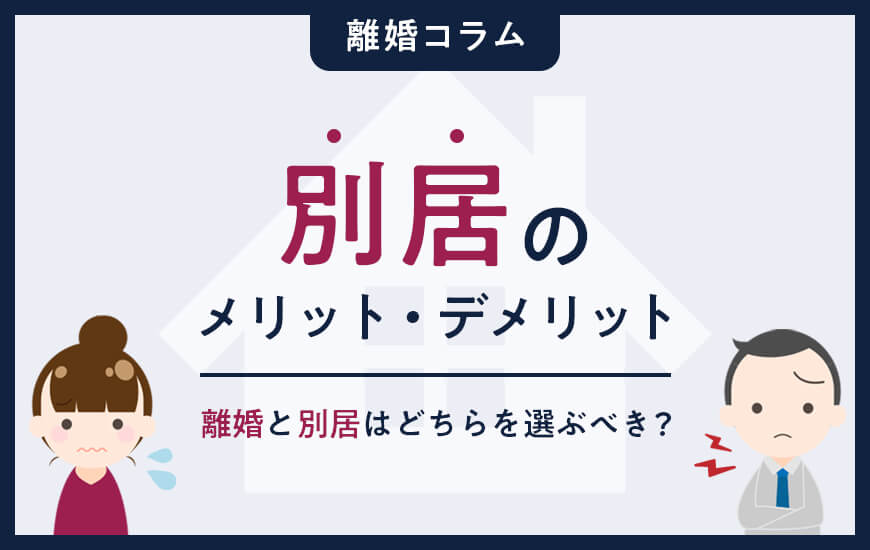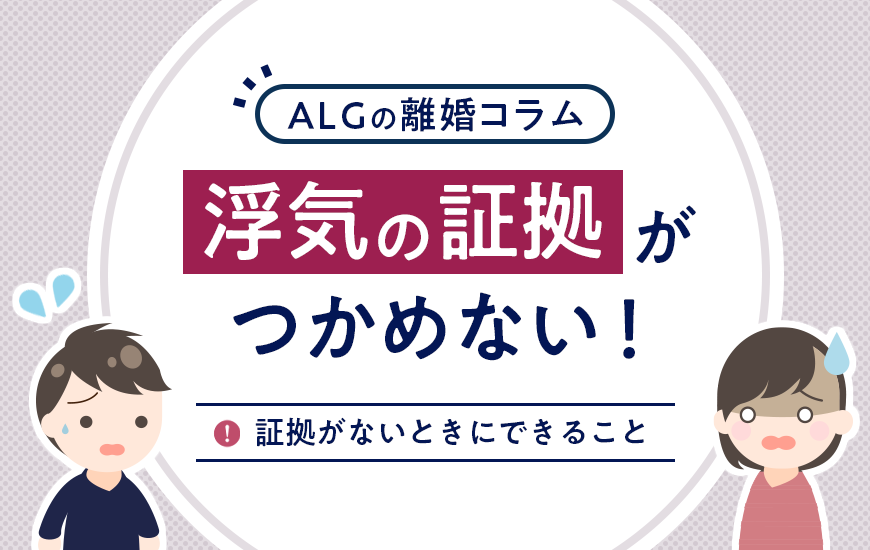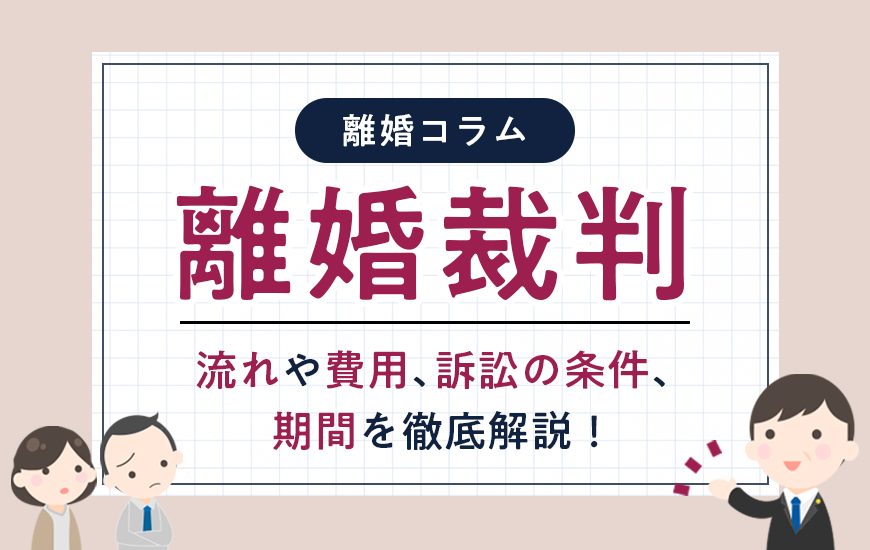離婚調停での不利な発言7つ!やってはいけないことや有利に進めるポイント
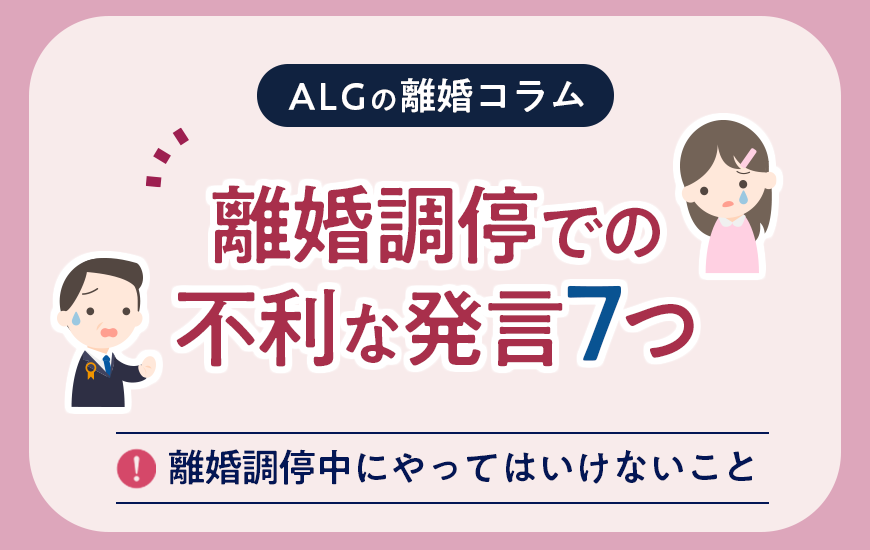
夫婦間で離婚や離婚条件について折り合いが付かない場合、家庭裁判所で離婚調停を申し立てることが一般的な流れになります。
離婚調停では、配偶者と直接話すわけではなく、調停委員を介して話し合いを行います。
調停委員は公平中立な立場にありますが、自分にとって不利になる発言や行動は控えた方がいいでしょう。
では、離婚調停において、不利な発言とはどのようなものなのでしょうか。
この記事では、離婚調停で不利になる7つの発言や、離婚調停中にやってはいけないことなどについて詳しく解説していきます。離婚をスムーズに進めるためにも、ぜひご参考ください。
目次
離婚調停で不利になる7つの発言とは
離婚調停では、配偶者ではなく調停委員を相手に話し合いを行います。調停委員は公平・中立な立場にありますが、不利な発言をしてしまうと、相手方の味方となってこちらを説得してくることもあります。
そのため、離婚調停を有利に進めたいのであれば、どのような発言が不利になるのかを知っておくことが大切です。
【離婚調停で不利になる発言】
- 相手の批判や悪口
- 証拠や根拠のない主張
- 過去の発言と矛盾する発言
- 離婚条件に固執しすぎる発言
- 相手に直接交渉するような発言
- 他に交際相手がいるとほのめかすような発言
- 譲歩しようとする発言
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
①相手の批判や悪口
離婚調停中は特に感情的になってしまい、相手を批判したり悪口を言ってしまったりする方もいます。
しかし、調停は相手の愚痴を吐き出す場ではありません。
調停において調停委員が知りたいことは、離婚の原因となる事実です。具体的な事実を説明せず相手の批判ばかりしていれば、離婚調停がスムーズに進まないだけでなく、良い印象を持たれず、たとえ事実を話していたとしても信用してもらえなくなるおそれもあります。
例えば、次のように、具体的な事実の説明もなく相手を批判する発言は控えましょう。
- 「夫は家事も育児も手伝ってくれないのに収入も低くて役に立ちません。それなのに偉そうな態度を取り、一緒にいるのが嫌になりました」
- 「妻は料理も美味しくないし、部屋も散らかっているし、妻としての役目を果たしていません」
② 証拠や根拠のない主張
証拠や根拠のない主張も離婚調停では避けるべきです。調停委員は事実を知りたがっているのであり、抽象的な発言ばかりしていても効果はありません。
例えば、調停委員から離婚したい理由を聞かれ、「夫が浮気をしているようです」と答えれば、具体的にどのようなことがあったのかを聞かれます。
しかし、そこで「女の感で分かるんです」といった程度のことしか答えられなければ、信用してもらうことは難しいでしょう。
それでも調停委員は相手に浮気をしたのか事実確認をしてくれますが、相手が浮気をしていないことやその証拠を説明すれば、調停委員からの信用は得られないでしょう。
③ 過去の発言と矛盾する発言
過去の発言と一貫性のない矛盾した発言は不利に働く可能性があります。
例えば、「夫は生活費を全く渡さない」と言っていたのに、「生活費の管理は私がしていて夫にはお小遣いとしてお金を渡している」と最初の内容を一転させるような発言です。
このように、最初の発言とは矛盾するような発言をすれば、調停委員に「この人は自分の都合のいいようにしか考えられない」という印象を与えやすくなってしまいます。
意見がころころ変わってしまえば、どの発言にも説得力がなくなってしまうため避けるべきでしょう。
④ 離婚条件に固執しすぎる発言
離婚条件に固執した発言も変えるべきでしょう。
例えば、「相手が離婚したいと言ってきたのだから、親権も譲らないし、財産分与もしない」と、離婚条件について一切譲らず、折り合いが付かなければ調停委員から「それならもう調停を終わりにして裁判で争ってください」と言われてしまうでしょう。
離婚裁判で争うこともひとつの手ですが、離婚が成立するまでさらに時間がかかってしまいますし、必ず希望条件が叶うわけではありません。
調停はあくまでも話し合いで解決を図る手続きです。離婚条件において、譲れる部分、譲れない部分を整理し、柔軟な話し合いによって譲歩する姿勢が大切です。
⑤ 相手に直接交渉するような発言
離婚調停が思うように進まないと、「相手と直接交渉する」と発言する方もいます。
しかし、このような発言は調停委員に危険人物だという印象を与えてしまうため、避けるべきでしょう。
例えば、子供との面会交流を求めていたが、相手方に拒否されたことを受けて「では、相手と直接交渉して会わせてもらうのでもういいです」というような発言です。
調停委員はこのような発言がされると、子供の身に危険が及ぶのではないかと心配し、面会交流を認めることに慎重になってしまいます。
スムーズに離婚調停を進めるためにも、相手に直接交渉するような発言は控えるべきです。
⑥ 他に交際相手がいるとほのめかすような発言
申立人は離婚したくて調停を申し立てても、相手が離婚に反対している場合もあるでしょう。
こうした場合、調停委員は申立人に対し「どうしてもやり直すことはできないか、そこまで離婚を望む理由は何か」を聞くことがあります。
それに対し、「他に交際している人がいるから」と正直に答えてしまうのは、かえって不利になるおそれがあります。
たしかに、離婚成立前であっても夫婦関係が破綻していれば、他の方と交際していても問題はありません。しかし、離婚調停中にほかに交際相手がいることを答えてしまうと、それが原因で婚姻関係が破綻したのではないかと疑われてしまい、話し合いが複雑化するおそれがあるため、控えるべきでしょう。
⑦ 譲歩しようとする発言
離婚調停では、離婚条件について安易に譲歩しようとする発言もよくありません。
なぜなら、離婚調停は裁判と異なり、できる限り当事者間で折り合いを付けて成立させようとするからです。
例えば、申立人が慰謝料200万円を請求しているのに対し、相手が100万円しか払えないと言っているケースを考えてみましょう。
それを聞いた申立人が「それなら仕方ないので100万円でいいです」と安易に合意してしまえば、調停委員に「この人は説得すれば譲歩する人だ」という印象を抱かせてしまいます。
その結果、養育費や財産分与など他の離婚条件についても不利な条件を押し付けられてしまうおそれもあります。
離婚調停では、譲れる部分と譲れない部分をはっきり主張することが大切です。
離婚調停中にやってはいけないこと
離婚調停にかかる期間は個別事情により様々ですが、大体3ヶ月~1年程度の時間を要します。
思うように調停が進まずイライラして次のような行動をとってしまうと、かえって不利になるおそれがあるため、注意が必要です。
【離婚調停中にやってはいけないこと】
- 相手に直接連絡をとる
- 調停を欠席する
- 子供を連れ去る
- 他の異性と交際する
- 相手に嫌がらせや脅迫などをする
- 一方的な別居をする
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
相手に直接連絡をとる
離婚調停中は、調停委員を介して話し合うのが基本的なルールです。
離婚と関係のない内容であれば問題ありませんが、そうではなく、相手と直接協議をしようとすることは避けるべきでしょう。
そもそも、夫婦で話し合った結果、調停を行っているのですから、これ以上話し合いが進むとは考えにくいです。また、調停委員に「ルールを守れない人」「自己中心的な考えの人」といった良くない印象を与えかねません。
なお、無理やり相手に対して連絡を取ることを要求すると、ストーカー規制法違反や脅迫罪などの罪に問われる可能性もあります。
調停を欠席する
離婚調停が進まないと、「もう出席しても意味がない」と思うこともあるかと思いますが、調停を欠席するのは避けましょう。
離婚調停を何回も欠席したり、無断欠席をすれば、調停委員に「非常識な人だ」と悪い印象を与えてしまい不利な結果につながる可能性もあります。さらに、調停を正当な理由もなく欠席すると、5万円以下の過料を科せられるケースもあります。
離婚調停は、あくまでも話し合いで問題の解決を図る手続きです。当事者が調停を欠席すれば話し合いにならず、調停不成立となります。
やむを得ない事情でどうしても調停に出席できない場合は、事前に家庭裁判所にその旨を連絡するようにしましょう。
子供を連れ去る
離婚調停中でも、面会交流だけは先に行われることがあります。どうしても親権が欲しいからと、子供の通っている学校の前で待ち伏せしたり、面会交流中にそのまま相手方に子供を返さず、子供を連れ去るケースも見受けられます。
しかし、このような行為は、かえって調停委員に「親権者に相応しくない」と悪い印象を持たれてしまい、親権の問題に不利に働いてしまうため、注意しましょう。
また、実の親であっても子供の連れ去りはその態様などによっては、未成年略取・誘拐罪に問われる場合もあります。
他の異性と交際する
離婚調停中とはいえ、離婚が成立するまでは法律上の夫婦関係にあります。
まだ同居していたり、相手が離婚を拒否しているのに配偶者以外と交際したりすれば、不貞行為とみなされる場合もあります。
不貞行為をした配偶者は離婚原因を作った側として有責配偶者となります。
有責配偶者となれば、基本的に離婚請求は認められないだけでなく、相手から慰謝料を請求されるおそれもあります。
したがって、離婚が成立するまでは他の方との交際は控えるべきでしょう。
相手に嫌がらせや脅迫などをする
調停では顔を合わせることはありませんが、当事者双方が出席します。
その際、相手を帰りに待ち伏せする、尾行して脅迫する、暴力を振るうなどの事件がまれに発生してしまいます。
当然ながら、このような行為は犯罪にもなり得ますし、調停委員の印象も極めて悪くなります。
なにより、相手との交渉もますます難しくなるばかりです。相手への嫌がらせは絶対にやめましょう。
一方的な別居をする
正当な理由なく一方的に別居すると、「同居義務違反」に該当する可能性があります。
また、夫婦はお互いに「同居・協力・扶助の義務」を負っており、一方的な別居は、「夫婦の協力・扶助の義務に違反した」として悪意の遺棄と判断されるおそれもあります。
悪意の遺棄は法律で離婚が認められる事由に該当しますので、「有責配偶者」となり、離婚請求が認められないだけでなく、相手から慰謝料を請求される場合もあります。
そのため、別居検討している場合は、相手の同意を得るようにしましょう。
ただし、相手からのDVや子供への虐待など、身の危険を感じる場合はこの限りではありません。速やかに警察やシェルターに避難してください。
離婚と別居については、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
離婚調停では何を聞かれるの?
落ち着いて調停委員と話すためには、あらかじめ質問内容を想定しておき、どのように答えるかを考えたうえで臨むことをおすすめします。
ここからは、第1回調停期日において、よく聞かれる質問について見ていきましょう。
- 結婚した経緯
なぜ離婚調停を行うに至ったかを把握するために、特に聞かれることが多い質問です。
過去の思い出話をする必要はなく、出会いから結婚までの流れを説明しましょう。
- 離婚を決意した理由、また離婚に同意しているか
申立人には「離婚を決意した理由」、相手方には「離婚に同意しているか」がよく聞かれます。
調停をどのように解決に進めていくか、調停委員が判断するためにとても重要です。
- 現在の夫婦関係の状況について
現状として、同居・別居の有無、生活費はどうしているのかなどもよく聞かれます。特に生活費は、婚姻費用の分担義務を果たしているかを確認するために重要な内容です。
- 子供に関すること
夫婦間に未成年の子供がいる場合は、親権や面会交流についてどう考えているのかを聞かれることが多いです。また、現在別居している状況であれば子供はどちらと暮らしているか、養育費の負担はどうなっているのか、も聞かれるでしょう。
- 夫婦関係が修復できる可能性について
調停は話し合いの場ですので、絶対に離婚しなければならないわけではありません。
一時的な感情であとから間違いに気付くこともありますので、夫婦関係の継続も十分に検討する必要があります。
- 財産分与、慰謝料、養育費についての考え
離婚の際には、財産分与や慰謝料、養育費などのお金の問題について争いになることが多くあります。特に養育費を請求する立場であれば、希望する具体的な金額やその根拠を説明できるようにしておきましょう。
- 離婚が成立した場合、その後の生活について
離婚後は夫婦が別の生活になるため、申立人の収入や養育に関する質問を受けます。住居の確保や生活費などについて、先を見越してきちんと考えていることを伝えられると良いでしょう。
離婚調停での不利な発言を避けて有利に進めるためのポイント
不利な発言を避けたからといって、離婚調停が有利に進むわけではありません。
離婚調停を有利に進めるためには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
以下で詳しく見ていきましょう。
調停委員を味方につける
離婚調停は、基本的に調停委員が当事者それぞれから交互に話を聞くかたちで進みます。
そのため、調停委員を味方につけるのが離婚調停を有利に進めるためのポイントといえるでしょう。
調停委員を味方につけるためには、次の点に気を付けておくべきです。
- 身なりや言葉づかいに気を付ける
調停委員に与える印象は大切です。ラフすぎる服装であったり、乱暴な言葉づかいは悪い先入観を持たれて損をする可能性もあります。
- 感情的にならない
突然泣き出したり、興奮して怒鳴ったりしてしまうと、調停の進行に影響が出てしまい、調停委員の心証が悪くなってしまいます。感情論ではなく、冷静に事実を話す方が説得力のある主張ができます。
具体的な事実に基づいて冷静に話す
調停委員は事実に基づいて判断をするため、抽象的な内容よりも、具体的なエピソードや証拠を提示することでより伝わりやすくなるでしょう。
例えば、「酔っぱらって言い合いになり、物を投げられ、腰を蹴られた」などDVを受けたことの具体的なエピソードを伝えることで、説得力が増すでしょう。
また、不貞行為の場合は、相手が不貞相手とラブホテルに出入りする写真や探偵事務所の報告書など、客観的な証拠を提示することで、自分の主張を理解してもらいやすくなります。
離婚調停の際には、状況証拠の収集や事実調査なども行っておくと、より有利に進められる可能性が高まります。
浮気の証拠集めについては、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
陳述書を提出する
陳述書とは、自身の考えや経験したこと等を記載し、言い分をまとめた文書のことです。
必ずしも提出しなければならないものではありませんが、事前に調停委員に内容を確認してもらうことで、スムーズに話し合いを進められることが期待できます。
〈陳述書に記入する一般的な内容〉
- (自分と相手方の)氏名、年齢、現住所
- (自分と相手方の)職業、勤務先、雇用形態、年収
- (子供の)名前、年齢、性別、学校または職業 ※子供がいる場合
- 離婚調停を行うに至った経緯
- 今後どうしていきたいか(例:離婚したい)
訴訟に進んだときのことを考える
離婚や離婚条件について、お互いが譲らなければ、調停は不成立となり裁判に発展する場合もあります。
調停とは異なり、裁判では、当事者それぞれの主張や提出した証拠を総合的に考慮して、裁判官が判決を下します。
そのため、自分の主張を裏付ける客観的な証拠がなければ、相手に有利な判決となってしまう可能性もあります。
また、裁判で離婚が認められるためには、民法で定められている法定離婚事由が必要です。
【法定離婚事由】
法定離婚事由は次の5つがあり、どれかに当てはまる事情がなければ裁判所に離婚は認めてもらえません。
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があったとき
離婚裁判については、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
弁護士に依頼する
離婚調停を行う際は、弁護士に依頼して進めることをおすすめします。
弁護士に依頼することには、以下のようなメリットが挙げられます。
- 代理人として弁護士が調停に出席し、法的な観点から主張・立証できるので、有利に調停を進められる可能性が高まる
- 書面の作成、提出、裁判所のやり取りなど煩わしい手続きを弁護士が代わりに行ってくれ、時間や労力が軽減できる
- 離婚条件での不利な内容や記載漏れに気づかずに合意してしまうといった取り返しのつかない失敗を未然に防ぐことができる
- 有効な証拠の収集についてアドバイスしてくれる
離婚調停を有利に進めるためにも弁護士法人ALGにご相談ください
離離婚調停では、これまでの夫婦の話し合いとは異なり、調停委員が間に入ります。
何気なく発した言葉が調停委員の心証を悪くしてしまい、不利な状況になってしまうことも少なくなりません。
離婚調停を少しでも有利に進めたいとお考えの場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば代理人として調停に出席できるため、ご依頼者様の主張を調停委員に分かりやすく主張・立証することが可能です。
また、相手方の意見にも的確に反論することができ、不利な調停を避けることができます。
離婚調停で不利な発言をしてしまうと、後悔の残る結果になりかねません。
離婚調停については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)