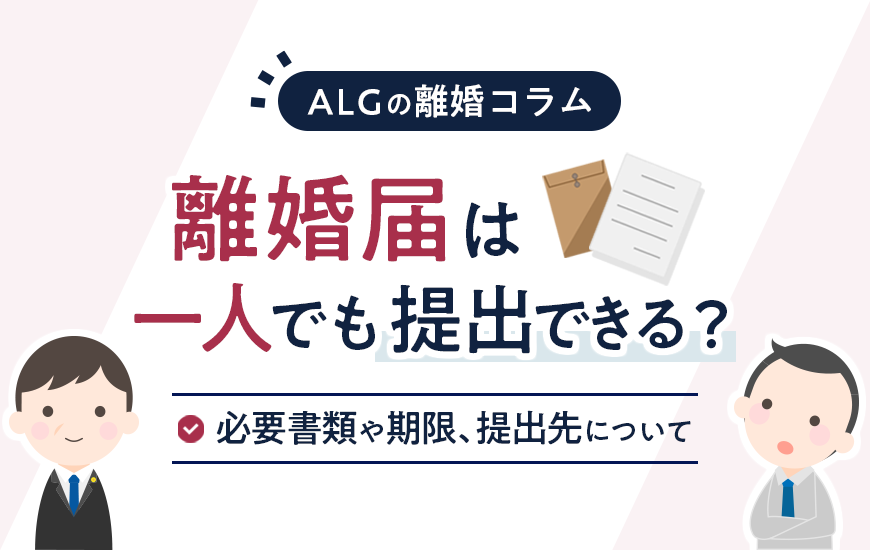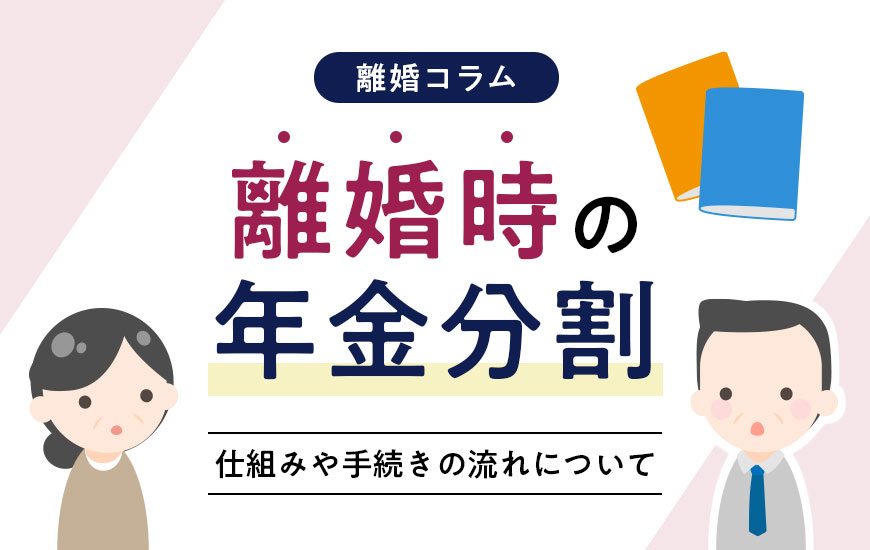離婚調停の成立後は何をすればいい?流れや必要な手続きなど
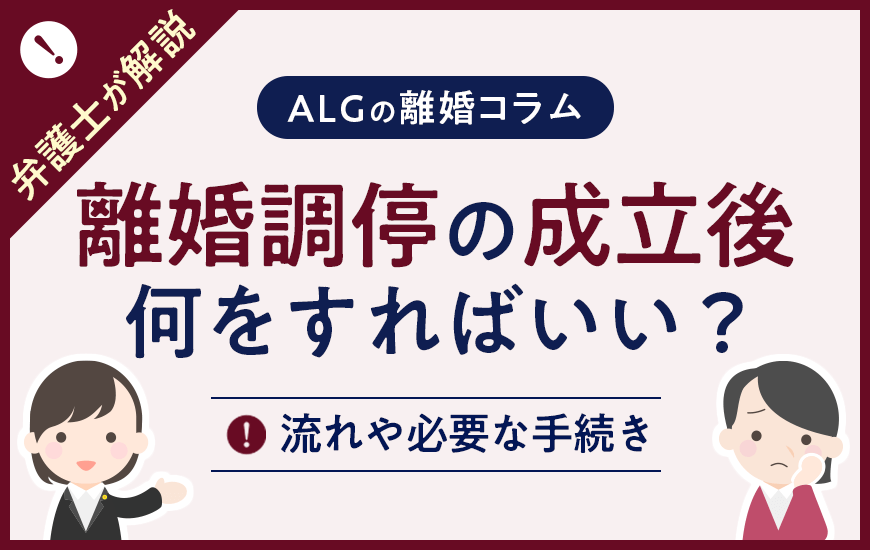
調停で離婚が決まると法律上は離婚が成立しますが、役所に離婚届を提出しなければ戸籍は婚姻中のままになってしまいます。
調停離婚の場合、夫婦の話し合いによって成立する協議離婚とは離婚届の書き方や提出方法などが異なる部分があるので注意が必要です。
また、離婚届の提出のほかにも、戸籍に関する手続きや保険・年金に関する手続きなど、調停成立後にやるべき手続きはたくさん残っています。
なかには期限が定められている手続きもあるので、スムーズに進められるよう離婚調停の成立後にやるべき手続きについて、本記事でわかりやすく解説していきたいと思います。
目次
離婚調停の成立後の流れ
離婚調停は夫婦双方が合意できれば成立し、家庭裁判所で調停調書が作成されます。
調停成立と同時に離婚も成立しますが、離婚したことを戸籍に反映させるためには、調停調書の謄本と一緒に離婚届を役所へ提出する必要があります。
離婚調停が成立して調停調書が作成された後は、次の流れで離婚届を提出します。
- 調停調書の謄本を請求
- 調停調書の謄本と離婚届を一緒に提出(10日以内)
以下、もう少し詳しく解説していきます。
①調停調書の謄本を請求
離婚調停の成立後に離婚届を提出するために、まずは家庭裁判所へ調停調書の謄本を請求して交付してもらいます。
調停調書の謄本の申請方法
- 来庁申請:裁判所に足を運んで申請する方法
- 郵送申請:郵送で申請する方法
調停調書の謄本は申請から2~3日ほどで交付してもらえます。
郵送の場合は1週間程度かかるため、離婚調停が成立したその場で申請するのが一般的です。
離婚届を提出するための謄本のほか、年金分割の際に必要な年金分割に関する内容のみを記載した調停調書省略謄本や、強制執行の際に必要な調停調書正本も必要に応じて一緒に申請しておくことをおすすめします。
②調停調書の謄本と離婚届を一緒に提出
交付された調停調書の謄本を、離婚届と一緒に役所へ提出します。
提出先は、夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場です。
なお、本籍地が遠いなどの事情がある場合には、お近くの役場に離婚届を提出することも可能です。
本籍地以外の役場へ離婚届を提出するにあたっては、離婚届と調停調書謄本のほかに、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)の提出も必要になります。
離婚届の提出期限
調停離婚における離婚届の提出期限は、調停が成立した日から10日以内です。
提出期限の10日を過ぎたからといって調停で合意した内容が無効になることはありませんが、5万円以下の過料が課される可能性があるので注意しましょう。
◆10日目が役所の閉館日だった場合は?
調停成立の日から10日目が土日祝日で役場が閉館していた場合には、その次の開館日が期限となります。
離婚届を提出する人
調停離婚における離婚届を提出する人(=届出義務者)は、調停を申し立てた申立人が基本です。
ただし、調停調書に「申立人と相手方は、本日、相手方の申し出により、調停離婚する」と記載されている場合には、相手方が離婚届の届出義務者となります。
◆届出義務者が10日を経過しても離婚届を提出しない場合は?
離婚届の届出義務者が、調停成立の日から10日を経過しても離婚届を提出していない場合には、相手からも離婚届を提出することが可能です。
離婚届を提出できる人については、以下ページもあわせてご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
調停離婚の場合の離婚届の書き方
調停離婚の場合も、離婚届は役所で取得できる通常の様式を使用します。
離婚届の書き方については、夫婦で話し合って成立する協議離婚とは異なり、調停離婚の場合は届出義務者の署名だけが必要で、相手の署名も証人も必要ありません。
調停離婚の離婚届の書き方
- 夫婦双方の署名は必要なく、離婚届の届出義務者の署名だけで足りる
※戸籍法の改正により2021年9月1日から捺印は不要 - 離婚の種別は「調停」
- 証人は必要ないので、証人欄は空欄のまま
離婚届不受理申出が提出されている場合
離婚届不受理申出が提出されている場合でも、調停離婚が成立していれば離婚届を受理してもらえます。
◆離婚届不受理申出とは?
離婚届不受理申出とは、自分の知らない間に勝手に離婚届を提出・受理されるのを防ぐ制度のことです。
申し出た本人が取下げない限りは離婚届を受理してもらえません。
調停離婚や裁判離婚の場合は、法的に離婚が成立していることになっているため、不受理申出が取下げられていなくても、離婚届は受理されます。
離婚届不受理届については、以下ページもあわせてご参考ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
離婚調停の成立後に必要な手続きは?
離婚調停の成立後は、離婚届の提出以外にも、次に挙げるようにさまざまな手続きが必要です。
- 婚氏続称の届出(3ヶ月以内)
- 子供の戸籍の変更
- 国民健康保険・国民年金の切り替え(14日以内)
- 年金分割(2年以内)
- ひとり親家庭に関する手続き
- 運転免許証やマイナンバーカードなど、その他の手続き
期限が定められている手続きもあるので、それぞれ次項で詳しくみていきましょう。
婚氏続称の届出
離婚後も婚姻中の氏を継続して使用したい場合は、離婚から3ヶ月以内に【婚氏続称の届出】を行う必要があります。
婚姻時に相手方の氏に変えた方は、離婚によって婚姻前の氏に戻ることになります。
ただし、婚氏続称の届出を行うことで、離婚後に婚姻中の氏で新しい戸籍が作られるので、継続して婚氏を使い続けることができます。
| 届出先 | 届出対象者の本籍地または住所地の市区町村役場 |
|---|---|
| 必要書類 | ・離婚の際に称していた氏を称する届 (役場の窓口またはウェブサイトから取得できます) |
| 届出期間 | 離婚調停が成立した日から3ヶ月以内 (離婚届と同時に届け出ることも可能) ※3ヶ月を過ぎた場合には家庭裁判所の許可が必要 |
子供の戸籍の変更
離婚によって婚姻時の戸籍から抜ける方が親権者となる場合、子供の戸籍を変更する手続きが必要です。
婚姻時に相手方の氏に変えた方は、離婚によって戸籍から抜けることになります。
このとき、戸籍から抜ける方が親権者となる場合でも、子供の戸籍は自動的に変更されないので、もとの戸籍に残ったままになってしまいます。
そこで、親権者の新しい戸籍へ子供の戸籍を移すために、次の手順を踏む必要があります。
①家庭裁判所に【子の氏の変更許可申立て】の審判を申し立てて、子の氏の変更の許可を得る
| 申立先 | 子の住所地の家庭裁判所 |
|---|---|
| 必要書類 |
|
②役場で【子の入籍届】を行います
| 届出先 | 入籍者の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場 |
|---|---|
| 必要書類 |
|
これらの手続きについて期限は定められていません。
ですが、親権者と子供の氏が違うことで不都合が生じるおそれもあるので、早めに入籍手続きを行うようにしましょう。
国民健康保険・国民年金の切り替え
調停離婚後すぐに就職しない場合は、国民健康保険や国民年金の切り替え手続きが必要です。
離婚調停が成立した日から14日以内に役場での手続きが必要で、うっかり忘れると保険料が未納となるばかりか、生活に支障をきたすおそれもあるので注意しましょう。
国民健康保険への加入
配偶者を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合は、役場で世帯主の変更手続きを、配偶者の社会保険を抜けて国民健康保険へ加入する場合は、配偶者の職場から資格喪失証明書を取得し、役場で国民健康保険の加入手続きをしなければなりません。
| 届出先 | 届出対象者の住所地の市区町村役場 |
|---|---|
| 必要書類 |
|
| 届出期間 | 離婚調停が成立した日、または扶養を外れた日から14日以内 |
国民年金の切り替え
婚姻時に第3号被保険者だった場合は、役場や年金事務所で第1号被保険者への変更手続きが必要です。
| 届出先 | 届出対象者の住所地の市区町村役場、または年金事務所 |
|---|---|
| 必要書類 |
|
| 届出期間 | 離婚調停が成立した日、または扶養を外れた日から14日以内 |
年金分割
離婚にともなって年金分割を行う場合は、分割を受ける方が離婚から2年以内に年金事務所で手続きを行う必要があります。
| 提出先 | 請求者の住所地の年金事務所 |
|---|---|
| 必要書類 |
|
| 提出期間 | 離婚調停の成立日の翌日から2年以内 |
年金分割については、以下ページもあわせてご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
ひとり親家庭に関する手続き
離婚調停が成立したら、ひとり親家庭への支援制度を利用するために、申請手続きをもれなく行いましょう。
ひとり親家庭が利用できる支援の一例
- 児童扶養手当
- 児童手当
- 特別児童扶養手当、障がい児童福祉手当
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度 など
たとえば、母子手当とも呼ばれる児童扶養手当は、申請した月の翌月分からの支給となるため、離婚調停成立後すぐに申請することをおすすめします。
| 申請先 | 申請者の住所地の市区町村役場 |
|---|---|
| 必要書類 |
|
その他の手続き
離婚にともない、氏名や住所に変更があった場合には、次に挙げる手続きも忘れずに行いましょう。
- 住民票の移動(転出届・転入届・転居届)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 自動車や不動産
- 住宅ローン契約
- 金融機関の口座
- クレジットカード
- 学資保険や生命保険の契約 など
こうした手続きには、印鑑証明や戸籍謄本などが必要になります。
期限の定めがない手続きがほとんどですが、早めに手続きを行いましょう。
離婚調停やその後の手続きでお悩みの方は弁護士法人ALGへご相談ください!
調停離婚が成立して安堵されている方も多いと思いますが、その後にすべき手続きは意外にたくさんあります。
離婚後の生活を整えるために必要な手続きばかりなので、取りこぼしなく円滑に手続きを進めるためにも、不安がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人ALGでは、離婚調停の手続きから、離婚が成立した後までトータルでサポートが可能です。
調停で取り決めた約束が守られなかったなどのトラブルにも対応できるので、まずはお気軽にご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)