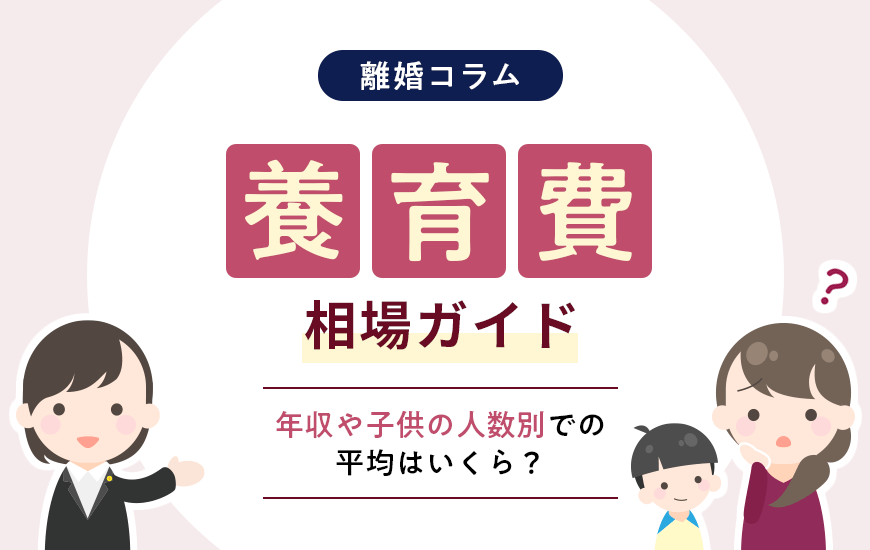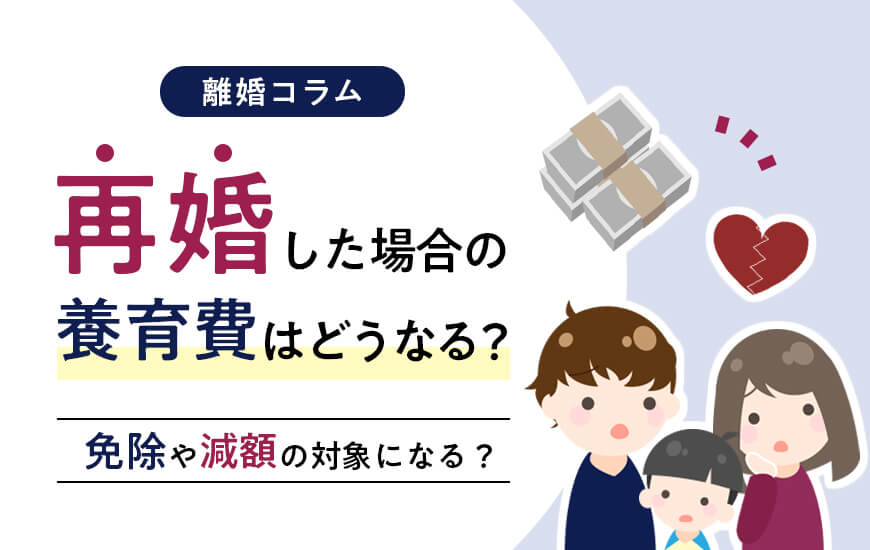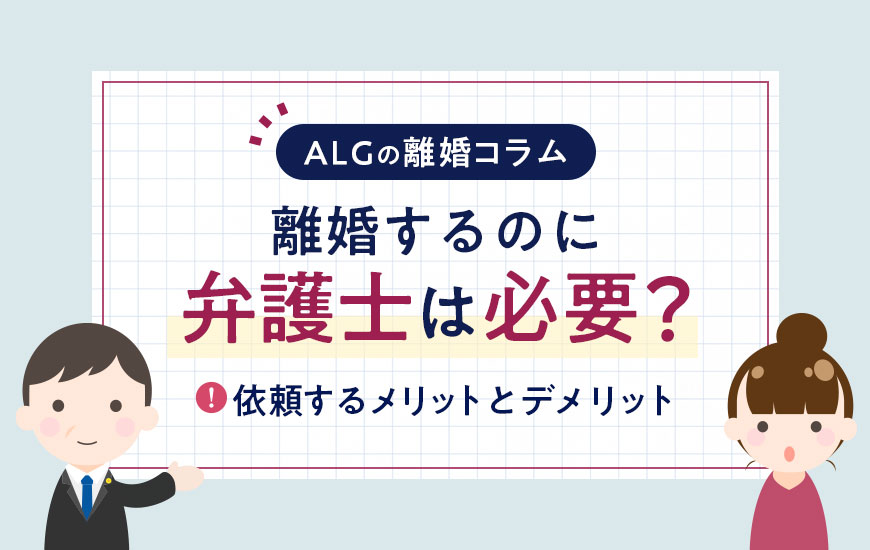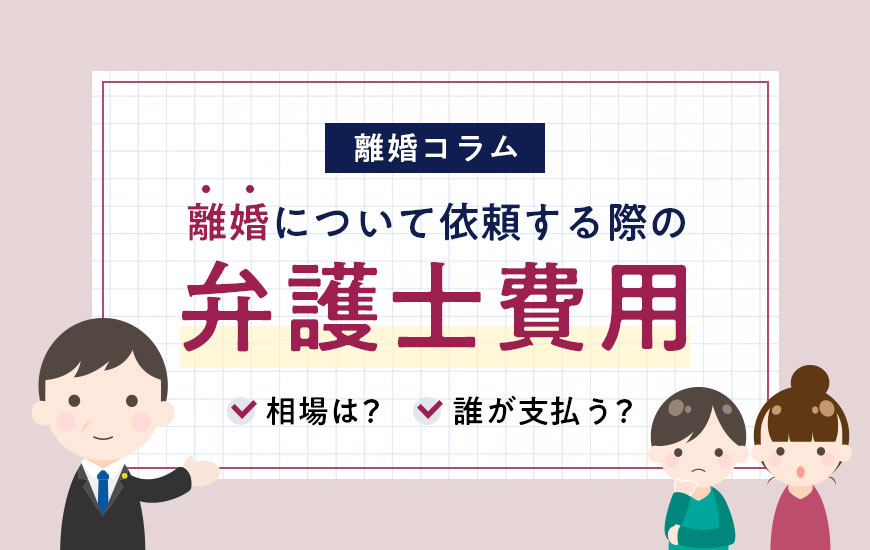離婚後に養育費を請求できる?方法や時効などの注意点を解説
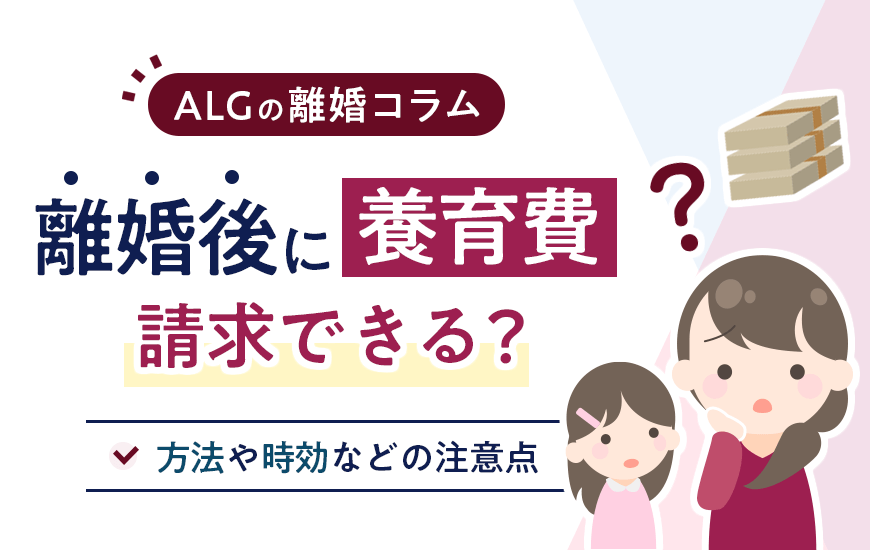
「とにかく早く離婚したくて、養育費の取り決めは後回しにしてしまった」
「自分の収入だけで十分だと思って養育費を決めないまま離婚したけど、事情が変わってやっぱり養育費を支払ってほしい」
など、養育費に関する取り決めをしないまま離婚が成立していた場合でも、離婚後に養育費を請求することができます。
離婚しても親と子供の関係は続きますし、親には養育費を支払う義務があるためです。
本記事では、離婚後に養育費を請求したいとお考えの方に向けて、請求方法や注意点について解説していきます。
目次
離婚後でも養育費は請求できる
離婚するときに取り決めていなくても、基本的には離婚後も養育費を請求することができます。
そもそも養育費とは、子供の監護・養育のために必要な費用のことです。
離婚したからといって親と子供の関係が切れるわけではないので、子供が経済的・社会的に自立するまで扶養義務が続くため、離婚後であっても養育費を支払わなければならないのです。
なお、離婚後に養育費が請求できるのは子供が20歳になるまでが一般的ですが、父母間で合意できれば、大学を卒業する22歳の3月まで養育費を請求することもできます。
養育費の相場
養育費の相場は、家族構成や父母の収入によって異なります。
養育費の金額は、父母間で話し合って自由に決めることができますが、このとき目安となるのが、裁判所が公表している“養育費算定表”です。
算定表は子供の年齢や人数ごとに選べるようになっていて、そこから父母それぞれの年収をもとに標準的な養育費の相場を求めることができます。
算定表の養育費の相場を目安にして、私立学校・大学への進学などの個別の事情を考慮したうえで、具体的な金額を取り決めるのが一般的です。
詳しくは以下ページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚後に養育費を請求する方法
離婚後に養育費を請求する方法は、父母間で話し合う方法と裁判所の手続きを利用する方法があります。
一般的には、次のような流れで進んでいきます。
- 元配偶者と話し合う
- 養育費請求調停を申し立てる
- 養育費請求審判へ移行する
それぞれの方法について、次項でもう少し詳しくみていきましょう。
①元配偶者と話し合う
まずは元配偶者に連絡を取って、養育費について話し合いましょう。
元配偶者と直接話し合うことが難しい場合や、連絡を取ることすら避けたい場合には、手紙やメールでやりとりをしたり、弁護士に代理人となってもらって交渉してもらったりする方法もあります。
話し合いの結果、養育費の金額や支払方法、支払期間などが決まれば、その内容を合意書などの書面にまとめておきましょう。
このとき書面を強制執行認諾文言付き公正証書にしておくと、取り決めた養育費が支払われなかった場合に、別途裁判などの手続きを経なくても強制執行の手続きをとることが可能になります。
②養育費請求調停を申し立てる
養育費について、元配偶者との話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に“養育費請求調停”を申し立てることができます。
養育費請求調停とは、父母の間に調停委員が入って双方の意見を聴き、助言や解決策を提案しながら、養育費の合意に向けて話し合う裁判所の手続きです。
養育費について合意できれば、金額や支払方法、支払期間などの合意内容が記載された調停調書が作成されます。
ただし、調停はあくまで話し合いによる手続きなので、父母間で合意できなければ調停は不成立となって、自動的に審判に移行します。
③養育費請求審判へ移行する
調停でも合意できなかった場合には、自動的に審判へと移行します。
審判では、調停での話し合いを踏まえて、父母双方から提出された証拠などをもとに、裁判官が養育費の支払い可否や、金額・支払方法・支払期限などの条件について決定を下します。
下された決定に不服申立てがなされなければ、審判書が作成されて終了となります。
なお、調停や審判の結果に従わず、養育費を支払ってもらえない場合には、裁判所に申し出ることで、裁判所から相手方に対して履行勧告や履行命令を発してもらうことができます。
それにも従わない場合には、調停調書や審判書を債務名義として、強制執行の手続きが可能になります。
強制執行手続きでは、給与や預貯金、不動産などの財産を差し押さえて強制的に養育費を回収することができます。
離婚後に養育費を請求するときの注意点
離婚後に養育費を請求する場合は、次のようなことに注意しましょう。
- 養育費の請求には時効がある
- 過去分の養育費は遡って請求できない
それぞれの注意点について、次項で詳しく解説していきます。
養育費の請求には時効がある
離婚後に養育費を請求する場合、一定期間が経過すると時効にかかって養育費の請求が認められなくなる可能性があります。
なお、養育費の時効は、離婚時に養育費の取り決めをしている・していないによって次のように異なります。
離婚時に養育費の取り決めをしていない場合
養育費の取り決めをしていない場合、時効はありません。
子供が経済的・社会的に自立していない限りは養育費を請求することができます。
ただし、取り決めがない以上、相手が任意に支払いに応じない限りは、過去の未払い分の養育費を請求することはできません。
離婚時に養育費の取り決めをしている場合
離婚時に養育費の取り決めをしていて、未払いとなっている場合には次のとおり時効が定められています。
| 離婚協議で合意し、公正証書を作成した場合 | 支払期日の翌日から5年 |
|---|---|
| 協議ではなく家庭裁判所の調停や審判で決定し、調停調書や審判書などが作成されている場合 | 支払期日の翌日から10年 |
※1・・調停成立時または審判確定時以降に発生した未払い分は支払期日の翌日から5年
過去分の養育費は遡って請求できない
過去に遡って養育費を請求することは、基本的に認められていません。
話し合いによって相手が任意で支払いに応じてくれればよいですが、そうでない場合は、相手に直接養育費を請求したときあるいは養育費請求調停を申し立てたときからの養育費の支払いしか認められないのが一般的です。
なお、調停の申立てよりも以前に直接相手に養育費を請求していた場合、その内容や日付を確定できるメールやLINEなどの証拠があれば、その日まで遡って養育費の請求が認められる可能性があります。
離婚後、再婚した場合でも養育費は請求できる?
離婚後、ご自身や相手方が再婚した場合でも、養育費を請求することはできます。
父母のいずれか、または双方がそれぞれ別の相手と再婚したとしても、養育費を請求する権利がなくなるわけではないので、養育費は請求できます。
ただし、ご自身の再婚相手と子供が養子縁組している場合や、相手方が再婚して扶養家族が増えている場合には、認められる養育費が相場より低めの金額となったり、再婚前に取り決めていた養育費の金額から減額を求められたりする可能性はあります。
受け取る側・支払う側それぞれの視点で再婚した場合の養育費について以下ページで詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
離婚後の養育費請求を弁護士に依頼するメリットや弁護士費用
離婚後に養育費を請求するときは、弁護士に交渉を依頼することをおすすすめします。
弁護士に依頼するメリットとして、次のようなものが挙げられます。
- 元配偶者や調停委員とのやりとりを任せられるので、ご自身の負担が軽減される
- 調停や審判の手続きを任せられる
- 適切な金額の養育費を獲得しやすくなり、増額についても交渉してもらえる
- 養育費の支払いが滞った場合も速やかに対応してもらえる など
離婚問題を弁護士に依頼するメリットについて以下ページで詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
養育費請求を弁護士に依頼するデメリットは弁護士費用がかかること
養育費請求を弁護士に依頼するとメリットがある一方で、弁護士費用がかかるというデメリットもあります。
一般 的な養育費請求にかかる弁護士費用の相場は、着手金が10万~30万円程度、報酬金が経済的利益の10~20%程度となっています。
離婚問題で弁護士に依頼した場合の弁護士費用については、以下ページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚後に養育費の請求をしたいとお悩みの方は弁護士法人ALGへご相談ください!
養育費は子供の健全な成長に欠かせないものです。
離婚後の養育費がいくら請求できるのか、どのように請求すればよいのかお悩みの方は、弁護士法人ALGまでご相談ください。
ご相談者様のご事情にそったアドバイスはもちろん、元配偶者の方との連絡や交渉を弁護士に任せることもできます。
離婚後の養育費請求は、ご自身だけではスムーズに進まないことも多いです。
養育費や離婚問題の経験豊富な弁護士が味方となってサポートいたしますので、不安や疑問に感じていることを、まずはお気軽に私たちにご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)