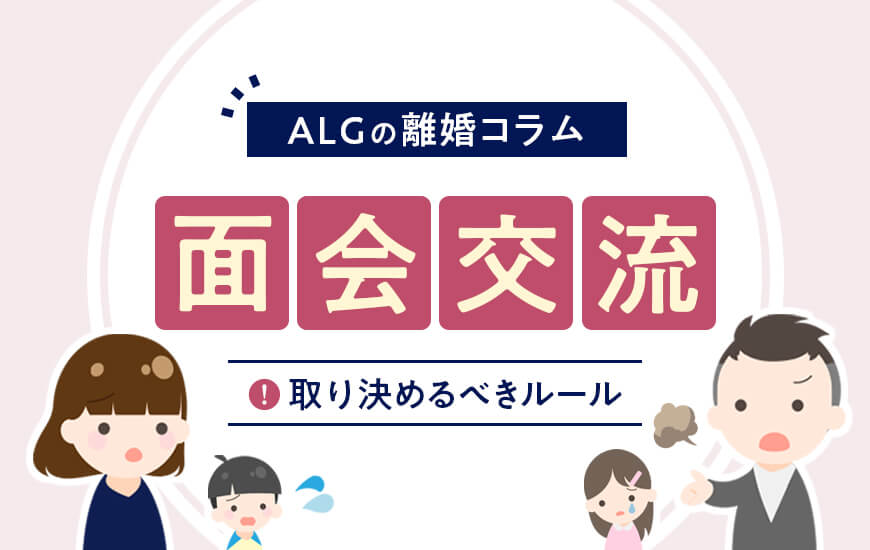面会交流調停で聞かれることは?調停を行う際の注意点や流れも解説
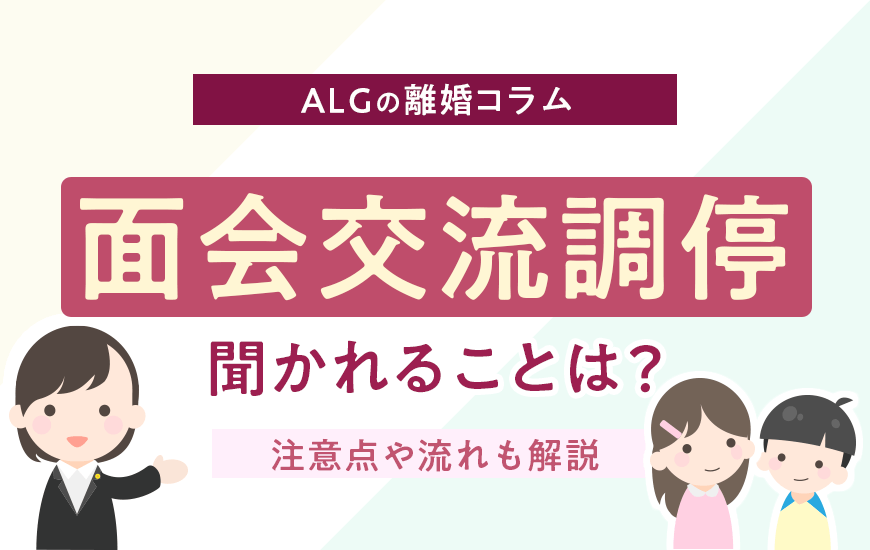
別居や離婚が理由で子供と離れて暮らすことになっても、直接会ったり電話やメールでやりとりをしたりして、定期的に親子としての交流をもつこと=面会交流ができます。
面会交流の可否や内容については父母間で話し合って決めることができますが、相手が応じてくれなかったり条件が折り合わなかったりして話し合いがまとまらない場合には、面会交流調停によって解決をはかる方法があります。
面会交流調停は家庭裁判所で行われる手続きなので、「どのように手続きを進めればよいか分からない」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、面会交流調停で聞かれることや調停の流れなど、面会交流調停の手続きについて詳しく解説していきます。
目次
面会交流調停とは
面会交流調停とは、別居や離婚によって離れて暮らす親子が定期的に交流をもてるように、面会交流について家庭裁判所で話し合いをする手続きのことをいいます。
- 相手が面会交流を拒否して、話し合いにも応じてくれない
- 面会交流の実施の可否や条件などについて相手との話し合いでは折り合いがつかない
など、父母間の話し合いで解決が難しい場合に、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てると、面会交流の可否や条件について、調停委員を介して解決に向けた話し合いが行われます。
面会交流調停で聞かれる5つのこと
面会交流調停では、まず申立人に対して、調停を申し立てた理由や経緯が確認されます。
その後、相手方に対して、申し立てられたことに対する意見や申立人の主張への反論、面会交流に応じたくないのであればその理由などが確認されます。
そのほか、面会交流を実施することが子供の幸せ(福祉)につながるのかを確認するために、申立人と相手方双方に対して、次のような事情が確認されます。
- 現在の面会交流の状況
- 子供との関係
- 離婚・別居に至った経緯
- 面会交流の条件(回数・時間・場所・方法)
- 面会交流に関して不安に思うこと
これらについて、あらかじめご自身の意見をまとめておき、調停では整理した意見を論理的に述べることが重要になります。
以下、共通して確認される事情について、もう少し詳しくみていきましょう。
現在の面会交流の状況
面会交流調停では、調停委員が問題点を整理するために、まず現在の面会交流の状況が確認されます。
具体的には、
- 離れて暮らす親子がどのくらいの頻度で交流しているのか
- 面会交流ができていない場合、いつから交流が途絶えているのか
- 面会交流が途絶えた事情や理由
といった内容が確認されたうえで、なぜ面会交流調停に至ったのか、父母双方がなにを希望しているのかを聞き取っていきます。
子供との関係
面会交流を実施することが子供の幸せ(福祉)につながるのかを確認するために、親と子供との関係についても確認されます。
具体的には、
- 離婚・別居前の子供との関わり方
- 離婚・別居後の子供との関わり方(面会交流の状況)
- 子供が面会交流を望んでいるかどうかと、その理由
などが確認されます。
たとえば、一緒に暮らしているときから親子の交流頻度が少ない場合や子供が面会交流に消極的な場合には、面会交流を実施することで子供に心理的な負担を生じさせるおそれがあることから、親子の関係性という観点から面会交流が子供の負担とならないかを判断します。
離婚・別居に至った経緯
面会交流を実施するにあたって、調停委員が父母間の問題を把握するために、離婚・別居に至った経緯についても確認されます。
- 離婚・別居に至った経緯
- これまでの父母間の感情的な対立の有無や原因
などの父母間の問題を把握したうえで、継続的な面会交流が実施できるための条件を検討していきます。
面会交流の条件(回数・時間・場所・方法)
希望する面会交流の条件についても確認されます。
- 面会交流の頻度(月に何回、何ヶ月に1回など)
- 面会交流の時間(何時から何時まで)
- 面会交流の方法や場所、および待ち合わせ方法
- その他の条件(プレゼント、宿泊、父母以外の親族との面会などの可否)
- 父母間の連絡手段 など
聞かれるのはあくまで希望する条件なので、ご自身の望んでいる率直な条件を伝えます。
ただし、子供の負担を考えず無理な条件を強固に提示することは、不利な結果を招きかねないため、避けるようにしましょう。
なお、面会交流で決めておくべきルールの詳細については、以下ページで詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
面会交流に関して不安に思うこと
面会交流に関して不安に思うことを聞かれた場合には、問題点やご自身の気持ちを整理して伝えましょう。
「相手が正当な理由なく面会交流を拒む」
「子供を連れ去られそうだから面会交流させたくない」
など、さまざまな事情があるとは思いますが、憤怒したり泣いたりして、感情のまま不安なことを伝えるだけでは、面会交流に関する問題が調停委員に正確に伝わらず、調停を有利に進めることが難しくなってしまいます。
不安に思うことは論理的に伝えるようにしましょう。
面会交流調停を行う際の注意点
面会交流調停では、面会交流は子供のためのものということを忘れずに、次のようなことに注意しましょう。
自己の利益・都合で面会交流を主張しすぎない
面会交流は子供の健全な成長のために行われるものです。別居親が自己の利益・都合だけで強固に自身の希望を主張しすぎると、子供の福祉を無視していると判断されかねません。
相手を非難しない
相手を非難ばかりしていると、父母間の感情的な対立が強くなり、継続的な面会交流の実施が難しくなってしまいます。
自分に有利な質問ばかりではない
自分にとって不利に感じるような質問をされることもあり、相手方に弁護士がいる場合には、ご自身にも弁護士がいないとより不利な状況に陥りやすくなります。
調停が不成立になることもある
面会交流調停を行えば必ず面会交流できるというわけではありません。
面会交流が制限されたり、場合によっては調停が不成立となることもあります。
面会交流が認められないケースは?
面会交流は子供が健全に成長するために不可欠と考えられていますが、面会交流を実施することで子供に悪影響を及ぼすなど、子供の福祉のために不適切と判断されると、面会交流が制限されたり、認められません。
具体的なケースをいくつか挙げてみます。
- 別居親が子供に対して暴力をふるう・育児放棄(ネグレクト)するなどの、虐待をしていた
- 別居親がDV加害者で、子供にも暴力をふるうおそれがある
- 別居親がアルコールや薬物の中毒者、あるいは重度の精神障害者で、子供に悪影響を及ぼすおそれがある
- 別居親が他者とトラブルを起こすなどして、子供に危険が及ぶおそれがある
- 別居親が面会交流時に子供を連れ去るおそれがある
- 別居親が面会交流のルールを遵守できない
- ある程度の年齢の子供(概ね10歳以上)が面会交流を拒否している など
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
面会交流調停の流れ
面会交流について父母間の協議で合意できれば調停を申し立てる必要はありません。
ですが、協議での解決が難しい場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることになります。
面会交流調停は、次のような流れで進みます。
- 面会交流調停を申し立てる
- 面会交流調停第1回期日
- 2回目以降の調停期日
- 調停成立
- 調停不成立の場合は審判に移行
以下、詳しくみていきましょう。
面会交流調停の申し立て
面会交流の調停を申し立てる場合、管轄の家庭裁判所に、申立書などの書類を提出する必要があります。
| 申立人 | 父親または母親 |
|---|---|
| 申立先 | 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所 または、当事者が合意で定める家庭裁判所 |
| 申立てに必要な費用 |
|
| 申立てに必要な書類 |
|
申立てが受理されると、2週間ほどで裁判所から父母それぞれに第1回調停期日の呼出状が送付されますので、日時や場所をしっかり確認しましょう。
面会交流調停当日の流れ
申し立てた家庭裁判所で、指定された日時に第1回の調停期日が行われます。
1回の調停にかかる時間の目安は2時間ほどで、主に次のような流れで進みます。
| ①受付・待機 |
|
|---|---|
| ②調停室入室・身分証の提示 |
|
| ③申立人の事情聴取 |
|
| ④相手方の事情聴取 |
|
| ⑤相手方と入れ替わりで申立人の入室 |
|
| ①申立人と入れ替わりで相手方の入室 |
|
| ⑦次回期日までの準備事項の指定 |
|
※同席したくないという希望がある場合には、別々に説明を受けることもあります。
2回目以降の調停期日
2回目の調停期日では、調停委員が父母双方の主張や要望を踏まえて、それぞれに対して合意に向け歩み寄るよう説得を試みます。
2回目の調停期日で合意できない場合は、必要に応じて1ヶ月~1ヶ月半に1回程度のペースで調停期日を繰り返すことになります。
調査官調査
父母の意見が対立し、なかなか合意できずに調停が難航している場合には、家庭裁判所調査官による調査(=調査官調査)が行われることがあります。
家庭裁判所調査官
家庭裁判所調査官とは、心理学や教育学などに関する専門的な知識や経験を有した裁判所の職員のことです。
面会交流の取り決めを行う際に重要な判断材料となる情報を、当事者と個別に面談するなどして調査し、明らかにする役割を担っています。
具体的には
- 父母の意向調査
- 子供の監護状況調査
- 子供の意向・心情調査
などが面談方式で行われ、必要に応じて家庭・学校訪問や試行的面会交流が行われることもあります。
調停の成立
複数回の調停を経て、父母双方が面会交流の条件について合意できれば、調停が成立します。
調停が成立すると、話し合いで取り決めた面会交流の内容を記載した調停調書が作成されます。
なお、調停調書には法的な拘束力があるため、調停で決定した内容が守られなかった場合には、履行勧告や強制執行といった法的手続きをとることが可能になります。
| 履行勧告 | 子供と離れて暮らす親からの申出を受けて、裁判所が取り決めた約束を守るように相手方を説得したり、勧告したりする制度のこと。 |
|---|---|
| 強制執行 (間接強制) |
相手方が調停で決定した内容を守らない場合は、一定期間内にその義務を履行しなければ間接強制金の支払いを命ずるなどして、自発的な債務履行を促すという制度です。 |
不成立の場合は審判に移行
調停を複数回経ても合意に至らない場合は、調停は不成立となって終了します。
調停が不成立となった場合、申立人が取り下げない限りは、自動的に審判手続きに移行します。
審判手続きでは、
- 父母双方の主張
- 提出された書面や証拠
- 調査官の調査報告
などを踏まえて必要な審理が行われ、「面会交流が子供の福祉にどのように影響するか」を最優先に考慮したうえで、最終的に裁判官が面会交流について判断を下します。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
面会交流調停を弁護士に依頼するメリット
面会交流調停はご自身だけで行うこともできますが、弁護士に依頼することで次のようなメリットを得られる可能性があります。
- 調停に同席してもらえるので、的確な主張ができる
※やむを得ない事情がある場合は、弁護士のみが出席して代理人として主張できる - 相手方の主張に対して、冷静に反論することができる
- 主張書面や証拠の提出、裁判所や相手方とのやりとりなど、煩雑な手続きを任せられる
- 譲れない条件や問題点を整理し、調停を有利にすすめるためのアドバイスが受けられる など
面会交流調停についてのお悩みがある方は、弁護士法人ALGにご相談ください!
父母の間で意見がすれ違ってしまい、なかなか面会交流が実現できない場合には、調停委員や裁判官、調査官などの第三者が関与する面会交流調停を行うことで、子供のための面会交流を実現させる方法が明確になることがあります。
とはいえ、面会交流調停は家庭裁判所で行われる手続きなので、抵抗や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
弁護士法人ALGでは、これまでに多くの親子や夫婦に関する問題に取り組んだ実績を活かし、面会交流調停の申立てを検討されている方や、調停を申し立てられてお困りの方のお力になれるようにアドバイス・サポートが行えますので、まずはお気軽にご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)