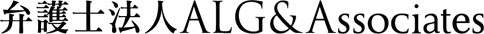個人再生ができないケースとは?失敗しないためのポイントや対処法など


個人再生は、自己破産のように財産を手放す必要がないので、「住宅などの財産を残したまま借金を大幅に減らしたい」という方におすすめの方法です。
ただし、借金を抱えている方であれば誰でも個人再生ができるわけではありません。
個人再生の条件を満たしておらず申立てが棄却されたり、再生計画案が不認可となったりして、個人再生ができないケースがあります。
本記事では、個人再生ができないケースについて、失敗しないためのポイントにも触れながら詳しく解説していきたいと思います。
個人再生ができない9つのケースとは?
個人再生とは、裁判所を介して借金を元金ごと大幅に減額してもらう手続きです。
住宅などの財産を残したまま借金を整理することができますが、手続き後は3年間(最大5年間)で残りの借金を返済していくことになるため、個人再生の利用にあたってはさまざまな条件を満たしている必要があります。
次のいずれかのケースに当てはまる方は、個人再生の申立てをしても認可してもらえないか、認可されてもメリットがなく、個人再生ができない、あるいは失敗する可能性があります。
個人再生ができない9つのケース
- 安定した収入がない
- 借金の総額が5000万円を超えている
- 借金総額が100万円未満
- 多額の財産を所有している
- 債務者の反対があった(小規模個人再生)
- 手続き費用が準備できない
- 特定の債権者だけに返済する
- 再生計画案の提出期限を守らない
- 個人再生手続き中に新たな借り入れをする
①安定した収入がない
安定した収入がないと、そもそも個人再生を利用することができません。
個人再生は手続き後も借金の支払義務が残るので、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」という開始要件があります。
正社員かどうかは問われませんが、雇用や自営による安定した収入があって、再生計画通りに最後まで支払いが継続できる見込みがなければ、個人再生を申し立てても裁判所は認めてくれません。
なお、個人再生には“小規模個人再生”と“給与所得者等再生”という2種類の手続き方法があります。
給与所得者等再生の場合は「安定した収入があること」に加えて「その変動幅が小さいこと」という特有の要件も加わり、「過去2年間の年収に20%以上の変動があるかどうか」を目安に判断されます。
②借金の総額が5000万円を超えている
住宅ローンや税金を除いた借金の総額が5000万円を超えていると、個人再生が利用できません。
個人再生は、法人向けの“民事再生”を個人向けに手続きの一部を簡略化したものです。
そのため、個人が現実的な返済計画を立てられる金額の上限として債務総額が5000万円以下であることと民事再生法によって要件が定められています。
借金の総額が5000万円を超える場合、個人再生の申立て自体認められませんが、すべての法人・個人を対象とする通常の民事再生を利用して借金を減らすことは可能です。
ただし、民事再生は手続きがより複雑で費用も高額になることから、実際には自己破産を選択するケースが多いです。
③借金総額が100万円未満
借金の総額が100万円未満の場合、個人再生をしても借金を減らすことができません。
個人再生では借金の総額に応じて最低弁済額が定められていて、住宅ローンを除く借金の総額が100万円未満の場合、そのままの金額が最低弁済額となります。
100万円未満の借金は減額されることなく、全額返済する必要があるので、個人再生をするメリットがありません。
仮に、最低弁済額を上回る金額で再生計画案を作成・提出しても認可されず、手続きは失敗となってしまいます。
そのため借金の総額が100万円未満のケースでは、任意整理で解決を図ることが多いです。
④多額の財産を所有している
多額の財産を所有していると手続き後の弁済額が高額になって、個人再生ができなくなる可能性があります。
個人再生の場合、自己破産のように財産を処分する必要はありません。
ですが、借金の総額に基づいて決まる最低弁済額を、所有している財産の総額(=清算価値)が上回る場合、清算価値が最低弁済額となって、月々の弁済額に対して収入が足りずに裁判所の認可が得られなかったり、仮に裁判所の認可が得られても途中で支払いが難しくなったりして、個人再生が失敗するおそれがあります。
だからといって、財産隠しはやめましょう。
個人再生では、自身が所有するすべての財産を正確に申告する必要があり、裁判所による財産調査も行われます。
財産隠しが発覚すると、再生計画が不認可となったり、認可された再生計画が取り消されて一括返済を求められたりして、さまざまなリスクを負うことになります。
⑤債権者の反対があった(小規模個人再生)
小規模個人再生の場合、債権者の過半数から反対(不同意)があると認可が得られずに個人再生ができなくなります。
小規模個人再生では、債権者に対して「再生計画案に同意するかどうか」を問う書面決議が行われます。
書面決議において、「債権者の半数以上」または「債権額の半数を超える債権者」からの反対(不同意)がある場合、再生計画は不認可となって個人再生手続きが廃止されます。
債権者から不同意の書面が出されるケースはそれほど多くありませんが、特定の債権者が債権額の多数を占める場合などでは注意が必要です。
⑥手続き費用が準備できない
裁判所へ支払う手続き費用が準備できないと、個人再生の申立てが棄却されてしまいます。
個人再生を申し立てるにあたっては、裁判所費用として2~3万円程度が必要になります。
- 申立手数料(収入印紙):1万円程度
- 予納金(官報公告料):1万3000円程度
- 郵便切手代:2000~5000円程度
これら裁判所費用のほか、個人再生の手続きを弁護士に依頼すると弁護士費用として50万~60万円程度が追加で必要となります。
弁護士に依頼せずに個人再生をご自身で行う場合、弁護士費用を準備する必要はなくなりますが、多くのケースで個人再生手続きをサポート・監督する“個人再生委員”が選任され、その報酬として15万~25万円程度の費用がかかります。
このような費用を準備できないと手続きを進めることができずに申立てが棄却となり、個人再生はできなくなります。
⑦特定の債権者だけに返済する
手続き中に特定の債権者だけに返済すると、個人再生ができなくなるおそれがあります。
個人再生では、すべての債権者に平等に対応する必要があり、手続き中に特定の債権者だけに返済する行為(=偏頗(へんぱ)弁済)は禁止されています。
手続き中に特定の債権者を優先して返済してしまうと、偏頗弁済した分だけ最低弁済額が増える可能性があるだけでなく、最悪の場合、個人再生の申立てが棄却されるおそれもあります。
親族や友人・知人からの借り入れは、迷惑をかけたくないからという理由で優先的に返済したくなるお気持ちもわかりますが、偏頗弁済は個人再生が失敗となる原因となり得るため、十分に注意しましょう。
⑧再生計画案の提出期限を守らない
裁判所から指定された期限までに再生計画案が提出できないと、手続きが廃止されてしまいます。
再生計画案とは、「個人再生手続きで減額してもらった借金を具体的にどのように返済していくのか」という借金の返済計画を定めた書面のことです。
個人再生を行う債務者自身が作成し、裁判所の認可を得ることで個人再生が成立します。
再生計画案は、民事再生法で定められた基準に従って適切な内容で作成する必要があり、作成や資料収集に時間がかかることも少なくありません。
ですが、提出期限を1日でも遅れてしまうと手続きは廃止され、個人再生ができなくなってしまいます。
これは、裁判所から提出した再生計画案の追完を指示された場合も同様で、補正した再生計画案の提出が1日でも遅れてしまうと手続きが廃止となるため、余裕をもって準備する必要があります。
⑨個人再生手続き中に新たな借り入れをする
手続き中に新たな借り入れをすると、個人再生の申立てが棄却される可能性があります。
個人再生の手続きを弁護士に依頼し、債権者へ受任通知が送付された後に新たな借り入れをすると、「支払不能な状態にあるにもかかわらず返済できるかのように装ってお金を借りた詐欺的な行為」とみなされ、申立てが棄却され、個人再生ができなくなる可能性があります。
それだけでなく、最悪の場合は詐欺罪に問われるおそれもあるので、個人再生の手続きを弁護士に依頼した後はクレジットカードの使用を含め、新たな借り入れをしないように注意しましょう。
お問合せ
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
- 24時間予約受付
- 年中無休
- 通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
個人再生の手続きで失敗しないためのポイント
個人再生の手続きに不備があったり、不誠実な対応をとったりすると、個人再生が失敗してしまう可能性があります。
そこで、個人再生の手続きで失敗しないための3つのポイントを紹介していきます。
- 個人再生の条件や棄却・却下事由を確認する
- 無理のない返済計画案を作る
- 弁護士へ相談する
個人再生の条件や棄却・却下事由を確認する
個人再生手続きの準備をするにあたって、「借金の総額が5000万円を超えていないか」、「再生計画に従って返済できる程度の安定した収入はあるか」など、個人再生の条件を満たしているかを確認しておきましょう。
あわせて、申立ての棄却・却下事由についてもあらかじめ確認しておくことで失敗を防ぐことができます。
個人再生の申立棄却事由
- 費用の予納がないとき
- 破産手続が進行していて、破産手続によることが債権者に利益があると考えられたとき
- 再生計画案の作成・可決・認可の見込みがないことが明らかであるとき
- 不当な目的で申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき
個人再生の条件を満たしていない場合や、申立棄却事由に当てはまる場合、個人再生ができない可能性が高いので任意整理または自己破産を検討する必要があります。
無理のない再生計画案を作る
個人再生で失敗しないためには、無理のない再生計画案を作ることも大切です。
実現不可能な返済計画は、個人再生が失敗する原因になります。
ご自身の収支をきちんと把握したうえで、最低弁済額や返済期間などを考慮し、収入に見合った無理のない返済計画案を作成して完済を目指すことが大切です。
個人再生の再生計画案は、民事再生法で定められた基準に従って適切な内容で作成する必要があるので、無理に自分だけで作成しようとせず、弁護士などの専門家に相談しながら作成することをおすすめします。
弁護士へ相談する
個人再生を検討している場合、債務整理手続きに詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、個人再生ができるかどうかのアドバイスだけでなく、代理人として個人再生手続きをサポートすることもできます。
弁護士ができること
- 借金や収入などの状況から、最適な借金問題の解決方法を提案できる
- ご依頼者様に代わって裁判所や債権者とのやりとりが行える
- 申立てに必要な書類の準備や、再生計画案の作成のサポートができる
- 弁護士が受任通知を送付することで、借金の取り立てをストップできる など
個人再生ができない場合の対処法
他の債務整理の方法を検討する
個人再生ができない場合、任意整理や自己破産など他の債務整理の方法も検討しましょう。
任意整理とは?
任意整理とは、裁判所を介さずに直接債権者と交渉をして、借金返済の負担軽減を図る方法です。
借金の元金までは減額されませんが、手続きの対象とする借金を選べて周囲に知られにくいという特徴があります。
- 借金の総額が100万円以下の場合
- 多額の財産を所有している場合
- 親族や友人からの借り入れを優先的に返済したい場合 など
自己破産とは?
自己破産とは、裁判所に破産を申し立てて免責の許可を得ることで、借金の支払義務を免除してもらう方法です。
高額な財産は手放すことになりますが、免責の許可が得られればすべての借金がゼロになります(税金などの非免責債権を除く)。
- 借金の総額が5000万円を超える場合
- 安定した収入が見込めない場合 など
任意整理と自己破産は、それぞれにメリット・デメリットがあるため、慎重に検討する必要があります。
詳しくは次のページをご参考ください。
さらに詳しく任意整理のメリットとデメリット再度個人再生を申し立てる
個人再生が失敗してしまった場合、再度個人再生を申し立てることも可能です。
再度、個人再生を申し立てるにあたっては、「個人再生ができなかった原因」を特定し、次のような対策を講じて原因を解消することが重要になります。
- 就職・転職や副業で収入を増やし、安定した収入を確保する
- 返済費用や個人再生手続きにかかる費用を積み立てる
- 収支を見直して、再生計画を立て直す など
個人再生はできないと諦める前に弁護士へご相談下さい
個人再生をすると借金を元金ごと大幅に減らせる分、さまざまな条件をクリアする必要があります。
「個人再生の条件を満たしていないかもしれない」
「申立棄却事由に該当するかもしれない」
など、個人再生はできないと諦める前に、債務整理に詳しい弁護士に相談してみましょう。
弁護士であれば、個人再生ができるかどうかの判断はもちろん、ご相談者様の状況に合った借金問題の解決策を提案することができます。
個人再生の手続きに不安がある場合は、弁護士が代理人となって各手続きをサポートすることも可能なので、個人再生を検討されている方や、個人再生が失敗してしまった方も、一度弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。
お問合せ
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
- 24時間予約受付
- 年中無休
- 通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。