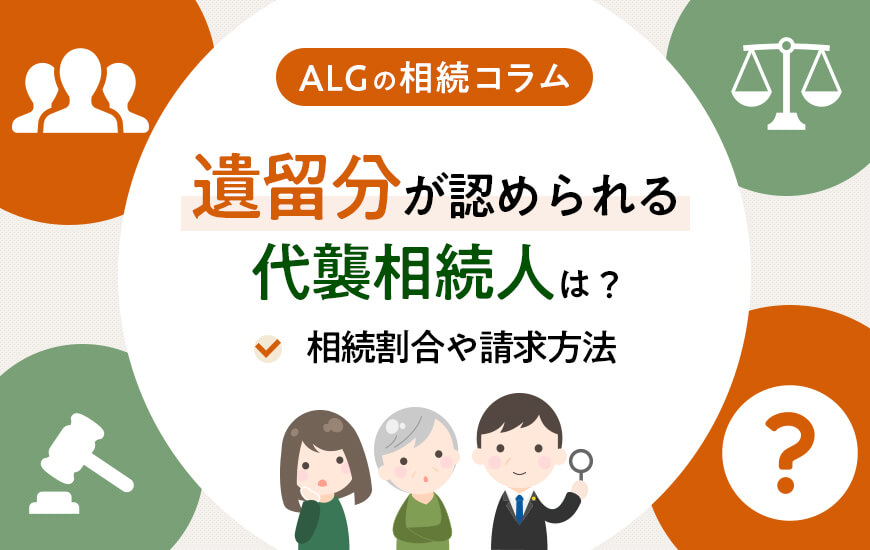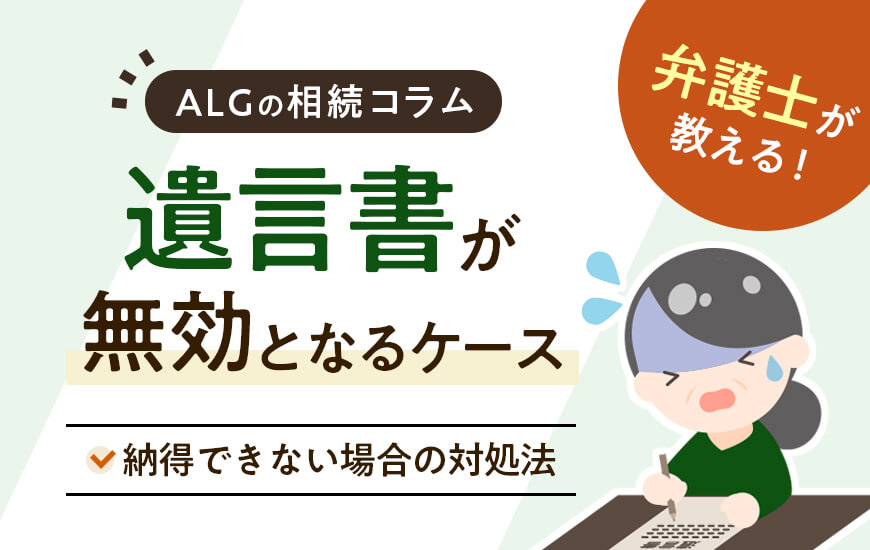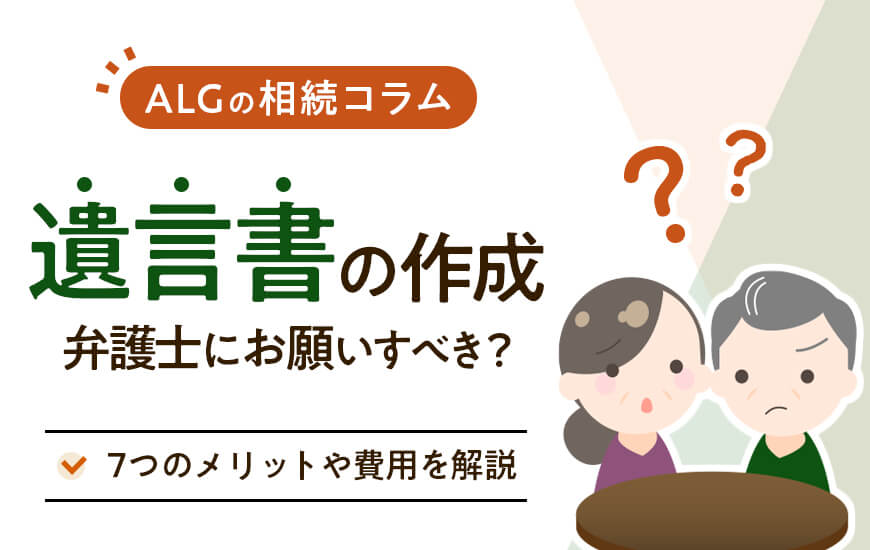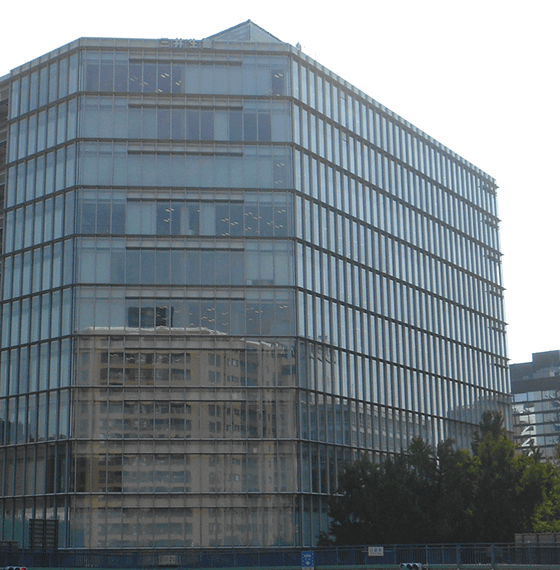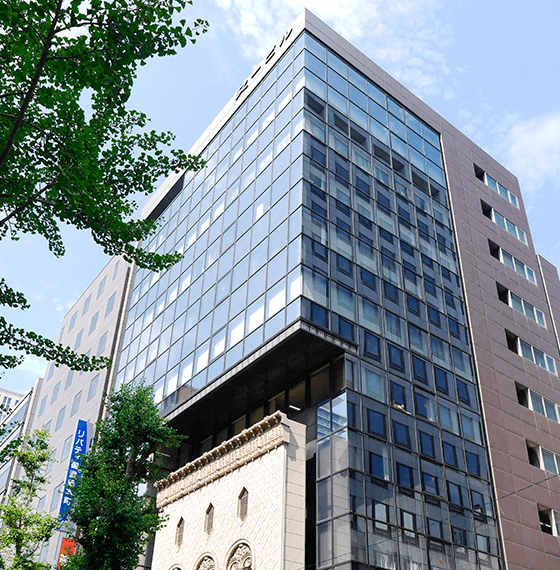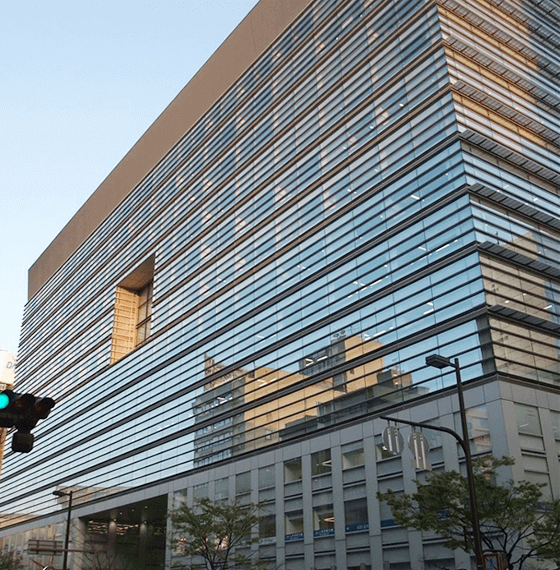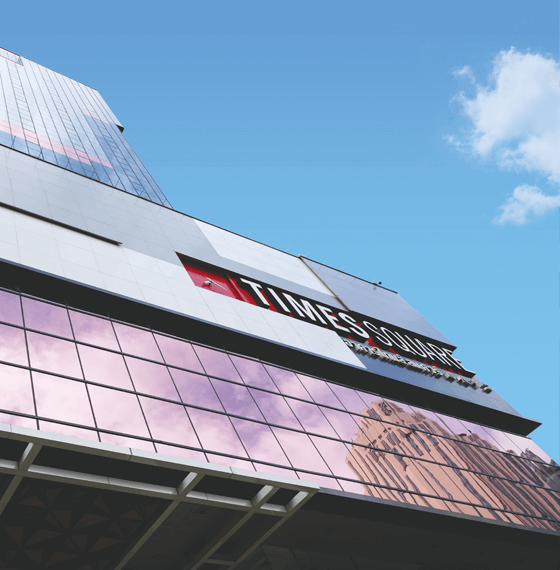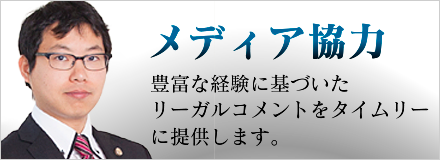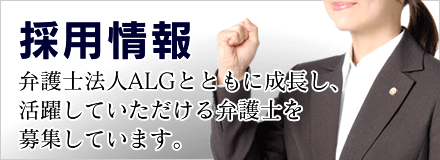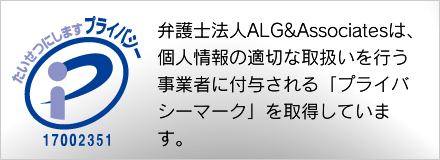兄弟に遺留分はない|3つの理由と相続する方法を弁護士が解説
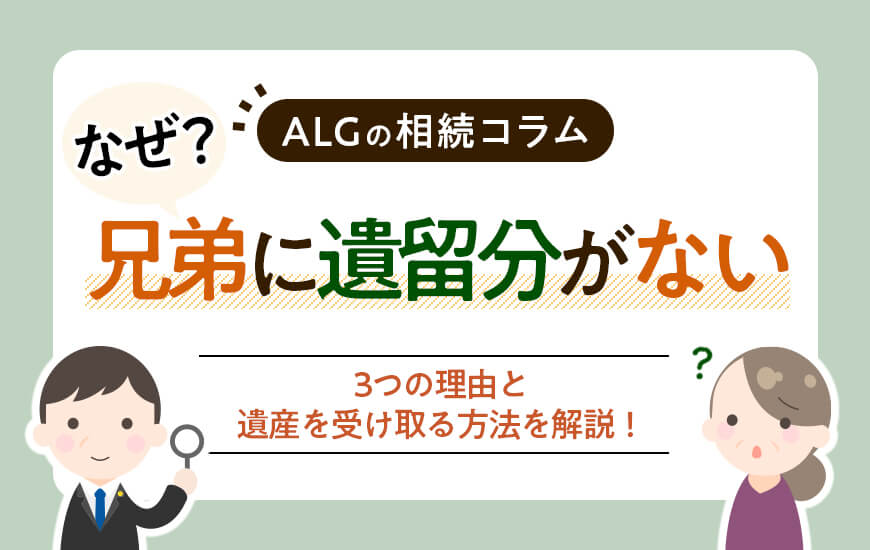
「兄弟に遺留分がない」と聞いて驚いた方も多いのではないでしょうか。
遺留分とは、特定の相続人に法律で保障された、最低限の遺産の取り分のことです。しかし、兄弟姉妹にはこの遺留分が認められていません。
なぜ兄弟だけが対象外なのか、その理由は民法の規定と制度の趣旨にあります。
この記事では、兄弟に遺留分がない理由や、遺留分がない兄弟が遺産を受け取るための方法についてわかりやすく解説します。
兄弟姉妹の相続について正しく理解し、トラブルを防ぐために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
なぜ兄弟姉妹に遺留分はないのか?
相続において、被相続人(亡くなった方)の兄弟や姉妹には遺留分がありません。遺留分とは、法律で一部の法定相続人に保障された、最低限もらえる遺産の取り分のことです。
配偶者や子供、親にはこの権利がありますが、兄弟姉妹には認められていません。
たとえば、「財産をすべて友人に渡す」という遺言があった場合、配偶者や子供、親は遺留分を請求することができます。
しかし、兄弟姉妹はこの権利がないため、遺言書に名前がなければ一切の遺産を受け取れない可能性があります。
兄弟姉妹が遺産を確実に受け取りたい場合は、遺言書で指定してもらう、または生前贈与を受けるなどの対策が不可欠です。
以下では、なぜ兄弟姉妹に遺留分がないのか、その理由について詳しく解説します。
兄弟は被相続人と関係が遠いから
法定相続人の相続順位は、次のように定められています。
- 配偶者は必ず相続人になる
- 第1順位:子
- 第2順位:両親等
- 第3順位:兄弟姉妹
このように、兄弟姉妹は相続順位からみると最も遠い関係であり、相続する可能性は高くないと考えられます。
そのため、優先度の低い兄弟姉妹は相続割合も低く設定されており、遺留分も設けられていません。
兄弟には代襲相続があるから
相続には代襲相続という仕組みが設けられています。
代襲相続とは、相続人になる予定だった人が被相続人よりも先に亡くなってしまった場合に、亡くなった人の子が代わりに相続人になる制度です。
もしも兄弟姉妹に遺留分を認めてしまうと、兄弟姉妹の代わりに相続する甥や姪の遺留分も認めることになるため、侵害された遺留分に相当する金銭を請求されてしまうおそれがあります。
そのため、被相続人との関係が遠い甥姪によって遺言書の効力が否定されることを防ぐために、兄弟姉妹の遺留分は認められていないと考えられます。
合わせて読みたい関連記事
生活に影響がないと考えられているから
被相続人と兄弟姉妹は年齢が近く、一方が一方を養っていることは少ないため、経済的に自立しておりお互いの財産を相続できなくても生活に支障はないと考えられます。
そのため、最低限の相続分を保障するための遺留分は設けられていません。
遺留分のない兄弟が遺産を相続する方法
兄弟姉妹には遺留分がないため、相続で財産を受け取る方法として、主に以下の4つがあげられます。
- 寄与分の請求を行う
- 遺言書の無効を主張する
- 遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行う
- 生前に遺言書を作成してもらう
寄与分の請求を行う
兄弟姉妹が法定相続人である場合には、寄与分が認められる可能性があります。
寄与分とは、被相続人の財産を維持・増加させるために特別の貢献をした人に認められる、追加的な相続財産の取り分です。
寄与分が認められる相続人は、被相続人の介護や事業の手伝い等を無償または低額の報酬によって行い、通常の扶養等を上回る貢献をしている者に限定されます。
ただし、遺言書によって遺贈された相続財産の相当額を、寄与分の請求によって取り戻すことはできません。また、これが認められるためには、特別な貢献を行った証拠を集める必要があります。
遺言書の無効を主張する
被相続人が遺言書を作成しており、その内容に従うと兄弟姉妹が財産を受け取れない場合は、遺言書の無効を主張できないか検討しましょう。
無効が認められれば、遺言書の効力は失われ、相続人全員による遺産分割協議が可能となります。
その結果、兄弟姉妹が法定相続分に従って遺産を受け取れる可能性が高まります。
無効を主張する際は、まず相続人同士で話し合い、それでも解決しなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停でも合意できない場合は遺言無効確認訴訟を提起する流れになります。
遺言書が無効だと主張できる主なポイントは次のとおりです。
- 認知症など、被相続人の遺言能力に問題がある状態で書かれている
- 遺言書の形式に不備がある
- 遺言書が偽造、変造されている
- 詐欺や脅迫によって書かされた遺言書である
- 遺言書の内容が公序良俗に反している
遺言書の無効について詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行う
遺言書がある場合、基本的にその内容に従って相続が行われます。
しかし、相続人全員が同意すれば、遺言書と異なる内容で遺産分割をすることも可能です。
この方法を遺産分割協議といい、相続人全員の参加と合意が条件です。
たとえば、遺言書で兄弟姉妹が相続から外されていても、他の相続人が同意すれば、兄弟姉妹にも遺産を分けることができます。
協議成立には相続人全員の署名・押印をした協議書が必要で、登記や金融機関の手続きにも使われます。
兄弟姉妹が遺産を受け取るには、他の相続人と遺産分割協議を行い、全員の同意を得ることが必要です。
生前に遺言書を作成してもらう
兄弟姉妹には遺留分がないため、確実に遺産を受け取りたい場合は、生前に被相続人に遺言書を作成してもらうことが重要です。
遺言書に「兄弟姉妹に財産を相続させる」と明記されていれば、他の相続人がいてもその意思が尊重されます。
特に被相続人が実家を守るために兄弟姉妹やその子供に財産を残したい場合など、どうしても相続財産の一部が必要な事情があるなら、生前にしっかり話し合っておくことが大切です。
遺言書を作成する際は、弁護士への相談をおすすめします。弁護士なら法律要件を満たした有効な遺言書を作成でき、無効リスクを防げます。
また、被相続人の意思を尊重しつつ、相続人間のトラブルを防ぐ内容に調整してくれる点もメリットです。
さらに、財産の分け方や税金対策など専門的なアドバイスも受けられるため、スムーズな相続手続きが可能になります。
遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットについての詳細は、こちらの記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
遺留分のない兄弟が相続人になるケースと相続割合
兄弟姉妹には遺留分はありませんが、法定相続人として第3順位に位置しています。そのため、一定の条件を満たせば遺産を相続することが可能です。
たとえば、被相続人に配偶者がいて、子供や親といった直系尊属がいない場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹となります。
この場合、配偶者が遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を受け取り、兄弟姉妹が複数いるときは、この4分の1を人数で均等に分けます。
また、被相続人に配偶者や子供、直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹だけが相続人となり、遺産のすべてを兄弟姉妹で平等に分割することになります。
相続税の2割加算に注意!
兄弟姉妹が財産を相続した場合は、相続税の2割加算が適用されるため、配偶者や子等が相続する場合よりも相続税額が増えるケースが多いです。
相続税の2割加算とは、相続する可能性が低かった人が相続人になったり、遺贈されたりした場合に、相続税額を2割上乗せする制度です。
相続する可能性が低かった相続人は、相続税を多く徴収しても困窮するリスクが低いと考えられること等から適用されます。
兄弟姉妹だけでなく、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていた場合に、代襲相続した甥姪も相続税の2割加算の対象となります。
兄弟の遺留分について不明点があれば一度弁護士にご相談ください
兄弟姉妹は遺留分を持たないため、遺言書で全財産を他の人に譲ると書かれてしまうと、財産をまったく相続できないおそれがあります。
しかし、被相続人との関係によっては納得できない方もいるでしょう。
そのような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、遺言書が無効となる可能性や、相続できる方法について法的観点から検討できます。
さらに、兄弟姉妹に確実に財産を残したい方にとっても、弁護士は心強い存在です。
被相続人の意思を尊重しながら、法的に有効な遺言書の作成や生前の相続対策などについてもアドバイスできるため、円滑で安心な相続を実現できます。
兄弟の遺留分について不明点があれば、一度弁護士にご相談ください。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)