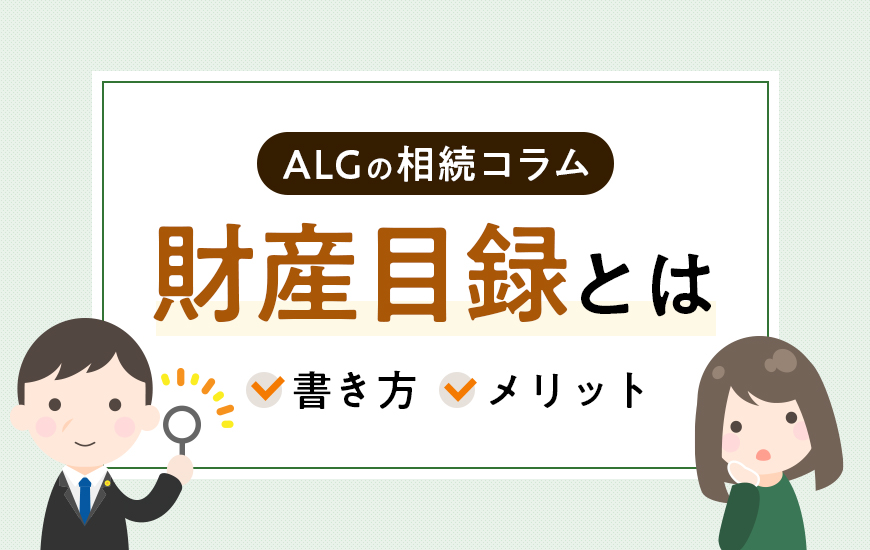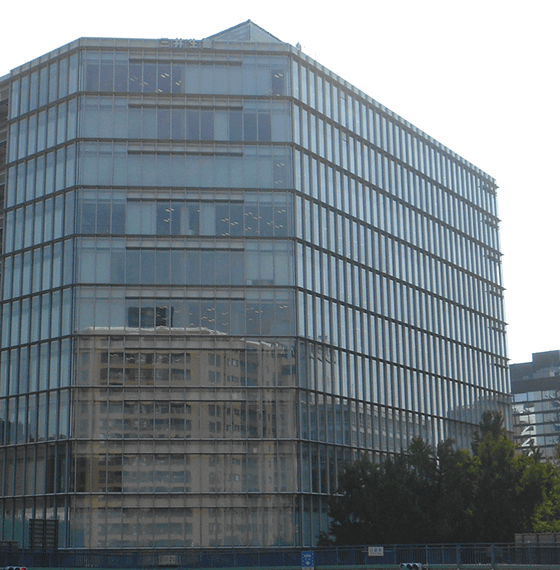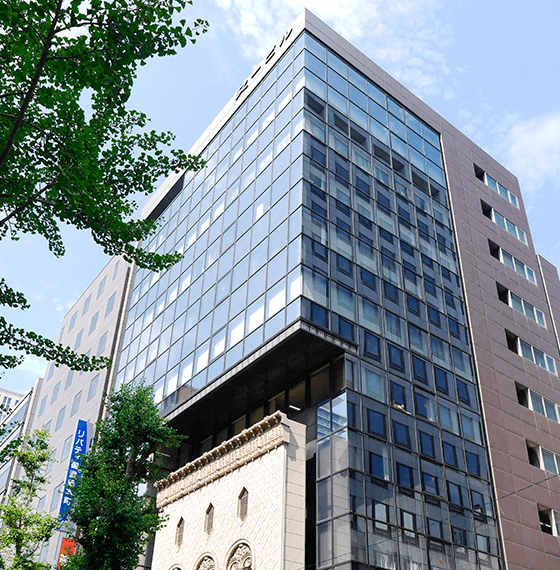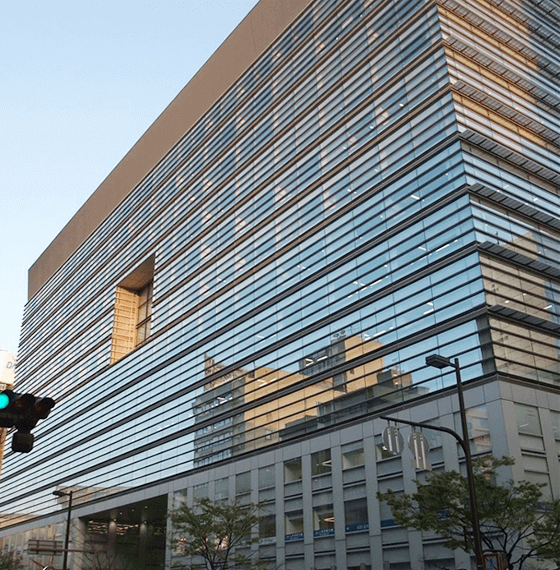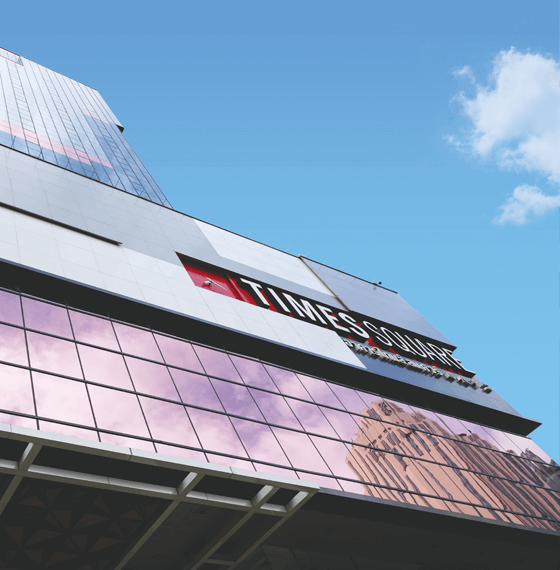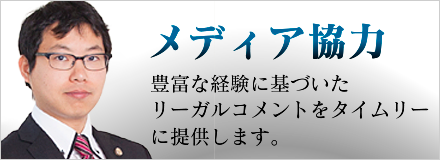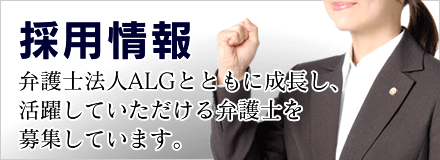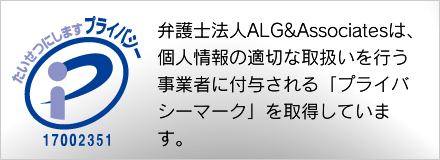遺産分割協議書の作成に必要な書類は?有効期限や注意点など
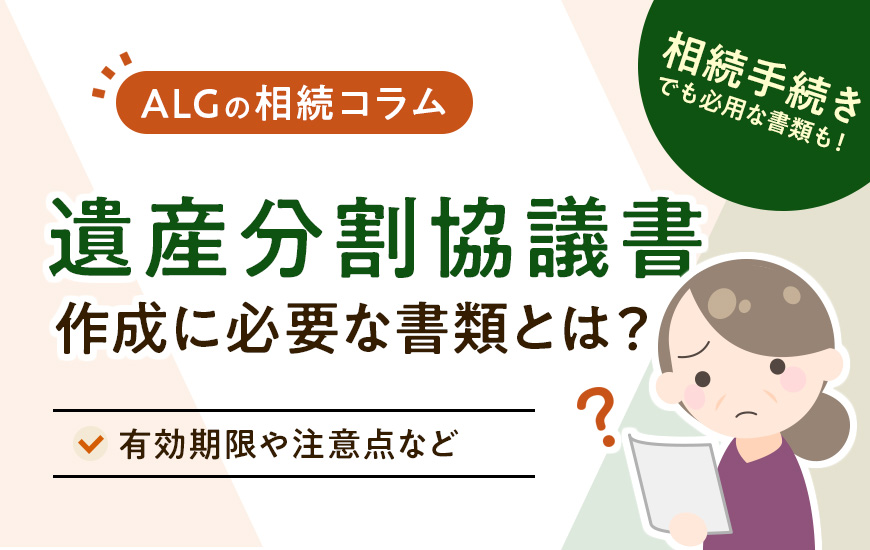
この記事でわかること
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その内容を文書にまとめたものです。
預金や不動産の名義変更など、相続手続きに欠かせない大切な書類ですが、作成には戸籍謄本や印鑑証明書など、さまざまな書類の準備が必要になります。
さらに、協議書を使って手続きを進める際には、不動産の謄本など、財産の種類に応じた追加書類も求められます。
この記事では、遺産分割協議書の作成に必要な書類、そして実際の相続手続きで必要となる書類まで詳しく解説します。
目次
遺産分割協議書を作成するための必要書類
遺産分割協議書を作成する際に必要な書類として、主に以下があげられます。
- 被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本等
- 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
- 全ての相続人の戸籍謄本
- 全ての相続人の印鑑登録証明書
- 預貯金や不動産など遺産の内容がわかる書類
- 財産目録
- 遺言書がある場合は遺言書
- 相続放棄者がいる場合は、相続放棄申述受理証明書
被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本等
遺産分割協議書を作成する際に最も重要なのは、相続人を正確に確定することです。
相続人を間違えてしまうと、協議が無効になり、後でトラブルになる可能性があります。
そのため、まずは被相続人が生まれてから亡くなるまでの身分関係を証明する書類を集めなければなりません。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、 改製原戸籍謄本を漏れなく収集することが必要です。
これらの書類を通じて、婚姻や離婚、認知、転籍、養子縁組など、被相続人の人生におけるすべての身分事項を確認し、隠れた相続人がいないかを調査します。
戸籍謄本
戸籍謄本とは、戸籍に記載されている家族全員の身分事項を証明する書類です。
戸籍には、出生や結婚、死亡といった個人の一生が記録されています。日本の戸籍は夫婦と未婚の子を単位として編成され、その写しが戸籍謄本です。
2024年3月からは戸籍法の改正により、本籍地が遠方にあっても、最寄りの市区町村役場で戸籍を取得できるようになりました。
ただし、取得者の兄弟姉妹の戸籍を請求する場合や、代理人による申請、郵送での請求は、従来どおり本籍地の役所で手続きする必要があります。手数料は1通450円程度です。
除籍謄本
除籍謄本とは、かつて家族が記載されていたが、婚姻や死亡、転籍などによって全員が抜け、誰も残っていない状態になった戸籍の写しです。
戸籍には通常、父母や子供などの家族が記載されていますが、結婚して新しい戸籍を作ったり、亡くなると元の戸籍から外れます。
このことを除籍といいます。また、本籍地を移したり、結婚や死亡により全員が戸籍から抜けると、その戸籍は閉鎖されますが、この閉鎖された戸籍のことも「除籍」と呼びます。
除籍謄本も、基本的に最寄りの市区町村役場の窓口で取得できます。
ただし、兄弟姉妹の除籍謄本を取得する場合や、代理人による取得、または郵送での手続きについては、引き続き本籍地の役場で行う必要があります。手数料は1通およそ750円です。
改製原戸籍謄本
改製原戸籍謄本とは、戸籍法の改正によって現在の形式に変更される前の古い戸籍の写しです。
日本の戸籍制度は昭和22年の家制度廃止や平成6年のコンピュータ化など、これまで何度も改正されてきました。
この改製時に一部の情報が新しい戸籍に引き継がれないため、過去の婚姻歴や養子縁組、認知などを確認する際に必要となります。
取得は基本的に最寄りの市区町村役場で可能ですが、兄弟姉妹のものを請求する場合、代理人申請、郵送請求は本籍地の役場で手続きが必要です。手数料は1通約750円です。
被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
遺産分割協議書には、被相続人の最後の住所を正確に記載する必要があります。その確認に使われるのが住民票の除票または戸籍の附票です。
住民票の除票は、転出や死亡により住民登録が削除された住民票で、被相続人の最終住所を確認できます。一方、戸籍の附票は、その戸籍に在籍していた期間の住所履歴を記録した書類で、不動産登記簿の住所と最後の住所が異なる場合などに必要です。
住民票の除票は、被相続人の最後の住所地の市区町村役場で、戸籍の附票は、被相続人の本籍地の役場で取得できます。手数料は1通200円~400円程度です。
全ての相続人の戸籍謄本
遺産分割協議書を作成する際に、相続人全員の戸籍謄本は必ずしも必要ではありません。ですが、相続登記や預貯金の名義変更など、後の手続きで求められることが多いため、協議書を作る段階でそろえておくと安心です。
また、被相続人が亡くなった時点で、相続人と同じ戸籍に記載されている場合は、その戸籍謄本を一緒に使うことができます。
たとえば、配偶者や未婚の子が同じ戸籍にいる場合は、別に戸籍を取り寄せる必要はありません。
全ての相続人の印鑑登録証明書
遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。
しかし、実印を押しただけでは、その印鑑が本当に本人のものか確認できません。そこで必要になるのが、印鑑登録証明書です。
印鑑登録証明書を添付することで、押印された印鑑が市区町村に登録された実印であることを証明し、相続人本人の意思で協議書に署名・押印したことを裏付けることができます。
印鑑登録証明書は、相続人の住民登録地の市区町村役場で取得できます。手数料は1通200円~400円程度です。
預貯金や不動産など遺産の内容がわかる書類
遺産分割協議書を作成する際には、相続財産の内容を正確に記載する必要があります。そのため、被相続人が残した財産を特定できる書類を事前にそろえておくことが重要です。
代表的なものは次のとおりです。
- 預貯金:預貯金通帳、口座残高証明書、定期預金証、利息計算書など
- 不動産:不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産評価証明書、公図、地積測量図など
- 自動車:自動車検査証(車検証)
- 有価証券:証券会社の残高証明書や取引報告書など
- その他財産:貴金属や書画、骨董品の鑑定書、ゴルフ・リゾート会員権の会員権証書など
- 負債:借入金残高証明書など
財産目録
財産目録は、遺産分割協議書作成の必須書類ではありません。
しかし、遺産の種類が多い場合などには、遺産を一覧にした財産目録を作成しておくと便利です。
預貯金や不動産、自動車、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も一覧化することで、遺産の全体像を把握しやすくなります。
その結果、遺産分割協議がスムーズに進み、トラブル防止にもつながります。また、相続税の申告や金融機関・法務局での手続きにも役立つため、作成をおすすめします。
財産目録の作成方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
遺言書がある場合は遺言書
遺産分割協議書を作成する際は、遺言書の有無を確認することが重要です。
遺言書があれば、基本的にその内容に従って遺産を分けるため、遺産分割協議や協議書は不要です。
一方で、遺言書に記載されていない財産がある場合や包括遺贈であった場合、相続人全員が合意して遺言と異なる分割をするなどの場合は、協議と協議書の作成が必要になります。
自筆証書遺言は法務局や自宅、貸金庫に、秘密証書遺言は自宅や貸金庫に保管されていることが多く、公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、正本は自宅や貸金庫に保管されていることが多いです。
相続放棄者がいる場合は、相続放棄申述受理証明書
相続放棄申述受理証明書とは、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、正式に受理されたことを証明する書類です。
これにより、その人が法律上、相続人でなくなったことが明確になります。なお、同様の証明となる書類として、相続放棄申述受理通知書もあります。 これらの書類は、遺産分割協議書を作成するための必須書類ではありません。
しかし、相続人の中に放棄した方がいる場合は、証明書を提示してもらうと安心です。
なぜなら、相続放棄をしたと口頭で言われても、裁判所での手続きが完了していなければ、その人は依然として相続人のままだからです。
その状態で遺産分割協議を進めると、協議自体が無効になったり、後々トラブルに発展する可能性があります。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
遺産分割協議書を使用する相続手続きと必要書類
遺産分割協議書は、以下のような相続手続きで必要となります。
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 預金の払い戻し
- 自動車の名義変更
- 証券会社での手続き
- 相続税の申告
これらの手続きに共通して求められる書類は、以下のとおりです。
【共通書類】
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続放棄申述受理証明書または相続放棄申述受理通知書(相続放棄者がいる場合)
続いて、手続きごとに追加で必要となる書類について詳しく説明します。
相続登記
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に法務局で相続登記の手続きを行う必要があります。
手続きには戸籍などの基本書類に加えて、次の書類が必要です。
- 相続登記申請書
法務局に提出する書類で、登記の目的や原因、相続人の氏名・住所、登録免許税、不動産情報などを記載します。ひな型や記載例は法務局のサイトからダウンロードできます。 - 不動産を相続する人の住民票
登記簿に記載する新しい所有者の住所を証明するために必要です。 - 固定資産評価証明書
登録免許税の計算に使用します。相続登記申請時の年度のものを、不動産所在地の市区町村役場や都税事務所で取得します。
相続登記について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
預金払戻し
亡くなった方の預貯金口座は、金融機関に死亡の連絡をすると凍結されます。
凍結解除や払い戻しを行うには、相続人が金融機関で手続きを行う必要があります。手続きには、戸籍などの共通書類以外に、次の書類が求められます。
- 預金名義変更依頼書
金融機関の窓口や郵送で取り寄せ可能です。遺産分割協議書に預貯金の取得者が明記されている場合は、通常、その取得者だけが手続きを行えば問題ありません。 - 被相続人の預貯金通帳、キャッシュカード
預貯金の相続手続きでは、被相続人名義の通帳やキャッシュカードの返却が求められます。紛失している場合は、金融機関に照会を依頼できます。
自動車の名義変更
亡くなった方が所有していた自動車を相続する場合、名義変更の手続きが必要です。
普通自動車と軽自動車など、車の種類によって手続き先や必要書類が異なりますが、ここでは、普通自動車について説明します。
普通自動車の名義変更は、新しい所有者の住所を管轄する運輸支局で行います。戸籍などの共通書類に加え、以下の書類が必要です。
- 移転登録申請書
運輸支局に提出する書類です。運輸支局の窓口や国土交通省のサイトで入手できます。 - 自動車検査証(車検証)
車の登録番号や車台番号など、名義変更に必要な情報を確認するために使います。 - 新所有者の車庫証明書
相続により車の保管場所が変わる場合に必要です。相続人の住所を管轄する警察署で申請し、発行までに約1週間かかります。
証券会社での手続き
被相続人の有価証券(株式や投資信託など)を相続するには、証券会社で名義変更の手続きを行う必要があります。手続きをしないと、売却や配当金の受け取りができません。
手続きには、遺産分割協議書などの共通書類に加えて、次の書類が求められます。
- 相続手続依頼書
証券会社の窓口や郵送で取り寄せることができます。 遺産分割協議書に、どの相続人が有価証券を取得するか明記されていれば、通常はその取得者のみが署名・押印などの手続きを行えば足ります。
相続税の申告
相続税の申告は、遺産の評価額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に基本的に必要です。申告にあたっては、戸籍などの基本書類に加えて、次の書類を準備します。
- 相続税の申告書
国税庁のサイトからダウンロードできます。 - 遺言書または遺産分割協議書の写し
遺産の分割方法を確認するために必要です。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済証明書も添付します。 - 財産に関する書類
預貯金残高証明書、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、株式や投資信託の評価証明書など - 特例適用に関する書類
小規模宅地等の特例や配偶者控除などの軽減措置を受ける場合、戸籍や住民票など特例に応じた必要書類や、申告期限後3年以内の遺産分割見込書の提出が必要です。
遺産分割協議書や必要書類の有効期限
遺産分割協議書には有効期限がなく、一度作成すれば将来にわたり効力を持ちます。
ただし、協議書に添付する書類には期限の有無があります。たとえば、除籍謄本や改製原戸籍謄本には有効期限はありません。これらは過去の事実を証明するもので、今後内容が変わることはないためです。一度取得すれば、基本的に再取得の必要はありません。
一方、現在の戸籍謄本や印鑑証明書、住民票など、相続人の現状を示す書類は、今後変更される可能性があるため、有効期限が設けられています。金融機関や不動産登記の手続きで提示する際、発行から3ヶ月以内や6ヶ月以内であることを条件とするケースが多いです。
必要書類の取得は、手続きのタイミングを踏まえて計画的に行うことが必要です。
遺産分割協議書の必要書類を集める際の注意点
遺産分割協議書を作成する際は、相続人を正確に確定するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集し、改正前の戸籍も取得しましょう。
戸籍や印鑑証明書などは、協議書作成だけでなく相続手続き全体を見据えて必要部数を準備することが大切です。
また、相続人に未成年者がいる場合、親権者が利益相反となるときは家庭裁判所に特別代理人を申し立てる必要があります。
さらに、認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合は、成年後見人の選任も求められます。
特別代理人や成年後見人の選任には時間を要するため、相続税の10ヶ月以内の申告期限を考慮し、早めに手続きを進めることが必要です。
必要書類集めは弁護士へ依頼できる
遺産分割協議書を作成するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や財産を特定する資料など、多くの書類をそろえる必要があります。
しかし、これらを自力で集めるのは非常に手間がかかります。役所や金融機関に何度も足を運ぶ必要があるうえ、必要部数や有効期限を間違えると、再取得が必要になることもあります。
さらに、書類に不備があると、相続登記や預貯金の名義変更などが進まず、相続税の申告期限に間に合わないリスクもあります。
自分で集めるのが難しいと感じた場合は、弁護士への依頼が有効です。弁護士なら、遺産分割協議や相続手続きに必要な書類を代理で収集することができます。
遺産分割協議書の必要書類についてご不安な方は、弁護士法人ALGへご相談ください!
遺産分割協議書を作成するには、戸籍謄本や印鑑証明書など、正確な書類の準備が欠かせません。
ただし、必要書類の収集には時間と労力がかかり、もし漏れや間違いがあると、相続登記や預貯金の払い戻しなどの手続きが進まなくなる可能性があります。さらに、相続税の申告期限は10ヶ月と短く、準備の遅れは大きな負担につながります。
こうした不安を解消するために、弁護士法人ALGでは、必要書類の収集から遺産分割協議書の作成、相続手続き全般まで一括してサポートいたします。
専門知識を持つ弁護士が対応することで、書類の不備やトラブルを防ぎ、円滑な相続を実現できます。
遺産分割協議書の必要書類や相続手続きに不安がある方は、ぜひご相談ください。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)