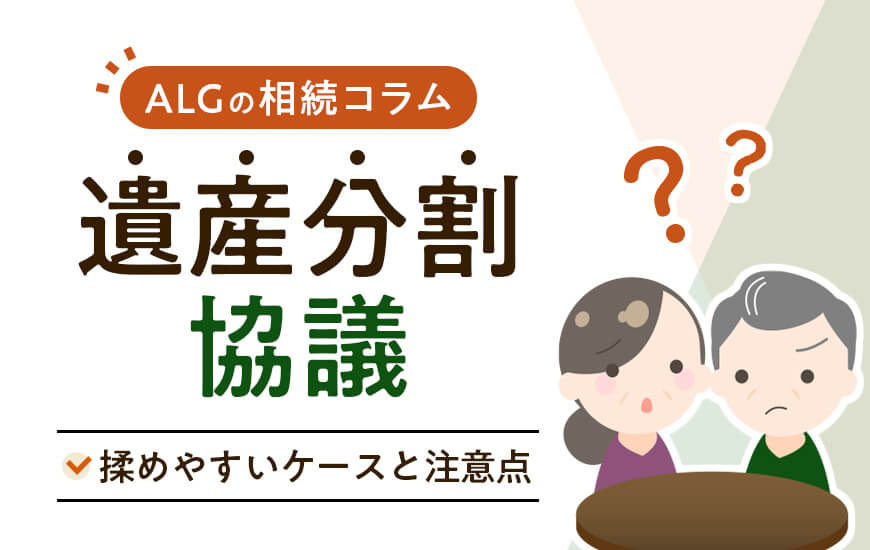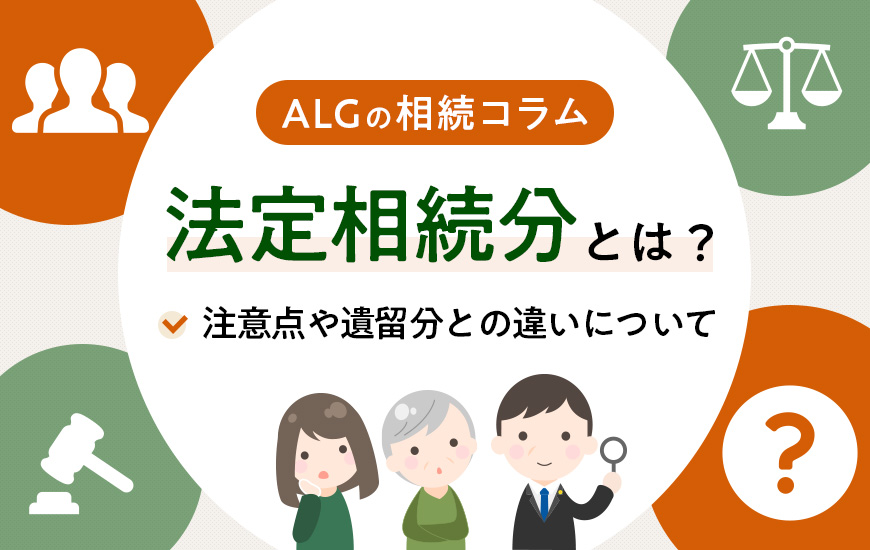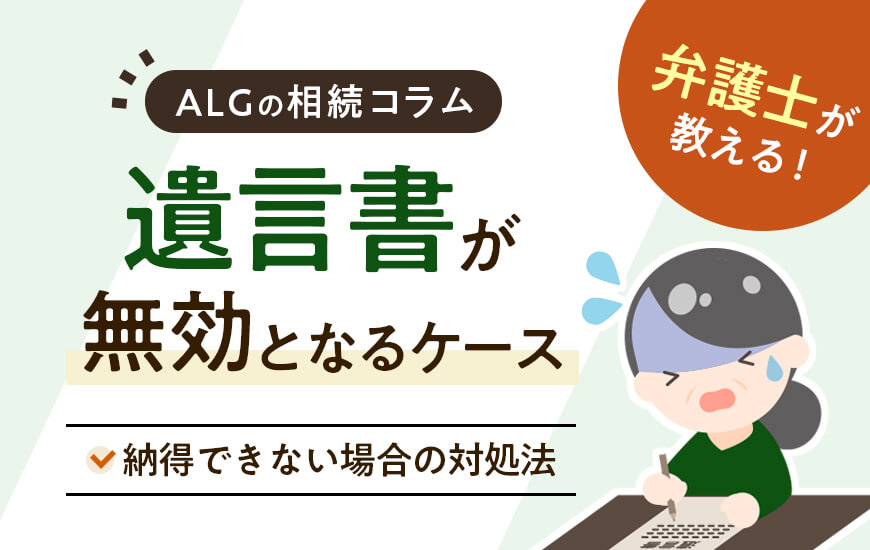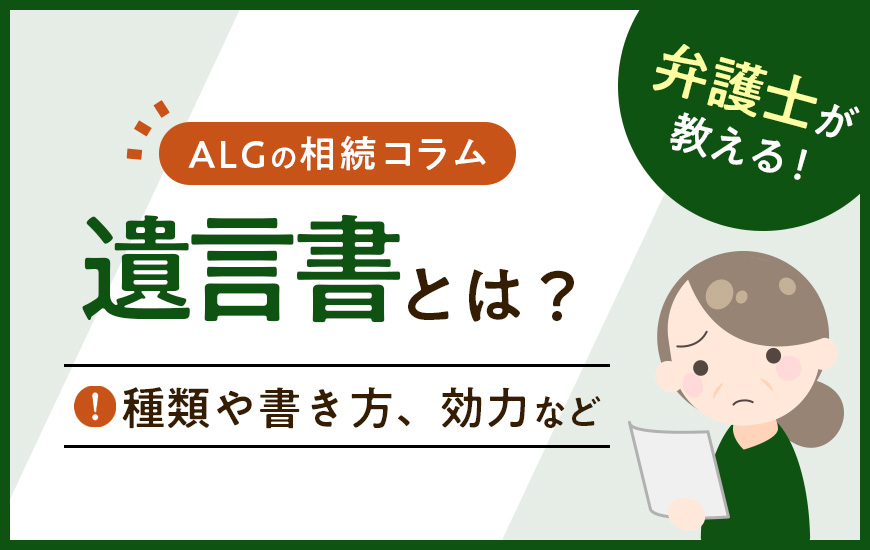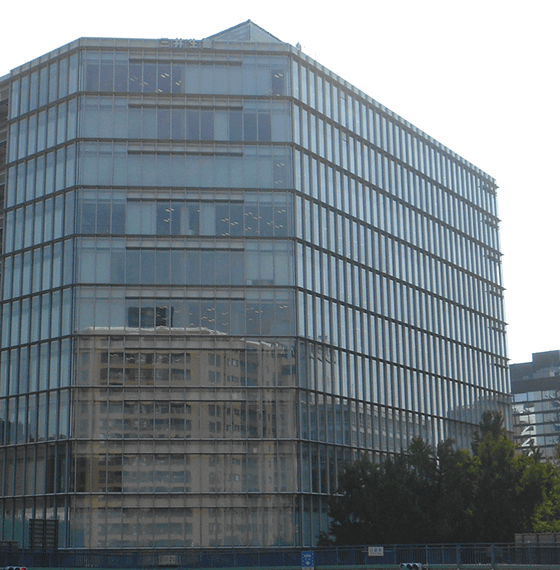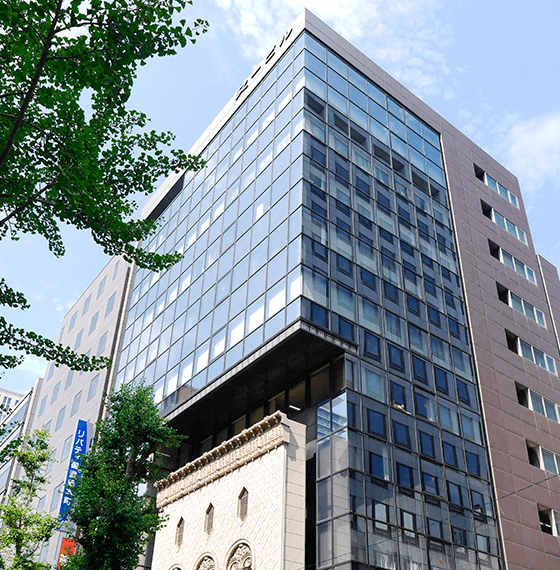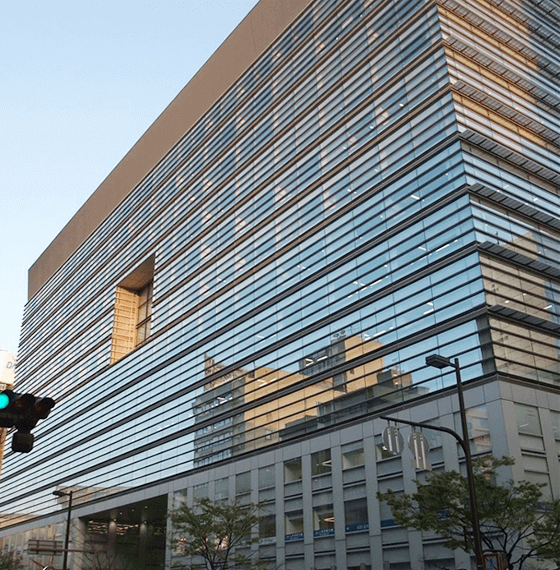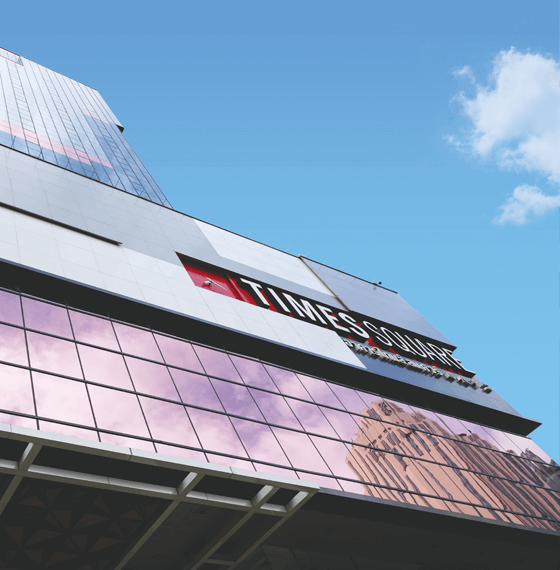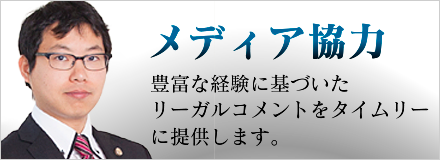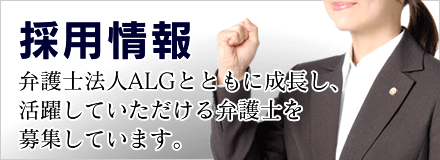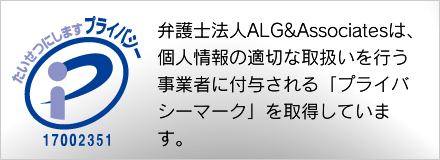認知症の相続人がいる場合の相続はどうなる?手続きや対策を解説
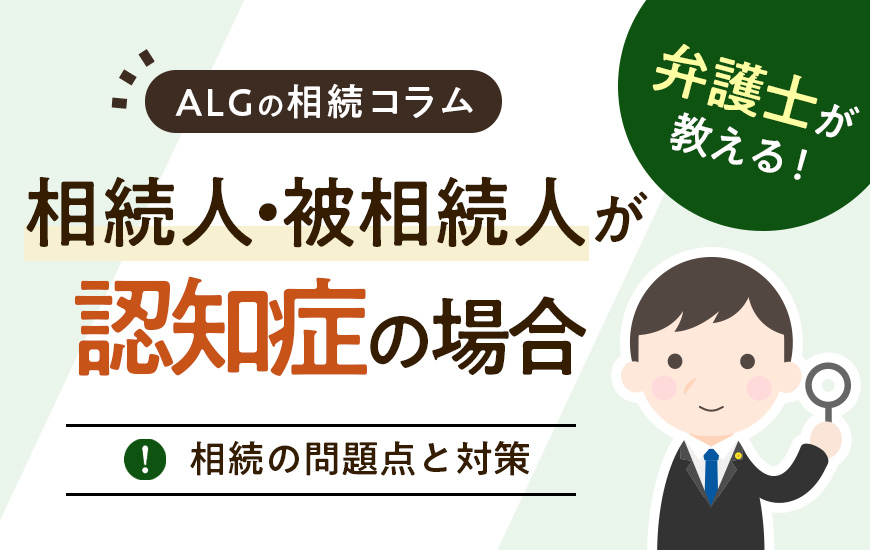
日本では高齢化が進み、相続人や被相続人が認知症を患っているケースが増えています。
認知症になると判断能力が低下し、遺産分割協議に参加できず、相続手続きが止まってしまうこともあります。
この記事では、認知症の相続人がいる場合の遺産分割の注意点や、被相続人が認知症になった場合の相続対策について、わかりやすく解説します。
相続トラブルを防ぐための準備方法も紹介していますので、ぜひご参考になさってください。
目次
【動画で解説】認知症の方がいる場合の遺産分割協議について
認知症の相続人がいる場合の相続はどうなる?
相続人の中に認知症の方がいると、相続手続きに大きな支障が生じます。
特に深刻なのは、認知症によって意思能力を失った相続人がいると、遺産分割協議を行うことができない点です。
このままでは協議は無効となり、相続を進めることはできません。
預貯金の解約や不動産の名義変更ができないだけでなく、相続税の申告にも影響が出る可能性があります。
対応策としては、家庭裁判所で成年後見人を選任し、その代理人が協議に参加する方法と、遺産を法定相続分どおりに分ける方法の2つがあります。
以下で詳しく解説します。
遺産分割協議ができない
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって初めて成立します。
しかし、相続人の中に認知症で判断能力が低下している方がいる場合、注意が必要です。
遺産分割協議は法律行為であり、参加する相続人には意思能力(自分の行為の結果を理解し判断できる能力)が求められます。
そのため、重度の認知症で意思能力を欠いている場合、その相続人が参加した協議は無効となります。
もっとも、「認知症=協議できない」というわけではありません。
症状が軽ければ、協議の内容を理解できる判断力が残っていることもあり、その場合は遺産分割協議に参加できる可能性があります。
ただし、判断は非常に難しく、後々トラブルになる可能性があるため、医師の診断書を取得するなど客観的な証拠を残すことが重要です。
遺産分割協議について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
成年後見制度
成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になった方を保護し、財産管理や法律行為をサポートする仕組みです。
家庭裁判所が選任した後見人が、本人に代わって重要な手続きを行います。
後見人がいれば、本人が意思能力を失っていても、代理人として遺産分割協議に参加し、協議を有効に成立させることが可能です。
ただし、成年後見には次のようなデメリットがあるためご注意ください。
- 手続きが複雑で時間がかかる
裁判所への申立てや書類準備などが必要で、後見人の選任までに数ヶ月かかります。 - 後見人は専門家が選ばれる可能性が高い
親族ではなく、弁護士や司法書士などの専門職が選任されるケースが多いです。 - 希望通りの遺産分割にならない可能性
後見人は本人の利益を最優先にするため、本人の取り分が法定相続分を下回るような協議は成立させにくくなります。 - 後見人への報酬が必要
報酬は本人の財産から支払われ、金額は財産額や業務内容によって変わります。
成年後見人に支払う報酬の目安
| 相続財産の目安 | 報酬の目安 |
|---|---|
| 相続財産が1000万円以下 | 月額2万円 |
| 相続財産が1000万円~5000万円以下 | 月額3万~4万円 |
| 相続財産が5000万円以上 | 月額5万~6万円 |
法定相続分
法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続割合のことです。
法定相続分で相続する場合、遺産分割協議は不要なため、認知症の相続人がいても遺産分割ができます。
ただし、次のようなデメリットがあるため、慎重な検討が必要です。
- 共有状態となるため、売却などが困難
法定相続分で分けると不動産は共有名義となり、売却や賃貸、担保設定には全員の同意が必要です。認知症の相続人がいると手続きが進められません。 - 預金の払い戻しには制限がある
遺産分割協議をしない場合、預貯金は1金融機関あたり「150万円」または「預貯金額×1/3×法定相続分」のいずれか少ない額までしか払い戻せません。 - 相続税の特例が使えない
配偶者控除や小規模宅地の特例など、相続税を軽減する制度は遺産分割協議が前提のため、法定相続分で分けるだけでは利用できません。
法定相続分について詳しく知りたい方は、こちらのリンクをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
認知症の相続人がいる場合の注意点
認知症の相続人がいる場合は、以下の点に注意する必要があります。
- 代筆すると無効になる
- 相続放棄できない
代筆すると無効になる
相続手続きでは、遺産分割協議書などの書類に相続人本人の署名・押印が欠かせません。
しかし、認知症のため署名が難しい場合でも、他の相続人が代筆するのは絶対にしてはいけません。
代筆された協議書は無効と判断される可能性が高く、手続きがやり直しになるおそれがあるからです。
さらに、代筆は私文書偽造罪などに該当するリスクがあり、善意であっても刑事責任は免れません。
成年後見人を選任して署名してもらうなど、正しい手続きを踏むことが必要です。
相続放棄できない
認知症によって意思能力を失っている相続人が、自ら相続放棄することは不可能です。
そのため、有効に相続放棄をするためには後見人を選任する必要があります。
ただし、法定後見人は本人を保護することを主な任務としており、本人が損をするような相続放棄をすることはできません。
被相続人に巨額の借金がある等、明らかに相続するべきでない事情があれば、後見人が代理して相続放棄してもらうことが可能です。
認知症の相続人がいる場合の相続対策
相続人に認知症の方がいる場合、遺産分割協議が進まず、相続手続き全体が滞るリスクがあります。
こうしたトラブルを防ぐためには、生前から対策が重要です。
代表的な方法として、以下の3つがあげられます。
- 遺言書を作成する
- 家族信託を利用する
- 生前贈与を行う
遺言書を作成する
相続人になる予定の人のなかに、認知症の疑いのある方がいる場合、遺言書を作成することが有効です。
遺言書によって全財産について相続人を指定しておけば、遺産分割協議をする必要がなくなるため、相続人の1人が認知症であっても問題が生じにくくなります。
ただし、有効な遺言書を作成することが条件となるため、形式的なミス等によって遺言書が無効になると遺産分割協議が必要となってしまいます。
遺言書を作成するときには、弁護士のサポートを受けて、有効な遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書が無効になってしまうケース等について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
家族信託を利用する
家族信託とは、財産から利益を得る権利を所有者に残したままで、その財産の管理や運用、処分等を行う権利を家族に委託する制度です。
例えば、父親と認知症の母親、息子一人の家族において、父親名義の不動産がある場合、父親が先に死亡すると、父親名義の不動産は母親と息子が共同で相続することになります。
しかし、母親は認知症のため、不動産を売却することができません。
そこで、父親と息子との間であらかじめ不動産について家族信託の契約をすることで、父親死亡後、受託者である息子に不動産を処分してもらうことによって、財産を処分できないリスクを回避できます。
ただし、家族信託をしたら、所有権移転及び信託登記を申請して財産の名義変更が必要です。
生前贈与を行う
生前贈与とは、被相続人が生きているうちに、自分の財産を子や孫などに贈与することです。
不動産や預貯金を移しておくことで、遺産分割協議を避けられ、認知症による相続トラブルの防止にもつながります。
ただし、年間110万円を超えると贈与税が課税され、2024年改正で相続開始前7年以内の贈与は110万円以下でも相続財産に加算されます。
認知症が進むと贈与自体が無効になる可能性があるため、早めの対策と計画的な贈与が重要です。
被相続人である親が認知症だった場合はどうなる?
親が重度の認知症になると、判断能力を失った状態とされ、遺言書の作成、生命保険の加入、生前贈与、家族信託、不動産の売却など、意思表示を伴う法律行為は無効になります。
これらの手続きは本人の意思能力が前提となるため、認知症発症後には行えません。
ただし、症状に波がある「まだら認知症」の場合、症状が軽いときに相続対策を行える可能性があります。
遺言書については、認知症であっても作成時に「遺言能力」があれば有効です。
遺言能力とは、遺言内容とその結果を理解し判断できる力を指します。
後の争いを防ぐためには、公正証書遺言を選び、医師の診断書や作成時の状況を記録しておくことが望ましいでしょう。
認知症が進行すると、遺言書の作成やその他の相続対策は不可能になるため、早めに弁護士などの専門家に相談し、適切な準備を進めることが重要です。
認知症の方がいる場合の相続はお早めに弁護士にご相談ください
相続人に認知症の方がいると、遺産分割協議が進まず、成年後見人の選任など複雑な手続きが必要になります。
また、被相続人である親が認知症になると、生前贈与や遺言書の作成といった相続対策が難しくなります。
こうしたトラブルを防ぐためには、早めに弁護士へ相談することが重要です。
認知症であっても、症状が軽度で判断能力が残っている場合には、遺言書の作成や一部の対策が可能なケースもあります。
諦めずに、専門家と一緒に最適な方法を検討しましょう。
さらに、認知症になる前に公正証書遺言の作成や家族信託などを準備しておくことで、将来の相続トラブルを減らせます。
相続に関する不安や疑問がある方は、相続問題に精通した弁護士にご相談ください。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)