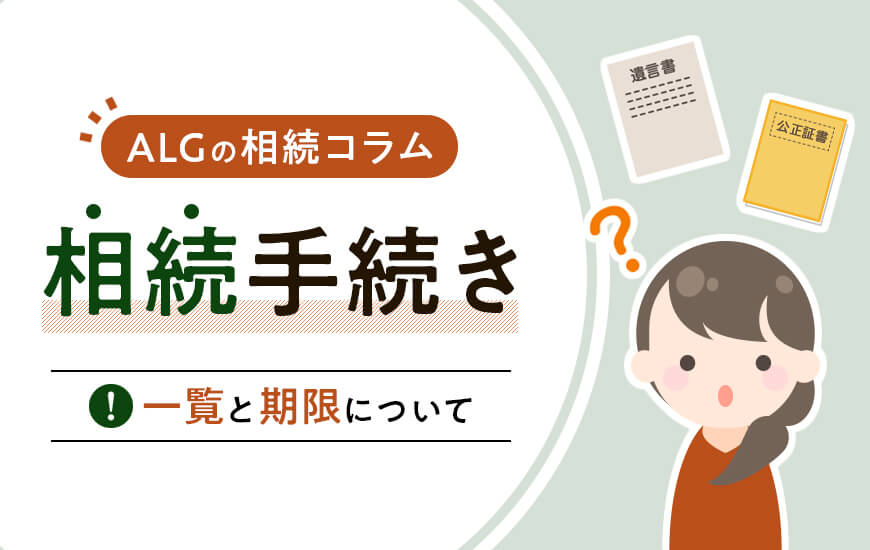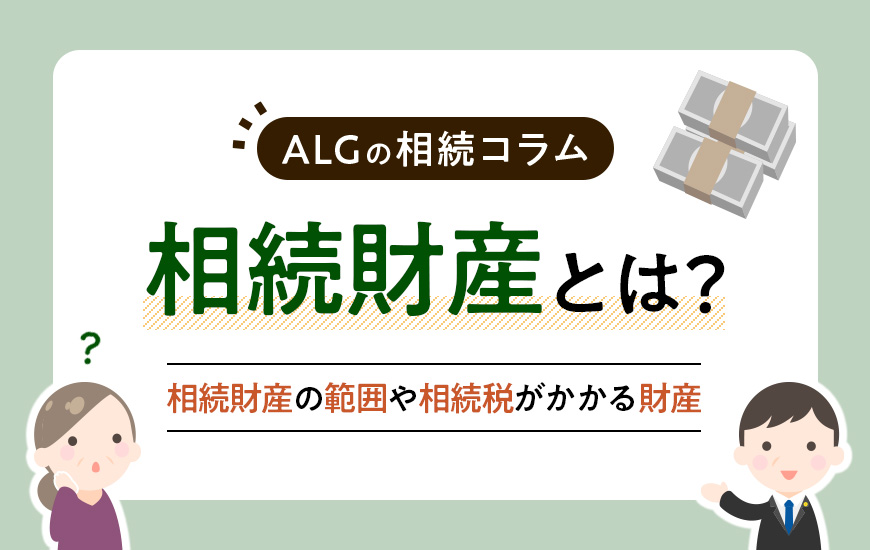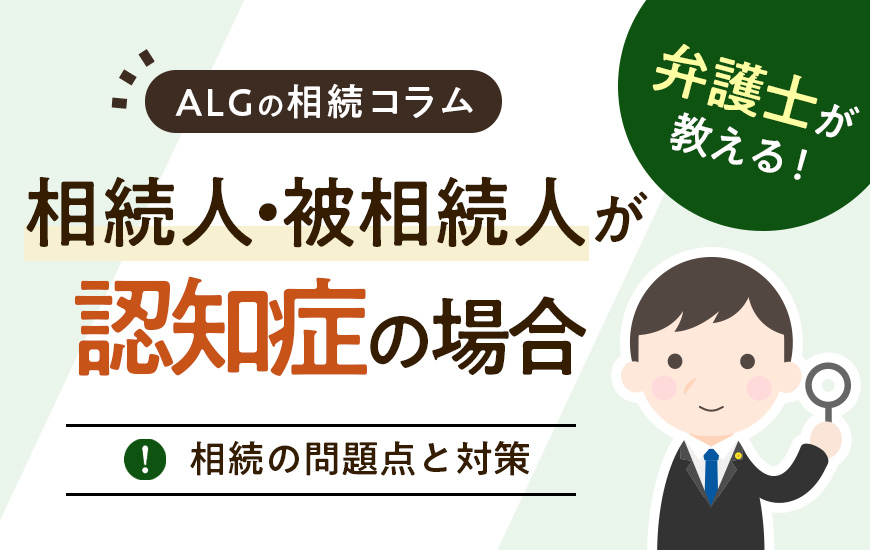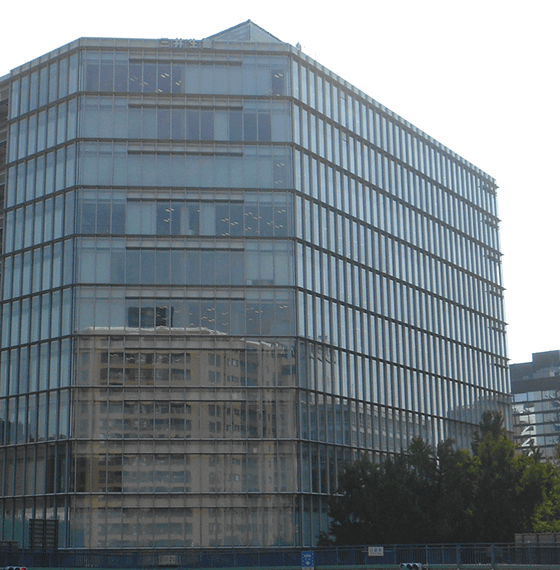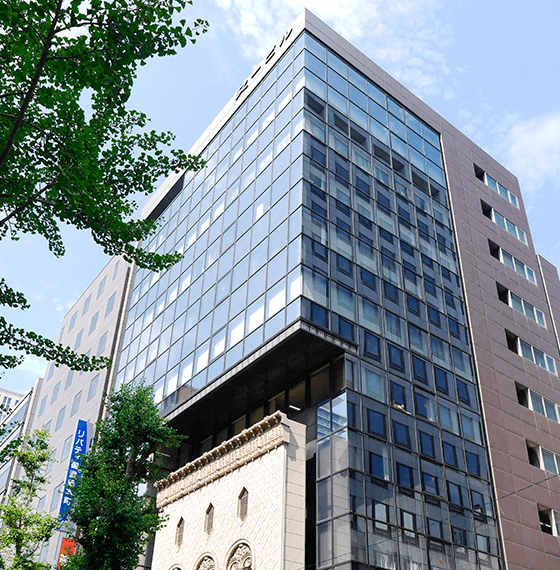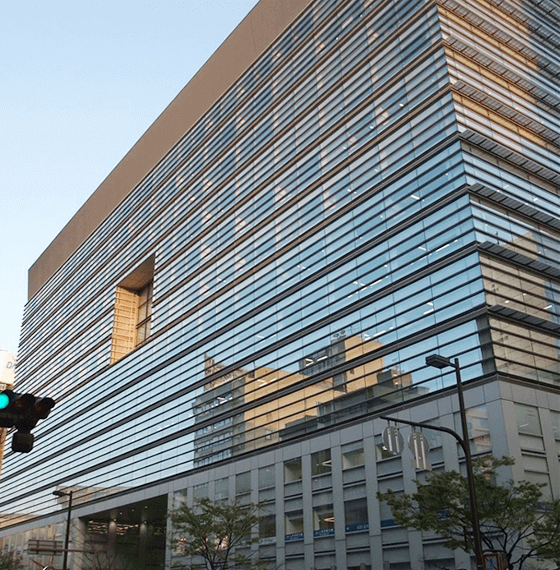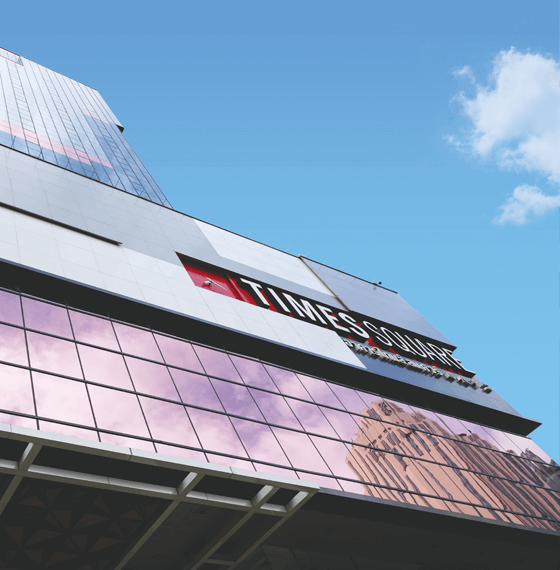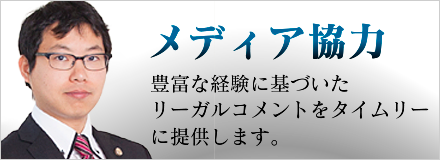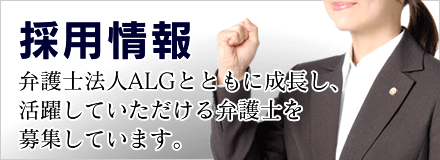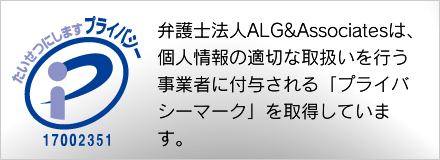相続の手続きをしないとどうなる?放置する8つのリスクとデメリット
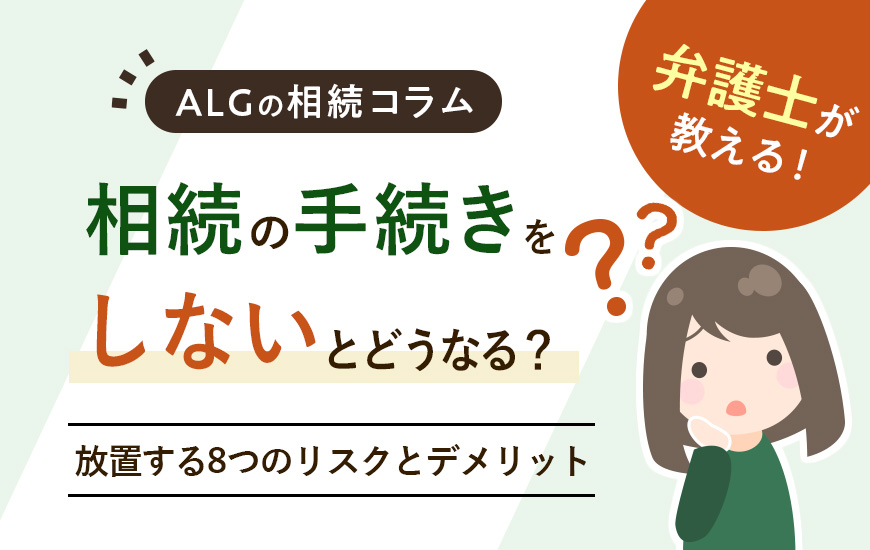
相続が発生しても、手続きの煩雑さや忙しさから「後回しにしよう」と考えてしまう方は少なくありません。
相続手続きは不動産登記や相続税申告、遺産分割協議など多岐にわたり、専門的な知識も必要なため、つい放置してしまいがちです。
しかし、相続手続きをしないまま長期間放置すると、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
この記事では、相続手続きを怠った場合に起こりうる問題点や法的なリスク、そしてそれを回避するための具体的な対策について解説します。
目次
相続の手続きをしないとどうなる?
相続手続きをしないで放置すると、様々なリスクやデメリットが生じる可能性があります。
たとえば、相続税の申告期限(10ヶ月)を過ぎると延滞税が課せられたり、相続放棄の期限(3ヶ月)を逃すと借金を引き継いだりするおそれがあります。
また、相続登記を行わないと不動産の売却や活用ができず、過料の対象にもなります。
さらに、預貯金や株式の権利が消滅したり、遺留分侵害額請求の権利を失ったりするリスクも見逃せません。
相続手続きは期限が定められているものが多く、放置するほど複雑化し、後の世代に負担を残してしまうことになります。
相続が発生したら早めに手続きに着手し、専門家のサポートを受けながら効率よく進めることが大切です。
相続手続きの期限一覧
相続手続きには期限が設けられているものが多く、これを守らないとペナルティや権利の消滅リスクが生じます。
以下に主要な手続きとそれぞれの期限をまとめましたので、ご確認ください。
相続が発生したら早めに手続きを済ませるようにしましょう。
| 期限・時効 | 手続き内容 |
|---|---|
| 3ヶ月 | 相続放棄・限定承認 |
| 4ヶ月 | 被相続人の準確定申告 |
| 10ヶ月 | 相続税の申告・納税 |
| 1年 | 遺留分侵害額請求 |
| 2年 | 埋葬料・葬儀代の受給手続き |
| 3年 | 生命保険金(死亡保険金)の受け取り 相続登記(令和6年4月1日以降) |
| 5年 | 相続回復請求権・取戻権 |
相続手続きの期限について詳しく知りたい方は、こちらのリンクをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
相続手続きをしない場合の8つのリスク・デメリット
相続手続きをしない場合のリスク・デメリットとして、以下があげられます。
- 預貯金の権利が失われる
- 株式の権利が失われる
- 借金の返済義務を負ってしまう
- 相続税に遅延税などのペナルティが加算される
- 相続登記でトラブルに発展する
- 遺留分侵害額請求ができなくなる
- 相続回復請求権や取戻権が消滅する
- 相続関係が複雑になる可能性がある
具体的な内容については次項で解説します。
相続手続きを放置することで思わぬトラブルが発生しないよう、相続が発生したら弁護士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。
預貯金の権利が失われる
銀行が口座名義人の死亡を知ると、その口座はいったん凍結され、相続人であっても自由に引き出すことができなくなります(一定の範囲内での払い戻しは除く)。
凍結を解除するには、預金口座の名義変更か解約の手続きをしなければなりません。
また、預金債権には時効があり、入出金等の取引がなく5年(信用金庫等では10年)が経過すると、払い戻しの権利が消滅するリスクがあります。
現時点では多くの金融機関が時効を援用していないものの、将来的に運用が変わる可能性も否定できません。
さらに、10年以上取引がない口座は休眠預金として公益活動に活用されることがあります。
払い戻しも可能ですが手続きが煩雑であるため、相続発生後は速やかに手続きを進めることが大切です。
株式の権利が失われる
株式を相続した場合は、速やかに名義変更を行うことが重要です。
上場株式であれば証券会社に連絡して、株式の名義を相続人に変更し、相続人の証券口座に振り替える必要があります。
また、非上場株式の場合は発行会社に申し出て株主名簿の書き換え申請を行わなければなりません。
手続きを放置すると株式は相続人全員の共有状態となり、個人の判断で売却や株主権の行使ができなくなります。
さらに、配当金の案内などが届かない状態が5年以上続くと、会社が株主所在不明と判断し、株式を処分する可能性があります。
売却益を受け取れる場合もありますが、5〜10年で権利が消滅します。
配当金も多くの企業で受け取り期限が3〜5年と定められているため、早めの手続きが不可欠です。
借金の返済義務を負ってしまう
相続では預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もそのまま引き継がれます。
たとえば、被相続人に多額の借金がある場合、何も手続きせずに放置すると、相続人がその返済義務を負うことになります。
こうしたリスクを避けるためには、相続放棄や限定承認という制度を利用するのが効果的です。
相続放棄とは、プラスもマイナスも含めて一切の財産を相続しないとする手続きで、家庭裁判所への申請により成立します。
また、限定承認は、プラスの財産の範囲内でのみ借金を返済する方法で、借金の額が不明なときや残したい財産があるときに有効です。
いずれも相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きする必要があるため、早めの判断と対応が求められます。
相続税に遅延税などのペナルティが加算される
相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
この期限までに相続人の確定、財産の調査、遺産分割協議を済ませておかなければなりません。
これらの準備が遅れると申告・納税が間に合わず、延滞税や加算税、場合によっては重加算税などのペナルティが課される可能性があります。
さらに、期限を過ぎると、相続税の優遇措置が受けられなくなるリスクもあるため注意が必要です。
期限内の申告・納付が難しいときは、法定相続分による未分割申告や、延納制度などの救済手段を活用することができます。
相続税の放置は負担増につながるため、早めに専門家へ相談し手続きを進めることが重要です。
相続税の課税対象となる財産についての詳細は、こちらのリンクでご確認ください。
合わせて読みたい関連記事
相続登記でトラブルに発展する
土地や建物などの不動産を相続した場合は、相続登記を行う必要があります。
令和6年4月1日より義務化され、相続登記を放置すると以下のようなリスクが生じます。
ペナルティの発生
相続人が不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
権利関係が複雑になり、手続きが困難になる
放置期間が長くなると、数次相続や代襲相続が発生し、相続人の数が増えて登記手続きが困難になります。
第三者に先に登記されて権利が失われる
相続登記をしていないと、遺産分割で自分が相続した不動産でも、他の相続人が勝手に売却・登記してしまった場合、善意の第三者に対して所有権を主張できなくなる可能性があります。
不動産の売却や担保設定ができない
相続登記がされていない不動産は、売却や金融機関への担保提供ができず、資産として活用できません。
遺留分侵害額請求ができなくなる
遺留分侵害額請求とは、被相続人が相続財産を特定の人物に贈与や遺贈するなどして、法定相続人の最低限の取り分(遺留分)が侵害された場合に、その侵害額を金銭で請求できる制度です。
遺留分は、配偶者や子ども、直系尊属などに法律で保障されており、兄弟姉妹には認められていません。
遺留分侵害額請求権には時効があり、相続開始と遺留分侵害の事実を知ったときから1年、または相続開始から10年を経過すると、請求できなくなります。
相続手続きを放置すると、遺留分の侵害に気づくのが遅れ、請求期限を過ぎてしまうおそれがあります。
大切な権利を失わないためにも、早めに相続手続きを進めるのがベストです。
相続回復請求権や取戻権が消滅する
相続回復請求権とは、相続人でない者が相続財産を占有・処分している場合に、本来の相続人が相続財産の返還を求める権利です。
共同相続人であっても、自分の法定相続分を超えて遺産を処分・占有していたら相続回復請求権の対象になります。
この権利は相続権の侵害を知ってから5年、または相続開始から20年で時効により消滅します。
一方、取戻権とは、共同相続人の一人が相続分を第三者に譲渡した場合に、他の相続人がその分を買い戻せる権利で、譲渡を知った日から1ヶ月以内に行使しなければなりません。
相続手続きを放置すると、このような重要な権利が期限切れで失われる可能性があるため、早めの対応が不可欠です。
相続関係が複雑になる可能性がある
相続手続きを長期間放置すると、予想以上に深刻なリスクが生じます。
たとえば、相続人の一人が亡くなり、被相続人の孫やひ孫が新たな相続人として加わると、相続関係は複雑化し、遺産分割に関する合意の取り付けがいっそう困難になります。
さらに、相続人が高齢になり認知症を発症した場合、遺産分割協議を進めるためには成年後見人の選任が必要となります。
家庭裁判所での手続きが加わることで、解決までに多くの時間と労力がかかることが予想されます。
加えて、相続人の中には連絡が取れなくなるケースもあります。
その場合は所在調査や公示送達といった追加手続きが必要となり、負担はさらに増大するでしょう。
相続人が認知症の場合の対処法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
>相続手続きを依頼できる専門家と選び方
相続手続きを依頼できる専門家として、司法書士、税理士、弁護士などがあげられます。
司法書士は、不動産の相続登記など、登記関連の手続きに強みがあります。
税理士は、相続税の申告や財産評価、節税対策など税務面でのサポートが得意です。
そして、弁護士は遺産分割協議の代理交渉や、遺留分侵害額請求など、法律トラブルへの対応が可能です。
交渉や調停、裁判まで対応できるため、相続に関する紛争が予想される場合には心強い存在です。
それぞれの専門分野や対応できる業務が異なるため、状況に応じて適切な専門家を選びましょう。
| 専門家 | 対応できる相続手続き | メリット |
|---|---|---|
| 司法書士 | 相続登記、相続人や相続財産の調査、銀行口座等の解約手続き、遺産分割協議書の作成など | 登記手続きに精通している |
| 税理士 | 相続税の申告、財産評価、税務相談など | 税務の専門家として節税対策や複雑な税務処理に強い |
| 弁護士 | 相続人や相続財産の調査、相続放棄や限定承認、遺言書検認の申立て、銀行口座等の解約手続き、遺産分割協議の代理、遺産分割協議書の作成、遺留分侵害額請求、調停・訴訟対応など | 法律トラブルに対応でき、交渉や裁判も任せられる |
| 行政書士 | 相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、自動車の名義変更、銀行口座等の解約手続きなど | 費用が比較的リーズナブル |
相続手続きをしないと様々なリスクが生じる可能性があります。お早めに弁護士までご相談ください。
相続手続きを長年放置してしまうと、相続関係の複雑化や資産の凍結、さらには税金の負担増など、様々なリスクが生じる可能性があります。
このような問題は、時間が経つほど解決が難しくなるため、相続が発生した段階で早めに専門家へ相談することが重要です。
なかでも弁護士は、相続人間の争いへの対応、遺産分割協議の代理、遺留分侵害額請求、調停・裁判など、法律面での幅広いサポートが可能です。
複雑な相続問題にも対応できる専門知識と交渉力を備えているため、安心して任せることができます。
相続に関する不安や疑問がある方は、相続問題を得意する弁護士法人ALGにぜひご相談ください。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)