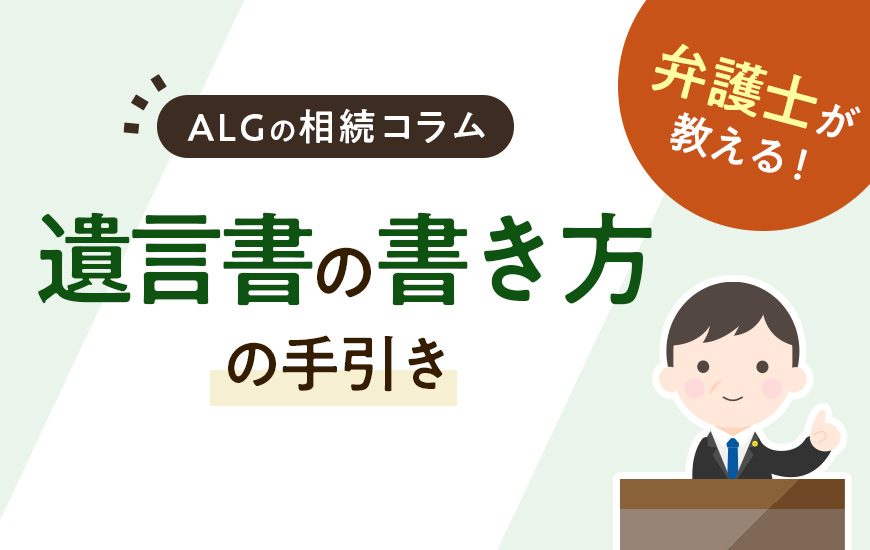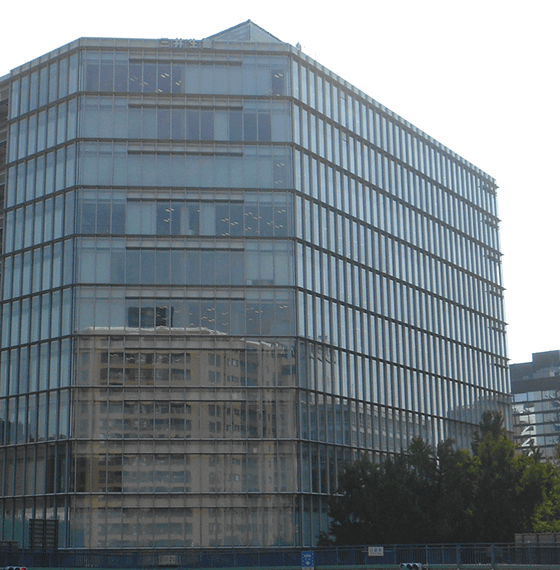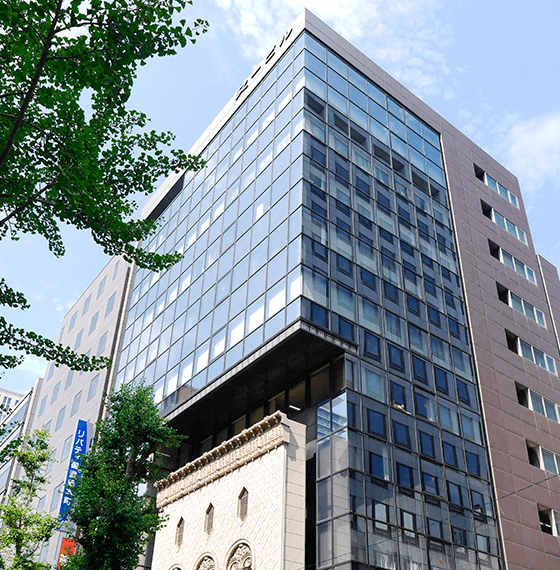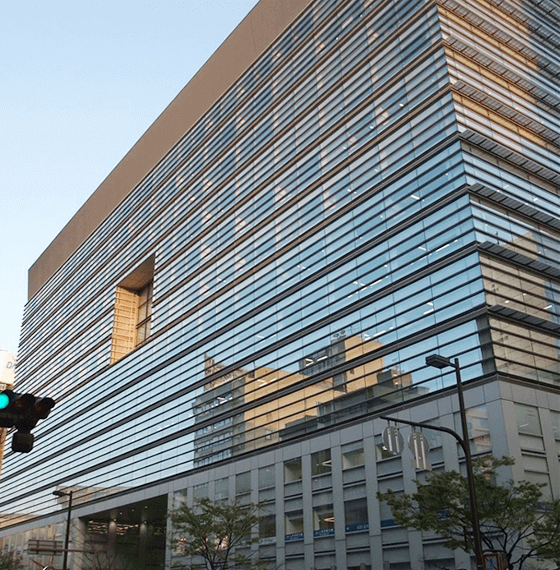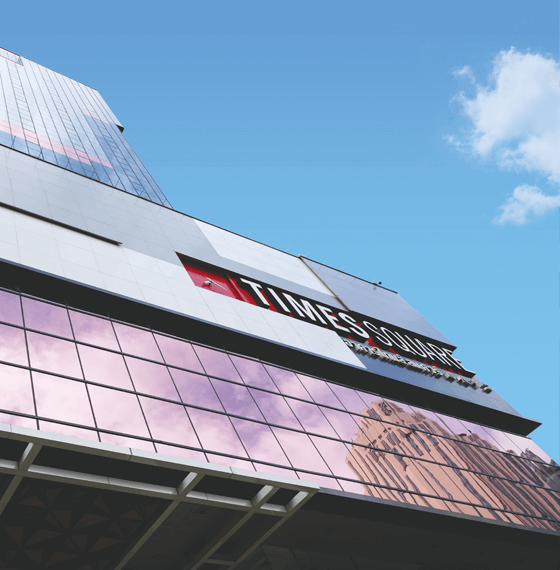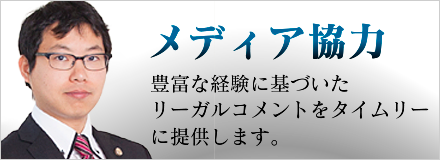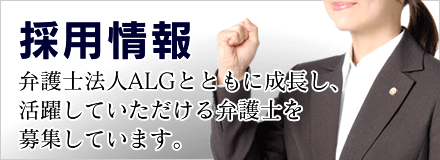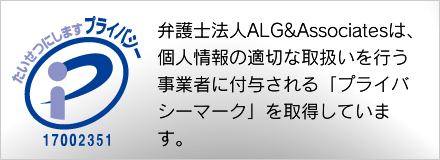孫に遺産を相続させるには?相続人となる3つのケースや注意点を解説
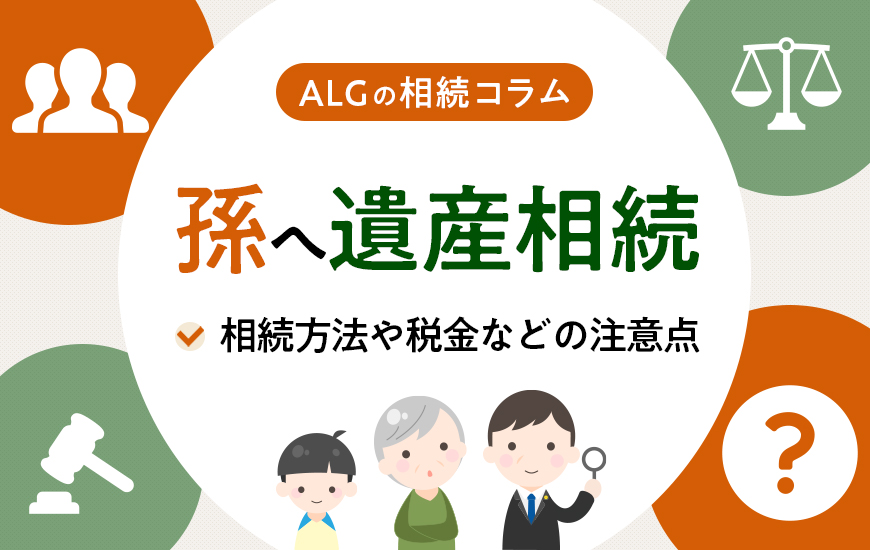
この記事でわかること
「かわいい孫に財産を残したい」と考える方は多いものの、基本的に孫には相続権がありません。
ただし、例外的に孫が相続人となるケース(代襲相続など)や、相続権がない孫に財産を渡す方法(遺言書の作成など)は存在します。
一方で、孫が遺産を受けとる場合には、相続税が通常より高くなる可能性や、他の相続人とのトラブルが生じるリスクもあるため、慎重な検討が必要です。
この記事では、孫が相続人になるケースや、孫に財産を遺すための方法、税金やトラブル防止のためのポイントについて解説します。
目次
原則として孫は法定相続人になれない
孫は、基本的に法定相続人ではないため、祖父母の財産を相続する権利はありません。法定相続人とは、相続財産を相続できると民法で定められている人のことです。
被相続人の配偶者は必ず法定相続人となりますが、その他の血族は、より高順位の人のみがなります。
法定相続人の相続順位は以下のとおりです。この中に孫は含まれていません。
| 第一順位 | 子(すでに亡くなっている場合は孫) |
|---|---|
| 第二順位 | 親(すでに亡くなっている場合は祖父母) |
| 第三順位 | 兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥・姪) |
このように、被相続人の子が生存している場合は、孫が相続人になることはありません。
孫が法定相続人となるのは、被相続人の子がすでに亡くなっている場合や、被相続人と孫が養子縁組をしている場合など、特定のケースに限られます。
孫が法定相続人になる3つのケース
孫が法定相続人になるのは、基本的に認められていませんが、特定の条件を満たす場合に限り可能です。
その代表的なケースは次の3つです。
- 遺言書を作成している
- 養子縁組をしている
- 代襲相続が発生している
遺言書を作成している
遺言書を作成することによって、法定相続人でない孫に対して、相続財産を遺贈することができます。
遺言では、相続する割合の指定や、特定の財産だけ相続させる指定、割合を指定しながら特定の財産を相続させる指定等が可能です。
ただし、遺言書を作成するときには、細かい決まりを守らなければ無効となるおそれがあります。
また、兄弟姉妹以外の法定相続人は、最低限の取り分として遺留分があるため、遺留分を侵害するとトラブルになるおそれがあります。
相続財産を確実に孫へ残したい場合には、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。
遺言書の書き方について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
養子縁組をしている
祖父母が孫と養子縁組をすると、法律上の親子関係が成立し、孫は法定相続人として相続できます。養子になった孫は実子と同じ扱いとなり、相続順位や相続割合も実子と変わりません。
被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が遺産の2分の1を取得し、残りの2分の1を実子と養子になった孫で均等に分けます。
配偶者がいない場合は、実子と養子になった孫で全財産を分けることになります。
このように、遺言書で指定がなくても、養子縁組をした孫は法定相続分に基づいて遺産を相続できます。
さらに、孫を養子にすることで法定相続人の人数が増え、相続税の基礎控除額が引き上げられるため、結果として税負担が軽くなる可能性があります。
ただし、節税目的だけの養子縁組は否認されるリスクがあり、特に死亡直前の縁組は注意が必要です。
孫との養子縁組について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
代襲相続が発生している
代襲相続が発生すると、とくに手続きを行わなくても孫が相続できます。
代襲相続とは、被相続人の子供が死亡した等の理由によって相続権を失ってしまった場合に、その子供(被相続人の孫)が代わりに相続することです。
孫が代襲相続するのは、次のような理由で被相続人の子供が相続権を失ったときです。
- 死亡
- 相続欠格事由への該当
- 相続人廃除
代襲相続をおこなう孫の相続分は、相続権を失ってしまった被相続人の子供の相続分を引き継ぎ、代襲相続する孫の人数で等分します。
遺産相続以外で孫へ財産を遺す4つの方法
遺言書や養子縁組、代襲相続以外にも、孫に財産を遺す方法があります。
代表的なものとして、以下が挙げられます。
- 生前贈与をする
- 教育資金の一括贈与を利用する
- 結婚・子育て資金の一括贈与を利用する
- 死亡保険の受取人を孫にする
税についてさらに詳しくお知りになりたい方は、以下の国税庁のサイトでご確認ください。
1.生前贈与をする
生前贈与とは、生きているうちに、自分の財産を誰かに贈ることです。
生前贈与を受けた人には基本的に贈与税がかかりますが、1月から12月までの1年間に110万円までであれば、生前贈与を受けても非課税となります。
贈与税の非課税枠の範囲内で生前贈与すると、1年の金額は大きくないものの、何年も続ければ多くの金額を生前贈与できます。110万円以内の生前贈与を繰り返す贈与方法を暦年贈与といいます。
ただし、事前の総額を決めてから毎年のように110万円以内の贈与を繰り返す等の贈与方法は、暦年贈与と認められないおそれがあります。
この場合、総額を1年で贈与したのと同じだけの贈与税がかかります。
また、代襲相続が発生した場合や孫を養子にした場合等には、相続が発生する前の3年以内の生前贈与に相続税がかかります。
なお、2024年1月以降は生前贈与加算の期間が7年に延長されるので、暦年贈与の開始時期が遅くなると、節税効果も低くなってしまうので注意が必要です。
2.教育資金の一括贈与を利用する
教育資金の一括贈与の特例とは、教育資金として使うために、最大で1500万円までの贈与を非課税で行うことができる制度です。
この制度を使うためには、主に以下のような要件があります。
- 贈与を受ける人が30歳未満
- 贈与する人は贈与を受ける人の両親や祖父母等である
- 贈与を受ける人の前年の合計所得金額が1000万円以下
なお、習い事のための費用等、学校以外に使う教育関連資金は、最大で500万円とされています。
また、贈与をした人が亡くなったときや、贈与を受けた人が30歳になったときに残額があると、その残額が相続税や贈与税の課税対象となるケースがあります。
この制度は、2026年3月31日まで設けられています。
3.結婚・子育て資金の一括贈与を利用する
結婚・子育て資金の一括贈与の特例とは、結婚や子育てに必要な資金を、最大1000万円まで非課税で贈与できる制度です。
結婚資金として非課税になるのは300万円までで、挙式や披露宴の費用だけでなく、新居の家賃や敷金、引っ越し費用なども対象に含まれます。
この制度を利用するには、主に以下の要件を満たす必要があります。
- 贈与を受ける人が18歳以上50歳未満で、前年の合計所得金額が1000万円以下
- 贈与する人が贈与を受ける人の両親や祖父母などである
利用する際は、金融機関で専用口座を開設し、結婚・子育て資金非課税申告書を税務署に提出する必要があります。
注意点として、贈与者が亡くなったときや、贈与を受けた人が50歳になった時点で口座に残額がある場合、その残額は相続税や贈与税の課税対象となります。
この制度は、2015年4月1日から2027年3月31日までの期間限定で実施されています。利用を検討している方は、早めに手続きすることをおすすめします。
4.死亡保険の受取人を孫にする
生命保険契約において、被相続人が死亡したときの死亡保険金の受取人を孫にすることによって、財産を遺すことができます。
このとき、孫が代襲相続人である場合等、法定相続人であるならば相続税の非課税枠が適用されるため、納める相続税の金額を抑えることができます。
死亡保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数によって計算できます。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
孫に遺産相続させる場合の注意点
孫を養子にすると、相続税の基礎控除額が増え、税負担を軽減できる可能性があります。また、遺言書を作成すれば、被相続人の希望どおりに孫へ財産を渡すことができます。
ただし、養子縁組や遺贈には注意が必要です。孫に遺産を相続させる場合、他の相続人とのトラブルが起きやすく、孫の税負担が増えることもあります。
こうしたデメリットを理解したうえで、慎重に検討する必要があります。
他の相続人とトラブルになりやすい
孫に遺産を相続させる場合は、他の相続人とのトラブルが起きやすい点に注意が必要です。
孫は基本的に法定相続人ではないため、孫に相続させる場合は、遺言書や生前贈与、養子縁組といった特別な手続きが必要です。
しかし、遺言や生前贈与で孫に多くの財産を与えると、配偶者や子供の遺留分を侵害し、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
また、養子縁組を行うと他の相続人の取り分が減ってしまうため、感情的な対立が生じ、遺産分割協議が難航するおそれもあります。
こうした親族間のトラブルを防ぐためには、生前に相続人へ意向をしっかり説明し、理解を得ておくことが大切です。
孫の税負担が多くなる可能性がある
孫を養子にした場合や、遺言によって孫に財産を遺贈した場合は、相続税が通常より2割加算されます。
ただし、代襲相続で孫が相続人になる場合は、この2割加算の対象外です。
また、孫が死亡保険金を受け取るときには、孫が法定相続人になっている場合を除いて、相続税の非課税枠は利用できません。
さらに、孫が法定相続人になっていなければ、不動産登記の際に支払う登録免許税も高くなります。加えて、生前贈与や遺贈によって不動産を取得したときは、不動産取得税も課税されます。
これらの税負担を踏まえて、どの方法で相続させるかを慎重に検討することが必要です。
孫に相続させたいとお考えなら弁護士法人ALGにご相談ください
孫に財産を遺す方法はいくつかあります。しかし、遺贈や生前贈与であれ、養子縁組であれ、トラブルを引き起こしてしまうリスクがあります。
特に、遺贈や生前贈与については、他の相続人の遺留分について考慮が必要です。また、孫の税負担についても考慮しなければなりません。
そこで、孫に財産を遺したい場合には弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、財産を遺す方法として、より妥当なものをアドバイスできるだけでなく、遺言書の作成等についてもサポートが可能です。
贈与の特例については、たびたび制度が変更されているため、最新の情報を確認するためにもぜひご相談ください。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)