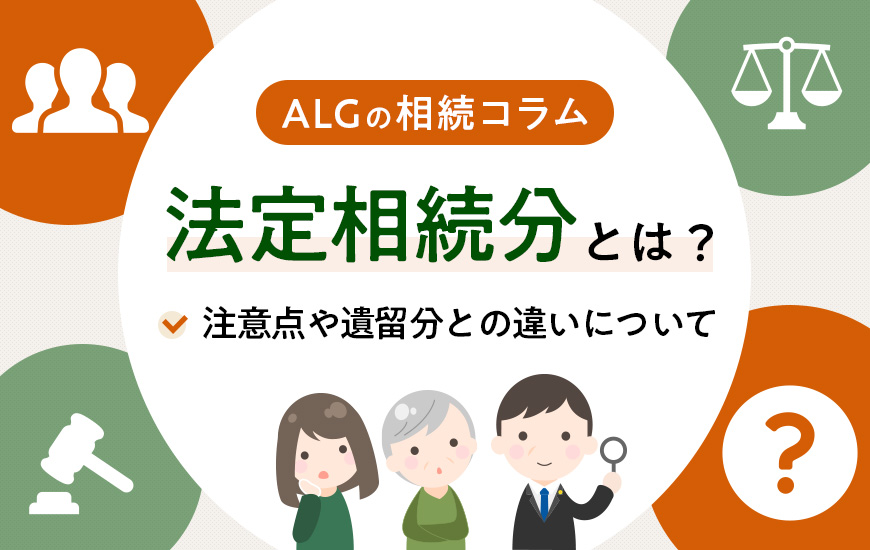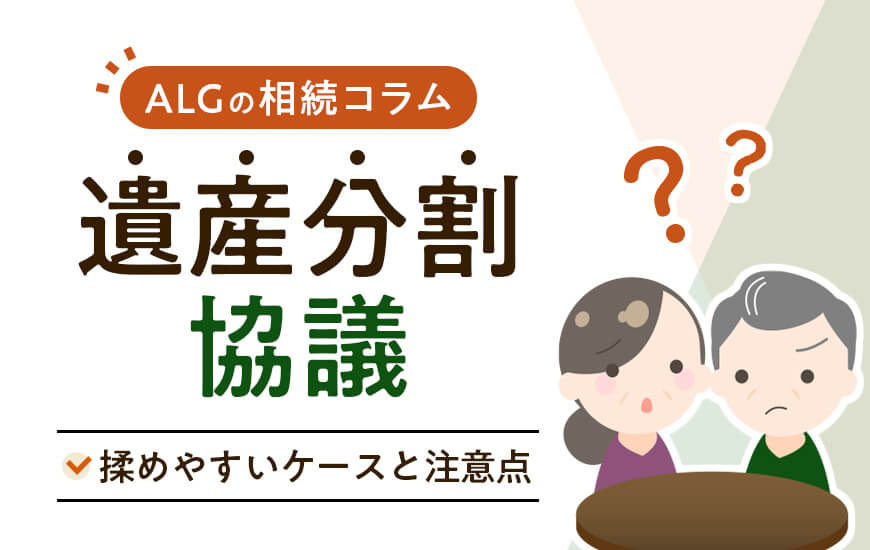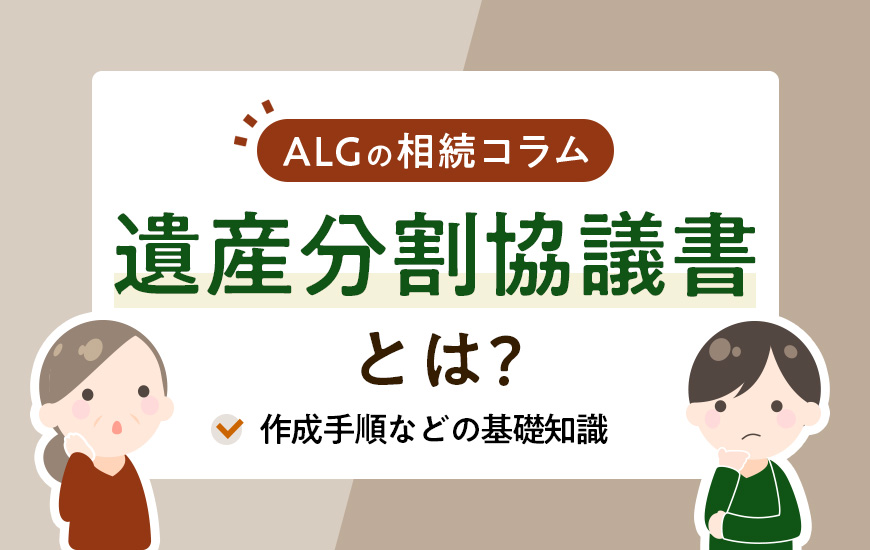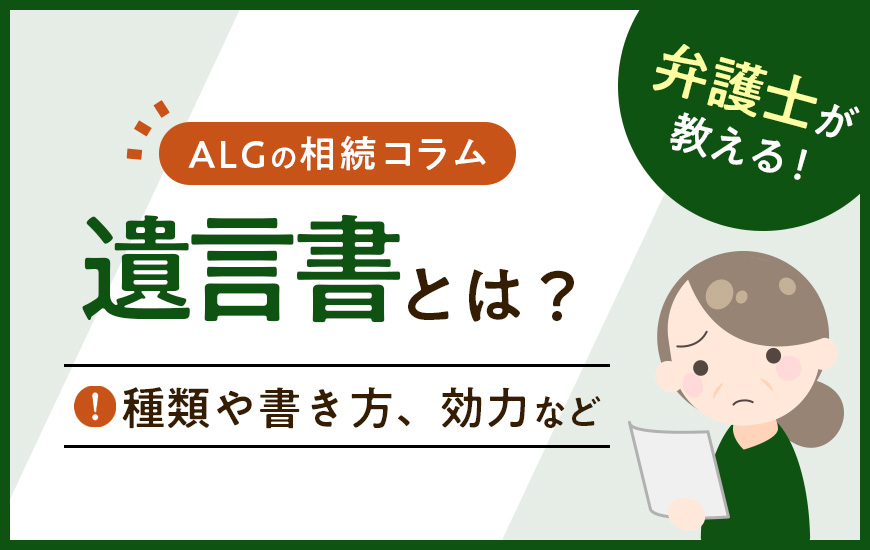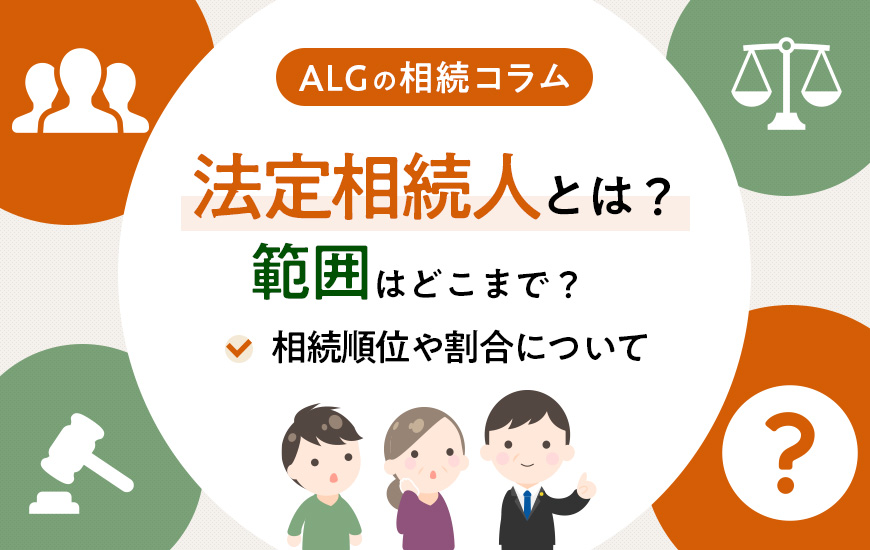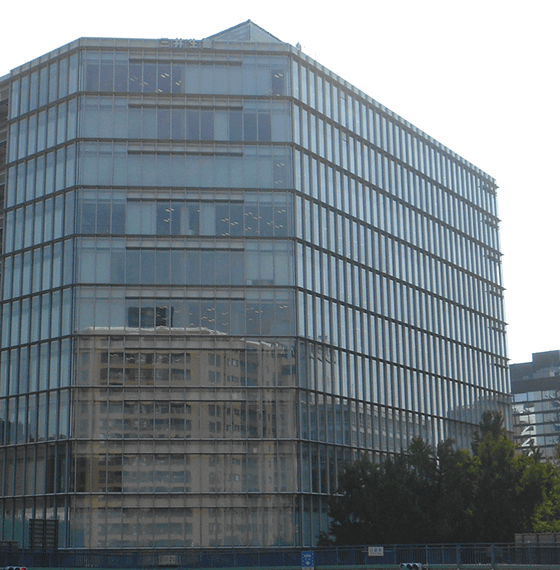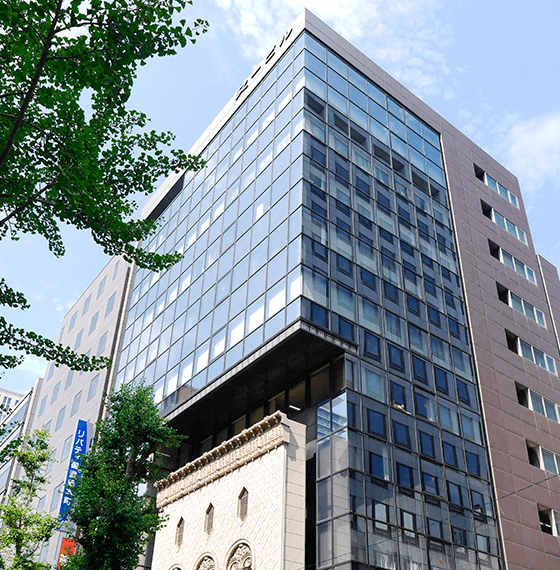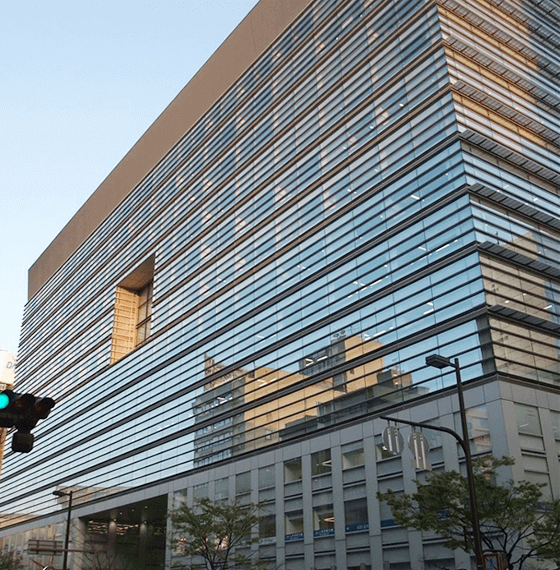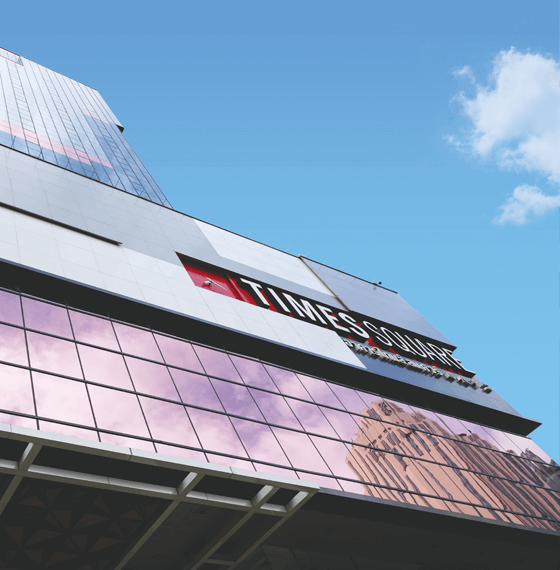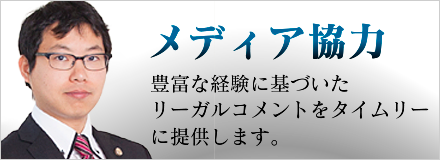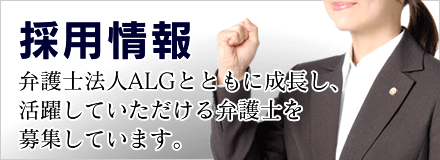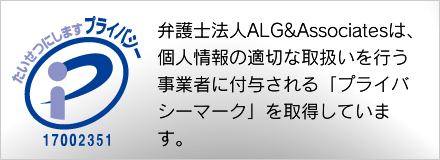【一覧表あり】相続登記に必要な書類とは?入手先や綴じ方などを解説
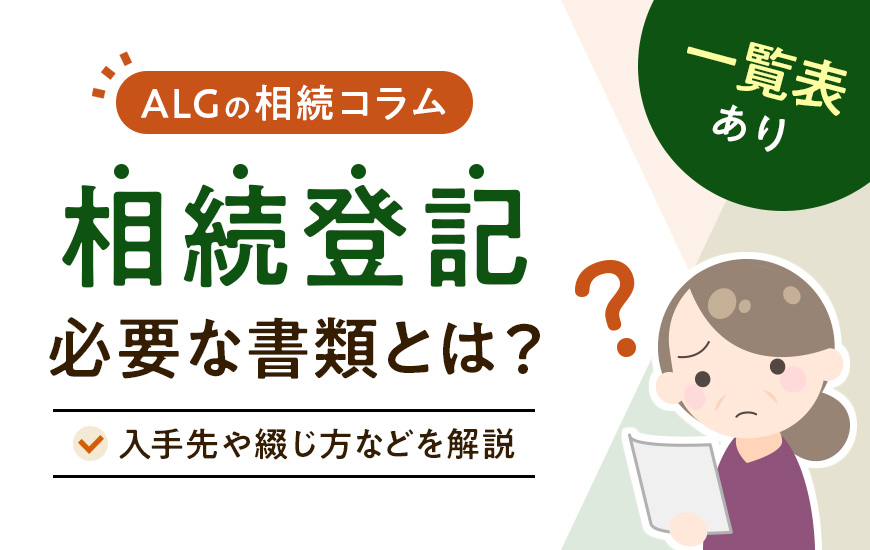
この記事でわかること
2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続した方は3年以内に登記を完了させる必要があります。そのためには、事前に多くの書類を準備しなければなりません。
さらに、必要な書類は「遺言書の有無」「法定相続分で分けるか」「遺産分割協議を行うか」など、状況によって異なります。
書類の種類や取得方法を正しく理解していないと、申請が受理されず手続きが滞る可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、ケースごとに必要な書類や入手先などについて解説します。
目次
相続登記の主要な必要書類
相続登記の申請に必要な書類は状況によって異なりますが、まずは共通して求められる基本書類を押さえておくことが、手続きをスムーズに進めるための第一歩です。
相続登記で特に重要な書類として、次のものがあげられます。
- 登記事項証明書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産取得者の住民票
- 固定資産評価証明書
- 相続関係説明図
- 相続登記申請書
登記事項証明書
相続登記を行う際は、登記申請書に不動産の情報を正確に記載することが不可欠です。そのために必要なのが、登記事項証明書です。
この証明書には、不動産の所在地や面積、所有者、担保の有無など詳細な情報が記載されており、以前は登記簿謄本と呼ばれていました。
古い証明書を持っていても、現在の登記内容と異なる場合があるため、必ず最新のものを取り寄せましょう。
登記事項証明書は法務局で入手でき、窓口での請求に加えて、オンライン申請や郵送請求も可能です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
相続登記を行うには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をそろえ、相続人を確定する必要があります。戸籍には親子関係や婚姻、養子縁組などの重要な情報が記載されています。
転籍や法改正によって複数の戸籍に分かれている場合は、現在の戸籍謄本だけでなく、全員が除籍された除籍謄本や、様式変更前の改製原戸籍も取得しなければなりません。
戸籍は本来、本籍地の役場で取得しますが、2024年3月から始まった広域交付制度を使えば、近くの役場で本人や配偶者、直系親族の戸籍をまとめて請求できます。ただし、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。
相続人全員の戸籍謄本
相続登記では、誰が相続人なのか、そして被相続人の死亡時に相続人が生存しているかを確認するため、相続人全員の戸籍謄本が必要となります。
被相続人の配偶者や未婚の子供については、現在の戸籍謄本が被相続人の死亡時の戸籍謄本と同一になる場合があります。この場合は、改めて取り寄せる必要はありません。
戸籍謄本は各相続人の本籍地の市区町村役場で取得しますが、本人や配偶者、直系親族の戸籍であれば、最寄りの役所の窓口でも請求できます。
被相続人の住民票の除票
相続登記では、不動産の登記簿上の名義人と被相続人が同一人物であることを証明するため、住民票の除票が必要となります。
除票は転出や死亡で住民基本台帳から除かれた記録で、氏名・住所・本籍が記載されており、死亡時の住所を確認できます。
戸籍には住所がないため、登記簿と戸籍の情報をつなぐ重要な書類となります。
取得は被相続人の最後の住所地の役場で行い、本籍の記載を忘れないようにしましょう。
登記簿の住所と死亡時の住所が異なる場合は、住所履歴を確認するため、戸籍の附票の提出も必要となります。
不動産取得者の住民票
相続登記では、不動産を相続する人の住所を証明するために住民票が必要です。
登記簿には名義人の住所が記載されるので、正しい住所を示す書類として住民票を提出します。必要なのは、不動産を実際に相続する人の分だけで、相続しない人の住民票は不要です。
住民票は、不動産を取得する人が住民登録をしている市区町村役場で取得することができます。
なお、マイナンバーが記載された住民票は使えないため、記載のないものを準備してください。
固定資産評価証明書
相続登記には登録免許税の納付が必要で、その金額は不動産の固定資産税評価額をもとに計算されます。そのため、評価額を証明する固定資産評価証明書が必要になります。
この証明書には不動産の所在地、所有者、評価額などが記載されており、不動産所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所)で取得できます。
必要なのは亡くなった年度のものではなく、登記申請を行う年度の証明書であるため注意が必要です。最新の評価額を確認し、正しい税額で申請できるよう準備しましょう。
相続関係説明図
相続登記を申請する際に役立つ書類のひとつが相続関係説明図です。被相続人と相続人の関係を家系図のようにまとめた図で、誰が相続人かを一目で確認できます。
必須ではありませんが、添付すると手続きがスムーズになり、コピーの提出なしに戸籍謄本の原本を返却してもらえるメリットがあります。
戸籍は銀行や相続税の手続きなどでも必要になるため、原本還付は必須です。
作成は、被相続人と相続人の氏名、住所、生年月日、続柄を記載し、線で結んで関係を示します。代襲相続や相続放棄などがある場合は、その情報も加えます。
相続登記申請書
相続登記の申請に使う書類が、相続登記申請書です。
申請書には、登記の目的や原因、相続人の氏名・住所、登録免許税額、不動産の情報などを正確に記載します。
ひな型は法務局のホームページからダウンロードでき、記載例も公開されています。
申請書が完成したら、戸籍謄本や固定資産評価証明書などの必要書類を添えて、不動産の住所地を管轄する法務局に提出します。
登録免許税は固定資産評価額 × 0.4%で計算し、収入印紙を申請書に貼付します。
【ケース別一覧表】相続登記の必要書類と入手先
相続登記の申請に必要な基本書類は、以下のとおりです。
相続登記の基本書類
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 最寄りの市区町村役場※ |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | |
| 被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地の役場 |
| 不動産取得者の住民票 | 不動産取得者の住所地の役場 |
| 相続する不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所在地の役場 |
| 登記申請書 | 申請人が作成 |
| 相続関係説明図(戸籍の原本還付を希望する場合) | 申請人が作成 |
※兄弟姉妹の戸籍やコンピューター化されていない戸籍の取得、代理人申請、郵送請求は、本籍地の役場で手続きする必要があります。
なお、相続の方法には、大きく次の3つのパターンがあります。
- 法定相続分通りに相続する場合
- 遺産分割協議により相続する場合
- 遺言により相続する場合
それぞれのケースによって、相続登記の申請に必要な書類が異なります。上記の基本書類に加えて、追加で提出しなければならない書類もあります。以下で、ケースごとに必要な書類を確認していきましょう。
法定相続分通りに相続する場合
法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの遺産の取り分のことです。
例えば、配偶者と子供が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子が残りの2分の1を均等に分けるのが原則です。
遺言書がない場合や遺産分割協議がまとまらない場合に、この法定相続分に従って登記を進めるケースが多く見られます。このときに必要となる書類と入手先は、次のとおりです。
法定相続分による相続登記の必要書類
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 最寄りの市区町村役場※ |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | |
| 被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地の役場 |
| 不動産取得者の住民票 | 不動産取得者の住所地の役場 |
| 相続する不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所在地の役場 |
| 登記申請書 | 申請人が作成 |
※兄弟姉妹の戸籍やコンピューター化されていない戸籍の取得、代理人申請、郵送請求は、本籍地の役場で手続きする必要があります。
法定相続分について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
遺産分割協議により相続する場合
法律では法定相続分が決められていますが、相続人全員の合意があれば、自由に遺産を分けることができます。法定相続人間で相続財産の分け方を話し合うことを遺産分割協議といいます。
協議で不動産を取得する相続人が決まったら、相続登記の申請を行います。
その際は、戸籍などの基本書類に加えて、以下の書類を提出しなければなりません。
遺産分割協議による相続登記の必要書類
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 遺産分割協議書 | 相続人全員で作成 |
| 相続人の印鑑証明書 | 各相続人の住所地の役場 |
遺産分割による相続登記には遺産分割協議書を添付します。
この協議書は法定相続人全員が署名し実印により押印する必要があり、印鑑証明書も添付しなければなりません。
遺産分割協議について詳しく知りたい方、また、遺産分割協議書の作成方法についての詳細はこちらの記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
遺言により相続する場合
被相続人が遺言を残して亡くなった場合、基本的にはその内容に従って遺産を分けます。
遺言によって法定相続人が不動産を取得する場合の、相続登記の必要書類は次のとおりです。
遺言により法定相続人が相続登記する場合の必要書類
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 不動産取得者の現在の戸籍謄本 | 最寄りの市区町村役場※ |
| 被相続人の死亡時の戸籍謄本 | |
| 被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地の役場 |
| 不動産取得者の住民票 | 不動産取得者の住所地の役場 |
| 相続する不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所在地の役場 |
| 登記申請書 | 申請人が作成 |
| 遺言書 | 自宅、貸金庫、公証役場、法務局など |
※兄弟姉妹の戸籍やコンピューター化されていない戸籍の取得、代理人申請、郵送請求は、本籍地の役場で手続きする必要があります。
遺言書で不動産を相続する場合は、取得する相続人がすでに決まっているため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要はありません。
準備するのは、被相続人の死亡時の戸籍謄本と、不動産を取得する人の戸籍謄本のみで十分です。
自筆証書遺言については、相続登記を申請する前に、家庭裁判所で検認を受ける必要がありますが、公正証書遺言や法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要です。
遺言により法定相続人以外の者が遺贈を受けた場合
遺言によって法定相続人ではない第三者が遺贈を受ける場合は、遺贈による所有権移転登記を行う必要があります。
この登記は、相続人全員または遺言執行者と、遺贈を受ける人との共同申請で行わなければなりません。
さらに、登録免許税率は課税価格の2%であるなど、他の相続方法とは手続きが異なるためご注意ください。
遺贈による所有権移転登記に必要な書類は以下のとおりです。遺言執行者を選任しているかどうかによって内容が変わります。
遺言執行者がいる場合の遺贈登記の必要書類
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 遺言者の死亡時の戸籍謄本 | 最寄りの市区町村役場※ |
| 遺言者の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地の役場 |
| 受遺者の住民票 | 受遺者の住所地の役場 |
| 相続する不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所在地の役場 |
| 登記申請書 | 申請人が作成 |
| 遺言書 | 自宅、貸金庫、公証役場、法務局など |
| 登記済権利証または登記識別情報 | 自宅、貸金庫など |
| 遺言執行者の印鑑証明書 | 遺言執行者の住所地の役場 |
| 遺言執行者選任審判謄本(家裁の審判で選任された場合) | 家庭裁判所 |
※兄弟姉妹の戸籍やコンピューター化されていない戸籍の取得、代理人申請、郵送請求は、本籍地の役場で手続きする必要があります。
遺言執行者がいない場合の遺贈登記の必要書類
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 遺言者の死亡時の戸籍謄本 | 最寄りの市区町村役場※ |
| 相続人全員の戸籍謄本 | |
| 被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地の役場 |
| 受遺者の住民票 | 受遺者の住所地の役場 |
| 相続する不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所在地の役場 |
| 登記申請書 | 申請人が作成 |
| 遺言書 | 自宅、貸金庫、公証役場、法務局など |
| 登記済権利証または登記識別情報 | 自宅、貸金庫など |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人の住所地の役場 |
※兄弟姉妹の戸籍やコンピューター化されていない戸籍の取得、代理人申請、郵送請求は、本籍地の役場で手続きする必要があります。
遺言書について詳しく知りたい方、また法定相続人については、こちらの記事をご覧ください。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続登記の必要書類の綴じ方
相続登記の書類には、並べ方と綴じ方のルールがあります。
法定相続による登記で、原本還付を希望する場合の一般的な並べ方は、次のとおりです。
- 登記申請書
- 収入印紙貼付台紙(登録免許税分の印紙を貼付)
- 委任状(代理人申請の場合)
- 相続関係説明図
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産取得者の住民票のコピー
- 固定資産評価証明書のコピー
- 相続人の戸籍謄本、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の原本
- ⑤~⑦の原本
申請書と印紙台紙はホッチキスで綴じ、割印を押します。次に、原本還付を希望する書類のコピーをホッチキスで綴じて割印し、一番上に原本還付 この写しは原本に相違ありません 氏名 印と記載します。
委任状や相続関係説明図、原本はクリップでまとめて添付しましょう。
相続登記の必要書類に有効期限はある?
相続登記の必要書類に、有効期限はありません。そのため、古い戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書なども使用できます。
ただし、相続人の戸籍謄本は必ず被相続人の死亡日以降に取得したものでなければなりません。相続人が現在も生存していることを証明するためです。
一方、固定資産評価証明書は登録免許税の計算に必要なため、登記申請年度の最新のものを添付する必要があります。
たとえば、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに申請する場合は、令和7年度の証明書を用意します。
また、特殊なケースとして、未成年者の親権者が法定代理人として登記申請する場合があります。
この場合、代理権を証明する戸籍謄本は発行から3ヶ月以内のものである必要があります。
相続登記の必要書類は自分で用意できる?
相続登記に必要な書類は自分でそろえることができます。戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書は役所で取得でき、登記申請書は法務局のサイトからダウンロード可能です。
自分で準備するメリットは、専門家への報酬が不要で費用を節約できる点です。
ただし、書類集めや申請書の作成には時間と労力がかかり、法律で定められたルールに従う必要があります。
不備があると法務局で補正を求められ、何度も足を運ぶ可能性もあります。
費用を節約したい方には有効ですが、正確な知識と根気が求められるため、専門家に依頼することをおすすめします。
代理人が相続登記する場合は委任状が必要
本来、相続登記は不動産を相続した本人が行うものですが、事情により本人以外が申請する場合は、委任状が必要となります。
委任状が求められるケースとして、弁護士などの専門家や親族に依頼する場合、共同相続で代表者が他の相続人分も申請する場合があげられます。
一方、未成年者の親権者や成年後見人、遺言執行者などが代理する場合は不要です。
委任状には委任者と代理人の氏名・住所、不動産情報などを記載します。専門家に依頼する場合は、専門家が委任状を用意するため、署名と押印だけで済みます。
相続登記の必要書類についてよくある質問
相続登記で提出した必要書類は返却されますか?
相続登記に必要な戸籍謄本や住民票などの書類は、原本の提出が原則です。
ただし、原本還付の手続きをすれば、登記完了後に返却してもらうことが可能です。
方法は、原本とコピーを一緒に提出し、コピーに「原本と相違ない」と書いて署名・押印するだけです。
戸籍謄本については、相続関係説明図を添えれば、コピーなしでも還付されます。
返却は法務局の窓口で受け取るか、返送用封筒を入れておけば郵送も可能です。
ただし、登記申請書や委任状など登記専用の書類は返ってきません。
相続登記に不動産の権利証は必要ですか?
相続登記では、不動産の権利証(登記済証・登記識別情報)の提出は不要です。
権利証は売買などで所有権を移転するとき、本人確認のために使われますが、相続登記は相続を原因とするため、その確認は不要です。
法務局では戸籍謄本などで相続関係を証明することで手続きを進めるため、権利証は必要ありません。
ただし、登記簿上の住所と被相続人の最後の住所のつながりが確認できない場合や、遺贈による登記、法定相続分で登記後に遺産分割する場合などでは、権利証が必要になるケースがあります。
相続登記についてお悩みの方は、弁護士法人ALGへご相談ください!
相続登記は、戸籍謄本の収集、申請書の作成など、専門知識が必要な複雑な手続きです。
書類に不備があると、申請が受理されず時間と労力が無駄になることもあります。こうしたトラブルを防ぐには、専門家への依頼が安心です。
弁護士に依頼するメリットは、相続登記の手続きだけでなく、遺産分割協議やトラブル対応まで一括してサポートしてもらえることです。
さらに、必要書類の収集も任せられるため、依頼者の負担が軽減されます。複雑なケースや相続人間で意見が分かれる場合も、弁護士なら法的な解決策を提示できます。
「相続登記について何から始めればいいかわからない」「書類の準備が不安」という方は、相続問題に精通した弁護士法人ALGにぜひご相談ください。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)