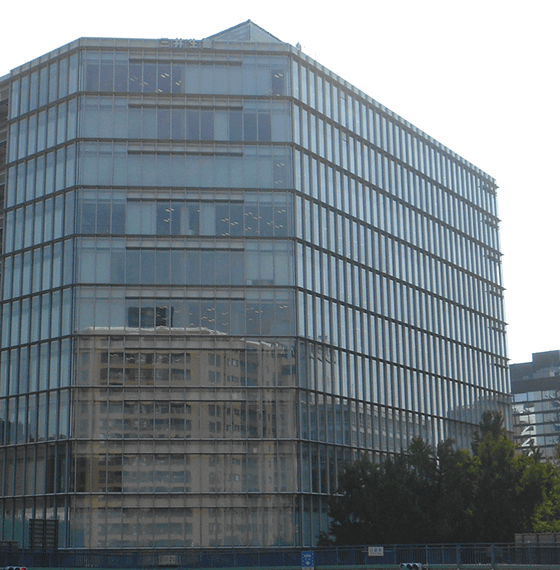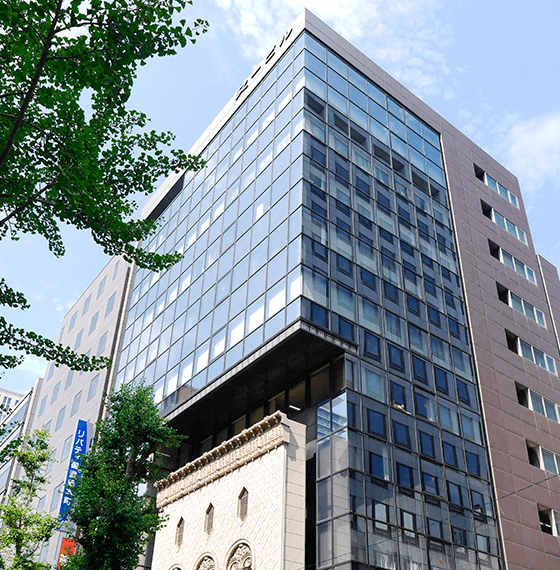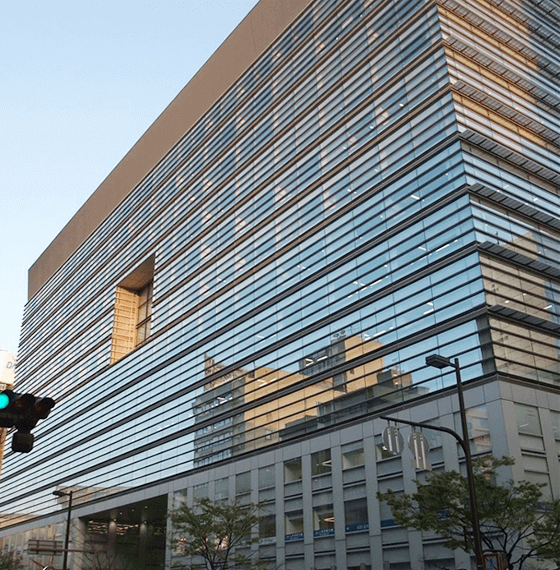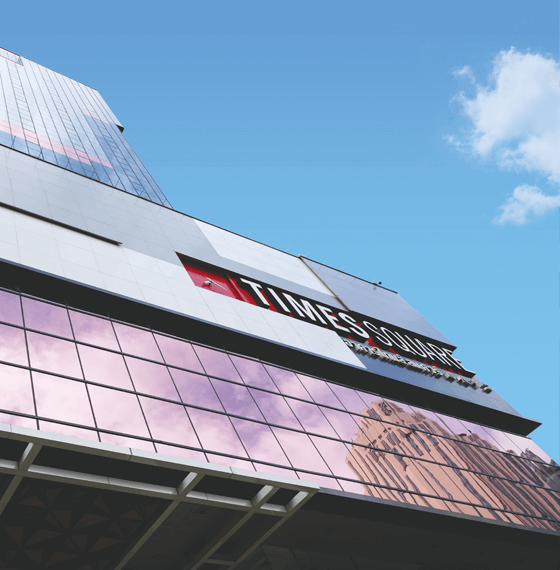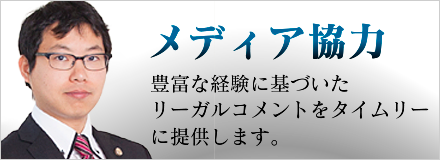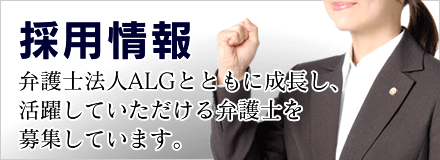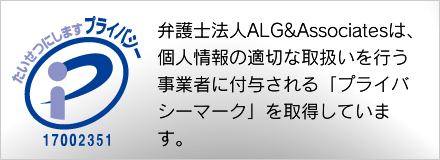相続財産清算人(相続財産管理人)とは?民法改正や選任の流れ、費用など
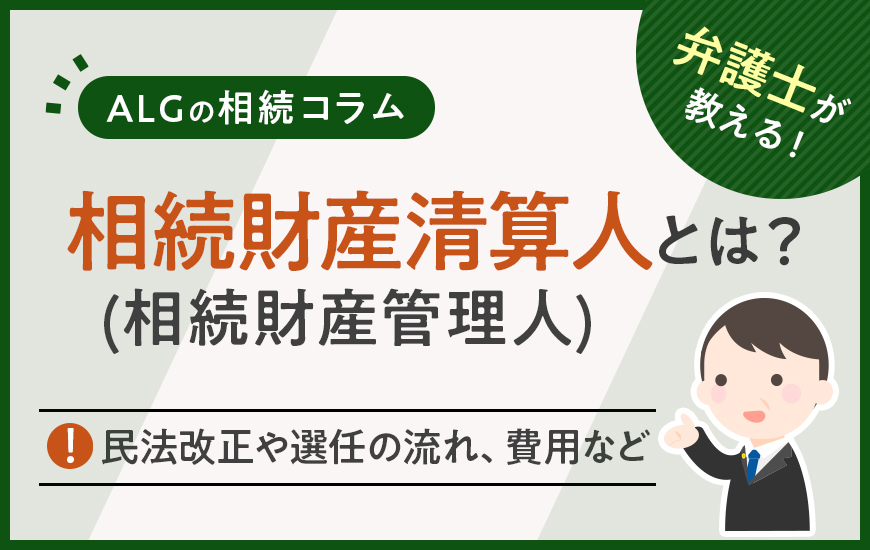
この記事でわかること
相続人がいない、または相続人全員が相続放棄をした場合、そのままでは遺産が放置され、借金の返済や不動産の管理ができません。
こうしたときに必要になるのが相続財産清算人(旧:相続財産管理人)です。
相続財産清算人は裁判所が選任し、相続財産を清算し、債権者や受遺者への支払いから国への引き渡しまで重要な役割を担います。
この記事では、相続財産清算人の役割や選任の流れ、誰が申立てできるのか、必要書類や費用などについて解説します。
目次
相続財産清算人(相続財産管理人)とは
相続財産清算人とは、相続人がいない場合に、亡くなった方の財産を管理し、最終的に清算する役割を担う人 のことです。
たとえば、Aさんが亡くなり、相続人全員が相続放棄した場合、借金の返済や不動産管理などが滞り、債権者や近隣住民に迷惑がかかるおそれがあります。
このような場合、債権者や特別縁故者などの利害関係人が家庭裁判所に申し立て、裁判所が弁護士などの専門家を清算人に選任します。
清算人は、預金や不動産などの遺産を調査・管理し、必要に応じて不動産を売却して現金化します。
その資金で借金を返済し、遺言で指定された受遺者や特別縁故者に分配します。最終的に残った財産は国に引き渡されます。
相続財産清算人の権限
相続財産清算人には、被相続人の財産を適切に管理するために、法律で定められた権限があります。大きく分けると保存行為・管理行為と処分行為の2種類です。
保存行為・管理行為とは、財産の価値を守るための行為です。家庭裁判所の許可は不要で、清算人自身の判断で行うことができます。
たとえば、不動産の相続登記や建物の修繕、預金口座の払い戻しや解約、賃貸契約の解除などが該当します。
一方、処分行為は財産の形を変える行為で、家庭裁判所の許可が必要です。不動産や株式の売却、家具や家電の処分、墓地の購入や永代供養料の支払いなどがあげられます。
許可を得ずに処分行為を行うと、清算人自身が損害賠償など法的責任を問われる可能性があります。
相続財産清算人には誰がなる?
相続財産清算人になるために特別な資格は不要ですが、家庭裁判所が適任と判断した人が選ばれます。
実務では、複雑な手続きに対応できる弁護士などの専門家が選ばれることが多いです。申立人が候補者を推薦することもできますが、最終的な決定は裁判所が行います。
ただし、清算人の選任を請求するには要件があります。
まず、申立人と被相続人に利害関係があることが必要で、債権者や受遺者、特別縁故者、相続財産の管理者、相続放棄した相続人などが該当します。
また、相続財産があることも条件です。財産が少ないと費用倒れのリスクがあるため、申立ては現実的ではありません。
さらに、相続人の有無が不明であることも必要で、相続人が判明している場合は、清算人を選任する必要がありません。
【民法改正】相続財産清算人と相続財産管理人との違い
2023年4月1日の民法改正により、従来の 相続財産管理人は 相続財産清算人に名称変更され、さらに新たに 相続財産管理人という制度が設けられました。これは単なる名前の変更ではなく、それぞれの権限を明確にするための改正です。
相続財産清算人は、相続人がいない場合や全員が相続放棄した場合に選任され、財産の管理だけでなく、処分も行えます。
不動産や預貯金などを売却してお金に換え、借金の返済や遺贈の実行、特別縁故者への分配、国庫への帰属まで担当します。
一方、新設された相続財産管理人は、遺産の保存や管理のみを行う者で、売却などの処分権限はありません。
不動産や預貯金の維持管理などに限られ、相続人がいるが管理が難しいような場合に利用されます。
相続財産清算人の選任が必要なケース
相続財産清算人は、相続財産を管理する人が誰もいないときに選任されます。
清算人の選任が必要なケースとして、以下があげられます。
- 相続人がいない
- 相続人全員が放棄した
- 遺言書で遺贈の指定があった
相続人がいない
法定相続人がいない場合は、遺産を管理する人がいないため、相続財産清算人の選任が必要となります。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。配偶者、子供や孫、親や祖父母、兄弟姉妹や甥・姪などが該当します。
これらの親族がすべて亡くなっている、または存在しない場合、相続人が不存在となります。
清算人の選任が必要なケースとして、被相続人にお金を貸していた債権者が返済を受けたい場合や、遺言で財産を受け取る予定の人がいる場合、倒壊しそうな建物など遺産を管理する必要がある場合があげられます。
さらに、内縁の配偶者や長年介護をしていた人などが、特別縁故者として財産分与を希望する場合にも、清算人の選任が求められます。
相続人全員が相続放棄した
相続放棄をすると、法律上は最初から相続人でなかったと扱われます。
相続権のある人全員が放棄すれば相続人がいなくなるため、相続財産清算人の選任が必要です。
特に、被相続人に多額の借金がある場合は全員が放棄するケースが多く、債権者などの利害関係人が家庭裁判所に申し立てて清算人を選任する必要があります。
なお、民法改正により、相続放棄をした場合、相続放棄の時点で相続財産を「現に占有」していた場合に限り、その相続財産の管理義務を負うことになりました。
例えば、青森県で暮らしていた両親が亡くなり、東京に暮らす子供が相続放棄した場合、子供がその家の保存・管理に全くかかわっていなければ、自宅の管理義務はありません。
遺言書に遺贈の指定があった
遺言書で第三者に財産を渡すと書かれている場合、その内容を実現する必要があります。
相続人がいるときは、相続人が遺贈義務者となり、受遺者(財産を受け取る人)に引き渡します。
しかし、相続人がいない場合は、財産を引き渡す相手がいないため、受遺者などの関係者が家庭裁判所に申し立てて、相続財産清算人を選んでもらう必要があります。
清算人は、不動産を売却して現金化するなど、遺言の内容を実現するための手続きを行います。
ただし、遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、清算人の選任を申し立てる必要はありません。
遺言執行者には、遺言を実行するための権限があり、相続人の同意なしで財産を管理・処分できるからです。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続財産清算人の選任方法・流れ
相続人がいない場合は、残された財産や借金を整理するために、相続財産清算人を選任する必要があります。手続きの流れは以下のとおりです。
- 必要書類の準備
- 家庭裁判所への申立て
- 審判
まず必要書類を準備します。
申立書、被相続人の出生から死亡までの戸籍、財産を証明する資料、利害関係を示す資料などが必要です。
申立書の書式や記載例は、家庭裁判所のホームページで確認できます。
次に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
申し立てできるのは、債権者や受遺者、特別縁故者などの利害関係人、または検察官です。
最後に、裁判所の審判があります。
裁判所が必要性を認めると、相続財産清算人が選任されます。
清算人は財産を売却して現金化し、債権者や受遺者への支払い、特別縁故者への分配を行い、残った財産は国に引き渡します。
相続財産清算人の選任にかかる費用
相続財産清算人の選任申立てには、申立て費用のほかに専門家報酬や予納金がかかることがあり、費用がかさむ可能性があります。
そのため、申立てを行うには、相続財産が一定額以上あることが前提となります。
申立て費用
相続財産清算人の選任申立てには、次のような費用がかかります。
-
収入印紙:800円
申立書に貼付する手数料です。 -
連絡用の切手:1000円~2000円程度
金額や内訳は裁判所により異なるため、事前確認が必要です。 -
官報公告料:5075円
清算人の選任と相続人の捜索を公告するための費用です。 -
必要書類の取得費用:数千円程度
戸籍謄本や住民票、登記事項証明書などの発行には手数料がかかります。 -
予納金(必要な場合のみ):10万~100万円程度
清算人の業務に必要な費用をまかなうために、事前に裁判所に預けるお金です。 -
専門家報酬:月1万~5万円程度
弁護士や司法書士などの専門家が清算人に選任された場合は、相続財産から報酬が支払われます。
予納金
予納金とは、相続財産清算人の活動に必要な経費や報酬をまかなうために、申立人が家庭裁判所に一時的に預けるお金のことです。
金額は財産の規模や内容、手続きの複雑さによって異なり、家庭裁判所が決定します。
一般的な相場は10万円から100万円程度とされています。予納金を支払う期限は、基本的に選任申立てを行ってから1ヶ月以内です。
相続財産に十分な現金や預貯金があれば予納金が不要になる場合もありますが、短期間で現金化できる資産が少ない場合は必要です。
なお、予納金はあくまで一時的な預け金であり、相続財産から報酬や費用をまかなえた場合は、余った分が返還されます。
予納金の支払いが難しい場合は、法テラスを利用して分割払いすることも可能です。
相続財産清算人の選任に必要な申立書類
相続財産清算人の選任申立てに必要な書類として、以下があげられます。
- 相続財産清算人選任の申立書(家事審判申立書に800円の印紙を貼付)
- 財産目録
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の子供およびその代襲者で死亡している方がいる場合は、被相続人の子供およびその代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合は、その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本
- 代襲者としての甥姪で死亡している方がいる場合は、その甥または姪の死亡記載がある戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続財産を証明する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しや残高証明書、有価証券の残高証明書など)
- 相続財産清算人の候補者を立てる場合は、候補者の住民票または戸籍附票
相続財産清算人を選任した後の流れ
相続財産清算人を選任した後の手続きの流れは、以下のとおりです。
- 家庭裁判所による選任公告
- 相続財産清算人による財産管理
- 債権者・受遺者に対する請求申出の公告や弁済
- 特別縁故者への財産分与
- 残った財産の国庫への帰属
①家庭裁判所による選任公告
相続財産清算人が家庭裁判所により選任されると、その情報はすぐに官報で公告されます。
公告には、清算人が選任されたことに加え、相続人がいる場合は一定期間内に名乗り出るよう求める内容が記載されます。
この公告は6ヶ月以上の期間を定めて行われ、期間内に申し出がなければ、相続人がいないことが確定します。その後、清算人は財産の管理や債務の支払いなどの手続きを進めます。
一方、公告期間中に相続人が現れた場合は、財産は相続人に引き渡され、手続きは終了します。
公告の目的は、見落とされている相続人がいないか確認し、誤って手続きを進めることを防ぐことにあります。
②相続財産清算人による財産管理
相続財産清算人が最初に行う大切な仕事が、財産目録の作成です。
不動産や預貯金、株式、債権、借金などすべての財産や負債を調査し、その内容を記載した財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。この目録は、今後の清算手続きの土台となる重要な書類です。
財産目録の作成後は、財産の管理を一元化します。
具体的には、亡くなった方の預貯金を解約して、相続財産清算人名義の口座にまとめます。不動産については、登記名義を「亡○○○○相続財産」に変更し、必要に応じて売却の準備を進めます。
また、未回収の債権があれば回収も行います。
③債権者・受遺者に対する請求申出の公告や弁済
相続財産清算人は、被相続人にお金を貸していた債権者や、遺言で財産を受け取る受遺者に対し、2ヶ月以上の期間を設けて、その間に請求の申し出をするよう官報で公告します。
この公告は、6ヶ月以上の相続人捜索期間が終わるまでに完了させる必要があります。また、すでに分かっている債権者や受遺者に対しては個別に通知し、請求を促します。
2ヶ月以内の公告期間内に請求の申し出がなければ、債権者や受遺者は弁済を受ける権利を失います。
公告期間が終わると、清算人は届出のあった債権者に対して、債権額に応じて弁済を行い、その後に受遺者への支払いを進めます。
④特別縁故者への財産分与
被相続人と特別な関係があった特別縁故者は、相続人捜索の 公告期間が終了してから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ財産分与を申し立てることができます。
被相続人と生活を共にしていた人、被相続人の療養看護に尽くした人、または特別なつながりを持っていた人は、特別縁故者として扱われます。
家庭裁判所は、被相続人との関係性や事情を踏まえて、相続財産の全部または一部を分与するかどうかを判断します。
決定後、相続財産清算人がその内容に従って、特別縁故者に財産を引き渡します。
⑤残った財産の国庫帰属
債権者への弁済、受遺者や特別縁故者への財産分与、相続財産清算人への報酬の支払いなどが終わっても、まだ財産が残っている場合、その財産は国のものとなります。
このとき、相続財産清算人は残った相続財産を国に引き渡す手続きを行います。
手続きが終わったら、清算人は、家庭裁判所に「すべての管理が終わった」という報告書を提出し、清算人の仕事は終了します。
相続財産清算人に関するよくある質問
相続財産清算人(相続財産管理人)の報酬はいくらですか?
相続財産清算人の報酬額は、家庭裁判所が決定しますが、一般的な相場は月額1万~5万円程度となります。
ただし、あくまで目安であり、実際の金額は財産管理にかかる手間や手続きの量などによって変動します。
たとえば、不動産の売却や債権回収など手間のかかる業務が多い場合は、報酬が高くなる傾向があります。 清算人への報酬は通常、相続財産から支払われますが、財産が不足している場合は、申立人が予納金として事前に裁判所に納める必要があります。
相続財産清算人(相続財産管理人)の予納金が払えない場合はどうなりますか?
相続財産清算人を選任する際には、20万~100万円程度の予納金が必要になる場合があります。
正確な金額や必要性は、家庭裁判所に申立てをして初めてわかります。
予納金は申立てから約1ヶ月以内に納める必要があり、期限までに支払わなければ清算人は選任されず、相続手続きは進みません。
支払いが難しい場合は、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用して立替払いを受け、分割で返済することも可能です。ただし、利用には収入や資産に関する条件があるため、事前の確認が必要です。
相続財産清算人(相続財産管理人)が誰であるか調べる方法はありますか?
まず、官報の公告を調べる方法があります。
相続財産清算人が選任されると、官報に被相続人の氏名や住所、清算人の氏名などが掲載されます。インターネット版官報で閲覧することができます。
もう一つの方法は、法務局で不動産登記申請書とその添付書類を閲覧することです。清算人が不動産の名義変更を行う際、申請書に清算人情報が記載されるため、これを確認することで特定できます。
ただし、この閲覧には債権者など利害関係人であることを証明する必要があります。
相続財産清算人(相続財産管理人)が必要なときは相続に詳しい弁護士にご相談ください
相続財産清算人の選任申立ては、相続人がいない場合に必要となり、債権者や受遺者、特別縁故者などが申立てできます。
ただし、手続きは複雑で必要書類も多いため、個人で対応するのは大変です。また、予納金の納付が必要になる場合もあり、遺産が少ない場合は費用対効果の判断も求められます。
弁護士に依頼すれば、申立ての必要性を正確に判断でき、書類作成や裁判所とのやり取りも一括して任せられます。
さらに、相続放棄や遺言執行など、その他の相続に関する疑問もまとめて相談できます。
被相続人にお金を貸していた方、生前に介護をしていた方、相続放棄後の管理に不安がある方など、相続財産清算人が必要な場合は、相続に詳しい弁護士にご相談ください。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)