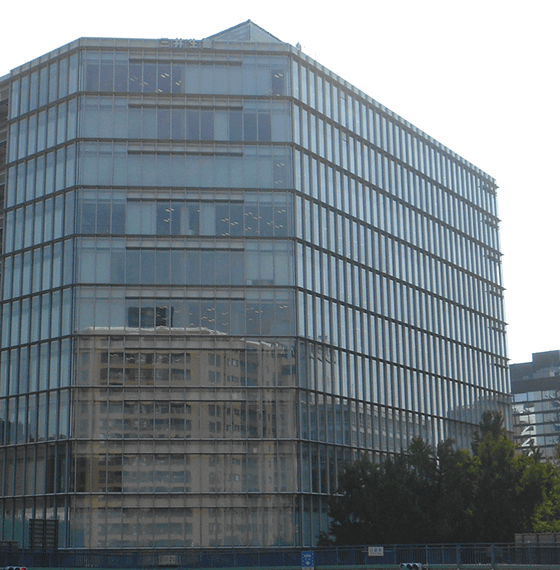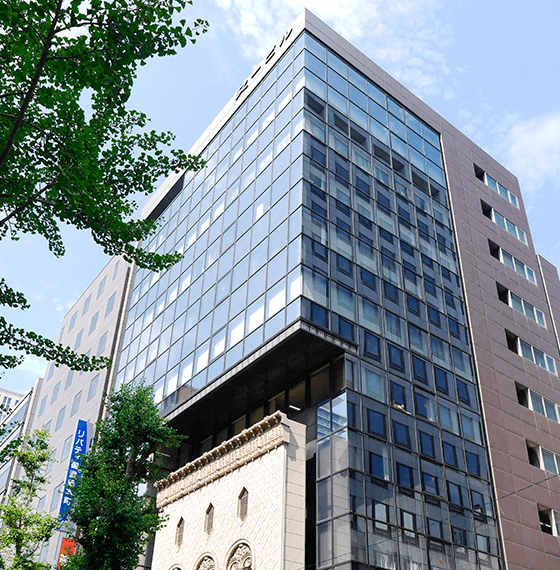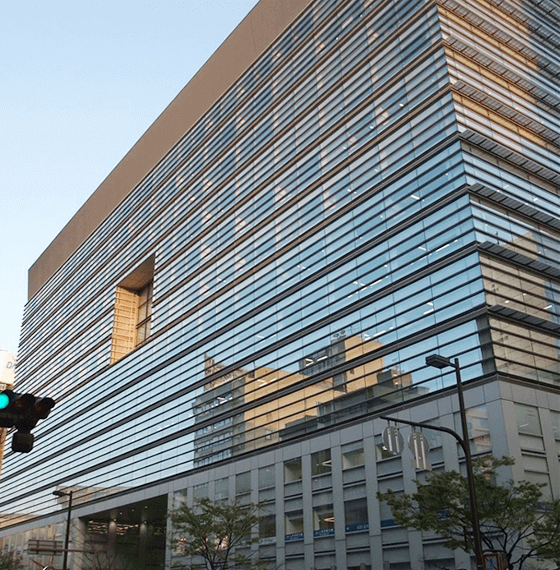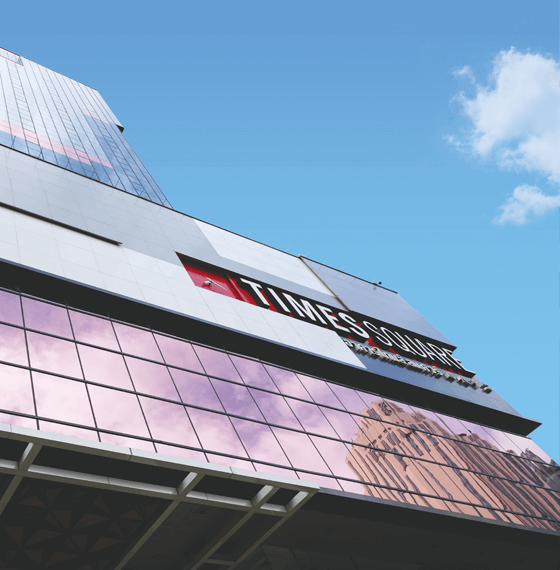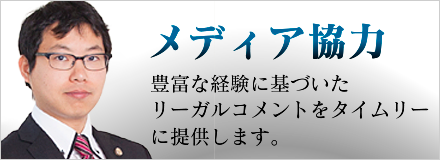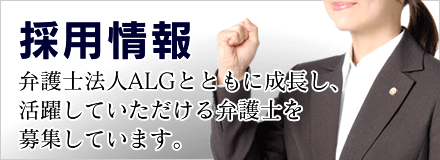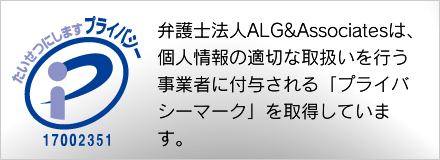特別寄与料とは?相場はいくら?請求方法・相続税などを解説
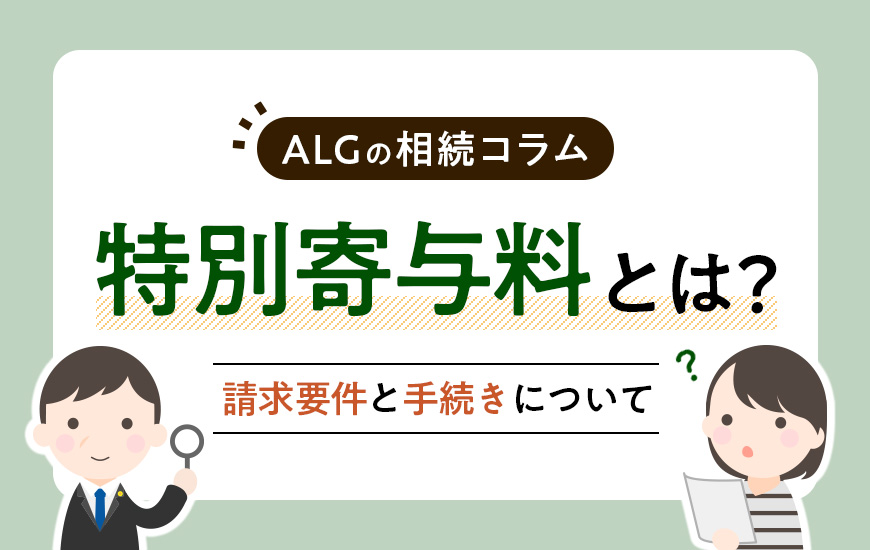
この記事でわかること
特別寄与料(とくべつきよりょう)は、相続人ではない親族が介護などで貢献した場合に、その努力に報いるために作られた制度です。
2019年7月1日の民法改正により新しく導入されました。従来の寄与分制度では、介護などを行った人が相続人でなければ、その努力に報いることが難しい状況でした。
こうした不公平を解消するために、特別寄与料が新設されました。
この記事では、特別寄与料の基本的な考え方や請求条件、請求方法などについて解説します。
目次
特別寄与料とは
特別寄与料とは、相続人ではない親族が、亡くなった方(被相続人)に対して無償で介護や家業の手伝いなどを行い、財産の維持や増加に貢献をした場合に、相続人へ金銭を請求できる制度です。
2019年7月の民法改正により導入されました。
この制度の最大のポイントは、相続権のない親族でも請求できる点にあります。
従来の寄与分は相続人にしか認められていなかったため、たとえば長男の妻が義父を長年介護しても、相続権がないため報酬を受け取ることはできませんでした。
しかし、この制度が導入されたことで、長男の妻にも、自らの権利として、特別寄与料を請求することが認められるようになりました。
特別寄与料の支払いの要否や金額は、まず当事者間の話し合いで決めますが、合意できない場合は家庭裁判所が判断します。
特別寄与料を請求できる人は?
特別寄与料を請求できるのは、被相続人の親族でありながら、相続人ではない人に限られます。親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族を指します。たとえば、被相続人の子の妻、被相続人の兄弟姉妹、甥・姪などが該当します。
祖母の兄弟の孫といった遠い親族も対象となるため、請求できる範囲は比較的広いといえます。この請求権を持つ人を特別寄与者と呼びます。ただし、相続人や相続放棄をした人、相続欠格や廃除によって相続権を失った人は対象外です。
また、被相続人と親族関係にない友人や内縁関係のパートナー、介護ヘルパーなどは、どれほど貢献していても特別寄与料を請求することはできません。
特別寄与料を請求するための要件
特別寄与料を請求するには、相続人以外の親族であることに加え、以下の要件を満たす必要があります。
無償で療養看護その他の労務を提供したこと特別寄与料を請求するには、被相続人に対して報酬を受け取らずに介護や看護、家業の手伝いなどの労務を提供していたことが必要です。
たとえば、長男の妻が義父を無償で介護したり、姪が農業を手伝って事業を維持したケースが該当します。金銭援助のみでは認められない点にご注意ください。
被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたことさらに、無償での労務提供によって被相続人の財産が維持または増加したことが求められます。
たとえば、介護サービスを利用せずに済み、介護費用を節約できた場合などがあげられます。
一方で、単なる精神的な支援や短期間の手伝いでは、特別寄与とは認められません。
特別寄与料の相場と計算方法
特別寄与料の金額に法的な決まりはなく、まずは当事者間の話し合いで決めるのが基本です。
当事者が合意すれば自由に金額を設定できます。ただし、特別寄与料の金額には上限があり、相続開始時の被相続人の財産から遺贈分を差し引いた残額を超えることはできません。
また、特別寄与料は寄与分とは異なり、遺産分割とは別問題ですので、遺産分割協議の中で決定できない点に注意が必要です。
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に申し立てて、調停や審判で金額を決定します。裁判所は、寄与の時期や方法、程度、相続財産の額などの事情を考慮して判断します。
以下では、家庭裁判所による特別寄与料の主な計算方法について解説します。
被相続人の看護をした場合(療養看護型)
療養看護型の特別寄与料は、次の計算式で求められます。
特別寄与料=介護日数×介護報酬相当額×裁量割合
介護日数自宅で実際に介護を行った日数を指します。入院期間や施設入所期間、介護サービスを受けた期間は原則として除外されます。
介護報酬相当額介護保険で要介護度に応じて決められる介護報酬基準額をもとに算定し、1日5,000~8,000円程度が目安です。要介護度が高い場合や長時間介護では上限に近い額が用いられます。
裁量割合親族には扶養義務があることや、介護が専門職によるものではない点を考慮し、報酬を調整するために用いられます。一般的には0.5~0.9で設定され、0.7が採用されることが多いです。
具体例介護日数:300日、介護報酬相当額:6,000円、裁量割合:0.7の場合、
特別寄与料=300日×6,000円×0.7=126万円になります。
被相続人の事業に従事した場合(家業従事型)
家業従事型の特別寄与料は、次の計算式で求められます。
特別寄与料=特別寄与者が通常得られたであろう給与額×(1−生活費控除割合)×寄与期間
特別寄与者が通常得られたであろう給与額賃金センサス(厚生労働省の統計)を参考に、家業と同種・同規模の事業に従事する同年齢層の賃金を基準とします。
生活費控除割合家業従事中に住居費や食費などを被相続人に負担してもらっていた場合、その分を差し引くための割合です。相場は0.3~0.5で、同居して生活費をほぼ負担してもらっていた場合は0.5が多く採用されます。
寄与期間実際に家業に従事していた期間を指します。
計算例通常得られたであろう給与額:20万円、生活費控除割合:0.5、寄与期間:5年間(60ヶ月)
特別寄与料=20万円×(1−0.5)×60ヶ月=600万円になります。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
特別寄与料の請求方法
特別寄与料の請求方法として、以下があげられます。
- 当事者同士で話し合う
- 家庭裁判所に調停を申し立てる
当事者同士で話し合う
特別寄与料を請求する際は、まず相続人と直接話し合うことが基本です。その際、自分がどの程度、療養看護や家業従事などをしてきたのかを具体的に説明できるよう準備しておくと良いでしょう。
そのためには、介護日誌や医療機関の領収書、家業に関する記録など、寄与の事実を裏付ける証拠を揃えておくことが大切です。
交渉がまとまり、合意に至った場合は、必ず書面で合意内容を残しましょう。口頭での約束だけでは後々トラブルになる可能性があるためです。合意書には、金額、支払い期日、当事者の署名や押印などを明記しましょう。
家庭裁判所に調停を申し立てる
相続人との話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てることができます。
調停はあくまでも話し合いの場であり、特別寄与料の金額や支払いについて全員の同意が得られないときは、調停は不成立になります。
その場合は、自動的に審判の手続きに進み、最終的に裁判官が特別寄与料の支払いの要否や金額を判断します。
特別の寄与に関する処分調停を申し立てるときの申立先や期限などの詳細は、下表にまとめていますのでご確認ください。
| 申立先 | 相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所 |
|---|---|
| いつまでに申し立てるのか | 相続が開始されたことと相続人を知った時から6ヶ月以内、または相続開始から1年以内 |
| 申し立てにかかる費用 |
|
| 必要書類 |
|
特別寄与料に請求期限・時効はある?
特別寄与料は、相続が開始されたことと相続人を知った時から6ヶ月、または相続開始から1年を経過したときには請求できなくなります。
特別寄与料の請求を考えている場合は、相続が開始されてから、相続人が誰かについての調査をすぐに始める必要があります。
特別寄与料には相続税がかかる
特別寄与料を受け取った場合特別寄与料は、税法上遺贈として扱われるため、相続税の対象になります。ただし、特別寄与料が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以内であれば申告は不要です。
超える場合は、金額確定を知った翌日から10ヶ月以内に申告・納税する必要があります。なお、配偶者や一親等の血族以外が受け取る場合、相続税額が2割加算となるためご注意ください。
特別寄与料を支払った場合特別寄与料を支払った相続人は、その金額を相続税の課税対象財産から控除できます。相続税を納税済みでも、特別寄与料の金額確定から4かヶ月以内に更正の請求をすれば、過払い分の還付を受けられます。
特別寄与料に関するよくある質問
特別寄与料と寄与分の違いは何ですか?
特別寄与料と寄与分は、どちらも被相続人に対して特別な貢献をした場合に考慮される制度ですが、対象者や対象となる行為に明確な違いがあります。
寄与分は、法定相続人のみが対象で、介護や家業への従事、金銭の出資、財産管理など幅広い行為が認められます。
一方、特別寄与料は、法定相続人以外の親族(6親等内の血族や配偶者、3親等内の姻族など)が対象で、無償で療養看護や家業の手伝いといった労務を提供した場合に限られます。
たとえば、息子の妻が義父を無償で介護していた場合、寄与分の対象にはなりませんが、特別寄与料の対象となる可能性があります。
このように、貢献した人が相続人かどうか、そしてどのような行為を行ったかによって、適用される制度が異なります。
特別寄与料は遺産分割協議書に記載できますか?
結論として、特別寄与料は遺産分割協議書には記載しません。
特別寄与料は相続人と特別寄与者(相続人以外の親族)との間で取り決めるものであり、相続人同士で遺産を分ける遺産分割協議とは別手続きだからです。
遺産分割協議書は相続人間で遺産の分配方法を決める書類であり、特別寄与料は対象外です。
そのため、相続人と特別寄与者との間で別途特別寄与料に関する合意書(協議書)を作成し、金額や支払い方法などを明記して署名・押印することが必要です。
なお、実務上は、相続人全員が合意すれば遺産分割協議書に記載するケースもありますが、必須ではなく、証拠性を考慮すると別途合意書を作成する方が安全です。
特別寄与料の請求については弁護士にご相談ください
被相続人の介護等を行っていたにもかかわらず、自分には相続権がないケースでは、特別寄与料の請求をしたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、特別寄与料は新しい制度であり、金銭を請求されると認識している相続人は少ないため、トラブルに発展するリスクがあります。
また、相続人を正確に把握することが難しいケースもあるため、自分で請求することのハードルは高いと考えられます。
そこで、特別寄与料の請求を検討している方は弁護士にご相談ください。弁護士であれば、相続人を特定する方法や、相続人から反発を受けた場合の対処等についてアドバイスができます。
請求期限が短いので、なるべく早い時点での相談をおすすめします。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)