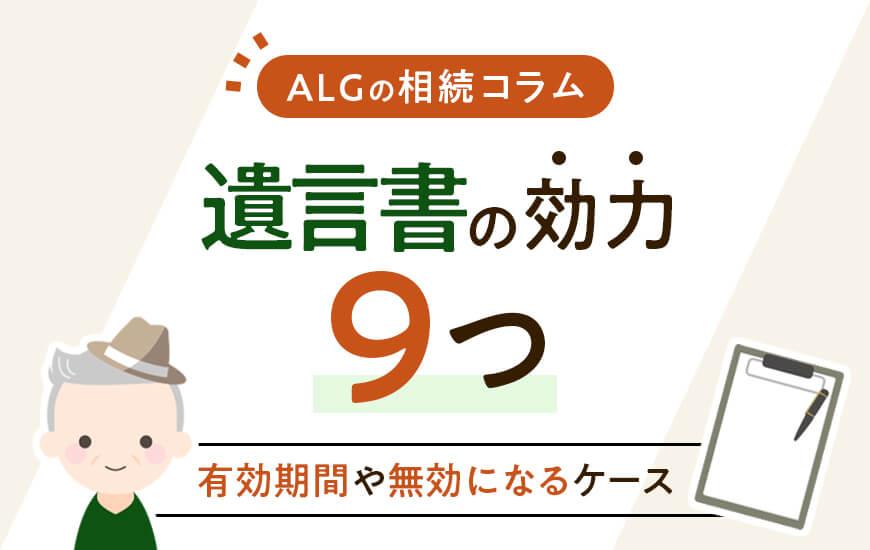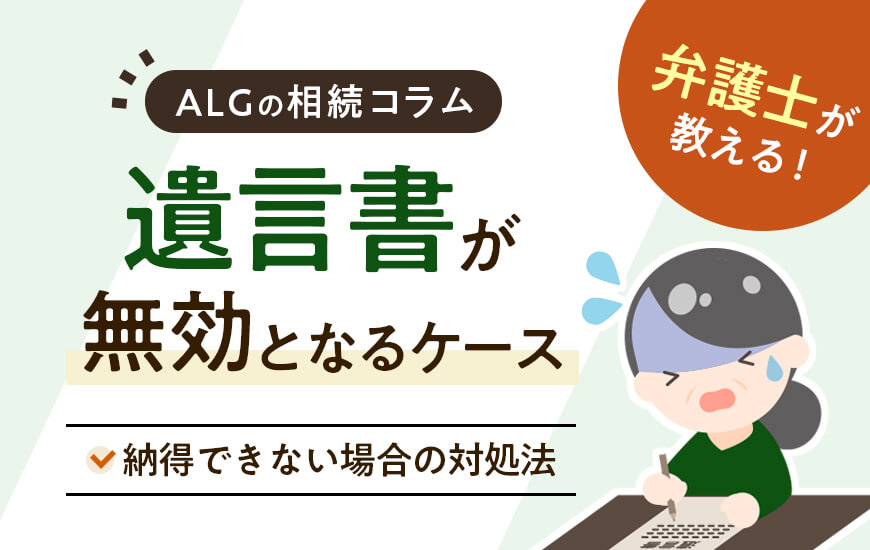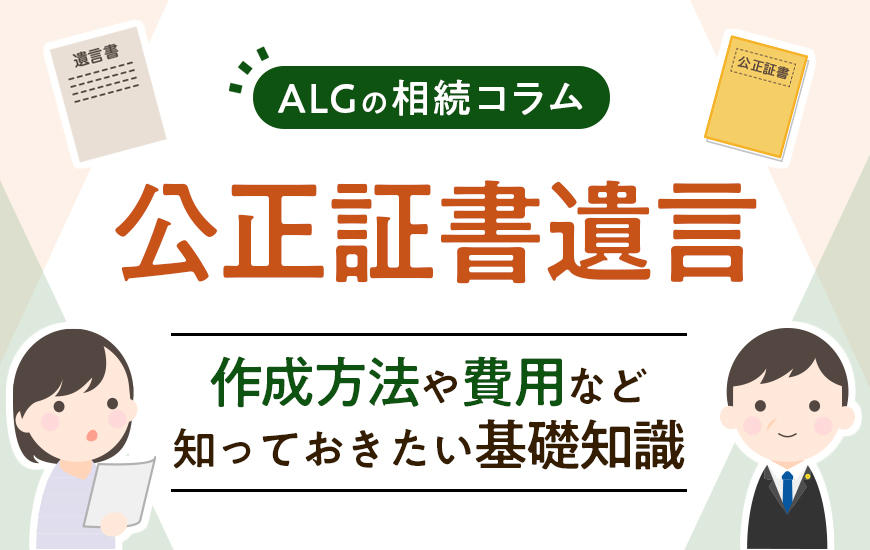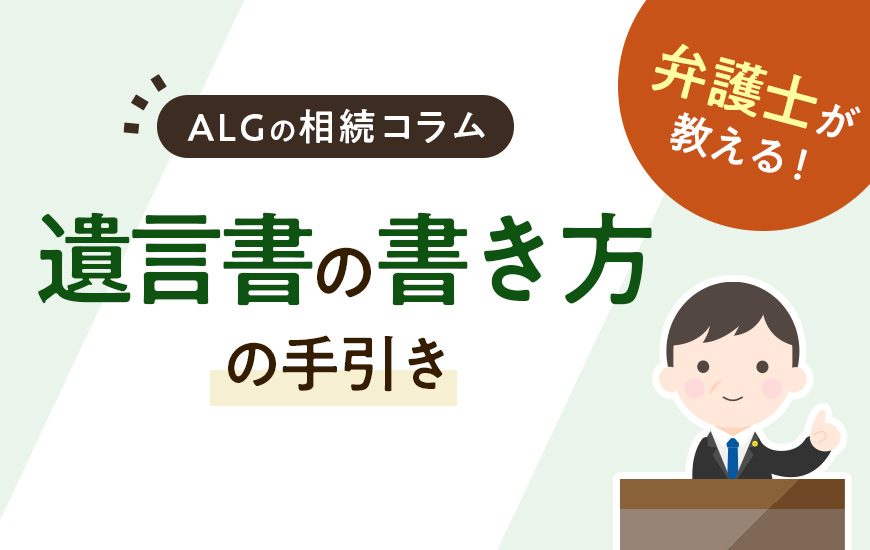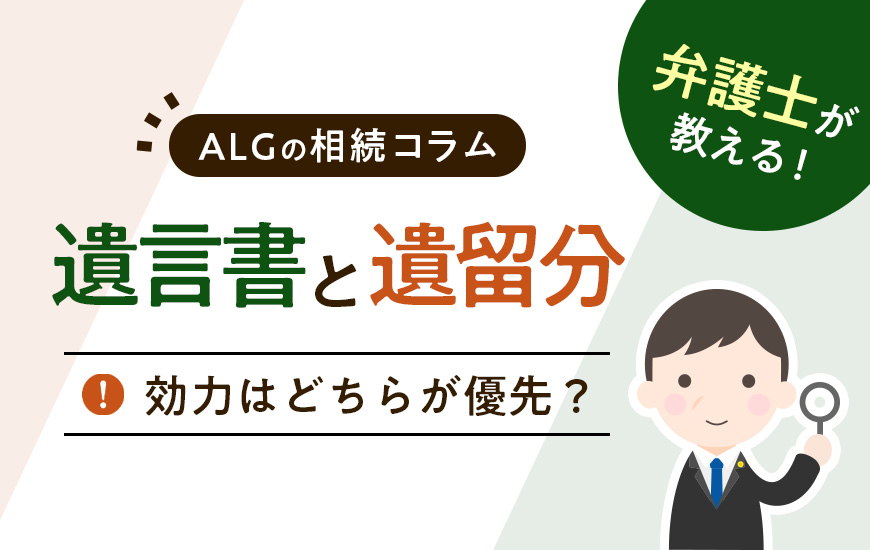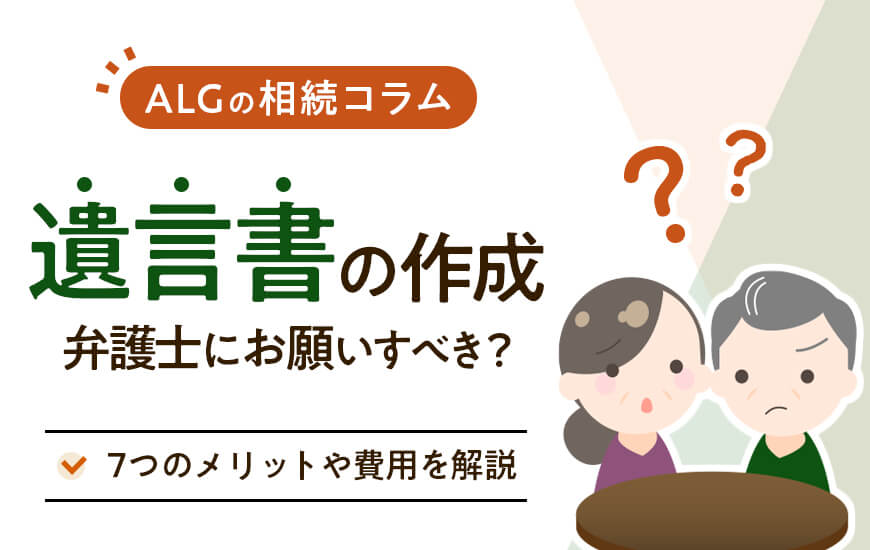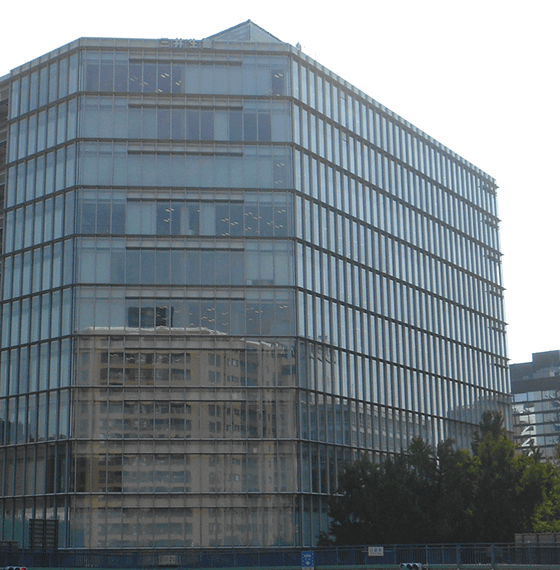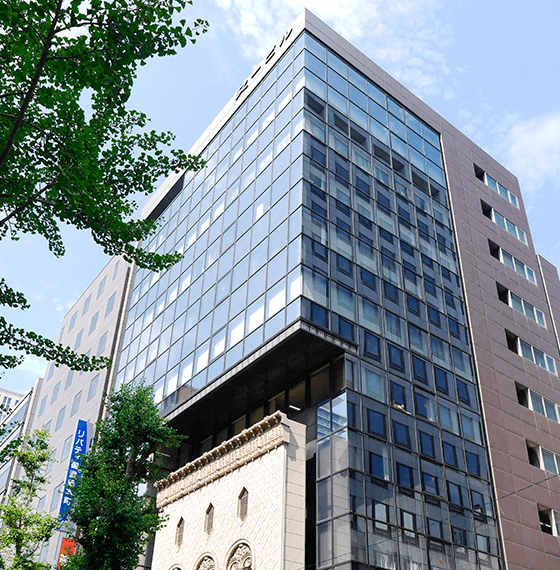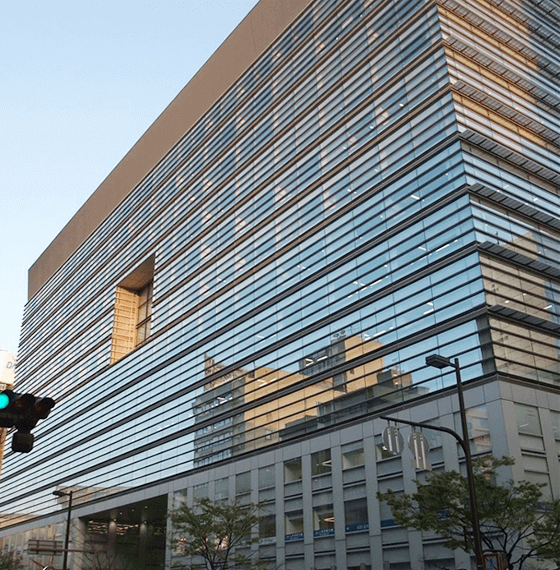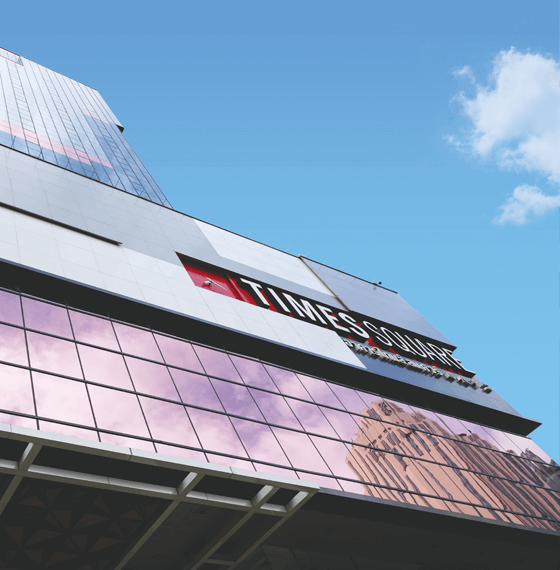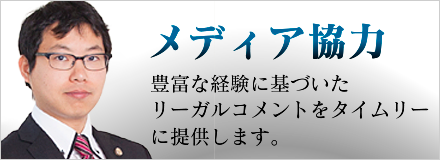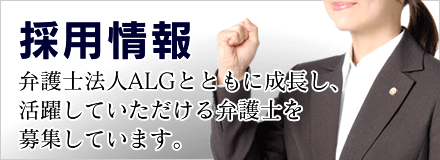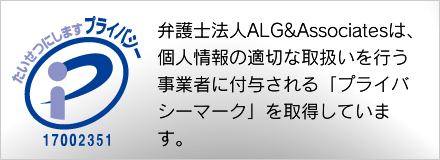遺言書とは?効力や種類、書き方などの基本をわかりやすく解説
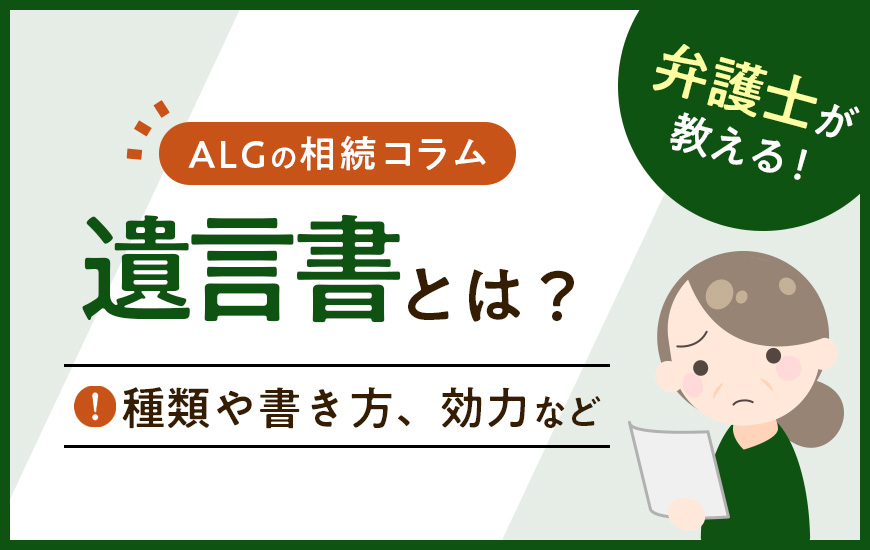
遺言書は、亡くなった方の意思を相続に反映させるための、大切な書類です。
しかし、書き方や手続きを誤ると、せっかく作成した遺言書が無効となり、相続人間でトラブルに発展するリスクがあります。
この記事では、自筆証書、公正証書、秘密証書という3つの遺言書の特徴、無効にならないための正しい書き方や手続きについて解説します。
遺言書を正しく作成することで、相続トラブルを未然に防ぎ、家族の安心を守ることができます。
目次
遺言書とは
遺言書(ゆいごんしょ)とは、自分の死後に財産をどのように分配するかという意思を示す法的書面です。
遺言書を作成しておくことで、家族が自分の財産を巡って争うことを防げます。
遺言書は15歳以上であれば誰でも作成でき、特に法定相続人以外に財産を渡したい場合や、法律で決められた割合とは異なる分け方をしたい場合に有効です。
たとえば、「長年介護してくれた友人に100万円を贈る」や「自宅は長男に、預金は妻に相続させる」といった希望を実現できます。
ただし、遺言書は法律で定められた形式に従って作成することで初めて効力を持つものです。
単なるメモや口約束では無効となるためご注意ください。
遺言書の効力
遺言書を作成することで、以下のような効力を発生させることができます。
- 遺言執行者の指定
- 相続分の指定
- 相続人が取得する遺産の内容の指定
- 遺産分割の禁止
- 遺産に問題があった時の処理方法の指定
- 特別受益の持ち戻しの免除
- 生命保険の受取人の変更
- 非嫡出子の認知
- 相続人の廃除
- 未成年後見人の指定
これらの効力は、遺言者が亡くなった時点で発生します。
たとえば、特定の相続人に多くの財産を与えたり、内縁の妻など相続人でない人に遺贈したりすることが可能です。
さらに、遺言執行者の指定や子どもの認知など、将来に備えた重要な決定も遺言書で行えます。
ただし、これらの効力を発揮するには、法律で定められた遺言書の形式を守ることが不可欠です。
形式を満たしていない場合、遺言書は無効になることもあるため、作成時には注意が必要です。
遺言書の効力について詳しく知りたい方は、こちらのリンクをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
① 遺言書が無効になるケース
遺言書が無効になるケースとして、以下のようなものが挙げられます。
- 遺言書としての形式を満たしていない場合
自筆証書遺言や秘密証書遺言については遺言者が自分で作成する為、日付や署名押印の漏れといった不備によって無効になるケースがあります。公正証書遺言については専門家である公証人が作成するので不備による無効は少ないです。 - 遺言者が遺言書を作成した時の意思能力に問題がある場合
作成時に認知症などを発症し、正確に判断する能力が失われていたと認められると、その遺言書は無効となります。意思能力の有無を確認するには医療記録や当時の動画などが必要なので、専門家に相談することで、より安心して対応できます。
遺言書が無効になるケースについては、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
遺言書の種類
法的効力をもつ遺言書には以下3種類があります。
| ①自筆証言遺言 | 遺言者本人が本文・氏名・日付を自筆します。財産目録についてはパソコンによる作成が可能です。法務局の補完制度を活用することができます。 |
|---|---|
| ②公正証書遺言 | 遺言者が話した内容を公証人が遺言書として作成し、公証役場で遺言書原本を保管します。 |
| ③秘密証書遺言 | 証言者が作成した遺言書を、公証役場で封印し、保管します。内容を公証人が確認しない為、遺言書の形式に不備の可能性があります。 |
どの形式を選ぶかは遺言者の自由です。また、どの遺言書であっても法的効果は同じです。
相続人が探しやすいように、どの遺言書を作成したのかを伝えておくと良いでしょう。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で書き、日付と氏名を記載し、押印することで成立する遺言書です。
パソコンや代筆は認められませんが、2019年の法改正により財産目録のみパソコンで作成できるようになりました。
費用をかけずに手軽に作成できるという良さがある反面、相続人らに発見されない場合がある、正しい形式で作成されておらず無効になるなどのリスクがあります。
自筆証書遺言は通常は自宅で保管し、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
しかし、2020年から法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。
これを利用すれば遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができ、検認も不要です。
自筆証書遺言のメリットとデメリットについて、下の表をご覧ください。
| メリット | ・ほとんど費用をかけずに作成できる ・内容を誰にも知られることなく作成できる |
|---|---|
| デメリット | ・ミスなどにより無効となりやすい ・自筆しなければならないため負担が大きい ・紛失するリスクや改ざんされるリスクがある ・原則検認手続きを行わなければならない |
②公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人により作成してもらう遺言書です。
公証役場で2人以上の証人の立ち合いのもと、遺言者が口頭で内容を伝え、公証人が文章にまとめて作成します。
身体が不自由である等の事情がある場合は、公証人に出張して作成してもらうことも可能です。
手間や費用はかかりますが、法律の専門家である公証人が、法的に正しい内容の遺言書を作成してくれるため、形式不備で無効になることはありません。
また、原本は公証役場に保管されるため、紛失のリスクはなく、検認も不要です。
確実に意思を残したい場合は、公正証書遺言が最も安全な方法といえます。
公正証書遺言について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご一読ください。
合わせて読みたい関連記事
③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう遺言方法です。
パソコンや代筆でも構いませんが、必ず自筆で署名・押印します。
遺言書を封印して押印し、公証役場に持参します。公証人と2人の証人の前で、「自分の遺言書であること、氏名、住所」を述べて、各自が署名・押印することで、遺言書の存在が法的に記録されます。
封印された遺言書は公証役場では保管されず、持ち帰って自分で管理します。
内容を秘密にできるのがメリットですが、手間や費用がかかり、形式不備などの心配も残ります。
検認も必要なため、現在は利用者が少ない方法です。
| メリット | ・パソコン等を使って作成できる ・遺言の内容を他者に知られずに済む ・遺言者が作成したことを証明できる |
|---|---|
| デメリット | ・ミスなどにより無効となるおそれがある ・費用がかかる ・2人の証人が必要である ・検認手続きを行わなければならない |
遺言書の書き方
自筆証書遺言を作成する場合は、次のポイントを押さえる必要があります。
- 全文を自筆で書く:本人が手書きで作成します。財産目録のみパソコン可ですが、各ページに署名・押印が必要です。
- 日付を正確に記載する:令和〇年〇月〇日と特定できる日付を記載します。
- 氏名と押印を忘れない:押印は実印が望ましいですが、認印でも有効です。
- 相続財産を正確に記載する:不動産や預金などは特定できるよう詳細に記載します。
- 訂正は法律のルールに従う:二重線で訂正し、吹き出しで追記、署名・押印を行います。
- 遺留分に注意する:相続人の最低限の取り分を侵害しないよう配慮が必要です。
遺言書は財産や家族構成の変化に応じて見直し、法務局での保管(手数料3,900円)を利用すると紛失や改ざん防止に有効です。
遺言書
1 遺言者は、遺言者名義である次の不動産を、妻 甲野 花子(◯年◯月◯日生)に相続させる。
①建物
所 在 ◯県◯市◯町◯丁目◯番地
家屋番号 ◯◯番◯◯
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造
床面積 1階◯◯平方メートル 2階◯◯平方メートル
②土地
所 在 ◯県◯市◯町◯丁目◯番地
地 番 ◯◯番◯◯
地 目 宅地
地 積 ◯◯平方メートル
2 遺言者は、遺言者名義である次の預金を、長男 甲野 一郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。
○○銀行◯◯支店 口座番号◯◯◯◯
3 遺言者は、遺言者名義である次の株式を、二男 甲野 二郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。
◯◯株式会社 普通株式 ◯◯株
4 遺言者は、遺言者の有する、本遺言に記載のない一切の財産を妻 甲野 花子に相続させる。
5 遺言者は、遺言執行者として、長男 甲野 一郎を指定する。
付言事項
みんなと楽しい生活を送ることができて、私は幸せでした。私がいなくなっても、みんなで仲良く暮らしてください。
これからも安心して暮らせるように、母さんには家を残すことにしました。一郎と二郎は立派な会社に勤めているので、遺した財産には手を付けず、なるべく取っておきなさい。
◯年◯月◯日
住所 東京都◯区◯町◯丁目◯番◯号
遺言者 甲野 太郎 印
遺言書の書き方について詳しく知りたい方は、こちらのリンクをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
遺言書の作成費用
- 自筆証書遺言
基本的に費用はかかりません。紙や封筒などの実費のみで作成できます。ただし、法務局の「遺言書保管制度」を利用する場合は、手数料3,900円が必要です。 - 秘密証書遺言
公証人に支払う手数料は一律11,000円で、さらに、証人への日当も発生します。 - 公正証書遺言
公証人手数料がかかり、相続人ごとの財産額に応じて算出します。たとえば、妻に2,500万円、長女に1,500万円を相続させる場合の手数料は、下表により、2万3000円+2万3000円+1万1000円(1億円以下の加算)= 5万7000円です。加えて、証人への日当や、公証人が自宅や病院に出張する場合は手数料が1.5倍となり、交通費や日当が必要です。
(公正証書遺言の手数料)
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円以上200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円以上500万円以下 | 1万1000円 |
| 500万円以上1000万円以下 | 1万7000円 |
| 1000万円以上3000万円以下 | 2万3000円 |
| 3000万円以上5000万円以下 | 2万9000円 |
| 5000万円以上1億円以下 | 4万3000円 |
| 1億円以上3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
| 3億円以上10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円ごとに1万1000円を加算した額 |
| 10億円以上 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
※財産額が不明な場合は一律1万1000円。
※全体の財産が1億円以下のときは、算出された金額に1万1000円が加算される。
遺言書の検認について
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と状態を確認し、相続人にその内容を知らせる手続きです。
目的は遺言書の偽造や改ざんを防ぐことであり、遺言の有効性を判断するものではありません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言を開封して執行するには、必ず検認を受ける必要があります。
一方、公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言は検認不要です。
検認の流れは以下のとおりです。
- 遺言書を発見したら開封せず保管
勝手に開封すると過料(罰金のようなもの)の対象になります。 - 家庭裁判所へ申立て
家庭裁判所に申立書や戸籍謄本、印紙、切手などを提出します。 - 検認期日に開封・確認
裁判官が相続人立会いのもとで遺言書を開封し、日付や署名、加除訂正の状態を確認します。 - 検認済証明書を取得
遺言書に検認済証明書を付けることで、不動産登記や預金解約などの相続手続きに使用できます。
①検認せずに遺言書を開封してしまったらどうなる?
遺言書を検認する前に開封してしまうと、5万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、開封したことで遺言書が無効になったり、相続人の資格を失ったりすることはありません。
重要なのは、開封してしまっても必ず検認を受ける必要があるという点です。
検認を受けないと、相続手続きが進められません。開封してしまった場合は、速やかに家庭裁判所へ報告し、検認の手続きを進めましょう。
なお、開封した遺言書を隠したり、廃棄したりすることは、相続人としての資格を失うリスクがあるため、絶対に避けてください。
遺言書を作成する際に注意すべき「遺留分」
遺言書を作成する際は、「遺留分」に配慮することが重要です。
遺留分とは、配偶者や子ども、直系尊属といった法定相続人に法律で保障されている、遺産の最低限の取り分を指します。
兄弟姉妹には認められません。
遺言書で財産の分配を自由に決めても、遺留分を奪うことはできません。
もし遺留分が侵害されると、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができ、遺言どおりの相続が実現しない可能性があります。
たとえば、遺言書に「全財産を妻に相続させる」と記載しても、子どもたちが遺留分を請求すれば、希望どおりに相続されない可能性があります。
そのため、遺言書を作成する際は、相続人ごとの遺留分を確認し、これを侵害しない内容にすることが、相続トラブルを防ぐうえで不可欠です。
遺言書と遺留分の効力について詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット
遺言書について弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
- 有効な遺言書を作成できる
遺言書は形式の不備や曖昧な表現な文言を用いたことによって無効になるおそれがあります。弁護士に依頼すれば、こうしたミスを防ぎ、適切な作成方法をサポートしてもらえます。 - トラブルが発生した場合にも相談できる
遺言書の内容に納得できない者などが有効性を争ってきても、すぐに相談して対応できます。 - 遺言執行者として指名できる
遺言執行者は誰でも指名できますが、手続きの負担や不正を疑われるリスクがあります。弁護士を指定すれば、専門知識で適切に対応してくれるため安心です。 - 手間を削減できる
登記簿など必要書類の収集、公証役場との調整、証人の手配などを弁護士に任せられます。
弁護士に遺言書作成を依頼する費用の相場は、遺言内容の複雑さや遺産額によりますが、10万円〜50万円程度が目安です。
遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
遺言書に関するよくある質問
①遺言書が2通以上出てきた場合はどちらが有効になりますか?
遺言書が2つ以上あるケースは実は珍しくありません。なぜなら遺言書は何度でも作成しなおすことができるからです。 基本的には作成日が最も新しいものが有効な遺言書となります。
しかし、それぞれの遺言書の内容が、同一の財産について書かれているとは限りません。例えば古い遺言書に「Aの土地は相続人Bに」、と記載され、新しい遺言書に「Cの土地は相続人Dに」と記載されていた場合、この2つの遺言は違う財産についての指定であり、内容が重複しないので、どちらも有効な遺言内容となります。
②遺言書にない財産が後から出てきた場合はどうなりますか?
遺言書に記載されていない財産は、その財産の分割方法が指定されていないので、相続人全員による遺産分割協議によって決めることになります。
ただし、遺言書の内容が個別の財産ごとに分割方法を指定する形式(例えば、「不動産Eは相続人Fへ」などの内容)ではなく、包括的な割合の指定(例えば、「遺産の2分の1を相続人Gへ」などの内容)であれば、遺言書に記載されていない財産であっても、この遺言書に指定された割合によって相続することになります。
また、遺言書に含まれない遺産が生じないように、遺言書には「その他、本遺言書に記載のない遺産は、全て相続人Aに相続させる」等と、記載しておくのが良いでしょう。
③遺産分割協議後に遺言書が出てきた場合はどうなりますか?
遺言書の形式が有効なものであれば、遺産分割協議が終わっていたとしても遺言書の内容が優先されます。
「せっかくみんなで協議したので見なかったことに・・・」と思うかもしれませんが、遺言書が無いことを前提とした遺産分割協議は、原則無効となります。
もちろん遺言書が見つかった後も、相続人全員の協議により、以前の合意と同じ内容で分割することに合意ができれば有効となります。
ただし、遺言書には法定相続人以外の者(受遺者)に遺贈させることが書かれていることもあります。この場合には、受遺者を含めて改めて協議をすることが必要になります。
④遺言書に有効期限はありますか?
遺言書に有効期限はありません。一度有効に作成された遺言書は、時間の経過や特定の出来事によって効力を失うことはないためご安心ください。
なお、公正証書遺言を作成した場合、その原本は公証役場で長期間保管されます。法律上は原則20年とされていますが、遺言書は「特別の事由」に当たるため、実際には140~170年程度保管されるのが通例です。
そのため、保管期間切れで効力を失う心配はほとんどありません。ただし、遺言書自体に有効期限はないものの、長期間が経過すると、相続人や財産の状況が変わる可能性があるため、定期的に内容を見直し、必要に応じて書き換えることが重要です。
遺言書でトラブルとならないためにも弁護士にご相談ください
遺言書は被相続人の意思を相続人に伝え、その意思を反映させた相続を実現するのにとても有用な制度です。
しかし、その作成に不備が生じやすいだけでなく、保管場所が分かりにくく見つけられなくなるなど、運用のつまずきによって無用のトラブルを発生させてしまうこともあり得ます。
遺言書について不安があれば専門家である弁護士が適任です。
弁護士は遺言書を作成するだけでなく、遺言執行者となることもできます。
そして、遺言書を発見したあとも、弁護士であれば必要な手続きや、分割についてなど広くアドバイスすることができます。
被相続人の意思を尊重し正しく受け継ぐためにも、まずは弁護士へご相談ください。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)