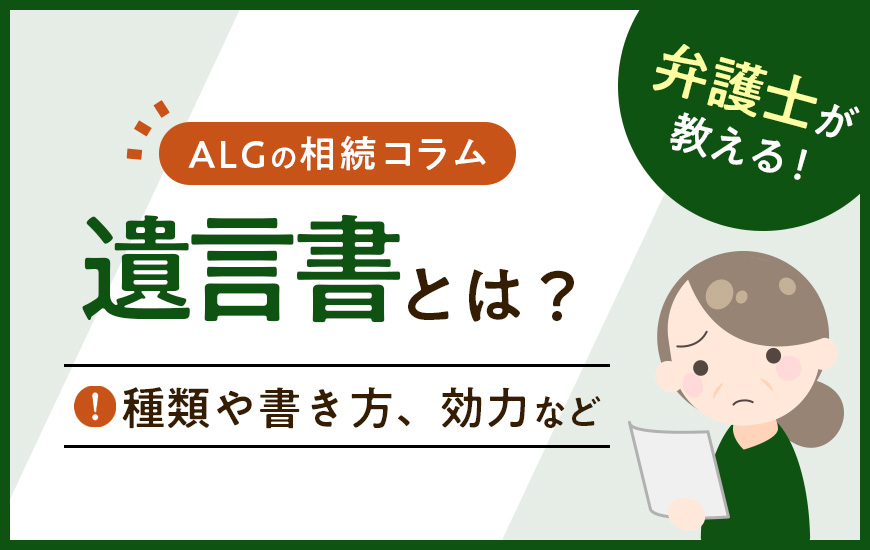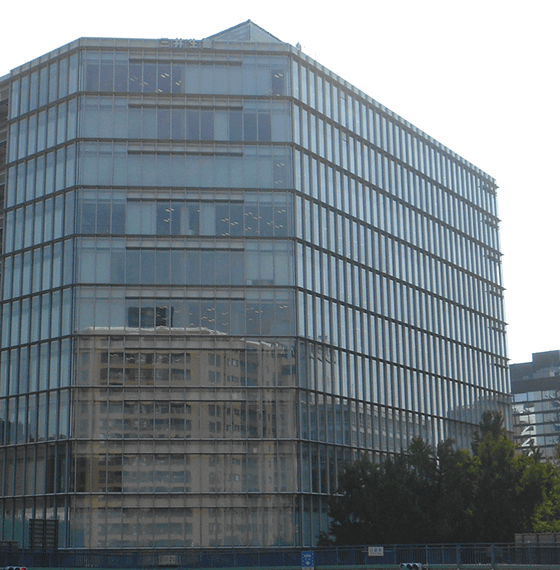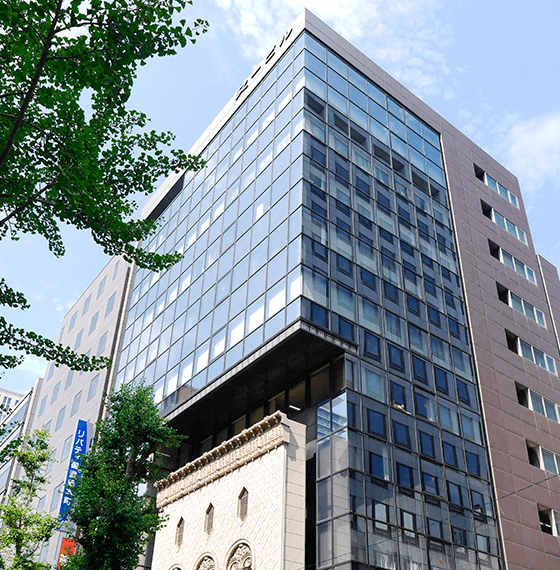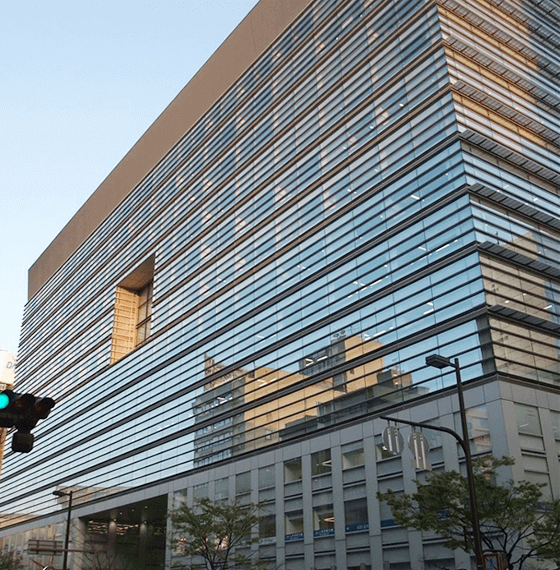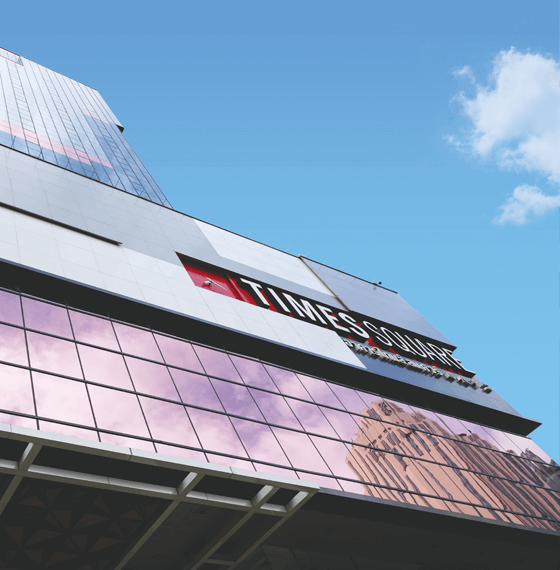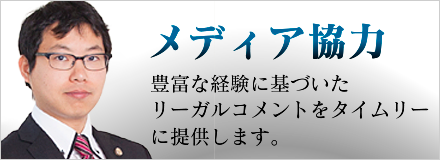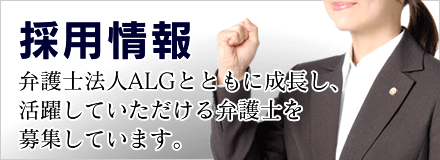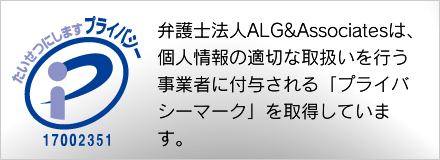遺言書を偽造されたらどうなる?対処法から予防策まで弁護士が解説
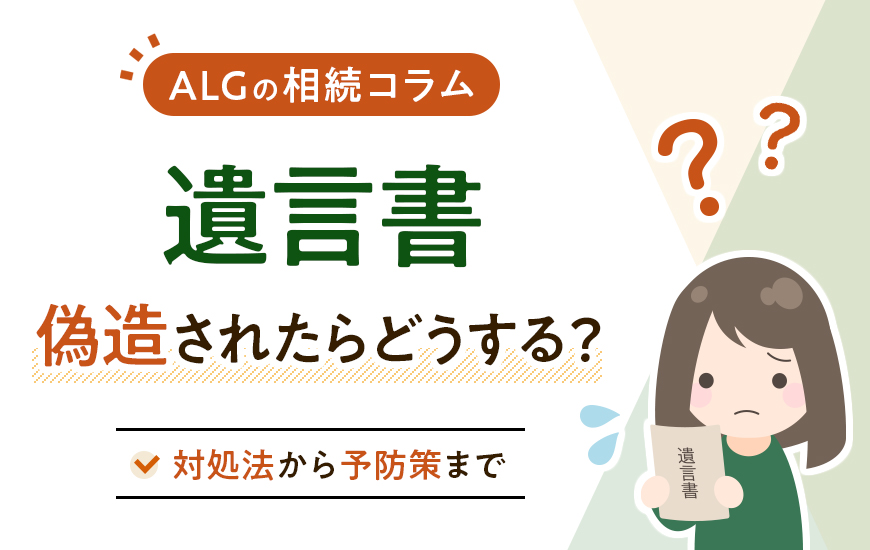
この記事でわかること
遺言書は、誰にも知られずに作成することが可能です。そのために、偽造されてしまうリスクがあります。
偽造された遺言書によって相続財産を分配されてしまうと、被相続人の考えが捻じ曲げられてしまい、相続人にとっては不公平な結果となります。
この記事では、遺言書を偽造すると受けるペナルティや、偽造が疑われる場合の対処法、偽造を防ぐための予防策、偽造についての裁判例等について解説します。
目次
遺言書の偽造とは?
遺言書の偽造とは、被相続人ではない者が、その名前を騙って遺言書を作成する行為のことです。
相続人である者が、自身に全財産を相続させる旨の遺言書を偽造するケース等があります。
自筆証書遺言が偽造されやすい理由
遺言書が偽造されやすいのは、自筆証書遺言であれば誰にも知られずに作成できるからです。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式があります。
自筆証書遺言とは、財産目録を除く全文を遺言者が自筆して作成する遺言書です。
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書です。
また、秘密証書遺言とは、遺言書の存在を公証人と証人に証明してもらう遺言書です。
どちらも、他者が関わっているため、偽造するのが難しくなっています。
自筆証書遺言は、他者が関わらずに作成されるため、知らないうちに偽造されているリスクが比較的高いです。
遺言書の3つの方式について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
偽造・破棄・変造の違い
遺言書に関する不正行為として、偽造だけでなく、「破棄」「変造」があります。
破棄は、遺言書を捨てる行為や燃やす行為等、遺言書をなかったことにしてしまう行為です。
変造は、被相続人が作成した遺言書に手を加えて、その内容を変えてしまう行為です。
遺言書の偽造の見分け方
遺言書の偽造を疑う必要のあるケースとして、主に以下のようなものが挙げられます。
- 遺言書の全文や訂正箇所が、明らかに他人の筆跡で書かれている
- 遺言書の作成年月日が、認知症等の影響が強くなってきた時期よりも後の日付となっている
- 被相続人の手に力が入らなくなっていたのに、綺麗な文字で長文が書かれている
- 被相続人と疎遠な親族が遺言書を発見し、発見者にとって都合の良い内容になっている
- 遺言書に書かれている文章の形式や言葉遣いが、被相続人のものとは異なる
- 遺言書が、生前に嫌っていた者に全財産を渡す等、明らかに不自然な内容になっている
遺言書を偽造したらどうなる?
遺言書を偽造すると、民事と刑事で、それぞれ重い責任を負うことになります。
遺言書の偽造によるペナルティについて、次項より解説します。
相続欠格者になる
民法891条5号により、遺言書を偽造した者などは相続欠格となるため、相続人となることができません。
相続欠格は、定められた言動をした者に対して自動的に適用されるので、他の相続人等が特別な手続きを行わなくても相続権は失われます。
ただし、相続欠格になった事実は戸籍等に記載されないので、遺産分割協議に相続人の全員が参加したことを証明する書類が必要となります。
そのため、相続欠格証明書を作成し、相続登記などの手続きでは添付する必要があります。
なお、相続権を失った者に子がいると、その子が代わりに相続します。このような相続を代襲相続といいます。
刑事罰に問われる
遺言書を偽造すると、刑法159条1項の有印私文書偽造罪が成立するおそれがあります。法定刑は3ヶ月以上5年以下の懲役とされています。
損害賠償を請求される可能性がある
遺言書を偽造して他人に損害を与えると、不法行為に該当すると考えられます。
そのため、偽造した遺言書によって相続人や受遺者が損害を受けた場合には、偽造した者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
遺言書の偽造が疑われる場合の対処法
遺言書の偽造が疑われる場合、主に以下のような対応を行います。
- 家庭裁判所で検認の手続きを行う
- 遺言書の偽造を立証する証拠を集める
- 遺言書無効確認の調停・訴訟を申し立てる
これらの対処法について、次項より解説します。
家庭裁判所で検認の手続きを行う
偽造を疑っていたとしても、遺言書は検認を受けてから開封しなければなりません。
検認とは、遺言書の状態を確認し、内容を明確にして、相続人にその存在と内容を知らせる手続きです。
遺言書を発見したら、速やかに家庭裁判所へ検認を申し立てる必要があります。
検認を受けずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。
検認を受けても遺言書が有効だと判断されるわけではないので、有効性については別途当事者で争います。
遺言書の偽造を立証する証拠を集める
筆跡鑑定
遺言書を被相続人が自分で書いたのかについて判断するときに、筆跡は重要な材料となります。
筆跡には書いた人ごとに特徴が表れるので、被相続人ではない者が作成したことを証明するために役立ちます。
ただし、筆跡鑑定だけで偽造を証明するのは難しいので、被相続人と遺言書で利益を受ける者の関係や、遺言書の作成日の前後における被相続人の様子等を考慮して判断されることになります。
認知症の証明
遺言書の作成年月日の当時、被相続人が重度の認知症であったことを証明できれば、自分から遺言書を作成する可能性が低かったと説明できます。
認知症であったことを証明するためには、長谷川式認知症スケールの点数や、診療録に記載されている被相続人の言動等を確認する方法があります。
なお、被相続人に意思能力がなかった場合には、本人が作成した遺言書であっても無効になる可能性があります。
遺言書無効確認の調停・訴訟を申し立てる
遺言書の偽造について争う場合、まずは当事者で遺産分割協議を行いますが、まとまらなければ家庭裁判所へ遺言無効確認調停を申し立てます。
調停が不調に終わった場合、遺言無効確認訴訟を提起します。
訴訟で遺言書が偽造だと認められれば無効となるため、遺言書に基づいて分配されていた相続財産について、改めて遺産分割協議により分配することになります。
協議がまとまらなければ遺産分割調停を申し立て、調停がまとまらなければ自動的に遺産分割審判へ移行します。
遺言書の偽造を防ぐための予防策
公正証書遺言で作成する
自筆証書遺言は偽造を疑われるリスクがあり、破棄されるリスクや変造されるリスク、誤って紛失してしまうリスク等もあるので、公正証書遺言を作成しましょう。
公正証書遺言とは、2人以上の証人が立ち会って、公証人によって作成される遺言書です。
原本は公証役場において保管されるため、偽造や破棄、変造、紛失等のリスクはほとんどありません。
ただし、公正証書遺言の効果を失わせるような自筆証書遺言を作成することも可能なので、絶対に安全なわけではありません。
また、相続財産の内容は数年経てば変わることが多いため、古い遺言書をそのままにしておくとトラブルを招くおそれがあります。
公正証書遺言を作成するために費用はかかりますが、定期的に作り直すことをおすすめします。
自筆証書遺言書保管制度を活用する
自筆証書遺言を作成する場合には、自筆証書遺言書保管制度を活用する方法もあります。
自筆証書遺言書保管制度とは、2020年7月10日に開始された制度であり、法務局に自筆証書遺言を預けることができます。
この制度を利用できるのは遺言書を作成した本人だけです。そのため、偽造でないことを証明できるだけでなく、破棄や変造、紛失のリスク等もほとんどなくなります。
また、遺言書に形式的なミスがないことも確認してもらえます。
ただし、遺言書が有効だと保証してもらうことはできません。
あいまいな表現をすると相続争いを引き起こしてしまうリスクがあるため、記載する内容には注意しましょう。
遺言書の偽造についての裁判例
遺言書が偽造されたとして争われた裁判例について、以下で解説します。
【事件番号 令2(ワ)28622号、東京地方裁判所 令和5年4月19日判決】
本件は、被相続人の長男である被告が自筆証書遺言である遺言書を偽造したとして、被相続人の二男である原告が遺言書の無効等の確認を請求した事案です。
遺言書は、400字詰め原稿用紙5枚に手書きされており、末尾に被相続人名義の署名押印がありました。この遺言書について、筆跡等から、署名を含めた全文を同一人が記載したと裁判所は認めました。
そこで、遺言書の署名と被相続人のものである署名を比較すると、明確に識別できるほどの相違があることから、偶発的に生じた相違ではなく、別人が記載したと考えるのが自然かつ合理的だと指摘しました。
そのため、本件の遺言書は被相続人の自署により作成されたものとは認められないので、遺言書の無効確認の請求を認容しました。
もっとも、本件の遺言書は、被相続人が知人等の第三者に協力を求めて代筆してもらった可能性があり、被告が偽造したとは認められないので、被告が遺言書の偽造による相続欠格であることは認めませんでした。
遺言書の偽造が疑われたら相続問題に強い弁護士にご相談ください
遺言書が偽造されてしまうと、相続分が不当に減らされてしまう等、大きな損害を受けるおそれがあります。
被相続人の生前の言動から、偽造だと確信できたとしても、証明できなければ遺言書に従った相続が行われてしまいます。
遺言書が偽造されたものである疑いが生じた場合には、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、遺言書が偽造されたことや、本物であることを証明するためのサポートを行うことができます。
また、遺言書を作成する場合には、自身の死後に偽造だと疑われてしまうと、自分の意思が相続に反映されなくなるおそれがあります。
遺言書の偽造を疑われないようにしたい場合にも、弁護士にご相談ください。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)