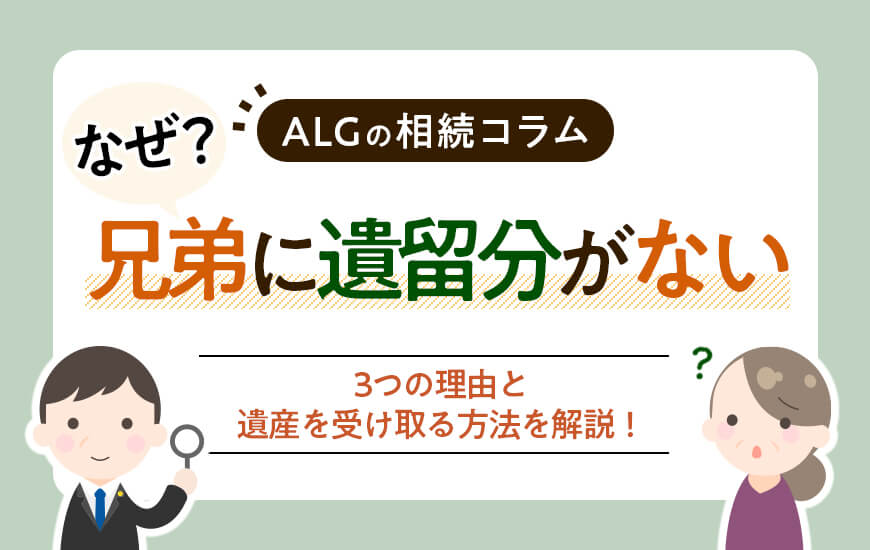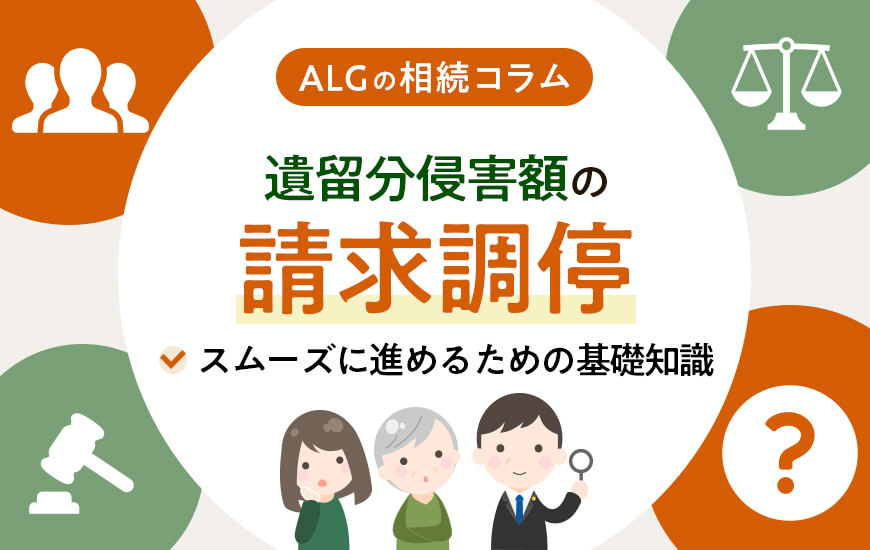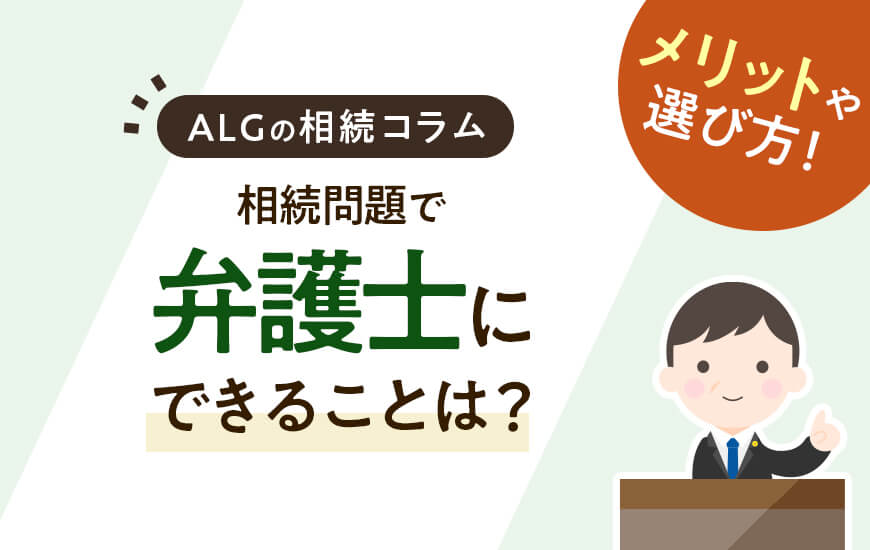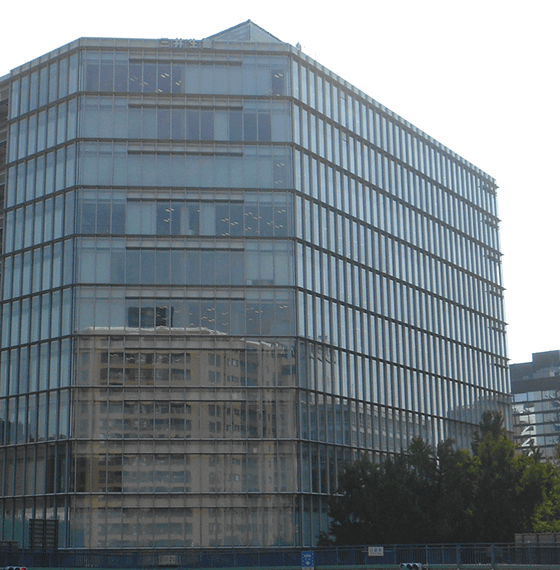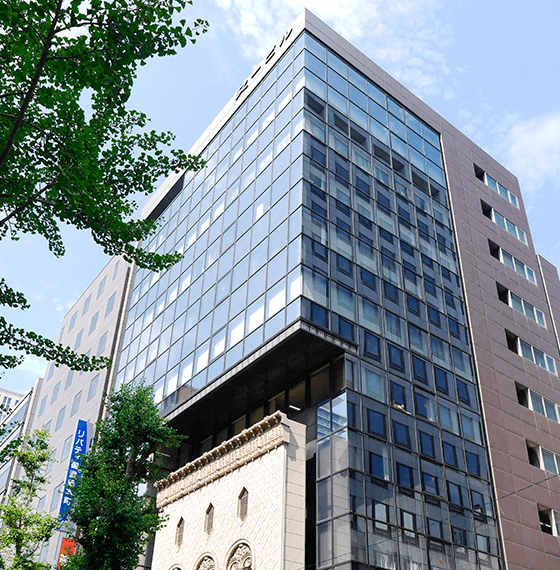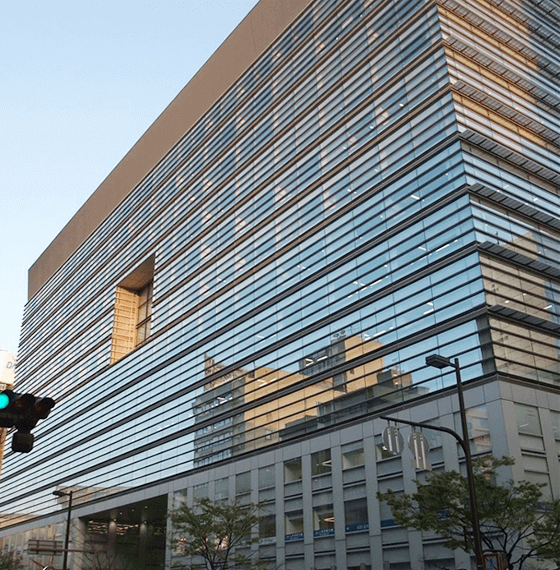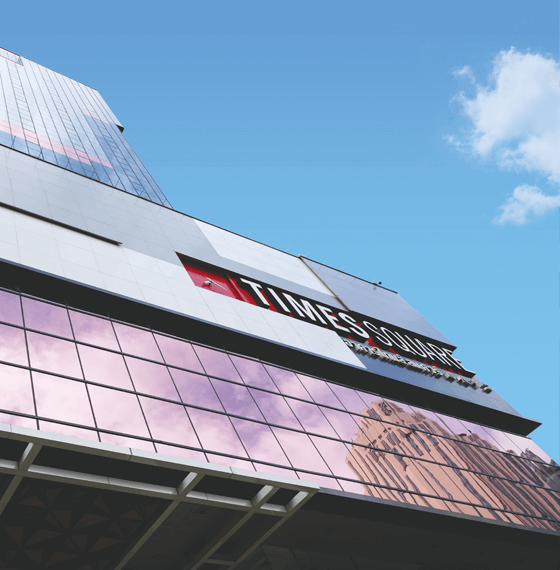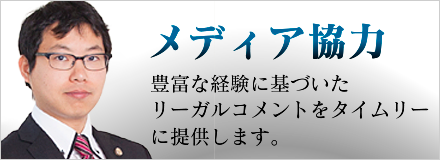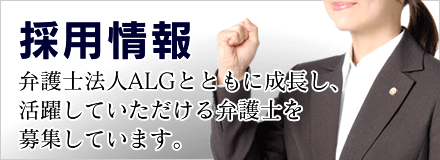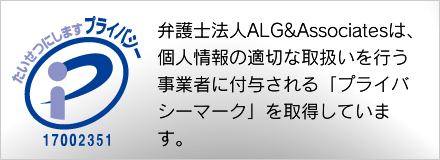遺言書の遺留分はどうなる?どちらが優先?対処法などを解説
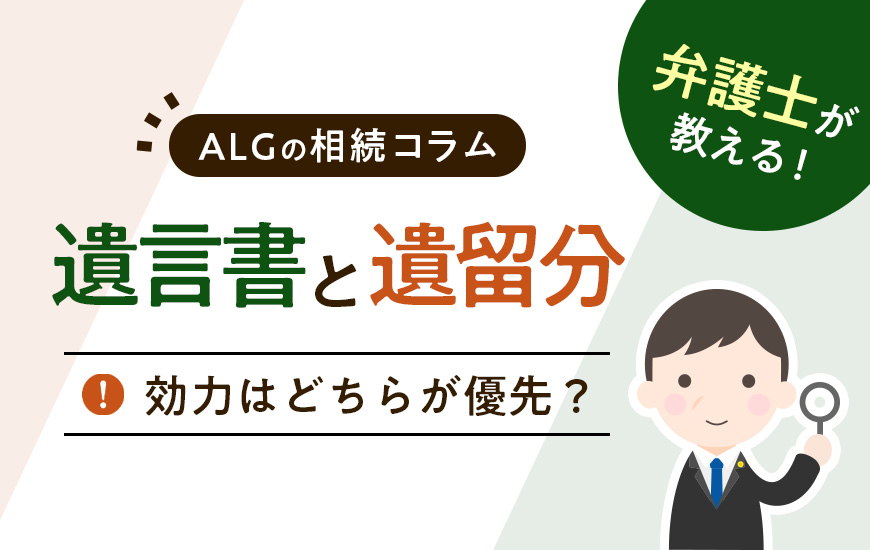
遺言書は、財産を自由に分けられる便利な手段と思われがちですが、注意が必要です。
民法には遺留分という制度があり、配偶者や子供などの相続人には、最低限の取り分が保障されています。
たとえ遺言書に「全財産を特定の者に渡す」と記載しても、遺留分を持つ相続人はその権利を主張できます。
遺留分を無視した遺言は、相続トラブルの原因になります。
遺言書を作成する際は遺留分の仕組みを理解し、適切な対策を取ることが大切です。
この記事では、遺言書と遺留分の関係や、遺言書作成時にすべき遺留分対策などについて解説します。
遺言書がある場合でも遺留分を請求できるのか?
遺言書があっても、遺留分を請求することができます。
遺留分とは、配偶者や子供、親など一定の法定相続人に保障された、遺産の最低限の取り分です。
兄弟姉妹には認められていません。
これは法律で認められており、遺言によっても取り上げることはできません。
遺留分の割合は、以下のとおりです。
| 相続人の組み合わせ | 遺留分 | 各人の遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 配偶者:1/4子:1/4 |
| 配偶者と父母・祖父母 | 1/2 | 配偶者:2/6父母・祖父母:1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者:1/2兄弟姉妹:なし |
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者:1/2 |
| 子のみ | 1/2 | 子:1/2 |
| 親のみ | 1/3 | 父母:1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | なし | なし |
例えば、被相続人に配偶者と子供が1人いて、遺産が1000万円なら、配偶者と子はそれぞれ250万円の遺留分を有します。
遺留分を侵害する例として、遺言で全財産を友人に遺贈する場合や、複数の子がいるのに長男だけに全財産を相続させる場合などがあげられます。
遺留分を侵害された相続人は、遺産をもらいすぎた人に対して、侵害された分に相当するお金を請求できます。
これを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分を請求できないケース
被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、基本的に遺留分侵害額請求はできません。
遺留分が認められない理由として、以下があげられます。
- 兄弟姉妹は被相続人と血縁関係が遠く、相続順位も低い。
- 兄弟姉妹は通常独立して生活しており、生活保障の必要性が低い。
- 兄弟姉妹には代襲相続が認められており、遺留分を認めると甥や姪にまで権利が広がり、相続関係が複雑になる。
なお、兄弟姉妹の子供である姪や甥にも、遺留分は認められていません。
兄弟姉妹や甥・姪に確実に財産を渡したい場合は、遺言書の作成や生前贈与など事前の対策が必要です。
兄弟姉妹に遺留分がない理由について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
遺言書と遺留分のどちらの効力が優先される?
遺言書と遺留分の効力の優先順位については、遺留分が優先されます。
被相続人がどれほど自由に遺言を作成できるといっても、この遺留分を完全に奪うことはできません。
ただし、注意すべきなのは、遺留分を侵害する遺言書が無効になるわけではないという点です。
遺言書そのものは有効であるため、遺留分権利者が遺留分を請求しなければ、基本的には遺言書の内容に従って遺産が分配されます。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
遺言書が遺留分を侵害している場合の対処法
遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は侵害した相手に対して「遺留分侵害額請求」を行い、侵害された分に相当するお金を請求できます。
たとえば、遺産が5000万円で相続人が長男と次男の2人、遺言で「全財産を長男に」と指定されても、次男は長男に、1250万円を請求することが可能です。
かつては「遺留分減殺請求権」といい、相続財産そのものしか取り戻すことができませんでした。
しかし、2019年の民法改正によって「遺留分侵害額請求権」に変わり、遺留分の請求は金銭の請求に限定されました。
ただし、相手の同意があれば現物での返還も可能です。
遺留分侵害額請求は計算や証拠収集が複雑で、請求期限もあるため、弁護士などの専門家への相談をおすすめします。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分権利者が遺留分侵害額請求を行うためには、主に以下のように手続きを進めます。
- 相続人と財産を調査する
- 遺留分を侵害した相手と協議する
- 内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行う
上記のような手続きによっても、侵害された遺留分に相当する金銭等の支払いに応じてもらえない場合には、裁判所に調停を申し立てるのが一般的です。
調停での話し合いにも応じてもらえない場合には、裁判によって請求します。
遺留分侵害額の請求調停について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求は、時効や除斥期間が成立すると、請求しても退けられるおそれがあります。
請求期限は次のとおりです。
- 相続の開始と、遺留分を侵害する遺贈等があったことを知ってから1年以内(時効期間)
- 相続の開始から10年以内(除斥期間)
また、遺留分侵害額請求の意思表示を行った後は、具体的な金銭を請求する権利となりますが、この請求権には、次の期限があります。
- 債権を行使できることを知ってから5年以内
- 債権を行使できるときから10年以内
遺言書を作成する際は遺留分への配慮が必要
遺言書の内容が遺留分を侵害していたとしても、形式に問題がなければ遺言書そのものは有効です。
たとえ「配偶者や子供に一切財産を残さない」という極端な内容であっても、遺言書の効力は失われません。
ただし、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」という強力な権利があります。
この請求が行われると、遺言どおりの財産分配はできず、請求を受けた側は金銭を支払う義務を負います。
その結果、相続トラブルや裁判に発展するリスクが高まります。 こうした事態を防ぐためには、遺言書を作成する段階で遺留分に配慮することが大切です。
法定相続分や遺留分を正確に把握し、侵害しない範囲で配分を工夫しましょう。
遺留分を請求された場合はどうする?
遺留分侵害額請求が正当な場合、基本的に支払いを免れることはできず、金銭の支払いで解決する必要があります。
しかし、相続財産の大半が不動産で、現金や預貯金が手元にないケースも少なくありません。
その場合は、相手に分割払いを提案する、不動産の売却が完了するまで支払いを待ってもらうよう交渉するといった方法が考えられます。
また、裁判所に期限の許与を認めてもらうことができれば、支払いの全部または一部を猶予してもらうことも可能です。
ただし、これらの対応には法的知識が不可欠であり、交渉に失敗すると調停や訴訟に発展するリスクがあります。
遺留分請求を受けた場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
遺言書作成時にすべき4つの遺留分対策
遺言の内容が遺留分を侵害していると、遺された相続人同士で遺留分トラブルに発展するリスクがあります。
そのため、遺言書を作成するときは、遺留分を考慮したうえで作成することが必要です。
遺言書作成時に行うべき遺留分対策として、以下があげられます。
- 遺言書の付言に想いを記載する
- 遺留分となる金額を減らす
- 生前に遺留分放棄してもらう
- 弁護士などを遺言執行者に選任する
(1)遺言書の付言に想いを記載する
付言事項とは、被相続人が遺言書を作成した経緯や、生前の自分の気持ち等を相続人等に伝えるための文言です。
本文には財産の分配方法等を記載しますが、付言事項には「想い」について書き残すことができます。
遺言者の想いを伝えることができれば、相続人間のトラブルを避けられる可能性があります。
ただし、付言事項に法的効力はないため、あくまでも「お願いする」ことになります。
付言事項には、以下のような文言を記載すると良いでしょう。
私の妻Aが今後も不安なく暮らせるように、私たちが住んでいる家と、十分な預金を妻Aに遺すことにしました。長男Bの取り分が遺留分よりも少なくなってしまいましたが、私の考えを尊重して、請求はしないようにお願いします。
(2)遺留分となる金額を減らす
法定相続人の遺留分を減らせば、遺留分侵害額請求の金額が少なくなるので、相続人が自費で支払える可能性が高まります。
遺留分を減らす方法として、以下のようなものが考えられます。
- 生きているうちに財産を使って減らしておく
- 自分が亡くなる10年以上前に生前贈与を行う
- 相続人にならない人に、亡くなる1年以上前に生前贈与を行う
- 養子をとる等の方法により法定相続人を増やす
- 生命保険に加入して、保険金の受取人を指定しておく
ただし、これらの方法はリスクを伴います。
遺留分を減らすために用いたときに、遺留分権利者から裁判等の手段によって正当性を争われるおそれがあるため注意しましょう。
(3)生前に遺留分放棄してもらう
遺留分は、生前に放棄することのできる権利です。そのため、被相続人が生きているうちに、遺留分権利者になる可能性のある人に遺留分放棄させることができます。
ただし、生前に遺留分を放棄させるためには、家庭裁判所の許可が必要です。そのため、当事者間で念書等を作成しても無効となります。
遺留分放棄の許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 本人の自由な意思によって遺留分放棄すること
- 遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること
- 遺留分放棄に対して、遺留分に相当する金銭などの給付等の見返りがあること
(4)弁護士などを遺言執行者に選任する
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために手続き等を行う人です。
遺言執行者になるための独自の資格はないため、親族等を指名することも可能ですが、専門的な知識がある人を指名するのが望ましいでしょう。
弁護士が関与することによって、遺言書の内容について、遺留分権利者を説得しやすくなる可能性があります。
また、遺留分権利者がどうしても納得しない場合であっても、弁護士であれば代理人として対応できるので、取り分の多い相続人等が直接話をせずに済みます。
相続問題を弁護士に依頼するメリットについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
遺留分を考慮した遺言書の作成や遺留分侵害のトラブルは弁護士にご相談ください
遺言書を作成するときには、相続トラブルを引き起こさないように、遺留分に配慮する必要があります。
しかし、自身の財産の多くが不動産である場合等、遺留分を確保しながら分配するのが難しいケースもあります。
そこで、遺言書による相続トラブルを防止したい方は、弁護士にご相談ください。
弁護士は、相続トラブルを未然に防ぐための助言や手続きをサポートできます。
また、遺言書の書き方が分からない場合等であっても対応できるので、ぜひお気軽にご相談ください。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)