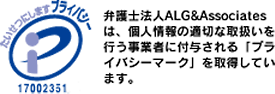接見禁止とは?禁止の理由や期間、解除する方法など弁護士が解説


家族が突然逮捕されると、不安や疑問が一気に押し寄せます。特に裁判所から「接見禁止」が命じられると、弁護人以外との面会や手紙のやり取りができません。
本記事では、接見禁止とは何か、その理由や期間、差し入れの可否、解除や一部解除の方法まで、弁護士がわかりやすく解説します。
目次
接見禁止とは
接見禁止とは、刑事訴訟法第81条に規定されている「勾留中の被疑者や被告人が、弁護人以外の人物との面会や手紙のやり取りを禁止する裁判所の処分」を指します。
通常、逮捕されると、警察から取り調べを受けた後に検察に身柄と事件の資料等が引き継がれ、逮捕から72時間以内に勾留するかどうかの判断が下されます。
検察官が、「被疑者の身柄を引き続き拘束した方が良い」と判断した場合、裁判所に対して勾留請求がなされます。
この間=逮捕から72時間(3日間)は、弁護人以外の人物(家族や知人)との面会は禁じられるのが基本です。
一般人の面会が許されるのは、勾留確定後となりますが、この段階で裁判所が接見禁止処分を下す場合があります。
接見禁止になぜなるのか?
接見禁止になるのは、主に捜査に支障をきたす事情があるからです。
具体的には、以下のような事情が挙げられます。
- 逃亡するおそれがある
- 容疑を否認している
- 共犯者の存在・組織犯罪が疑われる
このような事情が認められると、裁判所は被疑者または被告人が弁護人以外の人物とやり取りするのは危険だと判断し、接見禁止処分を下します。
逃亡するおそれがある
住居不定や無職、独身といった属性を持つ者は、刑事事件の手続きにおいて、「逃亡するおそれがある」と判断されやすいです。
住居不定は、どこに住んでいるのかが分からず、逃亡のリスクが高いと判断されます。無職は、社会的なつながりが弱いとみなされ、独身は監督者がいない=誰も見張る人がいないため、逃亡する可能性が高いと判断されやすいです。
逃亡のおそれがある中で、弁護人以外の人物とのやり取りを認めると、そのリスクを高める可能性があると考えられます。
そのため、裁判所は、接見禁止処分を命じて、リスクを回避するのです。
容疑を否認している
容疑を否認している場合は、自身にとって不利な証拠を隠滅したり、家族や知人の証言を変えさせたりする可能性があると判断されます。
そのような中で、一般人とのやり取りを認めると、「家族や知人に連絡を取って証拠の隠滅を依頼する」「口裏を合わせる」などの可能性が高まります。
したがって、接見禁止により、外部との連絡を遮断して証拠や供述が変わらないようにする必要があると裁判所は判断します。
つまり、被疑者や被告人が外部と連絡を取ることで、捜査が妨害されるリスクが高いと裁判所が判断した場合に、接見禁止となりやすいです。
共犯者の存在・組織犯罪が疑われる
共犯者の存在や組織犯罪が疑われる場合は、共犯者との連絡を防ぐ必要があると判断されます。
被疑者や被告人が共犯者と連絡を取れば、「逃亡を手助けする」「供述を一致させる」「証拠を隠す」などの行為がなされる危険があると考えられるからです。
面会者が家族や親しい知人であっても、共犯者に通じていないとは言い切れないため、弁護人以外の人物との面会が禁じられます。
特に、詐欺事件や薬物事件、暴力団事件などの場合は、共犯者の存在や組織犯罪が疑われやすく、裁判所から接見禁止処分を命じられる可能性が高いです。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
接見禁止の期間はいつからいつまで?
接見禁止の期間は勾留された日から原則勾留の満了日(または取消)までとするのが一般的です。
法律上、明確な期間の定めはなく、捜査状況や検察官、裁判官の判断で接見禁止の対象期間が決まります。
接見禁止が命じられるタイミングは、捜査がまだ初期段階である起訴前勾留(被疑者の段階)のときが一般的ですが、起訴後勾留の際になされる場合もあります。
接見禁止処分の通知はなされないため、家族に知らされないことがほとんどです。
弁護士が介入している場合は、弁護士を通じて知れますが、介入していない場合には、捜査機関に直接確認する必要があります。
なお、接見禁止が終了するのは、以下の場合です。
- 勾留満了
- 勾留取消
- 接見禁止の一部・全部解除
- 保釈(起訴後
裁判所が、主に「被疑者や被告人が外部と連絡を取っても、捜査の妨害にはならない」と判断した場合に上記が認められます。
逮捕後72時間以内は接見できない
逮捕後72時間以内は接見できないことが原則とされています。
検察官が被疑者を勾留するかどうかを決めるまでは、接見禁止処分に関係なく、弁護士以外の人物とのやり取りが禁じられています。
接見禁止処分は、証拠隠滅や共犯者との口裏合わせなどを防ぐために設けられている処分です。
そのため、勾留の決定後に接見禁止が必要かどうかを慎重に判断しなければなりません。
勾留が決まっていない段階では、そもそも証拠隠滅のおそれなどが具体的にどれだけあるのかが不明であり、接見禁止処分を命じるには根拠が乏しいとされています。
接見禁止を解除する方法
接見禁止を解除するには、以下の方法を取る必要があります。
- 準抗告・抗告
- 接見禁止処分の一部解除申し立て
- 勾留理由開示請求
上記の手続きを行い、裁判所がこれを認めると、弁護人以外の人物との面会や手紙のやり取りを許可してもらえます。
以下で、各方法を詳しく解説していきます。
接見禁止を命じられている方は、ぜひご参考になさってください。
準抗告・抗告
準抗告および抗告は、いずれも刑事手続において裁判官または裁判所が行った決定に対して不服を申し立てる手続です。
両者の主な違いは、決定を行った主体と手続の段階にあります。
<準抗告と抗告の違い>
- 準抗告
裁判官が行った決定に対する不服申立て(刑事訴訟法第429条)。
主に起訴前の段階で行われます。- 抗告
裁判所が行った決定に対する不服申立て(刑事訴訟法第419条)。
主に起訴後の段階で行われます。
裁判官・裁判所が申立てを認めると、接見禁止の一部または全部が解除されますが、証拠隠滅や逃亡などのおそれがないことを適切に主張・立証しなければなりません。
接見禁止処分は、そもそも強い理由に基づいて出される決定であるため、刑事事件を得意とする弁護士に依頼されることをおすすめします。
接見禁止処分の一部解除申し立て
接見禁止処分の一部解除申立ては、接見禁止が命じられている被疑者または被告人に対して、特定の人物に限り接見可能とするように、裁判所に求める手続きです。
「特定の人物」には、家族や恋人などが挙げられます。
接見禁止処分の一部解除の申し立ては法律上認められたものではなく、あくまでお願いに過ぎませんが、適切に主張できれば認められる可能性が高いです。
接見禁止処分の一部解除申立ては、以下のような流れで行います。
- 裁判所に申立書を提出する
裁判所に対して、接見禁止一部解除の申立書を提出します。通常、弁護人が代理で行います。
- 裁判官が検察官に意見を求める
申立書が受理されると、裁判官は担当検察官に接見禁止一部解除に対する意見を求めます。
- 検察官が意見書を提出する
検察官は、接見禁止一部解除に対する意見をまとめた意見書を裁判官に提出します。
- 裁判官が判断する
裁判官は、検察官からの意見書を参考にして、接見禁止を一部解除しても問題ないかどうかを判断します。
勾留理由開示請求
勾留理由開示請求は、勾留されている被疑者または被告人が、裁判所に勾留の理由を開示するように求める手続きを指します。
接見禁止を解除できる方法ではありませんが、勾留の理由は公開された法廷にて裁判官から開示されるため、法廷で家族や知人と顔を合わせられます。
もっとも、勾留理由開示請求の目的は、法廷で家族や知人の姿を確認することだけではありません。
裁判所が勾留を認めた理由が適切かどうか(適法かどうか)を確認し、不当な勾留を防ぐためでもあります。
なお、勾留理由開示請求ができるのは、以下の人物に限られます。
- 被疑者、被告人本人
- 被疑者、被告人の弁護人
- 法定代理人
- 保佐人
- 配偶者
- 直系の親族
- 兄弟姉妹
- その他利害関係人
再逮捕された場合は再度接見禁止になる可能性がある
一度接見禁止が解除されても、再逮捕されると再び接見禁止が命じられる可能性があります。
これは、刑事事件が事件ごとに管理される仕組みになっているためです。
再逮捕された容疑について、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことや共犯者がいないことを具体的に示せれば、接見禁止の解除を再度申し立てることが可能です。
ただし、再逮捕された容疑が重大な犯罪である場合や、共犯者の存在が疑われる場合には、再度接見禁止が続く可能性が高いでしょう。
それでも、弁護士が接見禁止の必要性がないことを適切に主張・立証できれば、接見禁止処分の解除が認められるケースもあります。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
接見禁止となった場合に弁護士に依頼するメリット
接見禁止となった場合、弁護士に依頼すると、以下のようなメリットを得られます。
- 逮捕直後から接見ができる
- 時間制限・回数制限なく面会できる
- 警察官の立ち合いなく、事件の内容を話せる
弁護士は、憲法や刑事訴訟法にて、勾留中の被疑者または被告人と自由に接見し、書類や物品の受け渡しができる権利=接見交通権が保障されています。
そのため、弁護士だけは逮捕直後から接見可能です。
逮捕直後から接見ができる
弁護士は、警察に逮捕されてから検察官が勾留請求を決定するまでの間(72時間)でも、被疑者と自由に接見できます。
通常、逮捕直後は、捜査機関の捜査が初期段階であるため、逃亡や証拠隠滅を防ぐために接見を禁じられます。
しかし、弁護士だけは、憲法や刑事訴訟法で被疑者や被告人と自由に接見できる権利(接見交通権)が保障されているため、早期段階から接見が可能です。
刑事事件は、検察官が勾留請求を行うまで僅か72時間しかなく、初動が重要となるため、弁護士の接見次第で刑事処分の判断が大きく変わる可能性があります。
逮捕直後から弁護士と接見できれば、捜査機関からの取り調べに対するアドバイスや弁護方針の構築が可能です。
早ければ早いほど、弁護士が活動できる時間は確保され、活動範囲を拡大できます。
そのため、弁護士への依頼はなるべく早めに行うのが得策です。
時間制限・回数制限なく面会できる
弁護士であれば、被疑者・被告人と時間制限や回数制限なく面会できるため、弁護活動を柔軟に進められます。
通常、一般の方が面会できる時間帯は、勾留先の刑事施設で若干異なるものの、平日の午前9時から午後5時まで(昼休憩を除く)とされています。
また、面会できるのは1日1回までと決まっていて、その他にも、「同時に面会できる人数は3人まで」「時間は15分~30分程度」といった制約があります。
弁護士は、このような制約に縛られないため、必要なときに何度でも面会できます。
これにより、今後どのような弁護活動を行っていくかなどの方針を弁護士と構築することが可能です。
警察官の立ち合いなく、事件の内容を話せる
弁護士の場合は、警察官の立ち合いなしに面会できるため、事件の内容を自由に話せます。
弁護士は守秘義務を負っているため、話した内容を本人の同意なしに他人に漏らされることもありません。
事件の内容について、弁護士とあらかじめ整理しておくことで、捜査機関からの取り調べで誤解や不適切な誘導を防ぐための準備ができます。
弁護士による法的なサポートを受けられれば、自分を守るための正しい選択ができるようになります。
なお、一般面会の場合は、警察官の立ち合いがあるため、その中で不用意に話すと不利な供述として記録されてしまう可能性があります。
接見禁止に関するよくある質問
接見禁止でも差し入れはできる?
接見禁止の決定が出ている中でも差し入れはできますが、制限や禁止とされているものもあるため、注意が必要です。
差し入れ可能・不可には、以下のようなものが挙げられます。
差し入れ可能
- 現金(生活費として)
- 衣類
- 公刊されている書き込みのない新聞、書籍 など
差し入れ不可
- 手紙などの通信手段となるもの
- 食べ物
- たばこ(嗜好品)
- ゲーム(娯楽品) など
なお、差し入れられるか分からないものについては、勾留先の刑事施設に直接問い合わせるのがよいでしょう。
また、弁護士はいつでも接見できるため、弁護士を通じて差し入れを渡すことができます。
接見禁止中に手紙のやり取りはできる?
接見禁止の処分は、被疑者または被告人が外部の人物とやり取りするのを防ぐ措置であるため、手紙のやり取り(郵送・差し入れの文書を含む)は原則できません。
接見禁止には、主に以下のような目的があります。
- 証拠隠滅の防止
- 共犯者との口裏合わせの防止
- 捜査への影響を避けるため
手紙のやり取りが許されてしまえば、接見禁止を命じた意味がなくなってしまいます。
そのため、被疑者または被告人にどうしても伝えたいことがある場合には、弁護士を通じてやり取りする他ありません。
また、「差し入れの中に手紙を入れればバレないのでは?」と思われる方がよくいらっしゃいますが、施設側が中身の確認を行うため、発見されれば受け取れません。
接見禁止命令が出された場合は弁護士法人ALGにご相談ください
勾留されて身柄拘束されるだけでも、社会生活上大きな不利益を受け、精神的、肉体的にも苦痛を受けます。
接見禁止にまでなると、両親、妻、恋人、友人らと留置場内での面会すらできません。
接見禁止となった場合でも弁護士ならば、面会は可能ですので、外部との連絡の橋渡しになることが可能です。
また、接見禁止について、裁判所に不服申立をしたり、接見禁止となっていること自体は受け入れるとしても、両親等、特定の者とは面会を認めるよう、裁判所に申請することもできます。
接見禁止に関して不安がある方は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。