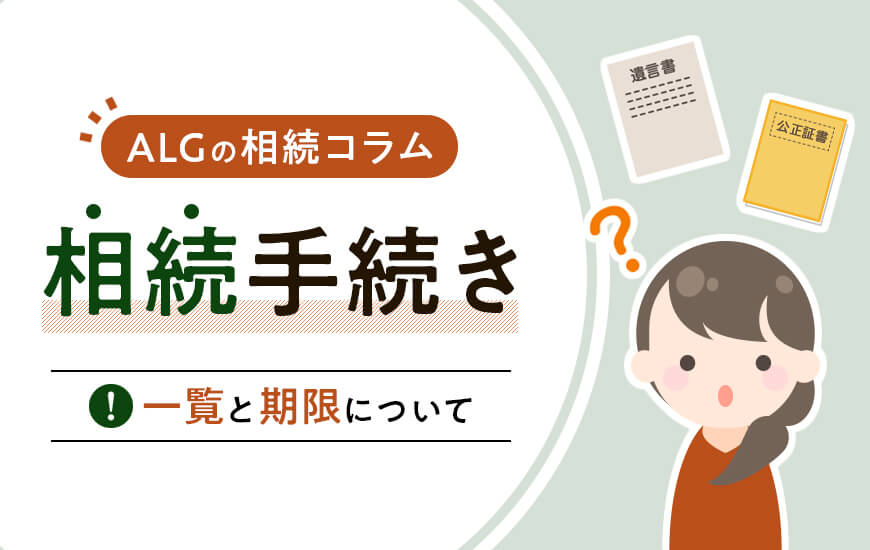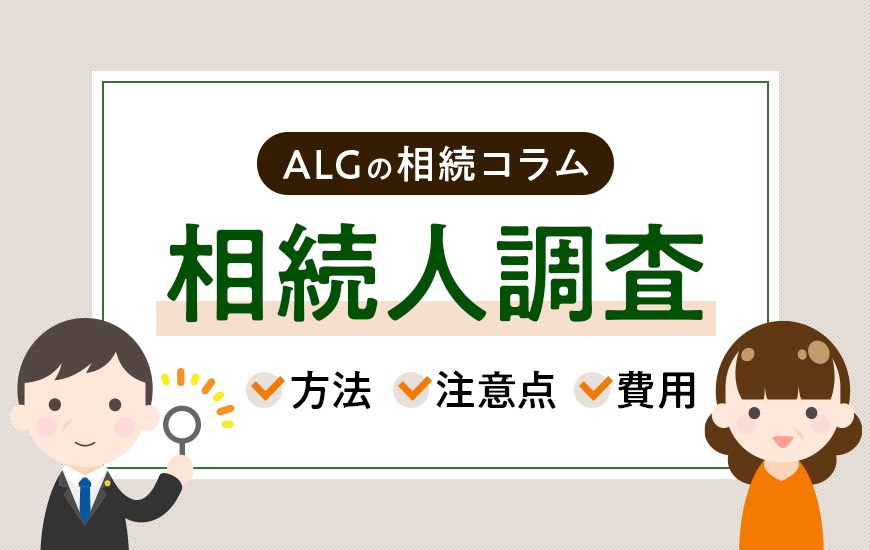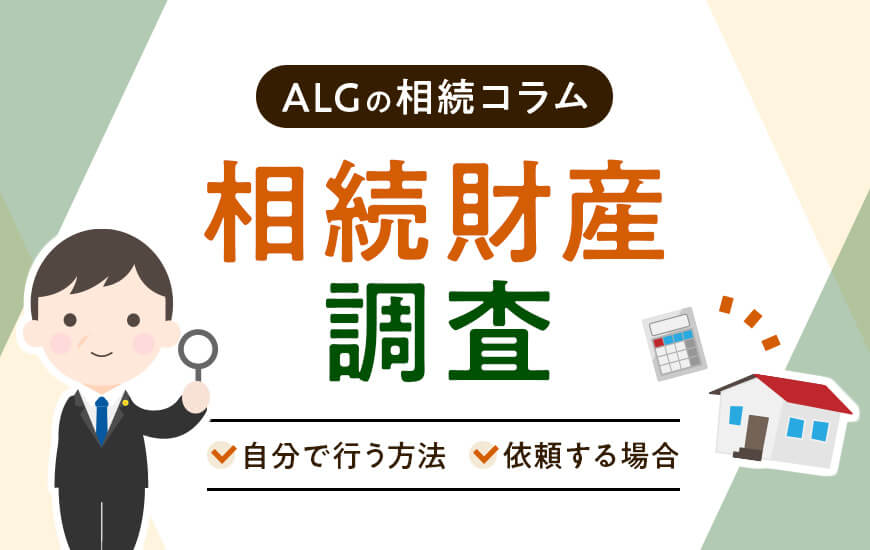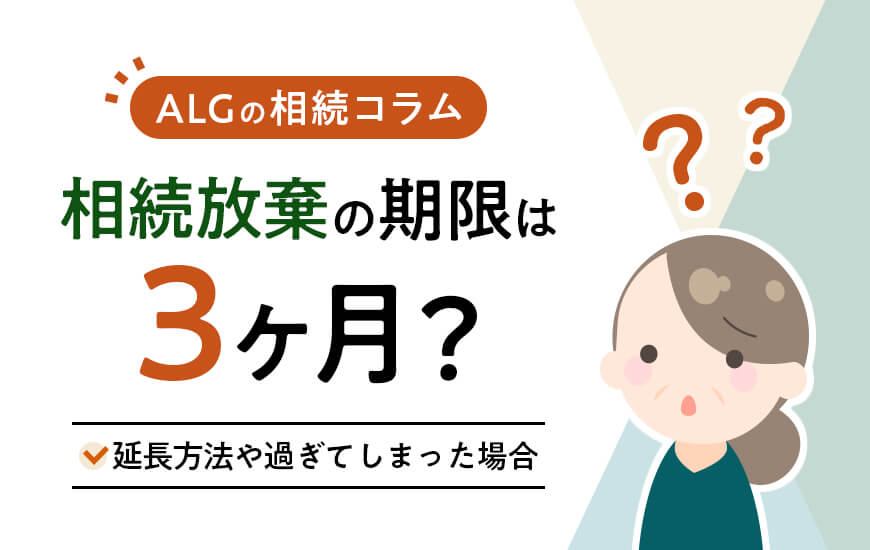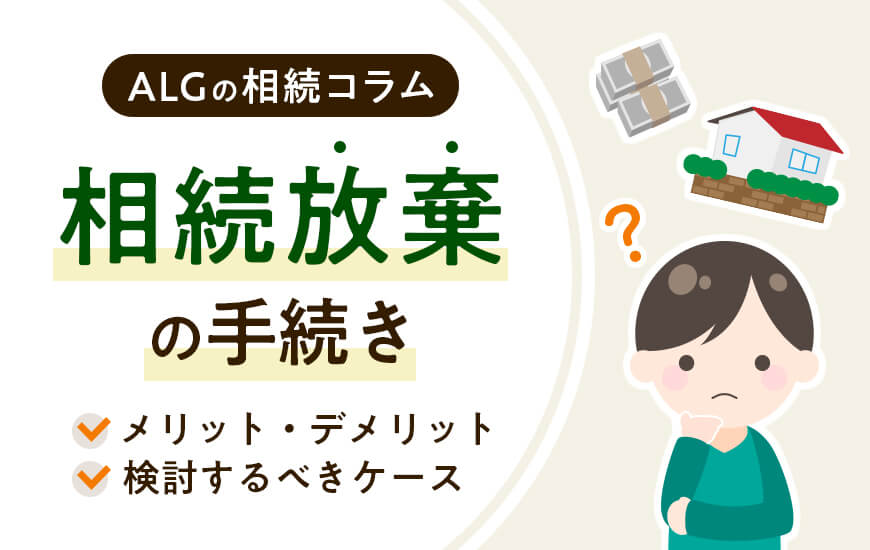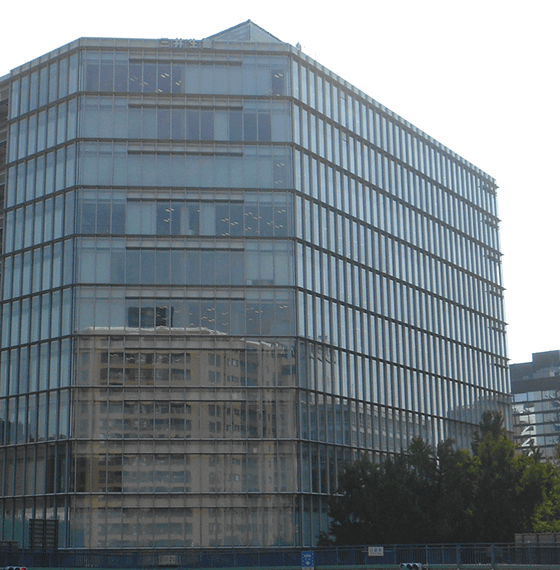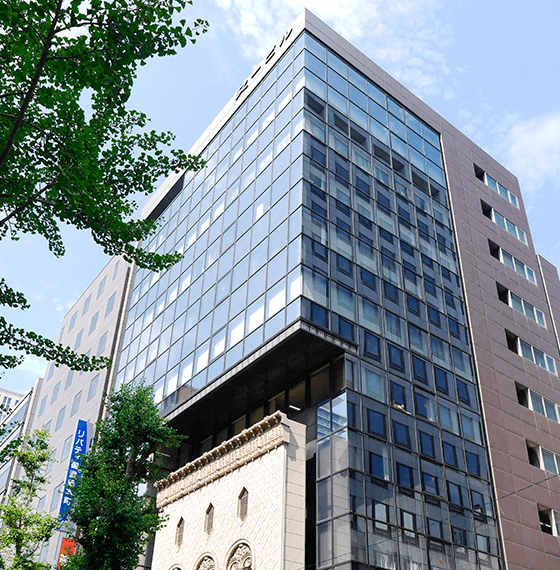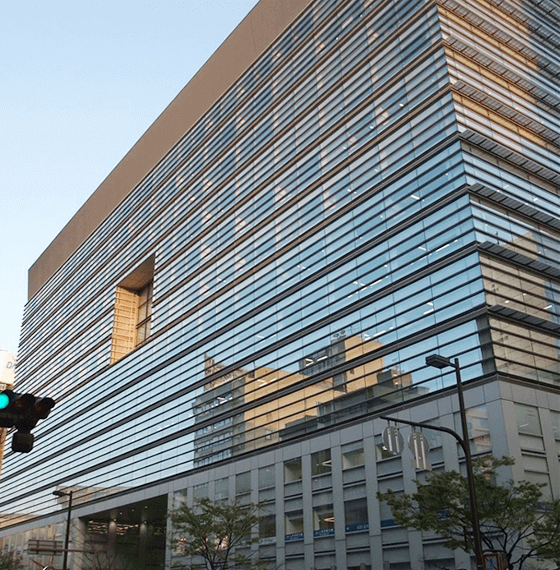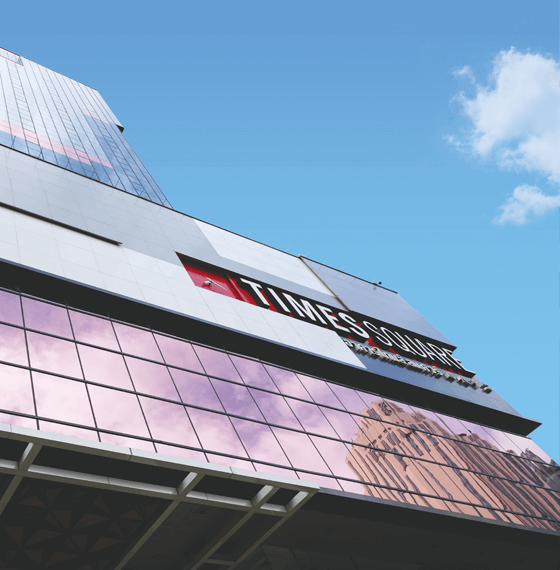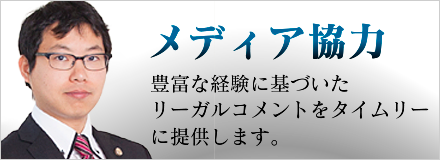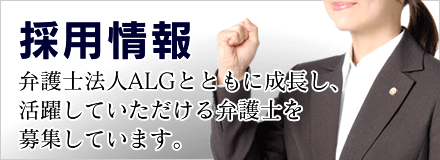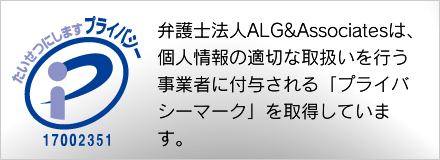実家を相続したらどうする?手続きや税金、やってはいけないことなど
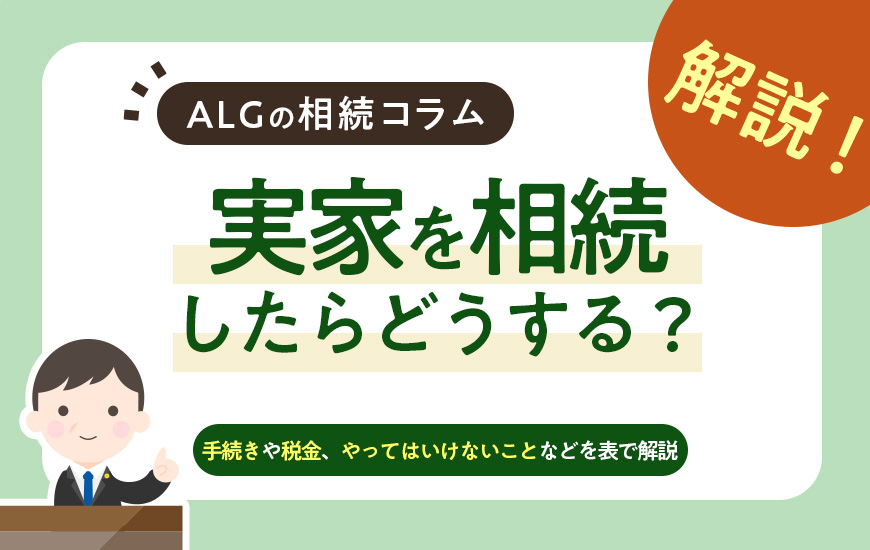
この記事でわかること
実家を相続する場合には、自分で住むケースだけでなく、住まずに活用するケースも考えられます。
思い入れのある実家を残したい相続人と、実家を売却して金銭等に換えてしまいたい相続人がいる場合には、活用方法などについて争いとなることもあるでしょう。
この記事では、実家を相続した場合について、手続きと期限、かかる税金、やってはいけないこと、弁護士に依頼するメリット等について解説します。
目次
実家を相続した場合の選択肢
相続財産に実家が含まれている場合には、主に以下のような対応が考えられます。
- 自分や兄弟が住む
- 賃貸に出す
- 更地にして土地活用する
- 売却して現金化する
- 相続放棄または限定承認する
これらの対応について、次項より解説します。
自分や兄弟が住む
相続財産に実家がある場合には、自分や兄弟姉妹などの親族が住むことが考えられます。家を購入すると数千万円かかることが多いので、実家に住むことができれば助かることが多いでしょう。
ただし、築年数が長い実家は修繕しなければならないケースが多いです。修繕費は、修繕の範囲や程度等によるものの、数百万円程度かかるケースもあります。
また、借家と違って固定資産税を払わなければなりません。毎年4月~6月頃に通知書が届き、一括で支払うか、4回に分けて支払う必要があります。
賃貸に出す
相続財産に実家があり、住む者がいない場合には、賃貸に出す方法があります。賃貸収入を得ることができれば、生活に余裕が生まれるかもしれません。
ただし、賃貸経営が順調にいく保証はなく、借主が現れないリスクや、借主とトラブルが発生するリスク等があります。
また、実家が古く、老朽化している場合には、リフォームしてから賃貸に出す必要があるでしょう。
更地にして土地活用する
相続財産に実家があり、住む者がいない場合には、更地にして土地を活用する方法があります。
新たにアパートやマンションを建てる方法や、駐車場にしてしまう方法等が考えられます。
活用方法によっては、初期投資が高額になるおそれがあります。土地の広さや利便性といったことを考慮して、最も有効だと考えられる方法で活用しましょう。
売却して現金化する
相続財産に実家があり、住む者がいない場合には、売却して金銭に換えてしまう方法があります。売却してしまえば、メンテナンスの手間や固定資産税がかからなくなるというメリットがあります。
また、一定の要件に当てはまるときは、売却により得られた利益(譲渡所得)の金額から最高3000万円までを課税対象から控除することができる特例があります。
ただし、売却する前に相続登記はしなければなりません。また、実家が先祖代々の土地に建っているケース等では、売却してしまうと親族等からの抗議を受けるおそれがあります。
売却を予定している場合には、遺産分割協議のときから話し合っておきましょう。
相続放棄または限定承認する
相続財産に実家があり、相続しても負担にしかならない場合や、実家以外の相続財産に高額な借金等が含まれている場合には、相続放棄や限定承認する方法があります。
相続放棄とは、相続人としての立場を放棄して、相続財産を一切受け取らない手続きです。他の相続人の同意がなくても可能であり、実家を含むすべての相続財産を受け取りません。
ただし、相続放棄するときに実家を占有していた場合には、相続放棄後も他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、保存義務が発生し、自己の財産と同一の注意で管理しなければなりません。
限定承認とは、相続財産に含まれるプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も相続する手続きです。
実家は手放したくないものの、相続財産に借金等が含まれており返済が負担になる場合には、限定承認すれば相続する借金等を抑えられる可能性があります。
ただし、限定承認は相続人の全員で行わなければなりません。また、余分な税金が発生するリスク等もあるので、限定承認の申立ては専門家に相談することをおすすめします。
実家を相続する際の手続きと期限
実家を相続するときの手続きと、その期限として、主に次のようなものが挙げられます。
- 遺言書の確認
- 相続人と相続財産の調査
- 相続放棄または限定承認(3ヶ月以内)
- 準確定申告(4ヶ月以内)
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
- 相続登記(名義変更)
相続手続きの一覧と期限を確認したい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
①遺言書の確認
実家を相続する者が遺言書によって指定されている場合には、基本的にその内容に従って相続するので、遺言書の有無は必ず確認しましょう。
遺言書がない場合には、相続人の全員が参加して遺産分割協議を行い、実家の相続人などを決めなければなりません。
手続きをスムーズに進めるために、早めに確認しておく必要があります。
②相続人と相続財産の調査
相続人と相続財産の範囲を確定するために、相続人調査と相続財産調査を行います。
相続人調査とは、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を調べる等して、法定相続人が誰であるかを確定させる手続きです。
相続財産調査とは、被相続人が遺したプラスの財産とマイナスの財産を洗い出して、相続財産の内容と評価額を確定させる手続きです。
どちらも、慣れない方にとっては大変な作業であり、手間と時間がかかります。自由な時間の少ない方等は、専門家に依頼することをおすすめします。
相続人調査や相続財産調査について知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
③相続放棄または限定承認(3ヶ月以内)
相続財産調査の結果により、実家を相続したくない場合には相続放棄、実家は手放したくないが相続財産に多額の借金が含まれている場合は限定承認を検討する必要があります。
期限は、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内です。
しかし、相続放棄すると、実家だけでなくすべての相続財産を放棄することになります。本当に相続放棄するべきなのか、慎重に検討するべきでしょう。
限定承認すると、時間と費用がかかるだけでなく、余分な税金がかかるおそれもあります。実家を手元に残すためだけに選択するべきではありません。
相続放棄や限定承認を行う前に、専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄の期限や実家の相続放棄について知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。
④準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人の生前の状況によっては、準確定申告を行わなければなりません。期限は、自己のために相続が開始されたことを知ってから4ヶ月以内です。
準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の、亡くなるまでの確定申告を相続人が代わりに行う手続きです。被相続人に事業所得があった場合や年収2000万円以上であった場合、公的年金が400万円以上であった場合等に行う義務があります。
手続きが遅れると、無申告加算税や延滞税といった余計な税金が発生するおそれもあるので注意しましょう。
⑤遺産分割協議書の作成
相続人の全員で遺産分割協議を行い、実家を相続する者も含めて協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
協議書がないと相続税の申告が煩雑になるため、相続税の申告期限よりも前に作成しておくと良いでしょう。
協議書は、相続登記や預貯金口座の名義変更といった手続きでも必要となることが多いため、遺言書がない場合には作成しておくと安心できます。
協議書の作成方法が分からない場合には、専門家に相談しましょう。
⑥相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
相続税の申告と納付の期限は、被相続人が亡くなったことを知ってから10ヶ月以内です。
それまでに納付しなければ、無申告加算税や延滞税などが発生してしまうため、必ず納税を間に合わせなければなりません。
ただし、被相続人が遺した相続財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかからないので申告する必要もありません。
相続税の基礎控除額は、次のような式によって計算します。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
なお、実家の土地等の評価額を抑えることのできる小規模宅地等の特例によって基礎控除額を下回るケースもありますが、このようなケースでは申告は必要となるため注意しましょう。
⑦相続登記(名義変更)
実家を相続したら、相続登記を行う必要があります。相続登記は2024年4月から義務化されており、不動産を相続したことを知ってから3年以内に行う必要があります。期限に遅れると、10万円以下の過料に処せられるおそれがあります。
実家を売却する場合や、賃貸に出す場合等であっても、その前に相続登記しておかなければなりません。
相続登記の義務化について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
実家を相続した場合にかかる税金と節税方法
実家を相続すると、主に相続税と登録免許税がかかります。また、実家を売却すれば譲渡所得税がかかるおそれがあります。
実家の相続によって発生する税負担を抑える方法として、主に次のような制度があります。
| 小規模宅地等の特例 | 被相続人が住んでいた実家等を相続する場合に、相続税について土地の評価額を最大で80%減額する |
|---|---|
| 配偶者の相続税控除 | 被相続人の配偶者が相続する場合、法定相続分または1億6000万円までは相続税を免除する |
| 相続空き家の3000万円特別控除 | 相続した実家が空き家であり、売却した場合に、譲渡所得税を3000万円控除する |
| 相続財産譲渡時の取得費の特例 | 相続した実家を一定期間内に売却した場合に、譲渡所得税の計算における取得費に相続税を加える |
相続税の計算について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
実家の相続でやってはいけないこと
実家の相続にあたっては、主に以下のことはやらないようにしましょう
- 実家を共有財産にする
- 放置して空き家にしてしまう
- 不平等な割合で相続する
これらの行為について、次項より解説します。
実家を共有財産にする
実家の相続でもめないように、相続人の共有財産にするケースがありますが、トラブルの原因になるおそれがあります。
共有財産にしてしまうと、共有者全員の同意がなければ、実家の売却や大規模なリフォーム、賃貸に出すこと等が困難となります。
また、管理する手間や費用、固定資産税の負担等が偏るおそれもあります。
共有者の1人が亡くなって新たな相続が発生すると、共有者が増えてしまい、共有者間の合意を得ることがさらに難しくなるおそれもあります。
不動産の共有はおすすめできないので、実家は単独で相続するようにしましょう。
放置して空き家にしてしまう
実家に住む者がいないからといって、実家を空き家にして放置すると、トラブルの原因となるおそれがあります。
空き家を手入れしないままでいると、建物の倒壊リスクや害虫の発生リスク、不法投棄が横行するリスク、不審者が住み着いてしまうリスク等が生じます。いずれも、周辺住民との関係が悪化し、場合によっては損害賠償請求を受ける原因となります。
また、自治体から特定空き家に認定されると、固定資産税が高くなってしまいます。行政代執行により実家が解体されると、費用を請求されます。
不平等な割合で相続する
相続財産の金額のうち、実家が高い割合を占めていると、平等な遺産分割が難しくなってしまい、不平等な相続により親族関係の悪化を招くおそれがあります。
実家以外の相続財産が乏しい場合には、代償分割や換価分割による平等な遺産分割を検討しましょう。
代償分割とは、実家を相続して遺産を多く受け取った者が、代償金を他の相続人へ支払うことによって、相続分を均等にする遺産分割方法です。
実家が残ることがメリットですが、相続人に代償金として支払うことのできる財産がある場合にしか使えません。
換価分割とは、実家を売却して金銭に換え、その売却代金を分配する遺産分割方法です。代償金を用意する必要がないことがメリットですが、実家を残すことはできません。
実家の相続手続きを弁護士に依頼するメリット
実家の相続手続きを弁護士に依頼する最大のメリットは、相続トラブルになったときに代理人として交渉してもらえることです。
単なる手続きであれば、他の専門家でも可能な場合がありますが、代理人として交渉できるのは基本的に弁護士だけです。
実家の相続では、他の相続人と争いになるリスクが低くないので、そのときに改めて弁護士に依頼するよりもスピーディーに対応できます。
相続問題を弁護士に相談するメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
実家の相続に関するよくある質問
実家の相続は長男が優遇される?
地域によっては、現在でも相続で長男が優遇される風習が残っていますが、法的には長男は優遇されません。そのため、長女や二男等が実家を相続する可能性があります。
遺産分割協議は当事者の話し合いなので、長男が実家を相続すると決めることができます。
しかし、法的な裏付けのない長男の権利を主張すると、他の相続人が反発して相続争いの原因となるおそれがあります。
長男に実家を継がせたい場合には、遺言書を作成しておく方法が考えられます。
実家の名義が親のままだと相続税はかからない?
実家の名義を親のままにしておいても、相続税や固定資産税はかかります。
現在では相続登記が義務化されているため、相続登記をしないままで放置すると、10万円以下の過料の支払いを命じられるおそれがあります。
また、相続登記しないままで放置すると、新たな相続が発生して相続登記が難しくなったり、実家が差し押さえられて自分の権利を主張できなくなったりするおそれもあるので注意しましょう。
実家の相続についてわからないことがあれば相続問題に詳しい弁護士にご相談ください
実家の相続では、実家に思い入れがあるか、資産価値があるか等様々な事情によって対応方法が変わります。
実家も含めて相続財産が乏しく、負担が大きいのであれば、相続放棄を検討する必要もあります。
実家の相続で、どのように対応するべきかを悩んでいる場合には、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、実家を相続するべきなのか、相続したら発生する負担はどのようなものであるか等についてアドバイスできる可能性が高いです。
実家について考えるべきことは多いので、より良い選択をするために、弁護士が詳しくお話を伺います。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)