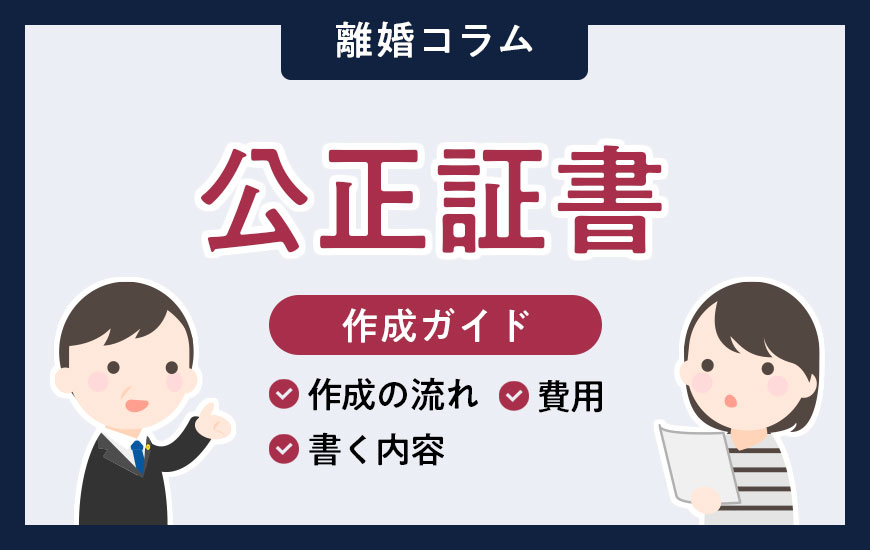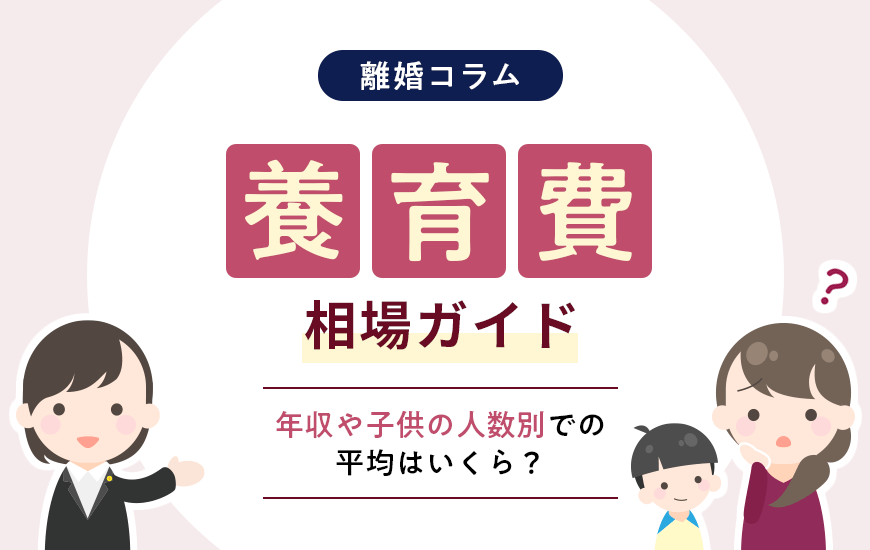離婚協議書のサンプル付き!効力や公正証書にする必要性などを解説
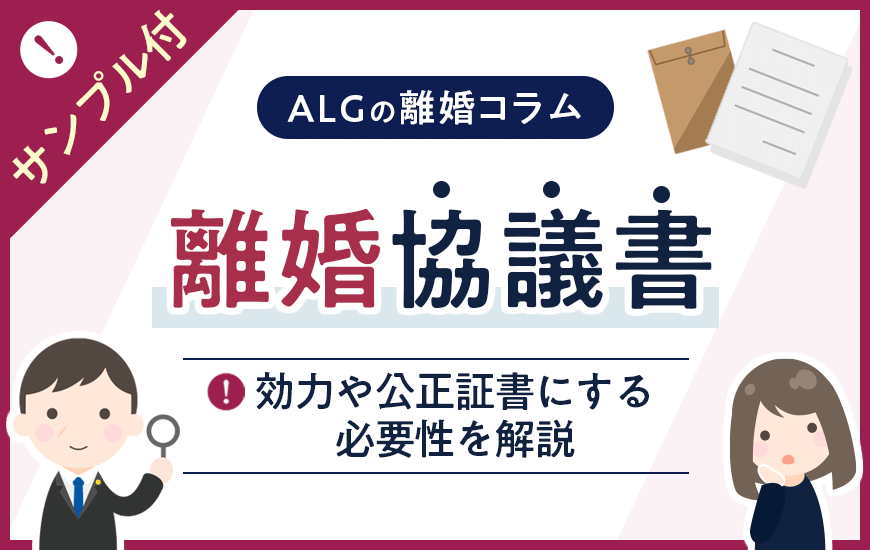
離婚協議書とは、夫婦が離婚する際に離婚の方法や、2人で取り決めた離婚条件の内容をまとめた書面のことをいいます。
離婚時に書面に残さず、口約束のみで慰謝料や養育費などを取り決めてしまうと、後から「言った・言わない」の争いとなり、支払いがされないおそれもあります。
そのため、離婚協議書を作成することは、非常に大事なことだといえます。
この記事では、離婚協議書に記載するべき内容や作成のポイントなどについて解説していきます。
目次
離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚の際に夫婦間で取り決めた約束事を書面にした契約書です。
取り決めた内容を「離婚協議書」として書面に残すことで、後から約束事の確認もできますし、合意した内容を巡って後から「言った・言わない」のトラブルになることを防げます。
また、取り決めた内容について相手が約束を守らない場合も、離婚協議書は有効です。
例えば、元配偶者が取り決めた慰謝料を支払わず、支払いを求める場合では、まずは本人に「離婚協議書で取り決めている」と心理的プレッシャーを与えることができます。
また、調停や裁判の手続きでも、離婚協議書は取り決めた内容を証明する大きな証拠となるでしょう。
なお、金銭の取り決めをした場合は、離婚協議書を強制執行認諾文言付公正証書にすることをおすすめします。
これによって、取り決めた慰謝料など金銭の約束が果たされない場合には、強制執行の申立てをすることで直ちに財産を差し押さえることができます。
離婚協議書の効力
離婚協議書を作成するうえで、重要なポイントは、法的拘束力が認められる内容にすることです。
法的に有効な内容の協議書を作成していなければ後々トラブルになる可能性があります。
また、離婚後に約束事を取り決めて離婚協議書を作成することは可能ですが、離婚を先にしてしまうと、相手が話し合いに応じない可能性もあります。
加えて、離婚にまつわる手続きには時効があり、年金分割や財産分与は離婚から2年、慰謝料は離婚から3年経つと時効により請求権が消滅してしまうため、離婚協議書はなるべく離婚前に作成するようにしましょう。
記載するべき内容
離婚協議書へ記載するべき内容を表にまとめましたので、ご覧ください。
| 記載内容 | 解説 |
|---|---|
| 離婚の合意 | 離婚届提出日など |
| 財産分与 | 対象財産の特定、支払う側・受け取る側の特定、金額、支払い方法、支払い時期など |
| 年金分割 | 年金分割をする時期、割合 |
| 慰謝料 | 金額、支払う側・受け取る側の特定、支払い方法、支払い時期など |
| 養育費 | 金額、支払う側・受け取る側の特定、始期と終期、支払い期限、支払い方法など |
| 親権者・監護者 | 親権者・監護権者の特定 |
| 面会交流 | 回数、時間、場所、方法など |
| 強制執行付き公正証書作成について | 清算条項について |
| 住所等を変更した際の連絡について | 公正証書にする場合は同意する一文を入れる |
| 清算条項について | 離婚協議書以外に財産その他の請求をしないことを約束する一文を入れる |
※当事者夫婦の事情によって記載内容は変わります
離婚協議書を作成する際のポイント
離婚協議書を作成する際のポイントとして、後々のトラブルを避けるためにも、離婚条件について夫婦でよく話し合うことが大切です。
離婚をする相手とは、なかなか話をしたくないと思われるかもしれませんが、離婚条件についての取り決めがお互い合意の上でないと、後で揉める原因となってしまいます。
まずは当事者双方が納得できるまで話し合いましょう。
話し合いがまとまったら、離婚協議書を作成します。
離婚協議書には、離婚届のように決まった書式があるわけではありません。
書式についてはインターネットでも多くのテンプレートや書式例がありますので、参考にされると良いでしょう。
なお、離婚協議書は手書きでもパソコン入力でもどちらでも構いません。パソコンの場合には、署名は自筆にするようにしましょう。
離婚協議書のサンプル(テンプレート)
以下の書式は、慰謝料について取り決めのない離婚協議書のサンプルです。
また、この書式はサンプルですので、個別具体的な状況に応じた最適な協議書を作成するためにも、離婚に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
離婚協議書
〇〇〇〇(以下甲という)と△△△△(以下乙という)は、甲乙間の婚姻の解消に関する件(以下、「本件」という。)について、以下のとおり合意する。
第1条(離婚の合意)
甲及び乙は、本日、協議離婚すること及び乙がその届出を速やかに行うことを合意する。
第2条(親権)
甲乙間の長男□□(令和□年□月□日生)、次男✕✕(令和✕年✕月✕日生)の親権者・監護権者を乙と定めて、乙において監護養育することとする。
第3条(養育費)
- 甲は乙に対し、前記子らの養育費として、令和〇年〇月から満20歳に達する月まで、1人につき1か月〇万円の支払い義務があることを認め、これを毎月末日限り乙が指定する口座に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
- 前記子らが大学またはこれに準ずる高等教育機関(以下「大学等」という。)に進学した場合、前項の養育費の支払いは、前記子らが大学等を卒業する月まで行うものとする。
- 当事者双方は、前記子らの病気、進学等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする。
第4条(面会交流)
- 乙は、甲が前記子らと月1回程度、面会交流することを認める。
- 面会交流の具体的な日時、場所及び方法については、前記子らの福祉に配慮して、甲及び乙が協議して定める。
第5条(財産分与)
甲は乙に対し、財産分与として金□円の支払義務の存することを認め、これを一括して令和□年□月末日限り、乙名義の□銀行□支店の普通預金口座(口座番号:1234567)に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は甲が負担するものとする。
第6条(年金分割)
甲は乙に対し、甲乙の婚姻期間中における双方の年金分割の割合を0.5とすることに合意し、その年金分割に必要な手続きに協力することを約束する。
第7条(清算条項)
甲及び乙は、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。
第8条(公正証書)
甲及び乙は、本件離婚協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作成することに合意した。
以上の合意成立を証するために、本書2通を作成し、甲乙が署名捺印の上、各自1通を保有する。
〇年〇月〇日
(甲) 住所
氏名 印
(乙) 住所
氏名 印
上記の「離婚協議書のテンプレート」は下記から無料でダウンロード可能です。
離婚協議書を公正証書にする必要性
「離婚協議書」と「公正証書」はどちらも離婚の契約書であることには変わりありません。
しかし、金銭のやり取りに関する契約(約束)については、強制執行認諾文言付の公正証書を作成することで、特別な機能を付けられます。
その機能とは、元配偶者が慰謝料や養育費などを支払う旨の取り決めをしたにもかかわらず、約束通りに支払わない場合に、裁判所の手続きを経ることなく、財産を差し押さえる手続き(強制執行)を行うことができることです。
離婚協議書は、離婚の契約書として法的な効力を持ちますが、強制執行認諾文言付公正証書のような機能を付けることはできません。
そのため、元配偶者から金銭が支払われない場合には、裁判上での手続きを新たに行わなければなりません。
以下の表で、離婚協議書と公正証書の違いをまとめましたのでご覧ください。
| 離婚協議書 | 公正証書 | |
|---|---|---|
| 法的効力 | 低い | 高い |
| 費用 | かからない | かかる |
| 作成者 | 離婚したい夫婦 | 公証人 |
| 強制執行 | 裁判をしなければならない | 裁判なしでできる |
| 偽造される可能性 | 可能性がある | なし |
離婚の公正証書については以下でも詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
作成の費用
離婚協議書は夫婦で話し合って作成するものなので、特別な費用は掛かりません。
一方、離婚協議書を公正証書にする場合は、公証人に作成手数料を支払わなければなりません。
手数料は、公正証書に記載する慰謝料や養育費の額によって異なります。
例えば、「月5万円の養育費を5年間支払う」という取り決めをした場合は、養育費の総額が、「5万円×12ヶ月×5年=300万円」となるので、公正証書の作成手数料は1万1000円となります。
公正証書なら強制執行が可能
公正証書と離婚協議書の違いに、強制執行をすることができるかできないかというものがあります。
強制執行とは養育費や慰謝料が支払われなかったなど、離婚に際しての決め事が守られなかった場合に強制的に給与や預金などの財産を差し押さえることです。
手元に離婚協議書しかない場合で、元配偶者が金銭の取り決めを守らず未払いとなった場合はどのように対応すればいいのでしょうか。
財産を差し押さえる「強制執行」の手続きをするためには「債務名義」が必要です。
離婚協議書は債務名義にはならないため、債務名義を得るために裁判所に調停や審判を申し立てる必要があり、非常に時間や労力がかかってしまいます。
公正証書の場合は、強制執行認諾文言付公正証書にすることによって、裁判を行わず、強制執行の申立てをすることで、元配偶者の財産を差し押さえることが可能です。
離婚協議書を公正証書にする流れ
夫婦で離婚協議書を作成した後に、「やっぱり公正証書として残したい」と思われる方もいるでしょう。
特に、金銭の取り決めをしている場合は公正証書にすることで、未払い時に強制執行の手続きをすることができます。
また、原本は公証役場で保管されるため、改ざんの心配がないことも大きなポイントです。
では、離婚協議書を公正証書にする流れについて見ていきましょう。
- 公証役場の公証人と面談をする
離婚協議書を持参のうえ、公証人と面談を行います。この時点では夫婦のどちらか一方が出向けば問題はありません。 - 公正証書の原案作成 夫婦で公正証書の原案を作成し、問題がなければそのまま作成に移ります。
- 作成日の予約
- 公証役場へ訪問
予約当日に夫婦双方(代理人でも可)で公証役場に訪問します。本人確認資料等を持参します。 - 公正証書の完成
公証人の面前で公正証書の読み合わせを行い、当事者が署名・捺印します。手数料を支払い、公正証書を受け取ります。
必要書類
離婚協議書を公正証書にするために必要な書類は以下のとおりです。
離婚協議書
戸籍謄本
- 公正証書作成後に離婚する場合:家族全員が記載されたもの
- 離婚済みの場合:双方の離婚後の戸籍謄本
不動産の登記簿謄本および固定資産税納税通知書
不動産の所有権を相手方に移す場合に必要となります。
年金分割のための年金手帳等
年金分割をする場合は、当事者の年金番号を公正証書に記載するため、年金番号がわかる資料が必要です。
その他
また、作成当日の持ち物は、以下のとおりです。
- 運転免許証などの身分証明書
- 実印と印鑑証明書
- 手数料
公正証書の手数料は基本的に現金払いとなるので、現金を用意するようにしましょう。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
離婚協議書についてよくある質問
離婚協議書を作成後に変更することは可能ですか?
基本的に、一度取り決めた離婚協議書は後から変更することはできません。
しかし、特に養育費は支払う側の収入増額・減額、受け取る側の収入の増額・減額など、離婚時には予測できなった事情が発生することもあります。
その場合には、お互いの同意があれば内容を変更することができます。まずは、相手方に相談してみましょう。
離婚の養育費については下記の記事でも詳しく解説しています。併せてご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
慰謝料や財産分与などを請求しない旨を離婚協議書に記載することはできますか?
財産分与をしない場合は、財産分与についての項目を記載する必要はありません。
しかし、財産分与をしないと決めて「この内容に同意し、ほかには何も請求しません」という一文を入れてしまうと後から変更が利かなくなってしまいます。
財産分与は離婚する夫婦双方の権利です。
相手側から一方的に財産分与はしないと言われている場合は、弁護士に相談しましょう。
離婚協議書は手書きでも効力がありますか?
離婚協議書は、手書きであっても夫婦の署名・捺印があれば契約書としての効力を持ちます。
手書きで記入作成する場合は、署名と同様に、鉛筆や消えるボールペンは避け、油性の消えないボールペンを使用するようにしましょう。
また、離婚協議書は、取り決めたことを証明する証拠として第三者に確認してもらう場合もあるため、誰が見ても分かるよう丁寧に字を書くように気を付けましょう。
離婚協議書に書かれたことを守らず、違反した場合はどうなりますか?
離婚協議書で養育費や慰謝料の支払いを取り決めたにもかかわらず、元配偶者がその約束を守らない場合、まずは元配偶者と話し合いを行いましょう。
話し合いの方法は電話やメールでも構いません。
それでも約束が守られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
もし、離婚協議書を「強制執行認諾文言付公正証書」にしていれば、家庭裁判所の手続きは必要ありません。
直接強制執行の申立てをすることができます。
離婚協議書についてお悩みの方は弁護士法人ALGへご相談ください!
離婚協議書は夫婦間で取り決めた条件をまとめた契約書です。
取り決めた慰謝料や養育費が支払われない場合においては、法的効力を持つ大事な書類となります。
しかし、法的効力を持つためには、離婚協議書の内容が法的に適切なものでなければなりません。
離婚に詳しくなければ、内容についての検討は難しいと思いますので、離婚協議書については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
離婚に詳しい弁護士であれば、離婚協議書の精査だけでなく、公正証書にしたい場合もサポートしていきます。
離婚協議書や公正証書の作成をお考えの場合は、まずは一度、私たちにお話をお聞かせください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)