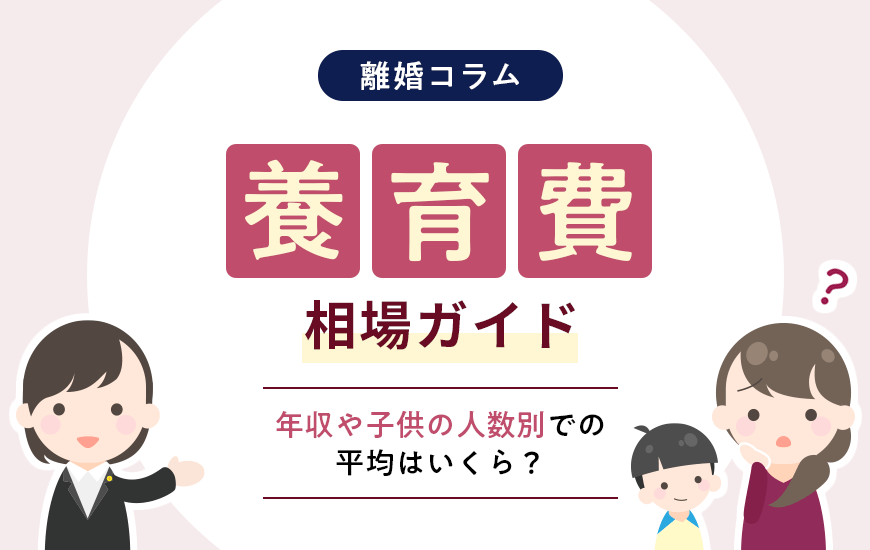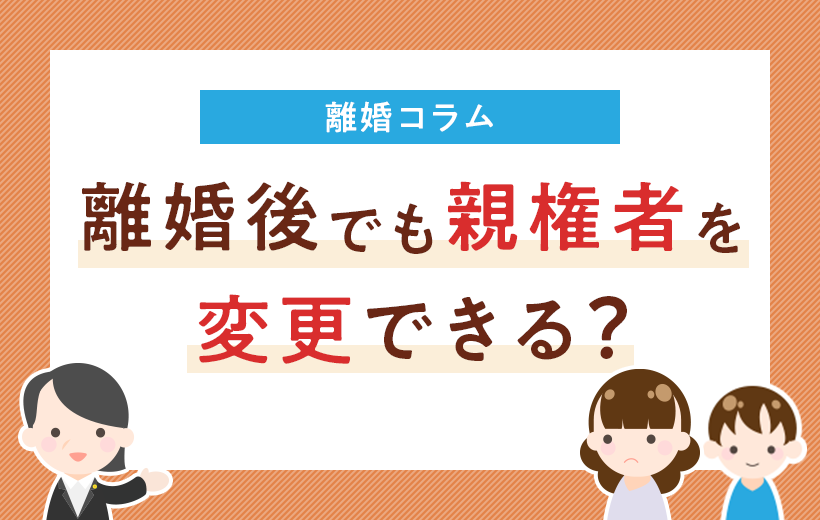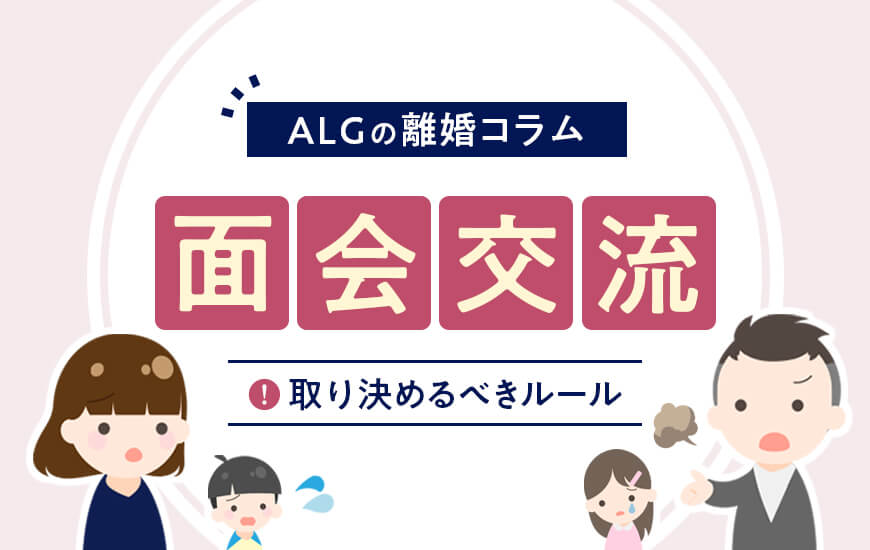離婚時に父親が子供の親権を勝ち取るためのポイント【事例付き】
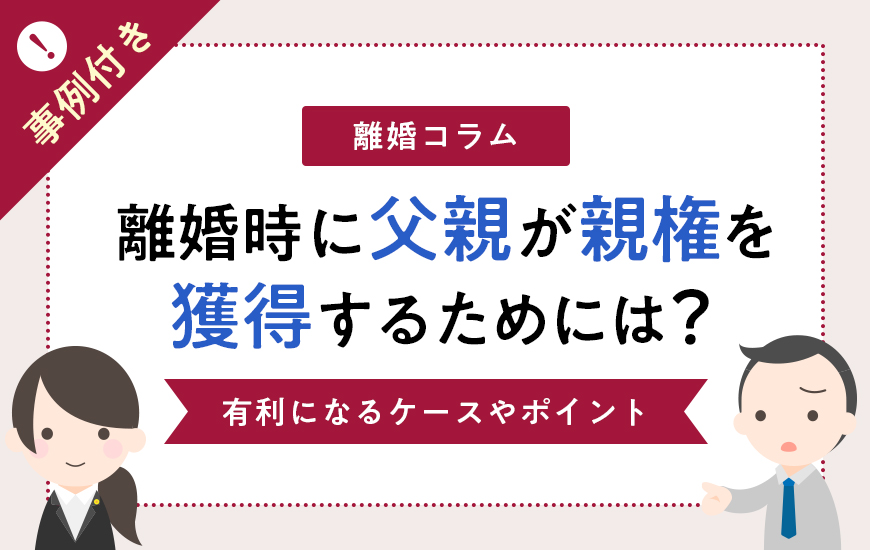
親権とは、未成年の子供を監護・養育(身上監護権)し、子供の財産を管理(財産管理権)する親の権限であり義務です。婚姻中は父母双方が親権者となりますが、現在の法律では離婚後は単独親権制度となりますので、離婚時に父母どちらかを親権者と定めなければなりません。
親権は「どちらと暮らした方が子供は幸せか」という観点から決めるため、実際に子供の面倒を多く見てきた母親が親権者となるケースが圧倒的に多く、父親が親権者となるケースは1割程度と少ないのが実情です。
この記事では、父親が親権を得るのは難しいのか、など父親が親権を勝ち取るために知っておくべきことについて解説していきます。弁護士法人ALGによる、父親が親権を獲得した解決事例もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
父親が親権争いで不利な理由
日本では、離婚後の親権について「単独親権制度」を導入しています。これは、父母どちらかを親権者と定めるもので、現在は母親の方が親権争いでは圧倒的に有利といわれています。
下表は、令和5年度の司法統計をまとめたものです。離婚調停や審判では、9割以上で母親を親権者として定めていることが分かります。
| 総数 | 1万6103件 |
|---|---|
| 母親が親権者 | 1万5128件 |
| 父親が親権者 | 1290件 |
父親は、なぜ親権争いで不利になるのでしょうか。その理由は、以下のようなものが考えられます。
- 子供が小さければ小さいほど母親が有利
- 仕事と育児の両立の難しさ
- 子供が母親を選ぶ
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
子供が小さければ小さいほど母親が有利
子供が小さければ小さいほど、一般的に、親権争いでは父親よりも母親が有利になります。
それは、子の福祉の観点から、子供は父親よりも母親と暮らした方が望ましいという「母性優先の原則」が、子供が乳幼児であればあるほど重視される傾向にあるからです。
もっとも、母性優先の原則は親権者の決定基準の1つに過ぎず、母親側の理由(精神病、愛情の欠落、虐待など)により、これまで母親が子供に対して母性的な関わりをしてこなかったといった場合には、母性的な関わりをしてきた父親が有利になる可能性もあります。
仕事と育児の両立の難しさ
共働き家庭が増えたといっても、父親が一家の大黒柱となって仕事に励み、母親が主に子供の監護をしている家庭が多いのが現状ではないでしょうか。
親権者の決定においては、これまでの監護実績が重視されます。そうすると仕事のために家にいる時間が短い父親は、母親に比べて監護実績が乏しく、不利になってしまいます。
また、子供の発熱や病気など不測の事態が生じたときに、仕事を休んだり、早退することで、すぐに子供のもとに戻れる職場環境かどうかも子供が小さければ小さいほど重視されます。
そのため、仕事と育児の両立の難しい父親には不利になってしまうのです。
子供が母親を選ぶ
普段から子供を主に養育しているのが母親の場合には、子供が父親よりも母親に懐いているため、母親と暮らすことを選ぶケースも多いでしょう。
子供が15歳以上であれば子供の意思を最大限尊重しなければならないとされています。また、15歳以下でも10歳程度であれば、一般的には子供の意思が尊重されます。そのため、父親にとっては不利となるでしょう。
父親が知るべき裁判所が親権者を決める時の基準
裁判所が親権者を定める際に重要視するのは子の福祉(しあわせ)です。では、どのような基準によって子の福祉を判断するのでしょうか。
裁判所が親権者を定める判断基準は、大きく以下の6点が重要視されます。
- 母性優先の原則
- 監護継続の原則
- 兄弟姉妹不分離の原則
- 子供の意思の尊重
- 監護体制の優劣
- 面会交流についての寛容性の原則
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
母性優先の原則
「母性優先の原則」とは子供にとって母親は必要不可欠であり、母親と暮らした方が幸せであるという考え方です。特に0~5歳の乳幼児期の子供の場合、親権者の決定においては母親が優先される傾向にあります。
しかし、近年は共働き家庭が増え、父親が子供の主な監護を行うケースも増えてきました。そのため、母親だから優先されるのではなく、監護者としてきめ細やかな育児ができるのかが重要視されるようになってきています。つまり、「きめ細やかな監護養育」ができるのであれば、父親も親権を獲得できる可能性があります。
具体的には、以下のような日常的な育児を父親で行っていることが重要です。
- 食事を食べさせる
- お風呂に入れる
- 寝かしつけをする
- トイレや排せつ物の処理
- 衣服を着せる
- 休日に出かけるなどのスキンシップをとる
監護の継続性の原則
監護の継続性の原則とは、これまでの監護・養育状況に問題がなければ、子供がこれまで育ってきた環境を変えないように、主に子供の養育をしてきた者が引き続き養育することが望ましいという考え方です。
離婚によって、子供はこれまで一緒に暮らしてきた親と離れるだけでも精神的な負担を負います。そこに引っ越しや転校などの環境の変化が加われば、子供の心理的ダメージは大きなものとなってしまうでしょう。
もっとも、離婚の話し合いの時点ですでに別居をしている場合は子供が一方の親の元で一定期間安定した生活を送っているのであれば、その現状を維持することが推奨されます。
兄弟姉妹不分離の原則
兄弟姉妹不分離の原則とは、子供の人格形成のためには兄弟や姉妹と一緒に育てる方が望ましいという考え方です。
複数の子供の親権の取り合いの妥協策として、例えば長女の親権者は母親、長男は父親というように、兄弟姉妹の親権者を分離させて養育するのは親の利益を考慮しているにすぎません。
子供にとっては、父母との分離だけでなく、強い絆のある兄弟姉妹とも切り離されることになり、二重の精神的負担を負うことになります。
そのため、兄弟姉妹が離れ離れにならないよう、一緒に引き取ることができる方が有利となります。
子供の意思の尊重
どちらの親と暮らしたいかという子供の意思も尊重されます。ただし、すべての年齢の子供の意思が尊重されるわけではなく、子供の年齢によって判断の重みが変わります。
年齢ごとの対応については、以下の表をご参考ください。
| 乳幼児~10歳前後 | 意思能力が乏しいとされ、意思以外の判断基準に重きが置かれる |
|---|---|
| 10歳前後~14歳 | 意思能力が認められ、子供の意思が考慮される |
| 15歳以上 | 審判・訴訟時に必ず子供への意見聴収が行われ、子供の意思が最大限尊重される |
監護体制の優劣
監護体制の優劣とは、経済・居住・養育・教育などの環境をみて、より子供にとって望ましい方を選ぶべきという考え方です。
しかし、経済力に関しては、養育費や公的援助を活用すれば賄うことができるため、あまり重視されない傾向にあります。
つまり、父親の方が経済力に優れていたとしても、それだけで親権獲得に有利とはならないということです。
面会交流についての寛容性の原則
面会交流についての寛容性の原則とは、子供の親権者となった場合には、非親権者と子供の面会交流に対して協力的・寛容であるべきという考え方です。
面会交流は、子供が両親のどちらからも愛されていると実感でき、子供の健やかな成長のために必要な機会です。そのため、面会交流に協力的な親の方が子供の利益を重視していると判断されます。
しかし、相手方が子供の虐待をするなど、面会交流を行うことで子供に危険が及ぶ場合には、この限りではありません。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
親権争いで父親が有利になる5つのケース
家庭の状況によっては、父親が親権争いで有利になるケースがあります。
- 継続した監護・養育実績がある
- 母親が育児放棄している
- 母親が子供を虐待している
- 母親が不貞相手との生活を優先している
- 子供が父親と暮らしたがっている
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
継続した監護・養育実績がある
裁判所が親権者を決定するうえで重要視するのが、「監護の実績」です。つまり、これまでどのくらい子供を監護してきたのか、ということです。また、父親が親権を獲得した後も子供の生活が離婚前と変わらないことも大切です。
例えば、以下のようなケースは父親が親権者として相応しいと判断される可能性があります。
- 父親が専業主夫として家事や育児を担ってきた
- 共働きの場合でも、父親の方が母親よりも育児に関わり、実際に子供の世話をしてきた
このように、日ごろから子供に対する監護意欲があるという姿勢が重要でしょう。
母親が育児放棄している
母親が育児放棄していることは、父親が親権争いで有利になるポイントのひとつでしょう。
具体的な「育児放棄」に該当する状況には、以下のようなものが当てはまります。
- 子供に食事を与えない、世話をしない
- 子供を不潔な状態のままにしている
- 子供が話しかけても無視をする、会話をしない
- 家や自動車に置き去りにして外出する
- 病気やケガをしても病院に連れていかない
このように、育児放棄をしている母親を親権者とすることは子供の利益(しあわせ)にかなっていません。そのため、子供を守る観点からも父親に親権が認められやすいでしょう。
母親が子供を虐待している
育児放棄と同様に、母親が子供を虐待している場合は、父親が親権者となる可能性が高いでしょう。
虐待とは、単に身体的虐待だけでなく、心理的虐待も含まれます。これらの違いは以下のとおりです。
| 身体的虐待 | 殴る、蹴る、叩く、やけどを負わせる、冷水を浴びせる、溺れさせる、戸外に閉め出す、縄やケージなどで身体を拘束する など |
|---|---|
| 心理的虐待 | 暴言を吐く、脅す、兄弟間で差別的に扱う、無視する など |
このような状況では子供の健やかな成長は望めません。一刻も早く虐待から抜け出すためにも、早急に弁護士に相談すべきでしょう。
母親が不貞相手との生活を優先している
母親側の不貞行為(不倫)が原因で離婚する場合、母親に親権を渡したくないと思われるかもしれません。しかし、不貞行為は夫婦の問題であり、母親としての監護実績に問題がない場合は、親権者の決定において不貞行為があったことは考慮されません。
ただし、母親が子供の監護養育よりも不貞相手との生活を優先し、子育てを疎かにしていた場合では、父親が親権交渉で有利になりやすいでしょう。
子供が父親と暮らしたがっている
子供が「父親と暮らしたい」と望んでいる場合は、父親が親権を獲得できる可能性があります。
特に子供が10歳以上であれば子供の意思が尊重されるケースが多いでしょう。
ただし、子供によっては親に気を使い本当の気持ちを言えない場合もあります。そのような場合には家庭裁判所の調査官が面談や調査を行う場合があります。
その際、子供に「お父さんと一緒にいたいよね?」「お父さんと暮らしたいよね?」と誘導してしまえばかえって不利になることが多いので注意しましょう。
父親が親権を取るには?7つのポイント
父親が親権を取るには、以下の7つのポイントがあります。
- 不貞をしても親権では有利な母親への対処
- 母親の子育ての問題点を証明
- 今後の子供と過ごす時間の確保
- 積極的な養育実績を作る
- 別居時に子供と離れて暮らさない
- 周囲からの子育てサポート体制を整える
- 学童期まで離婚しない
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
不貞をしても親権では有利な母親への対処
母親側に不貞行為など有責行為があり離婚に至った場合、「有責行為をしたのだから、親権者は父親にすべきだ」と思われるかもしれません。しかし、たとえ母親側の不貞行為で離婚に至ったとしても、それは夫婦間の問題であり、親権者の適格性とは別物です。そのため、母親の監護実績に特段問題がなければ、基本的に親権者の決定に影響を与えることはありません。
しかし、母親側が不貞行為の結果、親としての監護・養育責任を十分に果たしていないといえる場合には、親権者として不適切と判断される可能性があります。
そこで、母親が不貞行為により子育てを疎かにしていたことを裏付ける証拠を残しておきましょう。
【妻の不貞が発覚したらやるべきこと】
- 不貞の証拠をきちんと取っておく(ラブホテルや不貞相手の自宅へ2人で入る写真など)
- 子供を連れて父子で遊びに行き、その間に妻が不貞をしていれば証拠を押さえておく
- 部屋が散らかっているなど、家事を怠っていればその写真も残しておく
- 子供に対する態度が悪ければ、音声や動画を撮っておく
母親の子育ての問題点を証明
母親が子供の監護・養育能力に具体的問題がある場合は、それを主張・立証することも重要です。
母親が子供を養育することが子供のためにならない可能性が高いケースは以下のとおりです。
- 母親が子供に対して日常的に暴力を振るっていたり、暴言を吐いたりしている
- 母親に浪費癖があり、子供の経済的安定が阻害される可能性が高い
- 母親が精神疾患や薬物依存などで正常な判断を維持する能力が喪失・減退している
このような母親の行動は、子供の身体の成長や心の発達に大きな影響を与えてしまいます。子の福祉に反している母親は、親権だけでなく面会交流も認められない可能性もあるでしょう。
今後の子供と過ごす時間の確保
離婚後、子供と過ごす時間を十分に確保できることも大事なポイントです。
具体的には、以下のような準備をしましょう。
- 仕事の時間を調節できるようにする
- 父親の両親など周囲の協力が得られる体制を整える
このように、子供を養育する環境が整っていれば、父親が親権を獲得できる可能性が高まります。
積極的な養育実績を作る
親権を獲得するためには、子供の監護養育に携わってきた実績が重要です。これは、「子供のためにお金を稼いだ」という実績ではありません。あくまで「どれだけ子供に接し、子供の世話をしてきたか」という点が大切です。
仕事をしながらでも、養育実績を提示することで、父親も母親同様の実績が認められます。
養育実績作りのために以下のことを行いましょう。
- ご飯をあげたり、着替えさせるなどの日常の監護を細かくメモや日記に残しておく
- 保育園や学校の連絡帳を書いたり、送迎などを積極的に行う
- 休みの日に出かけたり、子供と遊んでいるところを写真に残す
別居時に子供と離れて暮らさない
裁判所が親権者を判断する基準に、「監護継続性の原則」があります。これは、子供の心身の安定のためにも、子供が一方の親のもとで一定期間安定し平穏に生活できているのであれば、その現状を維持すべきであるという原則です。
そのため、父親がそれまで主として子供の監護を担っていたのであれば、別居の際に子供を連れて行った方が親権獲得に有利になります。
一方で、それまでの監護実績が乏しいにもかかわらず、父親が親権欲しさに子供を連れて別居をし、その後子供が父親と平穏に暮らしていたとしても、それまでの主な監護者が母親と認められる場合には、子連れの別居が親権獲得に有利になるとは限りません。また、別居時に子供を連れて出たときの状況によっては違法な連れ去りと認定され、親権獲得に不利になる可能性もあるため注意が必要です。
子供を連れて別居しようと考えている場合には、一度弁護士に相談しましょう。
また、今まで主に監護を担ってきた母親が子供を連れて別居した場合には、親権獲得にあたり、圧倒的に母親が有利になります。早めに何らかの法的措置を取る必要があるため、早急に弁護士に相談してください。
周囲からの子育てサポート体制を整える
子供が病気になったなど、緊急で子供の世話をしなければならない事態が生じたとき、父親が仕事をどうしても休めない場合に、父親の代わりに子供の面倒をみたり、家事を手伝ってくれる存在がいるかどうかも親権者を判断する際の大きなポイントとなります。
両親や兄弟姉妹など複数名による手厚いサポートを受けられる状態であれば、親権獲得の可能性が高まるでしょう。
しかし、協力者と子供の関係が良好でない場合は、プラス要素にはなりません。あくまでも子供につらい思いや寂しい思いをさせないことが大切です。
学童期まで離婚しない
裁判所が親権者を判断する要素のひとつに「母性優先の原則」があります。特に乳幼児期の子供の場合、母親が主たる監護者であった場合には余程のことがない限り母親に親権が渡るでしょう。
そのため、少なくとも母性優先の原則が薄まる5歳を過ぎるまでは離婚を待った方が良いでしょう。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
父親が親権を勝ち取ることができた事例
弁護士法人ALGによる、父親が親権を勝ち取ることができた事例をご紹介します。
父親側が子供二人の親権を離婚調停で勝ち取った事例
(事案の概要)
相手方(母親)が子供を依頼者(父親)の両親に預け、友人と旅行と称して出かけていくことがあり、依頼者は不審に思い探偵に依頼したところ、相手方の不貞が発覚しました。
依頼者は離婚を決意し、子供の親権獲得を目指し、当事務所に依頼されました。
(担当弁護士の活動)
担当弁護士は、子供を監護養育する体制をしっかり構築することをアドバイスしました。依頼者が相手方の不貞を踏まえて話を進めていくと、相手方が自宅から出て別居することになりました。
また、別居後に相手方は不貞相手と同居していることも判明しました。
(結果)
これらを踏まえて離婚交渉を一気に推し進めることとし、粘り強く交渉した結果、相手方は親権を諦め依頼者が2人の子供の親権を獲得しました。
父親を親権者とする協議離婚が約3ヶ月という比較的短期間で成立した事例
(事案の概要)
相手方(母親)の精神疾患を原因として夫婦仲が悪化するとともに、相手方は入退院を繰り返しており、依頼者(父親)が仕事と家事・育児を両立させていました。夫婦関係の悪化により当事者間で離婚の意思が固まり、依頼者は2人の子供について親権獲得を希望され、当事務所にご依頼いただきました。
(担当弁護士の活動)
当初相手方は、両親の協力のもと親権を主張していました。担当弁護士は、現状の依頼者による監護や子供たちの生活環境について何ら問題はなく、変化すべきでないことを主張しました。
また、依頼者が親権者となった場合は面会交流を充実させることや、養育費は請求しないことなどの条件を提示しました。
(結果)
相手方と交渉を重ねた結果、依頼者が2人の親権者となることや面会交流を充実したものとすることで合意に至りました。
父親の親権についてよくある質問
父親が親権を獲得した場合、母親に養育費を請求できますか?
父親が親権者となり子供と一緒に暮らす場合は、非親権者である母親に養育費を請求することができます。
養育費とは、子供を監護・養育するために必要な費用です。離婚によって夫婦は他人同士に戻りますが、親と子供の縁が切れることはありません。そのため、離婚後に子供と離れて暮らす親であっても、当然に子供の扶養義務は継続します。
養育費の金額は当事者間の話し合いで自由に決めることができますが、揉めてしまう場合は裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にするのが一般的です。
養育費については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚後、父親から母親へ親権者を変更することはできますか?
一度決めた親権者を親の勝手な都合や気持ちで変更することは望ましくないでしょう。親権者を父親と母親どちらに指定するかは子供の人生にかかわる重大な事項であるため、親の話し合いだけで変更することは出来ません。
しかし、子供が親権者である父親から育児放棄や虐待を受けていたり、子供が親権者を母親に変えてほしいと望んでいるような場合は、調停の手続きによって親権者の変更が認められる可能性があります。
離婚後の親権者変更については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
親権が獲得できなくても子供に会うことはできますか?
親権が獲得できなくても、子供と離れて暮らす親は子供と定期的に面会したり、電話や手紙のやり取りをしたり、様々な方法で子供と交流することができます(面会交流)。
面会交流は子供が両親のどちらからも愛されていると実感し、健やかな成長のために必要な機会です。親権者の「会わせたくない」という思いだけで、面会交流を拒否することは基本的にはできません。
もし、親権で争っているような場合は、面会交流を充実させることを条件に親権を譲るという方法もあります。子供と接する機会が多くなれば、子供の成長を見守り、支えていることを実感できるでしょう。
面会交流について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
合わせて読みたい関連記事
母親が子供を連れて別居した場合でも父親が親権者になることはできますか?
以下のような子連れ別居の場合には、母親の親権獲得が不利になる可能性があります。
- 別居前の主たる監護者が父親であるのに、母親が親権獲得の目的で子供を連れて別居した
- 子供が今の生活を変えたくないといっているのに無理やり連れだした
- 子供が意思をはっきりと示せる年齢であるのに、子供の意思を確認せずに家を出た
これらの場合は、子供の意思に反して生活環境を急激に変えてしまうことから、子供の福祉に背いていると考えられるからです。
上記のような事情があれば、父親が親権者になれる可能性があります。
但し、子供が父親と離れていても、母親と安定した生活を送っている状態が一定期間続けば、監護継続の原則から、母親に有利になってしまいます。
そのため、母親が子連れ別居をした場合には、早急に弁護士に依頼し、速やかに「子の引渡しの審判・審判前の保全処分」を行いましょう。
父親が親権を獲得するためには仕事や働き方を変える必要がありますか?
例えば、仕事が激務で平日の帰りは遅く、また休日も仕事に追われているような場合には、働き方や仕事を変えることも検討すべきでしょう。
父親が親権を獲得する際に大切なのは、「現在の監護状況」と「今後の監護状況」です。父親の仕事が激務で子供とコミュニケ―ションをとる機会がない状況では、親権を獲得することは難しいでしょう。子供と関わる時間のない状態で親権者となってしまえば、子供はつらく寂しい思いをしてしまい、子供の福祉を守っているとはいえないからです。
父親が親権を獲得するためには、仕事や働き方を変えてでも子供と一緒に過ごす時間を作ることが重要です。
父親が親権を獲得したい場合、まずは弁護士にご相談ください!
日本では、現在単独親権制度となっており、親権獲得は母親に有利とされるのが実情です。しかし、父親だからといって親権を諦める必要はありません。
父親の親権については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。私たちは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。夫婦や子供の状況などご相談者様のお話を丁寧にヒアリングし、親権を獲得できるよう尽力いたします。
父親の親権についてお悩みの場合は、おひとりで悩まず私たちにご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)