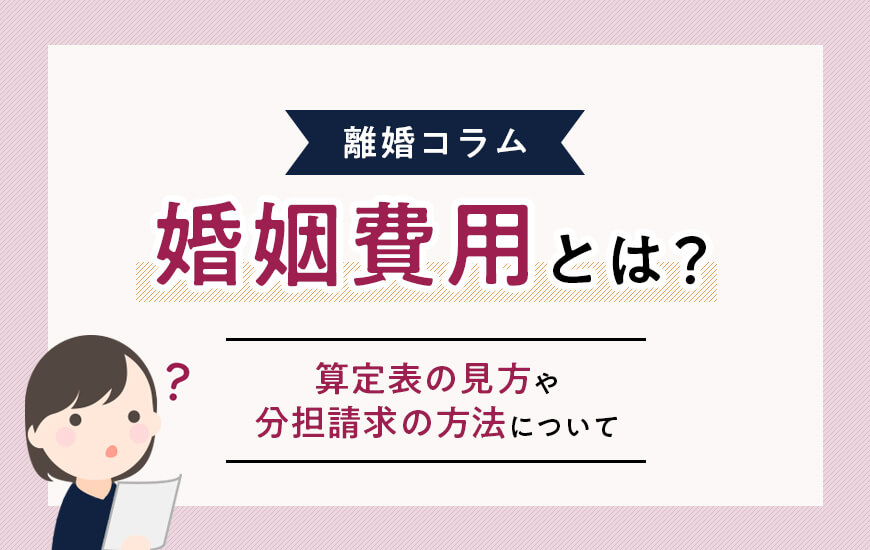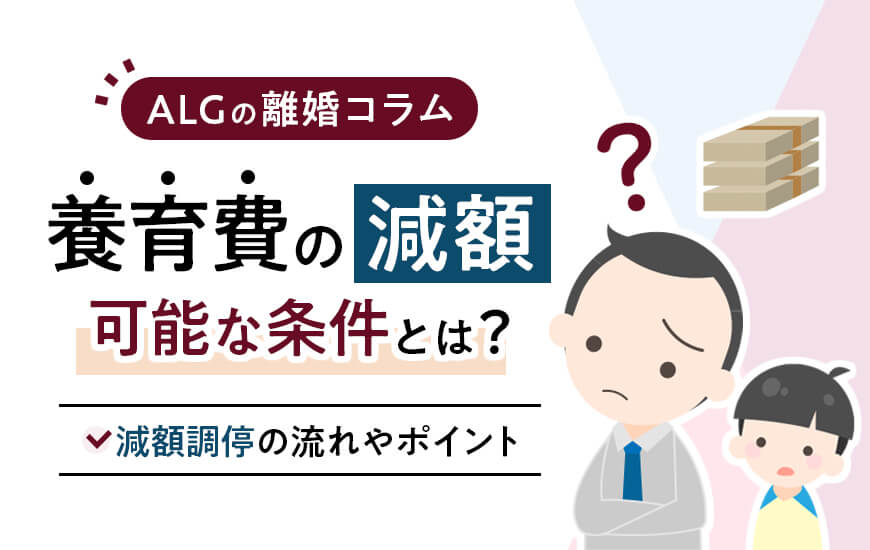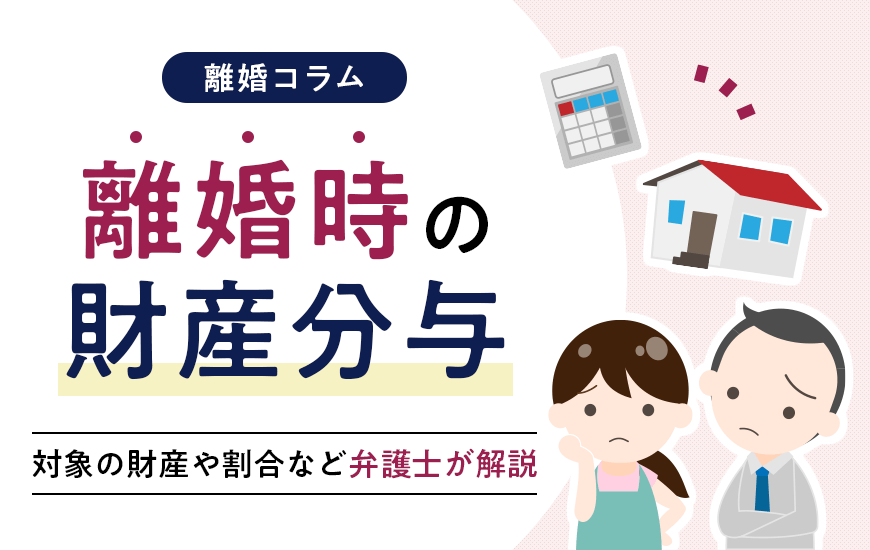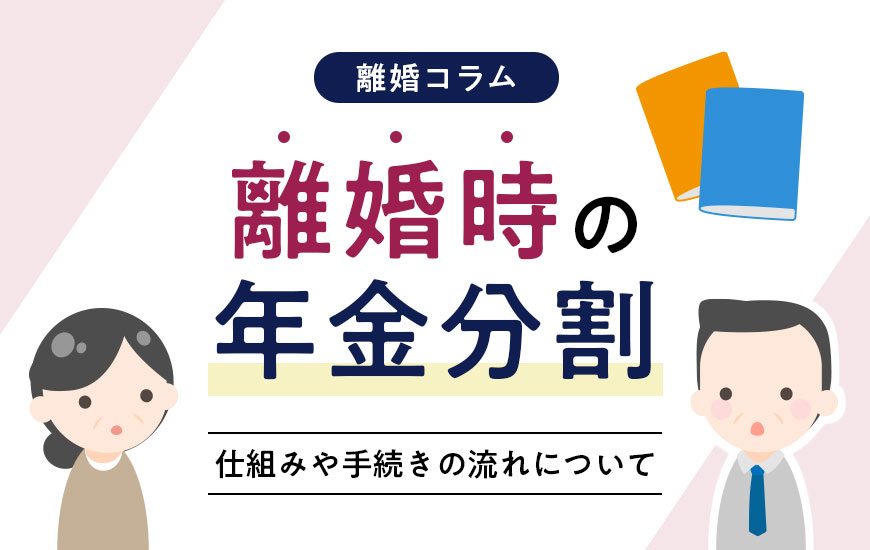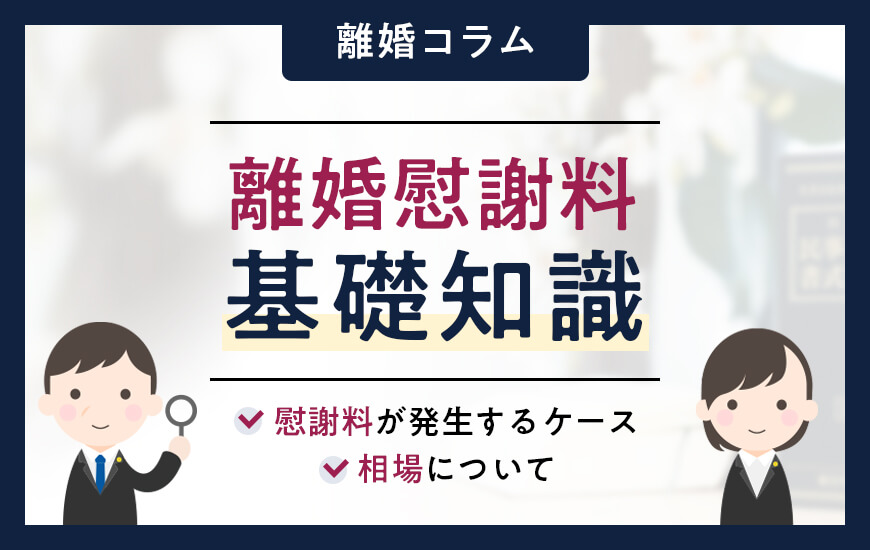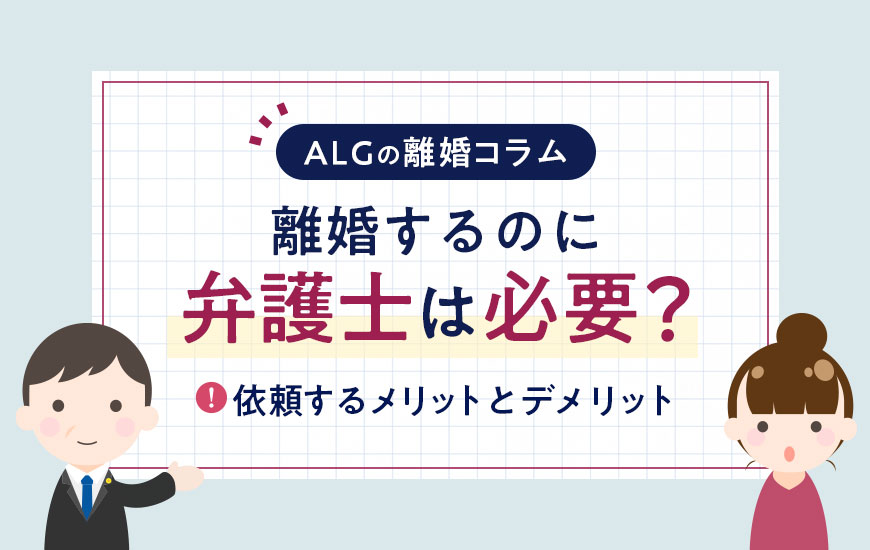離婚貧乏に注意!原因や後悔しないために知っておくべきこと
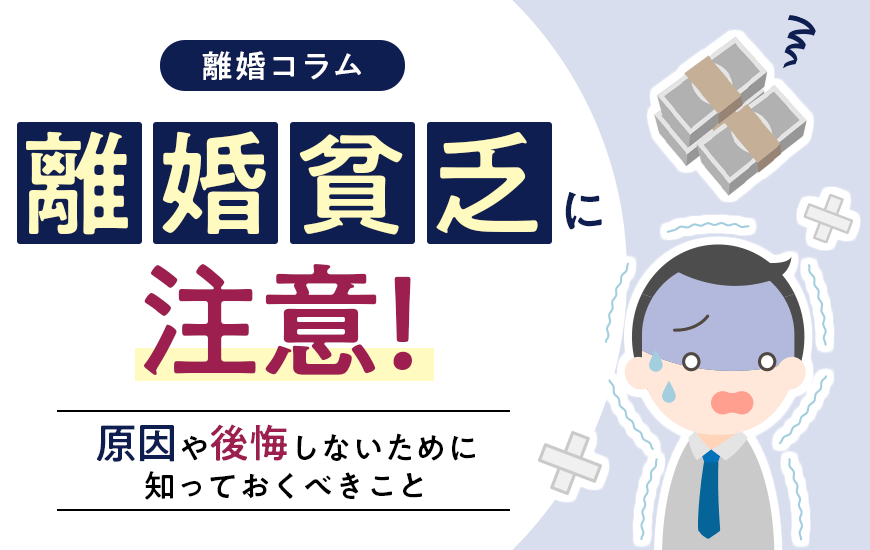
離婚して心機一転!幸せな人生を再スタートする人がいる一方で、離婚貧乏になってしまい、経済的な問題でお悩みの方も少なくありません。
離婚貧乏はその名のとおり、離婚によって貧困に陥ってしまうことを意味します。
離婚は経済的にも大きな影響をもたらすことから、離婚貧乏にならないように注意が必要です。
本記事では【離婚貧乏】に着目して、なぜ離婚貧乏に陥ってしまうのか、経済的な理由で離婚を後悔しないためにはどうすればよいのかを解説していきます。
お金が心配で離婚に踏み切れない方、離婚後の経済的な問題でお困りの方の参考になれば幸いです。
離婚貧乏とは
離婚貧乏とは、離婚によって貧困などの経済的な問題を抱えてしまうことをいいます。
離婚は経済的にも大きな影響をもたらします。
ところが、離婚にまつわるお金を把握していない、相場を知らないなどの知識不足によって離婚貧乏になってしまう方が少なくありません。
例えば次のようなケースです。
- 離婚調停や離婚裁判に必要な費用を把握していなくて、思わぬ出費となった
- 別居するにあたり、引っ越し費用が高額になってしまった
- 離婚時に財産分与や年金分割を請求できると知らずに損をした
- 養育費や慰謝料の相場を知らずに、不利な条件で合意してしまった など
離婚貧乏は、男性と女性とで特有の原因がみられるため、次項で詳しく解説していきます。
男性が離婚貧乏になる理由
男性が離婚貧乏になる主な理由は4つです。
- 離婚前の婚姻費用の支払い
- 養育費の支払い
- 財産分与
- 年金分割
男性の場合、養育費や年金分割などの離婚後のお金を支払う側になることが多く、経済面の負担が大きくなって離婚貧乏になる傾向にあります。
以下、詳しくみていきましょう。
離婚前の婚姻費用の支払い
離婚前の婚姻費用の支払いが負担となって、男性が離婚貧乏になることがあります。
◆婚姻費用とは?
婚姻費用とは、夫婦や子供の生活費のことで、衣食住の費用、教育費、医療費などが含まれます。
夫婦は法律上、互いの資産や収入に応じて婚姻費用を分担する義務を負っているので、離婚しない限り、収入の少ない側から収入の多い側へ婚姻費用を請求できます。
夫婦が別居すると生活費が二重に発生することになります。
多くの場合、収入が多い男性から婚姻費用を支払うことになるため、離婚貧乏になる男性が少なくありません。
離婚までの別居期間が長くなるほど男性が離婚貧乏になる可能性が高くなるため、離婚を検討されている方は早めに弁護士に相談し、準備することをおすすめします。
詳しくは以下ページより「婚姻費用分担請求を弁護士へ相談するメリット」をご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
養育費の支払い
男性が離婚貧乏になる理由で最も多いのが、養育費の支払いです。
◆養育費とは?
養育費とは、社会的・経済的に自立していない子供を監護・教育するために必要な費用のことです。
夫婦が離婚しても子供を扶養する義務は続くため、離婚後に子供と一緒に暮らして世話をする監護親から、子供と離れて暮らす非監護親へ養育費を請求できます。
離婚後、母親が親権を獲得し、父親が養育費を支払うケースが多いです。
ご自身の収入に見合わない高額な養育費を支払うことによって、自分自身の生活が困窮してしまう男性が少なくありません。
養育費の相場を知らず、高額な養育費を支払うことになってしまった場合には、養育費減額の交渉を検討しましょう。
詳しくは以下ページより「一度決めた養育費の減額」をご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
財産分与
離婚時の財産分与によって、男性が離婚貧乏になるケースもあります。
◆財産分与とは?
財産分与とは、離婚の際に夫婦の財産を貢献度に応じて公平に分け合うことをいいます。
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して築いた預貯金・不動産・車・家財道具・住宅ローンなどの共有財産で、将来支払われることが確実な退職金も含まれます。
男性の場合、次のようなケースで離婚貧乏になる方が少なくありません。
- 相手に有利な条件で財産分与することになった
- 離婚後も住宅ローンを返済することになった
- 将来もらえる退職金が減ってしまった など
退職金については老後に生活困窮者となる可能性が高く、財産分与について正しい知識をつけておくことが重要です。
詳しくは以下ページより「財産分与の対象となる財産」をご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
年金分割
離婚時の年金分割によって、男性が離婚貧乏となるケースがあります。
◆年金分割とは?
年金分割とは、夫婦が婚姻中に納めた厚生年金部分の記録を離婚時に分け合って、それぞれが将来受け取る年金額を調整することをいいます。
年金は老後の大切な収入源ですが、多くは男性が納めた年金記録を分け合うことになるため、受け取れるはずだった年金額が減ってしまって老後に生活困窮者となる可能性があります。
女性が離婚貧乏になる理由
女性が離婚貧乏になる主な理由は4つです。
- 再就職の難しさ
- 低収入
- 養育費の未払い・不足
- 年金分割
女性の場合、離婚後の収入と支出に変化が生じたり、養育費が未払いとなったりして離婚貧乏になる傾向にあります。
以下、詳しくみていきましょう。
再就職の難しさ
女性の場合、再就職の難しさから離婚貧乏になるケースがあります。
結婚や出産をきっかけに仕事を辞める女性も少なくありません。
離婚後の生活を安定させるには、女性が働いてしっかり収入を得る必要があります。
ですが、結婚や出産をきっかけに仕事を辞めた女性の場合、一度キャリアが途絶えてしまうと再就職が難しくなります。
とくに、離職からブランクが長くなる熟年離婚の場合、職務経歴やスキルが不足しているなどの理由で再就職に苦労する傾向にあります。
低収入
離婚後の低収入が原因で、離婚貧乏になる女性も少なくありません。
女性の場合、次のような理由から貧困につながるケースが多いです。
- ブランクがあって再就職が難航し、十分な収入を得られる仕事先がみつからなかった
- ひとりで小さな子供を育てていて、やむなく時間の融通がききやすい非正規雇用で働いている
- 正規雇用ではあるものの、子供がいて長時間勤務ができなくて収入が下がった など
とくに、離婚後女性がひとりで小さな子供を育てるケースで、思うように働けず低収入になってしまう傾向にあります。
養育費の未払い・不足
女性が子供の親権を獲得した場合に、養育費を支払ってもらえずに離婚貧乏になるケースが多いです。
幼稚園から大学卒業までにかかる教育費は、子供ひとりあたり1000万円以上必要といわれています。
これは国公立に通った場合の平均で、私立に通った場合には2500万円以上必要になります。
こうした教育費を含めた養育費の支払いについて、離婚時に取り決めていなかったり、取り決めた養育費が支払われなかったりすると、女性ひとりが養育費を負担しなければならず貧困に陥ってしまうケースが後を絶ちません。
養育費が支払われない場合には、当事者で話し合ったり調停などの法的手続きを利用したりして、しっかり相手に請求しましょう。
詳しくは以下ページより「養育費の支払いがなかった場合」をご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
年金分割
年金分割が思わぬ落とし穴となって、離婚貧乏になる女性も少なくありません。
年金分割できるのは、婚姻期間中に納めた厚生年金の記録部分だけです。
厚生年金に加入していない自営業者はそもそも年金分割の対象外ですし、結婚前や離婚後に納めた部分は年金分割の対象に含まれません。
そのため、老後の生活費としては心もとない金額しか受け取れないケースがほとんどです。
「年金分割で夫の年金を半分もらえるから離婚しても老後は安泰」と単純に考えしまうと、老後に生活困窮者となりかねませんので、あらかじめ年金分割について正しい知識をつけておくことが大切です。
詳しくは以下ページより「離婚する際の年金分割」をご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
離婚貧乏で後悔しないための注意点
離婚貧乏で後悔しないための注意点は次の3つです。
- 離婚後の生活を予測する
- 離婚条件の話し合いに妥協しない
- 受け取れる手当等の手続きはもれなく行う
離婚すべきか悩んだときや、相手と離婚について話し合うときに意識すべきポイントでもあるので、それぞれの注意点を次項で詳しく解説していきます。
①離婚後の生活を予測する
相手に離婚を切り出す前に、まずは離婚後の生活をシミュレーションして、離婚した後の生活でどのようなお金がどのくらい必要になるのかを洗い出しておきましょう。
具体的には、
- 離婚後の収入はどうなるか、どうやって生計を立てていくか
- 離婚後に引っ越す場合、どのくらい費用がかかるか
- 離婚後の衣食住にかかる費用はどのくらいか
- 子供の養育費にどのくらいお金が必要か
といったことをイメージして、離婚後に必要になるお金を工面する方法を含めて長期的な計画を立てておきましょう。
②離婚条件の話し合いに妥協しない
離婚について相手と話し合うとき、離婚条件についても話し合って取り決めておきましょう。
このとき、安易に離婚条件を妥協しないことが大切です。
「はやく離婚したい」と焦って離婚条件を後回しにすると、離婚後相手が話し合いに応じてくれない可能性もあるので、離婚前にしっかり話し合い、合意できた内容は離婚協議書などの書面にまとめておくと安心です。
| お金のこと |
|
|---|---|
| 子供のこと |
|
このほか、離婚原因が配偶者の不倫やDV・モラハラなどの不法行為にある場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料を請求する際は、相場を把握しておき、安易に妥協しないようにしましょう。
詳しくは以下ページより「離婚慰謝料の相場・請求できる条件」をご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚条件の相談は弁護士へ
離婚条件について悩んだり、夫や妻と話し合いが難航してお困りの場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
離婚問題に詳しい弁護士に相談すると、次のようなメリットがあります。
- 相手が無理な要求をしてきても適正な条件で離婚できるようにサポートしてくれる
- 離婚協議書や公正証書の作成もサポートしてもらえる
- 相手との話し合いを任せることもできる など
弁護士費用が心配な場合は、弁護士の無料相談や法テラスなどを利用して経済的な負担を軽くする方法もあります。
以下ページで「離婚問題で弁護士に依頼する必要性やメリット」について詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
③受け取れる手当等の手続きはもれなく行う
ひとり親家庭では、行政から手当が支給されたり、税の免除・控除が受けられたり、さまざまな経済的支援の制度を利用することができます。
これらは申請しないと支援が受けられないため、受け取れる手当等の手続きはもれなく行いましょう。
ひとり親家庭が利用できる支援の一例
- 児童手当
- 児童育成手当
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当、障がい児童福祉手当
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
- 税金の控除
児童手当
児童手当とは、子育て世代を経済的に支援するための国による制度です。
ひとり親に限らず、支給対象の児童をもつすべての家庭を支援するもので、2024年10月分から児童手当の対象が拡充されました。
| 支給対象者 | 0歳から高校生年代(18歳になって最初の3月31日まで)の児童を養育しているすべての方 |
|---|---|
| 支給額 (2024年10月~) |
年6回(偶数月)、次のとおり支給されます
|
※児童手当は申請者の所得にかかわらず全額支給されます
児童育成手当
児童育成手当とは、ひとり親家庭などの児童の健やかな成長に資することを目的とした、東京都独自の給付金制度です。
児童育成手当は“育成手当”と“障害手当”に区分され、支給要件や所得制限などの条件を満たせば両方の手当が支給されます。
| 支給対象者 | 条件のいずれかに該当する、0歳から高校生年代(18歳になって最初の3月31日まで)の児童を養育している方
|
|---|---|
| 支給額 | 年3回(6・10・2月)、次のとおり支給されます
|
| 支給対象者 | 条件のいずれかに該当する、20歳未満の心身に障がいのある児童を養育している方
|
|---|---|
| 支給額 | 年3回(6・10・2月)、次のとおり支給されます
|
児童扶養手当
児童扶養手当とは、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するための国の制度です。
所得と児童の人数に応じて支給額が異なります。
2024年11月から制度が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
| 支給対象者 | 0歳から高校生年代(18歳になって最初の3月31日まで)の児童を養育している方 ※心身に障がいのある児童の場合は20歳未満 |
|---|---|
| 支給額 (2024年4月~) |
年6回(奇数月)、次のとおり支給されます 【児童1人目の月額】
|
特別児童扶養手当、障がい児童福祉手当
離婚後、心身に障がいのある子供を育てる場合には、特別児童扶養手当や障がい児童福祉手当といった制度が利用できる可能性があります。
それぞれ支給要件や所得制限がありますが、条件を満たせば経済的な負担を減らすことができます。
| 支給対象者 | 20歳未満の心身に障がいのある児童を養育している方 |
|---|---|
| 支給額 (2024年4月~) |
年3回(4・8・12月)、次のとおり支給されます
|
| 支給対象者 | 20歳未満の心身に重度の障がいのある児童 |
|---|---|
| 支給額 (2024年4月~) |
年4回(2・5・8・11月)、次のとおり支給されます
|
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度とは、ひとり親家庭や寡婦の方の経済的自立をはかるために、生活費や、引っ越し・進学・就職などに必要な資金を貸し付けてくれる制度です。
所得制限があるので、利用できるかは事前に確認が必要です。
| 対象者 |
|
|---|---|
| 貸付金の種類 | 生活資金、住宅資金、就学支度資金など、計12種類 |
| 利子 | 貸付金の種類や連帯保証人の有無によって異なるが 無利子、または年利1.0% |
| 償還方法 | 貸付金の種類によって異なるが 一定の据え置き期間の後、3~20年 |
税金の控除
離婚後の経済的な負担を軽減するために、税金が控除される制度を利用できる場合があります。
具体的な制度の内容は次のとおりですが、自治体によって利用できる制度や条件が異なる可能性があるので、事前に確認することをおすすめします。
- ひとり親控除
(性別や結婚歴を問わずひとり親である場合に、所得税・住民税の控除が受けられる) - 寡婦控除
(結婚歴のある独身女性に扶養親族がいる場合に、所得税・住民税の控除が受けられる) - 国民健康保険や国民年金の減免制度
このほかにも、医療費の一部を自治体が助成してくれる医療費助成制度や、行政から手当を受けている場合に適用される上下水道料金の基本料金免除、JR定期券の割引、保育料の免除・減額などを利用することで、支出を減らせる可能性があります。
離婚後の経済的不安がある方は、弁護士法人ALGへご相談ください
離婚したい気持ちが強くても、離婚後のお金の問題を解決しなければ離婚貧乏となる可能性があります。
離婚後の経済的不安がある方は、早めに弁護士法人ALGまでご相談ください。
私たちはこれまでに数々の離婚問題に取り組んできました。
離婚後の生活が不安で離婚に踏み切れない方、取り決めた約束が守られずにお困りの方、離婚後に離婚条件について話し合いたい方、それぞれのお悩みに対して、弁護士が経験と知識を活かして離婚後の経済的な不安が軽減できるように全力でサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)