【基礎知識】面会交流|決め方・決めておくべきルール・拒否について
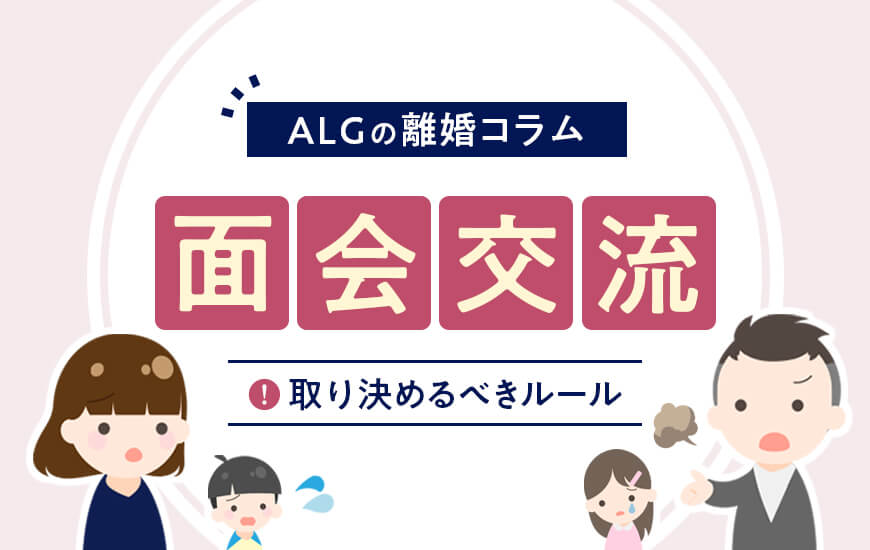
離婚や別居を検討中の方の中には、子供と離れることに不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、離婚や別居によって子供と離れて暮らすことになっても、子供と交流を持つ面会交流を行うことができます。
離れて暮らしても親子であることに変わりはなく、お互いに会いたいと思うのは自然なことであり、面会交流は子供の福祉の観点からも必要だと考えられています。
この記事では、面会交流とはなにか、面会交流の決め方や決めておくべきルールなどについて詳しく解説していきます。ぜひご参考ください。
目次
面会交流とは
面会交流とは、離婚や別居などで子供と離れて暮らす親が、子供と定期的に交流を持つことをいいます。
交流の方法は面会といった直接的な方法に限らず、手紙のやり取りなど間接的な方法もあります。
面会交流は、子供が両親のどちらからも愛されていると実感ができ、健やかな成長のために必要な機会です。
また、改正民法でも、離婚時には子供との面会についても協議するよう文言が追加されています(改正民法766条)。このことからも、面会交流が子供や離れて暮らす親にとってどれほど重要かが分かります。
面会交流の決め方
面会交流については、通常、以下のような流れで話し合われます。
- 夫婦間の協議
面会交流をするかしないか、その内容等の詳細は、夫婦で話し合って自由に決めることができます。
夫婦間で合意して取り決めた内容は、後に「言った・言わない」の争いになることを避けるためにも、通常、「合意書」や「公正証書」の形でまとめられます。 - 面会交流調停
夫婦間の協議で面会交流について合意できなければ、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てします。
面会交流調停では、裁判官や調停委員を交えて、面会交流の可否、方法、回数など具体的に話し合いをして合意を目指します。 - 面会交流審判
面会交流調停でも合意できなかった場合は、調停は不成立となり、審判手続きに移行します。
審判では、これまでの一切の事情を考慮して、裁判官が面会交流の実施の可否や内容などを判断します。
話し合いを始めるタイミング
面会交流について話し合いを始めるタイミングに、特段決まりはありません。
親権者については、離婚前に必ず定めなければ離婚届を受理してもらえませんが、面会交流については、離婚前に定めておかなくても離婚は成立しますので、離婚前に決めておいてもいいですし、離婚後に決めても問題ありません。
仮に離婚前に面会交流について話し合いをして取り決めておくと、離婚後、子供と離れて暮らすようになってからスムーズに面会交流を実現できる可能性は高いでしょう。
特に夫婦関係が悪化したまま離婚をした場合は、離婚後、面会交流を希望しても、子供と一緒に暮らす親と話し合いがうまく進められず、面会交流が実現しない事態に陥りかねません。
したがって、離婚する際に面会交流の話し合いをしっかり行っておくことをおすすめします。
面会交流調停・審判
夫婦間の話し合いで面会交流について合意できなかった場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。調停では、裁判官や調停委員を交えて、お互いの希望や意見を伝えて、助言を受けながら、面会交流の実施の可否や内容、回数などを話し合って調整します。
面会交流調停でも合意できなかった場合は、調停は不成立となり、審判手続きに移行します。
審判では、これまでのそれぞれの主張や提出した資料などを考慮して、裁判所が面会交流について判断をします。
判断するにあたって参考にするために、家庭裁判所調査官による調査や、試行的面会交流が実施される場合もあります。
申し立てに必要な費用と書類
面会交流調停の申し立てに必要な費用や書類等は、以下のとおりです。
- 収入印紙(未成年の子供1人につき1200円)
- 郵便切手(概ね1000円分前後。裁判所により異なる。)
- 申立書及びその写し 各1通
- 未成年の子供の戸籍謄本
なお、上記は標準的な必要書類であり、裁判所や係争内容によっては、追加資料の提出が求められる可能性があります。
家庭裁判所調査官による調査
面会交流調停では、家庭裁判所調査官という人達によって夫婦や子供の様子について調査が行われることがあります。調査官は、法律学、心理学、行動科学、教育学等の幅広い専門的知識をもとに、家事事件や少年事件の問題解決を図るための様々な調査を行う裁判所の職員です。
面会交流調停においては、調査官によって、以下のような調査が行われます。調査官からの調査結果は、調停や審判の内容に大きく影響します。
- 夫婦双方との面談
- 子供との面談
- 試行的面会交流(裁判所内で行われる、お試しの面会交流)への立会い
試行的面会交流とは
試行的面会交流とは、家庭裁判所調査官が立ち合うなかで、子供と離れて暮らす親と子供の面会交流を試験的に行い、面会交流をすることが子供の福祉にとって本当に望ましいのかどうかを見極める目的で実施されます。
面会交流は家庭裁判所内にある児童室で行われます。
児童室には、おもちゃやぬいぐるみなどの遊び道具や絵本が置かれています。
児童室の様子は、マジックミラー越しに観察できるようになっており、児童室に設置しているビデオカメラからもモニター室で観察できるようになっています。
その後、家庭裁判所調査官が面会交流中の親子の様子を観察・記録して、調査報告書にまとめます。
調査報告書の内容は、今後の面会交流の内容を定めるにあたって重要な判断材料となります。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
面会交流は基本的に拒否できない
面会交流は、子供と一緒に暮らす親の一方的な感情や都合だけでは、基本的には拒否することはできません。
しかし、面会交流を拒否することについて正当な理由がある場合は、例外的に、面会交流を控えるべきだと判断されるケースもあります。
では、具体的に、どのような状況で面会交流の拒否が認められるのでしょうか。次の項でみていきましょう。
面会交流をしない方がいいケース
面会交流は、子供の健やかな成長のために欠かせない機会ですが、子供の福祉(幸せ)に反する場合には、面会交流をしない方がよい場合もあります。
面会交流をしない方がいいケース
- 子供が本心から「会いたくない」と言っている
- 子供にDVをするおそれがある
- アルコール依存症や精神疾患などがある
- ギャンブルを行う場所や居酒屋などに子供を連れていく可能性がある
- 子供を連れ去る危険性がある
- 子供と暮らす親の悪口を吹き込み、子供を洗脳するおそれがある など
このように、面会交流をすることで、かえって子供がつらい思いをする可能性がある場合には、面会交流を制限・禁止するなど、慎重な判断が必要です。
拒否された場合の対処法
調停や審判を経て面会交流の内容が決められたにもかかわらず、面会交流を拒否されてしまったときの手段は、以下の2つが考えられます。
- 履行勧告の申し立て
裁判所から、子供と同居の親に対し、書面や電話で「約束通り面会交流をさせなさい」と勧告してもらうことができます。しかし、あくまでも勧告に過ぎず、法的な強制力まではありません。 - 強制執行の申し立て
同居の親が約束通りに面会交流を行わせない場合に、数万円の制裁金を支払わせることによって、自発的に約束を守らせ、面会交流を実現させる手段を、「間接強制」といいます。ただし、間接強制が認められるかどうかは、面会交流のルールの内容や法的な判断によるところが大きく、いかなる場合でも認められるわけではありません。
なお、強制執行のうち、直接強制(同居親の元から子供を強制的に連れ出し、別居の親と会わせる方法)は、子供の福祉の観点から、認められていません。
面会交流の決めておくべきルール・内容
いざ面会交流を実施する際に揉めないように、例として次のようなルールを取り決めておくと良いでしょう。
- 面会交流の頻度や時間
- 面会交流の場所
- 子供の受け渡し方法
- プレゼントやお小遣いなどの取り決め
- 学校行事への参加について
- 連絡手段
- 祖父母との面会交流
また、ルールを決める際は、次のような禁止事項も併せて取り決めておきましょう。
- 子供に相手の悪口を言わない
- ルールに違反した場合の取り決め
では、それぞれについて詳しく解説していきます。
面会交流の頻度や時間
「月に何回会うか」「何曜日の何時から何時まで会うか」など、面会交流の頻度や時間を当事者間で決めていきます。
面会交流の頻度が多すぎる、少なすぎることで揉めないよう、お互いが納得できる頻度を取り決めるようにしましょう。
面会交流の平均時間は、子供が乳児の場合は30分~2時間程度、幼児の場合は2~3時間程度、小学生の場合は半日~1日が多いようですが、いずれにしても明確な基準があるわけではありません。子供の年齢や意思によって判断しましょう。
面会交流の場所
面会日当日に子供と過ごす場所については、当事者間で自由に取り決めることができます。
取り決め例
- あらかじめ指定の場所(自宅や公園)だけに限定しておく
- 面会する親子で自由に決める
- 面会日までに別居親が決め、同居親の了承を得る など
なお、父母双方の合意により、「●●には連れて行かないでほしい」など、面会の場所を制限することも可能です。
子供の受け渡し方法
面会日当日は、子供の受け渡し方法についても事前に決めておくようにしましょう。
取り決め例
- どこで、何時に待ち合わせるのか
- 交通手段はどうするのか
- 誰が子供を連れていくのか
- 誰が迎えに行くのか など
約束の場所や時間、送迎方法を守らなければ、お互いに不信感が募り、今後の面会交流が上手くいかなくなることもありますので、取り決めた内容はきちんと守るようにしましょう。
また、夫婦が遠方に住んでおり、待ち合わせ場所まで新幹線や飛行機を使用し、交通費が発生する場合は、どちらが交通費を負担するのかについてもあらかじめ話し合っておきましょう。
プレゼントやお小遣いなどの取り決め
プレゼントやお小遣いについても、あらかじめルールを決めておくと安心です。
取り決め例
- お小遣いを渡す場合は、一度にいくらまで、月にいくらまで
- プレゼントを渡す場合は、誕生日やクリスマスなどのイベントのときのみ
- プレゼントの予算はいくらまで
- お年玉を渡す場合はいくらまで など
面会交流が行われるたびに高価なプレゼントを与えたり、高額なお小遣いを渡したりすると、子供は「父(母)に会うとなんでも買ってもらえてお小遣いがもらえる」と考えるようになり、トラブルに発展しかねません。
子供の健全な成長のためにも、親同士で事前にルールを決めておくことが大切です。
学校行事への参加について
入学式、卒業式、運動会などの学校行事や習い事の発表会への参加の可否などについても、当日いきなり参加して揉めるといったことのないよう、事前に決めておきましょう。
なお、通常、学校行事等では、親は子供の様子を遠くから見守っているだけであり、直接触れ合ったり、話したりして「交流」する時間はあまりありません。そのため、一般的には、これらの学校行事等への参加日は、「面会交流日」の日数にはカウントされないと考えられています。
連絡手段
普段や緊急時の連絡方法についても、夫婦であらかじめ決めておいた方が良いでしょう。お互いが了承すれば、電話、メール、LINEなど手段は何でも構いません。
しかし、ある程度子供が大きくなったからといって、同居の親の了承なく、勝手に子供と電話やメール、LINEなどで直接連絡を取り合ったり、SNSでつながったり、勝手に携帯電話を買い与えたりする行為は、同居の親からの不信感を買いトラブルになりかねないため、控えましょう。
祖父母との面会交流
「孫に会いたい」「おじいちゃん、おばあちゃんに会いたい」という気持ちは、子供と祖父母にとって当然の感情でしょう。
祖父母と孫が会うことについて、お互いに身体的・精神的な負担や不利益がなく、また、同居の親が認めるならば、取り決めたルールの範囲内で面会交流を行うことが可能です。
また、令和6年の民法改正により、家庭裁判所は、祖父母であっても、子供の利益のため特に必要があると認めるときには、子との面会交流の実施を定めることができるようになりました。
子供に相手の悪口を言わない
お互いに、子供に対し、相手の悪口を言わないことをルールとして定めておきましょう。
親からもう一方の親の悪口を聞かされることは、子供にとって非常に大きなストレスとなります。
面会交流自体を楽しめなくなることはもちろん、ときには自分自身の存在を否定されたような気持ちになったり、片方の親に対する激しい拒否反応を示したり、攻撃的になったりするケースもあります。
子供に悪口を聞かせることは、程度によっては心理的虐待と判断される可能性もあるほど、子供の福祉・健全な心身の成長にとって非常に有害な行為であり、お互いに控えるべきです。
ルールを違反した場合の取り決め
相手が面会交流の約束を守らなかったときに備え、「もしルールを破ったら一定期間面会交流を中止する」「回数を2ヶ月に1回に制限する」など、あらかじめルール違反時のときの取り決めを定めておくことも可能です。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
面会交流に関するよくある質問
面会交流のルールは後からでも変更することはできますか?
面会交流のルールを後から変更することは可能です。
面会交流の頻度や方法などは、お互いの生活環境の変化や子供の心身の成長に伴い、適宜見直していくことが子供のためになることもあります。
子供がある程度の年齢(概ね15歳以上)まで成長すれば、子供の意見も大いに尊重されるべきでしょう。
面会交流のルールを変更したい場合は、当事者の話し合いで解決できる場合は当事者間で解決して構いません。
当事者間での話し合いが難しい場合は、裁判所の手続き(面会交流調停または審判)を利用することにより、裁判所を交えて話し合うことが可能です。
子供が面会交流を拒否した場合は実施しなくてもいいですか?
子供の年齢によって、対応策は変わります。
具体的には、子供が未就学児の場合、子供が面会交流を嫌がるのは感情の起伏による一時的なものであったり、子供と一緒に住む親の顔色をうかがったりしている可能性があります。
実際に調停や審判など裁判所の手続きでは、子供と離れて暮らす親が不適切な行為をしていない限り、子供が嫌がっているとしても、面会交流を実施する方向で判断する傾向にあります。
一方で、子供の年齢が15歳以上であれば、面会交流に関して子供の意見を重視しますので、子供自身が面会交流を嫌がっているのであれば、実施しなくても問題ないでしょう。
なお、状況によっては10歳前後から子供の意思が反映される場合もあります。
面会交流調停を欠席するとどうなりますか?
仕事の都合や体調不良など、やむを得ない事情で調停を欠席する場合は、事前に裁判所に連絡をすることで期日を変更してもらうことができます。
一方、正当な理由なく欠席を繰り返すと、調停委員から「この人は自分の子供のことを誠実に話し合う気がない」といったマイナスの心証を持たれてしまい、調停が不利に進んでしまうでしょう。
また、正当な理由なく無断欠席を続けた場合は、そもそも話し合いが不可能と判断され、調停は不成立となります。
その後、審判に移行し、裁判官から最終的な判決が出されますが、審判の内容には無断欠席をした方の意向は反映してもらえないことが多く、注意が必要です。
母親(親権者)が面会交流に同伴することは許されますか?
面会交流の内容やルールは、基本的に父母間で自由に取り決めることができます。
そのため、子供と離れて暮らす父親と親権者である母親の間で合意できれば、母親が面会交流に同伴することができます。
特に、子供が幼い場合は、親権者である母親が同伴することで子供が安心して面会交流を行えるでしょう。
また、父親が母親の面会交流の同伴を拒否したい場合は、父母間で話し合うか、面会交流調停を申し立てる方法がありますが、どちらにせよ大切なのは、子供の成長と状況に応じて柔軟に判断することです。
養育費を支払わない相手との面会交流は拒否してもいいですか?
結論から言うと、相手が養育費を支払わないことは、面会交流を拒否できる正当な理由にはなりません。
腑に落ちないかもしれませんが、養育費を支払わない相手に対しても、面会交流をさせるべきだと判断される可能性が高いです。
面会交流と養育費は全く別の制度であり、「養育費を払わないなら子供に会わせない」という交換条件にすることは、基本的には認められません。
また、面会交流は子供の利益のために行われるものであり、たとえ養育費を払わない親であっても、会うことが子供にとって有害でない限り、子供のためにも面会交流は実施すべきだと判断される可能性が高いです。
養育費を支払わない相手に対しては、別途、養育費請求調停(審判)の申し立てや強制執行の申し立てにより解決することを選択肢に入れましょう。
再婚した場合の面会交流はどうなりますか?
基本的に、再婚をしたからといって元配偶者と子供の面会交流をとりやめることはできません。
面会交流は、子供や子供と離れて暮らす親の権利です。
たとえ以下のようなケースでも、非親権者が子供の実親であることに変わりはなく、面会交流の権利がなくなることもありません。
- 親権者が再婚した
- 親権者の再婚相手と子供が養子縁組をした
なかには、再婚相手が子供と元配偶者の面会交流を嫌がるというケースも見受けられますが、最も重視するべきは親の都合ではなく子供の福祉です。
したがって、再婚をしたとしても、子供の福祉の観点からは、面会交流を継続するのが望ましいでしょう。
面会交流について夫婦での話し合いがまとまらない場合は弁護士にご相談ください。
面会交流のルールの決め方は、さじ加減が難しく、ガチガチのルールで画一的に決め過ぎても、また、大雑把にし過ぎても、後々のトラブルに発展しかねません。
また、面会交流は、子供に「会わせたくない親」と「会いたい親」、両者の感情がぶつかり合う非常にデリケートな問題であり、「会わせたくない」「会わせてもらえない」などといったお悩みのご相談は、後を絶ちません。
しかし、何度も申し上げているように、面会交流は子供の幸せのため実施されるべき制度であり、子供自身が持つ権利と考えるべきです。
子供が夫婦の離婚問題の犠牲者にならないよう、面会交流のことでお困りのときは法律の専門家である弁護士へ相談しましょう。
「子供に会うためにはどうしたら良いのか」「子供の幸せにとっては何がベストな選択か」など、経験豊富な弁護士が、問題解決へ向け、全力でサポートいたします。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)



















