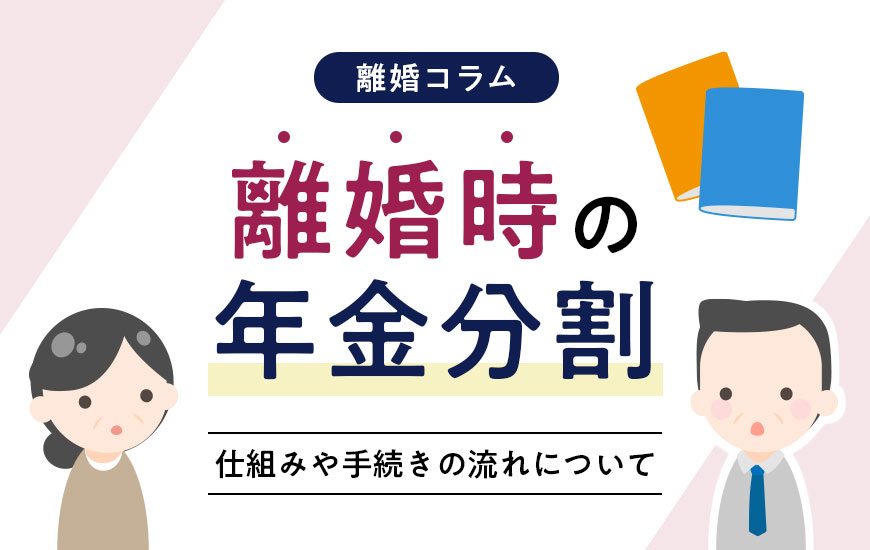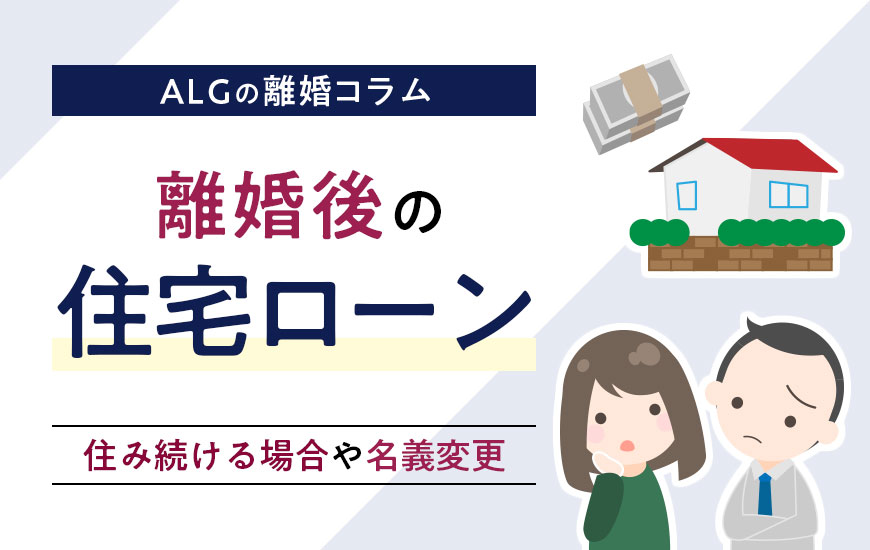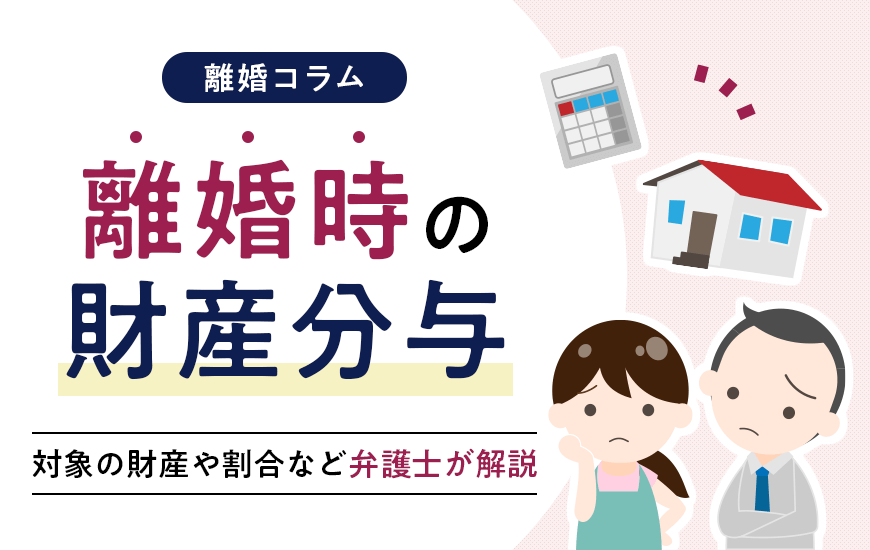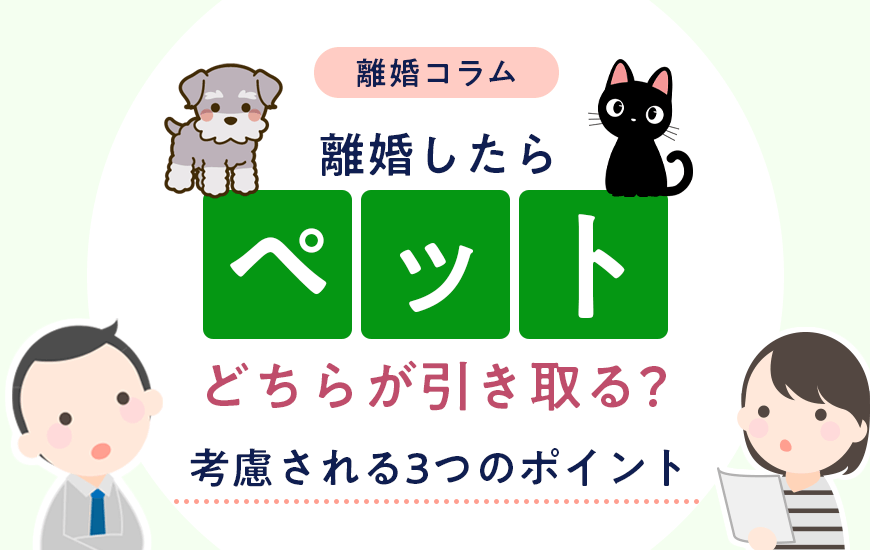共有財産とは?離婚時の財産分与の対象になるのはどこまで?
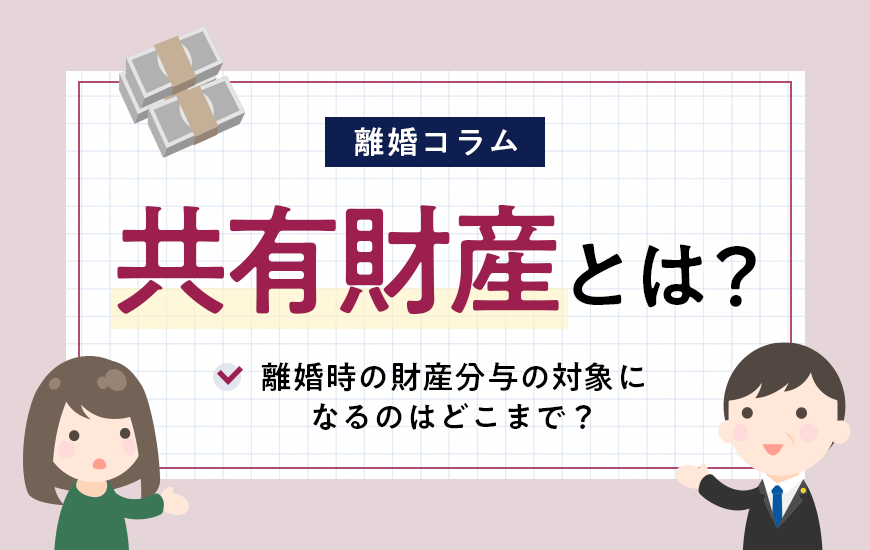
離婚するときには、婚姻中に築いた財産を夫婦で分け合うことになります。
これを財産分与といいます。
財産分与には、対象となる財産と対象にならない財産があり、対象となる財産のことを共有財産といいます。
離婚後の生活を精神的・経済的に少しでも余裕を持って過ごせるように、どのような財産が共有財産となるのかあらかじめ把握して、しっかりと財産分与することが大切です。
この記事では、共有財産となるものや、離婚時の分け方、財産分与の方法等について解説していきます。
目次
離婚で財産分与できるのは共有財産のみ
財産分与とは、婚姻中に夫婦が築き上げた財産を清算、分配することです。
ただし、財産分与では、すべての財産を財産分与の対象とすることはできません。
財産分与には、対象となる財産(共有財産)と対象とならない財産(特有財産)があるからです。
両者には、下表のような違いがあります。
| 共有財産 | 婚姻中に夫婦の協力により、形成・維持されてきた財産 |
|---|---|
| 特有財産 | 婚姻前から一方が有していた財産、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産 |
財産分与の対象である「共有財産」
共有財産とは、婚姻していた全期間において夫婦の協力によって形成・維持された財産のことをいいます。
車や住宅など大きな買い物をする場合は、夫単独の名義とする場合も多くありますが、財産分与では、夫婦どちらの名義であるかは関係ありません。
つまり、夫名義の車や家であっても、婚姻期間中に夫婦の協力によって形成・維持された財産なのであれば、共有財産として、財産分与の対象となります。
財産分与の対象となる共有財産は、原則として「別居まで」の間に夫婦間で形成・維持された財産となります。
そのため、婚姻関係にあっても別居後に得た財産については、共有財産とはみなされず、財産分与の対象とはなりません。
これは、たとえ婚姻関係にあっても、別居後については、夫婦が協力して得た財産とはいえないという考えに基づいています。
財産分与の対象でない「特有財産」
特有財産とは、婚姻前に形成した個人的な財産や、婚姻中であったとしても夫婦の協力を得ずに取得した財産のことをいいます。
共有財産とは異なり、財産分与の対象とはされません。
具体的には、以下のような財産が当てはまります。
- 婚姻前から夫婦どちらかが有していた財産
独身時代に貯めていた預貯金、婚姻前に購入した車や不動産などが対象です。 - 婚姻中に夫婦の協力とは無関係に取得した財産
婚姻中に発生した相続によって得た財産などが対象です。
ただし、本来は独身時代に築いた財産だったとしても、夫婦間で協力して価値の維持や増加に寄与した場合には、貢献度の割合によっては財産分与の対象となる可能性があります。
共有財産の対象になるものとは?
共有財産となる主なものには、以下のようなものがあります。
- 現金・預貯金
- 不動産
- 保険金
- 有価証券
- 自動車
- 家財道具
- 骨董品・絵画・貴金属など
- 退職金・年金
- ローンなどの借入
現金・預貯金
婚姻中に貯めた現金や預貯金は共有財産として財産分与の対象となります。
ただし、独身時代に貯めた預貯金については、特有財産として扱われ、財産分与の対象にはなりません。
へそくりや社内預金も、本来夫婦の家計に入れるべき財産として共有財産になります。
不動産
婚姻中に購入した家や土地などの不動産は、共有財産です。
また、婚姻中に夫婦のどちらかが、配偶者にだまって購入した不動産も共有財産として、財産分与の対象となります。
不動産は、そのまま分割できないため、以下の方法で財産分与します。
- 不動産を売却して現金化する方法
不動産を売って現金化するのは、最も分かりやすい方法でしょう。 しかし、ローンが残っている場合は注意が必要です。 - 一方は住み続け、もう一方は現金を受け取る方法
不動産を売却せずに夫婦のどちらかが住み続け、もう一方の配偶者に対して分与割合に応じた現金を支払う方法です。
保険金
婚姻していた間に加入した生命保険や学資保険なども共有財産として扱われます。
財産分与を行う際には、離婚時に保険をいったん解約して解約返戻金を夫婦で分割するという方法があります。
保険を解約せずに継続を希望する場合には、保険金の受取人側から相手に対して一定の清算金を支払う形で財産分与をすることもできます。
また、共有財産となる解約返戻金は婚姻期間中に保険料を支払った期間のみが対象です。
婚姻前から支払っている部分については特有財産として扱われ、財産分与の対象にはされません。
有価証券
婚姻中に購入した株式や国債も共有財産です。
有価証券は評価額が変動するため、離婚が成立した時点での評価額で財産分与することが一般的です。
自動車
婚姻期間中に購入した自動車は、共有財産です。
自動車を財産分与する方法には次の2つのパターンがあります。
- 自動車を売却する場合
売却で得た金額を夫婦で分け合います。 - どちらかが離婚後も所有し続ける場合
査定額に応じて、配偶者に相応の金額を支払う方法が一般的です。
また、独身時代から所有していた車は特有財産ですが、維持費用を共有財産から出していた場合には、共有財産となるケースがあります。
家財道具
婚姻中に購入した家具や家電製品などについても共有財産となります。
ただし、独身時代に購入したもの、結納金で購入したもの、嫁入り道具などは特有財産となり、財産分与の対象外です。
一般的には、財産分与の対象となる家電や家具は夫婦で分け合いますが、離婚後に使用しないものについては、売却し現金化して振り分けることもできます。
骨董品・絵画・貴金属など
婚姻していた期間中に購入した高価な貴金属、絵画、骨董品、着物などは共有財産です。
これらは、売却または査定で評価額を出したうえで金銭により清算を行うことになります。
また、両親から代々受け継いでいるような品や、独身時代に購入した品などについては、特有財産となり財産分与の対象外です。
退職金・年金
退職金も共有財産に含まれ、財産分与の対象となります。
しかし、財産分与の対象となるのは、退職金全体のうち、婚姻期間の年数分に限られます。
退職金が財産分与の対象となるかどうかは、以下のように判断します。
- 離婚時にすでに退職金を受け取っている場合
→手元に残っている退職金が財産分与の対象となる - 離婚時に退職金を受け取っていない場合
→将来退職金を受け取ることが確実である場合※は財産分与の対象
※退職金支給の確実性が高いとみなされるには、定年退職まで10年以内であることが目安となります。
年金は他の財産分与とは異なり、年金分割という制度で考えます。
年金分割とは、婚姻期間中に納めた厚生年金や共済年金の保険料納付記録を離婚時に夫婦で分け合うことです。
分け合うのは、年金額の計算の基準となる保険料納付記録であり、支給される年金そのものではありません。
離婚の年金分割については、以下のリンクで詳しく解説しています。
ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
ローンなどの借金
共有財産として財産分与するものは、プラスの財産だけではありません。
住宅ローンやカードローンといった借金などのマイナスの財産についても同様に財産分与の対象とされます。
共有財産(プラスの財産)と夫婦の債務(マイナスの財産)がある場合には、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、残った財産を分配する方法が一般的です。
ローンや借金はどのようなものが共有財産となり、どのように分配するのでしょうか。
見ていきましょう。
ローン
- 住宅ローン:住宅の現在の評価額からローン額を控除した額が財産分与の対象
- 自動車ローン:自動車を売却するか、譲り受ける側が支払うケースが多い
借金
- 夫婦の共同生活を営むために生じた借金は財産分与の対象
- 浪費やギャンブルなどのために一方が個人的に作った借金は共有財産には含まれない
離婚の住宅ローンについては、以下のリンクで詳しく解説しています。
ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
共有財産は離婚時にどのような割合で分ける?
離婚時に共有財産を、夫と妻でどのような割合で分け合うかは、実務上は夫婦で2分の1ずつ、つまり平等になるように分配するのが一般的です。
これは、婚姻生活中の共有財産への貢献度は夫婦で等しいと考えられており、一方が専業主婦(夫)であってもその貢献により共有財産の形成・維持ができたとみなされるためです。
しかし、例外的に個別具体的な事情によって割合が修正されることもあります。
例えば、次のようなケースです。
- 特殊な才能で資産形成した場合
- 財産形成に特有財産が寄与している場合
- 一方に浪費があった場合
- 同居していない期間があった場合 など
共有財産を財産分与する方法
財産分与の対象となる財産をリストアップし、夫婦で分配割合について話し合います。
基本的には2分の1ずつですが、話し合いにより双方が合意できれば自由に分配割合を決めることができます。
話し合いにより合意できたら、離婚協議書を作成し、公正証書にしておくことで後から「言った・言わない」といった争いに発展するのを防げるため安心です。
話し合いにより分配割合が決まらない場合は、家庭裁判所の調停や裁判の手続きを利用することとなります。
財産分与の手続きの流れについては、以下のリンクで詳しく解説しています。
ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
財産分与の請求に期限はある?
財産分与は、離婚するときだけでなく、離婚後にも請求できます。
しかし、離婚後に財産分与する場合は、離婚後2年以内に請求しなければならないという期限(除斥期間)が設けられています。
離婚後2年以内に財産分与の調停や審判の申立てを行っていれば、その間に2年が経過していたとしても、財産分与を受けることが可能です。
なお、2024年5月の民法改正により、財産分与請求権の除斥期間が2年から5年に伸長されることになりました。
この改正法は、2026年までに施行される予定であり、それまでは期限は2年のままであることに注意しましょう。
改正後には情報開示の制度も設けられる予定ですが、離婚後は相手方の行方が分からなくなるリスク等があるため、なるべく離婚時に請求することが望ましいでしょう。
離婚時に共有財産かどうか明らかでない財産があるとき
共有財産となるのか、特有財産となるのか、判断がつかないものは基本的に共有財産として扱われます。
民法762条2項では、“夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する”と定められています。
特有財産であることを主張したい場合は、そのことを立証する必要があるでしょう。
どうしても個人では、「共有財産」なのか、「特有財産」であるのかの判断が難しく、財産分与で揉めてしまうことも多くあります。
そのような場合は弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、どの財産が財産分与の対象となるのか判断できるだけでなく、特有財産として主張したい場合も、証拠を集め主張・立証していきます。
相手が共有財産を隠しているケースもあるため注意!
離婚を切り出す前に、隠し財産がないか調べておくことも大切です。
特に危ないのは、離婚を切り出したことで財産分与前に配偶者が財産を隠してしまうケースです。
相手が共有財産を隠してしまった場合でも、銀行名と支店名が特定できれば、弁護士照会制度によって相手の口座の有無など財産を調査することが可能です。
お困りの際は一度ご相談ください。
しかし、隠されてしまった財産をしらみつぶしに調査することはできないため、離婚を切り出す前に、隠し財産がないか調べておくのが得策です。
財産を把握するためには、以下のようなものを入手しておきましょう。
入手すべきもの
- 通帳のコピー
- 給与明細
- 不動産登記簿謄本
- 証券口座の明細
- 保険証券 など
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
離婚時の共有財産に関するQ&A
結婚後に飼い始めたペットは、共有財産として財産分与の対象になりますか?
たとえ我が子のように大切に育ててきたペットでも、法律上は「モノ」として扱われます。
そのため、夫婦が婚姻中に飼い始めたペットは、財産分与の対象となります。
しかし、ペットは土地や財産と違い、売却の対象にはならず、分割もできません。
平等に分配するためには、夫婦のどちらかがペットを引き取り、引き取った方が相手に対し、金銭や財産を補填する方法をとるのが一般的です。
合わせて読みたい関連記事
配偶者が通帳開示に応じてくれないため共有財産を把握できません。何か対処法はありますか?
共有財産を把握するために、相手方に通帳開示を求めても拒否される場合は、以下の2つの対処法が考えられます。
- 弁護士会照会制度
弁護士法23条の2に基づき、弁護士会を通して、弁護士が交渉や訴訟を行う上で必要となる資料や証拠を収集する制度のことです。
裁判外の手続きであるため、裁判の段階にとらわれずに利用することができます。 - 調査嘱託制度
裁判所を通して行う財産調査の手続きのことです。
調査嘱託を申し立てられたら、相手方が通帳の開示を拒否していても、開示しなくてはならなくなります。
ただし、申立てには相手方の通帳の銀行名や支店名などを明らかにする必要があります。
共有財産の使い込みが発覚した場合、離婚時の財産分与はどうなりますか?
離婚時に貯金など共有財産の使い込みが発覚した場合は、その分の金額を財産分与の際に請求することができます。
例えば、相手が100万円を使い込み浪費していた場合、財産分与の分割分+100万円を請求可能です。
しかし、「相手が共有財産を使い込んだ」という見極めは難しく、生活費や医療費、子供の習い事で使い込んでしまっても「必要な生活費」と判断され、無断で使っても「使い込み」とは断定できません。
また、婚姻前の貯金や受け継いだ財産から浪費をしていても、それは特有財産であるため、使い込みとはいえません。
相手が共有財産を使い込んだと判断するためには、以下のような事情を考慮します。
- 浪費の資金源は何なのか
- 夫婦の収入に占める浪費の割合はどの程度なのか
- 浪費によって家計が圧迫されたことが原因で婚姻関係が破綻したのか
相手が共有財産を使い込んだことを主張するには、その立証が必要です。
立証の方法や、使いこみの判断などは弁護士にご相談ください。
共働き夫婦で別財布だった場合、離婚時の共有財産はどうなりますか?
共働き夫婦が、それぞれの収入を自分の口座で管理していた場合でも、財産分与の対象となる共有財産は、夫婦のどちらかが専業主婦(夫)の場合と共通です。
以下のような財産は、基本的に共有財産に該当します。
- 婚姻中に得た、どちらかの名義になっている預貯金
- 給与収入から購入した不動産や自動車
- 家具や家電、宝石、貴金属などの財産
- 有価証券などの金融資産
- 退職金や年金の一部
共有財産でわからないことがあれば、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください
財産分与では、共有財産を明確にし、分配することが大切です。
しかし、共有財産がいくつもあり、どのようにすれば適切に分配できるのか、難しいことも多くあると思います。
財産分与については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士であれば、専門的な知識があるため、共有財産と特有財産を分けることができますし、いくつもある共有財産から不利にならないように分配交渉することが可能です。
また、相手が財産を隠している場合にも、弁護士であれば適切に対応することができます。
財産分与は、離婚後の生活を少しでも潤いのあるものにするために重要な項目です。
財産分与でお悩みの際は、まずは私たちに一度ご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)